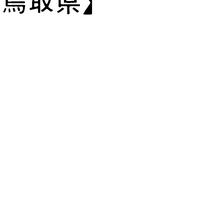精選版 日本国語大辞典 「鳥取」の意味・読み・例文・類語
とっとり【鳥取】
- [ 一 ] 鳥取県東部の地名。日本海に注ぐ千代(せんだい)川の下流域にある。天正元年(一五七三)山名氏の城下町となり、江戸時代は池田氏三二万石の城下町として繁栄。現在は県東部を後背地とする商工業都市。鳥取砂丘・鳥取城址などがある。県庁所在地。明治二二年(一八八九)市制。
- [ 二 ] 「とっとりけん(鳥取県)」の略。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「鳥取」の意味・わかりやすい解説
鳥取(県)
とっとり
中国地方の北東部にあり、日本海に面した県。面積は3507.14平方キロメートル。北は日本海を隔ててロシア連邦の沿海地方に対し、東は兵庫県、西は島根県、南は岡山・広島の両県に接する。因幡(いなば)と伯耆(ほうき)の2国からなる。県庁所在地は鳥取市。県名のもとは、鳥取部(ととりべ)がいた因幡国鳥取郷(ととりごう)で、戦国時代に鳥取城が築かれ、江戸時代には因幡、伯耆を治める池田氏の城下町となり、藩名、県名となった。
鳥取県は海流によって早くから大陸や北九州との交流があったと推定され、遺跡密度は畿内(きない)と肩を並べている。東西に細長い県で、鳥取、倉吉(くらよし)、米子(よなご)の3市を中心とする3定住圏からなるが、山がちであるため山陰線の開通が遅く、中央市場との連接は大正期以後のこととなり、産業の近代化が後れた。隠岐堆(おきたい)を中心とする大型巻網漁業や智頭(ちず)林業、畜産や砂地農業とナシ栽培などにより知られた農林水産県である。1960年代後半より電機産業の誘致や境港(さかいこう)の整備、中海(なかうみ)新産業都市計画などにより格差を縮めた。大山(だいせん)隠岐国立公園をはじめ国立、国定公園が四つあり、温泉も多く、観光県でもある。
人口は、1920年(大正9)の第1回国勢調査では45万4675人、2000年(平成12)には61万3289人であり、80年間に約16万人(指数135)増えた。この間、1955年の61万4259人をピークに過疎化が進行し、1970年には56万8777人となった。以後は微増に転じ、2000年には1970年に比べて7.8%増となった。これは社会増と自然増による。しかし65歳以上の人口構成比(2020)は32.5%であり、全国都道府県中第17位の高齢化を示している。2020年(令和2)の人口は55万3407人。
1889年(明治22)の市制町村制施行時には1市4町233村であったが、第二次世界大戦後の町村合併により、1953年には2市28町105村になり、2020年10月時点で4市5郡14町1村からなる。
[岩永 實・豊島吉則]
自然
地形
南部の岡山県境の中国山地は、三郡変成岩や花崗(かこう)岩類からなり、600~700メートルの低位侵食平坦(へいたん)面上には、高位侵食平坦面とみられる道後(どうご)山や残丘状の大倉(おおくら)山など、1000メートル級の山々がそびえ、その西部は比婆道後帝釈(ひばどうごたいしゃく)国定公園になっている。低位侵食平坦面上の川は浅い谷を緩く流れているが、下流の谷頭侵食部では急な峡谷や滝となり、石霞(せっか)渓や小鹿(おしか)渓(国の名勝)、三滝(みたき)渓などの名勝地となっている。大山火山帯の主峰大山(1711メートル)と岡山県境の上蒜山(かみひるぜん)(1200メートル)は大山隠岐国立公園の主要部をなし、その東方の氷ノ山(ひょうのせん)(1510メートル)などの兵庫県境の山地は氷ノ山後山那岐山国定公園(ひょうのせんうしろやまなぎさんこくていこうえん)を構成している。北流する千代(せんだい)、天神(てんじん)、日野(ひの)の3主要河川は、間・後氷期の旧内湾を埋積して鳥取、倉吉、米子の3平野を形成し、砂丘列の内側には潟湖(せきこ)群が並ぶ。一方、東部の山地が海に迫るリアス海岸には、典型的な海食地形が発達した浦富海岸(うらどめかいがん)(国の名勝・天然記念物)があり、鳥取砂丘(国の天然記念物)とともに山陰海岸国立公園の西縁部を構成している。このほか、三朝(みささ)東郷湖、奥日野、西因幡の3県立自然公園がある。
[岩永 實・豊島吉則]
気候
日本海沿岸気候区のなかの山陰型に属し、降雪やフェーン現象では北陸地方と共通しているが、より暖かく雪も少ない。年平均気温は鳥取市で14.9℃(1981~2010)で、山間部は約2~3℃低い。年降水量は鳥取市1914ミリメートル(1981~2010)、大山は2838.9ミリメートル(1982~2010)で、北西季節風に対向する大山や東部山岳地帯は深雪地となり、2メートル近くにまで達する。また標高500メートル以上の気候は、秋田県に似た多雨夏冷涼気候となる。
[岩永 實・豊島吉則]
生物相
寒地系と暖地系の混在が特徴。垂直的には、砂丘植物群落や沿海照葉樹林、内陸照葉樹林から下部夏緑樹林に移行、約600メートル以高では日本海型夏緑樹林(チシマザサ―ブナ群団)となり、約1200メートル以高では風衝低木、草原に移行し、大山山頂には特別天然記念物ダイセンキャラボクの純林がある。鳥取市の白兎海岸(はくとかいがん)のハマナス自生南限地帯は国の天然記念物に指定されており、琴浦(ことうら)町箆津(のつ)には県の天然記念物で暖地系のハマヒサカキがあり、ほぼ自生北限地帯とみられている。なお特別天然記念物オオサンショウウオの生息域として日野川流域や天神川流域と大山内小河川が知られる。鳥類ではコハクチョウ、カモなどが中海などに飛来し、大山など高山にオオタカ、クマタカもみられる。
[岩永 實・豊島吉則]
歴史
先史・古代
先史時代の集落跡や古墳などの遺跡数は1万を超え、分布密度は大阪府や奈良県に匹敵する。生活圏の形成は、大山山麓(さんろく)での尖頭(せんとう)器の出土からみて縄文草創期にさかのぼる。縄文・弥生(やよい)時代の遺跡は日野高原や大山山麓、沿岸砂丘帯などに多い。その特色は、貝塚が少なく、米子市目久美(めぐみ)遺跡にみられるように、縄文前期の遺跡が標高5メートル以下の低地にも分布すること、銅鐸(どうたく)15例と銅剣・銅鉾(どうほこ)2例から、通説では畿内(きない)、北九州の両文化圏の漸移地帯にあたること、玉造(たまつくり)遺跡22例のほか、弥生中期以後の西日本最大級の集落遺跡として福市(ふくいち)遺跡、青木遺跡(ともに国の史跡)が発見されていること、山陽側との交流をうかがわせる分銅形土製品が出土していることなどである。湯梨浜(ゆりはま)町の長瀬高浜遺跡のような砂丘地帯の古墳期遺跡がみられることも特色である。ついで四隅突出型の阿弥大寺(あみだいじ)古墳群(国の史跡)などの墳丘墓時代を経て古墳時代になり、注目される点は、40メートル以上の大型古墳54中の70%が伯耆にあること、梶山(かじやま)古墳(国の史跡)など彩色装飾古墳や線刻装飾古墳数が50に上ること、北九州や朝鮮半島との関係を思わせる石馬(いしうま)(国の重要文化財)が出土していることなどである。また、倉吉市の不入岡(ふにおか)遺跡(国の史跡)は10棟の大規模倉庫(8、9世紀)が発掘されている。また、米子市、大山町にまたがる地域に妻木晩田遺跡(むきばんだいせき)(国の史跡)があり、縄文時代の動物をとるための落し穴や弥生時代の墳丘墓、住居跡、古墳等が発掘されている。
奈良時代の廃寺跡は、伯耆14、因幡13が確認されており、そのなかには、琴浦(ことうら)町の斎尾(さいのお)廃寺跡(特別史跡)や、伯耆国分寺跡、伯耆国府跡、国分尼寺であった可能性が考えられる法華寺畑遺跡、伯耆国庁跡や因幡国庁跡(以上、国の史跡)などがあり、律令(りつりょう)体制の盛時を物語る。伯耆守(ほうきのかみ)として山上憶良(やまのうえのおくら)、因幡守として大伴家持(おおとものやかもち)らの万葉歌人も来任し、家持が759年(天平宝字3)元旦(がんたん)に詠んだ歌は『万葉集』の最後を飾る歌となった。また、東大寺の因幡国高庭庄(たかにわのしょう)などが置かれたが、11世紀初頭には荒廃した。米子市の上淀廃寺(かみよどはいじ)(国の史跡)からは壁画が出土している。
平安時代には、山岳信仰と結ばれた大山寺(だいせんじ)や三仏(さんぶつ)寺は天台密教の霊地となった。しかし律令制の乱れとともに院政初期以後に台頭した在地武士団や在庁官人の対立を背景に、寺院内部の抗争や両寺院の対立が激化した。1094年(嘉保1)の大山衆徒の上洛強訴(じょうらくごうそ)などはその現れである。
[岩永 實・豊島吉則]
中世
源平の争乱期には、大山寺と三仏寺は反平家勢力の拠点となったが、鎌倉時代になると、多かった皇室御領や大社寺領の荘園(しょうえん)内には、1258年(正嘉2)の「伯耆国河村郡東郷荘下地中分図(したじちゅうぶんず)」にみられるように、地頭(じとう)の私領化が進み、国衙(こくが)領にも同様な領主化が進んだ。
南北朝の争乱時代になると、伯耆の豪族名和長年(なわながとし)は隠岐(おき)脱出の後醍醐(ごだいご)天皇を船上(せんじょう)山に迎え、北朝軍を破って建武(けんむ)新政の先駆となった。しかし、新政の挫折(ざせつ)と長年戦死後の1363年(正平18・貞治2)、山名時氏(ときうじ)は因幡、伯耆ほか3国の守護職を安堵(あんど)され、以後山名氏は約200年間因幡と伯耆を支配した。しかし応仁(おうにん)の乱(1467~1477)後、内部抗争によって山名氏が弱化すると、出雲京極(いずもきょうごく)氏の守護代尼子氏(あまごうじ)は東進を開始し、伯耆に次いで因幡も治下にした。やがて尼子氏にかわって安芸(あき)(広島県)の毛利氏(もうりうじ)が因幡に入り、鳥取城をその前進拠点とし、部将吉川経家(きっかわつねいえ)を城主とした。しかし1581年(天正9)鳥取城は羽柴(はしば)(豊臣(とよとみ))秀吉に落とされ、因幡は織田氏の治下となり、伯耆の毛利氏と境を接することになった。
[岩永 實・豊島吉則]
近世
関ヶ原の戦い後、西軍にくみした因伯(いんぱく)の大名の多くは領地を没収され、かわって鳥取城に池田氏、若桜(わかさ)城に山崎氏、鹿野(しかの)城に亀井氏、米子城に中村氏が入城したが、1617年(元和3)因伯は姫路城主から鳥取城主となった池田光政(みつまさ)32万石の治下となった。さらに1632年(寛永9)光政は岡山へ移り、岡山から移封した池田光仲が鳥取城主となった。以後明治維新まで池田氏鳥取藩が続き、光仲を藩祖としている。藩制の特色は、家老筋に6か所の自分手(じぶんて)政治をゆだねていたことである。その間藩財政の窮乏打開のための請免(うけめん)法の施行をめぐり、1739年(元文4)には因伯両国に元文一揆(げんぶんいっき)(因伯一揆)が起こった。一方、国産奨励では弓ヶ浜の米川(よねかわ)用水の開削と新田開発、伯耆のたたら製鉄と綿業、因幡の和紙と木蝋(もくろう)などがあげられる。明治維新時、鳥取12代藩主慶徳(よしのり)は尊皇攘夷(じょうい)派で、朝廷と幕府や長州藩との間を周旋した。
[岩永 實・豊島吉則]
近・現代
1871年(明治4)の廃藩置県で鳥取藩は鳥取県となり、隠岐国を編入、ついで1876年には島根県に合併された。しかし共斃(きょうへい)社などによる旧士族団の抵抗もあり、1881年には鳥取県が再置された。一方、1883年には士族団が開拓農民となって北海道へ移住、鳥取村をつくり釧路(くしろ)市開発の先駆となった。産業開発では、在来の綿作と綿業にかわり、1891年以降は桑作と養蚕や製糸業が盛んになり、1904年(明治37)には千葉県松戸(まつど)から二十世紀ナシが移植され、まもなく全国首位の産地となった。1900年山陰線は資材輸送に便利な境(現、境港)から着工されたが、日清(にっしん)、日露の戦争に阻まれ、山陰線が全通したのは1912年で、中央市場との接触が後れたことは後進性の一要因となった。やがて満州事変を契機に境港は大陸貿易港、弓ヶ浜は空路基地として脚光を浴び、第二次世界大戦中・戦後も引き継がれた。
第二次世界大戦後の農業は、農地解放の目標達成率133%という民主化を背景に、桑作にかわる二十世紀ナシ栽培の普及、人工灌漑(かんがい)による砂地農業や畜産などの進展が顕著である。一方、工業では、電機産業のほか、女性労働力を背景にした縫製品や繊維工業などが農工併進の形で拡散した。1966年(昭和41)には中海(なかうみ)地区新産業都市計画が実施され、菅沢(すげさわ)ダムによる発電や工業用水道、米子鉄工団地、境港木工団地などの整備が進行した。観光人口は1951年の300万人から2002年(平成14)には879万人となった。治水では1931年(昭和6)の千代川新流路通水、1934年の新袋(しんふくろ)川通水でいちおう完了した。一方、1943年の鳥取地震、1952年の鳥取大火災を契機に県都鳥取市は耐震耐火都市となり、やがて駅高架と駅周辺の再開発のほか、新都市開発整備事業を進めた。1972年には弓ヶ浜半島と島根半島とを結ぶ境水道大橋の完成、1992年には米子自動車道の全線開通、1994年の智頭(ちず)急行智頭線の全線開通等徐々に交通の整備が進行した。2000年に起きた鳥取県西部地震ではマグニチュード7.3、日野町、境港市で震度6強を記録した。死者はなかったが、住居の全・半壊、落石などによる鉄道・道路の不通、液状化現象による被害は大きく、県は防災体制、防災計画の見直しと構築を進めている。
[岩永 實・豊島吉則]
産業
鳥取県の産業構造を生産所得と就業人口の構成比からみると、農林水産業の第一次産業比が全国平均よりも高く、製造業・建設業などの第二次産業比は低い。近年サービス業などの第三次産業比は67.0%(2010)と高まっている。また1人当り県民所得は205万5000円(2010)で、1人当り国民所得の72.7%である。
[岩永 實・豊島吉則]
農業
山地が多く耕地率は10.6%、うち水田率は67.7%という水田卓越県で、大山山麓や砂丘地帯の畑地や樹園地の多いことが特色で、ナシやラッキョウ・スイカ栽培、ブロイラー飼育などは全国的にみても主産地形成が進んでいる。農業粗生産額の構成比からみると、米の26%に次いで野菜、果実の順である。おもな生産物は傾斜地利用の二十世紀ナシで、2003年(平成15)現在栽培面積1040ヘクタール、生産量2万3200トンで、全国総生産量の49.7%を占め、質・量ともに首位にあり、二十世紀ナシの花は県花とされている。ほかに北条(ほうじょう)砂丘のブドウ、東部八頭(やず)郡のカキがある。また、北栄(ほくえい)町を中心とするスイカは全国第4位で3万1600トンの生産量をもっている。福部(ふくべ)砂丘のラッキョウは全国第2位で3140トン、ナガイモは2350トン、ネギは全国第6位で1万4800トンで集団産地化が進んでいる(2001)。畜産では、かつての役肉牛の因伯牛から酪農と和牛の基礎牛の生産と育成にかわった。ブロイラーの生産は全国第9位(2002)にある。農家の経営規模は、1~2ヘクタール層が25.0%、専業農家は全農家中14.3%でほぼ安定している。また農業所得は全国平均より低いが、農業所得を主とする主業農家では全国平均を上回るという特徴がある。
[岩永 實・豊島吉則]
林業
東部の智頭(ちず)・若桜(わかさ)地方は、西日本有数のスギ、ヒノキの林業地で、温暖多雨な古生層山地は植林に適し、鳥取藩の奨励以来の挿木(さしき)苗の造林法が特色である。西部の日野山地は古来たたら製鉄用の木炭産地で、たたら衰退後は製炭中心地となったが、第二次世界大戦後の燃料革命で衰微した。2001年(平成13)現在の林業粗生産額は23億2000万円でうち7割が木材、2割がシイタケを主とした栽培キノコ類である。
[岩永 實・豊島吉則]
水産業
対馬(つしま)暖流とリマン寒流が合流して湧昇(ゆうしょう)する隠岐諸島付近の大陸棚は、その北方の大和堆(やまとたい)とともに好漁場をなし、境港は日本海沿岸最大の漁業根拠地となっている。イワシ、サバ、アジなどの大・中型巻網漁業のほか、ベニズワイガニ籠(かご)網漁業、沖合イカ釣り漁業の基地でもある。一方、沖合底引網漁業は、東部の網代(あじろ)、田後(たじり)、鳥取の各港が中心で、カレイ、マツバガニ(ズワイガニ)、ハタハタを主とするが、マツバガニは乱獲で漁獲量が減少傾向にあり、漁期の短縮や漁獲量の制限等を行い、資源保護を図っている。
[岩永 實・豊島吉則]
鉱業
日南(にちなん)町多里(たり)にある若松・広瀬のクロム鉱山は、かつて耐火れんが用原料として全国首位の生産量を誇っていたが、輸入鉱石に押され閉山した。また人形(にんぎょう)峠、東郷などの堆積型ウラン鉱床の推定埋蔵量は約495万トンとされ、岡山県側の動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所(のちの核燃料サイクル開発機構。現、日本原子力研究開発機構の人形峠環境技術センター)では、1979年(昭和54)から2001年(平成13)までウラン濃縮プラントの運転が行われていた。なお岐阜県の東濃鉱山の発見により、埋蔵量は全国第2位となった。
[岩永 實・豊島吉則]
工業
工業製品の出荷額からみると、近年の不況の影響もあり、停滞傾向にある。出荷額順にあげると、(1)電子部品・デバイス、(2)食料品、(3)飲料・タバコ・飼料、(4)電気機械、(5)情報通信機械となっており、電子部品・デバイスがもっとも出荷額が多く、製造品の28.9%を占め、2968億円であった(2002)。鳥取県は鳥取市を中心とする東部、倉吉市を中心とする中部、米子市、境港市を中心とする西部の3地域に分けられるが、鳥取三洋電機(現、LIMNO(リムノ))とその関連企業などのある東部と、全国有数の水揚げ漁獲と結合した水産加工の西部が対照的である。なお、東部が出荷額では47.3%(中部12.8%、西部39.9%)、製造業事業所数では44.0%(中部20.7%、西部35.3%)、同従事者数では47.0%(中部18.9%、西部34.1%)と、高い構成比(2002)を示し、1990~1997年度間の誘致企業数144中41.0%を占めているのは、国道29号と中国自動車道の開通による京阪神との時間的距離の短縮による。
[岩永 實・豊島吉則]
開発
鳥取県では、国際貿易港である境港を中心に、世界各国との経済交流をさらに進めるため、さまざまな取組みを進めている。
境港を中心とする地域では、新しい整備計画「FAZ計画(輸入促進地域計画)」が1995年(平成7)に国の承認を受けて動き出しており、日本海を取り巻く国々の国際貿易の拠点となるよう、港湾・空港およびその周辺地域の整備が進んでいる。港湾施設では、境港外港で4万トン岸壁、1万トン岸壁が供用されており、2004年には5万トン岸壁も供用開始された。ほかに、大型クレーンが整備されており、倉庫、流通加工施設や、輸入品取扱企業の集積を進めている。また、米子市では1998年に米子コンベンションセンター「ビッグシップ」が開館した。また、新しい国際定期航路の開設も進めており、あわせて空港の国際化や鉄道、高速道路、航空網など、関西・山陽地方、ひいては全国各地域との高速交通ネットワークの構築を進めている。空港では、米子空港の2000メートル滑走路が1996年に完成、2009年には2500メートルに延長され、供用を開始した。この延長にともない、JR境線の路線が変更され、米子空港駅(旧、大篠津駅)が2008年に移転・開業している。
このほか、鉄道では1994年(平成6)の智頭急行智頭線(鳥取県智頭町―兵庫県上郡(かみごおり)町)の開通、高速道路網等の整備では、中国横断自動車道米子―岡山線の開通により山陽・四国との交流が活発になっている。また、中国横断自動車道姫路―鳥取線が2022年に全線開通し、鳥取―米子間の自動車専用道(山陰道)は2026年に開通予定である。重要港湾鳥取港も、大型岸壁の整備により物流拠点として供用開始されており、国内はもとより対岸諸国からの貨物船が入港している。
[岩永 實・豊島吉則]
交通
鳥取、倉吉、米子の3市は、東西系のJR山陰本線や国道9号で結ばれる。山陰と山陽を連絡する南北系の交通路は、東からJR因美(いんび)線、国道29号・373号・53号・179号・313号、JR伯備線、国道181号・180号・183号などがあり、中国自動車道や東海道・山陽新幹線と連接している。鉄道では、1982年に電化した伯備線を除きほかは複線電化が課題である。第三セクターによる智頭急行智頭線が1994年(平成6)完成。米子自動車道開通、米子―大阪・京都が約3時間で結ばれている。鳥取自動車道で中国自動車道、山陰自動車道と接続。山陰近畿自動車道、江府三次道路などが走る。なお、鳥取空港は東京と、米子空港は東京・ソウル・上海(シャンハイ)・香港(ホンコン)と結ばれている。
[岩永 實・豊島吉則]
社会・文化
教育・文化
藩校尚徳館(しょうとくかん)は1757年(宝暦7)から1870年(明治3)の間、藩士と子弟の教育にあたった。一方、幕末には約300の寺子屋があった。その間、鳥取藩医の稲村三伯(いなむらさんぱく)は大槻玄沢(おおつきげんたく)に蘭学(らんがく)を学び、辞書『波留麻和解(ハルマわげ)』(1791)を著し、歌人香川景樹(かがわかげき)は桂園(けいえん)派の祖となった。明治時代になると、尚徳館は師範教育に次いで中学校教育の発祥地となった。以後輩出したおもな学者や文化人は、日本初の理学博士村岡範為馳(はんいち)、唱歌の作曲家田村虎蔵(とらぞう)・岡野貞一(ていいち)、詩人生田春月(いくたしゅんげつ)・伊良子清白(いらこせいはく)、俳人尾崎放哉(ほうさい)、洋画家前田寛治(かんじ)、日本画家菅楯彦(すがたてひこ)、憲法学者佐々木惣一(そういち)、精神医学者橋田邦彦(くにひこ)らである。
高等教育機関は、1876年(明治9)に鳥取師範学校、1921年(大正10)に鳥取高等農林学校、1926年に鳥取県女子師範学校、1945年(昭和20)に米子医学専門学校が設立され、第二次世界大戦後、鳥取高等農林、米子医専などを統合して国立鳥取大学が創設された。このほかに公立鳥取環境大学、国立米子工業高等専門学校、鳥取短期大学がある(2018)。文化施設には、県立の博物館、図書館、とっとり花回廊、大山自然歴史館、山陰海岸学習館、公立の歴史民俗資料館など、私立の鳥取民芸美術館、渡辺美術館などがある。
新聞は、『日本海新聞』がある。前身は1883年(明治16)創刊の『山陰隔日新報』である。1885年(明治18)廃刊、『鳥取新報』と改題。1939年(昭和14)に『因伯時報』(1892)、『山陰日日新聞』(1908)と合同し、『日本海新聞』(一時『山陰同盟日本海新聞』)となった(1946年米子で創刊の『山陰日日新聞』は1963年合併)。1975年(昭和50)経営難で休刊、同年設立の新日本海新聞社に翌1976年引き継がれ『日本海新聞』を再刊した。放送は、NHK鳥取支局が1936年(昭和11)に、ラジオ山陰(現、山陰放送)が1953年に、日本海テレビジョン放送が1958年に開局、テレビ放送については3局とも1959年に開始した。
[岩永 實・豊島吉則]
生活文化
因幡と東伯耆、西伯耆の3地域社会に分かれ、地域性を異にする。方言は因幡と東伯耆が但馬(たじま)(兵庫県)を含む東部山陰方言に、西伯耆は出雲(いずも)(島根県)を含む雲伯(うんぱく)方言に属する。一方、県南の岡山県と接する地域のうちでも、因幡と東伯耆の場合は美作(みまさか)方言が、西伯耆の場合は備中(びっちゅう)方言が複合しているが、峠が低く日本海側と瀬戸内海側との交流が密であった西伯耆の場合は、備中方言との複合地帯の幅が広い。また大山以東の山地に多い木地師(きじし)起源の集落に対し、以西の日野山地では製鉄に関連するたたら、かんななどの小字(こあざ)名と金屋子神祠(かなやごのかみのほこら)の分布が多い。
衣生活では、晴れ着や普段着と仕事着があり、大正期までの普段着は手紡ぎや手織りの木綿、麻が主で、雪の下では綿入れの胴服(どうぶく)や袖(そで)なしを重ねて着た。水田地帯の野良着(のらぎ)は、紺か縞(しま)の木綿の筒袖(つつそで)か法被(はっぴ)で、山仕事はつづれにももひき、パッチをはいた。しかし漁師はそれをはかず、厚手のさくりや刺子(さしこ)を長めに着用し、冬は綿入れの袖なしを重ねて着た。冬の履き物では藁(わら)製のふんごみ(雪靴)やかんじき(雪輪)、雨具ではスゲ製のひねりみの、雪用には胴丸(若桜町)や防寒用のオッボ(倉吉市関金町地区)を着た。
第二次世界大戦前の農村の食生活は、麦米の混食が一般的で、いもやイリゴ(屑(くず)米)の粉でこねた餅(もち)ヤキモン(因幡)、イスンカダンゴ(伯耆)などのほか、粟(あわ)餅、栃(とち)餅、サツマイモの切干しを煮て粥(かゆ)にしたネボシ(弓ヶ浜)などの代用食があった。漁村ではダイコンやサツマイモなどの葉を混ぜた菜飯(なめし)や、海藻を混ぜたヒジキ飯、貝を混ぜたイガイ飯もあった。また副食には糠漬(ぬかづ)けの保存食ヘシコイワシ、甘味料にはギョウセン飴(あめ)(鳥取市三山口(みやまぐち))、甘茶、カキの皮などがあった。
民家の屋根は多雨多雪に備えて一般に急傾斜で、材料は平野部では藁、山間部では茅(かや)や笹(ささ)、奥地ではささ板や杉皮、石などをのせた屋根が混在した。屋根型は東伯耆の天神川以東は入母屋(いりもや)圏で、山間地域では角材千木(ちぎ)型(烏踊(からすおどり))、天神川以西の伯耆は寄棟(よせむね)圏で、とくに日野川流域では赤瓦(あかがわら)をのせた箱棟型が特色であった。冬の北西季節風が強い大山北麓(ほくろく)の集落では、防風林を巡らし、因幡東部の深雪地の民家では雪囲いで周りを囲むほか、若桜町の民家では道路側に雁屋(かりや)(雁木(がんぎ))を付設するなど、北陸的な地域性がみられた。農家の間取りは一般に座敷と土間を等分した四間取りが多く、トノグチ(玄関)に近く内厩(うちまや)(牛馬小屋)と通ずる小便所を設けていた。いろりには神棚を背に主人のヨコザがあり、ほかの座名は因幡と伯耆では異にした。
[岩永 實・豊島吉則]
民俗芸能
年頭に年神(としがみ)を迎え(南部(なんぶ)町、若桜町)、年神を送るトンドウ(鳥取市、米子市)が済むと、作柄を占う管粥(くだがゆ)の神事(倉吉市、大山町)がある。3月終わりに八頭町で行われる茂田神社(もだじんじゃ)の春祭では榊神輿(さかきみこし)が集落内を練り歩く。旧暦の3月3日に人形に穢(けがれ)を移して流すひな送り(鳥取市)や旧3月15日には九品山会式(えしき)で流れ灌頂大施餓鬼供養(かんじょうだいせがきくよう)が行われる(湯梨浜(ゆりはま)町)。4月の春祭では、4台の屋台を出す城山神社祭(鳥取市)と、神官が矢を射て悪疫を払い豊凶を占う百手の神事(ももてのしんじ)(鳥取市姫路神社)がある。5月には三朝(みささ)町の陣所(じんしょ)とよぶ綱引き(国の選択無形民俗文化財)、旧暦5月には鳥取市、岩美(いわみ)町の菖蒲(しょうぶ)綱とよぶ綱引き(国の重要無形民俗文化財)があり、6月の大山山開きでは山頂の梵字(ぼんじ)ヶ池の水をくむ古式の「もひ取り」(弥山禅定(みせんぜんじょう))神事が行われる。7月には茅の輪(ちのわ)くぐりのあと人形(ひとがた)を流す祭り(米子市、琴浦(ことうら)町)があり、月末から8月の盆にかけては、流れ灌頂(米子市淀江町)や、琴浦町のコナカリサン(この明かりをめどにと呼びかける仏迎えと仏送りの行事)があり、9月の仲秋の名月の日には因幡の古寺摩尼寺(まにでら)(鳥取市)でヘチマ供養が行われる。旧暦9月には高杉神社(大山町)の嫐神事(うわなりしんじ)がある。神がかりした氏子3人が正室の細(くわし)姫と側室の松姫、千代姫になり、嫉妬(しっと)して互いに打ち合い、神官が正室に勝ちを宣して鎮めるという神事。10月には主神の乗った船をタコが護(まも)ったとの由来から、伯耆(ほうき)町福岡神社の蛸舞(たこまい)式が行われる。秋祭の季節を迎えると、因幡南部の智頭町一帯では花籠(はなかご)祭りがあり、鳥取市では旧暦の10月に復活した亥の子(いのこ)行事もみられる。12月には西伯耆の各地で収穫感謝の申上げ祭りが催され、藁蛇(わらへび)を供えての荒神や水神の祭りがみられる。ともあれ、ひな流しや流れ灌頂、精霊(しょうりょう)送りなどには、『伯耆国風土記(ふどき)』逸文の少彦名命(すくなひこなのみこと)が常世(とこよ)に渡る神話に読み取られるように、海上他界信仰がみられる。一方、大山や摩尼山などには山中他界信仰の存在を思わせるものがある。また、荒神や塞神(さえのかみ)信仰が雲伯方言と同じく西伯耆以西に多いことが注目される。
県指定の無形民俗文化財の踊りは傘踊りと手踊りからなる。因幡の傘踊り(鳥取市)は、神前で雨乞(あまご)い踊りに狂死した五郎作老人慰霊のため、江戸末期に始まり、明治中期に剣舞の型を入れたものと伝える。それを群舞に改作したものが8月16日の鳥取しゃんしゃん祭である。日置(ひおき)のはねそ踊り(鳥取市)は、江戸中期に因幡に普及した踊りの名残(なごり)で、青竹を依代(よりしろ)として立てた梵天(ぼんてん)の周囲で踊る。牧谷のはねそ踊り(まきだにのはねそおどり)(岩美町)は古い伝承で、長柄(ながえ)傘の女と編笠(あみがさ)の女が一対となって踊る。そのほか、タカの餌(えさ)を鳥もちで刺してとる狂言風の踊りさいとりさし(三朝町、倉吉市)、念力節(がんりきぶし)につれて所作をする鳥取市の円通寺人形芝居(県指定無形民俗文化財)、落人(おちゅうど)慰霊の念仏踊りといえる江尾(えび)のこだいぢ踊り(江府(こうふ)町)、亀井踊(鳥取市)、浪人踊(湯梨浜町)がある。獅子舞(ししまい)には、鳥取市の大和佐美命(おおわさみのみこと)神社の獅子舞(県指定無形民俗文化財)のように、立耳との間に一角をもつ麒麟(きりん)獅子と朱面の猩々(しょうじょう)とによる舞いと、垂れ耳で無角の神楽(かぐら)獅子とときに鶏(とり)かぶとをかぶる天狗(てんぐ)面とによる舞いがある。麒麟獅子は正倉院御物や隠岐国分寺に保存され、大陸渡来を思わせ、分布は因幡と但馬で知られている。
現存する神楽は、日野郡の日南神楽(日南町)や、下蚊屋荒神(さがりがやこうじん)神楽などで、大蛇(おろち)退治や神能杵築(きづき)、八重垣(やえがき)などを上演する。
[岩永 實・豊島吉則]
文化財
特別天然記念物のダイセンキャラボク純林は大山頂上付近にあり、オオサンショウウオは伯耆南部の渓流に生息する。特別史跡斎尾廃寺跡(さいのおはいじあと)(琴浦町)は、法隆寺式伽藍(がらん)配置で白鳳(はくほう)時代の創立と推定。国の名勝・史跡の三徳山(みとくさん)(三朝町)内の国宝建造物三仏寺奥院(投入(なげいれ)堂)は8世紀初めの建築と伝えられ、三仏寺納経堂、地蔵堂、文殊堂は国の重要文化財。大山寺の阿弥陀(あみだ)堂(国の重要文化財)の原型も12世紀前半と考えられている。これらは平安時代の山岳仏教史上貴重な文化財である。同様に智頭町豊乗寺(ぶじょうじ)の絹本著色普賢菩薩(ふげんぼさつ)像(国宝、平安時代)は金銀の切金細工(きりかねざいく)の文様で彩られた仏画の優秀作。東郷町の伯耆一宮経塚(ほうきいちのみやきょうづか)出土品は康和(こうわ)5年(1103)在銘の経筒ほか9点で、その価値は高く、国宝に指定されている。このほか、江戸時代には因幡東照宮とよばれた樗谿(おうちだに)神社の本殿・唐門などや、福田家住宅・後藤家住宅など江戸時代の民家建築、明治建築の仁風閣(じんぷうかく)などが国の重要文化財に指定されている。
[岩永 實・豊島吉則]
伝説
鳥取市湖山(こやま)の「宇文の長者(うぶみのちょうじゃ)」は古くから知られている伝説である。湖山池の周辺にはすくも塚や長者の墓など、長者にまつわるものが多い。田植の際に長者が沈む太陽を扇で呼び戻し、その天罰で没落したという。これは柳田国男(やなぎたくにお)が『日を招く話』で指摘しているように、全国に流布する伝説である。米子市の安養(あんよう)寺には歯形の栗(くり)の話がある。「瓊子姫(たまこひめ)」は、隠岐へ配流になった後醍醐(ごだいご)帝の内親王。父帝を慕って車尾(くずも)まできたが、供を許されず、髪を切って尼僧となり、隠岐の見える地に庵(いおり)を結んだ。あるとき、栗を献じられ、この栗が芽生えたなら父帝の還御がかなうであろうと、栗を皮のままかみ砕き、祈願を込めて植えたのが芽生えて実を結んだという。県西部の豪円山(ごうえんざん)(大山(だいせん)町)の山頂に「豪僧豪円」の地蔵が立っている。関ヶ原の戦い後の国替のとき、米子中村藩は大山寺領の取り込みを図った。住職の豪円はその圧力に屈せず抗議し、その怨念(おんねん)によって藩主は死に中村氏は断絶し、寺領は安堵(あんど)になったという。県東部の岡益(おかます)の里(鳥取市国府町)に「安徳(あんとく)天皇御陵参考地」がある。台地にある謎(なぞ)の石堂が陵墓に擬せられたのは明治になってからのことである。平家一族とともに海底に沈んだ幼帝の後を追った祖母二位局(にいのつぼね)は、泉ヶ谷に葬られたと伝えている。鳥取砂丘の裏に「多鯰ヶ池(たねがいけ)」という池がある。宮下の長者の娘お種は、前世の因縁により大蛇になる宿命にあり、あるとき池に飛び込んでそこの主(ぬし)になった。それからその池を多鯰ヶ池とよぶようになったという。湯梨浜(ゆりはま)町に羽衣石(うえし)という地名があり、付近の大岩は天女が羽衣(はごろも)を干した所と伝えている。天女は羽衣を隠した男の女房になって子を生(な)したが、やがて羽衣をみつけだして天へ帰るという、諸国にある「天人女房」と同じである。
[武田静澄]
『『鳥取県史』全18冊(1967~1982・鳥取県)』▽『四宮守正著『日本の民俗 鳥取』(1972・第一法規出版)』▽『岩永實著『鳥取県地誌考』(1978・記念論文集刊行会)』▽『野津龍著『生きている民俗探訪 鳥取』(1982・第一法規出版)』▽『『角川日本地名大辞典31 鳥取県』(1982・角川書店)』▽『野田久男・清水真一著『日本の古代遺跡9 鳥取』(1983・保育社)』▽『『鳥取県大百科事典』(1984・新日本海新聞社)』▽『『日本歴史地名大系32 鳥取県の地名』(1992・平凡社)』▽『豊島吉則編『ビジュアルにっぽん再発見鳥取県』(1997・同朋舎)』▽『内藤正中他著『鳥取県の歴史』(1997・山川出版社)』▽『平山輝男他編『鳥取県のことば』(1998・明治書院)』
鳥取(市)
とっとり
鳥取県東部に位置する市。県庁所在地。市域北部は千代(せんだい)川下流域に形成された鳥取平野、千代川の埋積作用や砂丘の発達などで埋め残された潟湖(せきこ)の湖山(こやま)池、日本海沿いに発達した鳥取砂丘(国指定天然記念物)、河内(こうち)川、勝部(かちべ)川、日置(ひおき)川の流域などからなり、南部は中国山地と山地から流出する河谷からなる。また、南西部は岡山県と、東部は兵庫県と接し、東縁の扇ノ山(おうぎのせん)西麓(ろく)は、県内で大山(だいせん)に次ぐ深雪地である。鳥取砂丘など海岸部一帯は山陰海岸国立公園に含まれる。
1889年(明治22)市制施行。1923年(大正12)富桑(ふそう)村、1932年(昭和7)稲葉村、1933年中ノ郷、美保(みほ)の2村、1937年賀露(かろ)村、1953年倉田(くらだ)、面影(おもかげ)、神戸(かんど)、大和(やまと)、美穂(みほ)、東郷(とうごう)、大正(たいしょう)、千代水(ちよみ)、豊実(とよみ)、明治、松保(まつほ)、湖山、大郷(おおさと)、吉岡(よしおか)、末恒(すえつね)の15村、1955年米里(よねさと)村、1963年津ノ井村を編入。2004年(平成16)岩美(いわみ)郡の国府町(こくふちょう)、福部村(ふくべそん)、八頭(やず)郡の河原町(かわはらちょう)、用瀬町(もちがせちょう)、佐治村(さじそん)、気高(けたか)郡の気高町(けたかちょう)、鹿野町(しかのちょう)、青谷町(あおやちょう)を編入。なお、この合併により気高郡は消滅した。2005年特例市、2018年中核市に移行。JR山陰本線と因美(いんび)線、国道9号、29号、53号、482号、鳥取自動車道、青谷・羽合(はわい)道路、鳥取西道路などが通じる。鳥取空港があり、東京と結ばれている。面積765.31平方キロメートル、人口18万8465(2020)。
[岩永 實]
歴史
鳥取の地名は『古事記』の垂仁(すいにん)天皇の条に記される「鳥取部(ととりべ)」(水鳥などを捕(と)る部民)が居住した地とされ、『倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)(和名抄)』の鳥取郷の地。古い歴史をもち、縄文・弥生(やよい)期の直浪(すくなみ)遺跡、縄文期の栗谷(くりたに)遺跡などがある。国府地区は因幡(いなば)国府所在地であり、奈良から鎌倉時代に栄えた。周辺の丘陵地には古墳群が多く、魚、サギ、舟などの線刻装飾古墳もあり、魚などを描いた彩色壁画のある梶山古墳(かじやまこふん)や宮下(みやのした)の火葬墳伊福吉部徳足比売(いふきべのとこたりひめ)墓跡、中郷(ちゅうごう)付近の条里遺構中に発掘確認された因幡国庁跡などは国の史跡に指定されている。1466年(文正1)ごろ因幡の守護山名(やまな)氏は天神(てんじん)山城(鳥取市)に本拠を構えたが、1545年(天文14)山名誠通(のぶみち)は約6キロメートル東方の鳥取久松山(きゅうしょうざん)に出城を築き、1573年(天正1)山名豊国(とよくに)はこの城を本城とした。鳥取城下町の始まりである。1580年鳥取城は羽柴(はしば)秀吉により攻略され、一時毛利(もうり)方の吉川経家(きっかわつねいえ)が城主となったが、1581年経家も秀吉の攻撃を受け落城した。江戸時代は1617年(元和3)姫路から入封した池田光政(みつまさ)が鳥取城主となり32万石を領有、1632年(寛永9)には岡山藩の池田光仲が移封され、廃藩置県まで池田氏の治下にあった。鳥取城の南方に掘削された外濠袋川(ふくろがわ)は千代川河口の外港賀露に通じ、川舟や筏(いかだ)が往来した。用瀬地区は、天正(てんしょう)年間(1573~1592)には景石(かげいし)城があり、近世は智頭(ちず)街道の宿場町。鹿野地区は、1580年(天正8)以降亀井(かめい)氏3万8000石の城下町であったが、1617年(元和3)石見(いわみ)(島根県)津和野(つわの)へ移封、後、鳥取藩領となり、在町(ざいまち)化した。城跡や町割、町名などに亀井氏時代の名残(なごり)をとどめる。青谷地区は、奈良時代の山陰道の古駅で、江戸時代も宿場町であった。
なお、江戸時代の中心街は鹿野(しかの)街道沿いであるが、明治になって中心は東方の智頭街道沿いに移り、明治末の山陰本線鳥取駅の設置で若桜(わかさ)街道沿いが中心街となった。1978年(昭和53)には鳥取駅の高架化で駅周辺が市の中心となった。鳥取市街は低湿地にあり、大正期までしばしば水害にみまわれた。1943年(昭和18)には鳥取地震、1952年にはフェーン現象による大火災にあうなど大きな災害にみまわれたが、耐震・耐火都市に変わった。その後、面積約300ヘクタール、計画人口約6500人のニュータウンの建設や鳥取都市計画などが行われた。
[岩永 實]
産業
城下町であり、第二次世界大戦前までは消費都市的傾向にあり、工業も食品、木工、製糸に限られたが、戦後、鳥取三洋(さんよう)電機や日立(ひたち)金属、グッドヒルなど電機・繊維縫製品工業の町となった。製造品出荷額は県内有数。砂丘地帯では1955年(昭和30)から近代的な灌漑(かんがい)技術により畑地農業が安定した。近年は住宅地化が著しい。鳥取(賀露)港は沿岸・沖合漁業の基地で、カレイ、ハタハタ、ズワイガニなどの水揚げがある。環日本海諸国との貿易の拠点となる1万トン岸壁がある。船磯(ふないそ)と酒津(さけのつ)は江戸時代からの漁村で、夏泊(なつどまり)は海女(あま)漁業で知られる。農業は、水稲と果樹栽培を中心に、野菜・花卉(かき)栽培、畜産が盛ん。とくにナシ栽培は有名で、砂丘畑地利用のラッキョウ(砂丘らっきょう)やメロン栽培も知られる。古くから因州紙(いんしゅうがみ)の産地として知られ、現在も因州和紙の製造が行われている。「因州青谷こうぞ紙」「因州佐治みつまた紙」は県の無形文化財。鳥取砂丘、浜村温泉、鹿野温泉などの観光資源にもめぐまれ、観光も主産業となっている。千代川はアユ釣りが盛んでアユ料理が名物。佐治川は水石・庭石用で有名な佐治川石の産地。
[岩永 實]
文化・観光
久松山鳥取城跡(国の史跡)は山上(さんじょう)の丸に戦国時代の山城(やまじろ)城郭、山下(さんげ)に近世の城郭が残っている。内堀内には県立博物館と明治時代の洋風建築仁風閣(じんぷうかく)(国の重要文化財)がある。上町(うえまち)の鳥取東照宮(旧、樗谿神社(おうちだにじんじゃ))はかつて因幡東照宮とよばれた神社で、その本殿、拝殿および幣殿、唐門、学行院(がくぎょういん)の木造薬師如来(やくしにょらい)および両脇侍坐像・吉祥天像、常忍寺の絹本着色『普賢十羅刹女(ふげんじゅうらせつにょ)像』、福田家住宅などは国の重要文化財。国史跡には、布勢(ふせ)古墳、栃本(とちもと)廃寺跡、鳥取藩主池田家墓所などがあり、観音院庭園は江戸中期の作庭で国の名勝。「因幡(いなば)の菖蒲(しょうぶ)綱引き」は国の重要無形民俗文化財に指定されている。因幡の白兎(しろうさぎ)神話の白兎(はくと)海岸は、ハマナスの自生南限地帯として国指定天然記念物。砂丘上には白兎神を祀(まつ)る白兎(はくと)神社があり、その樹叢(じゅそう)は国指定天然記念物となっている。ほかに、松上神社のサカキ樹林、キマダラルリツバメチョウ生息地などの国指定天然記念物がある。このほか藩主池田氏の菩提(ぼだい)寺興禅寺(本堂は国の登録有形文化財)などがある。「大和佐美命(おおわさみのみこと)神社の獅子舞(ししまい)」「越路(こえじ)雨乞踊(あまごいおどり)」「円通寺人形芝居」「因幡の傘踊」「宇倍(うべ)神社獅子舞(ししまい)」「細尾(ほそお)の獅子(しし)舞」「余戸(よど)の雨乞(あまごい)踊」「日置のはねそ踊」、人形(ひとがた)に穢(けがれ)を託して川に流す「用瀬のひな送り」、2夜3日間潔斎(けっさい)した神官が、的を弓で射て五穀豊穣(ほうじょう)を祈る姫路神社の「百手の神事(ももてのしんじ)」は県指定無形民俗文化財。このほか8月16日の「鳥取しゃんしゃん祭」などがある。
岡山県境に近い佐治川の原流、谷奥の辰巳(たつみ)峠付近には堆積(たいせき)型ウラン鉱床、景勝地山王(さんのう)滝や猿渡(さるわたり)渓谷が、曳田(ひけた)川上流には三滝渓(みたきけい)がある。長尾(ながお)岬の付け根にある魚見(ようみ)台は好展望点。岬の突端の長尾鼻(ながおばな)は日本海に迫る安山岩質の溶岩台地で、39万カンデラの長尾鼻灯台がたつ。田岡神社のツバキ樹林、犬山(いぬやま)神社社叢(しゃそう)、坂谷(さかだに)神社社叢は県指定天然記念物。稲葉(いなば)山(因幡山(いなばのやま))は在原行平(ありわらのゆきひら)の和歌とゆかりが深い。八上(やかみ)の売沼神社(めぬまじんじゃ)は『古事記』の因幡の白兎神話に出る八上比売(やかみひめ)を祀(まつ)る。牛戸(うしと)は民芸の牛ノ戸焼の発祥地。浜村は民謡『貝殻節』で知られた温泉町。市内には荒木又右衛門(あらきまたえもん)や渡辺数馬(わたなべかずま)、後藤又兵衛(またべえ)(後藤基次(もとつぐ))、亀井茲矩(これのり)、山中鹿介(しかのすけ)らの墓所がある。ほかに、冬季に水鳥の飛来で知られる水尻(みずしり)池、因幡万葉歴史館、製紙用具などが特色の佐治歴史民俗資料館、山根和紙資料館などがある。鳥取市歴史博物館に収蔵・展示されている栗谷遺跡出土品は国の重要文化財。1994年(平成6)に天文台や宿泊施設を備えた「さじアストロパーク」が開館した。市街地南西方には県立の布勢(ふせ)総合運動公園、湖山池の青島公園や吉岡温泉がある。湖山池東方には鳥取大学が、市街地南東方には公立鳥取環境大学が立地する。
[岩永 實]
『『鳥取市誌』1~4巻(1972~2003・鳥取市)』▽『『新修鳥取市史』1~3巻(1983~1988・鳥取市)』
鳥取
とっとり
北海道東部、釧路(くしろ)市の一地区。1949年(昭和24)釧路市に合併。1884年(明治17)から翌年にかけて、鳥取士族105戸、513人が入植し、開拓に従事したことから、この地名が生まれた。大正年間から製紙工場も置かれた。釧路川西岸一帯を占め、現在の釧路市街地の一部を構成している。
[進藤賢一]
改訂新版 世界大百科事典 「鳥取」の意味・わかりやすい解説
鳥取[県] (とっとり)
基本情報
面積=3507.28km2(全国41位)
人口(2010)=58万8667人(全国47位)
人口密度(2010)=167.8人/km2(全国37位)
市町村(2011.10)=4市14町1村
県庁所在地=鳥取市(人口=19万7449人)
県花=二十世紀ナシ
県木=ダイセンキャラボク
県鳥=オシドリ
中国地方の北東部に位置する県。北は日本海に面し,東は兵庫県,南は岡山県,西は島根県,南西は広島県に接している。東西の長さ約170km,南北の幅は20~40kmで,東西に細長い県である。
沿革
県域はかつての因幡(いなば)・伯耆(ほうき)両国全域にあたり,ほぼ江戸全期を通じて池田氏の鳥取藩の支配下にあった。明治になって鳥取藩は支藩の鹿野・若桜(わかさ)両新田藩,および播磨国の福本藩(1868立藩)を吸収したが,71年(明治4)廃藩置県によって鳥取県となった。同年播磨国分を姫路県に分離し,島根県から隠岐国を併合したが,75年廃県となって島根県に合併された。80年因幡・伯耆両国をもって鳥取県が再置され,現在の県域が確定した。
鳥取県の遺跡
米子平野,倉吉平野それに鳥取平野など平野部を中心に,おもに弥生時代以降の遺構が分布することが特徴である。
その中で目久美(めぐみ)遺跡(米子市)は縄文時代の遺物(爪形文土器,条痕文土器,玦状(けつじよう)耳飾など)も出すが,弥生前期を中心とする大規模な遺跡である。福市遺跡(米子市)は弥生後期から古墳時代にかけての竪穴住居址152をはじめ,古墳6,横穴14,土壙墓28などからなる。青木遺跡(米子市)も弥生時代から奈良時代にわたる住居,墳墓などを含む。西桂見遺跡(鳥取市)では全国で最大級とみられる弥生時代末の,日本海側に特有の,いわゆる四隅突出型墳が確認されている。角田(すみだ)遺跡(米子市)では,太陽,舟,家,森,鹿などをパノラマ式にへら描きした貴重な弥生中期の土器(大型甕)が出土している。
古墳時代では,5基の前方後円墳などからなる馬山(うまのやま)古墳群(東伯郡湯梨浜町)が重要であるが,なかでも最大の4号墳は推定全長110mの前方後円墳で山陰前期古墳の代表例。国分寺古墳(倉吉市)も全長60mの前方後円墳で,舶載鏡や多くの鉄器をもつ4世紀後半の遺跡である。糸谷(いとや)古墳(鳥取市)も4世紀代で,ことに3号墳では石棺5,土坑墓2があり,1棺に4体などの合葬例があって注目される。長瀬高浜遺跡(東伯郡湯梨浜町)は,海岸砂丘下に埋もれていた特殊な遺跡として注目されていたが,調査の結果,弥生前期の土坑墓群から古墳時代前期~中期初頭の集落,中期の古墳群,中期前半ごろの祭祀址らしい埴輪群,さらに中世の墓地にわたる大遺跡であることが判明した。なかでも古墳時代中期の径33mの円墳(1号墳)は,墳頂に成人女性を被葬者とする石棺,墳丘周囲には幼児の小型石棺や円筒埴輪棺を配置するという珍しい構造をもつ。従来,山陰では鷺山古墳(鳥取市)のように魚文などを線刻で描く壁画古墳は知られていたが,終末期の円墳,梶山古墳(鳥取市)では,魚文,三角文,同心円文などが彩色で描かれている。この梶山古墳のすぐ近くにある6世紀から7世紀前半と目される石造遺構,〈岡益(おかます)の石堂〉(鳥取市)や石馬谷(いしうまだに)古墳(米子市)の〈石馬〉など,この地方独特の,大陸の影響をうかがわせる特殊な遺構も少なくない。陰田(いんだ)遺跡(米子市)は漢字らしい文字のへら書きされた6世紀後半ごろの須恵器が出土していて注目される。
歴史時代では,和銅3年(710)10月などの年号の刻まれた銘をもつ鋺(わん)形蔵骨器で有名な伊福吉部徳足比売(いほきべのとこたりひめ)の墓(鳥取市),法隆寺式伽藍配置をもつ白鳳時代寺院址の斎尾(さいのお)廃寺(東伯郡琴浦町),同じく白鳳時代と思われるが,東面し,南に金堂,北に塔を置くやや特異な伽藍配置をもつ大寺(おおでら)廃寺(西伯郡伯耆町),それに康和5年(1103)銘のある銅製経筒をはじめ金銅菩薩像2,銅板線刻弥勒像1,銅鏡2,檜扇残片,刀子片,瑠璃玉,北宋銭2,漆器片などを出土したことで著名な一宮経塚(東伯郡湯梨浜町)などがある。
→因幡国 →伯耆国
執筆者:狐塚 裕子
砂丘と火山
県域の大部分を山地が占め,林野率は7割以上に達する。南部の岡山県との県境をなす中国山地は,日本海側では一般に急斜面が卓越するが,山頂部に多少の平たん部を有する。山頂部の標高は1000~1300m,扇ノ山(おうぎのせん)(1310m),氷ノ山(ひようのせん)(須賀ノ山。1510m),道後(どうご)山(1271m)など標高1200mを超える山が10座にのぼる。山地は杉,ヒノキなどの林業地として利用され,扇ノ山,氷ノ山,三国山などにはブナの自然林が残されている。
県西部の大山(だいせん)は伯耆富士とも呼ばれ,中国地方随一の標高を誇る二重式火山で,直径30kmを超す雄大なすそ野を有している。山頂部は顕著な浸食作用によってやせ尾根となり,西日本には珍しいアルプス的な地形を示している。冬季,標高900m以上の山地では2mを超す積雪があり,火山斜面の多くは絶好のスキー場となる。大山から噴出した多量の火山灰は,広く県下の台地などを被覆しており,その表層は黒ボク土化している。黒ボク土は酸性のため土壌改良を必要とし,また風害や干害を受けやすかった。火山としては大山のほかに,東部の扇ノ山,氷ノ山,中部から西部にかけて蒜山(ひるぜん)などの火山がある。
低地は砂丘,砂州,沖積平野からなる。海岸線に沿って大小さまざまの砂丘が分布しているが,とくに倉吉平野と鳥取平野の海岸部にある北条砂丘と鳥取砂丘は最も規模が大きく,内部に岩盤や大山ロームより古い古砂丘が伏在しているため,起伏に富んだ砂丘地形を形成している。弓ヶ浜は長さ17.5km,幅3~5km,日本最大の湾央砂州で,〈大天橋〉と称揚される。このように砂丘や砂州が発達したのは,砂礫化した山地の花コウ岩や安山岩が河川によって搬出され,また,たたら製鉄用の砂鉄を採取する際に生じる多量の土砂が流出したことによる。
おもな沖積平野は,千代(せんだい)川下流の鳥取平野,天神川下流の倉吉平野,日野川下流の米子平野である。これらの沖積平野はかつては入江をなしていたが,砂丘や砂州の形成とともに潟湖となり,しだいに埋積されてきたものである。鳥取平野の湖山(こやま)池,倉吉平野の東郷池などは,そのような地形変遷のなごりである。したがって,自然堤防を除けば低湿地で,地盤が軟弱な場合が多い。
鳥取県は,冬季と6月,7月,9月に降水量が多く,〈因幡の雨,伯耆の風〉といわれるように,とくに東部で山陰型気候が顕著である。最大積雪量は鳥取市の129cmに対して米子市が80cm,年降水量は鳥取市の2018mmに対して米子市は1875mmである。一方,米子平野は西の出雲平野と連続し,東には大山のなだらかなすそ野が広がっているため,冬季は西風が卓越する。鳥取市の年平均気温は14.3℃,県域が南北に狭小なため気温の地域差は少ない。
二十世紀梨と砂地農業
県内の産業別就業人口は第1次産業14.0%,第2次産業30.4%,第3次産業55.5%(1995)で,全国的にみて第1次,第3次産業への依存度が高い。農家総数は約4万戸であるが,専業農家は1割にすぎない。鳥取県の農業はもともと米作を中心としてきたが,基盤となる沖積平野の面積が小さく,その発展には限界があった。第2次世界大戦後,大山山麓の黒ボク土地帯や海岸砂丘地の開発が進み,果樹や野菜の栽培,畜産が急速に伸展した。とくに二十世紀梨の栽培と砂丘地を利用する砂地農業は,鳥取県の農業の特色をなす。すぐれた風味をもつ二十世紀梨は,1904年に導入されて以来,栽培面積が拡大し,生産量は全国の二十世紀梨の生産量の首位,48.2%(1992)を占める。広大な砂州や砂丘地は,江戸時代には綿作やサツマイモが栽培され,明治以後は桑園として利用されてきたが,砂防林の造成,スプリンクラーによる動力灌漑の導入によって多彩な集約的土地利用が可能になり,タバコ,ネギ,ラッキョウ,ナガイモ,スイカ,ブドウなどの栽培が盛んに行われるようになった。鳥取県はかつては因伯牛の産地として知られたが,1957年を境に衰退し,代わって酪農,養豚,養鶏の比重が高まっている。林野は県域の3/4(1995)を占め,なかでも智頭(ちず)町は江戸時代以来,西日本有数の林業地で,製材工場が数多く立地している。かつて盛んだった木炭の生産は衰退し,近年は山村でシイタケ栽培が活発である。
漁業の比重は農業に比べて著しく低い。大和堆(やまとたい)や隠岐堆などすぐれた漁場をひかえているが,良港に恵まれず,零細経営が多い。その中にあって境港(さかいみなと)は天然の良港で,古くから西廻海運の寄航地,および漁港として栄え,日本海有数の漁業基地となっている。出荷額の1位はイワシ,2位はアジ,3位はスルメイカ(1995)で,沖合漁業が漁獲量の9割以上を占め,沿岸漁業は零細である。
低い工業水準
鉱業資源としてはクロム鉄鉱とウラン鉱がある。日南町多里のクロム鉄鉱山は,1900年ころ発見された日本の代表的なクロム鉄鉱床である。ウラン鉱は55年に岡山県境の人形峠付近で発見され,峠の岡山県側で粗製錬工場が操業している。
鳥取県の製造品出荷額は全国出荷額の0.4%にすぎず,47都道府県中44位である(1995)。業種別出荷額は,1965年には食品が首位を占め,木林,家具,紙・パルプなどを含む軽工業が8割以上を占めていた。その後,電気機械企業の進出などによって軽工業対重化学工業の比率は逆転し,現在は電気機械が首位で約4割を占め,食品,繊維・衣服,紙・パルプ,木材・家具がこれにつづく。伝統産業としては因州紙で知られる和紙製造,因久山(いんきゆうざん)焼,牛戸(うしのと)焼,上神(かずわ)焼などの窯業,弓ヶ浜絣などがあるが,いずれも規模が小さい。
山陰東部の交通と観光
東,西,南を山に閉ざされ,北は日本海に面し,しかも境港以外は良港に恵まれなかったため,明治期に鉄道が開通するまでの県外との交通は海陸両路ともきわめて不便であった。山陰本線が余部(あまるべ)橋の完成によって結ばれたのが1912年,ついで陰陽連絡線として伯備線(1928),因美線(1932)が開通した。また,94年12月の智頭急行智頭線の開通により,京阪神への時間が短縮された。国道もこれらの鉄道路線とほぼ並行し,山陰道として古くから利用されてきた9号線が海岸線近くを東西に走り,鳥取と姫路を結ぶ29号線,鳥取と岡山を結ぶ180号線などがほぼ南北に通じる。92年12月には大山の西~南麓をまわる米子自動車道が開通した。このような交通の整備に伴って,阪神経済圏との結びつきが強まってきている。空港は米子と鳥取にあり,東京,大阪への航空路が開かれており,また米子~隠岐間(98年より休止)も開かれている。
県の就業人口のうち,第3次産業が55.5%を占めていることからもうかがえるように,鳥取県の観光産業の比重は大きい。大山隠岐国立公園に含まれる大山火山群,山陰海岸国立公園に含まれる陸上(くがみ)鼻~鳥取砂丘の海岸部,氷ノ山後山那岐山国定公園に含まれる東部山岳地域,比婆道後帝釈国定公園に含まれる船通(せんつう)山,道後山など,すぐれた自然景観に恵まれている。また,岩井,皆生(かいけ),三朝(みささ)など10ヵ所にのぼる温泉地をかかえ,多くの保養客を集めている。
東部,中部,西部の3地域
県域は並走する千代川,天神川,日野川の3河川を中心として東西に並ぶ3地域に分けられる。
(1)東部地域 旧因幡国全域からなり,鳥取市を中心に岩美郡,八頭(やず)郡からなる。面積,人口とも県の約4割を占め,3地域中の首位であるが,人口密度は山地が多いため全県平均より低い。産業別就業人口の構成比では,3地域中で第1次産業が最低で,第2次産業が最高という点に特色がある。県庁所在地の鳥取市は1617年(元和3)以来,池田氏の城下町として栄え,米子,松江と並ぶ山陰の中心的都市の一つである。かつては消費型都市であったが,1966年に電気機械工場が進出して以来,工業化が促進された。食品,木材,家具,衣服,繊維などの工業も盛んである。千代川周辺の沖積平野は米作を中心として,海岸部の砂丘地では,福部砂丘のラッキョウをはじめ,タバコ,イチゴ,野菜などが各砂丘で栽培されている。周辺の丘陵地や山地の斜面は県中部の湯梨浜町の旧東郷町周辺とともに二十世紀梨の全国的な産地の一つとなっている。智頭町を中心とする南東部の山村地域は西日本有数の林業地として知られる。東部地域の漁港は賀露(かろ),網代(あじろ)を中心とし,夏はイカ釣り,冬はマツバガニ漁が行われる。また岩井,鳥取,吉岡,浜村などの温泉を有し,観光・保養地としても重要であり,白兎(はくと),浦富(うらどめ)の各海岸は海水浴場として有名である。
(2)中部地域 旧伯耆国の東半部を占め,天神川流域を主とし,大山北東麓の小河川流域を含む。行政上は倉吉市を中心に,東伯郡の町からなり,面積,人口(ともに県の約2割),人口密度とも3地域中最下位である。この地域の第1次産業人口の構成比は3地域中最上位を占め,農業依存の傾向が強い。中心都市の倉吉市は室町時代の守護大名の城下町として発達し,藩政時代は陣屋がおかれ,伯耆東部を後背地とする商業町として栄えた。明治以降は和鋼を原材とする稲扱千歯(いなこきせんば)や倉吉絣の生産地であったが,いずれも大正期には衰退した。現在は食品,電気機械,繊維,衣服などの工業が行われている。農業は米作の比重が低く,畜産,果樹,野菜など多角的な経営が行われている。北条砂丘ではタバコ,ブドウ,ナガイモが栽培される。大山北東麓の黒ボク土に覆われた台地は畑地として利用され,スイカ,梨,芝の栽培が行われている。また酪農,養豚,養鶏も卓越し,一時衰退していた和牛の飼育も漸増している。観光資源としては,修験道場として知られる三徳(みとく)山参詣に利用されてきた三朝温泉,関金(せきがね)温泉,東郷池湖畔の羽合(はわい)温泉(旧,浅津温泉),東郷温泉がある。
(3)西部地域 旧伯耆国の西半分からなり,日野川流域を中心に,大山北西麓の小河川流域を含む。行政上は,米子市と境港市を中心に西伯郡,日野郡の町村からなる。面積は全県の34%,人口は40%で3地域中第2位であるが,人口密度は最も高い。米子市は中世の城下町で,藩政時代は鳥取藩の陣屋がおかれ,弓ヶ浜の畑作地帯のワタを原料とする木綿,絣,日野郡特産の和鉄の集散地として栄えた。明治中期以後,その恵まれた立地条件によって山陰随一の商工業都市として発展,〈山陰の大阪〉と呼ばれた。近年は中海新産業都市の中核として,食品,木材,木製品,パルプ,繊維,鉄鋼,家電用モーターなどの工業が立地している。弓ヶ浜半島の北半部を占める境港市は,日本海屈指の漁港として,また貿易港として栄えている。この地域の農牧業は,米作を主とし林業を従とする南部地区,畜産を主とし集約的農業を営む北部地区,弓ヶ浜を中心にタバコ,ネギなど多角的な砂地農業を行う米子・境港両市近郊地区の3地域に大別される。観光資源としては大山,船通山,道後山などの景勝地を擁し,皆生温泉がその基地的性格をもっている。
執筆者:豊島 吉則
鳥取[市] (とっとり)
鳥取県東部に位置する県庁所在都市。2004年11月旧鳥取市が周辺の青谷(あおや),河原(かわはら),気高(けたか),国府(こくふ),鹿野(しかの),用瀬(もちがせ)の6町と佐治(さじ),福部(ふくべ)の2村を編入して成立した。人口19万7449(2010)。
青谷
鳥取市北西端の旧町。旧気高郡所属。人口8095(2000)。日本海に面し,町域の三方を中国山地の山々に囲まれて勝部・日置両川沿いの谷と合流点付近の平野部に集落が分布する。中心の青谷は両河谷の集落を後背地に発展した谷口集落で,《延喜式》の柏尾駅の所在地と推定されている。天正年間(1573-92)は亀井氏領の外港として朱印船貿易が行われ,江戸時代は宿場町,藩倉所在地として栄えた。現在は旧鳥取市と倉吉市の中間にあって商業も盛ん。平たん地での米作と山麓の梨栽培を中心とする農業が基幹産業で,日置川上流の山根,早牛は伝統的な因州紙の産地である。日本海に突出した大海食崖の長尾岬は釣りの好適地で,夏泊は海女の村である。国道9号線(旧山陰街道),JR山陰本線が通る。
河原
鳥取市中部南寄りの旧町。旧八頭(やず)郡所属。人口8382(2000)。町域には中国山地の山地帯が広く分布し,北東部で曳田(ひけた)川,八頭川が千代(せんだい)川に合流,合流点付近に中心集落の河原がある。河原の地名ははんらん原に立地したことに由来し,千代川の渡河集落として発達,江戸時代には上の茶屋と呼ばれた。千代川西岸には慶長年間(1596-1615)に着工された大井手川用水の取水口があり,樋口神社がまつられている。アユ漁,酒造が盛んで,散岐(さんき)・国英(くにふさ)地区の山麓部では御所柿,二十世紀梨の栽培が行われる。民芸陶器牛戸焼の特産がある。曳田川上流は三滝渓の景勝地で,曳田は《古事記》記載の八上比売と白兎の伝説の地といわれる。JR因美線,国道53号線が通じる。
執筆者:上田 雅子
気高
鳥取市北西部の旧町。旧気高郡所属。1955年浜村町と宝木,酒津,瑞穂,逢坂の4村が合体,改称。人口1万0004(2000)。日本海に面し,平滑な海岸に沿って浜村,宝木の砂丘があり,その南側には低湿な沖積平野や日光池,水尻池などの潟湖がみられる。中心の浜村は砂丘裏にある浜村温泉を核とした集落で,JR山陰本線浜村駅南側の勝見温泉(16世紀初めに開湯とされる)と北側の浜村温泉(1885年発見)からなり,明治末の鉄道開通以来,大きく発展した。単純泉,69℃。湯量が豊富で温泉プールもある。主産業は砂丘地での二十世紀梨,ブドウなどの果樹やタバコ,ラッキョウの栽培のほか,酒津,船津の2漁港を利用した沖合漁業である。民謡《貝殻節》は,かつて沖合でイタヤガイ漁が盛んであった際に歌われた労働歌で,今も広く愛誦されている。
執筆者:豊島 吉則
国府
鳥取市東部の旧町。旧岩美郡所属。人口8620(2000)。千代川支流の袋川流域に位置し,町域は扇ノ山(おうぎのせん)西麓の山地と鳥取平野の一部をなす低地からなる。古代から中世にかけて因幡国の政治・文化の中心地で,国府や国分寺が置かれ,今も庁,国分寺,法花寺などの字名が残る。平野部には条里遺構がみられ,推定国分寺跡,因幡一宮の宇倍神社,伊福吉部徳足比売墓跡(史)などがある。農林業を基幹産業とするが,旧鳥取市に隣接する西部では旧鳥取市への通勤者も多く都市化が進む。扇ノ山一帯は氷ノ山後山那岐山国定公園に含まれ,雨滝がある。学行院の木造薬師如来,吉祥天立像などは重要文化財に指定されている。
執筆者:上田 雅子
佐治
鳥取市南西端の旧村。旧八頭郡所属。佐治川に沿って東西に細長くのびる。人口2835(2000)。近世前期に佐治郷22ヵ村では特産としての因州和紙の製造が盛んで,盛時には紙すき農家が200軒をこえた。昭和に入って減少し,現在は協同組合による書道用紙の生産に活路を見いだしている。果樹,とくに二十世紀梨の生産が多い。佐治川中流域では,庭石や水石とされる佐治石を産するが,現在は自然保護条例によって採石が禁じられている。三原高原,猿渡り渓谷,山王(三王)滝や原生林など景勝に富むので,レクリエーション地区としての発展がはかられつつある。
執筆者:豊島 吉則
鹿野
鳥取市西部の旧町。旧気高郡所属。人口4594(2000)。河内川上流域に位置し,旧鳥取市の西に接する。町域は大山火山帯に属する鷲峰(じゆうぼう)山のすそ野に広がり,北部に低地が開ける。中心集落の鹿野は交通・軍事上の要地にあたり,中世は志加奴氏が支配したが,戦国時代には山名,尼子,毛利各氏の争奪の地となった。1580-1617年(天正8-元和3)の間は亀井氏の城下町であったが,以後は鳥取藩領となり,城も破却された。明治中期から大正にかけて製紙や製糸が盛んであったが,第2次大戦後衰退した。米作,果樹園芸,畜産などの農業を基幹産業とし,林業も盛んである。鹿野笠,民芸能面,うちわの特産がある。鷲峰山北麓には鹿野温泉(国民温泉。単純泉,55~72℃)がある。
執筆者:上田 雅子
鳥取
鳥取市中北部の旧市で県庁所在都市。1889年市制。人口15万0439(2000)。市域は千代川下流部の鳥取平野と周辺の山地からなり,県の政治,経済,文化の中心的役割を果たしている。千代川東岸の低湿な三角州に位置する中心市街地は,近世には池田氏の城下町で,袋川下流部の河道を付け替え,池沼などを埋め立てて形成された。1871年鳥取県が成立したが,75年からの5年間は県全体が島根県の管轄下におかれ,松江に中心が移ったため,鳥取の町は一時さびれた。80年鳥取県が再置されて県庁所在地となり,再び発展した。96年岩倉に歩兵第40連隊が誘致され,1920年には鳥取高等農林学校(のちの鳥取大学)が創設された。1912年山陰本線,32年因美線が全通し,大正期から第2次大戦前までは蚕糸業や木工業が盛んとなった。戦後,鳥取大学が湖山地区に統合・移転し,その跡地に66年三洋電機が誘致された。以来工業化が進み,電気機器,金属,機械などが県の製造品出荷額の42.6%(1995)を占めている。農業は米作のほか,砂丘地におけるブドウ栽培,山麓部での二十世紀梨の栽培が盛んである。
旧鳥取市は災害の多い都市で,千代川やその東部を流れる支流袋川のはんらんによる水害が毎年のようにあったのも,地盤の低い地形環境を反映している。1943年には鳥取地震で倒壊家屋4500戸以上,死者1000人以上という大被害をうけた。52年におこった鳥取大火では,市の中心部がすべて灰となった。このようなたびたびの災害を教訓として,都市の不燃化,千代川や袋川の改修,排水溝とポンプ場の設置,下水道の整備などの対策がすすめられた。鳥取砂丘や湖山池,久松山と鳥取城跡(史),鳥取温泉,吉岡温泉などの観光地がある。
執筆者:豊島 吉則
歴史
古代の因幡国邑美(おうみ)郡鳥取郷は,江戸時代に池田光政が河道を付け替える以前の旧袋川(湊川)より内側の,久松山(きゆうしようざん)麓を中心とする地域に位置したと推定され,中世には鳥執とも記された。中世において鳥取郷(荘)の存在を史料によって確認することはできず,鳥取が一つの所領単位を構成していたかどうかは明らかでない。中世に鳥取なる地名が広く用いられるようになるのは,1545年(天文14)布施天神山城主山名誠通が久松山に城を築いてからのことで,これ以後久松山は鳥取山,城下を流れる袋川は鳥取河とも呼ばれるようになった。鳥取城には当初,武田氏が拠って城を整備したといわれるが,鳥取城およびその城下が本格的に整備され栄えるようになるのは,73年(天正1)の冬に山名豊国がここを本城としてからのことである。鳥取城は80年と翌年の2回にわたる羽柴(豊臣)秀吉軍の攻撃を受けて落ちたが,この城の占める政治的・軍事的位置の重要性が鳥取なる地名を定着させたものといえよう。
執筆者:井上 寛司 1581年に秀吉が鳥取城を攻略した後,但馬豊岡から城主として移封した宮部継潤(けいじゆん)は,上美(うわみ)(邑美),法美,八上,高草の4郡計4万3600石と但馬国二方郡7370石の合計5万0970石を領知し,城郭を強化し城下町を整備した。しかし継潤は秀吉に従って鳥取不在のことが多く,その養子長煕(ながひろ)(元房)が領内を取りしきった。継潤の没後,1600年(慶長5)の関ヶ原の戦で長煕は西軍に属したため改易となり,鳥取城は東軍側の鹿野城主亀井茲矩(これのり)らの軍勢によって接収され,翌01年新たに池田備中守長吉が巨濃(この),邑美,法美,八上の4郡6万石をあてがわれ鳥取に入部した。山上の本丸天守閣の改築や城郭の拡張を行い,亀井氏の軍勢の鳥取城接収の小ぜりあいで焼かれた町の修復などの工事もした。また,鳥取の外港賀露(かろ)の地を亀井茲矩との領地交換によって支配下に収め,その整備・活用によって城下町の繁栄をはかった。このほか,千代川の堤防の強化を行い,領民を洪水の災害から守ったと伝えられる。17年(元和3)池田光政が播磨国姫路から鳥取に転封され,因幡・伯耆両国32万石を支配することになり,多数の家臣たちと入部し,やがて城郭の整備や,城下町とくに侍町の拡張を行った。旧袋川の南方に新たに河道を掘削して,それを袋川とし,城の外構すなわち防御用の堀および城下町と外港賀露との運河の役割を果たさせることにし,城郭に接近していた寺院・町家をその土手の近くに移し,跡地は侍町(武家屋敷)とした。光政の治政15年ののち,32年(寛永9)備前岡山城主池田光仲が,従兄にあたる光政と交替して転封し鳥取城主となり,以後12代慶徳まで因・伯両国を支配した。入部のとき,小者らを含む家臣ら約2800人(《保定纂要》巻二)とその家族,慶安寺など寺院や御用達商人などが随従した。
鳥取城下の武家人口は寛延(1748-51)ごろ約2万人,1870年(明治3)には士族・卒族とその家族あわせて3万2810人で,町家人口は1749年1万3125人,1810年(文化7)1万0228人,46年(弘化3)1万1440人,69年1万1574人であった。町数は1634年(寛永11)40,1778年(安永7)48で,町割りは大手を基点とする智頭(ちず)街道を基線に,西の鹿野街道,東の若桜(わかさ)街道が並行して南北方向にそれぞれ走り,それらに直交して東西に走る元大工町,上魚町,片原一丁目~同三丁目,本町一丁目~同四丁目などの町々があった。また前後約17回にもおよぶ大火があり,1724年(享保9)の黒川火事は最大の被害(焼失町数34,家数1065,竈数2651,侍屋敷数111,寺数2)を出し,1819年(文政2)の大路屋火事の被害(焼失町数14,家数およそ429,竈数およそ429,侍屋敷数8)も大きかった。町政組織としては町奉行(2名)のもとに,自治が許されて惣町を管轄する町年寄(2~4名)とそれを補佐する町代,各町の代表として町政にあずかる目代(1名)があった。
→鳥取藩
執筆者:山中 寿夫
福部
鳥取市北東端の旧村で,日本海に面する。旧岩美郡所属。人口3451(2000)。村域は鳥取砂丘の一部をなす福部砂丘,沼沢地を干拓してできた低湿水田地帯,東部・南部の山地からなる。直浪(すくなみ)遺跡,栗谷遺跡など縄文~古墳時代の遺跡が多い。古くから開発が進み,古代は《和名抄》記載の服部郷の地で,中世には服部荘が成立し,江戸中期以降細川池,湯山池などの干拓が進んだ。農業が主産業で,砂丘ではラッキョウ栽培,山麓部では二十世紀梨の栽培が盛んである。海士(あもう)と県(あがた)がラッキョウ栽培の中心で加工場がある。沿岸部一帯は山陰海岸国立公園に含まれる。国道9号線,JR山陰本線が通る。
用瀬
鳥取市南端の旧町。旧八頭郡所属。人口4324(2000)。千代川中流域に位置し,町域には中国山地に属する山地が広く分布する。中心の用瀬は千代川と支流佐治川との合流点に形成された谷口集落であり,近世には上方往来の街道筋に当たる宿場町として栄えた。高瀬舟水運の起点でもあり,2・7の六斎市も開かれた。農林業が主産業で,山林開発が進められ,製材業が行われる。かつては柳行李と茶の特産があり,金屋では鋳物製造が行われた。国道53号線,JR因美線が通じる。
執筆者:上田 雅子
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「鳥取」の意味・わかりやすい解説
鳥取[県]【とっとり】
→関連項目山陰地方|中国地方
鳥取[市]【とっとり】
→関連項目鳥取[県]|鳥取大学
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内の鳥取の言及
【賀露】より
…因幡国(鳥取県)高草郡に属し,千代川河口の港。《三代実録》に861年(貞観3)賀露神に従五位下を授くとあり,《因幡堂縁起》によれば997年(長徳3)賀留の沖で薬師如来像が漁網にかかり,海中から引き揚げられ,因幡守橘行平によってまつられたという。…
【鳥取[県]】より
…面積=3507.01km2(全国41位)人口(1995)=61万4929人(全国47位)人口密度(1995)=175人/km2(全国37位)市町村(1997.4)=4市31町4村県庁所在地=鳥取市(人口=14万6330人)県花=二十世紀ナシ 県木=ダイセンキャラボク 県鳥=オシドリ中国地方の北東部に位置する県。北は日本海に面し,東は兵庫県,南は岡山県,西は島根県,南西は広島県に接している。…
※「鳥取」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...


 鳥取県東部の市。
鳥取県東部の市。