脊椎動物が呼吸気を利用して発声器官を振動させて生じる音。このような音を発することを発声phonationという。発声は起源においては生殖と密接な関連があり,これが動物の集団生活において,仲間どうしの合図や,他に対する威嚇に用いられるようになるが,さらに高等動物では意志や感情の表現に用いられ,人間では言語音の発生となって,複雑な精神内容の表現も可能となっている。しかし,男女の声の違いや,二次性徴での〈声変り〉現象は,声の起源が生殖と密接な関連をもっていることを物語っている。なお,ヒト以外の動物の発声については〈発音器官〉の項を参照されたい。
ヒトの声
ヒトの声は声帯でつくられる。声帯は喉頭の内腔にある1対のひだで,声を出そうとすると,喉頭の筋肉の働きで,左右から正中線に寄ってきて,肺からの呼気を遮断するようになる。すると声帯より下方の圧力(声門下圧)が高まって,声帯を押し開こうとする。つまり声帯のところで,声帯を閉じようとする力と押し開こうとする反対方向の力が働くことになる。ここで下側の圧がさらに増すと左右声帯の間にすきまを生じ,ここを呼気が流れ出る。しかし同時に,下側の圧力がいったん下がって声帯は再び閉じてくる。しかもこのとき呼気の流れによって声帯が内側に吸い寄せられる現象も起こって,声帯の閉じる傾向が強められる。声帯がこのようにして閉じてしまうと,状態はまたもとに戻って下側の圧力の上昇が起こる。このように声帯のいちばん内側のふちのところは開いたり閉じたりという,一種の振動現象を呈し(声帯振動),そのつど少量ずつ呼気の流れが断続的に声帯より上方へ出ていくことになる。音というのは空気の疎密波であるから,声帯のすぐ上側のところで上に述べた原理で断続的な呼気流による疎密波が生ずると,これが周りの空気中へ伝播して音として聞こえるようになる。これが声である。この場合,声帯のところで生じた音は,咽頭や口の中などの共鳴腔を通り,この共鳴腔の形に応じた音色をもって口から外へ出ていくわけである。したがって声は,音叉(おんさ)でつくられるような純音ではなく,多くの倍音に富んだ複合音である。声の生成を別の表現でいえば,肺からの呼気の流れがもつ運動のエネルギーが,声帯のところで変換されて音のエネルギーとなって声として外へ出ていくということになる。
音としての声
このように,声は音の一種であるから,その性質として高さや強さという要素をもつ。声の高さは,声帯の振動数,すなわち1秒間に何回声帯が開閉して疎密波を生じたかで決まる。声の強さは,声帯が閉じる強さや,下方からの気流の圧力によって決まる。そのほか声が口から出てくるときにはことばの音としての音色をもつが,〈アー〉とか〈エー〉とかいうような母音の音色は喉頭より上側の共鳴腔の形で決まる。ことばには母音のほかに子音という成分があるが,これは喉頭のみでなく,舌,あご,くちびるなどの共鳴腔をつくっている器官がすばやい,しかも複雑な運動をすることによって生ずる。このような母音や子音が多数組み合わされて,ことばの音としての特徴をもって他人に伝えられるのである。
声とことば
人間以外にも声を出す動物は多い。サル,イヌ,ネコなどの哺乳類が声を出すメカニズムは人間と同じで,やはり声帯の振動を生じ,呼気流が断続されて声となる。ところが鳥では,喉頭より下方の,気管が左右に分かれる部分の近くに鳴管と呼ばれる部分があって,この部の膜の振動によって声を生ずる。人間以外の動物がことばをしゃべる能力をもっていないのは,根本的には脳の発達が不十分で,ことばという記号体系をあやつれるだけの知能がないからと考えられている。しかしかなり高度の知能をもつ類人猿の仲間では,発音器官の構造や動きに限界があるために,ことばの音がつくり出せないのだという主張がある。これは,類人猿の咽頭や口腔などを含む共鳴腔の形を,舌の運動能力などによってどのように変化させうるかを推定し,電子計算機を用いて,この共鳴腔で生ずる音の性質を調べた研究にもとづくもので,結論として,類人猿の場合でも人間と同じような音色をもつ,何種類もの母音をつくることは不可能であるという。
男の声と女の声
男女の声の違いは,主として声の高さの差による。子どもでは男女の差がないが,思春期になると男子では喉頭の軟骨が急成長し,声帯が長くなり,また厚みを増して声が低くなる。このような変化は男性ホルモンの作用によって起こり,これが〈声変り〉と呼ばれる現象である。声変りの結果男の声は,話声の範囲では女より約1オクターブ低い。
もちろん男でも女でも,ある範囲内で声の高さを変えることができる。この範囲を声域といい,男のほうが低いほうにずれている。高い声を出そうとすると,喉頭の筋肉の一つである輪状甲状筋と呼ばれる筋が働いて声帯を前後方向に引き伸ばし声帯の緊張が高められる。このとき声帯のいちばん内側の振動部分が薄くなり,質量が減って声帯の振動数が増し,声が高くなるのである。声を高くしていくとき,ある範囲の高さまでは声帯の内部にある声帯筋もだんだんに緊張を増して,声帯も比較的厚く,声帯も正中線で十分に閉じる。この範囲の声を〈地声〉という。しかし,ある高さを超えると声帯筋の働きが弱まり,声帯は急に薄く引き伸ばされるようになって閉じ方も不完全になる。このような状態で出る声を〈裏声〉という。前に述べた声域とは地声と裏声をあわせた範囲をさしている。地声,裏声の区別は男のほうが女よりはっきりしている。
子どもの声の高さと女の声の高さにはあまり差がないが,共鳴腔の大きさが違うので,音色は異なって聞こえる。テレビの漫画番組などで,成人女性が子どもの声のまねをすることがあるが,このようなときには,共鳴腔を縮めるようなくふうをして,子どもらしい声をつくろうとしていることが知られている。
声の病気
ある人の声が,その人の年齢や性などからみて不自然であるような性質をもっていれば,声の異常があると判断する。一般に声の異常としては,声がかれるとか,声がかすれるとか表現される状態が多く,これは声の音色の異常が起こっているもので,このような異常な声を総称して嗄声(させい)と呼んでいる。
嗄声は,声帯に病的な変化があって声帯の振動が不規則になったり,声帯が十分に閉じないで呼気がもれてしまうようなときに起こる。このような声を耳で聞くと,ざらざらした印象や,かすれたような印象をうける。声帯の振動の異常や,閉じ方の異常を起こす原因としては,癌などの悪性腫瘍,声帯の炎症,声帯ポリープや声帯結節などと呼ばれる声帯の良性限局性腫張,あるいは喉頭筋の麻痺による声帯の運動障害などがある。
一方,声の音色に変化がなくとも,たとえば男が非常に高い声で話したり,女が男のように低い声を出すのも,声の高さの異常の一種と考えられる。声の高さの異常としては,男子で声変りの時期になって喉頭軟骨が成長しても,いつまでも子どものように高い声で話す例があり,これを声変り障害と呼ぶ。こういう例では喉頭に形態的変化が起きてからも,喉頭の筋肉の調節がうまくできず,一種の裏声発声を続けている状態と考えられる。声変り障害は発声訓練で治癒することが多い。男の子で男性ホルモンの欠乏があると,思春期になっても喉頭が成長せず声変りも起こらない。
女が男性化作用のある薬剤を内服したり注射をうけたりすると,一種の声変り現象が起こり,声が低くなることがある。この種の薬剤としては,タンパク質同化ステロイドや,男女混合ホルモン剤があげられる。このような低音化はなかなか元に戻りにくいので,薬剤使用にあたって注意が必要である。
声帯に見かけ上まったく異常がなくても,声に変化を起こすことがある。その多くは心理的原因によるもので,心因性発声障害と総称することがある。たとえば,ヒステリーの一症状として,まったく響きのある声が出せず,ささやき声(すなわち声帯の振動しない状態)でしか話せない状態もある。これを心因性失声症と呼ぶ。このほか,のどがつまってしぼり出すようなふるえ声になってしまう状態もあり,痙攣(けいれん)性発声障害と呼ばれる。
喉頭に癌が発生して,放射線治療などでは処置することができず,手術的に喉頭をとり去ってしまう必要がある例がある。このような手術(喉頭全摘術)をうけると,発声器官としての喉頭がなくなり,気管の切断端をくびの前面に孔をつくって縫いつけ,そこから呼吸するようになる。したがってこの状態では手術前のように呼気を使って声を出すことができないので,別の方法で音を出して人と話をすることが必要になる。このような音は代用音声と呼ばれ,その方法の一つとして食道音声という方法がある。これは,食道内に空気をのみ込んで,これをはき出しながら,この空気流で食道の入口の粘膜をふるわせて,その部分で断続気流をつくり,音を出すものである。食道音声の修得にはかなりの練習が必要であるが,上手な発声では,低音ではあるがかなり自然に近い声として聞こえる例がある。最近では,気管と食道を狭い通路でつなげ,気管からの呼気を食道,咽頭に導いて,もっと楽に音をつくらせようという手術も考案されている。またバイブレーターをくびのところにあて,その振動音を使って声の代用とする方法もある。あるいは,気管の入口(気管孔)からの呼気で一種の笛を鳴らして音をつくる方法もあり,これらの器械を総称して人工喉頭と呼ぶことがある。
歌声
歌声も声の一種であるが,ふつうの話声と違った点があることが知られている。とくに,歌声としてよい響きのある声では,倍音の性質に特徴があり,2~3kHzくらいの成分のエネルギーが強いことが知られている。声帯の振動数(基本周波数)に規則的に細かい揺らぎがあることも特徴的で,これがビブラートと呼ばれる現象である。このような特徴には声帯の使い方ばかりでなく,共鳴腔の調節も関係していると考えられている。
声やことばは音響の時間的変化であるので,その性質を分析する方法として,声の各周波数成分のエネルギーの時間的変化を,器械を用いて表示することが行われている。このような器械はサウンドスペクトログラフsound spectrographと呼ばれ,これによって表示されたパターンを声紋と呼ぶ。
→音声学
執筆者:廣瀬 肇
 〈セイ〉
〈セイ〉 〈ショウ〉
〈ショウ〉 〈こえ(ごえ)〉「産声・裏声・鼻声」
〈こえ(ごえ)〉「産声・裏声・鼻声」 〈こわ〉「声色・声高・
〈こわ〉「声色・声高・

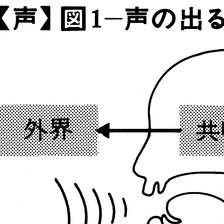



 (けい)+耳。
(けい)+耳。 けた形である。〔説文〕十二上に「
けた形である。〔説文〕十二上に「 なり。耳に從ふ。
なり。耳に從ふ。 を収める器の形である
を収める器の形である (さい)を加えることがあり、磬声は神を招くときに鼓つものであった。もと神聴に達する音をいう。
(さい)を加えることがあり、磬声は神を招くときに鼓つものであった。もと神聴に達する音をいう。


 声・悪声・威声・遺声・雨声・音声・家声・笳声・歌声・諧声・喊声・喚声・寒声・歓声・
声・悪声・威声・遺声・雨声・音声・家声・笳声・歌声・諧声・喊声・喚声・寒声・歓声・ 声・鼾声・雁声・希声・奇声・寄声・嬌声・金声・軍声・形声・渓声・
声・鼾声・雁声・希声・奇声・寄声・嬌声・金声・軍声・形声・渓声・ 声・五声・哭声・混声・四声・
声・五声・哭声・混声・四声・ 声・秋声・銃声・春声・女声・笑声・商声・象声・頌声・簫声・鐘声・上声・新声・人声・仁声・水声・正声・清声・千声・泉声・善声・楚声・双声・大声・嘆声・
声・秋声・銃声・春声・女声・笑声・商声・象声・頌声・簫声・鐘声・上声・新声・人声・仁声・水声・正声・清声・千声・泉声・善声・楚声・双声・大声・嘆声・ 声・男声・鳥声・聴声・砧声・
声・男声・鳥声・聴声・砧声・ 声・霆声・笛声・天声・伝声・怒声・濤声・徳声・
声・霆声・笛声・天声・伝声・怒声・濤声・徳声・ 声・肉声・入声・波声・罵声・吠声・発声・蛮声・飛声・美声・風声・平声・変声・鞭声・砲声・鳳声・謗声・梵声・妙声・民声・無声・名声・夜声・余声・容声・揚声・雷声・乱声・流声・令声・励声・
声・肉声・入声・波声・罵声・吠声・発声・蛮声・飛声・美声・風声・平声・変声・鞭声・砲声・鳳声・謗声・梵声・妙声・民声・無声・名声・夜声・余声・容声・揚声・雷声・乱声・流声・令声・励声・ 声・櫓声・和声
声・櫓声・和声