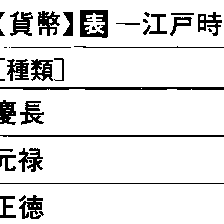精選版 日本国語大辞典 「貨幣」の意味・読み・例文・類語
か‐へいクヮ‥【貨幣】
- 〘 名詞 〙
- ① 商品の交換・流通を円滑にする一般的な媒介物。計算尺度、価値尺度、支払い手段、価値貯蔵手段、貸借の目的物などの機能がある。現在では、金貨、銀貨、銅貨、紙幣などが流通している。〔和蘭字彙(1855‐58)〕〔後漢書‐光武紀・下〕
- ② ( 紙幣に対して特に ) 金属製の通貨。
- [初出の実例]「右五品の貨幣を、銀貨幣と云ふ」(出典:小学読本(1873)〈田中義廉〉一)
改訂新版 世界大百科事典 「貨幣」の意味・わかりやすい解説
貨幣 (かへい)
貨幣の経済学
貨幣の定義・機能
貨幣とは,通常次の三つの機能を果たすものと定義される。すなわち,(1)決済手段(支払手段)としての機能,(2)価値尺度としての機能,(3)価値貯蔵手段としての機能である。貨幣の決済手段としての機能とは,広く社会で行われるさまざまの経済取引に際し,その取引の決済が貨幣の移転を通じてなされることを意味している。また,価値尺度としての貨幣の機能とは,取引される多様な財・サービスの価格を貨幣の単位,たとえば円やドルで表示することによって,それらの財・サービスの交換比率を統一的に表現することを可能としていることを示している。さらに,価値貯蔵手段としての貨幣の機能とは,人々が保有する財・サービスに対する購買力を将来へ持ち越すための手段として貨幣が役立つことを示している。今日では,貨幣と呼ばれるものは,ほとんどすべて,これら三つの機能を併せもっているものと考えてよい。実際問題として,三つの機能のうちの一部分だけを果たす貨幣(部分貨幣)は歴史的にみてもまれな現象であり,そのような貨幣の重要性は取るに足らない。そのような部分貨幣の例としては,植民地時代のアメリカのポンドや,最近に至るまでのイギリスにおけるギニーを挙げることができる。前者の例では,決済手段としてはスペイン硬貨が利用され,ポンドはもっぱら計算単位としてのみ用いられた。また,ギニーは,イギリスにおける一部の奢侈(しやし)品の価格や,ある種の儀礼的な謝金,公共団体への出資金などの額を表示する際にのみ,やはり計算単位として用いられたのである。
経済学の視点からみて最も本質的な貨幣の機能は決済手段としての機能であり,他の二つの機能は決済手段としての機能に付随した機能である。そして,経済取引における決済手段としての貨幣の導入は,経済社会の発展を支える重要な条件になったと考えることができよう。交換手段としての貨幣が存在しない経済においては,人々が直接に財,あるいはサービスを交換するという,物々交換が行われなければならない。このような物々交換では,一人の取引主体はみずからの保有する財・サービスを欲すると同時に,みずからが望んでいる財・サービスを保有している相手を探し出さなければならない。物々交換が行われるためのこの条件は〈double coincidence of wants〉と呼ばれるが,物々交換経済でこの条件を保証することはきわめて困難である。また,たとえば家畜など多くの財は分割して取引したり,運搬することがかなり困難であるために,きめ細かな交換取引は妨げられる傾向がある。このような理由により,物々交換経済における経済取引の規模は制約され,個々の主体はそれぞれ自給自足の経済生活を営むことを強いられるであろう。個々の主体,あるいはその集団が自分たちにとって比較的有利な生産活動に専門化することによって,社会全体として効率的な分業体制を形成するためには,上に述べたような物々交換の障害を克服することが必要だったのである。そのための社会的な手段が貨幣の導入なのである。
貨幣と信認
経済発展の比較的初期の段階では,共同社会の中でその有用性が広く認められている商品自体が,ごく自然に貨幣として使用される傾向がみられたようである。ある人がその商品を取引決済の手段として受け入れるのは,その商品を別の人に決済手段として受け取ってもらえることを信じているからなのである。このような貨幣は商品貨幣と呼ばれる。商品貨幣として使われる財は,時代や地域によって千差万別であったが,最も重要な位置を占めつづけてきたのは,金を中心とする貴金属であった。これらの貴金属が広く貨幣として受け入れられた理由の一斑は,分割可能性が高く,持運びに比較的便利であること,また高い耐久性をもっていること等の物理的性質に求めることができよう。しかし,それに加えてもっと重要な経済的理由が考えられる。それは,これらの貴金属の存在量(供給量)が非常に安定していたということである。そのために,これらの商品貨幣の購買力,すなわち他の商品との交換比率が大きく減価することがまれであったのである。この性質がこれらの商品貨幣が広く流布するためには不可欠の条件であったであろう。なぜなら,決済手段として受け入れた貨幣の購買力が大幅に減耗するかもしれないというような状況のもとではその貨幣を進んで受け入れようとする者はいなくなるだろうからである。貨幣が,貨幣として,つまり決済手段として一般に受け入れられるためには,〈他の人々が他の財・サービスと交換にこの貨幣を受け取るであろう〉という信認が存在していなければならないが,貨幣の購買力が十分安定しているということは,そのような信認を支えるための条件であったのである。このことは,後に述べるように,貨幣の制度が発展した現代の経済においてもまったく同様にあてはまることである。
貨幣経済の発達は,商品貨幣から,銀行券,政府紙幣のようなそれ自体の使用価値はほとんどまったく存在しない表券貨幣へという移行を伴っているが,この表券貨幣が貨幣として流通しうるのも,上に述べた信認が存在するからである。表券貨幣に対するこの信認を維持するためのくふうとしてとられたのが,表券貨幣の裏づけとして,商品貨幣を位置づけるという本位制度であった。表券貨幣をいつでもあらかじめ定められた比率で商品貨幣に兌換(だかん)しうるという制度的保証が,表券貨幣に対する人々の信認を支えたわけである。
近代から現代へかけての経済社会では,決済制度の中で表券貨幣である銀行券,さらには銀行預金が急速にその重要性を高めた。銀行は,それら表券貨幣を商品貨幣へ兌換することを原則としていたが,しかしよく知られているように,銀行が兌換に応じるための準備として保有する商品貨幣の額は,彼らが発行する銀行券や銀行預金の額の一部にすぎなかった。銀行にとって,このようなことが可能であった一つの理由は,銀行券や銀行預金を保有する多数の人々の中で,一定期間にそれらの兌換を求める者は限られているという,一種の大数の法則にある。しかし,より根本的な理由は,銀行は商品貨幣への兌換に応じる能力を十分にもっているという人々の信認が存在したためである。この信認が銀行券や銀行預金自体に決済手段としての機能を与え,決済制度における銀行の地位を支えたのである。経済学は,銀行がかち得ているこの信認を,ちょうど古くからの老舗がかち得ている〈のれんgood will〉と同じように,目には見えないが一種の資本財であるとみなす。貨幣の大宗が商品貨幣から表券貨幣へと移ることは,決済手段としての信認を支えるものが商品貨幣を形成している具体的な商品から,抽象的な資本財である信認へと部分的にせよ移ったものととらえられるのである。
法貨と預金通貨
今日の貨幣制度においては,中央銀行によって発行される紙幣,大蔵省によって発行される補助貨幣が決済制度の一つの基礎をなしている。しかし,これらはもはや金などの貴金属(商品貨幣)と兌換されることはない。一般に中央銀行の紙幣や補助貨幣は法律によって取引決済の手段として定められており,その意味で法貨とも呼ばれるが,この法貨に対する社会一般の信認は,中央銀行や大蔵省等の金融当局が〈十分な節度〉をもってこの法貨の供給量を制御し,その購買力の安定性を保つだろうという人々の期待に基づいているのである。
さらに,今日では,銀行が供給する預金勘定を通じる決済が非常に重要になっている。最も典型的なのは,当座預金を保有する主体がその口座あてに小切手を振り出して取引を決済するというものである。また,日本においては,普通預金からの振替えによる決済も広く行われている。このように,直接決済手段として使用される預金は要求払預金と呼ばれ,支払人の要求払預金口座から受取人の預金口座へ勘定を移すという銀行の業務活動がその決済のメカニズムを担っている。要求払預金によるこのような取引決済は,今日広く人々の間で受け入れられているので,この預金も貨幣の一部をなしているとみなされており,預金通貨と呼ばれる。この預金通貨は,預金者の求めに応じていつでも銀行が法貨と交換するという制度になっており,この法貨との互換性によって人々の信認が維持されているのである。
歴史的にみると,預金通貨は銀行制度の拡張とともにしだいに貨幣としての重要性を高めてきたが,その過程で預金と法貨との互換性はしばしば危機に直面した。それは,多くの銀行が経営破綻(はたん)をきたして,預金者に対し法貨による交換に応じることができなくなったためである。預金通貨の重要性が大きいだけに,この危機は一国の金融制度に深刻な打撃を与え,さらには経済システム全体を混乱させる原因ともなった。今日では,公共当局が法律に基づいて銀行のさまざまな活動を規制することによって,銀行経営の不安定化を防止したり,預金保険制度を導入することによって,上に述べたような金融的混乱の防止が図られている。この預金保険制度は個々の民間銀行に対して預金保険に加入することを強制する一方,それらの銀行がなんらかの理由で倒産した場合にも,預金保険でカバーされている一定額の預金に対しては公的機関である預金保険機構が倒産した銀行に代わって払戻しに応じるというものである。この預金保険制度のもとでは,預金者は個々の銀行の経営状態にわずらわされることがないので,不必要な預金の取立てを未然に防ぎ,ひいては銀行経営の破綻の波及が有効に防止されている。金融当局による法貨供給量の適切な制御と並んで,公共当局のこれらの適切な規制が,今日の貨幣に対する一般的な信認の基礎となっているのである。
貨幣と流動性
すでに述べたように,今日,貨幣として決済手段の機能を担っているものとして,現金通貨と預金通貨,すなわち銀行の当座預金を挙げることができる。しかし,今日ではそれ自体としては決済手段として機能することはないが,容易に現金通貨に変換可能な金融資産が存在している。その最も代表的なものは定期性預金である。定期性預金は,預金者が6ヵ月とか1年とかあらかじめ定められた期間銀行に取崩しを要求しない代りに,ある程度の利子を受け取ることができるものである。しかし,預金者にとって通常その利子を放棄すれば,定期預金を満期前に解約して,現金通貨や預金通貨へ変換することが容易に可能である。また,有価証券の一部,とりわけ満期が短く,かつ比較的容易にその流通市場を通じて売却することのできるような債券もやはり,定期性預金と同じような位置づけを与えることができる。このように比較的確実に,しかも手数をあまりかけずに現金通貨や預金通貨に変換できる金融資産は,高い流動性liquidityをもっていると表現され,それらの資産は流動的資産とか貨幣類似資産near moneyと呼ばれる。
今日では,最初に説明した機能に従う貨幣は,基本的ではあるが,いささか狭い定義であると理解されている。なぜならば,上記の貨幣類似資産が狭く定義された貨幣とほぼ同様の影響を経済に与えるであろうと考えられているためである。たとえば,現代の金融理論の基礎を構築したJ.M.ケインズは,マクロ経済の金融的側面を流動性選好(流動性選好理論)という概念によって叙述したが,その概念の中で扱われている貨幣は,実際に決済手段として機能するものばかりでなく,貨幣類似資産をも含んでいる。ケインズは,これらの資産が(ほぼ)確実に決済手段として機能するという意味で流動的であるのに対し,その他の金融資産はそのような流動性をもっていないがゆえに人々が進んでその他の金融資産を保有するためには,それらは利子を生まなければならないとして,利子率の存在を説明したのである。明らかに,このケインズ理論においては,価値貯蔵手段としての貨幣が強調されている。
いずれにしても,今日では,金融当局の公式の定義においても,狭く定義された貨幣から,かなり包括的な貨幣までいく通りかの定義が存在している(M1,M2,M2+CD,M3など。〈マネー・サプライ〉の項参照)。どの貨幣の定義が最も重要かは,この場合,絶対的なものではなく経済政策上の便宜に従って判断されることとなる。たとえば,一国の経済政策の最終的目標と目される物価上昇率,失業率等の経済変数と最も密接な相関関係をもつような貨幣の定義が,重要視されるべきであるということになろう。
金融上の技術革新と貨幣
要求払預金が貨幣として機能している背後には,銀行による支払人の預金口座から受取人の預金口座への振替業務が存在していることはすでに述べた。この業務は当然のことながら,人的資源や物的設備を要するものである。しかし,近年のエレクトロニクス関連技術の発展によって,このような振替業務の合理化が急激に進んでいる。このことは,決済制度における預金通貨の利便性を高め現金通貨(法貨)の必要性を低減させることに貢献している。その具体例としてキャッシュ・カードによる支払の急速な普及を挙げることができよう。そして,もっと重要なことであるが,この技術革新は,従来貨幣類似資産とみなされていた各種の金融資産の流動性を高める方向に積極的に利用されつつある。たとえば,アメリカでは,定期性預金を保有している主体が,必要に応じてその定期性預金を要求払預金へ自動的に振り替えて取引の決済に利用する可能性が開かれている。また一部の証券会社は顧客の投資信託出資金に対して小切手の振出しを可能とするシステムを開発している。このシステムのもとでは,投資信託への投資者は現金通貨はもちろん預金通貨に比べても有利な貯蓄手段を保有しうると同時に,それを要求払預金と同じように決済手段として使用することができるのである。これらの利便性の向上は,上に述べたように,エレクトロニクス関連技術を中心とする金融上の技術革新,エレクトロニック・バンキングによってもたらされたものであるが,これらの技術革新は現金通貨(法貨)を中心に据える伝統的な貨幣の概念に大幅な修正を迫るもののように思われる。
貨幣と経済政策
貨幣が経済において果たす役割の重要性については,古くから経済学者の一致して認めるところであったが,経済政策における貨幣の位置づけに関しては必ずしもそうではない。たとえば第2次大戦以後の資本主義諸国では,ケインズ経済学の強い影響のもとで経済における総需要を制御するための政策(総需要管理政策)の必要性,有効性が広く認められることになったが,そのような総需要管理政策において最も有効と考えられたのは政府,公共部門が財・サービスを購入する財政支出政策であり,貨幣の量の制御は二義的な位置しか与えられなかった。なぜならば,ケインズ経済学のもとでは貨幣量の変化は人々の支出(需要行動)にせいぜい間接的な影響を与えるにすぎないとみなされていたからである。経済における貨幣供給量(マネー・サプライ)の制御を重要視する考え方,すなわちマネタリズムは古典的な貨幣数量説の伝統を受け継ぐM.フリードマンら一部の経済学者によって絶えず主張されつづけたが,1960年代後半に至るまで経済政策に関する学説の主流とはなりえなかった。
以上のような事情は70年代に入って一変する。70年代の前半に世界的な規模で生じたインフレーションが,貨幣供給量の急増を契機として生じたことによって,政策当局者の間に貨幣供給量の制御の重要性が強く認識されることとなったためである。インフレーションが各国に共通する深刻な経済問題として浮かび上がるにつれて,マネタリズムの影響力も高まってきたとみることができよう。アメリカ,西ドイツをはじめとする先進諸国の中央銀行は,70年代半ば以降,貨幣供給量の増加率に前もって目標値を設定し,その目標値が実現されるように金融政策を運営するという,貨幣供給量の制御を非常に重視した政策方式をこぞって採用した。日本銀行も78年夏に,ほぼ同様の方式を採用している。
このような貨幣重視の経済政策は,1970年代後半から80年代初頭にかけて,インフレーションの抑制にある程度の効果を発揮したとみることができるであろう。しかし,同時に多くの国々で深刻な経済不況がもたらされる原因になったようにも思われる。さらに,すでに述べたような金融上の技術革新が,とりわけアメリカなどで,貨幣と貨幣類似資産との境界線を急速に不明確なものとしており,このことが中央銀行による貨幣の制御をきわめて難しいものにしていることも看過できない。70年代半ばから始まった貨幣重視の経済政策の将来は決して平たんではないように思われる。
執筆者:堀内 昭義
貨幣の本質
古くから,そして洋の東西を問わず,また経済学のみにとどまらず,哲学,社会学,心理学,文学など多くのジャンルで,貨幣について実にさまざまのことが語られてきた。以下,前項までの観点より少し広い観点から,貨幣に関するさまざまな議論をとりまとめることにする。
貨幣はさまざまに使われるが,これらは以下の四つのいずれか,あるいはそれらの複合だとみなすことができる。
(1)交換手段(購買手段) 前段[貨幣の定義・機能]において〈決済手段(支払手段)〉と名づけられていた機能は,財の交換・流通にかかわる交換手段と次の(2)にみる支払手段とに分けることができる。前段の〈決済手段〉の個所で説明されていたように,貨幣が交換手段の働きをすることによって,貨幣が存在しなければほんの偶然にしか起こりえない,いやまったく起こりえないであろう広範かつ大規模,そして複雑な財の組合せの交換が貨幣によって媒介される。
(2)支払手段 いろいろな関係から生ずる責務や債務を決済したり,それとは逆に人の歓心や労働奉仕,神聖さや人々の誉望を生じさせるために,貨幣が用いられることがある。この場合,貨幣は人間と人間の関係に直接かかわり働きかけることになる。信用売買・賃貸契約から生じた債務の決済,貢納・税金支払,罪の償い,招宴・饗応・袖の下,婚資,賃金支払,供物・寄進において貨幣が用いられる。〈現物支払〉という語があるように,一般の財がこうした目的で使用されることもあるが,貨幣による支払が多く行われている。支払手段とは,このようなかたちで貨幣が使用されることをいう。
(3)貯蔵(蓄蔵,退蔵,保蔵) 天災・不慮の事故,外的侵入・内部対立などから起こる社会秩序の混乱,老後の不安などに対して人々は財を備えおく。また高価な財を手に入れるために貨幣をためておく。あるいは,人はこれといってはっきりした外的な目的もなく,ただ手もとにもっていること自体に心理的な充足感を覚えるゆえに,すなわち自己目的化して財をためおく。このためおかれる財は身の安全性や自由のあかしであったり達成感のしるしであったりする。これらを財の貯蔵と呼ぶが,貨幣は貯蔵されることのある財のうちでも,有力なものである。
(4)価値尺度 財を生産したり消費したり,あるいは交換したり支払に用いたり,貯蔵したりすること,これらを総称して経済と呼ぶが,経済を構成している事物はそれぞれなんらかの評価を得て,経済を成り立たせる構成要素となっている。貨幣は,事物それぞれが各人においてどのように評価されているかを表す共通のものさし・尺度として用いられ,社会的に評価を統合する手段となっている。財物の評価だけでなく,支払手段をとおして,さまざまな人間関係の評価にも貨幣のものさしを用いる。こうした多くの場合,貨幣は量的な尺度として用いられるが,これと並行して,貨幣では評価できない,貨幣では手に入らないといったかたちで,質的な評価の尺度ともなる。また交換や支払の場を現に通過して貨幣によって現実に尺度されることのない事物でも,貨幣による尺度は人々の観念作用において陰に陽に働いている。このように社会的評価のものさし,すなわち価値尺度として貨幣は使われる。なお価値尺度に使われる財一般を価値尺度財(L.ワルラスはニュメレールnuméraireと呼んだ)という。
これらのなかでは価値尺度が最重要である。というのは,たとえば,物々交換のような場合,交換される具体的な財が交換しあう当事者おのおのにとって交換手段の役割を果たしている。また賃金などの現物支払においては,貨幣でない現物が支払手段として用いられ,穀物,宝石などのすがたで貯蔵される。これに対し価値を尺度する働きは,貨幣以外の財によって代位されることはない。また,貨幣以外のものが交換手段,支払手段,貯蔵に用いられる場合でも,観念作用において貨幣が価値尺度として作用しているからである。しかし,だからといって価値尺度の働きはそれ自体で作用するというのではない。たんに抽象的な量の体系が事物の価値を外的に尺度してまわるというのではない。貨幣が価値尺度に用いられるのは,貨幣それ自体,購買力をもって交換手段に用いられるからであり,人間関係の決済・形成力によって支払手段に使われるからであり,心理的にも充足感を与える作用力をもつものとして貯蔵されるからである。具体的で現実的な力をもって交換手段,支払手段,貯蔵のいずれか,あるいはこれらすべてとして使われて初めて貨幣は価値尺度になりうる。価値尺度の源は,貨幣がそれ自体,現実的な力であり価値であるというところにある。
これらから考えると,貨幣はそれ自体価値として,他の事物を尺度する働きを必ず伴いつつ,交換手段,支払手段,貯蔵に用いうるものである。貨幣は価値を尺度するから交換,支払,貯蔵に用いられるのでもないし,交換手段だから,支払手段だから,あるいは貯蔵されるから,価値を尺度することになるというのでもない。これらでありうるのは,貨幣のもつ力,貨幣のもつ価値自身にある。それこそが,上記のような貨幣の用い方・働きを成り立たせている基本であって,それは,貨幣が価値中の価値,すなわち価値の原基,価値の本位だということに基づいている。貨幣の本質はここにある。
貨幣は価値の原基として,事物の評価の基になりながら,財を交換せしめ,さまざまに人間関係をつくりあげ,交換・支払の人間関係から人間を退避せしめるなどして,経済生活を編成する要の役割を果たす。ちょうどわれわれが言葉(広くいえば,シンボル)の存在を前提にして,言葉によって会話し(交換),言葉によって相手の行動を縛り,惹起(じやつき)し,相手から縛られ,惹起され(支払),そして言葉によって記憶し(貯蔵),言葉によって思考する(価値尺度)ことから社会関係をかたちづくっているように,われわれは貨幣によって経済生活を成り立たせている。しかも,言葉によって思考するというとき,通常われわれは,時代によって,社会によって,あるいはさらに個々人によって様相は異なるが,さまざまの思考が陰に陽に最終的によるべとする言葉,その根拠を問うことをやめてそこを起点にそれにすがりついて思考し行動していかねばならない言葉,たとえば〈神〉〈天〉〈人道〉〈理性〉などを有している。貨幣が価値の本位だというのは,貨幣にかかわる事物一般を言葉にたとえれば,貨幣は上記の言葉のなかの言葉に当たるということである。貨幣とはこのようにまさに二重の意味においてシンボルであって,シンボルのなかのシンボルなのである。
貨幣の起源
貨幣がどこからどのようにして生まれたかについては多くの説がある。
(1)交換説 物々交換では交換の範囲が狭く限定される。シカを捕獲した猟師がこれと引換えにビーバーを得たいと思えば,ビーバーを手放してシカを得たいと思っている人物を探し出さなければならない。ぴったりと有無相通ずる関係は存在しないかもしれないし,たとえ存在するとしても,それを発見するには大いに手間がかかる。だから物々交換は偶然にしか起こらず,狭い範囲内でしか起こらないということになる。手もとに余剰が生まれ,交換によって多大の満足が得られるとなれば,物々交換を超えようとする圧力が生まれる。そこでシカを提供しビーバーを得たいとする者は,ビーバーをもってはいるがシカを欲しいとは思っていない人物しか見いだせない場合,あるいは,いまのところビーバーをもっている人も発見できない場合,さしあたってシカを,比較的多くの人が必要とし欲しがる,しかも日もちのする品,たとえばコーヒー豆と交換しておく。そうすればシカでビーバーを待つより,ビーバーを手に入れやすくなる。みながみな同じように,このコーヒー豆のような回り道をとるようになると,コーヒー豆が貨幣の役割を担うようになる。貨幣の誕生である。これによって交換も広範囲,大規模となっていく。この説はC.メンガーによって精緻(せいち)に展開されているが,A.スミスに始まる古典派経済学,およびマルクスによっても主張されているところである。
(2)装飾品貨幣説 上記の交換説で最後にどのような財が貨幣になるかを考えるとき,交換説は通常,食生活における日常品,すなわち小麦,塩などを念頭におくことが多い。交換説は経済力の低い水準で食べることのみに追われている人物を前提にしているからである。この前提を少し広げて,人間はどんな経済力の低い水準であっても,化粧したり装飾品をつけたりまとったりするものだとしてみる。すると,交換説をとる場合でも,貨幣に選ばれうる素材の範囲が広がる。食用に供する品よりも長もちするし,装飾品はその性格から個々人の所有観念の源であるとともに人目にさらされており,財の交換が起こる以前から公の評価がおのずからできあがっている。したがって物々交換が行きづまったとき,格好の回り道として,すでに評価の高い装飾品が選ばれて貨幣となる。いわゆる原始貨幣の例に,貝貨,アカガイの首飾,腕輪,ガラス玉などがあるのがこの説の有力な根拠である。この説は交換説と上記のように接合できるが,多くの場合交換説とは独立に,装飾品が罰金支払,貢租支払,婚資,贈答に用いられることから,これが貨幣となり,のちに交換手段になると主張される。つまり貨幣は支払手段として生まれるという説に接合されることが多い。この説はドイツの民族学者シュルツHeinrich Schurtzによって系統的に主唱された。ついでに付言すれば,シュルツは共同体の内部では財の交換は生ぜず,さまざまの支払関係が起こるだけで,この支払をなす手段として装飾品が使われるとし,これを対内貨幣Binnengeldと名づける。これに対し交易は共同体と共同体の接触から始まり,ここでは対外貨幣Aussengeldが流通しはじめるとしている。
(3)呪術説 貨幣にまつわりついている,支払・決済力や購買力,あるいは人々に獲得したいと思わせる魅力,これらの力の源が貨幣となっている物品に宿る精霊,呪力,縁起に発しているとみるのがこの説である。これは装飾品貨幣におけるよりも,さらにいっそう,人間に本来的につきまとう観念作用の不可思議な領域に注目する。フェティシズムの領域である。最も評価の高い装飾品というのも,たんに社会の審美眼によって決まってくるのではない。むしろ,精霊を宿しているといった集合表象が装飾品の価値を高くしている,あるいは美しいものにみせているといった側面もある。だから,貨幣になるのは装飾品に限らず,護符(御守),縁起のよいとされる石,武器でもある。これらは精霊を宿したもの,あるいは呪力そのものとして,婚礼,出産,通過儀礼,死亡,罪の償い,祭礼などの社会的儀礼の一環として授受され,支払・決済を果たす。また儀礼の面の強い贈与行為が,この物に含まれる霊ゆえに,贈与,うけとり,返礼という一連の連鎖,贈答となり,呪力をもつ物品が交換という形式をつくりだす,ともされる。これらはM.モースによって論じられている。
(4)宗教説 この説は牛が貨幣となっていたり,牛をかたどった鋳貨が貨幣となっていたことと,牛を聖なる動物とみたてる宗教が古代ギリシア,インドに存在することとに着目したものである。基本的な観点としては呪術起源説と同じであるが,大規模な社会を前提にしている点と宗教儀礼そのもののなかに価値の源泉をみる点でそれとは相違している。ドイツの経済史家ラウムBernhard Laumによって唱えられたものであるが,彼によれば,宗教儀礼において神にささげられる犠牲獣は,神への貢納ないしは神から聖性を得るための交換である。儀礼をつかさどる者たちは犠牲獣で報酬を受け,国家の書記官たちは獣の肉の一部で支払われる。こうして聖なる動物はその社会の一般的な支払手段となる。そして交換の手段ともなっていく。やがてはこの獣そのものではなく,この獣のなんらかのシンボルが宗教国家によって広く流通せしめられるようになる。
(5)貨幣国定説 これはG.F.クナップが《貨幣国定説》(1905)において主張したもので,貨幣の歴史的起源に関する説ではなく,貨幣の本質をどこに求めるかを示唆する,いわば理論上の起源説である。上記の宗教起源説は暗に宗教国家の存在を前提していたが,当説は国家(必ずしも宗教国家ではない)の存在を前提する。その国家は法律をもち,強制力をもつ,つまり実効力ある制度として成り立っているとする。この国家が,これが貨幣であると宣言・表明することによって,貨幣としての流通力をもつことになる。したがって貨幣たるもの,貨幣を構成する素材がなにであるかには無関係である。紙幣であっても,国家による宣言によって正統なる貨幣となっている。鋳造貨幣,国家紙幣は租税支払,財政支出によってその流通の循環が形成され,これが軸になって広く交換手段としても流通するようになるということが,歴史上のいくつかの経験から知られている。これが当説の根拠にもなっている。
このように貨幣の起源はさまざまに考えられているが,どれが正しいか,いまだ実証されていない。また今後とも実証されることはないだろう。資料に基づいて実証されるような性格の論題ではない。上記のいずれの議論も,貨幣のいずれかの要因に着目し,その存在がはっきりしているいわゆる原始貨幣を手がかりに,想定される貨幣のない状態と貨幣の生まれた状態をつなぐための,人間学的な推論を展開しているにすぎない。その意味ではおのおのそれなりの正当性を有している。と同時に人間学的な推論として,貨幣の起源はむしろ人間の,そして言葉の生誕と同時・同義であるとする説も有力である。
貨幣の変遷
貨幣をとりまく社会,文化,政治の違いに応じ,またそれらの変化につれて,素材,使用方法・機能,貨幣観,制度にも違い・変化があらわれている。それらは基本的に貨幣を貨幣にしている力の担い手(別様にいえば,フェティシズムの担い手)の相違から生じている。またその担い手の異なった貨幣が対峙するとき,それらは両立するのでなく,つねに巻き込み・巻き込まれる関係が生まれるところから,変化の一般的趨勢(すうせい)はつぎのようにたどることができる。
(1)原始貨幣 素材は,貝類,石類,皮革・歯・牙などの動物の体の一部,腰布・マットなどの植物加工物,塩・コーヒー豆・小麦・トウモロコシ・米・牛などの食用品,等々,その種類が驚くほど多い。これらいずれかを貨幣にもつ社会は,小規模の部族社会で,閉鎖性が強く,互いに他の社会に無関心で,原始貨幣どうし共存・併存する。これら素材はほとんど自然のすがたのままに近く,細工は簡単なものが多い。素材の表面に文字や絵(人物・動物などの)が刻まれることはない。自然のすがたに近い素材が貨幣としての力をもつのは,この素材に呪力・精霊・聖性・縁起が宿っているとみなされているためである。原始貨幣はこうしたかたちの人為性を帯びている。あるいは原始貨幣はそうした文化によって支えられている。この点で,技術文明のまっただなかにあるわれわれからみると,原始貨幣はフェティシズムをあらわにしたものだということになる。また,呪術的なるものに,そして,いわば静態的な文化に支えられているから,素材そのものはいくらも採集できるし,見つけることができても,貨幣になることはなく,貨幣が変化を誘発することもない。原始貨幣は静態的な文化の枠内にあって,贈答,支払といった儀礼性の強い場面で使用される。また使用方法が限定され,規範によって細かく規定されていることが多いところから,限定目的貨幣とも呼ばれることがある。
(2)鋳造貨幣(鋳貨) 社会の規模が大きくなるにつれて,権力が国家というかたちで制度として分化・独立する。また他方,規模の大きくなった社会の内外で,規範化された贈答に代わって市場交換・売買による財の流通が拡大する。大規模で広範な財の流通が慣習化し制度化していくには,権威・権力による支持・保護が必要であり,交換当事者相互が信頼を置くことのできる権威性を帯びた交換手段が必要である。また市場の拡大,交換手段の流通には,権力制度の分化・独立に伴って確立する税制においてどのような支払手段(財あるいは貨幣)を受け入れるか,も大いに関係している。これら要請に応ずるものとして鋳造貨幣が生まれた。素材は金属,とくに金,銀など貴金属が重要な地位を占めている。形は不定型の金属塊をなすのではなく,金属に鋳造加工がほどこされる。初期のころは,剣をかたどった鉄剣貨幣(古代イギリス,ブリタニア),鏟(さん)型・小刀型青銅貨(古代中国),スパルタの槍型鉄貨,クレタの三足容器の図像貨,獅子あるいは牛をかたどった鋳貨(古代ギリシア,小アジア),古代エジプトの腕輪型金銀貨などのように,原始貨幣の性格を形や意匠にとどめるもの,あるいは,旧約聖書にみえるヘブライの貨幣単位ケシタqeśîṭāh(羊を意味するヘブライ語),ローマの貨幣ペクニアpecunia(羊を主とする家畜を意味するラテン語)のように単位名称によって原始貨幣との系譜をとどめるものが多い。その後,鋳造貨幣は持運びの便宜,摩滅防止など技術的要因から一般的に円形をとることが多くなった。また,意匠には,王権発揚のため神話の銘文や武勲名高き英雄君主の顔を刻むことも多くなった。
鋳造貨幣はもともと金属のもつ耐久性,等質性,光沢,硬さという自然属性に基づき,人為によってもついに克服されなかった希少性に補強された,貴金属フェティシズムに発している。権力はこの貴金属フェティシズムを利用して,鋳造貨幣を流通させ,財の流通を活発にし,権威を制度として定着させる。鋳造貨幣においては,その表面に政治権力のシンボルが鋳刻されることで,政治権力が貨幣を支配するかにみえるが,それは表面的であるにすぎない。鋳造貨幣の本体は一定の純分,重量の金属からなっており,この面では政治権力は貴金属フェティシズムに呪縛されている。すなわち,鋳造貨幣は政治権力に支えられるというより,文化に支えられているといえる。この点では原始貨幣と同類である。ところが,この呪縛のなかでの政治権力の自己主張が,財政資金捻出のための悪貨鋳造であり,王権移行のたびの意匠変更,純分・量目の改鋳等である。この面から鋳造貨幣は変化の要因を帯びる。鋳造貨幣は歴史を有することになる。それは改鋳,悪鋳の歴史でもある。この点では原始貨幣と大いに異なっている。確認されている最古の鋳造貨幣は,前7世紀ころの,小アジア西部のリュディア王国のものである。だが,国家によって刻印された鋳塊をも鋳造貨幣に数えるとすれば,前2100年ころにはすでにあったということが楔形文字の文書解読から判明している。とすれば4000年以上も前から鋳造貨幣は存在していることになる。そして,この貨幣の時代は18~19世紀にまで及び,人類史上きわめて長い期間を占めている。
(3)紙券貨幣(紙幣,銀行券) (a)兌換銀行券 商工業など産業の発展に伴い,貨幣取引が大規模となり,活発となった。このため貨幣の流通量は巨大化し,流通速度は激化した。また,そうなることが求められた。鋳造貨幣流通の補助の役割を果たしていた為替手形,約束手形が銀行の発展につれて小切手,銀行券のかたちをとり,主役として産業発達の媒介をするようになった。この完成が中央銀行制度である。中央銀行は国家から銀行券発行の独占権を与えられる。また,その銀行券は法定貨幣(法貨)の規定を賦与され,一般的な流通性をもつに至る。実際には金あるいは銀の鋳造貨幣,その他金属の補助鋳貨も並んで使用されるが,貴金属は鋳造貨幣・地金銀のかたちで兌換準備として中央銀行に集中される。銀行券は広く国内一般に流通するとともに,預金銀行の準備となって,預金通貨(銀行貨幣)流通の裏づけともなる。預金通貨は,銀行預金に対して振り出される小切手が手形交換所などからなる支払決済機構によって銀行間で大規模に相殺され,振り出され支払に用いられた小切手の総額に比べ極小の銀行券の銀行間支払で決済されることから,こう呼ばれている。たとえば金本位制度であれば,中央銀行の金準備,一般流通と銀行の準備としての銀行券,産業流通における預金通貨--貨幣はこうした3層の構成をとる。このうち要をなす銀行券は兌換制度によって金準備の量と関係づけられる。銀行券の発行量はなんらかのかたち(比例準備制,保証準備発行制)で金準備量に規制される。兌換を維持するためである。このように兌換銀行券という貨幣は兌換制度をとおして,なお金フェティシズムに支えられてはいるが,それ以上に,中央銀行制や支払決済機構が機能するのを保証している不文律としての慣習,法律,議会,行政府,まとめていえば国家法制によって支えられている。この制度が完成をみたのは,1844年ピール銀行法によって保証準備発行制度をつくりだしたイギリスにおいてであるが,19世紀の後半には,先進諸国が同様の制度をとるとともに,国際的にもイギリス,ロンドンを中心にポンド金為替が世界的な銀行券として機能する国際金本位制が確立した。
(b)不換銀行券または国家紙幣 兌換銀行券から兌換制度をとり去ったもので,発行される銀行券の全額が政府の保証による。発行量,発行経路,つまり銀行券の管理は金準備に基づきなされるのではなく,政府・中央銀行に負うことになる。こうしたところから,管理通貨とも呼ばれる(管理通貨制度)。政府が直接発行する場合を国家紙幣と呼ぶが,基本的には不換銀行券とその性格を同じくする。この貨幣は全面的に国家法制が支えるが,国家法制のなかでも議会,行政府,つまりは政治権力に負うところが大きい。もともと銀行券の不換化,すなわち金本位制の停止は,貨幣を金に縛っておけば議会制度のもとでの政治権力の十分な行使が妨げられるとの危惧からであった。貨幣に残されていた歴史的,静態的な文化的要素の一つが政治権力を支える世論と恣意(しい)という変動的要素に置き換わった。管理通貨の〈管理〉の意味はここにある。変動しやすい政治が管理することから,この貨幣の価値は変動しやすい。ことにインフレーションへ向かう傾向が強い。この不換銀行券への形勢は20世紀に入って顕著となり,1931年イギリスが金本位制を離脱するに至り,世界的に決定的となった。アメリカのドルを除いて,ほとんどの国の貨幣が不換化した。第2次大戦後なおも兌換性を保持していたドル(連邦準備制度(=中央銀行)銀行券)も,71年金兌換を形式的にも停止し,国際的にも貨幣は完全に不換銀行券となった。
→紙幣 →発券制度
執筆者:吉沢 英成
貨幣の歴史
古代ギリシア・ローマ
ギリシア貨幣はヨーロッパにおける最初のものであるばかりでなく,その美術的価値において世界に誇るべきものである。銀はギリシアにかなり産出するから,銀貨を主とし銅貨を補助貨とし,金貨はもっぱらオリエントのもの(リュディア,ことにペルシア)が使われ,鋳造されたことは例外的であり,エレクトロンēlektron(金と銀との自然合金で,本土には産しない)貨幣はイオニアで造られたのみである。貨幣の単位はドラクマdrachmaとスタテルstatērが使われた。
クレタ時代には一定量の銅の延べ金があったが,貨幣とはいえない。小アジア西部には前9世紀ころから貨幣があったと思われるが,前7世紀からはリュディアの貨幣が最も進んでいた。この国から学んで,まずイオニアの諸市に前700年ころから貨幣の鋳造が始まり,ミレトス(うずくまるライオンを刻印),エフェソス(牡シカとミツバチ),クラゾメナイ(有翼のイノシシの前半部)その他の諸市のエレクトロン貨幣と銀貨とが造られ,都市の表象を刻印した。ギリシア本土では前660年ころ,カメを刻んだアイギナの貨幣が最も早い。これはアイギナ本位の始まりであるが,ついでエウボイア本位のカルキスの貨幣,これら諸国と比肩する交易国コリントスの貨幣(ペガソスの刻印),この3種が前7世紀ギリシア本土の主要なものであり,その他アテナイなども貨幣を造った。前6世紀とともに諸国の鋳貨は盛んになるが,ペイシストラトス時代のアテナイはラウリオン(ラウレイオン)銀山の銀を使って,注目すべき貨幣を造り出した。その4ドラクマ銀貨は両面に図像の刻印をした最初のものであり,表面にはアテナ神の頭部,裏面にはフクロウとオリーブを表したが,この刻印は以後のアテナイ貨幣の定めとなった。この世紀にはマケドニアなど北方ギリシアでも鋳貨されたが,富裕なシチリアと南イタリアの各都市では前7世紀からすでに造られ,前6世紀には同一の刻印を両面に陰刻と陽刻としたものがある。ことにシラクサの貨幣は戦車(チャリオット,これは後の世紀にも多くなる)を表し,すでに優秀な作品であった。前5世紀初めの,オリーブの冠をつけたアテナ神と翼を広げたフクロウ(マラトンのフクロウ)を表すアテナイの貨幣と,女王デマレテに似た女神と戦車競走とを刻んだシラクサの10ドラクマ銀貨とは,ペルシア戦争の勝利の記念である。すでにギリシア各都市はほとんど自己の貨幣をもっていたが,ペルシア戦争後は,アテナイの前述した図像のある各種単位貨幣が全ギリシア世界に流通したばかりでなく,小アジア,シチリア,南イタリアの諸市の貨幣にもアテナイのものを模してアテナ神が表された。しかしアクラガス,セリヌス,クロトンなど富裕な南イタリアとシチリアの諸市では,すぐれた貨幣の型製作者が造った。ことにアテナイ衰退後のシラクサの貨幣は最も優秀な作品となり,作者名が刻まれた。前4世紀となると,全ギリシアを通じてその美術様式も技術も大差なくなり,図像は前世紀の高貴なのに対して優美な様式となり,当時の大彫刻からの影響が認められる。なお銅貨が,この世紀半ばころからしだいに現れはじめた。
ヘレニズム時代とともに貨幣にも変化が起こった。貨幣はもはや小なる各都市国家のものではなく,大帝国の経済的統一の手段となった。装飾も時代の美術との密接な関係が失われ,君主の神化とともに国王または王朝の始祖の姿が,また国名ではなく国王の名と称号とが記される。そしてオリエントを征服した結果として,金貨が造られた。かくてアレクサンドロス大王をはじめ,諸君主の肖像が神や英雄の姿に代わり,しかもその容姿は個性的になったが,これはローマの貨幣への道であった。なおヘレニズム風貨幣はインドに至るまでのオリエントでも造られた。
ローマの最初の貨幣はギリシアと異なって貴金属製でなく,一定量の青銅の延べ金であり,また刻印せずに鋳造した。前340年の直後に通例の円形の青銅貨(アエス・グラウェaes grave)と銀貨が造られた。この青銅貨はアスasを単位とし,表面に両面神なるヤヌス,裏面に船首を表した。その他の貨幣には表面にユピテル,アテナ,ヘラクレスなど,裏面に船首を表したが,まだ粗雑なものだった。しかし,ローマの国力が伸張し,銀貨本位をもっていた南イタリアのギリシア諸市と接触するとともに,まったくギリシア式の銀貨が造られた。前269年であり,ピュロス戦争後のことである。このデナリウス貨(10アスに当たる)は表面に女神ローマの頭部と価格の数字(ギリシア貨幣は価格を表記しない)を,裏面には通商の神なるカストルとポリュデウケスの双生神と〈ロマノ〉の文字を表した。なお小額の数種の銀貨があり,青銅貨も補助貨として広く流通した。デナリウスはその後装飾に変化があるが,前2世紀からは鋳貨をつかさどる役人名,ローマの神話,また当時の歴史的事件,また当時のコンスル(統領)や将軍の像が表されてくる。かくて歴史上で有名なスラ,カエサル,ポンペイウスなどの像とその官職名を刻した貨幣が造られ,裏面にも人物の場合が多くなったアウグストゥスの帝政に続く。
帝政とともに金貨本位が併用された。その金貨は〈アウレウスaureus〉と呼ばれ,その半額の金貨も広く行われた。帝政以来は金・銀・銅貨を通じて,表面には冠をつけた皇帝の胸像とさまざまの尊称とを刻むのが通例である。銀貨と銅貨の鋳造権は元老院にあったから,裏面にSC(セナトゥス・コンスルトsenatus consulto)の文字を記した。しかし,ネロ帝以来は財政悪化するごとに貨幣が改鋳されてその質は低下し,金銀本位制が脅かされた。ディオクレティアヌスとコンスタンティヌスは良貨に回復しようと努めたが,後者のソリドゥス金貨は良質で,後にも西方に流通した。しかし,このころから貨幣の装飾は形式化された皇帝その他の像となり,文字が大きくなり,美術的にはますます低下した。なお,〈ローマ〉の項目中にある[ローマの貨幣制]を参照されたい。
執筆者:村田 数之亮
中世ヨーロッパ
中世ヨーロッパの貨幣は古代地中海文明の遺産であった。ビザンティン帝国(東ローマ帝国)ではソリドゥス金貨が本位貨幣とされた。そのデザインは皇帝の肖像と十字架を配し,7~8世紀ころからはキリスト像が現れ,帝権とキリスト教の発達を示している。ビザンティン貨幣,とくにソリドゥス金貨は13世紀まで,その領内だけでなくヨーロッパで広く流通して商取引に使用された。一方,ゲルマン民族は,フランク族を除いて,独自の貨幣を造らずにローマの貨幣鋳造を模倣した。西ローマ帝国滅亡後も,ガリア地方では各地に散在した造幣所でローマの貨幣が鋳造されつづけ,ローマ皇帝の肖像と名を刻印した貨幣が流通した。それはゲルマン民族の首長たちがガリアをローマ皇帝の名において支配したという政治的理由のほかに,当時の人々がローマ帝国の貨幣に慣れ,ローマ帝国の権威に依存した貨幣に執着しつづけたからでもあった。
しかしやがて6世紀以後,ゲルマンの首長たちは貨幣に自分の名を刻印しはじめる。ソリドゥス金貨は,イギリスを除くすべてのゲルマン民族で,カロリング朝の幣制改革による金貨鋳造の停止まで鋳造された。また,各地の造幣所で量目,純分もまちまちで,一般に品位の低い銀貨が鋳造され,そのほかイスラムやビザンティン帝国の貨幣が使用されて,貨幣流通は雑多を極めていた。銅貨もガリア地方ではメロビング朝初期3代の王の治下で,また,バンダル族,東ゴート族,アングロ・サクソン族で鋳造されるが,やがて鋳造は停止され,16世紀まで姿を消す。しかも,ゲルマン民族国家では貨幣鋳造権はもはや国家の独占ではなく,メロビング朝時代(5世紀末~751)には,王立造幣所で鋳造された貨幣のほか,教会,司教,荘園領主の名においても貨幣が鋳造され,さらに,各地の鋳造師によって造られた,権威をもたない多数の私鋳貨が流通した。ゲルマン法は金貨を唯一の基準としていたが,フランク・サリ族だけは例外で,サリカ法典のなかでは1ソリドゥス(金貨)=40デナリウス(銀貨)と二重勘定で定めていた。しかし,フランク・サリ族はそれほど多くの貨幣をもっていたわけではなく,計算はデナリウスでしても,支払は貨幣を使わずにそれと等価のあらゆる種類の物品で行うことが多く,ローマ時代にはかなり品位の高い銀貨であったデナリウス貨はメロビング朝初期には実体貨幣ではなく,たんなる計算単位となっていた。しかし,このような制度は不便であったので,7世紀初めころから,ふたたび実体貨幣としてのデナリウス銀貨の鋳造が始められ,このデナリウス貨が中世ヨーロッパの貨幣制度の基礎となった。
中世ヨーロッパの貨幣制度が確立されたのは,カロリング朝(751-987)の貨幣鋳造の中央集権化と幣制改革の努力によってである。カロリング朝時代には以前より重いデナリウス銀貨が鋳造された。一方,金はローマ時代に比べると希少になり,金貨の品位が落ちてきたので,7,8世紀ころより12デナリウスを1ソリドゥスと計算するようになっていた。カロリング朝が採用したのはこの比価であり,これはアングロ・サクソン族にも9世紀以後模倣されて根を下ろした。カール大帝治下,大きい数字を計算するのにリブラという名称がつくられ,240デナリウスを1リブラとして,240デナリウス=20ソリドゥス=1リブラという原則が確立した。リブラとソリドゥスとはデナリウスという実体貨幣の倍数を表す計算単位であり,ここにデナリウス貨を基礎とする中世ヨーロッパの貨幣制度が確立された。この計算システムはイギリスでは240ペンス=20シリング=1ポンド,フランスでは240ドニエ=20ソル=1リーブルとして長く維持された。その後ヨーロッパにおいて金の希少性がしだいに明白になり,金貨鋳造はフランク族ではカロリング朝のルートウィヒ1世(778-840,在位814-840)の治世以後停止され,アングロ・サクソン族でも1016年以後中断し,キリスト教ヨーロッパでは,その後,金貨は少なくとも土着の造幣所では13世紀まで鋳造されず,デナリウス銀貨だけが鋳造され,貨幣制度はデナリウス貨を基礎として統一された。
十字軍の遠征と北部イタリア都市を中心とする東方貿易(レバント貿易)の発達との影響のもとで,13世紀中葉に金貨の鋳造が再開された。金貨鋳造の再開はまずマルセイユ,フィレンツェ,ジェノバの地中海沿岸都市より始まり,イタリア諸都市に広がった。なかでも1252年にフィレンツェで鋳造されたフロリンflorin金貨(フィオリーノfiorino d'oro)は品質がよく,各国の金貨の模範となった。この金貨には聖ヨハネの立像とフィレンツェの紋章であるユリの花が刻印されている。また,ベネチアでは1284年に聖マルコとキリストの立像を刻印したゼッキーノzecchino金貨が鋳造され,ベネチアの繁栄につれてフロリン金貨と優位を争った。フランスではルイ9世(1214-70,在位1226-70)治下に金貨の鋳造が始められたが,その鋳造数はわずかであり,むしろ,フランス金貨史の真の起点は1295年のフィリップ4世(1268-1314,在位1285-1314)の金貨鋳造にあるとされる。
また,イギリスで初めて金貨を発行したのはヘンリー3世であり,1257年にフロリン金貨をかたどった金貨が鋳造されたが,これ以後ほとんど90年間,金貨鋳造は後を絶ち,商業上の必要から初めて金貨が鋳造されたのはエドワード3世治下,1344年のことであった。フランス,イギリスにおける金貨鋳造は中央集権国家成立の動きに関連していたが,地中海と北欧との間の通商上の要衝であったドイツでは,1342年に,ハンザ同盟のリューベックでフロリン金貨を模した金貨が鋳造された。一方,銀貨の鋳造も続けられ,従来のデナリウス貨より重い銀貨が鋳造された。その最初の例は1203年ベネチアによって,ついでフィレンツェによって与えられ,フランスでもルイ9世治下,1260年にトゥルノア重銀貨gros tournoisが鋳造され,ついでヘンリー3世治下のイギリスでも新銀貨が鋳造され,ドイツでは1476年にハプスブルク家のジギスムント大公が量目1オンスのターラーTaler銀貨を鋳造させた。神聖ローマ帝国の権威の象徴である大型のターラー銀貨は貨幣芸術の傑作の一つであり,17,18世紀のヨーロッパ諸国で模倣され,さらに,ドルdollarの名称の起源となった。こうしてヨーロッパ諸国は金銀複本位制にはいった。
執筆者:竹岡 敬温
古代オリエント
支払手段としての金属の使用は,メソポタミアにおいて最も早く証される。ここではすでに前4千年紀末の文書に銀の支払が示唆されている。支払に用いられた金属には銀や銅,金があり,前1千年紀には鉄が現れる。また,前2千年紀のアッシリアでは錫(すず)が一般的であった。これらの金属のなかで,早くから本位貨幣の性格を示していたのが銀であった。古くは大麦1グルgur(約252.6l)が銀1シクルšiqlu(約8.4g)に対応するとされ,銀が等価基準の役割を果たした。エシュヌンナ法典(前19世紀)は,銀1シクルに相当する諸種の品物の量を列記した標準価格表を掲げている。銀は粒銀,延べ棒,環の形をして秤量され,ときにはそれに刻印がなされた。重量単位はシクルのほかにマヌmanu(60シクル),ビルトゥbiltu(60マヌ)があった。アッシリア帝国の王センナヘリブ(在位前704-前681)は碑文のなかで半シクル青銅貨幣の鋳造を語っており,ペルシア帝国時代には後述のように金貨と銀貨が発行された。しかし,メソポタミアではセレウコス朝まで鋳造貨幣の流通はみられなかった。
エジプトでは,前3千年紀後半から秤量された銀が価値の基準として用いられていた。しかし,銀の計量単位は十二進法で,十進法をとるエジプトでは外来起源を示している。環形の金も支払手段として早くから使用された。長い間続いた銀本位は,前12世紀の第20王朝から銅本位に交代する。メソポタミア,エジプト以外でも銀本位の秤量貨幣が一般的であった。すでに前24(あるいは前26)世紀の北シリアのエブラ王国は,通商活動において銀を主要な支払手段としており,高価な品物の購入には金を使用していた。前1千年紀の著しい交易の発展に伴って,前7世紀には小アジア西部のリュディア王国やイオニアのギリシア諸市において,秤量貨幣から鋳造貨幣への移行が開始された。
前547年にリュディアを征服したアケメネス朝ペルシアは,この地方の貨幣鋳造を従来どおり継続させた。しかし,第3代ダレイオス1世(在位,前522-前486)は帝国正貨の発行を決意し,彼の名にちなんだダレイコスdareikos金貨とシグロスsiglos銀貨の2種を鋳造させた。どちらも表面に槍と弓を持った膝折り疾走の王の像を有し,きわめて純度が高く,帝国末期まで製作された。鋳造貨幣の流通は帝国西部に限られ,西部諸州のサトラップやフェニキア都市,小アジアのギリシア諸市は,大王特権に属する金貨を除いて,銀貨と銅貨の鋳造を認められていた。
前3世紀後半にセレウコス朝から独立したパルティアは,ヘレニズムの影響を受けながら独自の貨幣制度を成立させた。貨幣の単位はドラクマdrachmaとオボロスobolos(ドラクマの1/6)で,ドラクマ銀貨を本位貨幣とし,地方市場では青銅,銅,ときには真鍮(しんちゆう)の貨幣も流通していた。貨幣の表面には各王の肖像が通常左向きで描かれ,裏面には遊牧民の服装をして,弓を持って座した人物,おそらく建国者アルサケス1世が表現されている。テトラドラクマtetradrachma(4ドラクマ)銀貨の場合には,そのほかにテュケ女神が椅子にかけた王に冠を手渡している図柄が多くみられる。銘文は主としてギリシア文字を使用し,ギリシア語で王の称号を記している。しかし,最初期(前3世紀後半)のアルサケス1世の貨幣にはアラム文字によってイラン的称号を表現し,後1世紀後半のウォロゲセス1世以来パルティア文字の銘文も現れてくる。貨幣表面の記号から各地に造幣局が存在していたことが明らかにされる。また,ペルシアでは地方的君主が独自に貨幣を発行しており,裏面の拝火壇を伴った図柄はササン朝にも受け継がれた。
ササン朝の貨幣制度は多くの点でパルティアと異なった新しい特徴を示している。まず金貨が造られ,ローマの貨幣単位にならってデーナールdēnārと呼ばれた。本位貨幣はドラクマ銀貨であったが,パルティアより広く薄い造りで,この薄い貨幣はビザンティン帝国やアラブを経て西ヨーロッパにも影響を与えた。パルティア時代のテトラドラクマ貨は銀銅製として存続したが,まもなく廃止された。銅貨はパルティア時代に大量に生産されたものが流通しており,ササン朝ではわずかしか鋳造されなかった。なお,ドラクマはドラフムdrahm,オボロスはダングdangと呼ばれた。貨幣表面の王の肖像は右向きになり,正面向きもときにみられた。各王はそれぞれ固有の王冠表現を有しており,王冠の形からササン朝諸王の同定が可能である。裏面はほとんど拝火壇の図柄を示しているが,それはさらに三つのタイプに分類される。銘文はパフラビー文字で定式化された王の称号が記されている。治世年代の表記はペーローズ1世(在位459-484)の貨幣から現れる。造幣局の名称はワラフラン1世(在位273-276)時代から略字で示されている。ササン朝の貨幣は中央アジアの諸国家や諸民族,さらにはイスラムの貨幣制度にも大きな影響を及ぼした。
執筆者:佐藤 進
中東・イスラム時代
ウマイヤ朝の初めまでの初期イスラム時代には,アラブ・イスラム教徒は独自の貨幣を造ることなく,すでにそれまでに流通していた貨幣を使った。旧ビザンティン帝国地域では金貨が,旧ササン朝地域では銀貨が,旧貨幣の表面の彫像を削り取ったり,アラビア文字を鋳込んだりしただけで使われつづけた。
イスラム時代になって初めて独自の貨幣とその単位を作ったのはウマイヤ朝の第5代カリフのアブド・アルマリク(在位685-705)である。696年に肖像なしのアラビア文字だけ刻印された金貨が鋳造され,これは,その後イスラム世界における貨幣のモデルとなった。単位はディーナールとされ,1ディーナール金貨は,重量4.25gで品位は平均純度96%以上であった。それ以前に通用していたビザンティン帝国の1デナリウス金貨は4.55gであった。これ以後イスラム世界では1ディーナール4.25gが正式の単位となった。また698年には新しいディルハム銀貨が鋳造され,1ディルハム2.97g(ササン朝の1ディレム銀貨は3.98g)と定められた。
9世紀の初めまでは,ディーナール金貨は主として旧ビザンティン帝国領地域(シリア,エジプト)と北アフリカ,スペインで使われ,イラク,ペルシアではもっぱら中央アジア産の銀によるディルハム銀貨が使われた。しかしアッバース朝(750-1258)治下の9世紀の中ごろからは,西アフリカ産の金がイスラム世界に広く出まわるようになり,イラク,ペルシアでも金貨が鋳造されるようになり,もともと銀貨を使っていた地域では金銀二本位制となった。このようにイスラム世界では,金銀両貨が使用されたため,両替商が経済の分野で果たす役割はきわめて大きく,とくに商業には欠かせぬ存在となり,スーク(市場)のあるところにはどこでも両替商がいたほどである。両替商の業務は金融の各分野にも及び,手形,小切手などさまざまな金融制度を発達させた。またスカンジナビア各地で発見された何万枚もの〈アラビア銀貨〉は,主として9~10世紀のもので,アッバース朝治下の世界貿易の広がりを示している。
貨幣の鋳造はもともとカリフ政府の権利と考えられていたが,アッバース朝カリフのもとに独立した政権が成立するようになると,それぞれの王朝とも貨幣を鋳造した。たとえば9世紀後半のエジプトのトゥールーン朝(868-905)は高品位のディーナール金貨を発行し,東北ペルシアのサーマーン朝(875-999)はディルハム銀貨を発行した。中世の有名な思想家イブン・ハルドゥーンは,金銀貨を造ることは王権のしるしの一つであり,貨幣の品質について保証を与えることは支配者の重要な任務である,と述べている。
10世紀中ごろに貨幣史上の大きな変化が起きた。それまではごく小さな変化はあっても一般的にはきわめて安定した金貨の供給が特徴であったが,このころに金貨の品位がかなり低くなった。エジプトでは10世紀前半にトゥールーン朝が滅びた後アッバース朝の支配が回復したが,すでにそのころ金貨の品位の低下がみられた。アッバース朝の中心地イラクでは10世紀後半から11世紀にかけて品位が5%は低下して90%にまで下がった。一方エジプトではイフシード朝(935-969)のもとで再び高品位のディーナール金貨が鋳造された。
10世紀初めに北アフリカに成立したファーティマ朝(909-1171)はサハラ横断貿易を支配し大量の金を獲得し,品質のよい金貨を供給した。969年に本拠地をエジプトに移した後も,ファーティマ朝のディーナール金貨は高品位を誇り,ファーティマ朝帝国の経済的繁栄の基礎となった。
12世紀末から13世紀になると西アフリカ産の金はイタリア都市国家に吸収されるようになり,イスラム世界における金貨供給は全体的に衰退してきた。アイユーブ朝(1169-1250)は,中央アジアとヨーロッパの銀によりディルハム銀貨を鋳造し,金貨の供給減を補った。13世紀の中ごろ以降,アナトリア東部からペルシアまでを支配したモンゴルのイル・ハーン国も金貨よりも銀貨を本位貨幣とした。イル・ハーン国(1258-1353)は貨幣単位も新しくし,銀ディーナールという単位を使用するようになった。これはそれまでのディルハム銀貨よりかなり大きいもので,重さは12.9gあった。金銀の交換比率は,13世紀の初めには1対6以下であったのが,金の不足もあってイル・ハーン国時代には1対12くらいにまでなった。イル・ハーン国はまた,これまでのディーナール金貨よりも重いミスカル金貨も発行したが,通貨としては銀貨のほうが重要であった。
エジプトとシリアを支配したマムルーク朝(1250-1517)時代の前半は,安定した通貨供給が行われた。西アフリカ産の金が再び入るようになり,各スルタンはかなり品質の高い金貨を発行した。またアイユーブ朝時代末期に品質が低下した銀貨も,イル・ハーン国経由の銀の流入により品質が再び高くなり金貨と並んで使用された。
しかし14世紀後半になると国際的な貿易収支の悪化により通貨の原料である金・銀の購入自体が難しくなり,マムルーク朝の通貨制度は危機に陥った。銀貨の質はだんだん悪くなり,ついに15世紀の初めにはディルハム銀貨は鋳造されなくなった。後に銀貨は再び鋳造されたが半ディルハムと呼ばれる小さいものであった。金貨もイタリアのベネチアのドゥカット金貨やフィレンツェのフロリン金貨がしだいに優勢になり,15世紀前半には,それを使ってマムルーク朝スルタンが高品位のディーナール金貨に鋳直して用いることもあったが,結局はイタリア金貨が流通の最も重要な媒介となり,政府は自力で金貨を発行することができなくなった。
ヨーロッパ製の金・銀貨の中東への浸透はエジプトのみならず他の地方でもみられた。13世紀末から発展しはじめたオスマン帝国においても,オーストリア製の銀貨やベネチア製の金貨などが用いられた。自国製の貨幣が出るようになってもこれら外国製の貨幣は使われつづけた。14世紀前半に初めて独自の貨幣としてアクチェakçe銀貨というディルハム銀貨の1/3の貨幣が造られ,17世紀末まで政府の公式の勘定に使われることになった。15世紀後半には金貨も造られた。主要な貨幣であるアクチェ銀貨は最初は品位90%であったが原料不足のため繰り返し品質が下げられ,とくに16世紀末には,ヨーロッパにおける新大陸からの大量の銀の流入によって起こったインフレーションの影響を受けて物価が騰貴したためにアクチェ銀貨の品質はそれまでの半分以下にまで切り下げられた。その後17,18世紀には何度か品質の高い新しい銀貨が造られたが,財政難のために維持することができなかった。その後タンジマート期に入り国家財政の改革策の一つとして1840年に初めて紙幣が発行された。これは発行額に見合うだけの金準備をもつ兌換紙幣であるが,その後曲折を経ながらも近代的通貨制度の始まりとなり,伝統的な貨幣の役割は終りに向かった。
執筆者:湯川 武
インド
インド世界における交換および流通の媒介物の存在は,他の歴史的諸社会と同様に,起源を古くさかのぼるものであるが,その内実は多く不明のままである。ベーダ時代には,〈牛〉が価値の尺度であり,通貨としての役割も果たしていたが,今日考古学上の物的証拠によってその存在をたどることができるのは,銀製銅製の打刻印貨幣punch-marked coinをもって最初とする。形はおおむね方形だが不整で画一でなく,重量を一定にするために意図的に端部を欠くものもある。前7~前6世紀の北インドにおいて,初めは大商人(シュレーシュティンśreṣṭhin)や商人ギルド(シュレーニーśreṇī)によって造られ,しだいにその発行権が国王等の上位の支配者に移行していったと考えられている。この貨幣はマウリヤ朝下で大量に使用された。銘文をもたず,シンボリックな文様が刻まれているので,打刻印貨幣と呼ばれており,文様は一般には発行権威の認可印であると考えられている。この貨幣が西方世界との交易の影響を受けて造られたとする史家もいるが,今日ではその形状や土着的要素の強い文様等から,インド世界内の社会的・経済的発展によって独自に発達したと考えられている。文様を文献にみられる特定の政治勢力に対応させたり,その象徴性をある種の宗教性に由来するとする説もあるが,確実な証左が得られないのが現状である。時代下ってデカンのサータバーハナ朝の発行した鉛貨にも象徴的文様があしらわれているが,打刻印貨幣との間に影響関係があったか否かは定かではない。
その後西北インドに成立したペルシア人,ギリシア人,シャカ(サカ),パルティア等の諸勢力が発行した貨幣は,それぞれの故地や西方世界の影響下に造られたもので,同時代のインドの諸王朝も重量や意匠の多くをそれらに負った。王の像や称号を示す方式をはじめとして,ペルシアのダレイコス金貨やシグロス銀貨に倣った貨幣,アッティカ標準重量(ドラクマ)に従ったギリシア風意匠の円形銀貨などはその例であり,純度の高さで知られているクシャーナ朝の金貨はローマのアウレウス金貨の標準重量に従い,それがまた4世紀に興ったグプタ朝の金貨(ディーナーラdīnāra)に踏襲されている。グプタ朝崩壊以降,一般に貨幣発行は衰えるが,前代からの貨幣が引きつづき使用された。イスラム教徒配下のインドでは西方のイスラム諸王朝に倣った貨幣が発行されたが,偶像否定の信条に反して,インドのラクシュミー女神を表した貨幣が発行されたこともあった(ゴール朝のムハンマドの貨幣)。
このようにインド世界における貨幣は,西方世界からの影響を多く受けながらも,形や意匠の点で,一時的な中断はあったにしてもインド独特の表現を同時に示しつづけたといえる。ヨーロッパ大陸に比肩しうる広さをもつインド亜大陸では,歴史上大小さまざまの王朝が興亡を繰り返しており,画一的・統一的な貨幣が長期にわたって使用される場合はむしろ少なく,地方的な特色をもつ多様な貨幣が併用され,その使用期間もまた一つの王朝に限定されない通時代性をもっていた。
執筆者:石川 寛
中国
中国の前近代,いわゆる王朝時代に用いられた貨幣は金貨・銀貨・銅銭・紙幣・布帛(ふはく)(織物)など多彩である。最も古く交換の媒介物として用いられたと考えられるのは貝(子安貝)である。貝は殷人に宝物として尊重され,早くから貨幣的な役割を担わされていたらしい。少し時代は下るが,交換の媒介としては貝のほかにも鏟や小刀などがあり,それぞれ黄河の中流域(山西・陝西・河南),下流域(河北・山東)で用いられはじめた。黄河中流域は農耕地帯,下流域は狩猟・漁労の盛んな地方であり,鏟や小刀はそれぞれの地域で必需品として尊重されたものである。
春秋戦国時代に貨幣として広く流通するようになる布銭や刀貨は鏟や小刀のミニチュアとして造られたものである。布銭は初め空首布(柄をさしこむ穴〈銎〉の残っているもの)が,次いで平首布(銎部が扁平化したもの)が造られたが,両者は長く併用された。平首布は尖足布,方足布,円足布などきわめて多様な形式のものからなるが,時代が下るにつれて首・肩・足部が円形化していく傾向がある。布銭の鋳造発行は都市の商工業者によってなされたものらしく,都市名の刻まれているものが多い。他の貨幣の流通圏にも流通する関係で,他の貨幣との交換値を刻んだものも発行された。一方,刀貨は北方の明刀と南方の斉刀に大別される。明刀はより原初的な尖首刀の後をうけて造られたと考えられているが,刀身部に明字が刻まれているのが特徴である。斉刀は明刀に比べて刀身部が広く斉の地名を冠するものが多い。戦国後半期になると,明刀の柄環部が分離する形で明刀銭(中央に正方形の穴をもついわゆる方孔円銭)が造られ,斉刀の流通圏でも3種の方孔円銭( 化(あいか)銭)が造られた。なお,方孔円銭と起源を異にする円孔円銭が布銭の流通圏でも造られ併用された。他方,南方の楚国の領内では初め貝貨の系統に属する銅貝が造られたが,戦国期には銅貝の一種,蟻鼻銭が鋳造され使用された。また楚では同じころ,金貨(金餅・金版)が造られ額面の大きな取引に用いられた。金貨の使用はしだいに中原の諸国にも広がった。
化(あいか)銭)が造られた。なお,方孔円銭と起源を異にする円孔円銭が布銭の流通圏でも造られ併用された。他方,南方の楚国の領内では初め貝貨の系統に属する銅貝が造られたが,戦国期には銅貝の一種,蟻鼻銭が鋳造され使用された。また楚では同じころ,金貨(金餅・金版)が造られ額面の大きな取引に用いられた。金貨の使用はしだいに中原の諸国にも広がった。
戦国期の秦国では商鞅の変法の趣旨を継ぐものとして前336年,銅銭を発行したが,やがて半両銭と金貨(金餅)とをそれぞれ下幣・上幣とする貨幣制度を樹立した。ただし秦国では日常の交換には銅銭のほかに布(織物)も用いられ,銅銭との交換値も定められていた。秦の始皇帝は晩年(前210),秦国の貨幣制度によって貨幣の統一を企てたが,制度として定着しないうちに秦が滅亡したので,その制度化は漢帝国にゆだねられた。漢代初期には銅銭の重量・大きさをめぐって試行錯誤が繰り返されたが,前175年(文帝5),四銖半両銭の発行で安定した。さらに武帝のとき,三銖銭の暫定的発行(前120)を経て五銖銭が発行されるに及び(前119),銅銭の重量・様式は確定した。五銖銭は,以後,唐の621年(武徳4),開元通宝が発行されるまで,銅銭のモデルとされた。なお,このとき,五銖銭のほかに白金三品(3種の銀貨)や皮幣が制定されたが,白金は盗鋳の激発などのためにまもなく廃止された。五銖銭の発行後,貨幣経済はしだいに沈滞し,不況の様相を強めた。
前漢末,王莽(おうもう)は折からの経済不況の打開策の一つとして増幣を目的とする数次の貨幣改革を行ったが,そのうち,紀元10年(始建国2)の第3次改革は黄金1品,銀貨2品,銭貨6品,布貨10品,亀宝4品,貝貨5品,6系統28種の貨幣を一度に通行させるものであったから,人民は多数の貨幣に当惑し貨幣経済は混乱に陥った。後漢初期には王莽が第4次の改革で発行した貨泉・貨布が流通したが,40年(建武16),五銖銭が復活された。しかし五銖銭の復活は貨幣不足を促進したにすぎず,しだいに貨幣経済は行きづまり,実物経済へと移行した。なお,金貨は武帝時代より大量に海外に流出し,国内でも退蔵されて貨幣としての機能を果たさなくなった。
三国から隋・唐初に至る時代は貨幣経済の衰退期で,とくに北朝ではその傾向が著しかった。魏の文帝は後漢末期の銅銭不足の実情にかんがみ,221年(黄初2),五銖銭を廃止して穀物や絹布で取引させたが,しかし不都合が多かったため6年で五銖銭を復活させた。このとき,蜀では五銖銭の流通を前提として直百五銖(1枚が百銭に相当する)が,呉では当五百大泉,当千大泉が発行された。南朝では北朝の侵略に対抗すべく軍事財政を組む必要から新貨を発行した。宋では孝建四銖・二銖を,梁では五銖の鉄銭を発行したが,前者の場合,民間では新貨を嫌い五銖銭を変造した悪貨(鵝眼銭・綖環(えんかん)銭)が流通するようになった。後者の場合は悪性のインフレーションが発生したうえ,盗鋳が激増したため,民間では鉄銭を嫌って銅銭(五銖)で交換するようになり,梁の末年には銅銭を復活せざるをえなくなった。一方,北魏では平城時代は貨幣を発行せず,布帛で交換が行われたが,孝文帝の洛陽遷都の後(495),独自の貨幣,太和五銖を発行し,次いで永安五銖を発行した。北斉では常平五銖を,北周では五銖銭の流通を前提に布泉(五銖銭×5),五行大布(布泉×10),永通万国(五行大布×10)を発行した。このように南北朝時代にはいちおう五銖銭が基本的な貨幣として流通したが,銭文の形式は崩れる傾向にあった。
隋は全国を統一すると,五銖銭で貨幣を統一した。しかし隋を継いだ唐は621年(武徳4),開元通宝を発行して銅銭の様式に新紀元を開いた。唐では後に通宝や重宝に元号を冠したものが用いられるが,開元通宝は唐末にも鋳造され唐代を通して流通した。通宝・重宝に元号等を冠する様式はその後,清末まで継承されることになる。なお,安史の乱の際,史思明は得壱元宝,順天元宝を発行したが,以後,王朝に反旗を翻したものや異民族で対立王朝を開くものなども,その元号を冠した銅銭を発行するようになった。また唐の中葉以後,遠距離の商取引などに為替手形(飛銭)が用いられるようになった。
宋代になると,唐後半期以来の貨幣経済の隆盛をうけ,銅銭の需要が増大する一方,鋳銅技術の進歩もあって,銅銭鋳造額は飛躍的に増加した。北宋時代で最も多い年には年間鋳銭額は500万貫にも達したとされる。この時代には太祖の宋元通宝,太宗の太平通宝をはじめとして50種を超える銅銭が鋳造されたが,最も多く鋳造されたのは元豊通宝,皇宋通宝である。南宋時代には領土が局限されたこともあって,原料の供給が不足し,鋳銭額は激減して北宋の1/10に落ち込んだ。宋代にはこのように大量の銅銭が鋳造され流通したが,それでも通貨需要が大きかったために銅銭は不足しがちであり,銀や交子などの紙幣が流通に導入された。
紙幣(交子)は唐代後半に出現した飛銭の発達したものであるとされる。交子は四川の商人たちが連合し遠隔地の取引における鉄銭(当時四川など一部の土地で流通していた)の運搬の労を省く目的で銭手形を発行したことに始まる。やがて特定の富商たち(交子舗・交子戸)が中心となってその運営に当たったが,富商が衰微して運営が困難になると,交子の兌換をめぐって訴訟事件が起こったので,1023年(天聖1),政府がこれを官営化したのである。紙幣が盛んになるのは南宋時代になってからで,銅銭の供給が需要に追いつかなくなったことがその流通を促進した。
モンゴル人は中国を支配する以前,銀を通貨とする中央アジアの諸国と交渉をもった関係で銀を本位貨幣としていたが,中国を征服すると,金や宋が用いていた紙幣(交鈔)を通貨に採用しこれを銀に結びつけた。銀は南北朝ころから用いられはじめ,唐を経て宋代には貨幣として盛んに使用されるようになったが,通貨の主体は銅銭であった。元がいったん銀本位制を採用して以後,中国の貨幣には銀を本位貨幣として用いるようになった。その意味で元の銀本位制の採用は中国の貨幣史上,きわめて画期的である。元は紙幣を主要な通貨として一貫して使用したが,国初に制定した中統元宝交鈔(中統鈔)を一代を通じて用い,これに新たに発行する紙幣と併用させた。中統鈔は1260年(中統1)に発行され,南宋征服前後に兌換制度の廃止により大きく騰貴して以来,騰貴しつづけ,1346年(至正6)以後は財政難から紙幣が濫発され,ついに破局を迎えた。
明の太祖,朱元璋は紙幣の弊害を知りつつも,これを通貨に採用し,5種の洪武通宝(銅銭)を発行してこれと兌換せしめ,金・銀の流通を禁止した。しかし,すでに中国に深く根を下ろしていた銀は禁止にもかかわらず民間に広く流通し,紙幣の価値が下落し使用されなくなるに伴って,ついに1436年(正統1),正式の通貨として公認された。ただし銀は元代に通貨として定着したが,中国では清末まで秤量貨幣であった。明・清時代には一般に馬蹄銀が用いられたが,外国から鋳貨が流入しても,それは改めて秤量のうえ,使用されたのである。
清は銀と銅銭を併用した。銀1両を銅銭1000文に相当するものとしたが,両者の比価は銀の相場によって変動した。明の万暦(1573-1619)より清の前半期までは外国から多量の銀が流入したので(洋銀),銀の価は低かったが,嘉慶(1796-1820)以後,銀は逆に外国に流出し,銀価は高騰した。当時の税制は地丁銀と呼ばれ銀建てであったから,人民は銀価の変動の影響をもろに受けた。一般の人民は日常の交易には銅銭を用い,納税の際には銅銭を銀に換えて納付するのが常であったから,銀価が高くなると,納税に際して人民の手放す銅銭の額は必然的に大きくなり,その生活を圧迫した。
清朝における貨幣制度の改変はまず咸豊期(1851-61)に加えられた。このとき,太平天国の乱が勃発したので,軍事費調達の方策の一つとして貨幣の改制が行われたのである。小銭(1文),当四(4文相当)から当千に至る16種の銅銭(咸豊通宝)が発行される一方,大清宝鈔および銭票(鈔)の2種の紙幣が発行された。また太平天国側でも太平天国小銭(1文),当五銭から当百銭まで5種の銅銭が発行された。
清末の洋務運動の余波は貨幣にも及び,長い伝統をもつ貨幣の様式は一新された。1887年(光緒13)に銀元,すなわち方孔のない洋式の銀貨(光緒元宝)が発行されたのに続いて,1900年には銅元,すなわち1文から20文に至る5種の洋式の銅貨(光緒元宝,大清銅幣)が発行された。この銅元の発行は中国貨幣史上,重要な意義をもっている。戦国時代の明刀銭以来,連綿と続いてきた方孔円銭の伝統がここに至って消滅したからである。その意味では銅銭は,宋・元以後,地位は相対的に低下したとはいえ,旧中国を象徴する貨幣であったともいえるのである。なお民国以降については〈法幣〉〈元〉〈幣制改革〉等の項目を参照。
執筆者:稲葉 一郎
朝鮮
本格的な貨幣鋳造の歴史は高麗時代に始まる。996年に最初の鉄銭である乾元重宝が鋳造されたといわれ,その後,三韓通宝,三韓重宝,海東通宝,海東重宝,三国通宝,三国重宝などの鉄銭・銅銭が相次いで発行された。また,銀瓶(ぎんへい)あるいは闊口(かつこう)と呼ぶ銀貨が造られた。李朝政府は,建国初期の1401年に楮貨すなわち紙幣を発行して法貨とし,23年には朝鮮通宝という銅銭を,64年には鉄の箭幣(せんへい)を鋳造して普及させようとした。しかし,いずれも一部での流通にとどまり,一般の農民の間では米や布が交換手段として使用されつづけた。こうした状況は李朝後期に入って一変し,商品経済の発展に伴って貨幣の必要性が高まってくる。1633年と51年に常平通宝という銅銭が鋳造され,いったん中断したものの,78年以降は恒常的に鋳造・発行されて全国に広まった。開港以後の時期になると,日本貨幣が流入し,高額だが品質の悪い常平通宝である当百銭・当五銭などが発行されたことと相まって通貨の混乱を招いた。近代的な貨幣制度確立への努力がなされ,1894年の甲午改革では新式貨幣発行章程を定めて銀本位制の採用を目ざしたが,補助貨である白銅貨の乱発がインフレーションを呼び,日本円銀の内地流通承認などで混乱はさらに深まった。日本円銀を排除して金本位制を確立しようとする自主的改革の試みも日本の圧力に阻まれた。1905年から始まる朝鮮貨幣整理事業によって,朝鮮の貨幣制度は日本の通貨体制のもとに編入され,植民地期を迎える。日本の植民地期(1910-45)には朝鮮銀行券が発行されたが,米ソの軍政期を経て,独立後はそれぞれ南北両国でウォン(元)を基本通貨とする紙幣や貨幣が発行されている。
執筆者:吉野 誠
日本
日本における最古の鋳造貨幣には,菊花紋をもつ無文銀銭(菊文銀銭)と稲を表す文字が配されているとみられる無文銅銭(稲文銅銭)とがある。これらは飛鳥時代に朝鮮から伝来した鋳貨といわれる。最初の官銭は708年(和銅1)に鋳造された和同開珎(わどうかいちん)であった。これに続いて奈良・平安時代には万年通宝(760創鋳),神功開宝(765),隆平永宝(796),富寿神宝(818),承和昌宝(835),長年大宝(848),饒益神宝(859),貞観永宝(870),寛平大宝(890),延喜通宝(907),乾元大宝(958)が相次いで発行された。これらを総称して皇朝十二銭または本朝十二銭という。和同開珎には銀銭と銅銭とがあったが,そのほかの皇朝銭はすべて銅銭であった。皇朝銭のほかに760年(天平宝字4)には最初の金銭である開基勝宝および銀銭の大平元宝が造られた。皇朝銭の鋳造地は武蔵・近江・山城・大和・河内・周防・長門の各地であった。律令政府は蓄銭叙位法を定め,銭貨を蓄えた者に対して位階を与えるとか,諸国から政府に上納していた庸・調を銭貨に代えるとか,官吏の禄を銭貨で与えるなど,銭貨の流布を図るために種々の対策を講じたが,律令政府の支配力が衰えるとともに,その鋳銭事業も乾元大宝を最後として打ち切られた。
皇朝銭の鋳造が停止されてから,物品貨幣(自然貨幣)の稲米布帛(とうべいふはく)が再び使用されるようになったが,平安末期から唐の銭貨が日本に流入し,鎌倉時代には宋銭,室町時代には明銭が輸入され,国内で通用した。洪武通宝・永楽通宝・宣徳通宝などは代表的な明銭であった(宋元銭)。室町時代には中国の官鋳制銭のほかに,日本製の模造銭や私鋳銭が造られ,中国製の精銭と並んで日本製の鐚銭(びたせん)が使用された。そのため撰銭(えりぜに)の現象がみられるようになり,標準的な中国銭に対して日本製の銭貨は資質の悪い減価された悪銭として区別された。室町幕府や戦国大名の大内氏・武田氏・浅井氏・結城氏・北条氏や,戦国覇者の織田氏などはいずれも撰銭令を出し,貨幣流通の面から流通経済を把握しようとした。室町時代には銭貨(銭)のほかに金貨(金)・銀貨(銀)も鋳造され,戦国時代になると諸国の金山・銀山の開発が進み,戦国諸侯は独自の金銀貨を造り,軍用資金の充実を図った。安土桃山時代には豊臣秀吉が各種の金銀貨を鋳造し,これを軍資金とした。
江戸時代には徳川家康が1601年(慶長6)に幣制を統一し,金座・銀座・銭座を設けて金銀銭貨を鋳造し,この三貨を全国通用の正貨とした。金貨には大判(10両)・5両判・小判(1両)・2分金・1分金・2朱金・1朱金があり,銀貨には秤量貨幣の丁銀・豆板銀(小玉銀・小粒銀)のほか,定位銀貨として5匁銀・1分銀・2朱銀・1朱銀が造られた。銭貨には慶長通宝・元和通宝・寛永通宝・宝永通宝・天保通宝・文久永宝があった。金銀貨の改鋳は元禄,宝永,正徳・享保,元文,文政,天保,安政,万延の各時期に繰り返された。三貨の交換割合は,幕府により1609年に金1両=銀50匁=銭4貫文と定められたが,1700年(元禄13)には金1両=銀60匁=銭4貫文と改定された。この法定相場は市中では絶えず変動しており,実際には変動相場制が長く維持された。江戸時代に江戸を中心とした関東では金建て(金遣(きんづかい)=金単位の取引),大坂を中心とした関西では銀建て(銀遣(ぎんづかい)=銀単位の取引)の慣行がみられ,金経済圏と銀経済圏の二つの経済ブロックが形成されていた。幕府制定の三貨のほかに,大名領国では藩札と呼ばれる紙幣が発行された。最初の藩札は1661年(寛文1)発行の越前国福井藩札で,1871年(明治4)の調査によると全国諸藩の約80%に及ぶ244藩で藩札を発行していた。藩札のほかに民間紙幣の私札が近世初期から各地において発行された。
1871年4月,政府は造幣寮(のちの大蔵省造幣局。現,独立行政法人・造幣局)の開業に踏み切り,同年5月には新貨条例を制定して円という貨幣単位を採用し,江戸時代の両・匁・文の体制から切り替えた。新しい金貨・銀貨・銅貨は円形の貨幣となり,江戸時代の楕円形の大判・小判,なまこ形の丁銀,不定形の小粒であった豆板銀などが円形に統一された形状をもつことになった。さらに同年10月に紙幣寮(のちの大蔵省印刷局。現,独立行政法人・国立印刷局)が開設され,政府紙幣を製造し,のちに国立銀行紙幣・日本銀行券などの製造に当たった。
執筆者:作道 洋太郎
近代日本の貨幣法制
安政の開港により,日本へのメキシコ・ドルの流入と日本からの金貨の流出が激化し,貨幣制度は大混乱に陥った。明治新政府は,この混乱を静め,その経済基盤を確立するために,1868年太政官札(金札)の発行を布告したのを手はじめに,69年,民部省札,71年,大蔵省兌換証券,72年,新紙幣,開拓使兌換証券,81年,改造紙幣等々の紙幣を発行した。硬貨に関しては,当面,江戸時代の旧制によるとされたが,1869年以降,従来の四進法から十進法への変更,銀本位制ないしは金本位制の採用等々が種々検討された結果,71年の新貨条例により,金単本位制が採用されることとなった。しかし,東洋諸国で当時流通していたのは銀貨だったこともあり,新貨条例のもとで,1円銀貨も貨幣制度の外にあって貿易利便に資することが認められ,その国内での通用も否定されず,実質的には金銀複本位制ともいうべき制度がとられていた。その後,同条例は75年に貨幣条例と改称された。貨幣制度の形式的整備がこのように進む一方で,現実の通貨としては,太政官札以降の前記政府紙幣,為替会社紙幣,1872年の国立銀行条例による国立銀行券等の不換紙幣が主として流通していた。この混乱を整理し独占的に兌換券の発行を行わしむるために,82年,日本銀行条例によって唯一の発券中央銀行として日本銀行が設立された。84年の兌換銀行券条例は,日本銀行の発行する銀行券を規制するものであるが,同条例のもとで日本銀行券は銀貨準備銀行券とされ,この制度は,その後,日清戦争の賠償金を基にして金本位制度を採用する97年の貨幣法が制定されるまで続いた。同法はその後若干の修正をほどこされてはいるが,政府の発行する貨幣の基本的部分を定めるものとして今日に至っている。これを修正するものとして,1938年の臨時通貨法が現に流通している臨時補助貨幣の制度(1957年改正により,現在は100円,50円,10円,5円,1円,50銭,10銭,5銭,1銭)を定め,〈小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律〉(1953公布)が,貨幣法上の1円未満の補助貨幣たる銭,厘の使用を禁じている。
一方,現在日本で現実に流通している現金通貨の中心は,1947年の日本銀行法による日本銀行券である。その種類および様式は大蔵大臣によって定められ(33条),公私いっさいの取引に無制限に通用するものとされ(29条),その発行限度は大蔵大臣が閣議を経て定めるが,日本銀行の判断による限度外発行も可能となっている(30,31条)。
執筆者:来生 新
貨幣の製造
金属貨幣はほとんどが鋳造で製造されていたため,コイニングcoiningとは〈貨幣の鋳造〉という意味であった。しかし現在ではコインやメダルなどは圧印加工で製造され,この加工法をコイニングと呼んでいる。これは,薄肉の金属円板にポンチとダイ面の模様を圧縮によって写し出す鍛造加工の一種で,金属円板はポンチとダイの間に密閉して加工されるので,材料が外に逃げたり,ばりは生じない。浅い凹凸を刻印することは,小規模の加工の割には大きな圧力を必要とする。加工の際に用いる潤滑油は,表面にめり込んだり,化学反応を起こさないよう十分吟味が必要である。紀元前から現在まで多種多様のコインが鋳造,コイニングされ使われてきた。コイン収集の趣味もあり,オリンピックなどの記念コインは世界各国で発売されている。
執筆者:木原 諄二
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「貨幣」の意味・わかりやすい解説
貨幣
かへい
money 英語
Geld ドイツ語
monnaie フランス語
近代資本主義経済は、分業と私有財産制とを基礎とする結果、無数の個別経済(経済主体、単位経済)に分裂している。したがって近代経済は、この分裂した無数の個別経済をもって構成される一つの総合経済であるといえる。経済主体には生産の主体と消費の主体とがあり、相互に依存しあい、結び付いて、流通経済、市場経済を形成する。そしてそこに貨幣が介在する。このように近代経済における貨幣は、財貨=商品とともに各個別経済を結び付ける連鎖であるが、この場合の貨幣には、媒介的存在のものと目的的存在のものとがある。前者は商品を購入した対価として支払われる貨幣の流れで、貨幣は購買手段あるいは流通手段として機能する。後者では貨幣だけが一方的に流れ、より多くの貨幣となって(利子を付して)ふたたび還流してくることが期待されている。ここでは貨幣それ自体があたかも商品のごとく、需要供給、すなわち取引の対象となっているのである。
[原 司郎]
貨幣に関する学説・理論
金属主義と名目主義
このような役割をもつ貨幣の本質がなんであるかに関する学説には、今日、金属主義と名目主義の二つがある。広義では、前者に商品学説、素材主義が含まれ、後者には国定学説、指図証券説、職能学説、抽象学説などが入れられる。
金属主義によれば、貨幣はもっとも広く一般的に受領される商品となる。この結果、貨幣は他の商品と同じく、それ自体が素材価値をもたなくてはならない。すなわち、商品と貨幣との交換過程において、貨幣はそれ自身が価値ある商品としてそれ自体価値ある商品と交換されることとなる。かくて貨幣の本質は価値をもった素材に求められ、貨幣は商品あるいは価値ある財貨、とくに貴金属でなくてはならないと考える。この理論に従えば、素材価値をもたない貨幣の存在は認められないから、紙幣は貨幣たりえぬこととなる。紙幣が流通している場合でも、それが政府紙幣を意味している限り、流通手段としての貨幣の機能から生じた価値章標である。つまり紙幣は貨幣の使用を節約する代用物にすぎないこととなる。
金属主義においては、貨幣がそれ自身一つの商品として価値をもっていることから、価値尺度として他の商品の価値を測定しうる機能を果たしうるものと説明されている。そこで貨幣の本質的機能を価値尺度に求め、そこから流通手段、価値保蔵、支払い手段、世界貨幣といった諸機能を導いてくるのである。この学説は、イギリスの古典派経済学やマルクス経済学によって展開されてきた。主たる学者としては、リカード、クニース、ヒルデブラント、マルクスなどがあげられるが、とくにマルクスによって労働価値説に立脚した貨幣学説として確立されるに至った。これは商品学説ともいわれている。
これに対して名目主義では、金属主義の主張する素材価値たる商品性による一般的価値尺度機能を否定して、貨幣の本質を抽象的機能――一般的交換ないし流通手段――に求める。名目主義の立場をとる代表的学説にF・クナップの国定学説がある。貨幣は素材には関係なく国家の法制だけによって通用力を有するとし、貨幣の本質を流通手段に求めるのがこれである。名目主義は、さらに、貨幣は商品に対する一般的参加票券であるとするF・ベンディクセン、K・エルスターの票券説(指図証券説)、貨幣は貨幣としての機能を営むいっさいのものであるとするL・F・ミーゼス、K・ヘルフェリッヒの職能学説、さらに貨幣は商品価値の比率を表す抽象的計算単位であるとするR・リーフマンの抽象学説に発展した。このように名目主義は、20世紀に入ってからドイツを中心に盛んになったものであるといえる。
20世紀前半を代表する近代経済学者ケインズも、『貨幣論』(1930)において名目主義の立場にたって、貨幣を単なる購買手段の機能をもつものと考えて、計算貨幣という概念を使っている。ケインズの計算貨幣は、債務、諸価格、一般購買力がそれにおいて表現されるもので、金属主義でいう価値尺度としての貨幣の機能に相当するものである。
以下、名目主義の流れをくむ近代経済学における貨幣理論と金属主義を代表しているマルクス経済学における貨幣理論について解説することとしたい。
[原 司郎]
近代経済学における貨幣
2種の貨幣――計算貨幣と現実の貨幣
貨幣とは、取引の完結に際し生ずる債権・債務関係の決済のために用いられる手段、もしくは社会制度をいう。計算貨幣と現実の貨幣の2種がある。
計算貨幣は、国民所得の大きさを示したり、鉄1キログラムの値うちと綿(わた)1キログラムの値うちを比べたりする場合のように、経済的価値の集計や比較を行う際に一般に用いられる単位である。円、ドル、ユーロなどの称呼(となえ)がそれにあたり、おおむね国ごとに異なる。計算貨幣の多くは重量の単位でもあるが、これはかつて決済の多くが、それに使用する金属の重量をそのつど量る習慣があったことの名残(なごり)にすぎない。日本の計算貨幣である「円」が単に丸いことを表して、重量とはまったく無関係であることからもわかるように、計算貨幣は度量衡や時間などの単位とは切り離され、もっぱら経済計算のためにのみ用いられる抽象的単位であって、実体をもたない。「貨幣」とは、こうした計算貨幣で計ったとき、その価格(表された値)が固定かつ不変のものである。計算貨幣との関係をより明確にするために、貨幣を「現実の貨幣」とよぶこともあるが、両者の関係は、たとえば1万円札という「通貨」は、昨日も今日も明日も、「計算貨幣・円」の1万単位によって表されて変わらないという事実によっていっそう明らかになるであろう。
もっとも、通貨を計算貨幣で表した値は不変でも、通貨を通貨以外の財やサービスによって計った値は日々変動する。しかし一般に人は、たとえば100円の缶コーヒーが1000円になったとき、通貨で計った缶コーヒーの価格が10倍に上がったとはいっても、通貨の(缶コーヒーで計った)値うちが10分の1に下がったとはいわない。このように計算貨幣と通貨は経済生活の基準になっている。ただし通貨は、計算貨幣が抽象的単位であるのに対して、現実の経済的取引に伴って生ずる債務の最終的決済手段として働く実体でもある。
[堀家文吉郎]
2種の通貨――国家貨幣(あるいは現金通貨)と銀行貨幣(あるいは預金通貨)
特定の実質・形式のものを貨幣であると宣言する力を「貨幣高権(こうけん)」とよぶが、これを近代国家の確立とともに国家がもつことになった。国家は通貨の偽造に重刑を科し、納税を通貨によるべきものとし、また民間の通貨による取引決済を最終的なものと公認することで、貨幣高権を確実なものとした。法貨の成立である。その後、鋳貨の製造技術が発達し、偽造がむずかしくなるにつれて、鋳貨に打ってある額面価値と鋳貨をつぶしたときの素材価値とは離れていった。素材の財としての価値を問うことなく、鋳貨が流通したからである。鋳貨は財・サービスとはまったく別の、その素材を財として利用することを予定しない、貨幣という一つの資産となった。
その後、鋳貨は年を経るにつれて額面価値に対して素材価値を低下させていき、その極限に今日の補助貨や政府紙幣が位置するまでになっている。この系列の貨幣は、国家の権力が根拠となって機能する貨幣なので国家貨幣といわれ、それの現実の受け渡しによって流通する貨幣なので「現金通貨」ともよばれる。
国家貨幣とは別に、のちに銀行貨幣が生まれた。これは、民間の金融機関である銀行が、要求がありしだい即時に現金(国家貨幣)を引き渡すと約束した自己あて債務のことである。銀行貨幣は初め銀行券(銀行振出しの持参人要求払いの約束手形)の形をとっていたが、各種の銀行券が発行されて混乱を招いたので、銀行券の発行は中央銀行が独占することとなった。この場合でも、初めは中央銀行は銀行券の金兌換(だかん)を義務づけられ(銀行券と金の交換比率、すなわち金平価を国家が法定する金本位制度の下で)、人々は銀行券を金に交換できるもの(兌換銀行券)として信頼し、中央銀行はそのゆえに銀行券発行残高に対して一定の金準備(保証準備)を保有しなくてはならなかった。この意味で銀行券は金本位制度の下では信用貨幣(銀行に対する信用によって流通する貨幣)であったが、管理通貨制度となって金兌換が停止されるに至って(不換銀行券化)、国家が銀行券に強制通用力を与えることが、銀行券に対する信頼の基礎となった。この段階で銀行券は国家貨幣に編入され、銀行貨幣であることをやめた。日本の日本銀行券は国家貨幣である。
銀行券の発行ができなくなった銀行は、要求払預金を銀行貨幣とした。これは銀行券と違って形がなく、即時に現金にかえうるが現金ではなく、単なる銀行の帳簿上の数字で、預金者の小切手(銀行あてに振り出した要求払いの為替(かわせ)手形)や口座振替の指図によっても移動して債務の決済に用いうる銀行の債務である。銀行貨幣は、法的に債務を最終的に決済する国家貨幣とは異なり、銀行という民間の機関の債務への社会的信認を成立の根拠とするから、厳密な意味でこれを貨幣といえるかということについては議論がある。
しかし、要求払預金は、もともと不足がちの国家貨幣の使用を節約し、補充する意味で世に受け入れられたもので、(小切手の振出人を含めた)関係者がそれを即時に国家貨幣に取り替えることができないような状態にした場合については、厳しい自主的な制裁があり、また行政上の規制も厳重であるために、実際には現金化されないままに債務の決済に用いられているものである。したがって、制度的にはともかく、機能的には十分に貨幣の働きをしているといってよい。
このように、銀行の要求払預金は、預金のままに移動して貨幣として機能するために、他の金融機関の預貯金で前記と同じ性質の働きをするものをあわせて「預金通貨」とよばれ、統計的には現金通貨(国家貨幣)と並んで一国の貨幣量を構成する部分をなすこととなった。
[堀家文吉郎]
貨幣の機能――交換媒介と価値貯蔵
国家貨幣にせよ銀行貨幣にせよ、それが貨幣として働くということは、第一に経済的「価値の尺度」として働くということである。しかし、貨幣を計算貨幣で計った値が不変であるために、あたかも貨幣が価値尺度のようにみえるのであるから、これはむしろ現実の貨幣の機能ではなく、計算貨幣の機能というべきであろう。第二に貨幣は財やサービスを買うのに使われる。そしてその貨幣は財やサービスを売って得るのであるから、結局は貨幣は財やサービスの「交換の媒介」をしていることになる。しかし、貨幣が媒介をする交換は、財・サービスと貨幣を交換する段階と、貨幣と財・サービスを交換する段階の二つからなっており、二つの段階の間には通常時間的な隔たりがある。この二つの時点の間、貨幣は動くことがなく、1か所にとどまっているのであるが、その間貨幣は「価値貯蔵」の働きをしているのである。
しかし、交換の媒介と価値貯蔵の二つの機能は切り離すことができない。というのは、貨幣を手放す者は相手が価値貯蔵に役だてることを知るから手放すのであるし、貨幣を受け取る者は将来交換の媒介に用いうることを知るから保有するのである。人は、しかるべき財やサービスをしかるべき条件で提供する者に巡り会うまでの時間と煩労(すなわち情報コスト)と、受け取った貨幣を次に支払いに用いるときに被る減価などの損失(取引コスト)が、できるだけ少なくなるように試みて貨幣にたどり着いたのであった。けれども、これら二つのコストを可能な限り小さくし、交換媒介と価値貯蔵の二つの機能を貨幣が十分に果たすためには、貨幣を財・サービス一般で計った価格、すなわち貨幣が他財を支配する力、つまり「購買力」が不変で(あると少なくとも思われてい)なければならない。
幸いにして、貨幣を計算貨幣で計った価格が不変なので、今日1000円札で買えたものは明日は1000円札で買えないかもしれないが、今日も明日も1000円の正札がついたものは確実に買えるために、あたかも貨幣の購買力は不変だと思い込む「貨幣錯覚」が生じやすく、それが大きな支えとなってきたことは事実である。
[堀家文吉郎]
貨幣の需要と動機
貨幣が動く姿をみることはむずかしい。現金ならどうかというと、それも一瞬のことであるし、そのうえに貨幣には形のないものがある。それで、貨幣の量をとらえるには残高(ある一時点の量)によることになった。残高ならば、いつにせよ、すべてがだれかの手中にあるわけである。
貨幣を保有する動機には次の三つが考えられる。第一に、たとえだれにしてもある人の、ある期間中の貨幣の受け払いの累計額が等しくなっていても、期間中のすべての時点において受け払いの額が等しいということではない。他方で、債務には約束した時点でかならず債務を履行するという、若干の罰則を伴う誠実の原則があるので、債務は約束された時点でかならず決済されなければならない。このために若干の残高の保有が必要である(取引動機)。第二に、期待がそのとおりに実現するとは限らない。貨幣を使いたい財・サービスが思いがけず出てくることもあろう。その場合でも誠実の原則は働く。このためにも若干の残高が保有される(予備的動機)。第三に、貨幣はだれにでもいつでも受け取れるので、いまも将来も使う気はないものを売買してその差益を手にする機会をねらう目的でも、人は貨幣を手元に保有する(投機的動機)。このように貨幣保有の動機は三つあるけれども、その貨幣残高のどの部分がどの動機によるものかは具体的には示せない。しかし、一括して「流動性選好」ということはできる。
一般に資産の流動性には二つの要素がある。一つは他の財・サービスにかえやすいという性質、つまり市場性で、他は貨幣で計った価格が安定しているという性質、すなわち市場価値の安定性である。これら二つの要素は、どの資産にも多かれ少なかれある。しかし貨幣はこれら二つの要素において、他のどの資産よりも優れている(もっとも、貨幣にも他の財・サービスで計った価格(購買力)が変動するという難点はある。しかしそれは貨幣錯覚によって覆われている)。
[堀家文吉郎]
貨幣の供給――抽象化
19世紀と20世紀の変わり目ごろに、貨幣がなにゆえに貨幣たりうるかを問う貨幣本質論争が、素材の価値に根拠を置く金属主義と、それに反対する名目主義との間で争われた。しかしその後、現金(国家貨幣)さえも、紙というほとんどまったく無価値に近い素材でつくられるようになり、預金(銀行貨幣)が残高においても圧倒的に多くなったので、今日では結局、貨幣の働きをするものが貨幣だという考え(職能主義)が支配的になってきている。
このように貨幣が素材を問題としなくなる無体化の過程のなかで、貨幣を貨幣として使用させうる者の範囲が政府・中央銀行のほかに、民間金融機関一般(たとえば信用組合)へとしだいに広がってきた。そのうえ現今では、金融機関ではない企業・個人にも(預金担保や当座貸越の形で)あらかじめ信用枠が与えられていて、彼らはその枠を随時購買力となしうるから、一国の貨幣の供給可能量を残高としてはとらええない。それに、貨幣が人手をかえる早さは、近年の電子的な技術進歩の結果、著しく増大してきているので、一期間中に動いた、あるいは動くであろう本当の購買力の大きさ(延べ量)はとらえにくくなった。このため、政府・中央銀行の各種の試みにもかかわらず、貨幣供給量変動の効果の把握はますます困難になってきている。
それにもかかわらず、通貨当局(政府・日本銀行)は、物価安定・雇用安定などの目標達成の手段としての貨幣供給量全体を、常時正確に把握していなければならない。ところがこれはまったく不可能である。
[堀家文吉郎]
電子商取引における貨幣
インターネットによる電子商取引はバーチャル(仮想的)、ないしデジタル社会のものであるが、近年では著しく流行し、その重みを増してきている。ただし、この場合に機能しているのは計算貨幣であって、現実の貨幣ではない。この場合、計算貨幣の単位は、本来無国籍である当事者間の仮想的社会においては、取引当事者間の合意さえあれば、自国内で一般に広く使われている単位にとらわれる必要はまったくなく、外国の単位でも、あるいはそれらとさえまったく無関係な単なる「音」でもよい。しかし、財・サービスの取引が、取引として決済されるためには、現在では国家の法制が必要である。このことから将来、現実に世界国家に相応する組織が、現在の各国のように徴税権を確立し、治安の維持をまっとうしうるに至るのであればとにかく、それまでの間は仮想社会に、現在諸国にあるものに匹敵する現実の貨幣は存在しえない。
世界が国境を越えたグローバリゼーションの結果、インターネット社会をも包括する取引決済に用いうる貨幣をもつためには、世界国家(少なくとも世界連合)が成立し、それが機能していなければならず、この意味で貨幣は、現在のところ各国がもつ「貨幣高権」に支えられているのである。
[堀家文吉郎]
マルクス経済学における貨幣
貨幣の本質
商品の価値の実体は抽象的・人間的労働であり、価値の大きさは商品を生産するのに社会的に必要な労働時間によって度量されるが、商品価値は社会的なものであり、それ自体では表現されず、他の商品との価値関係においてのみ現象しうる。この価値の現象形態を価値形態という。この価値形態のもっとも単純な形態は、「x量の商品A=y量の商品B」である。この価値等式においては、両商品はまったく異なった役割を演じている。すなわち、A商品の価値だけが表現されており、B商品はA商品の価値表現の材料として役だっているにすぎない。A商品の価値はB商品の使用価値(商品体)そのものによって表現されているのである。この価値等式においては、x量のA商品はy量のB商品に等しいということによって、A商品はB商品に交換を申し出ているのであり、これによってB商品はA商品との直接的交換可能性を与えられる。他の商品の価値表現の材料として役だっている商品を等価形態という。上記の単純な価値形態が発展して、すべての商品が左辺に立ち、ただ一つの商品金(きん)が商品世界から排除されて右辺(等価形態)に置かれ、この金がすべての商品の価値を表現する一般的等価形態となり、すべての商品との直接的交換可能性をもつようになったとき、金は貨幣となる。この貨幣は次の3機能を果たしている。
[二瓶 敏]
価値尺度
貨幣=金の第一の機能である価値尺度機能は、商品世界に対して価値表現の材料を提供するということである。諸商品の価値が金という同一商品で表現されることによって、諸商品が価値としては質的に均等であり、したがって、諸商品の価値を量的に比較することが可能となる。労働時間が価値の内在的価値尺度であるのに対して、貨幣はその外在的価値尺度ということができる。「米10キログラム=金0.75グラム」というように、商品の価値を金の一定量で表現したものが価格である。すべての商品価値をさまざまな金分量で表現するためには、金そのものの分量を度量する基準を確定しておかねばならない。これを価格の度量基準という。価格の度量基準は根源的には重量の度量基準と一致していたが、一般的妥当性が必要なので、やがて法律によって調整される。日本の場合、1897年(明治30)の貨幣法第2条で、純金2分(750ミリグラム)をもって価格の単位となし、これを円と称すると定められていた。これによって商品の価格は、「米10キログラム=金1円」という法律上有効な貨幣称呼で表現されるようになる。商品にこのような貨幣称呼を付与する場合、現実の貨幣がそこに存在する必要はなく、価値尺度機能においては貨幣は観念的な存在にすぎない。しかし交換過程では商品は現実の貨幣に転化される。
[二瓶 敏]
流通手段
価格を付与されて流通過程に投ぜられた商品は次のような運動を行う。W(商品)―G(貨幣)―W(商品)である。これが商品の姿態変換である。このうちW―Gが販売であり、G―Wが購買である。商品の姿態変換W―G―Wのうち、困難なのは商品の販売W―Gである。というのは、無政府性的な商品生産のもとでは販売の成功はまったく偶然的だからである。商品の販売が行われて貨幣に転化することに成功したならば、貨幣はすべての商品との交換可能性を有しているので、次の購買に困難は存在しない。
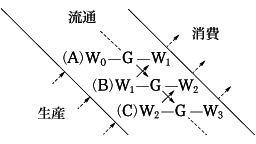
から明らかなように、A生産者にとっての購買G―W1は、B生産者にとっては商品の販売W1―Gである。このように商品の販売と購買は絡み合っているので、A生産者の商品の姿態変換W0―G―W1は、B生産者のそれW1―G―W2と絡み合っている。こうした諸商品の姿態変換の絡み合いを商品流通といい、それを媒介する貨幣を流通手段という。
商品は、生産されて流通に投ぜられ、そこでの持ち手変換ののち消費されて流通から脱落していくのに対して、貨幣は、出発点から遠ざかりながら絶えず流通にとどまっている。ある一定期間における商品流通を媒介するのに必要な貨幣量Mは、M=PT/V(P=商品の価格、T=商品総量、V=貨幣の平均流通速度)で求めることができる。これが流通貨幣量に関する法則であり、この法則の眼目は、流通必要貨幣量Mは、貨幣の平均流通速度Vを一定とした場合、流通諸商品の価格総額(PT)によって規定されるということである。貨幣の流通手段機能は、商品流通を媒介する一時的、瞬間的なものであるから、この機能に限って、銀や銅で鋳造された補助貨幣や、相対的に無価値な政府紙幣も、金の代理としてこの機能を果たすことができる。政府紙幣は政府が法的に強制通用力を与えるものであるから、流通必要金量を超えて発行しうるが、この場合には紙幣の代表する金量は低下し、商品価格は名目的に騰貴する。これがインフレーションである。
[二瓶 敏]
貨幣としての貨幣
価値尺度機能においては貨幣は観念的な存在であり、流通手段機能においては象徴によって代表可能であるのに対して、金が現身で現れ、価値の自立的存在として固定化される場合の機能を貨幣としての貨幣という。これは蓄蔵貨幣、支払い手段、世界貨幣という三つの存在形態をもつ。①蓄蔵貨幣は、商品流通がW―Gで中断されて流通から引き上げられ、流通手段としての機能が否定された貨幣である。蓄蔵貨幣の大部分は銀行に集積され、流通貨幣量を調節する機能を果たす。②支払い手段は、商品が信用で販売され、そこで取り結ばれた債権債務関係を、あとで貨幣が自立的に決済する場合の貨幣である。③貨幣は国内流通部面から歩み出て、世界市場に登場するとともに世界貨幣に転化する。貨幣はそこでは金の地金形態で表れる。世界貨幣は、国際収支の決済等の一般的支払い手段、一般的な購買手段として機能し、賠償金支払いのように富を他国に移譲する場合、富一般の絶対的物質化としても機能する。
[二瓶 敏]
貨幣の歴史
原始貨幣の生成
原始社会において物々交換が盛んに行われるようになると、物資の交換に伴う不便を取り除くために、交換の媒介物として物品貨幣(自然貨幣)が用いられるに至った。これが原始貨幣とよばれるもので、比較的処分の容易な物が利用された。その代表的なものとして、穀物(中部アメリカ、フィリピン、中国、日本)、布帛(ふはく)(中国、日本)、家畜(ギリシア、ローマ、南アフリカ)、農具(中国)、塩(エチオピア)、武器(古代イギリス)、毛皮(シベリア)などがあげられる。そのほか、子安貝、赤貝、羽毛、亀甲(きっこう)、鯨歯など、装飾品や儀礼的、呪術(じゅじゅつ)的な物もみられ、その生成には宗教的意義をもつ場合が少なくない。
その後、金属が用いられるようになると、原始貨幣をかたどった鋳造貨幣(鋳貨coin)が現れるに至った。金属は、保存性、等質性、分割性、運搬性など、貨幣の必要な条件をよく満たすことができたからである。中国の布貨、刀貨、魚貨などはその典型的な例である。
また、『旧約聖書』によれば、すでに紀元前2000年ごろに、エジプトやバビロニアにおいて金銀が秤量(ひょうりょう)貨幣として使用されていたとある。このようなものにはほかに、アッシリアの金銀、ペルシアやスパルタの鉄、アラビアの銅、メキシコの錫(すず)などがあった。
[作道洋太郎]
ヨーロッパの貨幣
ギリシアの貨幣
ヨーロッパにおける最古の鋳貨は、前7世紀にリディア王国で鋳造されたエレクトロン貨とされている。エレクトロン貨は金と銀との天然の合金であって、銀がおよそ30%含まれていた。これは鋳貨として一定の形状、品位、量目が定められてつくられた最初の貨幣であった。リディア王国の王侯ギゲスはエレクトロン貨にその価値を保証する刻印を打ち、価値の一様な金属の小片として使用した。その後、ギゲスの後継者クロイソスは、エレクトロン貨にリディア王国の証印を打ち、スタテル貨を鋳造させた。これは近東の各地において流通した。
リディア王国は前6世紀にペルシアによって征服されたが、ペルシア人は貨幣の使用を踏襲した。ペルシア帝国のダリウス(ダレイオス)1世(在位前522~前486)は金シェケルと銀ドラクマとを貨幣単位となし、金銀複本位制度を採用し、ダレイコス金貨ならびにシグロス銀貨を鋳造した。金銀比価は1:131/3と定められた。この比率は以後約2000年にわたって世界各地において用いられるところとなった。
ギリシアでは前6世紀にアイギナ銀貨を鋳造し、のちにアテネにおいても銀貨をつくった。後者の貨幣表面にはアテナ女神の顔、裏面にフクロウとオリーブの絵が刻み込まれている。これは良質の銀貨で、地中海沿岸の国際貨幣となった。前5世紀には、アテネのほかギリシアの都市国家はほとんど独自の貨幣をつくり、それがしだいに南イタリア、小アジア、シチリアの諸都市に及び、ヘレニズム時代にはオリエントにも波及した。前3世紀ごろには古代インドもギリシアの影響を受け、王やアポロンの像を取り入れた貨幣を鋳造した。
[作道洋太郎]
ローマの貨幣
ローマでは前3世紀に大型の青銅貨(アエス・グラウェ)および銀貨(デナリウス)が鋳造され、さらに前1世紀には金貨(アウレウス)がつくられた。アエス青銅貨には貨幣単位(アス)が刻印されており、その表面には両面神のヤヌスの神、裏面には船首の絵が取り入れられている。デナリウス銀貨にも青銅貨10アエスに相当する貨幣単位が刻印されており、その表面にはローマの神、裏面には通商の神であるカストルとポリデウケスの双生神の像とROMAという文字が刻まれている。デナリウス銀貨はローマの造幣所のほか各地で多量につくられ、地中海の西部から中部にかけて主要な通貨となった。また、アウレウス金貨はオリエントの造幣所において鋳造され、その表面にビーナスの像、裏面にインペラトールimperator(軍司令官)という文言や戦利品の模様などが配されている。カエサル(シーザー、前100―前44)の時代には、貨幣にCAESARの文字やカエサルの家紋であるゾウの絵などが刻み込まれている。
カエサルの死後、アントニウス(前82ころ―前30)は、初めガリアで、のちにはオリエントの造幣所で貨幣をつくったが、そのうち小アジアで鋳造された貨幣のなかには、クレオパトラとアントニウスの肖像をいっしょに刻印したものや、軍艦および軍旗のデザインを取り入れたものがみられる。また、アウグストゥス皇帝(在位前27~後14)は本位貨幣としてアウレウス金貨を採用した。この金貨は25デナリウス銀貨と等価とされ、1デナリウスは16アエス青銅貨と等価とされた。アウグストゥス皇帝までは、貨幣のデザインは一定していなかったが、同皇帝以後、貨幣には皇帝の肖像が入れられることになり、皇帝の人格を強調することによって貨幣を神聖なものとし、幣制の統一を実現しようとした。しかし、ネロ皇帝(在位54~68)からカラカラ皇帝(在位211~217)にかけて、ローマ帝国の財政は窮乏化し、金・銀貨ともに数度にわたって、品位、量目を落として改鋳された。コンスタンティヌス大帝(在位306~337)は幣制の改善に努め、アウレウス金貨にかえてソリドゥス金貨を鋳造したが、これは良質の貨幣で、のちに西方にも流布し、1000年以上にわたって通用した。
[作道洋太郎]
ビザンティン帝国の貨幣
ローマ帝国の再建を図り、東ローマ帝国(ビザンティン帝国)を建設したユスティニアヌス皇帝(在位527~565)は、皇帝の肖像を配したソリドゥス金貨をつくり、これを本位貨幣とした。ビザンティン時代には、金貨のほかに銀貨、銅貨も鋳造された。銀貨、銅貨には皇帝の肖像、キリストの胸像、十字架などの模様が取り入れられている。これらの金・銀・銅貨はビザンティン帝国の首都コンスタンティノープル(現在のイスタンブール)でつくられたが、ローマ、カルタゴ、ラベンナ、アレクサンドリアなどにおいても鋳造された。ビザンティン貨幣のうち、とくに金貨は地中海沿岸諸国において広く用いられ、6世紀から7世紀にかけて現在のフランス、ドイツ、ベルギー、オランダ、スカンジナビア、ロシア、バルカン、レバント、北アフリカなどにおいても通用した。
[作道洋太郎]
中世ヨーロッパの貨幣
ゲルマン諸国の幣制は古代地中海文明の遺産のうえに成り立っていた。当時、ゲルマン諸国ではローマ時代の貨幣が一般に慣れ親しまれており、ゲルマン人が占領地域をローマ皇帝の名において支配していた政治的理由もあり、ゲルマン人の首長たちはローマ皇帝の肖像を配した貨幣を鋳造した。しかし、その後しだいにゲルマンの支配者は、ローマ皇帝の名にかえて自分の名を刻印した貨幣に切り替えていった。
ローマ帝国では造幣権は皇帝すなわち国家にあったが、ゲルマン国家の場合、造幣権は国家の独占ではなくなっていた。メロビング朝時代には、王室の造幣所で鋳造された貨幣のほかに、教会、司教、荘園(しょうえん)領主の名においてつくられた貨幣もみられる。また各地の鋳造師によってつくられた放浪貨幣とよばれたものがあったが、品質は粗悪で、権威をもたぬ貨幣であった。
ゲルマン諸国のなかで、フランク系のサリ人だけはメロビング朝時代に独自の幣制を設け、サリカ法典のなかで1ソリドゥス(金貨)=40デナリウス(銀貨)と定め、ローマ時代に実体貨幣であったデナリウス銀貨を計算貨幣としてとらえた。しかし、この新しい体系は不便であったため、カロリング朝時代にはふたたび実体貨幣としてデナリウス銀貨が鋳造された。これはカロリング家の宮宰カール・マルテルの子ピピン3世(在位751~768)とその子カール大帝(在位768~814)によって行われ、新デナリウス銀貨は中世ヨーロッパの本位貨幣となるに至った。カール大帝の子ルイ(ルードウィヒ)1世(敬虔(けいけん)王、在位813~840)はソリドゥス金貨を鋳造したが、これには十字架と「神への贈り物」という文字とが刻印されている。
12世紀になると、十字軍の影響によってオリエントの金がヨーロッパにもたらされ、13世紀には各地で金貨が鋳造された。1251年にフィレンツェでつくられたフロリン金貨はとくに有名で、ヨーロッパの各地に流布し、各国において金貨を新鋳する場合のモデルとなった。フロリン金貨には聖ヨハネの立像とフィレンツェの紋章であるユリの花が刻印されている。
イギリスは、ローマに支配されていた時代にはローマ金貨のソリドゥスを用いていたが、ヘンリー3世(在位1216~1272)が1257年に鋳造したペニー金貨によって最初の自国通貨をもつようになった。1344年にはエドワード3世(在位1327~1377)によってフロリン金貨が導入され、その後ヘンリー7世(在位1485~1509)治下の1487年にはソブリン金貨が鋳造された。この金貨は、表面には王冠をかぶった国王の坐像(ざぞう)、裏面には軍隊の盾とチューダー家のバラの紋章が刻印されている。
[作道洋太郎]
近世の貨幣
16世紀に入って、アメリカ大陸から多量の銀がヨーロッパ諸国に流入し、そのため各国の金銀比価は激しく変動し、価格革命を引き起こした。これに伴ってヨーロッパの貨幣制度も大きな変化を示し、スペインのペソ貨は国際的に有力な貿易用の貨幣となった。ドイツでは1520年から大型のターレル銀貨が鋳造された。ターレル銀貨は、表面には肖像、裏面には紋章が配されており、やがてクラウン、ドル、ドゥカートン、エキュ・ダルジャン、パタコン、ピアストル、ルーブルといった各種の名称でヨーロッパ諸国の造幣所においてつくられるようになった。またイギリスでは、チューダー家のエドワード6世(在位1547~1553)のとき、それまでのソブリン金貨のほかに、ローマの幣制に倣った貨幣面に通用価格を表示したシリング貨やペニー貨が鋳造された。
近世になると、貨幣の鋳造に際して中央集権国家が造幣権を封建諸侯から奪い取り、幣制の割拠体制を打破して統一を図ろうとした点に特徴がみられる。貨幣の模様もキリスト、教会、城、都市、封建領主などにかわって絶対君主の肖像が取り入れられることが多くなった。
[作道洋太郎]
近代の貨幣
産業革命の結果、造幣機械の導入によって、均一な貨幣が大量に製造されるようになり、貨幣の製造費も低廉となった。18世紀の末期から19世紀の初めにかけて、マルク、フラン、リラ、ペセタなどの貨幣単位が現れるに至った。また19世紀のなかばごろから鋳貨と並んで紙幣が一般化するようになった。さらに19世紀後半から20世紀にかけて各国において金本位制度が採用され、世界的な規模で貨幣金融制度の統一基盤が形づくられた。
産業革命を最初に行ったイギリスでは、チャールズ2世(在位1660~1685)治下の1662年に造幣局に新設された工場で近代貨幣のギニー金貨を製造し、従来の金貨と取り替え、ついで銀貨と銅貨も製造した。その後ビクトリア女王(在位1837~1901)治下の1848年には2シリング金貨(フロリン)がつくられ、人々の人気をよんだ。
アメリカにおける最初の貨幣は、ボストン造幣局で1652年から1682年にかけてつくられたシリング銀貨、6ペンス銀貨、3ペンス銀貨であった。それまでにイギリス、スペインなどの貨幣が流入していたが、その数量は少なかった。独立戦争が終結し、アメリカの独立が承認された1783年には銅貨がつくられ、初代大統領ワシントンの肖像が刻印された。1785年には連邦会議において新しい幣制が採用され、ドルは正式にアメリカの貨幣単位となった。さらに1792年には通貨法と貨幣製造法が制定され、金銀複本位制度を採用することとなり、フィラデルフィア造幣局が開設された。同年10月に5セント貨幣、翌1793年に1セント、1/2セントの貨幣が製造され、1794年には有名な彫金家のロバート・スコットにより銀貨がつくられ、ついで1795年から金貨が製造された。
世界における紙幣の始まりは、1392年ロンドンに設立された金匠会社発行の金銀預り証「ゴールドスミス・ノート」であった。その後、イギリスでは1694年にイングランド銀行が創設され、最初の銀行券が発行された。この制度は、その後しだいに世界諸国に広がっていった。アメリカで最初の紙幣は、植民地時代の1690年にマサチューセッツで発行されたもので、その後18世紀初めまでにコネティカット、ニュー・ハンプシャー、ロード・アイランド、ニューヨーク、ニュー・ジャージーなどの諸州で相次いで発行された。
なお、戦争や革命など国家の変動期には、当面の経費をまかなうために政府紙幣が発行されたことがある。もっとも有名なものは、1789年のフランス革命に際して革命政府が発行したアッシニア紙幣と、アメリカで南北戦争(1861~1865)当時に発行されたグリーン・バック(緑背紙幣)とよばれる政府紙幣である。明治維新に際して維新政府が1868年(慶応4)5月に発行した太政官札(だじょうかんさつ)もこの系列に属するものといえよう。
[作道洋太郎]
中国の貨幣
殷(いん)から周時代の初めにかけては、貝殻、亀甲(きっこう)、真珠、宝石などが交換手段として用いられた。周の時代にはやがて布貨(布幣)、刀貨(刀幣)、魚貨(魚幣)が用いられるようになった。これらは物品貨幣の名残(なごり)をとどめたもので、円形の鋳貨が出現する以前における鋳貨の一種であったとみられる。布貨は農具として使われてきた鍬(くわ)や鋤(すき)の原型である鎛(ふ)から進化したもので、その形状から空首布(くうしゅふ)、尖足布(せんそくふ)、方足布(ほうそくふ)、円足布などに類別される。刀貨は家庭用の小刀から発展したもので、形態のうえから尖首刀、円首刀、反首刀に大別される。魚貨は内陸地方の生活必需品であった干魚が物品貨幣として用いられていたことに端を発して、これが交換用の鋳貨となるに至った。これらの布貨、刀貨、魚貨に次いで、周の時代には、垣銭(えんせん)または垣字銭(えんじせん)とよばれた円形の鋳貨がつくられた。これは環幣(かんぺい)ともとなえられ、丸い鋳貨に丸い穴があけられている。それが周の両甾銭(りょうしせん)になると、鋳貨の穴が四角になっている。
秦(しん)の始皇帝(在位前247~前210)は円形方孔銭(ほうこうせん)をつくり、銅銭による貨幣の統一を図り、旧来の布貨、刀貨などの使用を禁止し、造幣権を国家の手に収めた。これは漢代にも引き継がれ、漢の武帝(在位前141~前87)は五銖銭(ごしゅせん)を発行した。これはその後約800年にわたり中国の貨幣として存続した。漢を滅亡させた新(しん)の王莽(おうもう)(在位9~23)は大泉五十、契刀(けいとう)、貨布などの王莽銭を鋳造したが、新は15年で崩壊したので、王莽銭も一時的なものにすぎなかった。唐の高祖(在位618~626)は開元通宝を新鋳した。これは国内のみならず広くアジアの諸国において使用された。日本においては、7世紀後半に鋳造された銅貨である富本銭(ふほんせん)と8世紀初頭の和同開珎(わどうかいちん)(「わどうかいほう」ともよぶ)が、これをモデルとしてつくられたものである。さらに宋(そう)、元(げん)、明(みん)の銅銭も日本に流入し、鎌倉時代から室町時代にかけて、日本の貨幣の大部分を占めた。とくに明の成祖永楽帝(在位1402~1424)の永楽通宝はその代表的なもので、江戸初期まで通用した。
紙幣は宋代から発行され、金、元、明、清(しん)代へと引き継がれていった。元の世祖フビライ(在位1260~1294)の治世下には鋳貨を廃して紙幣を使用させたことが、マルコ・ポーロの『東方見聞録』にみられる。
明代にはスペイン銀、清代にはメキシコ銀やヨーロッパの洋銀が中国に流入し、全土に広まっていった。これに対抗するために、清代後期には新しい造幣所が設立され、ヨーロッパ型の銀貨や銅貨が大量に鋳造されるようになった。
辛亥(しんがい)革命の結果、1912年に中華民国が成立すると、国幣条例によって銀元が本位貨幣と定められ、孫文や袁世凱(えんせいがい)の肖像を刻印した貨幣が発行された。しかし、主要国はすでに19世紀後半から相次いで金本位制度に移行しており、銀価の変動は激しくなっていた。中国は最後まで銀本位国として残っていたが、1935年にはついに金本位制度の一つである金為替(かわせ)本位制度へと移行した。
[作道洋太郎]
日本の貨幣
古代の貨幣
日本における最初の官銭は、7世紀後半に鋳造された富本銭とされ、唐の制度を模倣して鋳銭事業が開始された。その後、奈良・平安時代には、708年(和銅1)に鋳造された和同開珎、万年通宝(760創鋳)、神功(じんぐう)開宝(765)、隆平永宝(796)、富寿神宝(818)、承和昌宝(じょうわしょうほう)(835)、長年大宝(848)、饒益(じょうえき/にょうやく)神宝(859)、貞観(じょうがん)永宝(870)、寛平(かんぴょう)大宝(890)、延喜(えんぎ)通宝(907)、乾元(けんげん)大宝(958)が引き続いて発行された。これらのうち富本銭を除く12の官銭を総称して皇朝十二銭または本朝十二銭と呼び習わしてきた。和同開珎には銀銭と銅銭とがあったが、そのほかの皇朝銭はすべて銅銭であった。皇朝銭のほかに760年(天平宝字4)には日本で最初の金銭である開基勝宝がつくられ、また同年に銀銭の太平元宝も鋳造された。
[作道洋太郎]
中世の貨幣
律令(りつりょう)国家における政治力の弱体化により、乾元大宝を最後として鋳銭事業は停止され、平安末期には唐の銭貨が日本に流入し、鎌倉時代には宋銭、室町時代には明銭が輸入され、日本においても通用した。洪武通宝、永楽通宝、宣徳通宝などは代表的な明銭であった。中世の貨幣には、このような中国における官鋳制銭のほかに、日本製の模造銭や私鋳銭がみられ、精銭(せいせん)と鐚銭(びたせん)とが並んで用いられたので、撰銭(えりぜに)の現象が発生した。室町時代には銭貨のほかに金貨や銀貨も鋳造され、さらに戦国時代になると諸国の金山、銀山が開発され、戦国諸侯により金・銀貨が盛んにつくられるようになった。これは領内の流通市場において必要とした貨幣というよりも、軍用金としてつくられたものであった。
[作道洋太郎]
近世の貨幣
安土(あづち)桃山時代には、豊臣(とよとみ)秀吉が各種の金・銀貨を鋳造し、これを軍資金とした。とくに、世界最大の金貨とさえいわれる天正(てんしょう)大判は有名である。天正大判には天正菱(ひし)大判と天正長大判とがあり、菱大判は1588年(天正16)に後藤徳乗に命じてつくらせたものと伝えられている。
江戸時代には幣制が統一され、金座、銀座、銭座(ぜにざ)において金貨、銀貨、銭貨の三貨を鋳造し、幕府は全国通用の正貨とした。金貨には大判(十両)、五両判、小判(一両)、二分判、一分判、二朱判、一朱判があり、銀貨には秤量(ひょうりょう)貨幣の丁銀、小玉銀(小粒(こつぶ)銀、豆板銀ともいう)のほか、定位銀貨として五匁銀、一分銀、二朱銀、一朱銀がつくられた。銭貨には慶長(けいちょう)通宝、元和(げんな)通宝、寛永(かんえい)通宝、宝永(ほうえい)通宝、天保(てんぽう)通宝、文久(ぶんきゅう)永宝があった。三貨のうち金貨と銀貨はしばしば改鋳され、幕府は財政窮乏を打開するために改鋳益金を収得した場合が多い。金貨のうち大判には、慶長大判(1601創鋳)、元禄(げんろく)大判(1695)、享保(きょうほう)大判(1725)、天保大判(1838)、万延(まんえん)大判(1860)の5種類があり、また小判には、慶長小判(1601)、元禄小判(1695)、宝永小判(1710)、正徳(しょうとく)小判(1714)、享保小判(1716)、元文(げんぶん)小判(1736)、文政(ぶんせい)小判(1819)、天保小判(1837)、安政(あんせい)小判(1859)、万延小判(1860)の10種類があった。小判は大判に比べて改鋳の機会が多く、それだけ小判には日常的な通貨の性格が比較的強かったとみられている。銀貨の丁銀および小玉銀は小判とほとんど同じように幕府によって改鋳が繰り返され、慶長丁銀・小玉銀(1601)、元禄丁銀・小玉銀(1695)、宝永二ツ宝丁銀・小玉銀(1706)、宝永永字丁銀・小玉銀(1710)、宝永三ツ宝丁銀・小玉銀(1710)、宝永四ツ宝丁銀・小玉銀(1711)、正徳丁銀・小玉銀(1714)、元文丁銀・小玉銀(1736)、文政丁銀・小玉銀(1820)、天保丁銀・小玉銀(1837)、安政丁銀・小玉銀(1859)の11種類に達した。これらの三貨の交換割合は幕府により1609年(慶長14)に金1両=銀50匁=銭4貫文と定められたが、1700年(元禄13)には金1両=銀60匁=銭4貫文と改定された。この法定相場は市中では絶えず変動しており、実際には変動相場制が長く維持された。
幕府貨幣の三貨のほかに、大名領国では藩札とよばれる紙幣が発行された。最初の藩札は1661年(寛文1)発行の福井藩札であった。明治政府により藩札処分令が発せられた1871年(明治4)の調査によれば244藩で藩札が発行されていた。
[作道洋太郎]
近代の貨幣
明治新政府は、1871年に新貨条例を制定するとともに、幣制改革のために造幣寮(現在の独立行政法人造幣局)と紙幣寮(現在の独立行政法人国立印刷局)を開設した。新貨条例において、日本の貨幣の単位は正式に円とされ、円の価値は純金1.5グラムと定められた。また、補助単位として銭、厘が設けられ、十進法が採用された。本位貨幣として20円、10円、5円、2円、1円の金貨、補助貨幣として50銭、20銭、10銭、5銭の銀貨、2銭、1銭、半銭、1厘の銅貨が鋳造されることとなったが、銀本位国に囲まれた日本の実情から、貿易の便宜上、1円銀貨の発行を定め、事実上無制限の通貨として認めた。そのため、新貨条例が金本位制度をとったとはいえ、現実には金銀複本位制度の性格をもつものとなった。このような金銀複本位制度を維持するにあたってもっとも重要なことは、金銀比価がつねに一定していることである。しかし、新貨条例による金銀比価は1対16であったが、その後銀価が低落を続けたため、金銀比価は上昇し、グレシャムの法則が働いて、金貨はまもなく流通界から姿を消してしまった。すなわち、実質的には銀本位制度になってしまったわけである。
明治政府は、このように新貨条例を定めて近代的貨幣制度を確立したが、これに前後して、当面の経費をまかなうために、太政官札(金札)、民部省札、大蔵省兌換(だかん)証券、開拓使兌換証券などを発行した。しかし、これらの紙幣は印刷技術が幼稚で、偽造されることも多かったため、政府は新紙幣に統一することとし、1872年2月から新紙幣を発行した。この紙幣は正式には明治通宝というが、ドイツで印刷されたため、一般にはゲルマン紙幣とよばれた。1881年からは、この新紙幣にかわって神功(じんぐう)皇后像の改造紙幣が国内で印刷され、発行された。
このような政府紙幣のほかに、殖産興業政策の一環として1869年に東京など8か所に設置された為替(かわせ)会社も紙幣を発行し、また、国立銀行条例に基づいて1873年から設立された国立銀行も、当初は金貨兌換紙幣を、1876年の同条例改定後は政府紙幣との兌換紙幣を大量に発行した。
これら各種の紙幣の整理は、1881年に大蔵卿(きょう)に就任した松方正義(まつかたまさよし)によって推進されることになった。1882年には中央銀行として日本銀行が設立され、国立銀行紙幣を新たに発行することは禁止された。1884年には兌換銀行券条例が制定され、翌1885年から日本銀行の銀貨兌換銀行券が発行された。この最初の日本銀行券には大黒天の像が印刷されており、100円、10円、5円、1円の4種類があった。1888年からはこれにかわって改造券が発行されることとなり、100円券には藤原鎌足(ふじわらのかまたり)、10円券には和気清麻呂(わけのきよまろ)、5円券には菅原道真(すがわらのみちざね)、1円券には武内宿禰(たけしうちのすくね)の肖像が採用された。なお、このころまでにつくられた紙幣の下絵および原版製作は、当時印刷局に招聘(しょうへい)されていたイタリア人エドアルド・キヨソーネによるものがほとんどである。
19世紀の後半に入ると、イギリスをはじめとして、欧米の先進諸国は相次いで金本位制度に移行し、その影響もあって銀価はますます低落の度を強め、銀本位国の経済を圧迫していた。日本も1897年に至り、ようやく金本位制度を基幹とする貨幣法を制定、公布した。これは日清(にっしん)戦争(1894~1895)の賠償金を準備金に設定したもので、円の価値を従前の純金1.5グラムから0.75グラムへと平価の半減を行い、本位貨幣として20円、10円、5円の金貨、補助貨幣として50銭、20銭、10銭の銀貨、5銭の白銅貨、1銭、5厘の青銅貨を鋳造するというものであった。また、日本銀行の銀貨兌換銀行券は金貨兌換銀行券に改定された。
[作道洋太郎]
現代の貨幣
第一次世界大戦が勃発(ぼっぱつ)すると、日本も大戦の影響を受けて1917年(大正6)に金輸出を禁止し、金本位制度を停止した。大戦後、主要国はただちに金本位制度に復帰したが、日本は戦後恐慌(1920)、関東大震災(1923)、金融恐慌(1927)などのため復帰が遅れ、ようやく1930年(昭和5)1月に金輸出を解禁した。しかし、たまたまアメリカに端を発した大恐慌が進行していた時期に旧平価で解禁したため、金の流出をもたらし、また、金本位制度維持のための緊縮政策は、大恐慌による海外からの打撃と相まって、国民生活に深刻な影響を及ぼし、翌1931年12月には金輸出再禁止が実施された。ここに日本における金本位制度は終わりを告げ、管理通貨制度へと移行したのである。
1931年9月の満州事変勃発後、日本では日増しに戦時体制が強化され、それとともに貨幣素材はしだいに悪化と軽量化の道をたどっていった。すなわち、1933年には補助貨幣の10銭、5銭が白銅貨からニッケル貨にかわり、1937年7月に日中戦争が勃発すると、翌1938年5月には臨時通貨法が制定され、ニッケル貨はアルミニウム貨に、「50銭ギザ」として親しまれていた銀貨は、富士山に梅花を配した50銭政府紙幣に切り替えられた。その後第二次世界大戦に入ると、1944年3月には10銭、5銭は錫(すず)貨に、1銭は錫亜鉛貨になり、同年8月には10銭と5銭の錫貨にかわって八紘一宇(はっこういちう)の塔のデザインのある10銭、楠木正成(くすのきまさしげ)像の5銭の日本銀行券が発行された。さらに戦争末期の1945年になると陶器製の10銭、5銭、1銭貨幣の製造さえ進められていたが、発行されないうちに終戦を迎えた。
第二次世界大戦後、インフレの異常な高進に対処するために、1946年(昭和21)2月には金融緊急措置令に基づいて旧円から新円への切り替えが行われ、新円として聖徳太子の肖像の100円券、国会議事堂の10円券、唐草(からくさ)模様を配した5円券、二宮尊徳(にのみやそんとく)の1円券が発行された。また、新しく菊紋と稲穂の10銭アルミニウム貨、菊紋と鳩(はと)の5銭錫貨、および産業立国を象徴する鍬(くわ)、つるはし、稲、麦、魚、歯車を配した50銭黄銅貨が発行された。このうち50銭黄銅貨は翌1947年には直径・量目を縮小し、図案も菊紋と桜花に改められた。1948年5月には小額紙幣整理法が制定されて、50銭以下の紙幣は同年8月末日をもって通用禁止とされ、回収が進められた。また同年9月には国会議事堂の5円黄銅貨、橘(たちばな)の模様のある1円黄銅貨が発行された。なお、1946年5月に連合国最高司令官総司令部(GHQ)から郵便切手ならびに貨幣に軍国主義的なものや超国家主義的なものを標榜(ひょうぼう)する図案を使用することを禁止する旨の覚書が出され、これらの新しい貨幣の図案を決定するに際してはGHQの規制を受けた。
1949年には1ドル=360円の単一為替レートが設定され、翌1950年からの民間貿易の全面再開への体制が整えられた。1949年には稲穂の模様の穴あきの5円黄銅貨が発行された。翌1950年にはアメリカのドル紙幣に似た横長の1000円券がつくられ、これには聖徳太子の肖像が用いられた。翌1951年には岩倉具視(ともみ)の500円券、高橋是清(これきよ)の50円券、宇治平等院の鳳凰(ほうおう)堂の10円青銅貨が発行された。
1953年7月には「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」が制定され、1円未満の小額通貨の廃止・整理が行われることになった。戦後のインフレによって銭や厘は通貨としても取引の額としてもすでに無意味になっていたのである。同年には新たに板垣退助(たいすけ)像の100円券が発行された。1955年には戦後初の図案公募による若木の1円アルミニウム貨、横から見た菊花の50円ニッケル貨が発行された。
インフレの進行とともに高額紙幣の発行が問題とされていたが、1957年には5000円券が、翌1958年には1万円券が発行され、ともに聖徳太子の肖像が取り入れられた。また、1957年には20年ぶりに銀貨が鋳造されることとなり、鳳凰の模様の100円銀貨がつくられた。しかし、この銀貨は先につくられた50円ニッケル貨と形や色が似ていて紛らわしかったため、図案を公募してつくりかえることとなり、1959年に稲穂の100円銀貨、大輪の菊花の穴あき50円ニッケル貨がつくられた。さらに1963年には伊藤博文(ひろぶみ)の1000円券、1967年には桜花の100円白銅貨、菊花三輪を配した穴あき50円白銅貨がつくられた。
その後の日本の高度成長に伴い、円安傾向の交換レートは是正されることになり、1971年12月に1ドル=308円の新為替レートが実施されたが、さらに1973年2月からは変動為替相場制へと移行することになった。
1982年4月には、15年ぶりに新しい貨幣として桐(きり)の模様の500円白銅貨がつくられた。
1984年11月には、紙幣のデザインを一新することとなり、形を従来のものより一回り小さくするとともに、1万円券には福沢諭吉(ふくざわゆきち)、5000円券には新渡戸稲造(にとべいなぞう)、1000円券には夏目漱石(そうせき)の肖像を採用したものが発行された。さらに、2000年(平成12)7月には九州・沖縄サミット(先進国首脳会議)と西暦2000年を記念して、新紙幣2000円券が発行された。表面に沖縄の首里城の守礼門(しゅれいもん)、裏面には国宝『源氏物語絵巻』の一部と紫式部(むらさきしきぶ)の肖像を採用した。2004年には偽造防止をおもな目的とした紙幣が発行された。うち5000円券は樋口一葉(いちよう)、1000円券は野口英世(ひでよ)に肖像を変更した。さらに2024年(令和6)には3Dホログラムなど新しい偽造防止技術を施した紙幣が発行され、1万円券には渋沢栄一(しぶさわえいいち)、5000円券には津田梅子(つだうめこ)、1000円券には北里柴三郎(きたさとしばさぶろう)の肖像が採用された。
なお、第二次世界大戦後にはこのほかに記念貨幣として、1964年に東京オリンピック記念貨幣(1000円銀貨、100円銀貨)、1970年に日本万国博覧会記念貨幣(100円白銅貨)、1972年に札幌オリンピック記念貨幣(100円白銅貨)、1975年に沖縄国際海洋博覧会記念貨幣(100円白銅貨)、1976年に天皇陛下御在位50年記念貨幣(100円白銅貨)、1985年に国際科学技術博覧会記念貨幣(500円白銅貨)、内閣制度創始100周年記念貨幣(500円白銅貨)、1986年に天皇陛下御在位60年記念貨幣(10万円金貨、1万円銀貨、500円白銅貨)が発行された。
その後、1988年に新貨幣法の「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」が施行され、記念貨幣を政令で随時発行する体制がつくられた。以後、おもな記念貨幣として、1990年に国際花と緑の博覧会記念貨幣(5000円銀貨)、天皇陛下御即位記念貨幣(10万円金貨、500円白銅貨)、裁判所制度100周年記念貨幣(5000円銀貨)、議会開設100周年記念貨幣(5000円銀貨)、1993年に皇太子殿下御成婚記念貨幣(5万円金貨、5000円銀貨、500円白銅貨)、1997~1998年に長野オリンピック記念貨幣(1万円金貨、5000円銀貨、500円白銅貨)などが相次いで発行された。
また、1998年4月には、戦時立法の日本銀行法(1942年2月公布)が改正・施行となり、日本銀行は開かれた独立性と政策決定の透明性を確保し、アカウンタビリティ(説明責任)を果たしていくことが重要となった。
[作道洋太郎]
その後も記念貨幣は多数発行されているが、そのうち1万円金貨には、天皇陛下御在位10年記念(1999)、2002FIFA(フィファ)ワールドカップTM(2002)、天皇陛下御在位20年(2009)、東日本大震災復興事業記念(2015)、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念(2018~2020)、天皇陛下御在位30年記念、天皇陛下御即位記念(2019)、近代通貨制度150周年記念(2021)、沖縄復帰50周年記念(2022)、2025年日本国際博覧会記念(2025)などがある。
[編集部 2025年5月20日]
『カール・マルクス著、長谷部文雄訳『資本論』第1巻第1篇第3章(1954・青木書店)』▽『J・G・ガーレイ、E・S・ショウ著、桜井欣一郎訳『貨幣と金融』(1967・至誠堂)』▽『D・パティンキン著、貞木展生訳『貨幣・利子および価格』(1971・勁草書房)』▽『久留間鮫造著『貨幣論』(1979・大月書店)』▽『J・M・ケインズ著、長沢惟恭訳『貨幣論』(1980・東洋経済新報社)』▽『J・ニーハンス著、石川経夫訳『貨幣の理論』(1982・東京大学出版会)』▽『前田拓生著『銀行システムの仕組みと理論――地域を支える中小企業金融の理解のために』(2008・大学教育出版)』▽『カール・マルクス著、武田隆夫他訳『経済学批判』(岩波文庫)』▽『三島四郎・作道洋太郎著『貨幣』(1963・創元社)』▽『造幣局泉友会編『原色日本のコイン』(1967・朝日新聞社)』▽『平木啓一著『コイン』(1968・文芸春秋)』▽『日本銀行調査局編『図録日本の貨幣』全11巻(1972~1976・東洋経済新報社)』▽『郡司勇夫編『日本貨幣図鑑』(1981・東洋経済新報社)』▽『小川浩著『日本古貨幣変遷史』(1983・日本古銭研究会)』▽『山口和雄著『日本の紙幣』(1984・保育社)』▽『E・ビクター・モーガン著、小竹豊治監訳『改訂増補 貨幣金融史』(1989・慶応通信)』▽『東野治之著『貨幣の日本史』(1997・朝日新聞社)』▽『山田喜志夫著『現代貨幣論――信用創造・ドル体制・為替相場』(1999・青木書店)』▽『山田勝芳著『貨幣の中国古代史』(2000・朝日新聞社)』▽『パルメーシュワリ・ラール・グプタ著、山崎元一・鬼生田顕英・古井龍介・吉田幹子訳『インド貨幣史――古代から現代まで』(2001・刀水書房)』▽『黒田明伸著『貨幣システムの世界史――「非対称性」をよむ』(2003・岩波書店)』▽『マーク・シェル著、小沢博訳『芸術と貨幣』(2004・みすず書房)』▽『ピエール・クロソウスキー著、ピエール・ズッカ写真、兼子正勝訳『生きた貨幣』新装版(2004・青土社)』▽『矢部倉吉著『古銭と紙幣――収集と鑑賞 無文銀銭から現行貨幣まで』改訂新版(2004・金園社)』▽『中村佐伝治著『日本のコイン』(保育社・カラーブックス)』▽『藤沢優著『世界のコイン』(保育社・カラーブックス)』▽『岩井克人著『貨幣論』(ちくま学芸文庫)』
百科事典マイペディア 「貨幣」の意味・わかりやすい解説
貨幣【かへい】
→関連項目古銭学|名目貨幣|名目主義
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
普及版 字通 「貨幣」の読み・字形・画数・意味
【貨幣】か(くわ)へい
 武十六年~初め王
武十六年~初め王 の亂後、
の亂後、
 に布帛金粟を雜用す。是の
に布帛金粟を雜用す。是の 、始めて五銖錢を行ふ。
、始めて五銖錢を行ふ。字通「貨」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「貨幣」の意味・わかりやすい解説
貨幣
かへい
money
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の貨幣の言及
【貨幣数量説】より
…貨幣量と物価の関係についての古典派の学説で,〈ある国の物価水準は,その国に流通している貨幣の量に比例して決まる〉というものである。すなわち,貨幣の量が2倍になれば物価もほぼ2倍になると考える。…
【金融】より
…売手はその指図書を銀行に持参すれば,所定の金額を取引相手の預金口座から自分の口座へ振り替えることができる。だから,現金と当座預金とが一般的交換手段といえるのであって,これらをまとめて貨幣ということが多い。そして,お金とは貨幣のことであり,金融とは貨幣が経済取引において一方から他方へととどこおりなく通ずることにほかならない,ということもできる。…
【経済学】より
…これに対してマクロ経済学は,一つの国民経済ないしは市場経済全体に関する集計的な経済変量がどのようなメカニズムによって決まり,その間にどのような関係が存在するかということを考察する。すなわち労働雇用量,国民総生産,国民所得,物価水準,利子率,貨幣供給量,財政支出,輸出入,為替レートなどがどのようにして決まってくるか,これらの諸量がどのように変動するかという問題を分析の対象とするわけである。マクロ経済学は雇用理論,所得理論,景気変動論ないしは景気循環論,恐慌論などに分類されることもある。…
【古銭学(古泉学)】より
…古代から近代にいたるまでの貨幣とメダルを取り扱う学問。メダルとは記念牌(はい)や徽章(きしよう)の類で,ある事件や人物を記念して作られたもの。…
【紙幣】より
…貨幣ないし現金通貨について,その素材が金属か紙かによって鋳貨(硬貨)と紙幣に分類する見方がある。この分類によると,紙幣は広義に解されて,政府の発行する政府紙幣(狭義の紙幣)と銀行券(現在は中央銀行の発行する中央銀行券)が含まれる。…
【造幣局】より
…貨幣の製造をおもな業務とする大蔵省の付属機関。その歴史は古く,1869年(明治2)太政官に造幣局が設けられたが,同年,造幣寮と改称,77年にふたたび造幣局となった。…
【通貨】より
…通貨とは狭い意味の貨幣を意味するが,場合によっては貨幣とまったく同義に使用されることもあり,明確な定義は存在しない。第1次大戦前の金本位制度のもとでは,商品貨幣としての金が本来の貨幣であり,銀行券は金との交換性を保持している場合にのみ本来の貨幣と同じ機能をはたすものと考えられていた。…
【フェティシズム】より
…このように商品がこれを生産した〈人間の意志を超えて動き出し,人間を拘束する〉存在となる事態を,マルクスは宗教の神になぞらえて商品世界の〈物神崇拝〉と呼んだ。このフェティシズム成立の最大の原因と考えられるものが貨幣である。何となれば,関係態である商品体系の中に一つの中心として貨幣が登場すると,その中心化によってそれぞれの商品があたかも個としての実体として存在するかのごとき錯視が生まれるからである。…
【メダル】より
…材料は銅,鉛および金,銀が使用される。賞牌(しようはい),記念章や勲章および古代ギリシア・ローマの貨幣もこれに含まれる。 古代ギリシアの貨幣は芸術的にも価値高い工芸品であった。…
※「貨幣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...