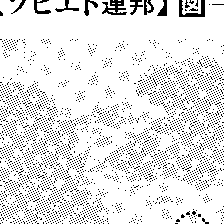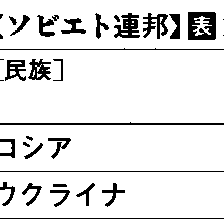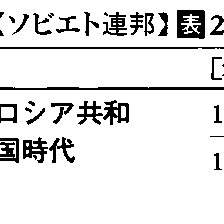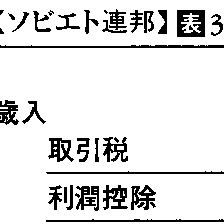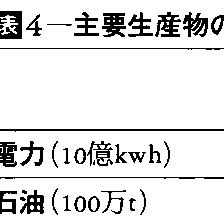精選版 日本国語大辞典 「ソビエト連邦」の意味・読み・例文・類語
ソビエト‐れんぽう‥レンパウ【ソビエト連邦】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「ソビエト連邦」の意味・わかりやすい解説
ソビエト連邦
そびえとれんぽう
Советский Союз/Sovetskiy Soyuz
総論
1917年の革命によってつくられ、正式には1922年に成立して1991年まで存在した、アジアとヨーロッパにまたがる世界最大の多民族国家。その面積2240万2200平方キロメートルは地球の全陸地面積の6分の1弱を占め、アメリカ合衆国の約2.4倍、日本の約60倍に相当した。100以上の民族が住み、人口は2億9010万(1991)で、中国、インドに次いで世界第3位であった。世界最初の社会主義国で、正式名称はソビエト社会主義共和国連邦Союз Советских Социалистических Республик(СССР)/Soyuz Sovetskih Sotsialisticheskih Respublik(SSSR)、英語ではUnion of Soviet Socialist Republics(USSR)、略してSoviet Unionとよばれた。ここでは、旧ソビエト連邦について解説する。ソ連崩壊の過程については別項の「ソ連崩壊と東欧の歴史的変革」を、またソ連崩壊後のロシアについては「ロシア連邦」を参照のこと。また旧ソ連の各構成共和国については、それぞれの項目を参照のこと。
[高野 明・外川継男]
国旗・国章・国歌
国旗は、矩形(くけい)の赤い布地の旗竿(はたざお)寄りの一角に金の鎌(かま)と槌(つち)があり、その上に金糸で縁どりした五光星が描かれている。
国章は、太陽の光と麦の穂で囲まれた地球を背景に鎌と槌が描かれ、15の共和国のことばで「万国のプロレタリアートよ団結せよ!」との銘が入り、上に五光星が描かれている。
国歌は、1918年から1943年までは『インターナショナル』であったが、1944年、新しいものにかわった。しかしこれにはスターリンを礼賛する歌詞が入っていたので、スターリン批判以後20年ほどは曲だけが演奏されるといった変則的な状態が続いたが、1977年からは手直しされて、また歌われるようになった。
[高野 明・外川継男]
国名の由来と国家体制
日本ではソビエト社会主義共和国連邦とよんでいたが、本来は「ソビエト体制の社会主義共和国の同盟」の意味である。ここには民族名や地名がないが、それはこの国の成り立ちからきている。「ソビエト」とはロシア語で評議会の意味であり、1905年の革命のときモスクワ北東のイワノボ・ボズネセンスク市で、初めて「ソビエト」という名の全市的な労働者の代表機関が生まれたのにさかのぼる。その後1917年の革命に際しては労働者、兵士、農民が自分たちのソビエトをつくり、これが革命において決定的な役割を果たした。レーニンはソビエトの重要性をいち早く認め、「すべての権力をソビエトへ!」のスローガンを掲げて臨時政府に対抗した。
ボリシェビキが政権を獲得した直後の1918年1月の第3回ソビエト大会において、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国が誕生した。その後1922年12月30日に、このロシア連邦共和国にウクライナ、白(はく)ロシア(ベラルーシ)、ザカフカス・ソビエト連邦社会主義共和国の3か国が加わって、ソビエト社会主義共和国連邦が成立した。
ソ連はロシア連邦共和国をはじめとして15の社会主義共和国からなる多民族の同盟国家であった。15共和国のうちウクライナと白ロシアはソ連崩壊後も国連に議席をもっているが、これは1945年のヤルタ会談で認められたものである。ソ連の憲法は、これら15の連邦構成共和国にソ連邦から自由に離脱する権利を認めていたが(第72条)、これは有名無実であった。
これら連邦構成共和国はいずれも人口100万以上の国であったが、それ以下の人口の民族・種族は自治共和国、自治州、自治区をつくり、共和国の下部単位をなしていた(タタール自治共和国のように人口100万以上の例外もあった)。自治共和国も連邦構成共和国と同様、それぞれ独自の憲法、最高会議、閣僚会議をもっていたが、共和国からの分離権はなかった。各共和国の地方行政単位は、地方(クライ)、州、自治州、自治区、地区、市、市内区、町、村で、市には共和国に直属するものと、州や地区に属するものとがあった。
ソ連の国権の最高機関は、連邦ソビエトと民族ソビエトの二院からなる最高ソビエト(会議)であった。最高会議は両院の合同会議において幹部会を選出し、その議長がソ連の国家元首とみなされた。1989年には新たに連邦人民代議員大会が設置され、また1990年3月には大統領制が導入され、大統領が国家元首となった。
最高会議はまた両院の合同会議においてソ連閣僚会議を編成した。その議長がソ連首相であった。また各地方行政単位ごとに、それぞれ人民代議員ソビエトがあり、その執行・処理機関として、議員のなかから執行委員会が選ばれた。その委員長は日本の知事や市区町村長と同様の職務と権限を有していた。このようにソ連は、連邦レベルから町村に至るまで各種のソビエトを通じて統治されることになっていて、連邦や構成共和国の国名にソビエトという語が入っているのも、ここからきていた。
[高野 明・外川継男]
共産党の役割
しかし実際にはソ連の国権の最高機関はソ連共産党であった。共産党の役割について憲法(1977)の第6条は、「ソ連共産党はソビエト社会を指導し、方向づける力であり、その政治機構、国家機関および社会団体の中核である」とその指導的役割を明記していた。理論的には共産党の最高の意志決定機関は党大会であったが、しかしこれは5年に1回、それも10日間ほどしか開かれなかったので、党大会で選ばれる中央委員会が、大会と大会の間の全活動を指導し、中央委員会の政治局、書記局および書記長を選出した。したがってこの中央委員会がソ連共産党の最高機関であったといえる。そのためソ連では共産党の書記長のほうが、最高幹部会議長や閣僚会議議長より重視された。しかし1989年ゴルバチョフが党の書記長と最高会議議長(元首)を兼任、さらに1990年大統領制の導入によって、共産党の指導的役割は低減した。このあと1991年のクーデターのとき、共産党の中央委員会はこのクーデターを傍観したところから、ゴルバチョフは書記長を辞任し、連邦最高会議は共産党の活動停止を決めた。
[高野 明・外川継男]
世界の中のソ連
ソ連は世界で最初の社会主義国である。しかし、レーニンの率いるボリシェビキが政権を掌握したあと、白衛軍や外国の干渉軍を破って政権の基礎を固めるためには数か年を要した。アメリカがソ連を承認したのは1933年のことであり、翌1934年ソ連はようやく国際連盟に加入が認められた。ソ連は1928年から五か年計画を実施して、社会主義の建設に乗り出したが、第三次五か年計画はナチス・ドイツとの戦争によって中断されてしまった。また1930年代から1950年代なかばまでスターリン主義が支配し、大規模な粛清と個人崇拝が行われた。
第二次世界大戦でソ連は参戦国中最大の犠牲者を出したが、戦後は東欧社会主義諸国の指導者として、セフ(経済相互援助会議=コメコン)やワルシャワ条約機構を組織して、アメリカに対抗する一大勢力となった。しかし早くも1948年にはユーゴスラビアが、1960年代初めには中国がソ連圏から離脱し、社会主義陣営にも分裂がみられるようになった。また1956年の第20回党大会におけるスターリン批判は、自由化を求める東欧諸国に大きな衝撃を与え、ハンガリーでは暴動が起こって、ソ連は武力でこれを鎮圧した。ソ連による軍事介入は、1968年のチェコ事件のときにも、1979年のアフガニスタンの政変のときにも、繰り返し行われた。
一方、ソ連が1957年に世界最初の人工衛星を打ち上げ、1961年に史上初の宇宙飛行を行ったことは、この国の科学技術の進歩を世界に示すところとなった。ソ連は通常兵器の分野でも核兵器の分野でも、アメリカに対抗しうるような軍事力をもつに至ったが、国民の生活レベルの向上は遅々としていた。
ソ連は1950年代のなかばから第三世界の開発途上国に経済援助と軍事援助を行い、また東欧諸国以外のモンゴル、ベトナム、北朝鮮、キューバ、アフガニスタン、エチオピアなどの社会主義諸国にも援助を行った。しかしソ連経済の停滞とともに、このような軍事支出や援助の増加が大きな負担になった。1985年3月、新たに共産党の書記長に選出されたゴルバチョフは、人事の刷新や経済の活性化を図るとともに、それまでのアメリカ偏重の外交から、西欧や日本にも相応の配慮を示した外交へと政策のニュアンスを変え、また中国との関係改善にも積極的な態度を示すようになった。ゴルバチョフはペレストロイカと新指向外交を掲げて改革に乗り出し、ベルリンの壁の崩壊と冷戦の終結のきっかけをつくった。しかし、経済改革は遅々として進まず、新たに民族問題が噴出して、1991年8月には改革に反対する党と政府の幹部がクーデターを試みたが失敗した。この結果ゴルバチョフは党書記長を辞任し、共産党は事実上解体した。このあと連邦構成共和国は次々に独立の宣言をし、ついに12月にはソ連邦は崩壊してバルト三国をのぞく12の共和国で独立国家協同体(CIS)がつくられた。
[高野 明・外川継男]
自然
地勢
ソ連の国土の南縁・南寄りに沿って高まる山地を西から列挙すれば、カルパティア、カフカス、コペト・ダク、テンシャン(天山)、パミール、ジュンガル、アルタイ、サヤン、ザバイカルの山地がそれであり、さらに東の東シベリアからはほぼ全域が山がちとなり、沿海地方、ベーリング海岸まで続く。カフカス、テンシャン、カムチャツカなどでは火山活動と地震の現象がみられる。南北に連なる孤立したウラル山脈は、一説に古生代のプレート衝突によって形成されたといわれるが、広い谷底をもつ老年期の山脈で、交通の障害は少ない。バイカル地方の山地は地塁が多く、階段状に落ち込んだものに湛水(たんすい)したものがバイカル湖であり、その軸方向は地塁の方向を示す。
ソ連の地勢の特色の一つは、世界有数の大規模な低地が広く横たわることである。西からあげると、東ヨーロッパ低地(ロシア平原)、西シベリア低地、その南のトゥラン低地、北極海岸に広がる北シベリア低地などである。ウラル山脈を無視すれば、世界最大の低地が出現する。東ヨーロッパ低地と西シベリア低地の北半部では、第四紀氷期にスカンジナビアとノバヤ・ゼムリャを中心とする二つの大陸氷河が南へ張り出し、第三氷期(ドニエプル氷期)にはキエフ(現、キーウ)付近まで、第四氷期(バルダイ氷期)にはモスクワ北方バルダイ丘陵にまで大陸氷河が南下した。その南方にあって直接氷河に覆われなかった地域も、周氷河地形を形成し、寒冷・乾燥気候のもとで黄土(レス)の堆積(たいせき)をみた。氷河が北に去った現在も、中部~北部では広範なアウトウォッシュ・プレーン、氷堆石堤、ボルガ川にみられるような両岸の非対称性、南ロシアから南シベリアでの黄土から黒土への変成、原流谷の運河化など特徴ある平野地形の形成と利用が顕著に観察される。カザフスタン地方を覆うトゥラン低地はもっとも乾燥した内陸流域で、ほぼ水平に堆積した中生層がわずかに隆起したのち侵食された台地が広範囲に残され、東に行くと「メルコソポーチニク」とよばれるバッドランド(悪地)や、「ジュンガルの門」(中国に通ずる地溝性の低地)が開ける。西シベリア(海成層をのせる)、北シベリアの低地には石炭、天然ガス、石油、一部に地下熱水鉱床の賦存(ふぞん)が知られるようになった。
[渡辺一夫]
河川
国土の南寄りの高峻(こうしゅん)な山地、北寄りの大きな低地の存在は、シベリアに世界的な長流(オビ、エニセイ、レナ、アムールなど)を生み出した。内陸流域には河川は少ないが、カスピ海に注ぐボルガ、アラル海に注ぐアムダリヤ、シルダリヤの長流がある。いずれも湿潤地域から流下する外来河川である。源流が標高5000メートルを超えるシベリアの大河は、長さ数百キロメートルの上流部を急流をつくって流下すると、標高100メートルほどの低地に出る(エニセイ川ではシベリア鉄道との交点が、ほぼこの地点にあたる)。そこから北へ4000キロメートルの長い道のりを、平均勾配(こうばい)がわずか1万分の1ほどで流下することになるので、曲流、分流、湿地化(水はけの悪いことの現れ)の現象が著しい。オビ川中流部のバシューガン湿原は、春の融雪時に一時的に日本ほどの面積が浸水する。河川の流量についていえば、春に年間総流量のなかばが流れ、残る9か月ほどは低水期ないし渇水期を迎える。東シベリアでは夏のモンスーンの影響で8~9月に第二の高水期がみられる。
河川は春の出水によって、中州や澪筋(みおすじ)の位置、形状、水深が変わるから、航行のためには、毎年出水後に測深、パイロット船の試験航行、標識の建て替え、河床の浚渫(しゅんせつ)などが必要であり、北極海に注ぐ大河下流では、夏の2、3か月しか航行できない。このような河川の性質を改良するために、河流制御、多目的ダム構築、運河掘削、流域変更などの計画が実行された。ドニエプル(ドニプロ)、ボルガはほぼ全流路にわたり低落差式ダムが建設され、河の縦断面は「カスケード」(瀑布(ばくふ))とよばれるような階段状となった。エニセイ川支流のアンガラ川は、バイカル湖を含めて「カスケード」化が進んでいる。航行改善を主要目的としたダムはボルガ水系のリビンスク、ドン川水系のツィムリャンスクなどに建設された。
[渡辺一夫]
気候
ソ連はユーラシア大陸の中央部から東部を占め、しかも全体として北に偏して位置する。ユーラシア大陸は地球最大の大陸塊であり、しかもソ連の国土は海洋の影響が大きい大陸西岸部を欠くこと、大陸中部以東で乾燥した内陸部は中緯度に出現することによって、ソ連の広大な国土の大半は、もっとも強い大陸性気候をもつことになる。これはソ連の気候の最大の特色である。気団の動きを主に述べれば、次のようになる。冬には、シベリア中部から東部にかけて現れる優勢な高気圧(シベリア気団、シベリア高気圧)は、バイカル湖付近に中心を置き、気圧は1040ヘクトパスカルに達し、きわめて優勢で安定している。中心域は晴天、無風、激しい放射冷却がおこり、ますます寒冷の度を加える。この高気圧の中心部から、高圧部が東に張り出すか、高圧気団が東に移動すれば、乾燥した強風(日本海を渡る間に水蒸気を含むようになる)が中国や日本の冬の天気を厳しくする。また、高圧部が南西から西に張り出すか、移動した場合、ソ連のヨーロッパ部、東ヨーロッパ、中部ヨーロッパが厳しい寒波にみまわれ、地中海地方にもその影響が及ぶ。大西洋上を低気圧が東進すると、前面に温暖前線が発生して南から湿った風が吹き込み、ソ連のヨーロッパ部に暖気と降水をもたらす。この現象は長い冬の間しばしばおこるので、大西洋の影響も加わって同緯度では西部のほうがはるかに温暖多雨となる。また、この現象が急激に発生すると、厳寒期のさなかに雪が融(と)け河水があふれる現象がおこる(「オテペリ」という)。ソ連西部の相対的高温は、次の例でもわかる。レニングラード(サンクト・ペテルブルグ、北緯60度)の1月平均気温-8℃に対し、内陸でははるか南方のアストラハン(北緯約46度20分)で同じ気温となり、さらに大陸東岸のウラジオストクでは北緯43度で-13℃である。1月平均気温の等温線を観察すると、ソ連のほとんど全域で0℃以下、東シベリアに寒極があり、北西部の等温線は緯度にほぼ直交する。ザカフカスの黒海沿岸、クリミア半島の南端そのほか小面積が0℃以上である。
夏には等温線は緯線にほぼ平行に並ぶ。シベリア高気圧(気団)は春に消失し、大陸中心部は逆に低圧部になる。周辺部(とりわけ大西洋岸)から湿潤な大気を含む気団が奥深く侵入するが、やがて含んでいる水蒸気を失い、高温で乾燥した大気となる。太平洋岸からは湿った夏のモンスーンが吹き込み、沿海地方、シベリア東部東寄りの地方に、湿潤・冷涼で晴天日数の少ない夏をもたらす。南部は中緯度高圧帯にあたるため、高温・乾燥の砂漠かステップ(短草草原)が広大な面積を占めることになる。
[渡辺一夫]
自然帯
ソ連の国土をいくつかの自然帯として簡略に概念化することは容易である。気候・土壌・植生・動物などの分布を関連づけて自然帯とよぶ概念をつくったのは、19世紀に活躍したロシアの自然地理学者たちであった。
自然帯は、ほぼ緯線に平行な帯状の数帯からなる。たとえば標式的なツンドラ(永久凍土帯)と標式的なタイガ(針葉樹林帯)の2帯にするか、その間の漸移帯を独立させて3帯にするかで、帯の数も変わってくる。次に、概念化された8帯からなるものに山地などの要素を加味したものを掲げる。北から南へ、の順である。気温などの数値は「目安」として示す。
(1)永久氷雪地帯
(2)ツンドラ 北極海岸でコケと地衣類のツンドラ。南部ではコケ、シダ、矮性(わいせい)のヤナギなどが混じるようになる。7月平均気温10℃、年降水量300ミリメートル。
(3)ツンドラ・タイガ漸移帯
(4)タイガ 北方の針葉樹林のタイガと、南方の針葉広葉混合樹林からなるものとに分けられる。7月平均気温18℃、1月平均-3℃~-40℃。年降水量700~800ミリメートル。ソ連のヨーロッパ部では、南にカシワ、ナラなど広葉樹林のタイガがみられる。
(5)タイガ・ステップ漸移帯 黒土、暗色栗色(くりいろ)土などの土壌帯は、ほぼこの位置にあたる。7月平均気温23℃。年降水量400ミリメートル。
(6)ステップ
(7)半砂漠 ステップと砂漠の間にある広大な漸移地帯。塩分に耐えるキク科(ヨモギ類)、イネ科などの植生が粗く地を覆う。年降水量300ミリメートル以下。
(8)砂漠
(9)亜熱帯 黒海北東岸、カスピ海西岸・東岸の平野部に、面積は狭いが「亜熱帯」と称する地域がある。前者は湿潤亜熱帯、後者は乾燥した亜熱帯である。北に偏した国土をもつソ連にとって重要な地域である。
(10)山地 標高が高くなるにしたがって現れるステップ、タイガ、いわゆるお花畑、氷河なども、自然帯の構成要素をなしているが、一括して「山地」とする。
[渡辺一夫]
地誌
ソ連には、20の経済地域があったが、ここでは、そのうちのあるものを統合して得た13の地域区分によって解説する。括弧(かっこ)内は、もととなった経済地域の名称(略記したものもある)である。したがって、西シベリア、東シベリアなどの領域は、日本での常識的領域とはかなり異なり、面積も広くない。
(1)モスクワ周辺(中央地域) モスクワ首都圏を含み、その影響の強い地域である。首都の都心から、管理中枢機能の一部、企画設計、試作実験施設などの進出が目だつ。その外周は、各種機械、エネルギー、建設、食品などの工場が立地し、レクリエーション地帯、別荘地帯と、園芸・家禽(かきん)・乳業地帯が展開する。また、モスクワからボルガ川、バルト海、カスピ海、黒海などへ通ずる河川交通システムの一環となる人造湖、運河、河港などのある都市も、北~東部を取り巻く。かつてこの地方は、増大する工業にエネルギー供給が追い付かず、深刻な危機を体験した。泥炭、褐炭が動員されたが、第二次世界大戦後はウラル、ボルガ地方からの供給(パイプライン、送電線)を受け、危機的状況からは脱した。東部にはボルガ‐オカ水系に沿うスズダリ、ウラジーミル、ヤロスラブリなどの古都があって、古代ルーシの民族と文化の形成の中心であった。古都巡礼のルートは「黄金の輪」の名で人気を集める。モスクワ南方にはトゥーラ、オリョールなど、西部にはスモレンスクなど、街道沿いの城砦(じょうさい)起源の都市があり、武具製作から発展した金属・機械工業をもつ。
(2)レニングラード周辺(北西部地域) レニングラード(現サンクト・ペテルブルグ)郊外には、ピョートル1世にちなむ史跡(ペトロドボレツ、プーシキンなど)、十月革命と第二次世界大戦戦跡が多い。三角州上に建設されたレニングラードは孤立した巨大な重工業都市で、資源を欠き、大戦中の包囲下で市民は困難な生活を強いられた。戦後はペチョラ、ボルガ、ウラル、ウクライナからパイプラインや送電線でエネルギー供給を受けた。ネバ川水系の輸送システムの入口にあたり、南東方には古都ノブゴロドがある。この地域の農林業は、近郊農業、乳酪、小麦・ライムギなどの穀作、北方の林業などである。
(3)コラ半島、白海沿岸、北部ウラル(北部地域) コラ半島(鉄‐ニッケル、燐(りん)灰石)、ペチョラ炭田、コミ‐ウフタ油田など、北極圏の南北に沿って地下資源の豊かな地域である。労働力の北への移動と、原燃料の南進が実行されている。たとえば鉄鉱石は水路と鉄道でリビンスク湖北岸のチェレポベツに運ばれて鋳鉄(ちゅうてつ)や鋼材にされ、さらに消費地レニングラードへ運ばれる。農林業は穀作よりも林業、トナカイと牛の飼育などが盛ん。ムルマンスク、アルハンゲリスクは、貿易港、漁業基地、海軍根拠地などの機能をもっている。
(4)ボルガ川流域(ボルガ‐ビヤトカ地域と沿ボルガ地域) ボルガ川の中・下流部は、イワン4世のカザン攻略(1552)以降ロシアに併合された。タタール人の要塞(ようさい)であったカザン、交易の港であったサマラ(クイビシェフ)、ツァリーツィン(のちスターリングラード、現ボルゴグラード)などは1930年代から重工業都市に変貌(へんぼう)した。後者は第二次世界大戦の凄惨(せいさん)な戦場(スターリングラードの戦い)となった。戦車工場があり、戦略要衝であったことがおもな理由であった。ボルガ中流部には1960年代に大きなダムと発電所が次々に構築されたこと、ボルガ・ウラル油田の近接などを理由に、機械工業のほか精油、石油化学などの新興部門が立地し展開した。サラトフ(精油、石油化学)、トリアッチ(小型乗用車)、ブレジネフ(現ナーベレジヌイエ・チェルヌイ。貨物自動車、カマ水力発電所)などのほか、ダム労働者住宅建設から開始されたジグリョーフスクなどがその例である。第一次産業部門は北・中部の穀作のほか、南部では畜産の比重が高くなる。畜産は、かつての遊牧が変化した放牧から集約的な舎飼いまで多様である。ボルガの貯水池から引いた灌漑(かんがい)用水を利用した牧草・飼料作も、乾燥した南部で行われるようになった。しかし都市用水、農業用水の需要急増に伴い、本流からの取水量も多く、ボルガ川下流からカスピ海に流入する水量の減少をもたらしたうえ、環境問題が早くから発生していた。
(5)ウラル(ウラル地域) 経済地域としてはウラル山脈と、その東西に展開する山麓(さんろく)地帯を含めたものである。開発は1928年以降、とくに第二次世界大戦当時「ソ連の兵器廠(しょう)」となったことに始まる。この地方は地下資源に富み、先発のウクライナ(ドンバス、ドニプロ)と並ぶ冶金(やきん)工業地帯に成長した。北から南の順に述べれば、セロフ(鋼)、ニジニー・タギル(鋼・特殊鋼)、スベルドロフスク(鋼、銅・ニッケル・アルミニウム。アルミはクラスノトゥリンスク)、チェリャビンスク(鋼・鉄道車両などの機械工業)、マグニトゴルスク(鋼)、オルスク(銅、クロム、精油)などに分かれ、大規模な工業地帯を形成する。ウラル西麓はボルガ・ウラル油田東縁にあたり、精油、石油化学が立地し、そのほかボトキンスク(上カマ水力発電所)、オレンブルグ(天然ガス田)などがある。
(6)西シベリア(西シベリア地域) 1890年代、クズネツク(現、ノボクズネツク)などで鉄道用炭の採掘が始まり、企業はカルテルを結んで巨利をあげた。しかし、本格的開発は第一次五か年計画で建設されたウラル・クズネツク・コンビナート以降で、ケメロボ(石炭化学)、ノボクズネツク(西シベリア製鉄所)を中心とするシベリア第一の重工業地帯となった。
はるか北方のオビ川の中流域は産油地帯で、分散して油田があり(スルグート、サモトロルなど)、さらに北には天然ガス田(ウレンゴイ、グープキンスコエ、ザポリャールヌイ、ベレゾボなど)が開発されている。石油と天然ガスはパイプラインで西シベリア南部やウラル以西に送られる。ノボシビルスク西郊には「シベリア科学都市」ともいわれるアカデムゴロドークがある。
西シベリア低地南西部~南部のステップは冬・春小麦地帯となりつつあり、中北部では粗放な畜産、トナカイ飼育と狩猟・漁労がある。
(7)東シベリア(東シベリア地域) 日本の常識と異なって東シベリアはザバイカル地方で終わり、その東のヤクート(現サハ)地方からは極東地域が始まる。西シベリア同様、最南部を東西に走るシベリア鉄道沿線に人口の大半が集中して主要な経済活動の地帯となる。タイシェト―バイカル湖北岸―レナ川上流を東進するバム(第二シベリア)鉄道の開通(1984)は、アンガラ・イリム鉄鉱床、ウドカン銅山など、沿線の地下資源開発のために役だつとされる。シベリア鉄道に沿うカンスク‐アチンスク炭田、アバカン炭田、アンガラ川の水力発電所群、アンガラ‐バイカル水上輸送系を媒介とする総合的な工業地帯の建設が見込まれているが、ソ連崩壊後は鉄道運賃が10倍にアップ、エネルギー資源も運べないなど、鉄道輸送の麻痺(まひ)状態により地域住民へのエネルギー供給にもこと欠く状態にある。イルクーツク、シェレホフ、アンガルスク、ブラーツクなどが将来の新工業地帯の中心となろう。北極海岸に近いノリリスク周辺は孤立した地下資源型工業地帯で、銅、ニッケル、石炭、天然ガスが採取される。それらの鉱工業従事者に供給する温室主体の生鮮野菜等を供給するソフホーズ(国営農場)が近郊に広がっていた。
クラスノヤルスク、イルクーツクなどの周辺は乳業、園芸などの地帯、シベリア鉄道沿線に穀作(春小麦)、畜産地帯が開ける。
(8)ソ連の極東部(極東部地域) ヤクート(現サハ)、マガダン、カムチャツカ、沿海地方、樺太(からふと)(サハリン)などを含む。広大だが一般に未開発で、アムール川中流、ウスリー川流域は早くから入植が始まっていた。ヤクートの砂金、ダイヤモンドのほか、各地に小規模な炭田・油田があるが、ヤクート地方の大規模な油田・炭田開発が期待される。いわゆる「寒極」を含む地域である。ハバロフスクを中心とするアムール‐ウスリー流域低地の都市(ウスリースクなど)、日本海岸のウラジオストク(太平洋艦隊根拠地および対日貿易港)、ナホトカ(対日貿易港)、北方沿岸のテチューヘ、ニコラエフスク・ナ・アムーレなども、貿易上重要性を増すであろう。
主要農業地帯はアムール‐ウスリー地域で、穀物(小麦)、酪農、畜産などの地帯であり、浅い山地は木材・林産加工が行われている。
(9)中央黒土帯(中央黒土地域) モスクワ南方の黒土帯の呼び名である。かつては黒土の豊かさに反し、多数の貧農が離村して社会問題となった。冬小麦、テンサイ、乳酪、食肉などの農業地帯で、モスクワおよびモスクワ以北の地域への食糧供給の任務をもっている。鉱産のうちで特筆されるのはクルスク地磁気異常帯(KMA(カーエムアー))の鉄鉱床が露天掘りで採取され、1960年代に選鉱所も建設されてソ連有数の鉄の生産地帯となったことである。中央黒土帯の主要都市はボロネジ(南方のノボボロネジスキーに原子力発電所がある)、クルスク(1986年西郊にクルスク原子力発電所が完成した)、リペツク、タンボフなどである。
(10)ウクライナとモルダビア(ドネツ‐沿ドニプロ、南部、南西部、モルダビアの各地域) ウクライナ東端はドンバス重工業地帯の西半にあたる。このほか、重工業地帯は、ハリコフ(現、ハルキウ)、ドニエプル川中流部沿いに展開する。ユーゾフカ(現、ドネツク)に1870年代にロシア最初の溶鉱炉ができてから、南部工業地帯とよばれるようになったが、本格的開発は1928年に開始された第一次五か年計画時代である。ハリコフのトラクター工場も、ソ連最初の大型水力発電所(ドニエプル・ダム)の建設も、同時代の成果であり、その後、キエフ、クレメンチュグ(現、クレメンチュク)など数座のダム建設によってドニエプル川は階段状の縦断面をもつようになり、重工業地帯の大きな中心となった。クリボイ・ログ(現、クリビー・リフ。鉄山)、シェベリンカ(ハリコフ南方の天然ガス田)、ニコポリ(マンガン鉱山)も重要な地下資源賦存地点である。キエフはルーシ建国とロシア正教によって知られる古都で、現在は機械、電気機械などの工業の中心となっている。西部へ行くと農業地帯の性格が強くなり、冬小麦、テンサイ、乳酪、食肉などの生産が多い。クリミア半島南岸は国際的保養地、避寒地として知られる。西端のモルダビアは丘陵を主とし、果樹(スモモ、リンゴ、ブドウ)栽培が盛んである。
(11)ベロルシア・バルト三国・カリーニングラード(ベロルシア地域と沿バルト地域) バルト三国は第二次世界大戦直前にソ連に併合された地域、カリーニングラード州はロシア連邦共和国の飛び地である。昔から軍馬やこはくで知られていたものの、後れた農業地帯であったが、沿岸部ではハンザ同盟の都市が活況を呈した。工業化に必要なエネルギー資源を欠き、コフトラヤルベ(エストニア)では油母頁岩(ゆぼけつがん)、泥炭などを動員してきたが、パイプラインなどによりウラル、ウクライナなどから石油などが運ばれるようになった。大都市(とくに各共和国首都)では電気機械、機械、輸送機器製造が進展し、たとえばミンスク(鉄道車両、トラクター)、リガ(電車、バス、船舶)、カリーニングラード(鉄道車両、船舶)などがある。
農業部門では、大都市周辺の近郊農業から草地での粗放な畜産まで種々あり、沿岸にはバルト海に出漁する漁業船団根拠地もある。カリーニングラードはかつてハンザ同盟の一中心で、18世紀からプロイセン領(旧称ケーニヒスベルク)として知られた。現在は国境の要地で、外港はバルチースク。
(12)中央アジアとカザフスタン(中央アジア地域とカザフスタン地域) この地域は自然的には内陸アジアの乾燥帯のなかばを占め、歴史的にはイスラム世界で、彼ら独自の文化圏を形づくる。しかし大都市や工業地帯にはスラブ系諸族も多い。従来の生業は、乾燥低地での遊牧と河川沿岸のオアシスでの自給農業で、著しい対照をなしていた。後者のなかからいわゆるシルク・ロード諸都市が発達した。現在、経済的に非能率な遊牧は廃され、畜産主体で穀作や飼料作をも行う農業にかわりつつある。ダム構築や灌漑用水確保が可能になったことが大きな原因で、ワタ、羊毛はこの地方の特産である。高峻(こうしゅん)な山地では移牧も行われる。
カザフスタン北部では小麦の大規模栽培が1960年代から始まり、パブロダール、ツェリノグラード、クスタナイなどがその中心。鉱産資源は、カラガンダ炭田(ソ連有数の生産量)、ジェズカズガンなどの銅山(バルハシ精銅コンビナート)、ブハラ北方のブハラ天然ガス田、グリエフ(現、アティラウ)とクラスノボーツク(現、トルクメンバシ)付近の石油、食塩、カリ塩などがある。アルタイ前山やテンシャン山系の水力開発が始められている。おもな都市は前記の諸都市のほか、タシケント、アシュハバード(現、アシガバート)、アルマ・アタ(現、アルマトイ)など南部山麓のオアシスから発展したもの、小都市でもヒバ、ブハラ、サマルカンドなど史跡に富むものがある。
(13)北カフカスとザカフカス(北カフカス地域とザカフカス地域) カフカス山脈を挟んだ北と南の地方は、自然的に大きな相違がある。北カフカスは広大なクバン、スタブロポーリエのステップが広がり、冷涼で乾燥し、冬小麦地帯としてソ連時代の末にはその屈指の穀倉となった。石油(マイコプ、クラスノダールの中規模油田)があり、ピャチゴルスクからエリブルース山麓に至る渓谷中にティルニアウス鉱山(タングステン)がある。ザカフカス地方は温暖で、黒海東岸には北国のソ連としては珍しい温暖多雨気候をもつ海岸平野がある。丘陵で柑橘(かんきつ)類、ブドウ、茶が栽培され、海岸にはイトスギ、シュロなどが植栽される。牧羊が盛んで、山地には移牧もある。カフカス山脈の東端アプシェロン半島はバクー油田を中心として中規模の油田が広がる。
北カフカス、ザカフカスとも保養・観光地が多く、前者ではとくにミネラーリヌイエ・ボードゥイ(略称ミンボードゥイ)、ソチ、後者ではバトゥーミ、エレバンなどに国内航空路線が集中する。保養地のほか、カフカス山中などに山岳スポーツ・登山基地が設けられるようになった。
[渡辺一夫]
歴史
時期区分
ソビエト連邦の歴史は、『ソ連共産党史』(増補第4版、1972)によれば、次の11の時期に分けられている。(1)社会主義革命の発展とソビエト権力の強化期(1917.10~1918)、(2)外国の軍事干渉と内戦期(1918~1920)、(3)国民経済の復興、ソ連邦の創設期(1921~1925)、(4)社会主義的工業化と農業の全面的集団化の準備期(1926~1929)、(5)全線にわたる社会主義の攻勢期(1929~1932)、(6)国民経済の社会主義的改造の完成、社会主義の勝利の時期(1933~1937)、(7)社会主義社会の強化、国防強化期(1937~1941)、(8)大祖国戦争期(1941~1945)、(9)復興と発展、社会主義世界体制の成立期(1945~1952)、(10)社会主義社会の発展期(1952~1958)、(11)社会主義社会の完成と共産主義への漸進的移行期(1959~1970)。また、『ソビエト歴史百科事典』第13巻(1971)の「ソビエト連邦」の項目における時期の区分は、ほぼこれと同じで、(1)1917~1918年、(2)1918~1920年、(3)1921~1925年、(4)1926~1940年、(5)1941~1945年、(6)1946年以降、となっている。1976~1980年に刊行された経済史『ソビエト経済』(全7巻)は、(1)1917~1920年、(2)1921~1925年、(3)1926~1932年、(4)1933~1937年、(5)1938~1945年、(6)1946~1960年、(7)1960~1970年代の各巻に分けられており、(6)は、「国民経済の復興と発達した社会主義経済の創設」、(7)は、「発達した社会主義の段階でのソ連経済」と題されている。ジュゼッペ・ボッファGiuseppe Boffa(1923―1998)の『ソ連邦史』(1979)では、革命、ネップの時代、工業化と集団化、個人権力、大祖国戦争、冷戦、フルシチョフ下の10年、の七つに区分されている。
ここでは、(1)革命期、(2)社会主義的改造と工業化期、(3)大祖国戦争期、(4)スターリン批判期、(5)「発達した社会主義」の時期、と五つの時期に区分して概観する(なお、革命前のロシアの歴史については「ロシア史」の項を参照されたい)。
[木村英亮]
革命期
十月革命
第一次世界大戦のさなか、1917年11月7日(ロシア暦10月25日)に首都ペトログラードでソビエト政権が成立し、世界最初の社会主義革命が成功した。この年の3月(ロシア暦2月)に起こった「二月革命」により、国会の勢力を中心として形成された臨時政府は、労働者・農民の平和と土地の要求にこたえることができず、兵士・労働者をつかんでいたソビエトでは、臨時政府を支持するメンシェビキとSR(エスエル)が多数を占めていた。これに対してレーニンを指導者とするボリシェビキは、「四月テーゼ」によって、ソビエトがただちに政権をとることを主張して勢力を急速に伸ばし、それを実現したのである。
ソビエト政府は、民族自決の原則に基づく、無併合・無賠償の即時講和を交戦諸国の政府と人民に訴えた「平和についての布告」、地主の土地の無償没収と分配を定めた「土地についての布告」を発し、ついで1918年1月には「勤労被搾取人民の権利の宣言」を採択して、新しい共和国の基本原則を明らかにした。以後1918年3月ごろまでに、広大な旧ロシア帝国領域の各地でソビエト政権が成立し、臨時政府の体制は一挙に崩壊した。1918年3月にはドイツと単独講和を結び、この前後に、銀行・運輸・大工業企業・外国貿易を国有化し、社会主義的改造のための態勢を整えようとした。
[木村英亮]
国内戦と諸共和国の誕生
しかし息をつく暇はなく、1918年なかばから、イギリス、日本をはじめとする帝国主義列強が軍隊を送り、反革命軍を助け、国内戦・干渉戦が始まった。ソビエト政権は、赤軍を創設してこれにあたるとともに、自家消費・種子分を除く穀物を農民から強制的に出させる食糧徴発制を土台とする「戦時共産主義」政策をとり、すべての力を国内戦勝利のために動員した。富農の穀物徴発には貧農委員会があたり、農村の階級闘争は激しくなった。1919年3月の第8回党大会では、「貧農に依拠しながら中農層と強固な同盟を結ぶ」政策が明らかにされ、中農を漸進的かつ計画的に社会主義建設に引き入れる方針がとられた。周辺諸民族地域では、国内戦のなかで、革命と反革命との激しい闘争が行われた。また、フィンランドでも1917年12月6日にセイム(議会)がロシアからの独立を宣言し、31日にソビエト政府がこれを承認した。一方、バルト海沿岸地方では、首都とほぼ同時にソビエト政権が樹立されたが、まもなくドイツ軍に占領され、反革命政権が成立した。しかし、これらを例外として、大部分の地域においてはソビエト政権が諸民族勤労者の支持を得て確立する。
ベロルシアでは、いったんミンスク市の権力を握ったソビエトを、1918年3月にドイツ軍が倒し、領域の大部分を占領したが、赤軍の反撃によって1919年1月1日にソビエト共和国が成立した。ウクライナでは、1917年12月25日にハリコフでソビエト政府が組織され、1918年1月にキエフの中央ラーダを廃した。まもなくペトリューラSimon Vassiliévitch Petlioura(1879―1926)政府が協商国の援助を得て勢力を伸ばしたが、1918年11月にソビエト政権が復活した。ウクライナは、旧ロシア帝国領域内で工業・農業とももっとも発展しており、労働者とともに農民やブルジョアジーの力も強く、闘争は激しく複雑な経過をたどった。ザカフカスでは、石油労働者の集中していたバクーで首都とほぼ同時にソビエト政権が成立したが、その他の地域では、アルメニアでは民族ブルジョアジーのダシナク(連邦党)、アゼルバイジャンではムサバチスト(ムスリム民主党)、ジョージア(グルジア)ではメンシェビキが圧倒的に優勢で、それぞれ政権を樹立し、トルコ、ドイツ、ついでイギリスの軍隊の支持を得る。バクー・ソビエトは1918年7月末に倒された。ソビエト政権は、イギリス軍の撤退後、1920年4月アゼルバイジャンで、同年11月アルメニアで、1921年2月にジョージアでようやく成立する。
中央アジアでは、1917年11月14日にタシケント・ソビエトが政権を樹立する。間接統治下にあったヒバ、ブハラ両ハン国は、1920年2月、8月の人民ソビエト革命を経て、1923年、1924年にそれぞれ社会主義共和国となった。
[木村英亮]
ソ連邦の結成とネップ
1922年12月、アゼルバイジャン、アルメニア、ジョージアが結合したザカフカス共和国と、ロシア、ウクライナおよびベロルシアの四つの共和国は、ソビエト社会主義共和国連邦(ソ連邦)を結成した。中央アジアでは、1924年に民族的に境界区分が行われてウズベク、トルクメンの二つの共和国が誕生し、1925年にソ連邦に加わる。この間、1921年3月、第10回党大会で、「戦時共産主義」から新経済政策(ネップ)への経済政策の転換が行われた。ネップの柱は食糧税政策で、これによって農民は余剰穀物の販売を許された。商業や小工業企業での個人経営が復活し、国内戦終了時の1920年に戦前水準の半分となっていた農業生産、7分の1に激減していた工業生産は復興に向かった。
[木村英亮]
社会主義的改造と工業化期
一国社会主義路線の確立
社会主義革命を指導してきたレーニンは、1922年健康を害し、1924年に没する。このころヨーロッパの革命的高揚期は終わり、資本主義は相対的安定を達成したが、ソ連も革命期を終わり、経済的にもいちおう復興した段階で、以後の建設の方針を決定しなければならない時期を迎えた。
この社会主義建設の方針をめぐって、1922年に党書記長となったスターリンと、トロツキー、ジノビエフとの間に、1926~1927年、激しい党内闘争が行われる。スターリンら主流派が、農民との同盟を保持しつつ一国で社会主義建設を進めるよう主張したのに対し、反対派は、政治的・経済的・軍事的にそれは不可能であるとして、世界革命論を唱えたのである。この闘争は主流派の勝利に終わり、スターリンの指導権が確立、その下で一国社会主義建設が始められる。
[木村英亮]
五か年計画による工業化
一国社会主義建設の路線に沿って、1928年10月から重工業優先の第一次五か年計画が開始された。これは、1920年作成の電化に基づく長期発展計画(ゴエルロ計画)、1921年設置のソ連計画委員会(ゴスプラン)によって作成され、1920年代後半に実施された単年度計画等の経験と、大部分の工業企業の国有化を基礎としている。
第一次五か年計画期には、1500の大工業企業が操業を始めた。突撃隊作業班を先頭とする大衆的社会主義競争によって建設のテンポは速まり、計画課題は1932年末までに完遂された。工業生産とくに機械製作・金属加工は大きく発展し、電力生産は2.7倍となり、ソ連は工業国へ変わった。失業は1930年になくなった。ウラル、シベリアにも大規模建設が行われ、連邦共和国・自治共和国でも連邦政府の援助によって工業化が始められ、非ロシア諸民族の労働者階級が増大した。続く1933~1937年の第二次五か年計画期には、工業生産は機械製作を中心にさらに発展し、粗鋼生産は二つの五か年計画によって4倍以上となった。1935年にはスタハノフ運動という作業能率増進運動が生まれ、全分野に拡大した。
[木村英亮]
農業の全面的集団化
農業生産はネップの下で、主として個人経営によって復興したが、1928年1月穀物調達の危機が起こった。その直接の原因は、価格が低いことに対する農民の不満と、見返りとなる工業製品不足による穀物の売り惜しみ、富農の投機と扇動と考えられるが、背景には、農民が中小農化したことによる自家消費率の増大があった。予約買付制なども試みられたが、根本的解決は、農民のコルホーズ(協同組合農場)への組織化の推進しかないことが明らかになった。1929年春、スターリンは、より漸進的な政策を主張するブハーリンら右翼反対派を攻撃し、年末の「大転換」によって全面的集団化運動を開始した。
1932年末には、播種(はしゅ)面積の4分の3以上が集団化され、農業の社会主義的改造は基本的に完了した。まだ少なかったトラクターや農業機械は国営のエム・テー・エス(機械・トラクター・ステーション)に集中され、契約によってコルホーズにサービスを行った。ソフホーズ(国営農場)も大規模に建設され、その農業機械によって周辺のコルホーズ農民を援助したほか、宣伝・教育活動を行い政治的な拠点となった。ロシア正教聖職者は個人農を支持したため、集団化と同時に激しい反宗教運動が行われた。
集団化運動は、とくに富農との激しい階級闘争を伴ったため生産は激減し、1913年に対する1933年の指数は、耕種101、畜産65となり、飢饉(ききん)と農村の荒廃をもたらし、犠牲は大きかった。1934年12月の党政治局員キーロフ暗殺を契機として、1936年から1938年にかけ三次にわたるモスクワ裁判と軍指導者の秘密裁判によって、ジノビエフ、カーメネフ、ブハーリン、トゥハチェフスキーら党や軍の指導者が次々に処刑された。この大粛清によって、たとえば1934年の第17回党大会で選ばれた党中央委員・同候補の7割が逮捕・銃殺された。この大粛清は、集団化による緊張とスターリン個人崇拝を背景として初めて理解できるであろう。
第一次、第二次の二つの五か年計画の期間に、都市と農村における資本主義的な要素は最終的になくなり、1936年12月、第8回ソビエト大会はソ連における社会主義の勝利を宣言、新しい憲法を採択した。
中央アジアでは、1920年代後半の土地・水利改革から集団化へと連続的な農業変革と並んで非識字者解消運動、女性解放運動が行われ、工業化の基礎が置かれたが、この憲法によってカザフ、キルギスは連邦共和国となった。またザカフカス共和国は解体され、アゼルバイジャン、アルメニア、ジョージアは独立の連邦共和国となった。
[木村英亮]
大祖国戦争期
戦争の接近
1930年代、ドイツ、日本などでファシズムが台頭し、ソ連は1934年に国際連盟に加入、1935年コミンテルン第7回大会で人民戦線戦術を決めるなど、反ファシズム勢力の結集を図った。しかし西欧支配層がドイツのオーストリア併合、チェコ侵略に対しても宥和(ゆうわ)的政策をとり続けたため、ソ連は1939年8月孤立を避けるためドイツと不可侵条約を結び、国内の態勢づくりを急いだ。1940年にはエストニア、ラトビア、リトアニア、モルダビアでソビエト政権が樹立されソ連邦は拡大した。1938年「張鼓峰(ちょうこほう)事件」、1939年「ノモンハン事件」と紛争が続いた日ソ間には、1941年4月、中立条約が結ばれた。
[木村英亮]
ドイツによる侵略と反攻
第二次世界大戦は1939年に始まっていたが、ドイツ軍は1941年6月突如ソ連に侵攻し、11月にはモスクワ、レニングラード近くまで占領した。しかし12月にはモスクワ近郊でソ連軍の反撃が始まり、ドイツ軍の電撃戦の失敗は明白となった。レニングラードはこの年9月に包囲され、防衛戦は900日も続いたがついに陥落しなかった。ドイツ側枢軸軍33万が包囲殲滅(せんめつ)された1942年9月から1943年2月にかけてのスターリングラードの戦いは、戦争の転機であった。ソ連軍の反攻が始まり、1943年7月クルスクの戦いで枢軸軍は50万以上を失った。アメリカ、イギリスはソ連と反ファシズム連合を形成し、武器を援助したが、1944年6月に連合軍がフランスに上陸するまで、枢軸軍の大部分は独ソ戦線に投入されていたのである。
ソ連軍は、ドイツ軍を追撃して東欧をファシズムの支配から解放、1945年4月ベルリンを包囲し、5月8日にドイツは降伏した。ソ連は、8月8日には日本に宣戦し、中国東北地区の日本軍を撃破した。この戦争(ソ連のいわゆる「大祖国戦争」)におけるソ連の勝利は、世界史に大きな意義をもっている。東欧諸国では人民民主主義政権が樹立され、帝国主義の植民地体制の崩壊が始まった。
[木村英亮]
復興
大祖国戦争によって、ソ連は国富の30%、2700万の人命という歴史に例のない損害を受けた。1942年に工業生産は1940年の66%、農業生産は38%にまで低下したが、開戦後1360以上の大企業、1000万以上の人が東部に疎開し、粗鋼などの重工業、戦車、航空機をはじめ兵器類の生産は急激に増大してドイツをしのぐに至った。戦後1946~1950年の第四次五か年計画によって引き続き復興が進み、1950年の工業生産は戦前水準を超えた。スターリンは、人民委員会議議長(首相)、国家防衛委員会議長、最高司令官などの権限を一身に集め、戦争を勝利に導いたが、その個人的権威は過度に高まった。戦後まもなく始まった「冷戦」という国際的緊張のなかで、個人崇拝はやがて最悪の様相を呈し始める。
[木村英亮]
スターリン批判期
「雪どけ」時代
1953年3月、1922年以来30年にわたって党書記長であったスターリンが急死した。後を継いで首相兼党第一書記となったマレンコフは、消費物資の生産に力を入れた。まもなく党第一書記となったフルシチョフは、カザフスタンの処女地開墾などによって農業生産の向上を図り、こうして、国民生活はしだいに豊かになってきた。ソ連はすでに原爆を保有していたが、1953年には水爆実験にも成功、1955年にはワルシャワ条約機構を成立させるなど軍事的な力をつけ、朝鮮、インドシナの戦争を休戦に導いた。このころアジア・アフリカ諸国の発言権も強まり、周・ネルーの平和五原則が声明されるなど平和共存の気運が盛り上がった。1956年2月、第20回党大会では、フルシチョフが秘密報告でスターリン個人崇拝を厳しく批判し、「雪どけ」を一挙に推し進めた。反対するマレンコフ、モロトフらは、まもなく失脚に追い込まれた。
[木村英亮]
社会主義世界体制の確立
1950年代、工業生産の伸びは目覚ましく、冶金(やきん)や機械製作などのほか、後半には石油化学など新しい分野も急速なテンポで発展した。中央アジアなど周辺の諸民族共和国も本格的な工業化の時期に入った。
東欧諸国では、ユーゴスラビア、ポーランドを例外として、1960年前後に農業経営がすべて生産協同組合か国営農場によって行われるようになり、社会主義的改造を完了した。ソ連はこのころ「発達した社会主義」の段階に入ったとされた。
1957年、人工衛星スプートニク1号打上げによって人気を高めたフルシチョフ党第一書記は、1958年ブルガーニンを解任して首相をも兼任、国連総会で完全全面軍縮を提案、アイゼンハワー、ケネディらアメリカ合衆国大統領と会談、1961年には新しい党綱領作成にイニシアティブをとるなど精力的に活動した。しかし、中国共産党との路線上の対立を国家的対立に至らしめたことや、「キューバ危機」など外交上の失敗、党組織の改革・工業管理組織の改変・農業政策などの内政上の失敗を原因として、1964年に失脚した。
[木村英亮]
「発達した社会主義」の時期
アメリカに接近する経済力
1964年10月、フルシチョフ失脚後、党第一書記(1966年に書記長と改称)はブレジネフ、首相はコスイギンによって引き継がれた。新政権は、工業管理・計画制度改善の試みを推し進め、最新技術導入、自動化、巨大なコンビナート・大発電所の建設を行った。エレクトロニクス・無線工学等の部門も発展、工業・農業を含めた地域生産総合体がつくられ始めた。穀物生産は1978年には2億3720万トンと1953年の3倍近くに増大、畜産においても、牛・羊・豚の頭数で世界一、二となった。農業の機械化・化学化・電化も格段に進み、欧米諸国に比べ低かった農業労働の生産性の向上、飼料の増産に力が注がれた。
[木村英亮]
新憲法の採択
ブレジネフは、1976年、元帥、国防会議議長、1977年には最高会議幹部会議長を兼任、1982年11月に没するまで18年間という長期にわたって党と政府を率いた。この間、1974年にソルジェニツィンを国外追放、1980年にはサハロフをゴーリキー市に流刑するなど、反体制知識人に対する締め付けを強めたが、国民生活は全体としてみれば、豊かになってきた。中央アジアやシベリアも発展し、諸民族間の実質的な平等に向けての経済的建設・文化的接近も進み、文字どおりのソ連邦となってきたと考えられた。1977年の新しい憲法は、この段階を文書として確定したものといえよう。
セフ(経済相互援助会議=コメコン)を通じての東欧社会主義諸国との経済的結合も強化され、1971年には「総合プログラム」を採択し、新段階を画した。1968年のチェコ介入に際しては「制限主権論」を唱え、政治的・軍事的団結を強調した。アメリカとは、1972年以降毎年穀物を輸入し、1972年ニクソン大統領とSALT(ソルト)(戦略兵器制限交渉)‐Ⅰ、1979年カーター大統領とSALT‐Ⅱに調印するなど共存路線を求めたが、1979年12月のソ連軍アフガニスタン介入以後、関係は悪化した。
[木村英亮]
ゴルバチョフ政権と第27回党大会
1982年のブレジネフ没後、党書記長は、アンドロポフ、チェルネンコとかわり、1985年、54歳のゴルバチョフが就任した。新政権は、経済改革の推進と徹底的な綱紀粛清・労働規律強化によって、鈍化した経済成長を高めようとし、とくに、数年来不作続きの農業生産を、1982年の「食糧計画」によって向上させようとした。1984年10月の第二シベリア鉄道開通をてことしてシベリア開発も着実に進めていた。
1986年2~3月の第27回党大会では、党の中核をなす政治局の12人中8人がアンドロポフ以降の新メンバーとなるなど、ブレジネフ期における人事の停滞を打破して、党と政府の指導部が大きく若返った。
この大会で採択された新しい党綱領では、「社会主義社会を全面的に完成し、その可能性と優越性を共産主義へのいっそうの前進のためにもっと十分に有効に利用する」ことがうたわれた。また同時に決定された、2000年を目ざす「経済社会発展の基本方向」では、科学技術進歩の加速、社会的生産の構造的再編、管理システム・経営方法の改善によって、国民所得・工業生産の2倍化を予定していた。
グロムイコにかわったシェワルナゼ外相の下で西欧に平和攻勢をかけるなど、国際政治面でも積極的にイニシアティブをとろうとし、中国との関係も改善された。
[木村英亮]
大統領制とソ連の崩壊
ゴルバチョフはペレストロイカ(改革)路線を進め、1990年には共産党一党制の廃止、大統領制などを断行し、社会主義の枠内での民主化を進めようとした。しかし民族主義の波は東欧からソ連にも及び、1991年12月ソ連は解体、独立国家共同体(CIS)が創設された。
[木村英亮]
政治・外交・防衛
政治制度
ソビエト連邦は社会主義国家であり、全権力は人民に属し、人民は人民代議員ソビエトを通じて国家権力を行使することになっていた。1977年10月7日に採択された憲法は、ソ連を「発達した社会主義社会」と規定し、国家の性格を「社会主義的全人民国家」としていた。ソ連はロシア連邦、ウクライナ、ベラルーシ、ウズベク、カザフ、ジョージア、アゼルバイジャン、リトアニア、モルダビア、ラトビア、キルギス、タジク、アルメニア、トルクメン、エストニアの15のソビエト社会主義共和国からなる「単一の連邦的多民族国家」であり、各共和国は連邦からの脱退権をもっていた。
ソ連の最高国家権力機関はソ連最高会議(国会)であり、連邦会議と民族会議の二院によって構成されていた。両院は同権で、同数の代議員からなり、両院の意見がどうしても一致しない場合には最終的には全人民投票によって決定された。最高会議は通常、1年に2回招集され、1回の会期は2、3日であった。閉会中は、両院合同会議で選出される最高会議幹部会が最高国家権力機関の機能を果たす。なお1990年3月の憲法改正で、大統領制が導入され、最高会議幹部会議長にかわり大統領が国家元首となった。大統領は、軍の統制権、首相・閣僚・最高裁判所長官などの任命権、非常事態宣言の発令、法案の拒否権などが与えられ、初代大統領にはゴルバチョフが選出された。
国家権力の最高執行機関は、ソ連最高会議両院合同会議で組織されるソ連閣僚会議(政府)であった。閣僚会議は、議長、第一副議長、副議長、大臣、国家委員会議長のほか、閣僚会議議長が推薦し、最高会議が承認したソ連の他の機関や組織の責任者からなり、共和国閣僚会議議長も職務上、ソ連閣僚会議の構成員であった。議長が首相にあたり、議長、第一副議長、副議長、および閣僚会議が決定するその他の政府構成員により幹部会が組織された。省と国家委員会には全連邦的なものと連邦・共和国的なものがあった。前者は、ソ連の全域にわたって直接に、またはその設置する機関を通じて、その管轄下にある行政部門を指導し、あるいは部門間の管理を行うもので、後者は、通常、共和国の同名の省または国家委員会を通じて、その管轄下にある行政部門を指導し、あるいは部門間の管理を行うものであった。
ソ連における唯一の政党は共産党であった。党は、憲法で、ソビエト社会の「指導的かつ先導的勢力」であり、「政治制度および国家・社会組織の中核」として認められていた。党の最高機関は、5年に1回以上開かれる大会であり、大会は内外政策の基本方針を決定し、中央委員会と中央監査委員会を選出した。中央委員会は、決議権をもつ中央委員と審議権のみをもつ中央委員候補からなり、6か月に1回以上総会を開き、大会間のすべての党活動を指導した。中央委員会は政治局と書記局および書記長を選出し、中央委員会付属党統制委員会を組織した。政治局は政治局員と同候補からなり、通常、週に1回、木曜日に会議を開き、中央委員会の総会間の党活動を指導し、書記局は当面の活動を指導した。党統制委員会は党規律の順守状況を点検し、党からの除名処分などに対する訴えを検討した。中央監査委員会は6か月に1回以上会議を開き、党予算の執行状況などを監査した。しかし1990年3月の憲法改正により、共産党の「指導的役割」が放棄され、建国以来の一党独裁制にかわり、複数政党制の導入が決定された。
1986年2~3月に開かれた第27回大会では中央委員会の政治路線と実践活動が承認され、綱領新版が採択され、規約が修正され、1986~1990年間および2000年までの期間のソ連経済社会発展の基本方向が確認された。また、中央委員307人、中央委員候補170人、中央監査委員83人、計560人の中央機関構成員が選出された。同年3月6日に行われた第1回中央委員会総会では、ゴルバチョフが書記長に選ばれたのをはじめ、政治局員12人、政治局員候補7人、書記11人(書記長を含む)が選出され、ソロメンツェフMikhail Sergeevich Solomentsev(1913―2008)が党統制委員会議長として承認された。中央監査委員会議長にはカピトノフIvan Vasilievich Kapitonov(1915―2002)が選出された。
共産党の直接の指導のもとに活動する青年組織として全連邦レーニン共産主義青年同盟(コムソモール)があった。コムソモール員は14歳から28歳まで、共産党員は18歳以上ということになっていて、23歳までの青年はコムソモールを経てしか入党できなかった。
ソ連における選挙は、ソ連最高会議から共和国最高会議、自治共和国最高会議、地方(クライ)、州、自治州、自治区、地区、市、市内区、町、村の人民代議員ソビエト(会議)に至るまで、秘密投票による普通・平等・直接選挙によって行われていた。選挙権と被選挙権は満18歳以上のソ連公民に与えられたが、ソ連最高会議代議員の被選挙権だけは満21歳以上であった。選挙区はいずれの選挙でも定員1人の小選挙区で、選挙ごとに決定された。立候補者は選挙運動の過程で1人に絞られる。つまり信任投票であった。ソ連、共和国、自治共和国の最高会議代議員の任期は5年、地方以下のソビエト代議員の任期は2年半であった。
1984年3月4日に実施された第11期ソ連最高会議選挙では、連邦会議750人、民族会議750人(1選挙区では候補者死亡により後日行われた)、計1500人の代議員が選出されたが、その内訳は、労働者35.2%、コルホーズ(協同組合農場)員16.1%、党員・党員候補71.5%、非党員28.5%(うち、コムソモール員15.0%)、男67.2%、女32.8%、30歳以下の代議員22.0%であった。ソ連最高会議の選挙では落選者はほとんどいないのが通例であったが、1959年10月にリコール手続法が施行されて以来、1979年3月の選挙までの20年間に11人の代議員がリコールされた。
ソ連には、ソ連最高裁判所、共和国最高裁判所、自治共和国最高裁判所、地方・州、自治州・自治区の裁判所、地区(市)の人民裁判所、軍隊内の軍法会議などがあった。ソ連最高裁判所が最高の裁判機関であり、各級裁判所の裁判活動を監督したが、法律の解釈権はソ連最高会議幹部会にあった。ソ連最高裁判所の長官、長官代理、裁判官、人民参審員は5年の任期でソ連最高会議で選出され、共和国最高裁判所長は職務上、ソ連最高裁判所の構成員となると決められていた。軍法会議の裁判官は5年の任期でソ連最高会議幹部会によって選出され、人民参審員は2年半の任期で軍人集会において選出された。
ソ連検事総長はソ連最高会議によって任命され、共和国、自治共和国、地方、州、自治州の検事を任命した。自治区、地区、市の検事は共和国検事によって任命され、ソ連検事総長の承認を必要とした。検事総長以下すべての検事の任期は5年であり、検事局の諸機関はソ連検事総長にのみ従属し、いかなる地方機関からも独立してその権限を行使した。
ソ連の政治制度は立法・行政・司法の三権分立ではなく、人民が決定し、実行し、評価するという政治制度を目ざしていた。違憲立法審査権がソ連最高裁判所ではなくソ連最高会議幹部会にあるのはその表れであった。地方行政ではよりいっそうこの理念の実現に努めていた。
[中西 治]
地方行政
ソ連の地方行政の単位は、共和国、自治共和国、地方(クライ)、州、自治州、自治区、地区、市、市内区、町、村であった。共和国はそれぞれが主権をもつ国家で、独自の憲法と最高会議および同幹部会、閣僚会議、最高裁判所を有し、外交権をもった。ウクライナとベラルーシは国際連合に代表を送っていた。自治共和国も独自の憲法と最高会議および同幹部会、閣僚会議、最高裁判所を有していたが、共和国からの分離権はなかった。ソ連には1985年1月1日当時自治共和国20、地方6、州123、自治州8、自治区10、地区3211、市2152、市内区641、町3968、村4万2176があった。
地方以下の行政単位の国家権力機関はそれぞれの人民代議員ソビエトであった。各ソビエトは代議員のなかから執行委員会を選出したが、その議長が日本の知事、市長、町村長に相当していた。1985年2月24日に実施された統一地方選挙では、15共和国最高会議で6728人、20自治共和国最高会議で3460人、地方以下の人民代議員ソビエトで230万4703人の代議員が選出された。この選挙では、地区、町、村のソビエトの90の選挙区において候補者が当該選挙区の全有権者の過半数の信任を得られず落選し、34の選挙区において候補者が選挙民から忌避されて選挙運動期間中に立候補を辞退した。また、1970年から1980年までの10年間に約4000人の代議員がリコールされた。
地方以下のソビエト代議員の内訳は、労働者44.5%、コルホーズ員24.8%、党員・党員候補42.8%、非党員57.2%(うち、コムソモール員22.4%)、男49.7%、女50.3%で、直接生産に従事する労働者と農民が過半数を占めていた。彼らはソビエト総会出席などで職場を離れるときも平均賃金は支給された。
地区(市)人民裁判所の人民裁判官は5年の任期で普通・平等・直接選挙により秘密投票で地区(市)の公民によって選挙され、人民参審員は2年半の任期で就業地または居住地の市民集会において公開投票によって選挙された。自治区から共和国に至る裁判所または最高裁判所の裁判官と人民参審員は5年の任期で当該ソビエトまたは当該最高会議によって選出された。
ソ連には、国家計画の遂行を統制し、国家規律の違反や官僚主義と闘い、国家機関の活動を改善するのを助ける人民統制という制度があった。この人民統制の初級組織は、すべての企業、施設、官庁で活動する任期2~3年の人民統制グループで、このグループに属する人民統制員は勤労者集団の総会で選出された。人民統制員は勤務の余暇に無報酬でこの仕事に従事した。人民統制グループは村、町にもつくられ、市区以上には人民統制委員会が置かれた。いずれも当該ソビエトによって組織され、任期は当該ソビエトと同じであった。人民統制の最高指導機関はソ連最高会議両院合同会議で組織されるソ連人民統制委員会であった。人民統制機関の活動は経済、社会、文化、国家管理などの面に限定され、裁判、捜査、調停などの活動には及ばなかった。
ソ連では各企業、機関、学校ごとに労働組合が組織されており、高等・中等専門教育機関と職業技術学校の学生・生徒も組合員であった。各労組は産業別、地域別に結集し、5年に1回開くソ連労組大会が全ソ連の最高機関であった。また大会間の指導機関として全連邦労組中央評議会が組織されていた。ソ連の労組は各レベルで組合員の賃金と労働条件の決定や社会保障の実施などで大きな影響力を行使していた。ほかに消費生活で重要な役割を果たすソ連消費組合中央連合(ツェントロソユーズ)のような組織もあった。
ソ連ではあらゆるレベルで党が政策の基本を決定し、国家機関がそれを具体化し、法制化し、実行していくという形をとっていた。しかし、実際には党政治局員がソ連最高会議幹部会議長やソ連閣僚会議議長を担当しており、党機関員と国家機関員は密接な人的関係にあった。党としては、党機関が政治指導機関に徹し、国家機関にとってかわることのないよう努力していたが、党機関と国家機関の機能の癒着の傾向がみられた。党の書記長や第一書記が当該レベルの国家機関の最高指導者よりも上位にあるごとく、ソ連は党主導型国家であった。
[中西 治]
外交
ソビエト政権は第一次世界大戦中の1917年11月7日に誕生した。それはロシアの民衆の厭戦(えんせん)と平和への願いを背景とするものであった。ソビエト政権は発足後ただちに「平和の布告」を発し、すべての交戦国の政府と国民に戦争を即時中止し、無併合・無償金の公正で民主的な講和を結ぶよう呼びかけた。しかし、英仏米日などの同盟国はこの呼びかけを無視し、ロシアを戦争に引きとどめておくために反ソビエト政権派を支持し、ロシアに軍隊を送った。ドイツ、オーストリア・ハンガリーなど交戦相手国と結んだブレスト・リトフスクの講和条約はロシアから広い領土と多額の金を奪うものであった。ソビエト政権は内外の敵と戦うために戦時共産主義体制をとった。
1920年代に入ってソビエト政権の勝利が確実となり、諸外国の承認が本格化した。1921年3月に英ソ通商協定が調印され、イギリスがソビエト政権を実質的に承認したのをはじめ、1924年にはイタリア、中国、フランス、1925年には日本がソ連を正式に承認した。しかし、アメリカのソ連承認は1933年11月のことであり、ソ連が国際連盟への加入を認められたのは1934年9月のことであった。しかも、そこにはすでに日本とドイツはいなかった。これら2国は1936年に防共協定を結び、1937年にはイタリアがこの協定に加わった。ソ連は日独伊三国によって東西両面から挟撃される形となった。
1939年5月にモンゴル人民共和国と「満州国」との国境地域ノモンハンで軍事衝突が起こり、ソ連・モンゴル軍と日本・満州軍が相戦うことになった。他方、ヨーロッパでは、ドイツが1938年にオーストリアを併合し、チェコスロバキアからズデーテン地方を割譲させていた。ドイツはさらに東方へ進出しようとしていた。ソ連はアジアとヨーロッパで同時に戦うという危険に直面した。ソ連は1939年8月にドイツと不可侵条約を結び、この危機を回避した。
1941年6月、ドイツがソ連を攻撃し、ソ連も第二次世界大戦に巻き込まれた。ソ連は米英と組んで日独と戦うことになった。1945年8月にソ連は日本に正式に宣戦布告した。日ソ戦争は短時日で終わり、第二次世界大戦は終結した。ソ連はヨーロッパとアジアで領土を拡大した。1975年夏にヘルシンキで開かれたヨーロッパ安全保障協力会議はヨーロッパでの戦後処理を確認した。ソ連はヨーロッパの大国としての地位を完全に確立した。
1970年代後半以降、中近東、アフリカ、アジアでのソ連の活動は活発化した。1979年12月のソ連のアフガニスタンへの軍事介入はソ連外交の質の転換を意味した。それまでのソ連外交は受け身であった。1917年から1919年末まではソビエト政権をもちこたえることで精いっぱいであった。1920年代から1930年代なかばまでは国際社会に認めさせることが主要な外交目標であった。やっと認めさせたときにも、日独伊のような強力な反共国家が存在した。その攻撃を跳ね返し、勝利したとき、ソ連はヨーロッパの半分でその地位を確立した。これを全ヨーロッパで認めさせるのにさらに30年の歳月を要した。ハンガリーとチェコスロバキアへの軍事介入は獲得した地位を確保し、認めさせるためのものであった。しかし、アフガニスタンへの軍事介入は新しい土地への進出であり、新たな安全保障圏を獲得するための積極的な行動であった。ソ連外交は受け身から攻勢に転じた。
ソ連のグローバル・パワーとしての活動の展開は、もう一つのグローバル・パワーであるアメリカとの関係を先鋭化させた。1980年代前半にアメリカの反ソ十字軍態勢とソ連の常時臨戦即応態勢が対峙(たいじ)した。米ソ核戦争の危険が増大した。こうしたなかで1985年11月にレーガン大統領とゴルバチョフ書記長の米ソ最高首脳はジュネーブに会し、米ソ不戦を確認したが、アメリカの戦略防衛構想(SDI)については意見が一致しなかった。1986年1月にソ連は20世紀中に核兵器を全廃するよう提案した。同年2月に開かれた第27回党大会でゴルバチョフ書記長は、核破局を防止し、文明が生き残るために全世界の諸国家と諸国民の協力を訴えた。ソ連は階級や国家の利益よりも人類と文明の生存を重視するようになった。
ソ連は人類史上最初の社会主義国家であり、武器と戦争のない世界を目ざして出発した。しかし、現実には資本主義諸国の包囲のなかで生き延びることが当面の最大の課題であり、そのためには権謀術数を弄(ろう)することもあった。それでも1922年には全般的軍縮を提案し、1932年と1959年には全面完全軍縮を提案、その後、核兵器の完全廃絶を具体的に提案した。ソ連外交を決定する要因としてイデオロギーと安全保障と経済的利益などがあり、時により、状況によって、いずれかが前面に出ることはあったが、その動向を正しく把握するためには、これらの諸要因を総合的に検討せねばならなかった。
[中西 治]
防衛
ソ連の武装勢力は、国防省に属する戦略ロケット軍、地上軍、空軍、防空軍、海軍の5軍種と、後方支援隊、民間防衛隊、国家保安委員会(KGB)に属する国境警備隊、内務省に属する国内隊からなっていた。ソ連領は16の軍管区に分けられ、海軍は北洋、バルト、黒海、太平洋の4艦隊とカスピ小艦隊、レニングラード海軍区を有した。在外部隊はドイツ駐留軍、北方集団軍(ポーランド駐留)、中央集団軍(チェコスロバキア駐留)、南方集団軍(ハンガリー駐留)の4軍で、モンゴルとアフガニスタンに駐留するソ連軍は隣接する軍管区に属するとみられていた。
ソ連軍は完全に党の指導下に置かれ、軍が独自に行動できないようになっていた。軍の最高統帥権は、ソ連最高会議幹部会が組織する国防会議および同じく最高会議幹部会が任命する最高司令部にあったが、国防会議議長も最高司令官も党書記長が兼任した。国防会議と最高司令部の構成は明らかにされていなかったが、党書記長のほかに前者には閣僚会議議長、国防大臣、参謀総長、国家保安委員会議長、国家計画委員会議長およびその他の必要な人、後者には国防大臣、政治総局長、国防第一次官、5軍種総司令官などが入っていたとみられていた。国防大臣以下各級指揮官は党員であったが、ほかに、党中央委員会軍事部の資格をもつソビエト陸海軍政治総局とその下部組織である政治局・政治部が軍隊内に置かれ、政治局長・政治部長が政治担当指揮官代理(ザムポリト)として政治指導を行っていた。国防省には参与会、軍種・軍管区には軍事委員会があり、政治総局長・政治局長はこれらの会の構成員であった。国防大臣以下指揮官は重要問題の決定にあたってはこれらの会の意見を徴さなければならなかった。
ソ連では1945年の第二次世界大戦の終結後、アメリカの核独占を打破する努力がなされ、1949年には最初の原子爆弾の製造に成功した。1953年には世界最初の水素爆弾を完成し、1957年にはアメリカに先駆けて人工衛星を打ち上げ、大陸間弾道弾(ICBM)の発射実験が行われた。核ミサイル兵器の開発と関連してソ連の軍事戦略に大きな変化が起こった。1959年12月には戦略ロケット軍が創設された。1960年1月のソ連最高会議でフルシチョフ党第一書記兼首相は、核ミサイル兵器の出現によって戦争の形態が一変し、一国の国防力は兵隊の数ではなく、核ミサイル兵器の数によって決まり、この点でソ連がアメリカを上回っているとの考えを明らかにした。しかし、実際にはソ連がアメリカよりも立ち後れていることが1962年10月のキューバ危機の際に明白になった。ソ連は1960年代後半以降、核ミサイル兵器の増産に努め、1969年にICBMの数でアメリカに追い付いた。1972年5月に調印された戦略兵器制限協定(SALT(ソルト)‐Ⅰ)は、ICBMの保有数をアメリカ1054、ソ連1618に制限した。アメリカの質をソ連の量によってカバーし、均衡を保とうとするものであった。1979年6月に調印されたSALT‐Ⅱは、ICBM、潜水艦発射弾道弾(SLBM)、戦略爆撃機、空対地弾道弾の総数を米ソ双方とも2400に制限し、1981年1月1日以降これを2250に削減しようとするものであった。SALT‐Ⅱは、アフガニスタンへのソ連の軍事介入に抗議してアメリカが批准しなかったが、SALT‐ⅠとSALT‐Ⅱは、米ソ双方が力の均衡を認め、それにより平和を維持しようとする考えを有していたことを示すものである。ソ連はこの均衡をアメリカが破ることを許さないという態度をとった。
ソ連の兵力は公表されなかったが、公表国防費は1969年から1974年まで年170億ルーブル台で、1985年と1986年は190億ルーブル台に増えた。ソ連では普通義務兵役制が実施されて、満18歳に達した男子は教育水準と軍種に応じて最高3年までの現役軍務についていた。イギリス国際戦略研究所編『ミリタリー・バランス1985~1986』によると、1985年7月1日当時のソ連の総兵力は正規軍530万人、内訳は戦略ロケット軍30万人、地上軍199万5000人、空軍57万人、防空軍63万5000人、海軍48万人、鉄道建設部隊・労働部隊61万5000人、司令部および一般支援要員70万5000人。ほかに国境警備隊25万人、国内隊35万人、計590万人であった。アメリカ国防総省編『ソビエト・ミリタリー・パワー1986』によると、ソ連の核戦力はICBM1396、長射程中距離核戦力(LRINF)553、SLBM983、戦略爆撃機847、戦術航空機は6300、地上軍は201個師団、戦略防衛戦力は迎撃機1210、対衛星攻撃兵器(ASAT)と地対空ミサイル(SAM)が計9000、弾道弾迎撃ミサイル(ABM)100、海軍は航空母艦3、主要水上艦艇280、その他の戦闘艦艇392、戦闘用舟艇745、補助艦艇300、潜水艦375、海軍航空機1645であった。
[中西 治]
経済・産業
概説
社会主義諸国は国有化を基礎に中央集権的性格の強い計画経済を営んできた。とりわけソビエト連邦は、ロシア革命時の土地国有化および半年後の重要産業の国有化を基に、1920年代ネップ(新経済政策)期の大幅な市場経済放任ののち、1930年代には中央集権的指令的計画経済を体系化・制度化し、いわゆる五か年計画を積み上げてきた。第一次五か年計画は1928~1932年であるが、第二次世界大戦による中断などを経つつも計画は着々と進められ、カレンダーイヤー(暦年)にあわせた五か年計画(第十一次1981~1985年、第十二次1986~1990年など)となっていた。また産業的にも、ソ連末期には農業そのものも事実上国有化し計画経済のなかにいっそう深く組み込もうとしていた。
この中央集権的指令的計画経済は、ノーメンクラツーラ(指命職名表)に基づく重要管理者ポスト人事の任命制、財政・金融の完全な一体化、機械・資材など生産手段の非市場化(配給制)、国定価格など行政的価格決定制、貨幣指標よりも現物指標を重視すること、企業長単独責任制と労働組合の福祉活動への限定、職種別賃金等級表の国定制などを特徴とする。そして、こうした特徴がよく作用する分野においては相当の成果をあげてきた。すなわち、巨大な建造物建設工事や大規模エネルギー開発、輸送網の拡充、軍需工業の展開、また、行政機構の官僚制的組織化、賃金上昇圧力の抑制、物価騰貴の抑制、基礎的消費財の大量供給などがそれであり、こうした成果は途上国の追求目標となっていたのみならず、一部先進諸国もうらやむほどのものであった。
だがその反面、五か年計画の発足時が「スターリン時代」の幕開けでもあったことに象徴されているように、人事面での民主主義の欠落、企業のイニシアティブの欠如、価格の非弾力性による需給アンバランス(滞貨・不足・行列)、とくに高級消費財不足、開発投資への刺激の不足、職種階層化と「学歴社会」化などが絶えず問題とされてきた。1960年代なかばに始まった経済改革はこれら諸問題の解消を目ざすものだったのである。
しかし以上の成果と欠陥とはもともと盾の両面であり、全体として共産党という集権性の強い政党の一党支配という独特の政治構造と関係していたので、経済改革はこの政治の壁と衝突せざるをえなかった。1968年のチェコ事件、1981年のポーランド事件などがそれを示している。
さらに、米ソ冷戦下の軍拡時代のなかで軍事費の負担が大きくなっていたのみならず、激しい工業化・都市化の進展でエネルギー消費は激増し、さしもの豊かな地下資源採取にも問題が生じ、さらには都市生活の定着で生活が高度化し酪農品需要増加から飼料問題・穀物問題が深刻化していた。そして、経済成長率、資本投資効率の傾向的低下が生じていた。このことは、単にソ連自身にとって問題なばかりではなく、その国民経済の規模が巨大なだけに、世界経済にとっても重大な問題を投げかけていた。
[中山弘正]
資源・エネルギー
ソ連は資源に恵まれていたゆえに一国社会主義が可能であったが、最近の地球的規模での資源問題の深刻化をソ連だけ免れることはできなかった。急激な工業化・都市化はエネルギー消費を激増させた。総人口約2億7600万人のうち都市人口は1億8000万人に達し、モスクワの860万、レニングラード(現サンクト・ペテルブルグ)の490万、キエフの240万をはじめ、100万都市は22に達し、50万以上の都市なら51に及ぶ。ソビエト政権下で新たに1203都市が生まれたといわれるが、地方都市の群生と成長とは実に著しかった。西側諸国の都市と比較すると、一般にソ連の都市はネオンサインも極度に少なかったし、レジャー産業も皆無に等しいので、この面でのエネルギー消費は抑えられていたとみられるが、他面、実用・産業用のエネルギー消費は当然急増していたのである。
ソ連自身が公表していた「燃料エネルギーバランス」によれば、石炭・石油・天然ガスなど地下資源によるエネルギー供給が圧倒的比重を占めている。水力も増加しているが、「その他」のなかの原子力も増大していた。原子力は原則として旧来の伝統的エネルギー資源の欠けた所(ウラル以西)での立地が図られてきて、レニングラードなどでも導入された。原子力発電の設備容量はアメリカ、フランスに次ぎ第3位であったが、総エネルギー中の石油・天然ガスの比率約7割、石炭の約2割5分などと比較すると発電量の比重は小さかった。しかし、さまざまの問題点を抱えていたことは、1986年4月のチェルノブイリ事故がそれを表している。
エネルギーの供給面では、外国への輸出が1割以上にも及び、全体としてのゆとりを示していた。輸出の86%ほどは東欧向けであった。
エネルギー供給上の問題点としては、ウラル以東のいわゆる東部の供給比率が急速に高まっていたことがある。とくにシベリア開発が声高く叫ばれ始めた1960年代以降、東部地域でのエネルギー供給は加速度的にその比重を高め、供給のなかば以上に達した。しかし、エネルギー需要の7割以上はヨーロッパ・ロシア地域であるため、輸送のコストが大きくなっていた。それに加え、東部でもしだいに貧坑が掘られねばならない状況となっていた。
[中山弘正]
工業
エネルギー・燃料工業などでのソ連の生産力水準はアメリカにすこし劣るだけで、他の先進工業国に比較すると相当高い水準にあった。このエネルギーに支えられて、ソ連の工業生産高も空前の規模に達していた。
鉄鋼生産高はアメリカを抜いて世界第1位を誇っていたし、鉄鉱石はやはり東部依存の増加であるとはいえ、群を抜いていた。化学肥料、セメント、木材、トラクターなどでもアメリカと肩を並べ、とくに、機械・金属加工などでの自動化の推進、工作機械製作機の改善、巨大ダンプカーなど生産財部門の進展は顕著であった。
化学繊維、綿織物、皮革といった消費財生産高も統計的にみる限り世界的水準にあったが、実際にはその質は問題であった。あとの「衣食住」の項でも述べるように、1960年代以降、繰り返し商品の質の向上が問題とされねばならない状況が確かに存在していた。鉄鋼の場合も、消費財向けの薄板などの生産は少なかったので、総生産高からだけではこの部門についての総括判断はできないのである。鉄鋼の場合、生産面でも酸素吹込転炉の普及率は低いなどの問題点もあった。
このように概して生産財に強く消費財に弱いソ連工業であったが、このギャップを埋めるべく西側技術の導入が進んだ。しかしこのことは多くの問題をはらむことにもなったのである。また、工業面でも労働力の流動性の大きいことが問題で、計画当局としては定着率の向上に腐心していた。
[中山弘正]
技術
マルクス・レーニン以来の「科学的社会主義」を理念とするソ連は、科学・技術の発展にはとりわけ力を注いできた。毎年の『ソ連邦国民経済統計集』も「科学・技術進歩」にはかなりのページを割き、1940年には1万人弱であった「科学労働者」は1984年150万人に増加しており、これは「世界の全科学労働者の4分の1である」と注がつく。原子力、宇宙開発、物理、数学、生化学などでの功績が誇示された。科学面への投資も年150億ルーブル(1971~1975平均)から250億ルーブル(1981~1984平均)に急増していた。機械化や自動化、ロボット化、コンピュータ化も進められていた。青少年のあこがれは宇宙飛行士であり、科学者、技術者であった。原子力発電所も、有人宇宙飛行もソ連が世界に先駆けた。軍事技術や産業でも大型・重機械などの技術は世界的水準とみられていた。しかし、1980年代以降の世界的な「軽・薄・短・小」化、「先端技術」の面では、西側に数年から十数年の差をあけられていたとみられている。産業でも軽工業、民需面での技術に関しては、ソ連自身もその遅れを意識していた。教育改革(後述)でコンピュータ化が叫ばれていたが、そもそもハード部分を教育界にどの程度確保しうるかが問題であった。技術の開発は原則として中央集権的に専門化していたのでメリットもあったが、一方、企業レベルへの普及、そのインセンティブに乏しいこと、またこれには価格面からの刺激(特別超過利潤といった形の)が小さいこと、なども問題とされた。
トップのほうの科学者は量質とも群を抜いていたとしても、それを支える普通教育修了・職業専門教育出身者、日本の「高卒」ぐらいの層では国民経済の需要が3分の1ぐらいしか満たされていなかっただけでなく、1970年代なかばで国民経済就業者の3割が初等教育以下であり、中等・高等教育を身につけた労働者の割合は「アメリカの1950年代初頭ぐらい」とソ連のなかで論じられていたように、中・下級の科学技術者層に問題が大きかった。チェルノブイリ原発事故もこうした中・下層技術者の問題が重要な要因として指摘されねばなるまい。
[中山弘正]
財政・金融
現代国家はいずれの国をとっても国民経済のなかで財政の比重が大きいのであるが、ソ連邦ほど財政が国民経済と大きく重なり合い、再生産に重大な機能を果たしてきた国はまれであろう。もともとロシア近代化の過程でも財政はきわめて重大な役割を演じていたし、金融は自立性が小さく「財政の侍女」とよばれていたのであるが、1920年代の末ごろから計画経済が制度化される過程で、早くも財政は主役を演じ始めていたのである。
日本の法人税を4割とすると、ソ連の企業利潤控除は6割であった。国民所得計算方式上の違いはあるとしても、ソ連では財政は国民所得の3分の2にも達していた勘定になる。たとえば、これに対照される日本の数字は4分の1ないし2分の1であろう。
ソ連邦財政の歳入の二大柱は取引税と利潤控除であり、すこし離れて個人所得税が続いていた。次項でみる経済改革のなかで、企業の自主性の強化が叫ばれたが、このことは当然に国営企業の利潤のうち財政へ控除される部分の比率の低下をもたらすはずであった。実際それは、1965年の70%から1971年の57%にまで低下し、のち、ふたたび増大しまた低下したが、集権性の強い構造は変わらなかった。
歳入中の取引税は消費財にとくに大きく課せられていたものであり(もともとは革命前のウォツカ酒税であった)、一部生産財部門の恒常的赤字(計画欠損とよばれた)とともにその不合理・アンバランスさが指摘され、この種の税を縮小していくことが目標とされて、一時は利潤控除よりも小さい割合に下がり、1980年では逆にそれを凌駕(りょうが)するに至ったが、その後また下がった。
ソ連邦財政は全体として黒字均衡財政を堅持し、国債も発行していたとはいえごくわずかであり、物価抑制でも一貫しているなど、西側諸国にはない強い統制力ももっていた一方で、経済改革の必要性は絶えず叫び続けられていた。
金融は、西側諸国の「信用創造」機能と多数銀行の競争システムを早くから捨てていた。ソ連には「消極的貨幣(パッシブ・マネー)」しか存在しないなどと表現されたが、金融面を一元支配していた国立銀行は財政とタイアップして集権的な資金配分機関化している面が強かった。とはいえ、1980年代前半には鉱工業、農業などへの長短期資金の貸付残高は伸びていた。
[中山弘正]
経済改革
鉱工業・技術・財政のこうした発展は、革命時ロシアが農業国だったこと、またその後、干渉戦・独ソ戦・冷戦に絶えずさらされてきたことを考えると、驚くべき成果といわねばならないが、それだけに経済発展が新たな段階に達した1960年代ごろからは多くの問題点が出てこざるをえなかった。
その中心は、中央集権的指令的なシステムそのもののもつ弊害である。短期間に急成長を遂げえた理由の一つは組織性に求められようが、それは「概説」の項で掲げたような諸特徴、つまりひとことでいえば「軍隊風の」位階制的集権組織であった。安いものを大量に生産し、道路・鉄道などインフラストラクチャーをつくっていく段階でそれは有効であったが、消費が高度化し多元化する段階では弊害が感じられた。過度の集権性を打破するために1965年以降「経済改革」が実施され、「市場」要素を大幅に導入しつつ、企業の自主性を強化し、利潤指標を重視して最終的需要にまでメーカーが責任をもつシステムの実施が試みられたのである。この「利潤刺激の新方式」は、統計上は1968年にはソ連邦工業企業数の54%、同生産額の72%、同労働者の71%、同利潤額の81%にも及んでいたが、このころがピークで、その後はこうした比率の数字だけは大きくなり続けたものの、実態としての改革はほとんど挫折(ざせつ)してしまったのである。1968年8月のチェコ事件が転機となったのである。
すなわち、1960年代に入ってからチェコスロバキアでも類似の改革が実施に移され、従来の中央集権的指令的経済を「外延的」方式と批判し、技術革新・商品「質」の高度化・経済効率重視の「内包的=集約的」方式の導入が試みられた。しかし、ソ連の場合と異なり、企業内の民主化(労働者の発言力の強化)が重視されたことと、市場という概念のなかに必然的に「発達した西欧市場」を含めていたことのゆえに、経済改革はやがて政治改革にも拡張され、共産党一党支配の否定・複数政党制要求にまでも及んだのである。ここに至ってソ連は軍事干渉に踏み切り、あわせて自国内部の改革派の抑圧に転じたのである。それ以後の経済運営では集権化のほうに振り子が傾き、スターリン時代に形成されたソ連型の経済構造の抜本的変革はなされないままであった。
しかし、経済改革に失敗したといっても工業化は絶えず進んでいるわけであり、部分的改革・手直しはその後も行われてきた。もともと集権性の弊というものは、集権性が100%貫徹して生じているというよりも、中央の計画当局のプランと現場・企業レベルの実態とに齟齬(そご)が生じ、現場では自前の調達等々をせざるをえないことから生ずる滞貨や不足なのである。表は計画で裏はアナーキーといった実態から生ずる浪費が問題とされたわけである。
そしてこの根本的構造が克服されないままで、軍事費負担の急増などが生じたために(近年の軍事技術の進みぐあいは著しく、かつ大規模投資を要することはいうまでもない)、投資効率の低下が問題となった。すなわち、とくに1970年代に入ってから拡大再生産の平均テンポは明らかに傾向的に鈍化しはじめ、西側諸国の多くよりは高いとはいえ、従来の経済運営に問題が生じていたことが明瞭(めいりょう)であった。かつてとほとんど同じ経済改革の提言がゴルバチョフ書記長の下で繰り返されたことは、問題の構造性を示していたといえよう。
[中山弘正]
農業
ソビエト国民経済のなかで農業の比重は著しく減少したとはいえ、実は農業問題は依然大きかった。国民所得の伸び率の低下した年度は、かならず農業生産の対前年比が減少を示していた。農業生産の安定的な成長は、ソ連経済全体の順調な発展の鍵(かぎ)を握っていたとさえいえるのである。
ネップ期の小農を中心とした体制は、1930年の全面的強制的集団化以降、集団農場体制にかわっていったが、スターリン批判後も根本的批判はないままに、むしろフルシチョフ農政(1953~1964)、ブレジネフ農政(1965~1982)を経て、いちおう定着してきていた。
すなわちフルシチョフ農政は、集団農場群に対する政治上の拠点でもあったエム・テー・エス(機械・トラクター・ステーション)の解体を含め、カザフ共和国などでの処女地開拓、コルホーズ(協同組合農場)の統合強化、ソフホーズ(国営農場)化の推進、農産物買付価格引上げなどの意欲的政策を展開し、その結果、スターリン時代の集団農場といえばほとんどがコルホーズをさすといった状況から、ソフホーズが重要な比重を占めるところにまで変化したのである。ブレジネフ農政もまったくこれに倣ったために、1960年代後半以降は集団農場はコルホーズ、ソフホーズが社会化経営のほぼ対等な担い手となった。これに個人副業経営が加わり、ソ連農業経営の三大類型となっていた。「商品」化された農産物のなかでの個人副業の比重はさほど大きなものではないが、自家消費分も含めた「総生産高」中の比重では、個人副業は畜産、野菜、ジャガイモなどを中心にほぼ3分の1の比重を占めていた。
ブレジネフ期に入ってからとくに推奨されていたものに、統合体、企業間企業と称する、従来の企業を出資主体とする新複合体があった。これは、西側でアグリビジネスとよばれる農業関連企業との複合も目ざしており、その意味で農工コンプレックスでもあった。
農業への資本投資はもとはほとんどコルホーズが自ら行っていたのであるが、徐々に国家投資分の比重が高まり、それが全体の約3分の2にも達してきた。のみならず、コルホーズ投資分も内実は国立銀行の資金援助を受けたものが増えていた。
ソフホーズ化すなわち国営農場の比重増大は、人事面・計画面での国家の全面的掌握を可能にしたとはいえ、もともと赤字ばかりであった経営類型だけに、全体として国家財政の負担を増した。加えて、消費者価格を据え置いたままで生産者からの買付価格は引上げを続けていたため、逆ざや現象が生じ、この価格差補助金は、財政の10分の1、農業関係予算のなかば近くにも達し、約250億ルーブル、国防費をしのぐとさえいわれた。コルホーズも統合を重ねつつ、しだいに内実(人事、価格、賃金など)は国営農場と大差ないものとなってゆき、全体として「農業の国有化」とよぶべき状態になった。スターリン時代、ほとんど対価なしで総収穫の4~5割をも調達していたころの農業は工業化の蓄積源泉だったとみられるが、1980年代ではむしろ逆に被保護産業化していたとさえいわねばならなかった。
こうした企業経営面、財政面からの熱心で大規模な農業政策の展開にもかかわらず、1979~1984年の6年連続不作とさえいわれたほどに農業生産の成果は安定上昇とはいいがたかった。ソ連政府が強調していたように、穀物をはじめとした農産物の生産高は五か年平均でみると、第十次五か年までは伸び続けてきたが、第十一次(1981~1985)では2億トン以下に低下した。1年1年の穀物収穫高の振幅もたいへんに大きく、1970年代からは、ソ連は大量・恒常的な穀物輸入国となっていたのである。革命前ロシアが大規模な穀物輸出国であったことは有名であり、第二次世界大戦後も1960年代までは(1963年凶作時を例外として)年400万~600万トンをも輸出してきただけに、それ以後のソ連の農業事情での変貌(へんぼう)は注目する必要があるわけである。1980年代のなかばの穀物輸入量は年平均4000万~5000万トンにも達していたことが知られているのである。しかし国内生産量自体が著しく大きいので、輸入依存度(約25%)をとれば日本などよりは小さかった。しかし全体のスケールが大きかっただけに、この輸入量自体が世界経済を文字どおり震撼(しんかん)させたほどだったのである。
ロシア革命のスローガンは「平和」「土地」と並んで「パン」であったし、ソ連は長くパンの問題に悩んできた。過酷・非情な農業集団化(反抗した農民が家畜を大量に殺し、また自らも家畜のように追われていった)も穀物調達問題を契機としていたのである。しかし、1980年代のソ連の大量・恒常的穀物輸入はパンの問題というよりも飼料問題であった。米を1000万トン生産しながら、2000万トン近い飼料を日本も輸入しているように、都市化により酪農品消費が激増したソ連でも「1トンの肉を食べるために10トンの飼料」というぜいたくな悩みを解決せねばならなかったのである。穀物輸入問題は次の「対外経済関係」の問題につながっていた。
不作が頻発する最大の理由は寒冷・乾燥という厳しい自然条件であろうが、加えて、フルシチョフ農政以来開拓された辺境の不安定度がとくに大きかったこと、労働の季節的ピークを崩すことが困難なため、労働力の流出が著しいこと、機械・設備の維持・修繕に問題が多かったこと(部品供給体制の悪さも含めて)、保管・運搬・流通機構に欠陥が多かったこと、など社会的要因による逸失も少なくなかったのである。ソ連といえば日本の60倍という面積、40倍という耕地、と「広大さ」が先入観にあるが、自然が濃く残っているのはウラル以東であり、ヨーロッパ・ロシア部では農用地化はエコロジカルにはもはや限界の50~70%も耕されていたといわれる。それゆえ、開拓されて比較的新しい辺境でも、また伝統的地帯でも、自然現象が厳しいときには、大量かつ一挙の大損害を受けることになりやすかった。
[中山弘正]
対外経済関係
穀物輸入の増大は当然その対価となりうる商品輸出の増大を要請する。そして一国の対外経済関係は普通、国際収支表に総括されるのであるが、ソ連はそれを公表していなかった。金移動や軍事関係のようなものが秘密扱いだったからであろう。
加えて、ソ連の対外経済関係を複雑にしていたものに、次のような事情がある。貿易は総合で黒字なのだが、これが対セフ(経済相互援助会議=コメコン)および対途上国貿易であげた黒字と、対西側貿易での赤字の組合せからなっていて、前者のかなりの部分をなす対社会主義諸国貿易は、振替ルーブルといって交換性のない外貨で決済されていたのである。
ソ連の対外援助も1980年代前半では年間100億ドルにも達すると推測されていたが、これもむろん公表されていなかった。
振替ルーブル決済分を省いて交換性通貨による国際収支を西側で推計したりしていたが、穀物輸入が増大したのに伴って増える貿易赤字を石油や金販売、軍需品販売などで埋めようという努力がなされていたほか、外資導入が積極的に行われていたのである。
ソ連自身の貿易統計だけからでもはっきりいえることは、輸出入の商品構成において1980年代に至り機械・設備の輸出比が落ち輸入比は高く、燃料・電力輸出すなわちエネルギー資源輸出比が著しく高まっていたことである。1970年代に西側の技術や資本が大幅に導入されてきたことの結果がこのような形で現れたともみられるのであり、急成長を誇ってきたソ連経済も、かつて西欧資本の債務奴隷に陥っていた帝政ロシア時代の悪夢にしつこく付きまとわれていたといわざるをえない。
[中山弘正]
社会
概説
ソ連社会は社会主義諸国に共通にみられる独特の社会構造の原型をなしていた。それはむろん西側諸国との共通性ももっていたが、同時にまったく特有ないし対照的なものでもあった。ここでは、一般庶民の衣食住をひととおり検討したあと、この独特の社会構造を、社会を分散させ多元化させる方向の要素(都市化、民族問題、宗教、世代)と、逆にそれを統合していこうとする要素(マスコミ、党、職種位階、教育)の順でみていくことにする。
[中山弘正]
衣食住
ロシア革命のスローガンの一つであった「パン」の問題は、1960年代以降ほぼ解決されていた。穀物輸入問題は飼料問題であり、食用パンのためには国内農業の半分もあれば十分なところには達していた。都市の公共食堂では食べ残しが目だち、「パンは屑(くず)ではない」「パンの保存の仕方」といったポスターを食堂やパン屋にみかけた。とくに伝統のある黒パン(ライムギパン)の消費は落ちていた。都市化、食生活の高度化で酪農品消費はすっかり定着するとともに、野菜、果実などの消費も増大していた。日本人の食生活と比較すると、バター、肉、牛乳などの消費量は数倍も大きかった。食料品は概して安く、しかもその価格は長期にわたり安定していた。これは酪農品の場合など財政からの価格差補助金などもあるからでもあったが、高級品の不足はあっても一般品には事欠かなかった。
衣類は化学繊維も含め生産量増加も著しかった。市民の衣料もカラフルになり向上しており、とくに冬場の衣料はさすがにしっかりしていた。靴などを含め基礎的なものは満たされていた。パンティ・ストッキングがよい土産(みやげ)品となったことは有名であるが、やや高級な製品、上質の柔らかい下着、子供用品、婦人用ブーツ、ジーンズなどは著しく品薄で店頭に行列が絶えなかった。
住宅建設に注がれた努力もたいへんなものであり、大中都市の郊外には大集合住宅・大団地群が続々と誕生していた。それでも、建設が予定よりも長引くという事情はしばしば指摘されていたが、これは供給を上回っての需要の爆発的拡大圧力が背後にあったからであろう。都市は行政的にも人口流入を制限していたが、それでも事実上流入は大きく、住宅事情は厳しかった。集合住宅でも間借りは多く、1区画(クバルチーラ)を1家族で占有するということが庶民の願望であった。大都市ではタイプ刷り週刊の『住宅交換情報』誌が発行されていてすぐ売り切れた。これを見ると、たとえば、3DKの中に「もう1人」居住しているなどと自分のほうの居住条件が記されていた。住宅も基本的には私有財ではなかったので、安い賃貸料を払えばすむのであり、商品化しえないので「交換」となるわけであるが、1980年代前半期には分譲方式が人気をよんでいた。頭金は多額だが間取りに注文ができ、事実上の相続も効いた。
こうした衣食住の状況であったが、教育費も文化費も安かったといえる。ただし、教育でも、下宿等の付帯費用はむろん小さくなかったし、文化に関しては、いわゆるレジャー産業がソ連の場合ほとんど存在しなかった点に特徴があろう。エロ・グロのいかがわしい産業はむろんのこと、バー、キャバレー、パチンコ、マージャン、プロスポーツ、そして喫茶店すらもたてまえ上ほとんど存在せず(隠された裏社会は若干存在したとしても)、文字どおり「労働者・農民」の国という感じで、制度上は健全な社会であった。
[中山弘正]
都市化
都市の成長については先にも触れたが、都市化は、社会的分業を複雑化し深め、いきおい人々や職種の階層・グループも多元的に錯綜(さくそう)する。革命直後のように国民の圧倒的多数が農業・農村とのつながりで生活していたころとはおのずから様相を異にしていた。都市は雑多な知識産業を生み、インテリも育てる。サミズダート(自主出版)も都市で育ったのである。
[中山弘正]
民族
ソ連には100以上もの民族があり、『国民経済統計集』に載っている大分類だけでも60余、小分類も入れて90余に達していた。「国際」(メジュドゥ・ナロードヌイ=民族間)会議が、国内だけでしばしば開かれていた。
1989年センサスで、ロシア人が1億4516万人で50.8%といちばん多く、ウクライナ人4418万で15.5%、ウズベク人1670万、ベラルーシ人1004万、カザフ人814万、アゼルバイジャン人667万、タタール人665万がこれに続いていた。ドイツ人は200万人前後存在していた。
帝政ロシアでは、ツァーリズムは諸民族の牢獄(ろうごく)といわれたが、革命後はアメリカの黒人問題のような差別問題はなくなったといわれた。確かに目に見える差別はなかったが、民族問題はむろんいろいろと存在していた。
最多数を占めるロシア人は、ソビエト社会のエリートであるといわれ、いわゆる民族共和国でも、その国の顔たる第一書記はその民族出身だが、実権は第二書記のポストを占めるロシア人が握っている場合がほとんどだと、エレーヌ・カレール・ダンコースHélène Carrère d'Encausse(1929―2023、フランスの社会学者)は分析した。第二書記は、1977年ロシア以外の14の共和国のうち12までがはっきりとしたロシア人であった。ソ連の社会学者たち自身の諸調査によっても、進学率や高資格精神労働への登用などでロシア人は有利であった。とくに地方では都市部はロシア語とロシア人が支配的であり、そのため農村出身の民族青年が適応(アダプタチヤ)できずに村に還流するケースさえ少なくないとされていた。
ところが、人口増加率ではロシア人のそれは低下していたが、逆に民族共和国では相当高かったのである。数十年先には構成比が大幅に変化することが予想されていた。実際、モスクワなどではひとりっ子の家庭がほとんどであったが、民族地域では5、6人の子持ちは普通であった。1980年の人口の自然増加率は、ロシア連邦共和国(むろん全部がロシア人というわけではないが圧倒的多数)では1000人に対し4.9人であったが、バルト三国とウクライナ共和国を除き、他の民族共和国はこれをはるかに上回り、タジク29人、ウズベク26.4人、トルクメン26.0人、キルギス21.2人、アゼルバイジャン18.2人、アルメニア17.2人といった高い増加率を示していた。
ウクライナ民族の場合、ロシア革命時に激烈な民族独立運動また独自の農民運動(マフノ運動)などがあったのを、ロシア人が中心となった赤軍が遠征・征服するという不幸な事情があったため、根強い反ボリシェビキ感情が残っており、しばしば、教育機関や公用語使用問題でのトラブルや経済改革期の共和国の自主決定権限の強化など、緩やかだが大きな対立が起こった。一部には当局も手を焼くような粘り強い民族自立運動が続けられていた。
バルト三国は1940年にソ連邦に組み込まれたわけで日も浅いことと、次の「宗教」の項でみるような独自の宗教事情にあるため、民族問題として大きい比重を占めていた。またクリミア・タタールのように、スターリン時代に強制移住させられた民族もある。ノボシビルスク市郊外には第二次世界大戦期ドイツ人が同じように強制移住させられ、今日もそこに住んでいる。
民族別調査で、10年前と比較して絶対的・相対的に減少した(34万人)ものにユダヤ人がある。調査は申告制のためロシア人等として登録した者もあるかもしれないが、減少は確かなことであり、ソ連もヨーロッパと共通にユダヤ人問題を抱えていたことを示している。革命後のソ連社会は一種の能力主義社会であり、ユダヤ人は大いにその能力を発揮したといえる。その結果、たとえば「科学労働」など高資格熟練の分野への進出は著しかった。それだけに他の民族からの反発も強く、分野によっては、入試・就職での差別が大きな問題となってさえいた。
[中山弘正]
宗教
民族と絡まりつつソビエト社会の亀裂(きれつ)をもうひとつ複雑にしていたものに宗教問題があった。革命前、圧倒的多数はロシア正教(ギリシア正教)であり、かつそれは国教でもあったのであるが、政教分離の結果、正教は大きな打撃を受けた。しかしながら、正教徒はソ連で相当厚い社会層をなし、とりわけ農村部に多かった。ソビエト農村社会学者の調査によれば、多い地域では住民の4割前後、少ない所でも1~2割が正教徒であった。多くの正教教会堂はほとんど廃墟(はいきょ)と化して寂しい姿をさらしていたが、礼拝活動の行われる「活(い)きた」教会も散在していた。
バルト三国の宗教事情は異質であった。リトアニアはカトリックが支配的(628教会、1974)であり、エストニアはその信徒が住民の3分の1にも達するといわれるほどルーテル派プロテスタントが多く、ラトビアもルーテル派が30万人信徒中の多数を占めるといわれた。これらの地域では、無神論を宣揚しようとする当局と分厚い信徒層をもつ活きた教会との間で葛藤(かっとう)があった。
バルト三国を別として、ソ連でプロテスタントといえばバプティストというくらいバプティスト(浸礼派)の活動は活発であった。全国約5000教会といい主要都市にはかならず一つはあり、大都市では複数ある場合もまれではなかった。モスクワ(会員5000)とレニングラード(会員2000)はそれぞれ一つに制限されていた(もっとも衛星都市にそれぞれ数個の教会をもっていた)が、ウクライナ共和国ではキエフの7教会に代表されるように著しく活発であった。若い信徒が多く『兄弟通信』誌を隔月刊で出していた。
アフガニスタン事件とともに大きくクローズアップされたソ連内のイスラム教徒は、見方によっては5000万人にも達していた。キリスト教と同じように、モスクはわずか200に制限されていたにもかかわらず、非公式な場での活動・教育は盛んであった。約150教会が中央アジアとカザフスタンにあるといわれたが、こうした民族共和国地域のとくに農村部では「信者」は無神論者を圧倒していた。
[中山弘正]
世代
西側にもある程度共通するが、世代の差異は革命理念国家であるだけに強かったとみられる。すなわち、老世代はスターリン時代に青春を送った硬イデオロギーの世代であり、青年層のなかでは戦無派が圧倒的であった。あとに「マスコミ」の項でもみるように国防省のキャンペーンは絶えず行われ、それに、なによりも徴兵制があったために、日本とは異なるとはいえ、世代のギャップは広がりつつあった。
たとえば都市の若者は、軽音楽・ジャズの選好性が高く、読書も老・中年世代の「戦争もの」よりも「探検もの」「恋愛もの」に傾いていた。「経済発展・民主主義・大衆の管理参加」と「平和維持・国防力強化・規律強化」と2系列の価値を示したとき、この両者の選択比重は、老世代で1対4、中年世代で1対3なのに、青年層では1対2となっていた。この世代ギャップがときに非行を生み暴力を生む。敵味方の単純区分イデオロギーではこの亀裂は把握しきれなかったのである。
[中山弘正]
言語
ソビエト社会のなかを走る以上のような亀裂をつなぎ留め、統合していこうとする力もまた存在した。
ロシア語の普及はそのもっとも基礎的なものであったろう。民族別人口を掲げた表の注として、「ソビエト人民の兄弟的友愛、統一の強化にはロシア語が重要な役割を果たしている。1979年調査でロシア語を母語と示した者1億5350万人、このうち1億3740万人がロシア人、1630万人が他の民族であった。このほかに6130万人が、第二言語としてロシア語を自由に操ることができると答えている」と記されている。世代のギャップに触れたが、実は若い世代ほどロシア語が広がっており、ロシア文化の受容度は、民族文化に固執する老世代より大きくなっていたのである。徴兵制で18歳からの2~3年を過ごす軍隊で軍事用語がロシア語であったことも、ロシア語の普及には大きい力を発揮していたという。
[中山弘正]
マスコミ
マスコミに関して、まずデータをあげると、新聞は8000余種類(1980年8088種、1984年8327種と増加ぎみであった)で、1回の発行部数は1億8000万余部、年間では423億部とされていたので、平均すると1紙2万部強(500万部)発行ということになるが、これは1000万部以上とされる党の機関紙『プラウダ』(全国紙)から、地方都市の政府系機関紙、さらには種々の分野(芸術、文化、体育、教育、軍事など)ごとの新聞までを含んでおり、平均数字の意味は小さい。8000余種の新聞のうち約65%がロシア語のものと思われる。約2850種は非ロシア語新聞であった。定期刊行の雑誌は、1960年3761種から1984年5231種へと増加しており、年間発行部数も7億8000万部から33億4000万部へと伸びており、年平均64万部でマスコミとしての重要性は小さくなかった。ただしここではロシア語の比重が2割ほども上昇する。
1986年前半のラジオ受信機の生産台数は520万台、テレビは550万台(うちカラーテレビ250万台)で、前年同期比でもそれぞれ5%、2%(7%)の増産ぶりであったが、増産に励んできたかいもあってかラジオの世帯当り普及率は1970年78%(個人当りでは24%)から、1984年ついに100%(31%)に達し、テレビもこの間に61%(18.5%)、101%(31%)と計算上は全世帯普及を果たした(ちなみに1984年で、冷蔵庫もほぼ100%、洗濯機は78%、ミシン63%、テープレコーダー41%、電気掃除機46%であった)。ただし、テレビも中型・小型は少なく、ましてや日本のようなミニテレビはまったく存在しなかったといってよい。ラジオもきわめて単純な形のものが広く使用されていた。
さて、こうした新聞や雑誌、またラジオやテレビで扱われる情報の質的内容について述べると、マス・メディアに対する党のコントロールの徹底していたことがまず注目されるのである。共産党機関紙『プラウダ』と政府機関紙『イズベスチア』という2大新聞をはじめすべての新聞は、党のがっちりした政治プロパガンダの枠のなかでの情報を取り扱うにすぎなかった。一般にいわゆる「社会面」(殺人、火事、争議、スキャンダルなど)の記事というものは存在せず、また外国についての情報は、流されているとはいうものの、労働運動や革新党派の大会といったものが中心で、明らかに一般的なものではなかった。たとえば毛沢東(もうたくとう)の死(1976年9月)は日本などではトップ記事で特集記事がいくつも組まれたりしたが、『プラウダ』は小さなベタ記事ですませた。同じころのミグ25戦闘機の日本亡命事件なども、しばらくの間はなにも報道されず、かなり日時が経過したのち、政府の日本政府非難の声明という形で初めて報道網にのっていた。明らかに情報はそのときの党の政治方針にあわせた強力な統制の下に置かれていて、日本などでのような過剰とさえ思われる報道合戦もないかわりに、一般庶民は一般の社会的事件についてはほとんど知らないままであった。
情報統制の貫徹はむろんラジオ・テレビにも及んでいた。白黒テレビの多いモスクワの4チャンネル・テレビ網で、どこでもいちばん多いのは軍や政治のことであった。よろめきドラマやエロ・グロ・ナンセンス、どぎつい漫画といったものもないきわめてまじめな番組が多かったのであるが、ここにも社会的事件報道はなかった。軍はゴールデンアワーを占めて、つい昨日のことのように独ソ戦に関連した番組を絶えず流し、国境守備隊の苦闘を写した。ラジオもピオネール(共産主義少年少女組織)の歌から始まってクレムリンの大時計で終わる。
いずれのマス・メディアでも共通して権力批判は絶対に存在しなかった。なぜならば、これらのメディアは権力そのものの物だったからである。『文学新聞』『スポーツ新聞』『農村生活』など紙誌の種類は多かったが、革命記念日などの第一面の構成はまったく統一されており、統制の徹底ぶりを示していた。また、概して広告が存在しない(広告特集号を出す夕刊紙などもあるが)点も特徴の一つだったといえよう。どぎついエロ・グロや刺激的な子供漫画もなく――テレビの子供番組は夜8時15~30分の『おやすみなさい』のみ――子供の教育にはよいが、政府に批判的な言論はいっさいなく、社会的事件報道がなく、党・政府の主張と解説、軍の宣伝……と戦時下日本の情報構造を思い出させた。
なお、映画、演劇にもある類型があり、西欧タイプの青年が登場し、自由にふるまうがやがて挫折(ざせつ)し、心を入れ替えて軍隊に入るといったものであった。西側の鑑賞にも堪えるような芸術性の高いものはまれで、大衆向けのものはこうした比較的類型化したものであった。
このような情報の徹底した管理統制は、終局的には共産党の世界観を民衆の間に浸透させることを目標にしていたのであるが、いろいろな要素で多元化傾向の強まっているソビエト社会を締める機能を果たしていたのである。
[中山弘正]
党
ロシア二月革命のころわずか2万余人といわれた党員は、1930年には100万人を超え、1990年では1750万を数えるそれ自体膨大な社会内社会をなしていた。
1980年代の党員の特徴をいくつかあげてみよう。
(1)女性党員の増加が著しい。1920年ころ1割にも満たなかった女性党員は約4分の1にも達し、その割合はなおも増加傾向にあった。
(2)党員の学歴は顕著に高まっていた。1927年には高等教育(含大学)修了者は1%にも満たず、6割以上もが初等教育止まりであったが、1970年代なかばには高等教育卒は4分の1にも達した。これはむろん一般国民の教育水準の上昇という傾向の反映でもあるが、しかし、実は党員中での高等教育卒は一般国民中のそれよりもはるかに高い水準であり、党が学歴の面でもエリート集団と化していたことが明らかである。
(3)いわゆる「専門家」としての中等・高等教育を受けた「コムニスト・スペツィアリスト(専門家共産党員)」が増加していたこと。革命後まもない軍隊や企業で、党と専門技術者との管理指導上の主導権問題は深刻であり、中国などでも「紅か専か」といった形でしばしば問題となってきたわけであるが、ソ連ではこうした形でしだいに解決が図られていたともいえよう。1939年にもなお15%に満たなかったこの種の党員は、なかば以上にまで増加していたのである。
こうした特徴をみせながらも、それ自体巨大な集団となっていた党は、完全な位階制が貫徹し、下級細胞からトップの党中央委員会政治局、書記長に至るまでのピラミッドを形成していた。上のほうはノーメンクラツーラ(指命職名表)に登用され、情報、人事、商品購入、諸施設利用などで種々の特典をもったが、現場の平党員は『プラウダ』一つで情宣にあたるといった状況であった。この軍隊方式の秘密組織は、官僚社会、企業などにも広く浸透し、ソビエト社会の最終的紐帯(ちゅうたい)をなしていた。
[中山弘正]
職種位階
ソビエト社会内のあらゆる小社会で共産党は影のように存在し、この小社会に対してもっとも強い権限をもつことによって、多極化するソビエト社会をくくっていたのである。このマルクス・レーニン主義党は世界観党であったからその理念に応じて社会をつくってきたのであり、それゆえソビエト社会全体が一つの位階制社会と特徴づけられたのである。
社会自体の存亡を決めるものとしての軍事、またこれを支える科学、対外威信としての芸術・体育などもソビエト社会のなかで最高の位階を占めていた。これを支える工業が次位にきたが、軍需工業と関連深い重工業が上位で、軽工業はこれに次ぐ。ついで農業、これも国営農場、協同組合農場、個人副業の順となっていた。商業、サービス、消費といった分野は位階のもっとも下部に位置していたのである。
こうした産業別位階ともいうべきものは、それぞれの部門の労働者・職員の賃金にも端的に反映していた。1984年で、工業、農業、商業の月平均賃金は204.6ルーブル、176.4ルーブル、145.9ルーブルであった。
そして、それぞれの分野中の企業・機関では、トップマネジメント(行政管理責任者)、技師、一般労働者という位階が貫徹していたが、労働者のなかは精神労働から肉体労働へ、また有資格熟練度によって職種位階制が組まれていた。これはたとえば農業企業の場合の完全なピラミッド型をなしており、最下位層は特別な「資格(クバリフィカチヤ)」をなんらもたない雑役者だったのである。
そして、職種位階の下位の者ほど「自分がその企業の管理運営に影響を与えている」という自覚が小さかった。いわば企業参加度も職種位階の上位ほど高かったのである。以上から当然予想されるように、党員存在比率も職種位階が高いほどに大きかった。党員の学歴上昇とか専門家・党員の増大といったことが、こうした党のあり方の反映でもあったわけである。
信者など宗教者、非党的思想の持ち主が、概してこうした職種位階の上位とは無縁であることもまた予想されたところであるが、ソビエト社会学者の調査はそのことを明示していた。かくて、ソビエト社会は、学歴位階=職種位階=所得位階=参加意識位階=党員位階=宗教者逆位階、という位階制の強い社会として特徴づけることができた。そしてその貫徹が、複雑に多元化するソビエト社会をミクロのレベルでも締めくくっていたのである。
こうした職種位階構造を決める決め手となっていたのは、実は教育体系であった。
[中山弘正]
教育
日本でも教育制度の改革が問題になっているが、ソ連でもブレジネフ後、教育改革が日程に上り、できるところから実施に移す方針がたてられた。「普通教育学校および職業学校改革の基本方針」(1984年4月党中央委・閣僚会議決定)をはじめ一連の立法措置が集中的になされたが、第27回党大会(1986年2~3月)の書記長演説でも「一本立ての一貫教育体制の創設」「普通教育学校と職業学校の改革」などが強調された。
この教育改革の骨子は4点に集約される(北海道大学スラブ研究所・報告16による)。
(1)学校制度上の改革 3・5・2の10年制(満7歳から)を、4・5・2(満6歳から)の11年制とする。また、既存の職業技術学校(複数のコースがあった)をすべて中等職業技術学校とし、その年限を一律3年とする。
(2)教育内容・方法面の改革 学級定員の削減、教育課程の再検討、教育方法の改善、労働教育の比重増大、社会主義的人格形成などが目標とされた。前半40名、後半35名の1クラス上限を30名、25名に引き下げ、生徒の過重負担軽減、学習内容の重複排除を図るとともに、今日の科学技術の発展に見合うようにカリキュラムを再検討する。また「つめこみ」「暗記主義」の反省の上にたち、ゼミ・討論形式、個人指導などを積極的に導入し、7~11年生では選択授業の時間数を増やす。コンピュータ教育の推進を図り、かつ労働教育の時間数を著増する。また、国章・国旗・国歌の活用、新しい生徒規則の作成などで、革命や戦争を体験していない新世代のいわば「道徳教育」が検討された。
(3)学校と地域・家庭との連携の強化 各学校が協力企業をもち、労働教育指導者、設備・備品を提供してもらうことや、校外施設、学童保育制学校の拡充、「子供の部屋」などを設置し、地域の子供たちの遊びや学習を指導すること、共産党の青少年組織を労働に結び付けていくこと、また道徳や健康面での家庭の教育責任の再確認などが目ざされた。
(4)教員の資質・待遇の改善 教職専門科目・教育実習時間の増加、特定教科についての教員養成課程の4年から5年への延長、研修の充実、教員給の30~35%引上げ、優秀者称号(上級教師、功労教師等)の付与などが計画された。
この教育改革は、スターリン期(1931)、フルシチョフ期(1958)に次いで大きく、1990年まで毎年110億ルーブルの財政支出増という予算措置も伴っていた。改革は1986年度(9月開始)より、実施できるところから始めていくこととされていた。
さて、制度上、以上のような「教育改革」がゴルバチョフ書記長の下で推進されていたが、その機能の本質的性格という点からみると、旧にせよ新にせよ、この教育体系こそが人々を各分野の職種位階に振り分けたのである。たとえば、農業企業で最下位を形成する「馬使役=手労働」層は、そのほとんどが義務教育そのものを受けていないか、初等教育止まりの人々だったのである。
これがマルクスらの考えた社会主義社会であったかどうかは、わからない。しかし「序列」というものがきわめて重んじられたところに、この社会の特徴がよく表れていたのである。
[中山弘正]
文化
概観
ソビエトの文化という概念は、一見きわめて明快のようにみえるが、その内実はかなり複雑なものがある。というのは、ソビエトという名称は「ソビエト社会主義共和国連邦」の略称であるが、この15の共和国から成り立つ連邦の指導的立場を占めていたのがロシア連邦共和国であり、ソビエトと称しながらも、実質的にはロシアとそれほど違わない受け取り方が行われていたからである。もちろん、厳密な意味ではそれは間違っているといえるが、文化という点ではそれを許容する側面もないわけではない。いや、日本においても、ソビエトの文化というとき、15の共和国それぞれの文化を総合したものという考えよりも、革命後のロシア文化という受け取り方が強いことも事実である。事実、革命前のロシア帝国も、以後のソビエト連邦の各共和国の大部分をその支配下に置いており、それらの地方の文化をまったく反映していなかったわけではない。したがって、ソビエトの文化を語るにあたって、まずその伝統的なロシアの文化について語ることは当然であろう。
ロシアの文化を考えるとき、まずなによりも重視しなければならないのは、その独特な風土である。一般的にいって、だれしも考えるのは、その広大な自然であろう。果てしなく続く地平線の眺め、あるいは、うっそうたる森、悠々と流れる大河、こうした自然環境がロシア人に及ぼした有形無形の影響は、ロシアの文化に色濃く反映されている。しかも、異国の人々には恐怖すらおこしかねないそうした茫漠(ぼうばく)たる眺めも、ロシア人にとっては一種の安らぎ、自由の感覚をもたらすものだといわれている。また、厳しい自然はロシア人に耐えることを学ばせた。この耐久精神はロシアの文化にさまざまなよき影響を与えているといえよう。一見、鈍重そうにみえるその国民性も、時と場合によっては、激しく燃え上がり、きわめて積極的な行動に出ることもある。いわゆるロシア人の分極的精神なるものも、ロシアの自然と密接につながっているものである。
以上のことは革命前のロシアについてのものであるが、それは以後のソビエトにも継承された。しかし、ソビエト時代になると、そうしたロシア的なもののほかに、共産主義というイデオロギーが加味されてきた。それが文化的側面でどのような影響を与えてきたかは個々の分野で触れるが、いちばん大きな違いは、かつてロシア文化のバックボーンとされていたロシア正教が、ソビエト時代になって共産主義イデオロギーのために、迫害あるいは弾圧されたという点である。しかし、それと同時に、その後もなお農村地帯ではロシア正教は大きな力を保っているし、教会においても第二次世界大戦後の雪どけ以来、かなりの勢力を回復しているといわれている。そして、このロシア正教を基盤とするロシア人の信仰に裏づけられた博愛の精神は、「ダブラター」доброта/dobrotaとロシア語で表現される善良さによって広く世界に知られている。
[木村 浩・亀山郁夫]
国民性
前述のように、革命前のロシア人はロシア正教を基盤とする宗教生活がその中心にあったが、革命後はそうしたよりどころが消え、家庭生活や親子関係にも大きな変化が生まれた。教会の暦によって1年の生活が決まっていた農村部では、いわゆるコルホーズ(協同組合農場)での生活に初めのうちはかなり混乱があったといわれている。そこでは年齢的な格差がなく、80歳の老人も25歳の屈強の若者も同一賃金となったが、それは経済的な面だけでなく、精神的な面でも大きな影響を及ぼした。親子関係も、教会に通う母親とそれを批判的に眺めている子供たちの間では、当然のことながらトラブルが生まれた。国家権力による教会の破壊という背景のなかで、こうした親子のトラブルが進行し、かつて大家族的な親愛感にあふれていた家庭生活に冷たいすきま風が吹き込んだ。とくに、家庭生活の根幹につながる結婚にも、この傾向は顕著に現れた。革命後は性の解放が叫ばれ、旧来の道徳観が否定されたこともあって、伝統的なロシアの結婚制度は廃れ、自由恋愛とその結果としての離婚が多くなった。離婚はアメリカとともに世界でもっとも多いといわれていた。
しかし、それと同時にソビエトでは男女同権がすべての分野で行われた。高等教育機関では女性の占める数が男性を上回るほどで、その結果として大学・研究所で働く女性はきわめて多かった。一方、肉体労働にしても、機関車のかまたきといった重労働にまで女性が進出した。いずれにしても、結婚している男女のほとんどが共働きであり、そのために子供たちの家庭教育が満足にできないという声が1960年代から社会的な問題として論議されてきた。もっとも、夫婦共働きは否定面ばかりではない。経済的に裏づけされた余暇を積極的に楽しむ傾向も現れ、長い夏休みを家族連れで黒海の海岸で過ごすなど、革命前には一般庶民には考えられなかったゆとりある生活も生まれていた。
スポーツには国家的に大きな力が注がれ、各種のスポーツ・クラブが市民のために開放された。オリンピックでのソ連選手団の活躍ぶりは有名であるが、そうした選手たちも学生を除いてほとんどこうしたスポーツ・クラブのメンバーであった。
ソビエトは政治的には厳しい統制の下にあったので、一般庶民はいわゆるマイホーム型のゆとりある安定した生活を志向する人々が多くなっていた。イデオロギー最優先の国家において、かえって脱イデオロギー型の市民が増えていったことは皮肉な現象といえるだろう。そして、このような傾向は、ソビエト文化全般にさまざまな意味でその影響を及ぼしていたものと思われる。
[木村 浩・亀山郁夫]
文化施設
ソビエト国家建設の理想のなかには、文化を広く一般大衆のものにするという旗印があった。そのため1920年以降、国家は博物館、劇場、公園などの整備に力を尽くしてきた。とくに、モスクワの赤の広場に面して建つ歴史博物館はじめ、各地の博物館の整備には物心両面から国家的援助が行われた。もちろん、これはソビエト建国の大義を国民に徹底させるという眼目があり、そのために政変のたびに展示品がかわるという変則的な状況も生まれた。たとえば、革命の時点で赤軍の司令官であったトロツキーについては歴史博物館からも姿を消した。フルシチョフ失脚後はそうした場所でのフルシチョフの像が撤去された。また、スターリン批判後の一時期も同様であった。すなわち客観的な歴史観が支配するのではなく、つねに時の権力者の意向にかなうものにされてきた。しかも美術館などでもこの傾向があり、たとえばシャガールのような亡命画家については十全の配慮がなされなかった。今日世界の抽象絵画の起源とされているカンディンスキー、マレービチ、タトリンなどについても、ソ連の美術館ではそのごく一部しか展示していなかった。
これに反して一般市民の休息の場所としての公園は、イデオロギーとは無関係なため、各地で数多く建設され、市民に親しまれてきた。すなわち、文化と休息の公園といわれるこれらの公園は、モスクワのゴーリキー公園を筆頭に、全国各地に設けられた。
一方、歴史的建造物の保護管理についてはさまざまな紆余(うよ)曲折があった。革命後、ロシア正教が弾圧されたことについてはすでに述べたが、そのために有名な教会が破壊され、今日からみれば取り返しのつかない文化的損失となった。たとえば、モスクワの中心部にあった救世主キリスト大聖堂のごときは、その跡地にソビエト大宮殿を建設するはずであったが、それができず、その後、フルシチョフ時代に当時世界最大といわれた屋外プールがつくられるに至った。しかし、クレムリン内の諸教会はこれを修復し、いまなおモスクワのシンボルとなっている。このほか、雪どけ以後、スズダリ、ウラジーミル、ノブゴロド、プスコフ、ザゴルスク、キエフその他で従来放置され荒れ果てていた正教寺院が修復され、歴史的建造物として保護されてきた。
また、芝居好きのロシア人のために劇場は新しいものも次々に建造されたが、レニングラード(現サンクト・ペテルブルグ)のキーロフ劇場(現マリンスキー劇場)、あるいは、モスクワのボリショイ劇場、芸術座、マールイ劇場など革命前からの有名劇場も、革命前に劣らず華やかな舞台を提供してきた。一般的にいって、ソビエトにおける文化施設はかなり高い水準にあったといってよいだろう。
[木村 浩・亀山郁夫]
芸術
ソビエト1920年代は世界的にみても革新的な芸術が花咲いた時期であった。今日、ロシア・アバンギャルド芸術とよばれるそれらの運動には革命の掲げた進歩的なイデオロギーが新しいフォルムのなかに具現されているかにみえた。たとえば、文学におけるマヤコフスキー、美術におけるマレービチ、タトリン、そして映画のエイゼンシュテイン、演劇ではメイエルホリドなどの仕事はそれのなによりの証明であった。とくに映画は大衆啓蒙(けいもう)の手段としてきわめて高く評価されていたので、国家的援助の下に目を見張る展開を示した。演劇もまた芝居好きの国民性と、またいわゆるアジプロ演劇という側面もあって、大きな活動の場を与えられた。もっとも、芸術座でも革命後10年余りはチェーホフの芝居を上演できない時期があった。チェーホフの戯曲がプチ・ブルジョア的であるとの批判を受けたためである。今日からすれば、まことに苦笑させられることだが、歴史的な事実は事実として書き留めておくべきであろう。
一方、プロレタリアートのためには固有の「階級文化」が必要だと主張して、狭隘(きょうあい)なセクト的見解を抱いていたプロレトクリト(プロレタリア文化教育団体)の運動がおこり、従来のインテリゲンチャ出身の作家たちを圧迫し、アジプロ文学を流行させた。しかし、この運動は結局のところその性急さと狭隘なセクト的傾向のためにほとんど実りある成果をあげなかった。そして、ソビエト当局もそれを自覚して、やがて旧インテリゲンチャの保護に乗り出し、「消極的に革命を受け入れた作家たち」いわゆる同伴者作家の登場となった。こうして生まれた新しい文学は、1930年代初期にある種の成果をみせたが、1937、1938年の大粛清のころからふたたびその活気を失っていった。
しかし、対ドイツ戦が始まると、皮肉なことに一種の自由がよみがえり、戦争文学としての佳品が生まれた。第二次世界大戦が終わると、まもなく冷戦が始まり、ソビエトにおいてはコスモポリタニズム批判の嵐(あらし)が吹き荒れ、主としてユダヤ系作家の多くが粛清され、暗い日々が続いた。1953年3月、スターリンの死はソビエト文学界に「雪どけ」をもたらすことになった。そして1960年代初期にはいわゆる第四の世代と称する若年の作家たちが輩出し、1920年代に次ぐ第二のソビエト・ルネサンスを迎え、未来への明るい期待がソビエトの創造的インテリゲンチャに生まれた。
だが、その期待も1968年8月のチェコ事件によって無残にも消えてしまった。戦後の雪どけはまたソルジェニツィンという大作家を登場させていたが、その彼もついに『収容所群島』をパリで公刊したため、1974年2月、トロツキー以来といわれる国家権力による個人の国外追放の処分を受けるに至った。そして、彼の追放を機に、革命直後の知識人亡命のように、多くのソビエト文化界の活動家たちが西側へ亡命していった。このため、ソビエト文化を考える場合、本国ソビエトだけでなく、西側で活動したソビエト文化人の仕事をも視野に入れるべきであろう。
[木村 浩・亀山郁夫]
言論・出版の自由
ソビエト建国の大義たる共産主義イデオロギーは、第二次世界大戦後、東ヨーロッパにその同調国を生むことになったが、1956年のハンガリー事件、1968年のチェコ事件などにみられるように、かならずしも政治・経済・文化の面でその優越性は実証されなかった。いや、少なくとも文化面ではイデオロギーのためのマイナスが目だつようになった。その最たるものは、言論・出版の自由がかならずしも保障されていないことにあった。憲法の条文上では一見保障されているかにみえても、その実大きな制約を受けており、検閲という形で文化の各部門が入念にチェックされていた。しかし、雪どけ以来、西欧の自由な空気が流れ込み、スターリン時代の恐怖を知らぬ若者たちは、サミズダートと称する一種の地下文書を作成、それを流布させていった。これはソビエト史上初めての現象であり、それは一編の詩に始まって、短編、中編、長編にまで及び、しかも単に文学ものだけでなく、社会科学、自然科学の面にまで広がりをみせた。もちろん、初めは傍観していた当局も、やがてそれへの取締りを強化し、そうした活動家を逮捕投獄した。これはまたソビエトにおける人権運動とも密接に絡んでおり、アカデミー会員のサハロフ博士のような人物までが参加するようになり、国際的にもこうした動きは広く知られるようになった。もちろん、当局の厳しい弾圧は続いていたが、チェルネンコ死亡後のゴルバチョフ書記長の登場によって新しい雪どけへの期待も一部では生まれた。ロシア時代はもちろん、ソビエト時代になっても数々のすばらしい成果をあげてきた創造的ロシア人が、その創造力を十全に発揮するためには、言論・創造の自由が保障されることが先決であることはすでに万人の目に明らかであった。ゴルバチョフがこの決断をするか否か、ソ連の文化人たちは厳しいまなざしで見守った。1986年春に検閲機関である「グラブリット」が解体され、以後は文化関係の検閲は行われないとのニュースが流れた。「グラブリット」そのものがこれまで秘密のベールに包まれていたので、その解体も公表されたわけではない。しかし、同年6月末に開かれた第8回ソ連作家大会では、従来みられなかった活発な発言が行われ、かつて反革命のゆえに発禁となったパステルナークの『ドクトル・ジバゴ』の出版を要求する作家たちの声が目だった。また、同年4月末のチェルノブイリ原発事故の報道にも、検閲の感じられないものがあり、検閲廃止が単なるうわさではないことがうかがえた。一部にはソルジェニツィンについては作家大会でも一言の言及がなかったことをあげて、ゴルバチョフ以後の雪どけにもある枠があったことを指摘する声もある。しかし、世界的な状況からみても、ソビエトにおける自由化はもはや避けられない時の流れとなっていたのである。
なお、最後に蛇足までに付け加えると、ソビエト文化といった場合、当然のことながらソビエト連邦内に居住していた諸民族の文化をも包含したものとしての「ソビエト文化」である。しかし、個々の共和国の文化は、その指導的地位にあったロシア文化の影響下にあり、文学ひとつをとってみても、その潮流と傾向はほとんど同じものであったといっても過言ではない。ただ、時と場合によって、モスクワを遠く離れていることによって、各共和国の民族色の陰でやや独自の動きをしていたといえるだろう。しかし、今後は中央での政治的状況を反映して、各民族の文化にも従来よりいっそう明らかな民族的特殊性が生まれてくるに違いない。それはまたロシア文化をも豊かにするものであろう。
[木村 浩・亀山郁夫]
日本との関係
帝政ロシアと日本
ロシア人が日本について最初に情報を得たのは13世紀後半、元(げん)のフビライ・ハンのもとにおいてであった。その後1637年にフランドルの地理学者メルカトルの『地図帳』がロシア語に訳され、そのなかにヤポーニャ(日本)の地図と簡単な記事が現れた。
17世紀の末にカムチャツカ半島を探検したコサックの隊長アトラーソフVladimir Vasil'evich Atlasov(?―1711)が、原住民の集落で大坂出身の漂流民デンベイ(伝兵衛、生没年不詳)を発見し、日本と千島に関する情報を得た。この報告に接したピョートル大帝はデンベイを招いてその話を聞いた。日本に関心を抱いたピョートルはデンベイに、ロシア語を習ったうえで日本語を教授するよう命じた。
ロシア人が日本の北辺に渡来するようになったのは18世紀の後半からである。このときから日本とロシアは隣国どうしとなった。1778、1779年(安永7、8)の二度にわたって、ロシアの毛皮商人が得撫(うるっぷ)島から北海道の東部にやってきて交易を申し入れた。しかし松前藩は幕府にこの事実を知らせず、交易の申し出を拒絶した。仙台藩医工藤平助(くどうへいすけ)は、蝦夷(えぞ)地のロシア人に関する風聞とオランダ語で出版されたロシアの歴史と地理についての翻訳書をもとにして『赤蝦夷風説考』上下(1781、1783)を著し、蝦夷地の開発とロシアとの貿易を説いた。
ついでロシアは1792年(寛政4)に最初の遣日使節アダム・ラクスマンを、1804年(文化1)に第2回使節としてニコライ・レザノフを日本に派遣し、漂流民を送還したうえで通商を求めた。しかし鎖国政策をとる幕府は二度ともこの申し出を拒否した。ロシア側は、このような拒絶の裏には、日本との貿易の独占をねらうオランダが糸を引いているのではないかと考えた。事実、日本とロシア(ソ連)の間には、江戸時代にはオランダが、幕末から日露戦争まではイギリスが、そして第二次世界大戦後はアメリカが第三国として介在し、強い影響力を両国間に行使してきた。
1853年(嘉永6)、アメリカのペリーが浦賀に来航した1か月後、3回目のロシアの使節プチャーチンが長崎へ来航し、通商と国境の画定を申し入れた。その結果1855年2月7日(安政1年12月21日)「日露通好条約」(下田(しもだ)条約)が結ばれ、日露の国境は択捉(えとろふ)島と得撫島の間に決まったが、樺太(からふと)(サハリン)については双方の意見が折り合わず、国境を定めず両国民雑居の地とされた。明治維新後、新政府は榎本武揚(えのもとたけあき)をロシアに派遣し、1875年(明治8)「サンクト・ペテルブルグ条約」(千島・樺太交換条約)を締結。その結果、全千島列島が日本領に、樺太全島がロシア領となった。
ロシア政府は1858年(安政5)箱館(はこだて)(現在の函館(はこだて))に領事館を開設し、領事館付属の2代目司祭としてニコライが着任した。彼は1872年(明治5)に上京し、神田駿河台(するがだい)に復活大聖堂(ニコライ堂)を建てるとともに、7年制の正教神学校を開設して、伝道と教育に努めた。その結果1880年には日本全国で教会数69、信徒数は6099にまで達した。神学校卒業生のなかからは小西増太郎(こにしますたろう)(1862―1940)、昇曙夢(のぼりしょむ)、瀬沼夏葉(せぬまかよう)(1875―1915)といったロシア文学の翻訳家や山下りん(1857―1939)のような聖像画家が現れた。ロシア文学は1881年に二葉亭四迷(ふたばていしめい)がツルゲーネフの『あひびき』と『めぐりあひ』を翻訳出版したときから本格的に紹介されるようになった。とくに明治30年代からはトルストイ熱が流行し、1916年(大正5)~1919年には、月刊の『トルストイ研究』が、1919~1920年には『トルストイ全集』が発行されるまでになった。このほかドストエフスキー、チェーホフ、ゴーリキーなどの作品も次々に翻訳され人気を博した。
極東における日本とロシアの対立はついに日露戦争を引き起こし、1905年(明治38)「ポーツマス条約」が結ばれた。これによって樺太の北緯50度以南が日本領となった。またこの条約に基づき1907年日露漁業条約が結ばれ、これ以後、北洋の漁業権は国家権益とみなされるようになった。
日露戦争後、日本は満州における権益を確保するために、ロシアとの接近を図った。その結果、満蒙(まんもう)地域における日露両国の勢力範囲を画定するために、1907年から1916年にかけて4回にわたって日露協約が結ばれた。第4回目の協約は秘密協定を含むもので、中国の服属と英米の中国進出の阻止をねらった軍事同盟であった。
[高野 明・外川継男]
ロシア革命から第二次世界大戦まで
1917年十月革命によってボリシェビキが政権を獲得し、ドイツと単独講和を結んで戦線を離脱した。これに対し日本は米・英・仏などの連合国とともに干渉戦争を開始した。日本の派兵は7万余、期間も1918年8月から1922年10月に及び、連合国のなかでも最大の規模であった。この間1920年には尼港(にこう)事件が起こり、当時ソビエト政権を承認していなかった日本は、事件の交渉相手がいないことを理由に、1925年5月まで北樺太の保障占領を続けた。
1924年にまずイギリスがソ連政府を承認し、続いてイタリア、フランスもこれに倣ったが、日本も1925年に「日ソ基本条約」を結んで国交を回復した。
1932年(昭和7)の「満州国」建設後、関東軍の勢力は年を追って増大し、ソ・満国境において1938年に張鼓峰(ちょうこほう)事件が、1939年にノモンハン事件が発生、日本軍は大敗した。
1939年8月ナチス・ドイツはソ連と不可侵条約を結び、その1週間後にポーランドへ侵入、第二次世界大戦の幕が切って落とされた。翌1940年10月、近衛(このえ)内閣はドイツの提案にのって日独伊三国同盟を結んだ。ついで1941年4月には松岡外相がスターリンと会談して、「日ソ中立条約」が締結された。その直後に独ソ戦が始まったが、日本の軍部のなかには対ソ侵攻論が台頭し、7月から8月にかけて70万の兵を動員して「関特演」(関東軍特種演習)が行われた。これは対ソ作戦準備行動であって、事実上日ソ中立条約を侵犯するものであった。
[高野 明・外川継男]
第二次世界大戦後
日本がソ連と国交を回復したのは、第二次世界大戦後11年たった1956年(昭和31)のことである。この年10月、首相の鳩山一郎(はとやまいちろう)がソ連を訪問して「日ソ共同宣言」が調印された。当初鳩山内閣は、歯舞(はぼまい)・色丹(しこたん)島の返還をもって平和条約を締結することを考えていたが、この年8月当時のアメリカ国務長官ダレスが外相・重光葵(しげみつまもる)に対し、もし日本が国後(くなしり)・択捉(えとろふ)両島をソ連に譲るならアメリカは永久に沖縄を占領し続けるだろうといったところから、領土問題は棚上げにして国交回復に踏み切ったのであった。
日ソ間にはこれより5か月前に「日ソ漁業条約」が結ばれていた。これにより、日ソ両国は資源保護のため協同措置をとることと、年間のサケ・マス漁獲量を協議して決めることが定められた。しかし1957年の第1回日ソ漁業交渉のときからこの漁獲量をめぐって毎年のように対立が続き、当初11万~12万トンであったのが、1986年には2万5000トンを切るまでになった。ソ連は1976年12月に最高会議幹部会令で200海里漁業専管水域の設定を宣言し、翌1977年3月から実施した。これは中南米諸国やアメリカの200海里宣言に追随したものであったが、日本の北洋漁業に大きなショックを与えた。1986年には、ソ連は200海里内の日本の漁獲量を前年の4分の1の15万トンと大幅に削減するとともに、底刺網漁を全面禁止した。これによって、明治以来続けられてきた北洋漁業は大きな転換を迎えるに至った。従来、日ソ漁業交渉は日ソの政治関係のバロメーターといわれてきたが、これがかならずしも通用しなくなったのは、ソ連とともにアメリカ、カナダもサケ・マスの母川国主義と北洋の資源保護を強く主張し、いまやこれは世界的な傾向になったからである。
1957年には日ソ間に通商条約と貿易支払協定が締結された。これにより貿易が軌道にのるとともに、そのなかでシベリア開発の協同プロジェクトが重要な地位を占めるようになった。このようなものとして極東森林資源の開発(第一次は1968年に契約、第二次1974年)、ウランゲリ港(ボストーチヌイ港)の建設(1970年)、パルプ材とチップの開発輸入(第一次1971年、第二次1985年)、南ヤクート原料炭開発(1974年)、サハリン大陸棚石油・天然ガスの探鉱(1975年)、ヤクート天然ガス開発(1974年)などがある。日ソ貿易は1958年の輸出入合計4000万ドルから1982年には55億8100万ドルに達した。日本はアメリカに追随して1980年からソ連のアフガニスタン侵攻に抗議する経済制裁に加わったが、この間に旧西ドイツやフランスはソ連からの天然ガスの輸入を見返りにシベリア開発に協力して対ソ貿易を伸ばした。日ソ貿易はつねに日本側の大幅な輸出超過できた。政治環境を別にしても、日ソ貿易はソ連側の厳しい外貨事情によって制約されており、日本の対外貿易のなかで占める割合もきわめて小さかった。
1973年に首相の田中角栄が総理としては鳩山のあと初めてソ連を訪問し、「日ソ共同声明」が発表された。これにより日ソ関係は経済や文化の面で多少の進展をみたが、領土問題ではまったく変化がみられなかった。1978年8月、日本は中国と「日中平和友好条約」を結んだ。これはいわゆる覇権条項を入れるか否かで双方の意見が対立し、6年近くも交渉が難航していたものだったが、この条約がいかなる第三国にも向けられたものでないことを明記することによってようやく締結に至った。しかしソ連からみれば、これは日本がソ連を袖(そで)にして中国と手を握ったことを意味した。
1985年3月ゴルバチョフ政権の登場から、ソ連は従来のアメリカ偏重から西欧や日本も重視するようになってきた。このようななかでソ連は、その停滞ぎみの経済を活性化するために、西ヨーロッパや日本からハイ・テクノロジーを導入することに意欲を示し始めた。
翌1986年には外相の安倍晋太郎(あべしんたろう)(1924―1991)がモスクワを訪問して文化協定が調印された。このときも領土問題はまったく進展がみられなかったが、これによって日ソ間の対話が定着するようになった。
1991年4月、ゴルバチョフ大統領が訪日した。これはロシア・ソ連の歴史を通じて初めての国家元首の日本訪問であった。このとき大統領はシベリア抑留中に死んだ3万7400人の名簿を日本側に引き渡すとともに、亡くなった人々に哀悼の意を表明した。日本政府はこの機会に北方領土問題でなんらかの進展がみられることを期待したが、共同声明のなかに日本側が求めた島の名が盛り込まれることはなかった。しかし、貿易、経済、文化交流、環境問題などの分野で15に上る合意文書が署名され、今後の日ソ関係の発展の基礎がつくられたかにみえた。だがその8か月後のソ連の解体によって、日ソ関係は新たな局面に入り、ソ連時代とはまた違った新しい問題が生ずるようになった。
なお、「日ロ関係」「北方領土」の項も参照されたい。
[高野 明・外川継男]
『川端香男里他監修『ロシア・ソ連を知る事典』(1989・平凡社)』▽『『ロシア地域(旧ソ連)人名事典』(1992・日本国際問題研究所)』▽『横手慎二他著『CIS(旧ソ連)地域』(1995・自由国民社)』▽『ジャック・ロッシ著、梶浦智吉他訳『ラーゲリ(強制収容所)注解事典』(1996・恵雅堂出版)』▽『石井規衛著『文明としてのソ連』(1995・山川出版社)』▽『マーチン・メイリア著、白須英子訳『ソヴィエトの悲劇 上下』(1997・草思社)』▽『ミハイル・ゴルバチョフ著、工藤精一郎他訳『ゴルバチョフ回想録 上下』(1996・新潮社)』▽『A・I・ソロビエフほか著、柴田義松訳『ソビエト連邦――その国土と人々』(1977・帝国書院)』▽『ピエール・ジョルジュ、野田早苗訳『ソビエト連邦の地理』(白水社・クセジュ文庫)』▽『E・H・カー著、塩川伸明訳『ロシア革命』(1979・岩波書店)』▽『スティーヴン・F・コーエン著、塩川伸明訳『ブハーリンとボリシェヴィキ革命』(1979・未来社)』▽『ギネス・ヒューズ他著、内田健二訳『赤い帝国――発表を禁じられていたソ連史』(1992・時事通信社)』▽『ロビン・ミルナー=ガランド著、吉田俊則訳『ロシア・ソ連史』(1992・朝倉書店)』▽『塩川伸明著『終焉のなかのソ連史』(1993・朝日新聞社)』▽『木村英亮著『増補版・ソ連の歴史――ロシア革命からポスト・ソ連まで』(1996・山川出版社)』▽『田中陽児他編『世界歴史大系 ロシア史 3』(1997・山川出版社)』▽『ロイ・A・メドベージェフ他著、下斗米伸夫訳『フルシチョフ権力の時代』(1981・御茶の水書房)』▽『下斗米伸夫著『ソビエト政治と労働組合』(1982・東京大学出版会)』▽『藤本和貴夫著『ソヴェト国家形成期の研究 1917―1921』(1987・ミネルヴァ書房)』▽『シャルル・ベトレーム著、高橋武智他訳『ソ連の階級闘争 1917―1923』(1987・第三書館)』▽『平井友義著『30年代ソビエト外交の研究』(1993・有斐閣)』▽『クリストファー・アンドルー他著、福島正光訳『KGBの内幕』(1993・文芸春秋)』▽『斉藤治子著『独ソ不可侵条約――ソ連外交秘史』(1995・新樹社)』▽『富田武著『スターリニズムの統治構造――1930年代ソ連の政策決定と国民統合』(1996・岩波書店)』▽『ニコラス・ワーク著、荒田洋訳『ロシア農民生活誌 1917―1939』(1985・平凡社)』▽『岡田裕之著『ソヴェト的生産様式の成立――スターリン体制の政治経済学的分析』(1991・法政大学出版局)』▽『中山弘正著『ロシア 擬似資本主義の構造』(1993・岩波書店)』▽『木村雅則著『ネップ期国営工業の構造と行動』(1995・御茶の水書房)』▽『奥田央著『ヴォルガの革命』(1996・東京大学出版会)』▽『梶川伸一著『飢餓の革命』(1997・名古屋大学出版会)』▽『山内昌之著『スルタン・ガリエフの夢――イスラム世界とロシア革命』(1986・東京大学出版会)』▽『渓内謙他編『スターリン後のソ連社会』(1987・木鐸社)』▽『中井一夫著『ソヴェト民族政策史――ウクライナ 1917―1945』(1988・御茶の水書房)』▽『高橋清治著『民族の問題とペレストロイカ』(1990・平凡社)』▽『ヘドリック・スミス著、飯田健一監訳『新ロシア人 上下』(1991・日本放送出版協会)』▽『塩川伸明著『ソヴィエト社会政策史研究』(1991・東京大学出版会)』▽『エレーヌ・カレール=ダンコース著、山辺雅彦訳『民族の栄光――ソビエト帝国の終焉 上下』(1991・藤原書店)』▽『ボクダン・ナハイロ他著、高尾千律子他訳『ソ連邦民族・文化問題の全史』(1992・明石書店)』▽『木村英亮著『スターリン民族政策の研究』(1993・有信堂)』▽『ナーディア・デューク他著、李守他訳『ロシア・ナショナリズムと隠されていた諸民族』(1995・明石書店)』▽『ソルジェニーツィン著、染谷茂他訳『仔牛が樫の木に角突いた――ソルジェニーツィン自伝』(1976・新潮社)』▽『J・E・ボウルト編著、川端香男里他訳『ロシア・アヴァンギャルド芸術――理論と批評 1902―34年』(1988・岩波書店)』▽『沼野充義著『永遠の一駅手前――現代ロシア文学案内』(1989・作品社)』▽『アンドレイ・サハロフ著、金子不二夫他訳『サハロフ回想録 上下』(1990・読売新聞社)』▽『亀山郁夫著『終末と革命のロシア・ルネサンス』(1993・岩波書店)』▽『袴田茂樹著『文化のリアリティー 日本・ロシア知識人 深層の精神世界』(1995・筑摩書房)』▽『水野忠夫著『囚われのロシア文学――ソヴェト政権下の文芸活動』(中公新書)』▽『原暉之著『シベリア出兵――革命と干渉 1917―1922』(1989・筑摩書房)』▽『和田春樹著『北方領土問題を考える』(1990・岩波書店)』▽『ロシア史研究会編『日露200年――隣国ロシアとの交流史』(1993・彩流社)』▽『ボリス・スラヴィンスキー著、加藤幸廣訳『千島占領――1945年夏』(1993・共同通信社)』▽『原暉之他編『スラヴと日本』(1995・弘文堂)』▽『中村喜和他編『ロシア文化と日本――明治・大正期の文化交流』(1995・彩流社)』▽『ボリス・スラヴィンスキー著、江沢和弘訳『日ソ中立条約』(1996・岩波書店)』
改訂新版 世界大百科事典 「ソビエト連邦」の意味・わかりやすい解説
ソビエト連邦 (ソビエトれんぽう)
Union of Soviet Socialist Republics
ユーラシア大陸の北部,ロシアの地に存在した歴史上初めて誕生し,終焉した社会主義体制の国家である。その国土は広大で,北極海をはさんで対峙(たいじ)する資本主義・民主主義の国アメリカ合衆国と対抗し,現代の世界政治に圧倒的な影響力をもった。なお,この国の1917年以前の歴史,文化については〈ロシア〉〈ロシア帝国〉,また1991年以後の国家の状況については〈ロシア連邦〉〈独立国家共同体〉などの項を参照されたい。
名称
〈ソビエト〉とはロシア語で〈会議〉の意味であるが,1917年の二月革命で各地に〈労働者・兵士代表ソビエト〉,〈農民ソビエト〉が生まれ,それらを母体に,十月革命後,ロシア,ウクライナ,白ロシア(ベロルシア)の三つのソビエト社会主義共和国が成立した。これらのソビエト共和国が1922年にザカフカス社会主義連邦ソビエト共和国を加えて同盟条約を結び,国家の同盟,連合Soyuzとして一つの国家をつくったのである。したがって,正確にはソビエト社会主義共和国連邦ではなく,ソビエト社会主義共和国同盟ないし連合というべきである。日本では第2次大戦前より〈ソ聯邦〉という訳語が用いられており,戦後一時期〈ソ同盟〉と称すべきだと強い主張がなされたが,結局慣用の力で,〈ソ連邦〉が定着するにいたった。
注目されることは,この名称には,歴史的・地理的・民族的呼称をまったく含んでいなかったことである。成立時の人々の考えでは,革命が拡大し,新しいソビエト共和国が出現し,同盟加入を求めてくれば,限りなく拡大していけるものと想定されていたのであろう。しかし,その後の現実では,ソ連邦は旧ロシア帝国の版図以上には拡大されなかった。したがって,ソ連という言葉はロシアという言葉と結びつけられて考えられるのは自然であるが,本来のソ連邦成立の原理からすれば,ロシアはソ連の一部にすぎない。
執筆者:和田 春樹
自然
ソビエト連邦が1991年末に崩壊し,15の連邦構成共和国はそれぞれ独立したため,現在は旧ソ連の領域の4分の3を占めるロシア連邦と,ウクライナ,ベラルーシ(旧白ロシア),モルドバ(旧モルダビア),バルト3国(エストニア,ラトビア,リトアニア),カフカス3国(グルジア,アルメニア,アゼルバイジャン),中央アジア5国(ウズベキスタン(旧ウズベク),カザフスタン(旧カザフ),キルギスタン(旧キルギス。ただし現在の国名正称はキルギス共和国),タジキスタン(旧タジク),トルクメニスタン(旧トルクメン))の14共和国に分かれている。ここでは旧ソ連全域を概観する。
位置,領域
ソ連邦はユーラシア北部を緯線方向(東西)に長く広い国土をもっていた。総面積2240万km2は地球陸地の6分の1弱を占め,中国とアメリカ合衆国を合わせた面積より大きく,ソ連を除くヨーロッパの4.5倍にあたった(ソ連崩壊後のロシア連邦の面積はソ連の76%に当たる1707km2)。島嶼(とうしよ)を除くと,ソ連はタイミル半島のチェリュスキン岬からトルクメン(現トルクメニスタン)共和国クシカ市にわたって南北約4000kmに延びていた。東西の長さは約1万km前後で,西端はカリーニングラード州グダンスク湾の砂嘴(東経19°38′),東端は大陸部ではベーリング海峡に面するデジニョフ岬,島嶼部ではベーリング海峡ラトマノフ島(西経169°2′)であった。したがって理論上は11時間の時差があるが,実用上は最東端部の2時間分の経度を同じ時間帯に組み入れているので10時間となる。GMT(グリニジ標準時)正午はモスクワ15時,ハバロフスク22時(経度の上ではほぼ日本と同じ時間帯にあるが,日本標準時より1時間進んでいる),チュコート半島で翌日午前0時である。このほか,ソ連は北極海上の多くの島を領有していた。極東部では日本とのいわゆる〈北方領土〉問題(後述の[日ソ関係]を参照),中国との国境でもいくつかの地点で境界問題があったが,これらはロシア連邦に引きつがれた。
ソ連は12ヵ国に接する長い国境線約2万km(ロシア連邦では14ヵ国,1万9900km)のほか,北極海に面する約4万kmの海岸線をもっていた。北極中心の正距方位図法を見れば一目瞭然であるが,ソ連の北極海諸島とカナダの北極海諸島の最短距離は約1500kmであり,またソ連と北アメリカ大陸は北極海を隔てて向き合っていたという認識も必要であろう。
地形
国土の南縁から南寄りにかけて顕著な山脈が連なる。カルパチ,クリム(クリミア),カフカス,コペトダグ(コッペダーク),パミール,天山,アルタイ,サヤンなどが西から東へ連なり,東シベリアより東方は全体に山がちである。このほか,国土の中央西寄りに南北に走るウラル山脈が孤立する。とくに隆起エネルギーの大きいのは天山からパミールにかけてであり,ソ連の最高点である天山のコムニズム峰(7495m),これに次ぐ高峰ポベーダ(勝利)峰(7439m),レーニン峰(7134m)もこの近辺にある。なおカムチャツカ半島とその付近,中央アジア南部の山岳地方,ザカフカス地方などは地震が多い地方である。
ソ連の国土の一つの特色は,広大な低地が分布することであった。ソ連のヨーロッパ部は東ヨーロッパ低地(ロシア平原)であり,ウラル山脈(二つのプレートの衝突により形成されたという説もある)を除けば,シベリアのエニセイ川まで続く西シベリア低地と合わさって世界第一の広大な低地となる。西シベリア低地南方にもわずかな高まり(標高200mに満たない分水界で北極海と内陸との流域を分ける)を隔ててトゥラン低地があって,カスピ海東岸からカラクム,キジルクムの砂漠と〈ジュンガリアの門〉を経て中国(新疆ウイグル自治区)へと続く。これらの大きな平野は長大な河川の流路となり,シベリアでは北極海に注ぐ源流からの長さ5000km前後のオビ川,エニセイ川,レナ川,東へ注ぐアムール川(黒竜江)がある。ヨーロッパ部では3000km級のボルガ川,ドニエプル川があり,中央アジアではアム・ダリヤ,シル・ダリヤの長流がある。いずれも高峻な山地を駆け下りる短い上流(ボルガ川,ドニエプル川の源流は丘陵である)に次いで,勾配の緩い中流と落差のきわめて小さい下流がひじょうな長さをもってこれに続く。たとえばシベリアでは,オビ川やエニセイ川はシベリア鉄道との交点から河口までの3000km以上は,落差が約100mしかない。
大河川の中・下流では河川の曲流と三日月湖,河跡湖を含む湿地が流れに沿って広く分布し,春には大はんらんを起こす。オビ川中流のバシュガン湿原では日本の面積ほどの一時的な浅い湖が出現し,アム・ダリヤでは春の洪水を利用して綿作地の土壌の塩ぬきを行う。また大河川の最下流部では長大な三角州が形成される。これらの性質はヨーロッパ部の大河川でも,規模は多少小さいが同様である。河川流量の年間配分もきわめて不均等で,年間流量の半ばまでが春~初夏の3ヵ月に流れ去り,残り9ヵ月は渇水期となり,喫水の深い大型船は航行にも支障がおこる。ボルガ川とドニエプル川の全域,オビ川とエニセイ川の上流などでいわゆる〈多目的ダム〉が次々と構築されている一つの理由は,電源開発のほか,洪水制御,水運の改善にあることも了解できるであろう。
現在の地表は,第四紀の氷期によって大きな影響を受けた。氷河に覆われた地域ではもちろんのこと,氷河に覆われなかった南方地域においても,周氷河地形や気候変化の影響を大きく受けている。最も広く氷河に覆われたのは第四紀のドニエプル氷期(西ヨーロッパのミンデル~リス氷期に対応し,大陸氷はキエフ付近まで南下)である。現在の地表に深く爪跡を残しているのはバルダイ氷期(ウルム氷期に相当)で,モスクワ北方バルダイ丘陵でとどまった。それより北では湿地,湖沼が多く,迷子石や終堆石堤が残され,土壌はやせ,開拓に多大の努力を要する。
鉱物資源
石炭,石油,天然ガスなどのエネルギー資源,鉄,マンガン,カリ塩,非鉄金属,アスベスト(石綿)などは世界有数の埋蔵量を誇っていた。国土が広大であることから当然でもあるが,問題はそれら天然資源の賦存(ふそん)あるいは分布状態にあった。次々と発見される資源は,当然のことながら人跡未踏のザバイカルの山地(たとえばウドカンの銅鉱石)や人口密度1人/km2以下のレナ川流域(たとえばレナ炭田)などのように,豊かな埋蔵であっても,それをどのようにして工業原料,エネルギー,労働力と結びつけるかという,いわゆる工業立地問題を解決しなければならなかった。航路や鉄道の改良と延長,長距離超高圧送電(通常600kV),流体燃料のパイプ輸送,労働力の東部への移動奨励などは,天然資源の賦存の不均等性是正に関連する技術あるいは政策とみてもよかった。
天然資源の賦存を概観すると次のようであった。石油:カフカス,ボルガ・ウラル,ヨーロッパ部の北部,西シベリア(チュメニ),中央アジア,サハリン(北樺太)などに産する。石炭:ドネツ(ドンバス),西シベリア(クズネツク),ウラル北部(ペチョラ),カザフスタン(カラガンダ),東シベリア(カンスク・アチンスク,ツングース,レナ,ヤクート南部)。鉄鉱石:ヨーロッパ部(クリボイ・ログ,クルスク付近),ウラル,東シベリア(アンガラ・イリムスク鉄鉱床,アルダン地方)など。アルミ原鉱(ボーキサイトのほか,蛍石,カスミ石などを含む):北ウラル,コラ半島,シベリアの各地,ザカフカスなど。銅:ウラル東麓,カザフスタン(バルハシ湖北西岸),ザバイカル(ウドカン)など。ニッケルとコバルト:北シベリア(ノリリスク),コラ半島,アルタイ東方(トゥバ自治共和国)など。タングステンとモリブデン:北カフカス(エリブルス北方渓谷),中央アジア,極東地方など。ダイヤモンド:東シベリアのヤクート地方。カリ塩:西部ウラル(ペルミ地方),白ロシア共和国。地域によってエネルギー資源に乏しい場合には,地表を覆う無尽蔵の(しかしカロリーは石炭の1/2以下しかない)泥炭を燃料とする小規模火力発電所が稼働していた。塵芥を燃料として電力と熱水を都市に供給する〈熱供給センター〉も都市の郊外に多数建設されていた。
気候
ソ連の気候を一言でいうなら,冷涼な大陸性気候が支配的で,逆にいえば広大な国土面積のわりには気候は単純である。一般にソ連では冷涼な短い夏と寒く長い冬,その間に短い春と秋が入る。広くはないが,大西洋に近いヨーロッパ部の北西部(たとえばレニングラード州)と黒海沿岸部などでは湿潤な海洋性気候,太平洋に近接した沿海州などではモンスーン気候がみられ,黒海東岸周辺では小面積の亜熱帯気候地域がある。高峻な山脈は国土の南縁にあり,ソ連の気候に大きな影響をもたない。ウラル山脈が気候に与える影響も小さい。
ソ連の気候の大きな特色の一つは,冬の強大なシベリア気団(高気圧)の存在で,これはソ連のほとんど全土の気候を支配する。シベリア気団は寒冷でその中心はバイカル地方からモンゴル高原上空にあり,最も発達した場合の気圧は1040hPaに達する。真冬には1020hPa等圧線はシベリア全土と,ソ連のヨーロッパ部のうち北西部を除く大半を覆う。この気団の移動(日本では〈吹出し〉という)に起因する季節風は,東は東アジア,西はヨーロッパに,ときには地中海地方に影響をもつ。シベリア気団の支配下にある地方では,そしてとくに中心部では極寒,晴天が続き,雪は少ない。ソ連のヨーロッパ部の一部では,大西洋から東進する低気圧との間に前線を生じ,曇天と降水をもたらす。天気は悪いが地表の放射冷却が少なく,寒さはそれほど厳しくはない。1月の平均気温はほとんどソ連全土にわたり0℃以下で,0℃を超えるのはクリミア半島南岸,黒海沿岸,ザカフカスの一部などわずかな地域しかない(これらはソ連解体後のロシア連邦からは外れた地域が多い)。海洋性気候の影響下にあるソ連ヨーロッパ部の北西部では,1月の平均気温は0℃以下でもわりあい暖かく,レニングラード(現サンクト・ペテルブルグ。1月の平均気温-8℃)はずっと南にあるモスクワより2~3℃も暖かく,内陸部のアストラハン(カスピ海北岸)とほとんど同じである。1月の等温線は,ヨーロッパ部の北西部では,緯線と平行せず,むしろ経線と平行するように描かれるのが大きな特色で,レニングラード港は不凍港(実際には厳寒時には短期間結氷する)といわれるのである。
夏にはシベリア気団は消失し,逆に低圧部ができる。これに向かって西では大西洋から,東では太平洋から海洋性の気団が進入してくる。西からの湿気を含んだ大気は途中で湿気を失い,シベリアへは高温乾燥気団として到達するから,シベリアの夏は晴れて雨が少ない。太平洋からは夏のモンスーンとして知られる南東風が内陸部に吹きこみ,沿海州は冷涼で多湿の気候となる。ヨーロッパ部の南部はアゾレス高気圧から東へ張り出す高圧部に入り,晴天・酷暑の夏を迎え,半砂漠や砂漠が広く分布する一因をつくる。夏と冬の間には短い春と秋があるが,モスクワ地方ではおだやかで比較的長い〈黄金の秋〉を楽しむことができる。
自然帯
ソ連の国土は急峻な山脈が南方に偏在し,大半が起伏の影響を受けることが少ないため,北から南へ,東西に長い数条の自然帯が識別される。もともと,気候,土壌,植物,動物の諸相は一地域では互いに密接な相互関連をもっており,この考えはとくにロシア・ソ連の自然科学の中で発展して〈自然帯〉の概念となった。数条の自然帯は,永久氷雪帯を除くと次のようになる。
(1)ツンドラ 北極海上の島嶼の南部,北極海岸に沿う大陸部に主として分布し,東部の山地では山岳性のツンドラとなり,南方へ張り出す。コケ・地衣類とわずかの低木が特徴であり,これは北方の極地ツンドラでは前2者,南方の低木ツンドラでは後者が多くなる。通常,年間降水量は300mm以下であるから,気温が高ければ当然砂漠になるが,ここは過湿地帯で水たまりも多い。夏季には日照時間が長く,地下1m程度までは凍土が融解するが,その下は地下300~400mまで凍結したままであるから,融水の逃げ道がないためである。ツンドラ帯と次の森林帯との間に広大な漸移帯があり,背の低い細いカバノキ,マツ(シベリアではカラマツも含む)などが主体となる。この部分は広いので,レソ・ツンドラ(森林凍土混合帯)と呼び,独立の自然帯とすることも可能である。
(2)タイガ ソ連の自然帯の中で最も面積の広いのはこの部分であった。年間降水量は300~600mmほどで,いずれの自然帯より多雨である。冷帯の植生の特徴として,少数の種が大面積を占める(主としてトウヒ,マツ,カラマツ,モミ属からなる)。針葉樹のタイガ(暗いタイガまたは黒いタイガ)が広大な面積に分布するが,南にゆくと針葉・広葉混合林,次いで面積は狭いが広葉樹林が現れる。カバノキ,ヤマナラシ,オオバボダイジュ,トネリコ,ニレ,ナラのような広葉樹のタイガ(明るいタイガまたは白いタイガ)が多くなる。地域的にはさらに西シベリア以西の西タイガ(樹種が多い),東シベリア以東の東タイガ(カラマツが優勢となる),極東地方のタイガ(カエデ,カシワ,ドロヤナギ,トネリコなどの樹種からなる)など,いくつかの地域的性格がみられる。土壌はポドゾルが一般的で,土地の生産力は低く,所々に湿原や湖沼が分布する。この地帯は毛皮獣,狩猟獣(オオジカ,ヒグマ,キツネ,テン,リスなど)の生息地として知られる。農牧地とするためには,排水,酸性土壌の矯正,有機質肥料の投下など,長期にわたる土壌改良が不可欠である。広葉樹のタイガとその南に続くステップとの間は,土壌の分類の上ではいわゆる黒土帯であり,ウクライナから南シベリアを幅200~300kmで横断し,東シベリアから中国東北地方,沿海州に至る。モンゴル高原の北の縁辺部にも黒土帯は点在する。シベリア鉄道の大部分は,おおまかにいえば黒土帯に入植した人々の農村集落を連ねて建設されたということもできる。
(3)ステップ タイガから南下して,降水量が少なくなり(年間300~400mm),乾燥が強くなると,カシワやナラなどの森の間に草原が広がり(この景観をロシア人はポーリェpoleと呼ぶ),ついには草原となる。短い春に野一面にスイセン,アヤメ,ケシなどの花が次々に咲くステップ,イネ科(ハネガヤ,ウシノケグサなど)を主としたステップなどに分かれるが,南に下るとヨモギを主とする単調な草原となり,さらに南下すると裸地がまじり,幅広い漸移帯(半砂漠として一つの帯を設ける場合もある)を経て最も乾燥の激しい砂漠となる。現在ヨーロッパ部の黒色土(チェルノーゼム)ないし栗色土からなるステップは,農業適地として長い歴史の間にほぼ開拓されてしまったか,もとの植生の形をとどめぬまでに人手(火入れなどを含む)が加わっている。良好な農牧地とするためには灌漑が必要な部分も多く,河川から用水を引き(たとえば南ウクライナ・北クリミア運河),溜池を掘るなどのことが行われている。
(4)砂漠 年降水量は150mm以下で,春に大半が降る。植生は貧しく,カラクム,キジルクムなど中央アジアの砂漠ではほとんど植生を欠く部分もある。中緯度に位置する砂漠であるから,冬には寒冷になり,雪も降る。アラル海北半は結氷する。
(5)その他の自然帯 黒海北東岸から東岸にかけて,小面積だが北国のソ連としては重要な亜熱帯性森林(日本の概念では暖帯林と記した方がよい),山地の山岳ステップ,高緯度の山地の山岳ツンドラなどがみられる。また,高い山岳地帯では低地のステップ,次いで森林帯,ステップ,高山植物帯などの自然帯の垂直変化がよく観察される。
執筆者:渡辺 一夫
住民,言語,宗教
住民
人口2億8888万(1990)のソ連邦は多民族国家であり,民族数は100以上に上った(ロシア連邦になった後でも,多民族性には変りない)。大は総人口の52%(1979年センサスによる。以下同じ)を占めて全土にわたって分布するロシア人(1億3739万)から,小はネギダール族(満州・ツングース族に属し,ハバロフスク地方に住む)のように人口500しかない少数民族まで,きわめて多様であった(表1)。
ロシア人と同系の東スラブ民族に入るウクライナ人と白ロシア(ベロルシア,現ベラルーシ)人は人口数でそれぞれ第2位(4234万),第4位(946万)を占め,ロシア人と合わせて総人口の72%に達していた。
人口数第3位の民族は,中央アジアに住むチュルク諸語に属する言語をもつウズベク人であった。中央アジアの主要民族はそのほかに,ウズベク人と同系のカザフ人,トルクメン人,キルギス人,イラン語系の言語をもつタジク人であった。上記5民族の総人口はソ連全体の9.8%であるが,人口増加率がきわめて高いことが特徴的である。ソ連全体では1970-79年の人口増加率は8.4%で,そのうちスラブ系3民族は5.8%であるのに対して,上記5民族は31.8%に達していた。この地方には漢民族系でイスラム教徒であるドゥンガンやウイグル人,また朝鮮人(大部分は1937年に極東地方から強制移住させられた)などの民族もいる。
チュルク諸語系の民族はソ連に20民族あるといわれるが,そのおもなものは上記のほかに,ボルガ中流,南ウラルのタタール人,チュバシ人,バシキール人,南シベリアのアルタイ人,トゥバ人,ハカス人,東シベリアのヤクート人,カフカス地方のアゼルバイジャン人,ノガイ人,カラチャイ人,バルカル人などである。
ザカフカス地方の主要民族は上記のアゼルバイジャン人と,古い文化をもつアルメニア人,グルジア人であるが,言語系統も文字も伝統宗教も異にしている。カフカス山中から北麓にかけては,グルジア語と同系のカフカス諸語の言語をもつカバルダ人,イングーシ人,アディゲ人,チェチェン人が居住し,山脈の南と北に分かれて,イラン系のオセット人の集団がある。面積5万km2,人口165万のダゲスタン地方は,主要民族だけで10,言語は30を数えることのできる,世界でもきわめて特異な地域である。
ヨーロッパ・ロシア北西部から東ウラル地方,および西シベリア北部にかけてフィン・ウゴル語派に属する言語をもつ民族がいる。主要なものは西からエストニア人,カレリア人,コミ人,マリ人,モルドバ(モルドビン)人,ウドムルト人などフィン語系の民族と,西シベリアのハンティ人,マンシ人,それにネネツ人のウゴル語系の民族である。
モンゴル系の民族には,バイカル湖の近くに住むブリヤート人と,ボルガ下流に住むカルムイク人(カルミク人)がいる。
シベリア・極東のタイガ地帯,ツンドラ地帯には,主として漁労,狩猟(毛皮獣,海獣など),トナカイ飼育に従事している民族が多く住んでいる。上記のハンティ,マンシ,ネネツもその一部であるが,大部分はツングース語系諸族と旧シベリア諸族(パレオアジアート,古アジア諸族とも呼ばれる)である。前者には西シベリアからオホーツク海沿岸に分布するエベンキ族,アムール川下流,サハリン,沿海州に分布するエベン族,ナナイ族,ウリチ族,ウイルタ族(旧称オロッコ族),オロチ族などの民族が属し,後者にはコリヤーク族,チュクチ族,イテリメン族(旧称カムチャダール族),ニブヒ族(旧称ギリヤーク族),ユカギール族,ケート族などの民族が属する。
インド・ヨーロッパ語族に属する言語をもつ民族には,前記のロシア人,ウクライナ人,白ロシア人(ベラルーシ人)のほかに,バルト海沿岸にリトアニア人とラトビア人,ウクライナの南に,ルーマニア人と言語・文化の面で近いモルダビア(モルドバ)人がいる。また極東地方にはユダヤ人もいる。
なおユダヤ人はソ連で人口が減少している例外的な民族(1970年から27万人減)で,その原因は国外移住である。出国理由の社会的背景は,民族的偏見のきわめて少ないソ連人のなかに例外的に根強く残っているユダヤ人に対する伝統的な偏見である。ユダヤ人自治州が,ユダヤ人口の多いウクライナ,白ロシア,リトアニアではなく,極東のハバロフスク州に1934年に設置されたのも,その反映といえよう。
言語
ソ連ほど多種多様な言語をもつ国はなかった。民族区分は主として言語によっているから,民族の数だけ言語があるということもできる。この多数の民族間の共通語はロシア語である。1979年の時点でロシア語を母語とする人口は1億5350万,そのうち1630万が非ロシア人であり,そのほか母語以外にロシア語を自由に使える人が6130万いた。ロシア語がソ連の共通語になったのは,相対的に高いロシア文化の担い手であるロシア人が,支配民族としてロシア全土に分布していたという帝政ロシアの文化状況を,ソ連が受け継いだからである。大部分の非ロシア民族にとっては,自民族の発展を図るにはロシア人の技術・文化を媒介とせざるをえなかったし,個人のレベルでも,エリート層に入るためにはロシア語を自由に使えることが必要不可欠であった。この個人レベルでの問題は,以後も変わっていない。こうした状況が民族的自負心を傷つけ,ロシア人に対する潜在的反感を育てている面があったといえる。
ソ連の法律は15の連邦構成共和国の言語で公布され,裁判では連邦構成共和国,自治共和国,自治州,自治管区の言語(計53言語)か,もしくはその地区の多数住民が用いる言語で発言する権利が保障されていた。また母語で教育を受ける権利も法律で保障されており,57言語(1978)で小・中・高校の教育が行われていた。ただし,裁判と教育における母語使用の権利は,必ずしも確実に遵守されてはいなかった。
120を超えるソ連内の言語(言語学者の間でも,方言と独立した言語との認定の基準に違いがあるため,この数は学者により,かなりの差がみられる)のうち,文章語をもつものは65であった。古くから文章語をもつ言語のうち,エストニア語,ラトビア語,リトアニア語はラテン文字を,グルジア語,アルメニア語は独自の文字をもっている。ソ連のユダヤ人の話すイディッシュ語にも独自の文字があるが,ロシア語を母語とする者が多く,またカフカスや中央アジアに住む少数のユダヤ人は現地の言語を母語としている。
イスラム文化圏に入る民族の文章語には,かつてはアラビア文字が使われていたが,ソビエト政権下で文字改革が行われて,ロシア文字を用いるようになった。ブリヤート語,カルムイク語でかつて用いたモンゴル文字もロシア文字にかわった。十月革命後に初めて文章語ができた言語が多いが,これらはロシア文字を用いている。シベリア・極東に住む少数民族語は,革命後,1930年代初めにはラテン文字による北方統一文字が試みられたが,1937年以降ロシア文字に統一された。
宗教
ソ連では宗教統計が発表されなかったので詳細は不明であるが,最大の宗派は,帝政時代に国教であったロシア正教会である。ロシア正教はロシア人,ウクライナ人,白ロシア人の間だけでなく,モルダビア(モルドバ)人,チュバシ人,ウドムルト人,モルドバ(モルドビン)人,マリ人,コミ人,ヤクート人などの間にも広く普及していた。
同じ東方正教会でもグルジアには別個のグルジア正教会があり,アルメニアには東方諸教会系のアルメニア教会がある。カトリックはリトアニアに,ルター派はエストニアとラトビアに多かった。ソ連の西部地方に多数いたポーランド人は主としてカトリック信者であり,カザフスタン,西シベリア南部に多いドイツ人はルター派信者であった。
ソ連で第2の宗教はイスラムであった。そのうちシーア派はアゼルバイジャンに普及しているだけで,南ウラルのバシキール自治共和国(ソ連解体後はバシコルトスタン共和国)からカザフスタン,中央アジアにはスンナ派が普及している。カフカスのダゲスタン地方の住民もスンナ派信徒である。[住民]の章で述べたように,中央アジアの主要5民族の人口増加率が高く,さらに,アゼルバイジャン人の増加率も25%と高いため,イスラム教徒の比重はしだいに高くなっていたし,絶対数も増加していると推測している学者もいた。
仏教(ラマ教)はブリヤート人,カルムイク人,トゥバ人の間に信者をもっている。そのほか,ユダヤ人のなかにユダヤ教が,シベリア・極東の少数民族のなかにはシャマニズムが残っている。なおソ連における宗教のあり方については,[社会]の章の〈教会〉を参照されたい。
執筆者:米川 哲夫
歴史
ソ連は,第1次世界大戦のさなかに,この戦争に対する民衆の反発を基礎にして,歴史上初めて社会主義者が全国的に権力を掌握し,総力戦下の統制経済の経験と,マルクス主義的理論に基づき資本主義社会とは原理的に異なった社会の実現を目ざした国である。この国は長期にわたり国際共産主義運動の本拠であった。そういうものとしてこの国の歴史が世界史に与えた衝撃力と影響は巨大であった。この国の歴史は,また後進国,低開発国が特定の方式で急速な工業化を成し遂げた一つの典型であるともみることができる。さらに,広大な国土に強力な国家が出現し,周辺に多くの同盟国を得て,世界第2の強国となり,その核武装によって,アメリカと並んで,人類の運命を左右しかねない存在となった。
革命と内乱
十月革命は,ツァーリ権力に代わったブルジョアジーと穏健社会主義者の連合政権である臨時政府の行詰りの結果起こった。平和と土地と民族自治を求める労働者,兵士,農民,被圧迫民族の声の高まりを背景に,レーニンのボリシェビキは,首都ペトログラード(現,サンクト・ペテルブルグ),北西部,中部の労兵ソビエトの支持に基づいて臨時政府を打倒し,政権を掌握した。レーニンは,世界戦争から救われるために,これを生み出した資本主義体制を打倒せねばならないとして,ドイツに出現した総力戦遂行の経済体制を革命権力が実行することによって,社会主義へ向かおうとした。新政権は土地は全人民のものと宣言して,農民たちの志向に承認を与えたが,憲法制定会議を解散して,ソビエト権力の全国化を目ざし,その過程で早々にウクライナ民族主義と衝突した。人々があれほど熱望した平和を実現する努力も実を結ばなかった。即時停戦に応じたのはドイツだけで,ドイツとの講和をめぐる対立から,ようやくにしてできた左派エス・エル党との連立も解消されてしまった。
ドイツとの過酷な講和で得たのはつかのまの安らぎにすぎなかった。農民からの強制的な穀物徴集をめぐって1918夏には左派エス・エル党と武力衝突にいたり,そのままチェコ軍団の反乱,反ボリシェビキ諸軍の行動開始,外国干渉軍の侵入を迎え,恐るべき内戦が始まった(シベリア出兵)。レーニン政権は,共産党一党国家となり,すでに実現していた全工業の国有化や穀物独裁などを基礎に〈戦時共産主義〉の経済をとり,徴兵制で赤軍を建設して,内戦に勝ち抜いた。2年7ヵ月の内戦が終わった21年のロシアは,国土の荒廃に加えて,100万人以上の死者を出す深刻な飢饉に見舞われた。しかし,1919年に生まれたコミンテルンを通じて,ヨーロッパとアジアの双方へ革命の影響は広まり,この国は〈全世界の被圧迫者の祖国〉と仰ぎみられるにいたった。
ネップ期
レーニンは内戦時の農民の不満をなだめるために,1921年穀物の割当徴発制に代えて現物税制を採用し,ついには商業の自由を認めるネップ(新経済政策)体制に移行した。ネップのロシアは政治的には一元主義的であったが,社会・経済的には多元主義的な体制といえるだろう。国営企業を拠点に経済の復興を図りながら,農民を説得によって徐々に集団経営へ導くことが目ざされた。非政治的なものであれば,さまざまな社会団体が活動を認められた。
レーニンとスターリンは22年のソ連邦の成立をめぐって意見が対立した。スターリンは初め,各共和国を自治共和国としてロシア共和国に吸収する案すなわち〈自治化〉案を推進し,一方,レーニンは,ロシア共和国を含めて,すべての共和国は新しい〈同盟〉の中に同等の権利をもって加入すべきであるとする〈ソ同盟〉案を出した。その後民族問題の処理でもさらに対立し,レーニンは23年スターリンを党書記長のポストから解任せよとの指示を書くにいたった。その直後レーニンは発作を起こして廃人となり,1年後に死去した。この間スターリンはジノビエフ,カーメネフと協力してトロツキー派を抑え込むことに成功した。次いで一国社会主義論を採ったスターリンとブハーリンは提携して,ジノビエフ,カーメネフ派と争い,27年にはトロツキー派とも組んだこの合同反対派を完全に失脚させた。
この対立の背景には,経済が1926年に第1次大戦前の水準にまで復興し,ネップの漸進主義に対する不満が頭をもたげているという事情もあった。27年にはコミンテルンの路線が中国で行き詰まり,戦争の脅威のうわさが国中をとらえ,穀物の調達危機が発生した。スターリン派は農民に対する強制措置を辞さず,翌28年にはシャフトゥイ事件(ドネツ炭田で破壊工作が行われたとして大ぜいの鉱山技師が逮捕され,公開裁判にかけられた事件)を機に技師・専門家への圧迫に乗り出して,工業化テンポの引上げを進めた。
上からの革命
ついに29年,ブハーリン派は追放され,スターリンの〈上からの革命〉が発動された。その構成要素は,(1)超高度の工業発展五ヵ年計画,(2)全面的集団化,(3)階級戦争としての文化革命,である。これらの目標は青年労働者の熱狂をかき立てつつ,強権的に推し進められた。五ヵ年計画は国の工業化を目ざすと同時に,経済の計画化を目ざすものであった。ソ連はめざましい工業国となり,一元化された国営計画経済が出現した。この中で労使関係観も変化し,労働組合は相対的自立性を失って,準国家機関化した。農業の集団化は共同体的小農経営の改造を目ざして,都市から労働者党員を送り込み,抵抗する農民をクラークとして追放しつつ,一挙に進められた。過程はジグザグであったが,数年間のうちに個人農は姿を消して,準国家機関的な農業生産協同組合コルホーズに組織された。
文化革命は既成の学術・文化権威を攻撃し,学術・文化のボリシェビキ化を図るものであった。31年にこの動きにはストップがかけられたが,青年労働者に対する技術教育の拡大と技術者・学者文化人の,党・国家への無条件服従が生み出された。さらに,〈上からの革命〉によって労働組合以外のさまざまな社会団体も廃止されるか,準国家機関化されるか,あるいは,そのようなものとしての新団体(作家同盟など)が生み出された。こうして,共産党国家の肥大化のもとで,党と国家と社会団体の一体化,国家と社会の一元化は完成し,新しい社会体制が生まれた。34年の第17回党大会は社会主義の〈勝利〉を宣言した。大恐慌に苦しむ資本主義体制下の世界にとって,この体制は人類の未来を示す新しい文明として仰ぎみられた。国内では1932-33年の飢饉の傷跡は深刻であった。34年にかけて緊張緩和の措置がとられたが,その年の12月,新任の党書記キーロフが暗殺され,これが旧反対派の所業とされたことは,暗雲の前ぶれであった(キーロフ暗殺事件)。
スターリン独裁へ
35年のコミンテルン第7回大会は反ファシズム人民戦線の結成を呼びかけた。ナチズムは国際共産主義運動とソビエト国家の凶悪な敵として確定された。このときソ連は人類の希望を担っていた。しかし,スターリンの名が冠された新憲法が〈世界で最も民主的な憲法〉として36年12月に公布される一方で,ジノビエフ,カーメネフら旧反対派の幹部が〈ゲシュタポの手先〉として死刑を宣告される公開裁判が始められた。この動きは37年初めに打ち出されたスターリンの階級闘争激化理論によって加速され,トハチェフスキーら軍幹部の〈陰謀〉が6月に摘発されると,大量テロルの嵐が荒れ狂うことになった。党,政府,企業の幹部がドイツや日本のスパイとして処刑されたり,ラーゲリに送られ,そのあとは,〈上からの革命〉期に教育を受けた若い幹部が埋めた。しかし,軍の受けた打撃は簡単には埋められなかった。テロルの実相は国外へ伝わらず,公開裁判は反ファシズムへのソ連国家の決意を印象づけた。
このテロルを通じて,スターリンの個人独裁が出現し,スターリン主義体制が完成したとみうるが,ここでできたものは〈上からの革命〉期に成立した体制に対する追加的な,第二次的な構造であったと考えるべきである。ともあれ,極度に強力なスターリンの指導の確立があったからこそ,39年8月,一転して,国是ともいうべき反ファシズムの旗を下ろして,ナチス・ドイツとの間に不可侵条約を結ぶことも可能となったのである。スターリンはソ連の国益のためにこの挙に出たのだが,ドイツがポーランドに侵入すると,ポーランド領の東半分を占領し,ドイツとの間に友好境界条約を結んだ。ドイツとの接近から得た最大の獲得物は,混乱した日本との間に日ソ中立条約を40年に結んだことであったろう。この間フィンランドとの戦争で国境地帯を割譲させ,40年には,旧ロシア帝国領であったバルト海沿岸の3国をソ連邦に併合するなど,強引な安全保障策を追求した。しかし,ついに41年6月22日,ナチス・ドイツはソ連を電撃的に奇襲攻撃した。
独ソ戦争
スターリンがこの時点での攻撃を予想せず,また正確な情報をも挑発として退けていたため,不意を打たれたソ連軍は壊滅的打撃を受けて敗走し,ヨーロッパ・ロシアの大半が年末までに占領されてしまった。しかし,ようやくソ連軍は冬将軍にも助けられてモスクワ郊外で敵を撃退した。包囲されたレニングラードはこの冬60万人もの餓死者を出しながら耐えぬいた。42年11月スターリングラード(現,ボルゴグラード)方面で反撃に転じたチュイコフVasilii Ivanovich Chuikov軍はドイツ第六軍を包囲全滅させた。43年8月,クルスクでの戦い(クルスク戦車戦)でドイツ軍との決戦に勝って以後は,ソ連軍は退却するドイツ軍に対する追撃戦に移った。東ヨーロッパを解放して,ドイツ領内に入ったソ連軍は45年4月ベルリンに入城し,5月2日ドイツ軍は降伏した。
〈大祖国戦争〉と呼ばれるこの戦争で,戦闘員・非戦闘員あわせて2700万人がソ連の人口から失われた。国土の荒廃は言語を絶するものがあった。しかし,人々は進んでナチスとの戦いに赴き,敬服すべき勇気を発揮した。このソ連国民の闘いこそ,ナチス・ドイツを打ち破った最も重要な力であった。ドイツに対する勝利ののち,アメリカの求めで,ソ連はヤルタ協定に基づいて,ヨーロッパから軍を東へ送り,8月8日日本に宣戦布告し,満州(中国東北)の関東軍を攻撃した。これによって日本をポツダム宣言受諾に追い込んだのである。
戦後スターリン期
戦後には,領土を拡大し,かつ東ヨーロッパ諸国と北朝鮮を自らの勢力圏に収めたソ連は,アメリカと並ぶ強国として,国際政治に重きをなした。米ソは協力して国際連合を創設したが,やがて激しく対立するにいたり,〈冷戦〉が始まった。国内的には,戦争中自主性を高めた民衆・知識人を再統合し,体制のゆるみを引き締めるため,ジダーノフ批判と呼ばれる,とくに厳しい知識人統制が加えられた。東ヨーロッパではソ連の意に従わないユーゴスラビアをコミンフォルムから除名した。他方,国内の経済の復興はようやく進み,49年にはソ連も原爆を保有するにいたった。中国革命も成功したこの年に,国内には反ユダヤ主義的なコスモポリタニズム批判の波とレニングラード事件が起こされている。50年にスターリンは日本共産党にアメリカ占領軍との対決を命じ,北朝鮮の武力統一戦争(朝鮮戦争)を全面支持したが,どちらも成功するにいたらなかった。
52年に13年半ぶりに開かれた第19回共産党大会で,スターリンは全世界の共産党の代表たちから偉大な指導者とたたえられた。しかし,その偏執狂的な警戒心から政治局員にも疑いをかけ,ついに53年1月ユダヤ人医師団事件を引き起こした。
フルシチョフ期
その緊張の中で,53年3月3日,スターリンは死去した。独裁者の死はソ連史に大きな変化を呼び起こすこととなった。ユダヤ人医師団事件はでっちあげであったと発表されたあと,今度はそれを明らかにしたスターリンの内相ベリヤが打倒され,次いでスターリンの指名した後継者マレンコフ首相が失脚した。党の実権を握ったのは,内戦時に入党した出稼ぎ農民の子フルシチョフであった。彼は農業面の行詰りを大胆に告発して信頼を集め,処女地開墾のキャンペーンを進めた。ユーゴスラビアとの関係を改善するための訪問ののち,56年3月,第20回共産党大会で,スターリンの〈個人崇拝〉のもたらした恐るべき諸結果を暴露する秘密報告を行った。無数の人々が名誉回復されてラーゲリを出た。スターリン批判はハンガリー事件のように東ヨーロッパでの動揺を呼び起こし,それがソ連国内の再引締めを招いた。しかし,スターリン派のモロトフらがフルシチョフ追落しを策して,逆に失脚すると,フルシチョフの地位は盤石のものとなり,58年ブルガーニンから首相の職を取り上げ,党第一書記と兼任するにいたった。
彼は平和共存を唱えて,59年にはアメリカを訪問した。61年には,第22回党大会で,〈全人民国家〉への移行を宣言し(全人民国家論),70年までにアメリカを経済的に追い抜き,80年までに共産主義を基本的に建設するという夢想的な新党綱領を採択させるとともに,第2次スターリン批判を行った。その結果,ソルジェニーツィンという無名の作家のラーゲリ小説が刊行され,大きな衝撃を与えた。こうして1960年代には,革新的で楽観主義の気分が社会の中に横溢した。
しかし,フルシチョフの平和共存政策は中国との厳しい対立を招き,一方,62年10月にはキューバ危機でアメリカから屈辱を被り,おそらく軍部の中心に不信感を生ぜしめたであろう。他方で,農業政策も欠陥を露呈して,フルシチョフの権威を失墜させ,党機構を工業・農業担当に2分割する62年の改革は党の幹部たちから強い反発を招いた。この結果,64年10月,フルシチョフはその部下たちによって抜打ち的に辞職を強いられるにいたった。
ブレジネフ期
フルシチョフに取って代わったのは,ブレジネフ党第一書記とコスイギン首相といった党と政府機構の上層幹部の代表者であった。彼らはスターリンの〈上からの革命〉で上昇し,フルシチョフの〈スターリン批判〉でテロルの恐怖から解放された人々であった。彼らはこれ以上の改革,民主化を好まず,安定的成長の方向に政策を向け直した。安定志向は民衆の要求にも沿うものであったといえる。農業政策の手直しや若干の経済改革が行われ,新年金法や週休2日制などの福祉向上の措置がとられた。民衆は私生活の自由を享受するようになった。他方で68年のチェコスロバキアへの介入を契機として,国内の改革派勢力を解体させ,私生活の枠内の自由で満足している人々以外の〈異論派〉を法によって弾圧した。軍部との関係を改善して,アメリカと対等な軍事力を構築するために軍備の拡張を進め,ついにこれを達成した。同時に,デタント政策を継続し,この面で70年西ドイツとの条約調印を果たした。第三世界に対する政策はむしろ積極化させ,アンゴラなど多くの新興国に援助を与えて,自らの影響下に置いた。ブレジネフは77年にポドゴルヌイNikolai Viktorovich Podgornyi(1903-83)から最高会議幹部会議長(元首)のポストを取り,党書記長と兼任するにいたった。この年,新しい憲法が制定された。
ブレジネフのソ連においてはスターリン的第二次構造の除去に立って,〈上からの革命〉でつくり出された社会体制の成熟が達成されたといえよう。
ところで,70年代には異論派が次々と国外へ追放され,そのサミズダートも国外へ紹介出版された。ユダヤ人の出国は認められ,76年までに13万人が出国した。これらの人々や出版物がソ連社会の現実を西側世界に伝えたことは,ソ連イメージの低下をもたらした。他方で安定は停滞と腐敗をも生んだ。経済成長が鈍化し,改革派が抑圧された結果,閉塞的気分が広まった。アメリカからの穀物輸入は食肉生産の拡大のため,なくてはすまされぬものとなった。腐敗はブレジネフの身内のスキャンダルという形をもとった。国際的には,アメリカ,中国,日本の3国提携に危機感を抱き,対抗的に結んだベトナム,アフガニスタンとの軍事同盟の一角を守ろうと,79年12月,アフガニスタンに軍隊を入れ,親ソ政権の擁立を図ったが,反政府ゲリラとの戦闘は泥沼化した。これを契機として,アメリカとの関係は著しく悪化した。また東ヨーロッパでもポーランドで〈連帯〉運動が起こり,その抑えこみにはかつてないほど苦しめられた。
アンドロポフ期
ブレジネフは82年11月,多くの未解決の問題を残して76歳で死去した。後任となったのは,68歳の国家保安委員会議長アンドロポフYurii Vladimirovich Andropov(1914-84)である。内政も外交もこれからというところで健康を急速に害したアンドロポフは,84年2月死去した。その後継者は彼よりもさらに年上のチェルネンコKonstantin Ustinovich Chernenko(1911-85)となった。結果的には,チェルネンコは,若いゴルバチョフMikhail Sergeevich Gorbachyov(1931- )への期待を高めるだけの役割を演じて,翌年死亡した。
ペレストロイカ期
ペレストロイカ期モスクワ大学法学部出身のゴルバチョフは,85年3月の就任演説で〈グラスノスチ(公開性)〉を強調して注目をひいた。その年の末に早くもレーガン・アメリカ大統領と会見するなど,米ソ関係改善に対する積極的姿勢も際立った特徴であった。86年2月の第27回党大会では,フルシチョフ綱領に代わる新党綱領を採択させたものの,古い思想はなお指導部をしめつけ,経済発展の〈加速化〉戦略の誤りも明らかになりつつあった。ゴルバチョフは4月になって,〈社会生活のあらゆる部面のペレストロイカ(建て直し)〉が必要だと語りはじめ,これが4月26日のチェルノブイリ原発事故ののちに党中央委員会の方針となり,〈革命〉的改革としてのペレストロイカがはじまることとなった。まずグラスノスチが,公開性の拡大から検閲の廃止,自由言論という原意の方向に発展した。86年末にはゴルバチョフはレーガン大統領とのレイキャビーク会談で戦略核半減,戦域核全廃の提案を出して世界を驚かせた。
87年は〈ペレストロイカ元年〉といえる。1月には,ペレストロイカが社会の民主化と不可分であることが宣言され,6月には,企業の独立採算制と自主管理制を導入する経済改革が決定された。12月にゴルバチョフが訪米し,戦域核,INF(中距離核戦力)全廃条約に調印したのは,〈新しい思考〉に基づく外交の最初の勝利であった。89年3月に行われた人民代議員選挙ははじめての自由選挙となり,エリツィンが驚異的な得票を首都で獲得した。5月末から開会された人民代議員大会の完全テレビ中継は国民を熱狂させた。ゴルバチョフは圧倒的な支持で,大統領的な最高会議議長に就任した。なお,この間89年2月にはアフガニスタンからの撤兵も完了した。
90年2月の党中央委員会拡大総会をうけて3月に臨時人民代議員大会が開かれ,共産党の指導的役割という憲法上の規定を削除して複数政党制の導入を決め,大統領制を新設した。初代の大統領には国民の直接選挙ではなく,人民代議員大会でゴルバチョフが選ばれた。
この大統領選出とともに,のびのびとなっていた共和国と地方のレベルの選挙が完全に自由な選挙としておこなわれた。ロシア共和国の選挙で〈民主ロシア〉が大勝し,5月に開会されたロシアの人民代議員大会で,エリツィンが最高会議議長に選ばれた。バルト3国では3月のリトアニアを皮切りに,独立宣言を採択するにいたったが,6月にはロシアの代議員大会も〈主権宣言〉を採択し,ソ連邦はもはやもとのままにはとどまれなくなった。
ソ連邦終焉
ゴルバチョフ書記長に忠実であった党内官僚は強い危機感をもった。8月彼らは休暇中のゴルバチョフを別荘に監禁して,クーデタを断行した(8月クーデタ)。19日副大統領ヤナーエフをキャップにした国家非常事態委員会が設置された。エリツィンのロシア政府はソ連のクーデタ政権に宣戦を布告して,戦いに立ち上がった。クーデタ派はホワイト・ハウスに立てこもったエリツィンらを押しつぶす武力が動員できず,敗北した。
ゴルバチョフは22日にモスクワへ戻ったが,エリツィンに押されて,クーデタに加担するか,闘わなかったソ連共産党を自ら解散するほかなかった。また独立を宣言する各共和国の動きを抑えて,ソ連邦を再建することも不可能になっていた。12月ウクライナが国民投票で独立を宣言すると,エリツィンはロシア,ウクライナ,ベラルーシ3国での独立国家共同体の設置,ソ連解体を決めた協定を結んだ。ゴルバチョフはまきかえそうと抵抗したが,かなわず,91年12月25日,辞任に追い込まれ,ソ連は終焉した。
執筆者:和田 春樹
政治
政治制度
ソ連邦は,1922年に形成され1991年末に崩壊するが,それまでは15の連邦構成共和国(ロシア,ウクライナ,白ロシア,ウズベク,トルクメン,タジク,グルジア,アゼルバイジャン,アルメニア,キルギス,カザフ,モルダビア,リトアニア,ラトビア,エストニア,以上加盟順)からなっていた。各共和国は建て前としては連邦離脱の権利を有する主権国家であり,その主権国家の合意により,ソ連邦が国防,外交,貿易,治安などをほぼ独占的に管轄し,立法,行政,経済の一般指導と単一国家予算の作成を行っていた。実際は事実上の単一国家であって,ソ連邦共産党の集権的構成,経済・文化,言語などの諸政策から各共和国の働きは限定され,むしろソ連邦への一体化,〈ソビエト民族〉への一体化・接近が図られてきた。しかしペレストロイカのもとで民族問題が噴出し,経済的分権化を図ることとも関連して,民族の自主性強化や連邦制の見直しが課題となっていたが,連邦制のあり方をめぐって対立し,1991年末にソ連邦は崩壊した。
制度上,ソ連邦の最高権力機関は当初は最高会議Verkhovnyi Sovet SSSR,1989年からは新設されたソ連邦人民代議員大会であって,ソ連邦にかかわるあらゆる問題を審議した。これは定例,年1回召集され,その選挙は地域別,民族=地域別,および社会団体(ソ連邦共産党,労働組合,科学アカデミー,その他の全国的自主団体など)から各750名ずつ,計2250名からなっていた。選挙は18歳以上の市民による直接秘密投票であるが,89年の選挙から複数候補制が実施された。人民代議員大会は国家権力の常設立法・執行・統制機関として連邦会議と民族会議の2院からなる最高会議(各院271名)を選出したが,これは議会にあたり,年2回3~4ヵ月ずつ会期が続いた。最高会議には幹部会が設けられ,議長,第一副議長のほか,15の共和国の議長が副議長となり,このほか各常設委員会の議長なども加わり,以前の儀礼的なそれより大きな役割を果たすものと考えられた。実際,最高会議には国際問題,国防・安全保障など14の委員会(コミテートkomitet),また両院には四つずつの常任委員会(コミッシヤkomissiya)がつくられていて,法律の起草や計画の立案に役割を果たすものとされた。91年8月のクーデタ後,9月初めの臨時人民代議員大会は,独立に動く各共和国の圧力のなか,臨時の国家評議会等をつくって,自ら解体を宣言した。
また,90年の人民代議員大会で大統領制が新設され,初代大統領にM.ゴルバチョフが選ばれた。もっとも彼は,1991年末のソ連崩壊により,最後の大統領でもあった。大統領は首相・閣僚の任免を提案し,議会を通過した法案を拒否して最高会議に差し戻す権限を持ち,軍の最高司令官で,宣戦布告,非常事態宣言を出せ,対外的には国家元首として外交交渉を主導することになっていた。法律に違反したとき人民代議員大会によってのみ解任される。大統領のもとに大統領会議(閣僚会議のメンバーなどから15人を大統領が任命)と連邦会議(各民族共和国の利害を代表する)が置かれ,政策立案や民族問題にたずさわった。なお,1988年から任期制が導入され,役職者は2期10年を超えることはできなくなった。
権力の分割を図り,〈法治国家〉の理念のもとで司法機関の役割を高めることもゴルバチョフの政治改革の柱であり,憲法監督委員会が人民代議員大会から選ばれることが規定された。検事総長,最高裁判所長官も,最高会議議長の提案で最高会議が選んだ。このほか,大衆による行政・経済への監督と参加をめざす人民統制委員会の議長,国家仲裁本部長も同じ手続きがふまれるものとされた。
人民代議員大会,最高会議が,ごく単純化していえば,国会にあたるとすれば,内閣にあたるのが閣僚会議Sovet Ministrov SSSRであり,これは〈ソ連邦国家権力の最高執行,行政機関〉とされたが,法律の施行のため広範な〈決定および命令〉を発した。選挙後最初の人民代議員大会で,最高会議議長の推薦により,まず首相職にあたるソ連邦閣僚会議議長が選出され,次いで最高会議において閣僚会議議長の提案にもとづいて各閣僚,国家委員会議長を含むリストが決定された。閣僚会議は企業の直接的運営を行う経済官庁を含むため,大きな権限を有し,とくに党中央委員会との合同決定の形態でしばしば重要な経済・行政上の決定を行っていた。しかし実際の運営は,党政治局員を含む15名程度の閣僚会議幹部会がその常設機関として,日常的政策決定にあたった。もっともこれは,革命後の人民委員会議Sovet Narodnykh Komissarov SSSR(1923年7月~46年3月)のように政策決定の中心であることはなく,むしろ党政治局,中央委員会が決定したことを履行する実務機関と考えられた。各閣僚も通常,政治職というより専門技術官僚が多かった。
この下にある各省には,連邦水準にのみ置かれて,全国一律に行政,経済を担う全連邦的省と,各共和国の省を通じて間接に執行を行う連邦的・共和国的省の区別があった。各省が特定の分野ごとに組織されるのに対し,分野を横断して組織されるのが,各種の国家委員会(国家計画委員会,科学技術国家委員会など)であった。この区分は,その後ロシア連邦でも踏襲された。
このように国家機関は,実際はソ連邦共産党,とくにその中央委員会政治局で決定されたことを執行する性格が強かった。憲法上も共産党はソビエト社会の〈政治システム,国家機構……の中核〉であると規定されていた。しかし,90年初めに党と国家とは分離されることになり,国家の党からの自立性が強調された。
しかも党それ自体が一つの政治体制を構成しており,党書記長,政治局・書記局と党大会,中央委員会総会の相互関係は,議院内閣制の下での首相,内閣と国会とに機能的には似ていた。中央委員会機構自体が行政分野ごとに細分化されてきたが,政治改革により一般的政治指導に純化され,部も統合された。党機関がすべてを決定し,国家=行政機関はこれを履行するだけと考えるのも正しくない。
このほか,重要な組織として,全連邦労働組合中央評議会のような労働組合や,全連邦共産主義青年同盟(コムソモール)があり,それぞれ職場,学校などに組織された。しかし,いずれも党の指導下にあって,それぞれ独自の統轄機構,利害を有し,また《トルード》紙をはじめとする宣伝手段を有していた。後者の下にはピオネールという少年・少女の組織もあった。また作家同盟など科学・文化団体,協同組合のような社会団体も,党の監督下にあった。
次に,ソ連邦の地方の政治構造についてごく簡単に触れてみよう。ソ連邦の行政区分では通常,全連邦の下に,構成共和国,地方(クライ),州(オーブラスチ),管区(オークルグ),地区の下級単位があり,そのほか自治共和国や自治州が置かれることもある。ロシア共和国の場合,自治共和国16と自治州5をもっていた。これはその後,ロシア連邦になって21共和国ができ,自治州は一つとなった。また市は通常,州や地区(ライオン)レベルの下にあるが,モスクワやレニングラードのように行政上共和国レベルに従属した例もある。大都市の下には,地区が置かれた。これらの行政単位には,それぞれ会議(ソビエト)が形成されたが,民主集中制の原則が貫かれており,選挙制,報告義務と並んで上級機関の決定に下級機関が服さなければならなかったことは,党の組織と同様である。
ソ連の地方政治においても共和国や州,地区の第一書記をはじめとする党官僚機構が,事実上政策決定の中心にあり,人事,動員や経済の運営に大きな役割を果たしてきた。モスクワやウクライナ,カザフなどの有力地方党書記は,しばしば政治局の有力構成員となった。党機関内部では,組織,工業,農業など各種の利害が代表されるよう構成されていた。それぞれ,ソビエトや官庁,労働組合などと相補的構造をもっていることは中央レベルと同様である。地方ソビエトの経済的権限が拡大し,議長の役割も無視できなかった。また地区のソビエトや党委員会は企業,施設,学校を指導・統制し,社会主義競争の促進や決定の履行,動員に関心を払った。さらに地方党組織が,KGBや裁判にも統制を行うことは中央と同様であった。党とソビエトの末端機関,大衆組織は,人々の教化や参加の回路として重要な役割を果たしていた。とくに党の初級組織は,企業,施設,学校などにつくられ,そこでの任務の遂行を監督し,人事などをコントロールしていた。しかし,〈法治国家〉の理念により,ペレストロイカ以後は党も〈法の下の平等〉の扱いを受けるようになった。
政治過程
ソ連邦の政治構造は,とくにスターリン体制以後,共産党と国家が一体化し,各機構が絡みあった体系をなしてきた。そこにおける政策決定でもまた,党中央委員会機構をはじめとする党官僚制の役割が大きかった。有給・専任の党職員を組織する党中央委員会機構,とくに書記局を背景に,党書記長は,党の内閣ともいうべき政治局でも中心に位置した。政治局は,この党中央委員会書記局の関係者をはじめ,モスクワ,ウクライナといった地方党組織の代表者,および閣僚会議議長や,軍事・外交を含む国家行政の指導者など十数名の政治局員,およびそれに準ずる候補とから成っていた。ソ連の最高の政策決定はここで行われるのが通常であった。もっとも規約上は最高機関である党大会や,党中央委員会総会が,政治局の対立を解決した例も,1957年の反党事件やフルシチョフの失脚のように皆無ではなかった。
政治局は通常は週に1回程度開かれ,党と政府の重要議題を審議したが,その内容は外交上の決定から,靴の生産,小説の公表の許可にまで及んだ。また,特定の問題については政治局の下に特別の小委員会が置かれることもあった。政治局には名目的な議長職はなかったが,党の書記長が大きな発言力を有した。党に対して独裁的支配を行ったスターリンの死後には集団指導体制が強調され,フルシチョフ(当時は第一書記)の退陣後は,書記長と閣僚会議議長との兼職が行われなくなった。その後新たに党の書記長が最高会議幹部会議長を兼務する形がブレジネフ時代に現れた。ゴルバチョフ時代には当初このポストは分離していたが,1989年新設の最高会議議長(元首)に,90年にはやはり新設の大統領(元首)に党書記長兼務で就任した。
共産党は1921年以来分派・グループを禁じ,スターリン時代には反対派も存在しなくなったこともあって,政治局での討論内容や意見・利害の対立は必ずしも判然とはしなかった。それでもフルシチョフ時代には中央委員会総会の議事が公開され,アンドロポフ書記長になって政治局の議題が公表されるようになった。分派の禁止は政策をめぐる対立を表面化させない効果をもつが,かわって党,国家での主要人事が党機関の有するノメンクラトゥーラ(指名職名表)によって上から行われ,党内部での選挙制は意味をもたないため,登用を介して非定型な人間関係ができやすかった。ソ連で指導者の〈個人崇拝〉や縁故主義,主観主義がときに問題化した理由である。
しかし党中央委員会内部には,重工業,イデオロギー,軍事,外交といったように,強い制度的利害が表出されている分野も存在した。これらの利害関係が固定化すると一種の利益団体として機能した。また外交,法律,経済など専門家の比重が高まり,政策決定が制度化,合理化される傾向もみられた。したがって〈党の指導的役割〉が社会,国家の各領域ごとにどの程度の比重をもつかについては,各分野の発達の歴史的経緯によって異なった。
とくにスターリン時代の重工業化政策は,膨大な技術者,労働者を含む中央集権的指令経済構造を生み出し,その後の発展の型を規定した。これにはフルシチョフが〈鉄食い〉と述べた軍産複合体の保守的利害も微妙に絡みあっていた。このためスターリン以後,消費財や農業,畜産への重点の移行がマレンコフやフルシチョフなどの指導者によって唱えられたが,実効性に乏しく,フルシチョフの地方国民経済会議による分権化は失敗した。その後もコスイギンらによる経済改革など,企業や〈合同(オブエジニェニエ)〉レベルに決定権限を移す試みが成功しなかった理由には,各種の集権的機構の制度的利害からの抵抗が考えられる。もっとも,工業化自体は合理的な志向をもつ技術者などを生み出したわけであり,分権化を要求するのもこのような層であった。
これとの対比でいえば,農業部門は工業化政策の犠牲となってきた。このため農業関連の制度的利害は,多くの場合過小に反映されがちであり,指導部は,大きな抵抗もなく農業政策の転換を行うことができた。しかし,その転換が地区党委員会やコルホーズにより履行される制度的保障もまた十分には存在しなかった。他方,農業投資が増加し,その優先順位をめぐって,伝統的農業地域,シベリア,中央アジア,非黒土地帯などの各関係者が競い合う局面もみられた。これらは工業部門でもみられたが,一種の民族的争点とも関連して,ソ連における政治の重要な側面となっていた。
またソ連ではイデオロギー部門の比重も大きく,かつスターリン主義の保守的影響がこの部門に残ることになった。そのため小説や歴史論文,映画や演劇の発表までが政治的争点となりがちなことは,ソルジェニーツィンらの事件で知られていた。このため1960年代後半からは創造的な知識人らはネオ・スターリン主義の台頭に抗議して,民主化運動,異論派運動を育ててきた。クリミア・タタールやユダヤ人のような民族運動,宗教運動,人権運動,自由労働組合運動などは,党や国家の定めた枠の外にも広がり,緊張緩和政策のもとで国際的争点ともなった。当局はこれに対し刑法90条や190条の〈反ソ活動〉を理由に取り締まり,活動家や知識人の市民権剝奪を行った。しかしイデオロギー的宣伝の効果はしばしば両義的であり,市民が不満を訴える根拠を提供することもあった。特定の機関や職員に不満が生じた場合には訴願を受け付けることも党中央委員会をはじめとする党機関の役目であった。また〈ブレジネフ憲法〉58条は公務員の不法行為に対する市民の損害賠償請求権を規定し,国家と市民との利害の不一致を間接的に認めた。グラスノスチ(公開制)のもとで意見の多元性が公認されて以後,宗教など異論が認められ,多様な意見への寛容がすすめられた。ペレストロイカ期には,ヤコブレフの下の宣伝部が,もっとも〈反社会主義的〉と評された。
そのほか軍事部門もソ連の政治では無視できなかった。ソビエト権力の初期には,党の支配がフランス革命のように軍人により倒されることへの懸念もあり,赤軍には通常の党組織に加えて各種の政治的指導・統制の回路があった。中隊以上に設けられる政治部は党中央委員会直属であった。宣戦布告や動員,軍の最高統帥部人事は大統領の権限であり,大統領が発案して国防会議が具体的決定を行った。これは同時に軍需関係の省への指導も行ったが,閣僚会議にも軍事工業小委員会があった。KGBも国境警備隊を組織し,軍事的機能を有した。民間の防衛協力組織も党の指導下にあった。またソ連軍は,ワルシャワ条約機構を通じて東欧での軍事,治安にも関心を払うほか,国内の農業活動に動員されることもあった。ブレジネフ時代にソ連軍は増強され,アメリカと対等の軍事力をもつようになったが,その後ペレストロイカのもとでこれが否定され,〈防衛のための防衛〉〈合理的十分性〉の原則に従って軍縮に向かった。軍事産業の民需への転換もペレストロイカの柱となった。
執筆者:下斗米 伸夫
司法
ソ連邦の裁判所は,ソ連邦最高裁判所と連邦を構成する各共和国の裁判所(共和国最高裁判所,州(地方)裁判所,人民裁判所)および軍法会議からなっていた。ソ連のすべての裁判官は選挙によって任命され,彼らは選挙人または自分を選出した機関に対し報告義務を負い,リコールされうる立場にあった。裁判官と人民参審員は独立であり,法律だけに従うとされ,いかなる国家機関も裁判過程に干渉することを許されず,そのことが社会主義的適法性の遵守にとっての保障とみなされていた。しかし,法制上のこうした要請は司法の実態には必ずしも結実しなかった。〈電話法〉といわれた行政機関や共産党の機関から電話で具体的な裁判に関連して担当裁判官に〈指示〉や圧力が加えられ,裁判が政治や〈縁故〉によって影響される状況が少なくなかった。ペレストロイカは,そうしたソ連司法の実態を知らしめ,その改革の必要を説いた意味で,法治国家(法の支配)の実現をめざすという司法改革にとっても大きな画期をもたらした。
沿革
こうしたソ連の裁判所制度は,1917年の十月革命によって旧裁判所が廃止され,地方ソビエト選出による裁判官と人民参審員からなる人民裁判所(民事・一般刑事事件を審理)と革命法廷(反革命・重要刑事事件を審理)が組織されたことから出発した。前者は県単位の人民裁判官大会が選出する人民裁判官会議を,後者は全ロシア中央執行委員会のもとに破棄審を,それぞれ上級審としていた。当時,きわめて短期間ではあったが,だれでも告訴人,弁護人,訴訟代理人になれるという〈全市民的訴追・弁護制〉が試みられたことは興味深い。
ネップ(新経済政策)に移行した22年以後の司法改革により,裁判所制度は一元化され(軍法会議等の特別裁判所などを除いて),すべての裁判所の活動を統轄する最高裁判所が設置された。その結果,人民裁判所-県裁判所-最高裁判所という体系(三審制ではなく破棄手続による二審制)が成立した。22年には,集権的な検察機構が設立され,刑事事件における公訴人としての機能だけでなく,国家活動を適法性の観点から監督する〈一般監督〉機能をもった。ほぼ同時に,社会団体としての弁護士会も組織された。その成立は,当時急速に進んだ法典編纂(民訴法典,刑訴法典を含む)と密接に連動したものであった。36年のソ連憲法(スターリン憲法)は,裁判官の独立をうたうとともに,人民裁判所からソ連邦最高裁判所にいたる新しい選挙制の裁判所体系(ソ連崩壊まで基本的に維持)をうちたてた。しかし,当時の裁判の実態は,刑訴特例法でテロ事件,反革命事件などの被告から弁護権,上訴権が奪われるなど,憲法上の原則にも,適法性の原則にも反する重大な問題をかかえており,その克服は,56年第20回党大会の〈スターリン批判〉後にもちこされた。
1977年憲法以後
1991年まで存在したソ連の司法制度は,60年代の諸改革を経て,77年憲法制定後の法改正によったものである。裁判所体系の基層は,地区(市)人民裁判所で,各選挙区で直接・平等選挙,秘密投票で選出される裁判官(任期5年)と,職場または居住地ごとの市民の集会において公開投票により選出される人民参審員(任期2年半)とからなっていた。検察官,弁護士には特別の法曹資格(弁護士の場合,高等法学教育を修了し,2年以上の法律専門職の実務経験を積み,3ヵ月以下の試験期間を要する。実務経験がないか不足する場合,半年ないし1年以下の修習制度がある)を要求されるが,裁判官には特別の資格は要求されることはなかった。定数は各地区(市)ソビエトが定めるが,通常,裁判官は5~8名,人民参審員は裁判官に1名つき75名であった。
人民裁判所に対する上級審は,州,津法,自治州,自治管区,モスクワ,レニングラード両市(自治共和国最高裁判所も同格)に組織された。そのすべての裁判官と人民参審員は,それぞれに対応する人民代議員ソビエトにより選挙された。(任期5年)。これら州,地方などの裁判所は,民事部,刑事部,おろび幹部会からなり,同一地域の人民裁判所から任意の事件を引き取り,第一審として審理することがあるとともに,人民裁判所の判決に対する上訴(または告訴)を第二審として審理を行った(ここには,人民参審員は加わらない)。この第二審はソ連に独特なもので破棄審と呼ばれた。幹部会は,監督審(確定判決につき,異議申立てに基づく再審理)審理と再審および人民裁判所の裁判官の規律違反事件の審理を担当した。
共和国最高裁判所は,各共和国内の最高裁判機関で,全裁判所の活動を監督した。この判決は,監督審手続による再審理の余地を残すのみで,大多数の民事・刑事事件の最終審であった。またソ連邦最高裁判所は,ソ連邦全体にわたる裁判権をもち,全裁判体系の最終審であった。これらの最高裁判所の裁判官,人民参審員は,該当する最高会議(〈最高ソビエト〉とも訳される)により選出され(任期5年),民事部,刑事部,幹部会,総会から成っていた。最高裁判所もまた,とくに重大な事件と下級審の任意の民事事件を第一審として審理することがあり,第二審(破棄審),監督審,再審を行った。総会(人民参審員は加わらない)は,問題別に,法令をどのように解釈すべきかという〈指導的説明〉を採択し,裁判所活動の統一を図るという機能を果たしてきた。この〈指導的説明〉は拘束力をもたず,裁判所を拘束する有権的解釈は,最高会議幹部会の権限に属していた。ソ連邦最高裁判所は,いわゆる違憲立法審査権はもたないが,立法的解決の必要な問題について提議権を行使することができた。また,この裁判所には,その他に軍法会議の最終審としての軍事部があった。
なお,ソ連では法人間の財産事件は国家仲裁機関が,職場での労働紛争は労働紛争処理委員会(人民裁判所でも扱う)が解決にあたってきた。また,職場,居住地での軽微な犯罪などは同志裁判所が,少年事件は未成年者問題委員会が,社会的自治機関として問題の解決にあたってきた。
ソ連の検事は,単に刑事訴訟だけでなく,民事についても当事者に代わって訴えを行い,民事訴訟に参加し,民事・刑事事件の確定判決について異議申立ての権利をもつという独特のものであった。また,ソ連邦検事総長を頂点とする中央集権制をとり,地方の検事は,ソビエト諸機関から完全に独立していた。弁護士は,弁護士会の一員(法律相談所を通じ)として活動するが,刑事事件では起訴段階以後にその活動が限定されており,改善を求める声も強かったが,その実現はソ連の崩壊直前まで着手されなかった。企業,国家機関,労働組合には専門職としての法律顧問がおり,弁護士は直接市民とのみかかわることになるが,弁護士会の自治はかなり認められているといえよう。
ペレストロイカ以後
社会主義の〈再生〉をめざしたペレストロイカは,司法分野でも多くの改革の方向を提示した。その最大のものは,従来は否定されてきた憲法裁判制度を導入したことであろう。
改革の試みは,ソ連崩壊前の1980年代末から着手されるが,実際にその制度化がすすむのはソ連の崩壊後になってからといってよい。ここでは,ロシアを例にとって現在の司法制度の概観だけを示しておくことにする。
まずロシアの裁判制度は,連邦レベルに(1)連邦憲法裁判所,(2)連邦最高裁判所,(3)連邦最高仲裁裁判所の三つの裁判所をおき,普通裁判所の系列では,連邦最高裁判所の下に,ロシア連邦を構成する共和国・州・地方・連邦直轄都市(二つ)に共和国最高裁判所,州裁判所,地方裁判所,市裁判所が同等の位置にあるものとして設置され,その下に市裁判所,地区裁判所または複数の自治体にまたがる間自治体裁判所という日本の地方裁判所にあたる裁判所(かつての人民裁判所)がおかれている。名称は別にして,新しい制度としては,帝政時代にあった治安判事制の復活,陪審制の導入があげられ,第一審では陪審員の参加するもの,人民参審員の参加するもの,または裁判官の独任制もしくは3人の合議制などの複線的な審理のあり方がとられるようになっている。
仲裁裁判所は,かつての行政機関としての仲裁機関を裁判機関化したもので,最高仲裁裁判所の下に連邦全体を10の管区に分けてそれぞれに管区仲裁裁判所をおいている。
憲法裁判所は,ソ連末期の憲法監督委員会の経験をも踏まえて,ロシアで1991年に設置されたもので,旧ソ連諸国の大半の国でも導入された新しい制度である。連邦の法律や大統領令,政府決定,さらには連邦構成主体の定める法令の合憲性を判断し,憲法秩序と人権の擁護を課題とするもので,市民も申立てを行うことができることとされており,すでにいくつかの違憲判決も下しており,立憲主義・法治国家の実現にむけてその役割が期待されている。こうした裁判制度の改革とともに,憲法に人権思想を取り入れ,刑事訴訟手続における市民の権利・自由の擁護を手厚くした。被疑者・被告人が,逮捕時から弁護人依頼権を保障されることなどがその代表例である。また,司法による人権保障制度の改革とともに,人権オンブズマンの制度を新たに導入したことも注目しておいてよい。
→社会主義法
執筆者:竹森 正孝
外交
革命外交から共存外交へ
十月革命は本来,単に国内体制の変革にとどまらず,既存の国際関係のラディカルな組替えをも含意していた。ボリシェビキ指導者は,ロシア革命が西ヨーロッパ先進国の革命によって支援されない限り生き延びることはできないと確信していたからである。したがって,1918年11月のドイツの無条件降伏に続く中部ヨーロッパの激動は,帝国主義の戦線の全面的崩壊を予告するものと受け取られ,19年3月に創設されたコミンテルンには,世界革命の参謀本部の役割が期待された。しかし実際には,先進国で革命は起こらなかった代りに,ソビエト権力も孤立したままで存続しうることが明らかになり,ソ連邦と外部世界との間に,〈不安定ながらも一定の均衡〉(レーニン)が成立した。この特殊な均衡状態から不安定要素をできるだけ取り除くことを任務とした〈共存〉外交がここに登場する。伝統的外交の復権でもあった。
しかし先進国革命への強い期待が残っている限り,国際体系の現状承認を前提とする外交は,まだ本来の機能を完全に取り戻すことはできなかった。事実,通常の外交業務を担当する外務人民委員部の活動が,コミンテルンの活動と競合し,効果が減殺されるようなことも,初期にはまれではなかった。ソビエト共和国とドイツ間の正式の外交関係を確立したラパロ条約(1922年4月)までの両国関係のたどったジグザグの道は,このような二元性の反映でもあった。
ソ連外交につきまとっていたこの種の不透明さは,スターリンの〈一国社会主義論〉の成立をまってある程度解消された。ソ連一国だけの努力で社会主義を建設できるとするこの理論は,あくまで先進国革命に固執するライバルのトロツキーの〈永久革命論〉に対抗して打ち出されたが,同時に24年以降の資本主義世界の相対的安定期におけるソ連を取り巻く国際環境の顕著な変化に対応するものでもあった。すなわち24年には,イギリス,フランス,イタリアなど列強のソ連承認が相次ぎ,日本も翌25年その後に続いた(ただしアメリカはだいぶ遅れて1933年。表2)。
こうしてスターリンの理論は,ロシア革命の長期の国際的孤立のもとでの生残り戦略であり,当然そこでは対外活動の重心はこれまで以上にソ連の国家的安全保障に置かれることになった。外務人民委員部とコミンテルンの対抗関係は,後者の前者への従属という方向でしだいに解消されていった。20年代末からソ連は,対外政策の分野でははっきりと現状維持に転じ,周辺の国々との中立・不可侵条約網を広げ,外からの干渉の危険を排除することに努めた。しかし,いわゆる〈資本主義による包囲〉が続く限り,このような消極的安全保障には限界があるから,積極的安全保障,すなわち自力防衛の方法にも努力を怠らなかった。28年に始まる五ヵ年計画のおもなねらいは,国防力の基礎となる重工業基盤の創出であった。
33年1月,ドイツにおけるナチス政権の出現は,満州事変以来ソ連の極東国境に対する重圧となっていた日本の動きと相まって,ソ連にとって重大な脅威を意味した。しかし資本主義世界が現状維持と現状打破の二つの国家グループに分裂したことは,ソ連に前者の側に立って集団安全保障の理念の使徒として活躍するチャンスを与えた(1934年11月,国際連盟加入)。ソ連のデモクラシー諸国への接近政策は,35年夏のコミンテルン第7回大会で決定された〈人民戦線〉戦術で補強された。しかし新路線も,起源からみれば,コミンテルンの自主的判断が一定の役割を果たしたことは確かであったが,実践の過程でソ連外交の必要に適合させられ(たとえばスペイン内乱中の反スターリン左派勢力の粛清),結局は状況を切り開くダイナミズムを失っていった。他方,イギリス,フランスの採った宥和政策の頂点たる38年のミュンヘン協定(ミュンヘン会談)は,ヨーロッパの安全保障システムからのソ連の排除を明らかにした。ソ連外交の方向転換はここに不可避となった。39年の独ソ不可侵条約はその回答であった。同時に結ばれた〈秘密議定書〉に見られるように,スターリンはいまや露骨な〈権力政治〉の道に踏み出した。すなわち,第2次世界大戦の勃発に際してソ連は,さしあたり局外に立って,北はバルト諸国から南はベッサラビアに至る近隣諸国を犠牲にした領土拡張を追求したが,反面ドイツからの侵略の可能性を過小評価する誤りを犯した。41年6月,ドイツの対ソ攻撃とともにソ連,アメリカ,イギリスの共同戦線が構築され,〈大同盟〉は枢軸国に対する勝利の原動力となった。45年,ヤルタ会談での秘密協定を受けてソ連は8月,日本に宣戦した。
戦後,スターリンは少なくとも47年半ばころまでは,国内復興のための米ソ経済協力,その前提としての米英ソ三大国中心の平和維持にそれなりに関心をもっていたようである。しかし,トルーマン・ドクトリン,マーシャル・プランによって米ソ協調の望みが断ち切られると,スターリンはコミンフォルムの創設に始まる東ヨーロッパの衛星国化を強行し,また東側陣営の自己幽閉を推し進めた。〈冷たい戦争〉はインドシナ,朝鮮半島では〈熱い戦争〉に転化した。
共存政策の活性化
53年3月のスターリンの死は,ソ連に革新の風を導入するきっかけとなり,対外政策の面では,53年から56年にかけて,朝鮮とインドシナにおける休戦協定(朝鮮戦争,インドシナ戦争)の促進,ジュネーブ会議への参加,ドイツおよび日本との国交回復,コミンフォルムからの破門以来,完全に冷えきっていたユーゴスラビアとの関係改善など,多彩な〈平和攻勢〉が展開された。56年2月の第20回共産党大会でフルシチョフ第一書記は,帝国主義が続く限り戦争は不可避であるとするレーニン以来の命題を否定し,核時代における平和共存に至高の価値を認めた。またアジア・アフリカ新興国の中立主義に眼を向け,援助を通じて影響力の伸長を図るようになったのもこの頃からであった。しかし第20回党大会で一挙に表面化したスターリン批判は,東欧諸国で混乱を引き起こし,秋にはハンガリーで発生した反政府暴動の鎮圧にソ連軍が投入されなければならなかった(ハンガリー事件)。さらにスターリン批判は,中ソ間の潜在的対立要因に火をつけることになり,当初の党レベルでのイデオロギー論争は,60年代には国家間関係に跳ね返るようになった。
〈冷たい戦争〉からの軌道修正も決してスムーズにはいかなかった。1959年秋のフルシチョフの訪米を経て,翌年5月に設定された東西首脳会談はU2型機事件によって中止され,架空の〈ミサイル・ギャップ〉を理由に軍備増強に踏み切ったケネディ民主党政権のもとで,米ソ関係は62年秋のキューバ危機によって,ついに核戦争の瀬戸際にのぞんだ。しかし危機は,核大国としての米ソの責任を両国指導者に痛切に意識させることになり,核戦争の防止というミニマムの共存条件について暗黙の合意が生まれた。
世界強国のジレンマ
フルシチョフ時代のソ連は軍事力でアメリカに近づき,第三世界にいくつかの足場を築くことに成功していたが,64年10月に成立したブレジネフ政権は,この遺産を引き継ぎ,さらに世界の大国への成長を助けた。その対外政策は,国内政策と同じく慎重な保守主義で際だっていた。その見本は東ヨーロッパにおける政策である。1956年以後,ソ連は東ヨーロッパ諸国に相対的により大きな自主性を認めるようになっていたが,68年春,チェコスロバキアで〈人間の顔をした社会主義〉を目ざす実験が始まると,しだいに警戒心を強め,ついに8月,ソ連・東欧5ヵ国軍隊を進攻させて改革の動きを圧殺した。そして個々の社会主義国は社会主義共同体全体に対し責任を負っているという〈制限主権論〉(またはブレジネフ・ドクトリン)を定式化した。こうしてソ連は,社会主義体制の〈自由化〉には絶対的限界のあることを明示した。いずれにせよチェコスロバキア事件はプロレタリア国際主義の理念を蹂躙(じゆうりん)し,共産主義運動の〈多中心化〉を促進し,中ソ関係をさらに悪化させた(1969年3月,ウスリー川で中ソ武力衝突)。
一方,東西関係の分野では,69年に入ってから,対決より交渉のスローガンを掲げたアメリカのニクソン共和党政権の発足,西ドイツのブラント政権による〈東方政策〉の展開によって,ソ連が戦後求め続けてきた東・西ヨーロッパの現状承認の見通しが開け,また米ソ関係の改善を軸に,いわゆるデタントの時代が開幕した。75年7月,アメリカ,カナダを含むヨーロッパ35ヵ国のヘルシンキ会議とそこで採択された最終文書は,デタントの輝かしい里程標であった。ソ連はすでに70年代初め,〈いまやソ連抜きで解決できるような重要な国際問題はない〉(グロムイコ外相)と言いきるまでになっていたが,この自信を支えていたものは,72年5月の第1次戦略兵器制限交渉によって確認された米ソ間の戦略的均衡の達成であった。この均衡を背景に,ソ連はアメリカ,西ヨーロッパ,日本との政治的・経済的関係の改善に努めた。ソ連のねらいは,米中接近を牽制し,西側工業国からの資本・技術の輸入によって経済的発展を維持することであった。しかしソ連は,国際政治の中心部におけるデタントは周辺部までカバーすべきであるとするアメリカ側の解釈を受け入れなかった。第4次中東戦争の後,一時,中東問題での発言権を失ったかにみえたソ連は,アフリカでは,76年から77年にかけてアンゴラ,エチオピアに大量の軍用資材を送り込み,親ソ政権をもり立てることに成功した。
第三世界におけるソ連のこのような行動は,着実な軍備増強と相まって,西側諸国を警戒させることになり,78年の日中平和条約,79年の米中国交正常化を経て,逆にソ連の孤立化が深まった。79年クリスマスに始まるソ連軍のアフガニスタン侵攻は,伝統的な勢力圏の外での初めての大規模な武力行使として,東西関係を一挙に凍りつかせた。しかし介入は,この孤立化に伴う危機感とアフガニスタンにおける親ソ政権の消滅への不安から出た応急策であり,地政学的動機に促された計画的なものではなかった。それまでのソ連の第三世界における活動も,現地の諸条件の中から生じた機会につけ込むという意味で受動的であり,あらかじめ立てられた戦略デザインに基づくものではなかったとする見方が一般的である。
しかしアフガニスタン事件を境に一挙に高まった〈ソ連脅威論〉を背景とした国際緊張のエスカレーションに対し,ソ連は量的な意味での対米戦略的均衡を機械的に追求するだけにとどまり,大韓航空機撃墜事件(1983)にみられるように国際世論から自らを孤立させた。ブレジネフ時代末期の内外政策の〈停滞〉を打破するためには,若く行動力あるゴルバチョフ政権の登場(1985年3月)を待たねばならなかった。
新思考外交
新政権の優先的外交課題は,もはや一刻の猶予も許されなくなったソ連社会のラディカルな改革〈ペレストロイカ〉のために有利な国際環境の創出と維持であった。ここにこれまでとは異質な国際政治観が〈新しい思考〉の名のもとに説かれるようになった。これは現代世界の相互依存関係に立脚して,安全保障の分野では軍事的手段に代えて政治的手段を重視し,核,南北問題,あるいは生態学的危機のような〈グローバルな諸問題〉に対して体制を超えた共同の取組みの必要を力説する立場である。こうして軍備管理交渉における柔軟姿勢,一方的軍縮措置の実施,首脳会談方式の活用,第三世界へのコミットメントの縮小など,ソ連外交は着々と成果をあげているかのようにみえた。しかし一国の対外的地位が究極的にはその国が代表する道義的,経済的価値に依存する以上,年を追って深まる一方の国内体制の危機は,ソ連外交の作用範囲をいや応なくせばめ,最後にはソ連邦の解体とともに,ソ連外交はロシア外交へと主体を代えた。
しかし1989年末までには明らかになった冷戦の終結にとって,〈ゴルバチョフ外交〉が決定的役割を演じたことは忘れてはならない。
軍事
1917-28年
もともとボリシェビキにとって,軍隊は支配階級に奉仕する暴力装置であり,革命によってまっさきに解体されるべき対象であった。そこで,ロシア革命を取り巻く状況が,革命政権もまたみずからの軍隊を組織することを余儀なくさせたとき,具体的な青写真はまだなかった。こうしてソ連軍の草創期の歴史は文字どおり試行錯誤の連続であった。
二月革命後,ボリシェビキは工場単位で赤衛隊を組織する一方,正規軍部隊内での宣伝活動を展開した。11月8日,革命権力の成立を宣言した第2回ソビエト大会は陸海軍問題委員会の設置を決議したが,翌18年初め,労働者農民赤色陸軍(赤軍)および同海軍(以下便宜上,両軍併せて赤軍と呼ぶ)の創設と軍事問題人民委員部の新設が布告された。ペトログラード(のちレニングラード,現サンクト・ペテルブルグ)の赤衛隊と守備隊を母体とする志願制の最初の赤軍部隊がペトログラード南方でドイツ軍の進撃を食い止めた2月23日は,のちに陸海軍デーと命名された。4月以降になると,連合国側からの軍事干渉の重圧が加わって情勢はいっそう厳しさを加えたため,やがて革命の理念に反して徴兵制を施行せざるをえなくなり(ただし兵役義務は労働者と農民に限定),赤軍の兵力は10月末までに80万,1年後には300万に増大した。統帥系統では,18年末に労農国防会議が既設の革命軍事会議(RVSR)の上位に置かれ,野戦参謀部が作戦の指導に当たった。
当時の赤軍にとって最大の難問は,階級的ないしイデオロギー的純粋性と戦闘効率とを,いかにして両立させるかであった。RVSR(議長トロツキー)の採った応急策は,旧帝政軍の将校を〈軍事専門家〉として赤軍に編入し,その政治的目付役としてコミッサールを併せて配置することであった。イデオロギーか,専門的知識・技術かのジレンマは,その後も長く尾を引くことになるが,このほかにも組織原則(正規軍対民兵)をめぐる論争があり,いずれも赤軍誕生時の事情に起因する。
ソビエト政権は20年の終りころまでには軍事的危険から脱し,軍隊の復員も始まった。23年秋には平時編成に戻り,兵力は51万6000人まで縮小した。24年から25年にかけて,いわゆる〈軍制改革〉によって,民兵・正規軍混成制への移行が進んだ(1928年には民兵師団は全体の56%を占めた)。25年に起きたもう一つの大きな改正は,作戦・訓練の分野で指揮官をコミッサールの後見から解放する〈単独責任制〉が導入されたことである。コミッサール制の実質的廃止に等しいこの改正は,軍における党員の増加ということで正当化された。
1928-53年
30年代は赤軍にとって第2の変動期であった。1928年に始まる第1次五ヵ年計画の優先目標の一つは,赤軍装備の近代化であった。20年代半ば以降,党の正統理論となった〈一国社会主義論〉と裏腹の関係にあったのが自力防衛の立場であり,これは当然に軍事力の重視につながってゆく。いまや赤軍が革命の軍隊から国家の軍隊へと変貌するのは避けられなかった。いずれにせよ工業化の成功は軍備面での目ざましい進歩を可能にし,世界にさきがけて機甲部隊や空挺部隊が編成され,北洋艦隊および太平洋艦隊も新設された。物量と機動力を組み合わせた縦深作戦という,当時としては破天荒な戦術理論が生まれたのも,工業化の成功がその背景をなしている。軍での階級制が復活し,RVSRに代わって国防人民委員部が設けられ,構成も正規軍本位に戻った。30年にはすでに全狙撃師団のうち正規師団は77%を占めるまでになった。プロフェッショナルの時代が始まったわけである。
しかし順調に伸びつつあった赤軍に突如スターリンの粛清が襲いかかった。37年5月にコミッサール制が再導入された直後,トハチェフスキー元帥以下,最高首脳7名が逮捕され銃殺刑に処せられ(6月),これを合図に粛清は赤軍内部に荒れ狂い,その犠牲者は全将校団の5分の1に達した。とくに将官クラスへの打撃は甚大であった。赤軍戦力の大幅な低下はおおうべくもなかった。
第2次世界大戦が勃発すると,ソ連はただちに兵役法を改正して従来の階級的出自による差別を撤廃し,さしあたり中立を維持しつつ赤軍を矛として防衛空間の確保の意味も持つ版図の拡大に努めた。しかしフィンランドとのソ・フィン戦争は,赤軍の士気の停滞と戦闘能力の欠陥を暴露したため,単独責任制への復帰,将官・提督制の復活,機甲軍団の再編成などの応急措置が相次いで実施されたが,態勢の立直しが整わないうちに,41年6月22日,独ソ戦を迎えた。不意をつかれて,緒戦時には敗走を重ねた赤軍は,やがて反撃に転じ,4年に及ぶ死闘を勝ち抜いた。45年8月,ソ連は日本に対し宣戦し,極東赤軍は日本軍を圧倒した。戦争終結時の赤軍総兵力は1136万5000人に達していたが,48年までには287万4000人に縮小された。
戦後の再建過程は同時にスターリンの専制支配の再確立の過程であり,軍(1946年に赤軍はソ連軍と改称。国防人民委員部および海軍人民委員部は統合されて軍事力省となり,50年に陸軍省と海軍省に分離され,53年に再統合されて国防省に改編)も〈個人崇拝〉のもとで窒息し,核時代(ソ連の原爆保有は1949年)という新しい軍事技術的環境に対応した軍事理論の発達は押しとどめられた。
1953年以降
53年3月のスターリンの死とともに,ソ連軍の歴史も新しい段階に入った。まずスターリン時代に着手されていた研究・開発プロジェクトが一斉に開花し始めた(1953年8月の水爆実験,57年8月の大陸間弾道弾(ICBM)実験など)。54年から57年にかけては核兵器・核戦争に関する討論が公然と行われるようになり,また独ソ戦の経験を一面的に絶対化したスターリン軍事理論は否定された。フルシチョフは,核兵器の抑止力を全面的に信頼し,結局は実行されなかったが,民兵制度の復活すら示唆するほどであった。59年12月には戦略ロケット軍が新たに設けられた。
64年10月の政権交替は,軍事政策に本質的ななんらの変化をももたらさなかった。ただし60年代後半にはNATO(北大西洋条約機構)の柔軟反応戦略に対抗して,通常局地戦争から全面核戦争にいたるあらゆる事態に対処できる準備の必要性が強調された。70年代に入ると,第1次戦略兵器制限協定が象徴する対米戦略的均衡の実現を足場に,ソ連はアメリカとの対等性の名のもとに軍事力の国外展開能力を重視するようになった。遠洋海軍力の育成,アンゴラ,エチオピア,あるいはアフガニスタンへの介入は,この能力の実現をある程度立証している。同時に軍事力増強が西側諸国に与える衝撃を和らげるため,ソ連指導者は70年代末から,戦略的優位の追求という目標を一貫して否定し続けてきた。しかしソ連は〈対等で同一の安全保障〉の原則にあくまで固執し,アメリカもまた〈力の立場からの交渉〉の構えを崩そうとしないため,両国の接点は容易に見いだせないままであった。
1985年のゴルバチョフ政権の登場以来,ソ連軍もまたペレストロイカの渦に巻き込まれ,大きな転機に立たされている。ゴルバチョフ政権のもとで打ち出された〈新しい思考〉は,なかんずく国家的安全保障の問題と深くかかわっているからである。その具体的表れが〈合理的(防衛)十分性〉や〈防衛的軍事ドクトリン〉という概念である。
たしかにこれらの概念は基本的に相対的な量を問題にするために,一義的な定義に到達することは容易ではなく,したがって軍事問題における保守派の抵抗の余地が残っている。しかしそれでも中距離核戦力(INF)全廃条約(1987年12月調印),アフガニスタンからのソ連軍の完全撤退(1989年2月),89年に始まる50万人にのぼる一方的兵力削減計画など,たんに軍事費の重圧の軽減にとどまらない,発想の転換の端緒を感じさせた。しかし,改革派が軍の〈聖域〉に踏み込めたのは,永年の特権に守られてきた軍の一時的脱力感のおかげであった。したがってペレストロイカの波が保守派によっておしとどめられるようになると,力を背景に巻き返しの先頭に立つ将軍たちの出現はさけられなかった。この動きにピリオドを打ったのは,やはり91年夏のクーデタの失敗であった。
統帥と構成
ソ連軍の統帥機関には国防会議,中央軍事会議,参謀本部があった。国防会議の存在は76年に初めて明らかにされたが,議長たる共産党書記長のほか数名の政治局員(このほか参謀総長,国家計画委員会議長を含める人もいる)がメンバーとみられ,国防政策の最高決定機関であった。中央軍事会議は国防省に設けられた合議制機関で,国防相が主宰し軍最高首脳を網羅していた。平時における戦略的指導に当たり,戦時には大本営(スタフカStavka)がこれに代わる。参謀本部は軍と国防省を媒介し,基本的戦略計画を策定し,各軍の任務を画定する。最も重要な部局は作戦,情報,組織・動員の3部とされている。なお政治教育の総元締めである陸海軍政治本部は党中央委員会の一部局でもあった。ソ連軍は地上軍,海軍,空軍,国土防空軍,戦略ロケット軍の5軍種に分かれていたが,このほか後方勤務部,民間防衛本部および部隊,国境警備隊,内務省軍隊が含められたこともある。最後の二つは,それぞれKGB(カーゲーベー)と内務省の管轄であった。
ソ連領内に設けられている軍管区の数は16,うち中国西北部に接した中央アジア軍管区(司令部アルマ・アタ,現アルマトゥイ)は1969年秋に新設されたものであり,バイカル湖以東にはザバイカル(司令部チタ),極東(司令部ハバロフスク)の2軍管区があった。いくつかの軍管区を併せて軍事作戦区がつくられていた。防空管区のうち,モスクワ,バクーの二つには特別の地位が与えられていた。このほかポーランド,ハンガリー,チェコスロバキア,東ドイツに計31個師団のソ連軍が駐留していたが,1994年夏までにはすべて本国に撤退した。また,アフガニスタンに展開されていた10万5000人(1983年現在)のソ連軍は,1989年2月までには撤退を終了させた。。海軍にはバルチック,北洋,黒海,太平洋の4艦隊があり,カスピ海には小艦隊が配置されている。党・政治活動の指導では,前記の政治本部の下に,各軍に政治部,軍管区,防空管区,艦隊,師団,連隊,中隊にも似たような機関が設けられ,その責任者が政治担当副指揮官となっていた。89年央現在の推定兵力数は正規軍総兵力426万人(うち戦略ロケット軍29万,地上軍160万,海軍44万,空軍45万,国土防空軍50万など)で,このほか計57万人の国境警備隊と内務省軍隊があった。
執筆者:平井 友義
経済,産業
革命前のロシアは鉱工業のほとんどの分野でアメリカ,イギリス,フランス,ドイツに遅れていたが,旧ソ連邦は,いくつかの分野でアメリカには劣るものの,ヨーロッパでは第1位の鉱工業生産高を誇っていた。アメリカと比べて経済発展度は1960年代以降急速に高まっていると自己認識され,国民所得や工業力全体ではやや低いが,石油,鋼,化学肥料,セメント等々では1980年代末までの20年ほどの間に〈追いつき追い越し〉たとされていたのである。1970年代から欧米諸国が大量の失業者とインフレーションとの同時存在(スタグフレーション)に悩まされていただけに,驚くほど長期間にわたり安定した物価水準を維持しつつ,しかもかなりの成長を遂げていたソ連経済が,非マルクス系経済学者からも注目されていたことは当然であった。革命前ロシアの外国資本による産業の分断支配,革命後の内戦,干渉戦,さらに2000万人の死者を出したという第2次世界大戦などでの困難を考慮すると,旧ソ連の経済的達成はまさに驚異的というべきものであった。
鉱業,重工業を中心にしたこのようなソ連経済力の上昇が,独特の〈計画経済〉制度に支えられてはじめて可能であったことはよく知られている。〈計画経済〉の理念は,マルクス《資本論》が資本制社会を〈無政府的〉〈事後的調整〉の社会と把握したことの否定面として形成されたが,ソ連邦でこれが現実に制度化をみるのは1920年代の末からである(第1次五ヵ年計画は1928-32年)。1981-85年第11次五ヵ年計画,86-90年第12次五ヵ年計画というふうに〈計画経済〉が積み重ねられてきていたのである。結果的には,第13次5ヵ年計画に入った年にソ連邦は崩壊したことになる。積み重ねられた〈計画経済〉は市場経済とはかなり異なっていたので,以下そのおもな特徴を掲げる
(1)市場での自由競争は排除され,中央計画当局が国民経済全体を計画し,行政的生産単位たる企業に対し,義務指標を課すことで経済を営んでいた。(2)国有企業(農業の半分以外はほとんどがそれであった)があげる利潤は全体がまず国家のものと考えられ,1970-80年代ではそのほぼ5~6割(日本では法人税は4割)が財政歳入として中央にいったん吸い上げられるのみならず,企業手もと分処理についても細かく上部の指示があった。(3)とくに生産財に関しては機械・資材補給省という担当省が存在していたことからもわかるように,商品化が排除されていた。(4)一般商品価格は市場で競争の中で形成されたのではなく,国家ないし共和国の価格委員会が最終的権限をもち,これを決定していた。(5)企業・機関の管理者人事は,原則として上部(管轄官庁,党)の指名によった。(6)賃金も職種ごとの賃金表が国家レベルで決定され,一定の賃金ファンドの中から配分されていた。
土地をはじめとして重要産業部門をことごとく国有化し,教育・文化活動なども国家的事業とされる独特の国家主義的社会の中で,このようにきわめて中央集権性の強い指令型の計画経済が営まれていたわけである。鉱業の一大発展を支えた条件の一つには,シベリアをはじめとした資源の豊富さがあったであろうが,それとともに,ソ連政府が技術者・専門家を優遇し,一定の教育体系を用いて専門職種で熟練度の高い有資格熟練労働者(クワリフィツィーロバンヌイ)を継続的に大規模に育てたことも指摘されねばなるまい。あらゆる産業分野で有資格熟練労働者は優遇され,一般に高教育水準=高資格=高賃金=管理上の高地位,といった連関の位階制がみられ,それが全体の中央集権指令型の国民経済を支えていたのである。
とはいえ1970年後半から,ソ連経済の成長率は著しく低下してきていた。国民所得(その計算方式は,とくに第3次産業部門の評価が西側諸国より低いという特徴をもっていた)の成長率は公表統計においても2~3%台というかつてなく低い水準さえ記録するようになっていた。成長率の鈍化をもたらした要因の一つが,農業生産高の低迷であったことは明らかで,農業生産高が前年を下回った年の国民所得は必ず低迷していた。しかもかつて長く穀物輸出国であったものが,1972年以降はほぼ恒常的な一大穀物輸入国に転じてしまった。そのほか,成長率の低下をもたらした要因には,石油危機以降増大していた輸出石油の価格の大幅下落,アフガニスタン戦争の出費なども指摘されていた。
1985年登場したゴルバチョフ政権はこの経済成長率低迷を脱出するため〈加速化〉というスローガンを掲げたが,従来の経済管理システムをそのままにした〈加速化〉はかえって歪みを大きくした。そのため,その後の〈経済改革〉は従来の〈計画経済〉を根本から問い直し,〈市場経済〉に傾斜していくという意味で,全面的な構造的改革へと向かってきていたといわねばならない。以下,国民経済の諸分野ごとに簡略にその実態と改革の動向とを検討したうえ,ペレストロイカのもとでの〈経済改革〉全体の問題点を解明しておこう。
財政
中央集権指令型の計画経済の展開の中では,国家財政がきわめて大きい役割を演じたことは当然で,いわば財政は国民経済の再生産に西側諸国以上に深く食い込んでいた。国家財政の規模と国民所得とを単純に対比しても,前者は後者の5~6割に達し,計算方式の差異や財政投融資の存否などを考慮したとしても,日本の単純な対比から得られる2割前後という数に比し,かなり高かったといえる。もともと帝政ロシア時代から財政が国民経済の中で大きな比重を占めていたのであって,1920年代末の計画経済のスタート時から財政をその重要なてことしてきた伝統をもっていたのである。
歳入の利潤控除が諸部門の国営企業の利潤の吸上げ分であったが,これと並び取引税が従来大きな柱をなしていた。もともとは帝政時代のウォッカ酒税に起源をもつ取引税は,消費財に著しく比重が偏っていたために,経済改革を推進した人々は,〈経済的に根拠のある価格を〉との観点からこの取引税の比重を引き下げていくことを主張した。そして事実,1960年代後半以降,一時この比重は利潤控除よりも小さなものとなったのであるが,経済改革の後退とともに取引税は再び最大歳入項目となっていた。しかしペレストロイカのもとで,再度,取引税の伸びは抑えられ,利潤控除が最大の歳入の柱となりつつあった。個人所得税の比率があまり動いていなかったほか,国債は発行されていたがきわめてわずかであった点などが,西側諸国と異なる旧ソ連財政の特徴を示していた。
さて歳出の半分以上が国民経済費に当てられていたが,先にみたような中央集権指令経済のもとで,これは企業・諸機関などへの諸投資,諸分野への補助金など企業レベルの再生産活動の一端に食い込んでいた国家資金であった。3割台を占める社会文化費とは,教育費,科学研究活動費,保健・社会保障などの支出であった。軍事費で旧ソ連当局により公表されていたのは,唯一〈国防費〉(表3)の項目だけであったが,これによると旧ソ連末期にはその絶対額が据え置かれていたために,歳出中の比率は顕著な低下を示していた。しかし旧ソ連の末期頃,ゴルバチョフ書記長自身によって,〈国防費〉は上記数字の3倍以上と訂正され,また内部の改革系の雑誌などでは〈軍産複合体〉関係の比重は国民所得の50%にも達するといった論文もあらわれたりしていた。正確な実態はついにわからずじまいであったが,軍需産業の比重の大きいことはソ連崩壊後の各国とくにロシア連邦などの〈市場移行〉をきわめて困難なものとしたことは銘記される必要があろう。
もともと超大国アメリカと核兵器の増強をはかりながら対峙し,しかも絶えざる技術革新にさらされていた軍需工業をはじめ,国防のために旧ソ連が割いていたコストが公表数字で全部であるとは西側諸国は見なしていなかった。1970年代の前半まででも,実際の軍事支出はこの財政表上の公表数字の少なくとも2~3倍と推測されてきたのであった。アメリカCIA推計軍事費をソ連の公表国民所得と対比すると,その約17%前後だったことになる。しかし,1968年チェコスロバキア事件以降,アフガニスタン侵攻,ポーランド問題と,軍事支出はむしろ増大する一方で,中距離核ミサイルの緊張がこれに拍車をかけていたこともまちがいなかった。いずれにしろ軍事費の膨張は国民経済を圧迫し,成長鈍化を加速させた要因の一つとみられよう。とはいえ,軍需工業は武器輸出という形で重要なハードカレンシー(交換性通貨)の収益手であるとも見なされていたので(アメリカの推計では旧ソ連の武器輸出による収益は1980年代末,毎年10億~15億ドルという),軍事支出はその二面性への注意が必要であった。
金融
財政と併せて金融が問題であり,現代諸国では一般に財政・金融の一体化が進んでいるが,旧ソ連邦の場合は,西側でいう信用創造という意味での金融は原則として存在しなかった。ゴスバンク(国立銀行)のほとんど独占的で圧倒的な一元支配下に金融はおかれていたともいえる(1987年の改革により,ゴスバンクは中央銀行として機能することになり,5行の商業銀行が新設された)が,これもいわゆるアクティブ・マネー(能動貨幣)を供給するものではなく,計画経済の枠に沿って動く物財のいわば逆等価の記帳をもって主務としたものである。いわば資金の受入れ窓口であり,資金配分機関なのであって,利殖を求めての投資機関ではなかった。確かに利子は存在していたが,一般にきわめて低利であり,〈計画欠損〉といわれる連続赤字の部門などにも貸付けが行われ,債務が累積していたことをみると,厳格な取立てが行われていたとも思えない。株式投機とか投資信託などは公的に排除されていたし,乱立する私的信用機関の預金獲得競争などはむろん存在していなかった。むしろ企業レベルの予算制約の過度のゆるやかさが経済効率を低下させているとした経済改革派は,企業がせめて流動資金だけでも企業自己責任で借り入れ,返済すべきことを主張したぐらいであった。ペレストロイカといっても実状は日本の国鉄赤字にも似て,オール国有企業システムの中にあり,金融の役目はむしろ消極的であった。庶民の賃金などは貯金局がその媒介窓口となっていたが,それはちょうど日本の郵便局のようなものである。
鉱工業
先進工業諸国と比較した旧ソ連末期の鉱工業生産高は表4のとおりであり,ソ連経済力の大きさがわかろう。また耐久消費財の世帯別公表普及度は,時計546%,ラジオ96%,テレビ101%(カラーテレビは34%),カメラ35%,冷蔵庫92%,掃除機70%,ミシン65%,乗用車17%(1987。ただし,以上は都市と農村との全体の平均であり,両者の格差はまだ相当残っていた)で,ほぼ日本の高度経済成長後半期ころの状況であったろうか。ただし,以上はあくまで数量比較の問題であって,商品の質では西側諸国のものの方がはるかに高級であったといえる。このことは繊維製品などでも同様であったばかりか,実は重工業関係でも指摘できた。例えば鉄鋼業では薄板に弱い等々の〈質〉の問題が大きかったことは常識でさえあった。
1960年代初頭の経済成長率の鈍化を契機に,その論議がかつてなく高まり,65年以降ついに実施に踏み切られた経済改革の重要諸課題の一つは,この〈商品の質〉の問題であった。改革派は従来の過度に中央集権化された指令経済を分権化し,企業を単なる行政機構から自主性をもつ経営体へと移し,〈統御された市場メカニズム〉を導入することによって,商品の質問題,経済効率問題,成長率低下問題など多面的問題の解決を企図した。そのため,(1)価格体系の見直し,決定メカニズムの改組,(2)取引税縮小の方向,(3)財政歳入面では利潤控除分の増大を目ざす,(4)義務指標の数の縮小,(5)総生産高・原価という指標を重視してきたものを総販売高・利潤指標重視に切り替える,(6)企業手もと分利潤を増加し,その労働者集団への物的刺激を強める,等々の計画経済制度上の改革を行おうとしたのである。計画経済であまり重視されていなかった〈利潤〉〈利子〉が経済効率を高め,企業が消費者の真の需要にこたえる良質の商品を責任をもってつくるためのてことなると考えられたのである。表3に示されるような財政面にあらわれた取引税を上回る利潤控除の増加は,同時に企業の手もとに残される利潤残余の増大をも伴っており,新しい経済刺激方式は3年目の68年に国有工業企業総数の54%(2万6850企業),生産総額の72%,工業労働者の71%,利潤総額の81%に達していた。
旧ソ連の統計によれば,この比率はその後も増大を続け,新方式はほとんど全国有企業に波及していったかのようであったが,実は改革はチェコスロバキア事件(1968)を契機に後退していたのである。スターリン時代に中央集権指令型の計画経済制度が導入されていた東ヨーロッパ諸国では,ソ連と時を同じくして経済改革が進められていたが,とくにチェコスロバキアでは検閲廃止,被告の人権保護,政府の党からの自立等々いろいろの分野の社会改革が一挙に推進され始めていた。言論,集会,出版,結社などの自由をブルジョア的として否定し去り,共産党一党支配体制の上にこそ集権指令経済を築いてきたソ連は,チェコスロバキアの〈人間の顔をした社会主義〉を受け入れることができなかった。
68年8月の軍事介入と民主化の挫折はソ連内でも反改革派を鼓舞するものであった。経済改革の挫折は旧来の集権制への復古,市場原理の後退を意味した。70年代以降,鉱工業生産高が見かけ上あれだけ伸びながらも,その後もなおいろいろの問題が指摘されたのはこの改革の失敗の影響といって過言ではなかった。取引税の増大などのほか,価格体系のひずみの例とされていた石炭業が,改革期以降しばらくの間だけ黒字部門となっていたものが再び赤字部門に転落したことなどにも,その事情は反映していたのである。経済改革の失敗がソ連崩壊を促進した要因の一つであったことは確かであろう。
農業
第10次五ヵ年計画期(1976-80)までは平均水準では穀物生産高は増加してきていたが,旧ソ連邦はその末期に数百年に1度とさえいわれる6年連続の凶作を経験した。年間3000万~4000万tに達する穀物輸入が日常化していた。輸入総額中のその比重も,かつての3~5%から10%にも達した。工業化,都市化が酪農品需要を激増させ,飼料需要が急増してきていたためであった。政府はすでにフルシチョフ時代から,(1)農産物買付価格の引上げ,(2)農業労働者の所得保証,(3)農作業の機械化,農業の化学化,(4)コルホーズの統合・巨大化やソホーズへの転換,(5)個人副業経営の容認・奨励など,さまざまの政策を打ち出して対処してきたが,農業はアキレス腱といわれる状況からついに脱することに成功しなかった。その原因の第1には,乾燥・寒冷地帯が広いという自然条件の厳しさを挙げねばならないが,何百万という中堅農民が逮捕,投獄,流刑などの犠牲になったといわれる農業集団化をはじめとした諸社会的原因を無視することはできない。
農企業のトップ人事はコルホーズも含め実質的には上部機関(共産党)が掌握していた。彼ら企業指導者層の多くは都市の大学農学部などの出身で顔は都会に向き,生活様式も都会風で,地元よりも上部指令に忠実であろうとする傾向が強かった。農企業下層には特別の資格をまったくもたない無資格不熟練労働者(老人,婦人が多い)が旧ソ連末期にも約半数を占めていたのであり,この農村下層とトップの間に機械手や畜産労働者が位置し,ここでも教育水準,所得,管理上の責任権限に明瞭な位階制が貫徹していた。ところが,青年たちは高等教育機関,兵役を二大パイプとして農村から脱出していたために,農企業は絶えず老齢化,弱体化の危機にさらされていたのである。また野菜,果樹,ジャガイモ,酪農などを中心に残っていた個人副業は,集団農場と補完関係もあった一面,作業の季節ピークの重なりなどから,それとの緊張関係も強かった。ブレジネフ時代以降も,政府が農業に投資してきた資金は莫大な額に上ったとみられるが,それは農産物生産高の目ざましい増大とは必ずしもつながっておらず,そのために価格差補助金の累積のような形での矛盾は深まる一方であった。旧ソ連末期に請負耕作が奨励され,実質的な集団農場離れが強まっていたところに,ソ連農業の直面するジレンマの決定的な様相が反映していた。
商業
1920年代のネップ期には存在していた私営商店も,30年代には国営や協同組合商店に取って代わられ,旧ソ連末期にはこの2類型で全取扱商品高の98~99%(うち国営69~73%)を占め,商業も集権型に徹していた。残り1~2%が自由市場での取引であったが,これはむろん一般工業製品も含む統計であり,農産物に限ればこの自由市場の比重ははるかに高かった。旧ソ連では社会給食(公共食堂)も商業に含めており,しかもほとんどの婦人が社会的職業に就いていたため,社会給食企業数は1965年の19万から87年の34.5万に増え,その就業者をも含めての〈商業労働者〉は,445万から777万へと飛躍的に増大していた。農業就業者がこの間31%から19%に低下していたのと対照的に,この分野の就業者は6%から8%に比重を増していた。にもかかわらず市場原理の導入をも意図した経済改革挫折の影響もあってか,全体としてのサービスの悪さは旧ソ連期を一貫して続いたのであり,スーパーマーケット方式の導入といった改善が一部にはみられたものの,全体としての需要過多・供給過少(とくに高品質のもの)からくる〈行列〉は結局解消しなかった。それどころか,ソ連崩壊のなかで2年間ほどは〈行列〉はかえって長くなっていた。またドル・ショップと一般商店との差異は以前よりも少なくなってきていた。
労働
国営企業の労働者総数は1965年から87年に7700万から1億1860万へと増加していた。しかし旧ソ連邦末期の工業生産成長寄与率はその圧倒的部分を労働生産性の増大に負うており,労働者数の増大による部分は小さかった(1961-65年前者60.3%,後者39.7%。76-80年90.3%対9.7%)。農業部門からの新規労働力の流入などもしだいに期待できなくなっていた。このこともあって,もともと高かった労働者の流動性が強まり,企業はその定着化に腐心していた。流動の直接の原因は,賃金水準への不満も多かったが,専門資格が生かされていないなど労働条件への不満も高まってきていた。経営,労働組合,党の三者体制(トレウゴリニクtreugol'nik)は1930年代から企業長単独責任制へと移り,現場の位階制は強まっていたが,旧ソ連邦末期でも例えば平均月221.9ルーブル(1987)の工業労働者賃金は,技術者・職員234.0ルーブル,労働者219.2ルーブルと格差表示されていた。なお労働者の半数強は婦人であったが,平等性の強い社会とはいえ,婦人にはこれらが負担であったことは,出生率の低下などに如実に反映していた。ポーランドの〈連帯〉に呼応した自主労組運動はいち早く弾圧されたことなど,〈ソ連労働者階級の状態〉も行き詰まっていたといわねばならない。
外国貿易
貿易バランスはソ連邦末期ころ,毎年40億~50億ルーブルもの黒字であったが,その内訳をみると,対西側赤字,対発展途上国・対共産圏の黒字から成っている。しかも黒字のかなりの部分は非交換性通貨によるものであり,西側諸国への支払には直接は転用できなかった。金や武器の販売を含むはずの国際収支は非公開であったが,増大する穀物輸入の支払問題は深刻なものとみられていた。石油および同製品の輸出額は総額の4割近くに達し(天然ガスも合わせると5割近い),1960年ころの20%未満と比較し,相対的には旧ソ連の工業国的性格を強めていたとさえ思われる。〈昔穀物,今石油〉の輸出構造は注目に値する特徴であった。
交通,通信
日本の面積の60倍という広大な旧ソ連では交通は重大問題であった。貨物輸送は伝統的に鉄道を主としており,第2シベリア鉄道(BAM(バム))も完成をみていた。気候条件の悪さもあり,舗装道路の発達度が低かったことからも,自動車輸送の比重はアメリカなどより低かった。石油輸出とも関係するが,パイプライン輸送量が顕著に増大していた。旅客輸送では1970年代後半に自動車が鉄道を抜いてしまい,20年前鉄道の5分の1にすぎなかった航空が鉄道の半分に達していた。
都市化が激しい勢いで進んできていたため,都市・近郊交通問題は旧ソ連でも深刻であった。マイカーは公共交通機関を優先させてきた政策的影響で,相対的には西側諸国より比重が小さかったが,通勤ラッシュ,通勤遠距離化,ターミナル駅の混雑(とくに休日前),また交通事故などの現象はここでも日常化していた。日本ではほとんど姿を消した路面電車(トランバイ)は,首都でさえむしろ延長工事をしていたが,それとともに地下鉄路線も全国的にいよいよ伸びていく傾向にあった。東京圏の地下鉄営業距離約200kmに対しモスクワ197km(1984)を比較しても,旧ソ連がすでに相当の地下鉄国であったことは明らかであろう。
通信量も爆発的ともいえる増加を示していた。電話や電報なども飛躍的に増大していた。しかし家庭の電話の普及率は旧ソ連邦末期でもまだ低く,日本の国鉄の〈緑の窓口〉にみられるようなコンピューター処理はほとんど普及していなかった。民生部門が遅れていたのである。紙幣に対し硬貨でつり銭が出る切符の自動販売機などはまったくみられなかった。また政策的な面も多少あったのであろうが,コピー機器は街にはほとんど存在しなかった。これが大量に登場するのはやはりソ連崩壊後である。このような情報処理の構造自体が経済効率の低下,ひいては体制崩壊への要因の一つになったといえよう。
執筆者:中山 弘正
社会
社会保障
社会保障はソ連がその充実ぶりを最も誇った領域であった。すべての勤労者が民族,性,信教などの差別なく普遍的に社会保障の恩恵を受けて,財源が国費と社会的資金によってまかなわれるので,勤労者の賃金からの積立ては行われていない。また社会保障がきわめて多面的であり,万能であるとも主張された。しかしながら,全国民に対する同一基準の年金制度の確立は意外に遅く,コルホーズ農民への年金を定めた1964年10月17日の法によって成就したのである。老齢年金の受給年齢は,男が60歳,女が55歳であるが,特殊のカテゴリーの者については5~10年早く支給された。受給に必要な勤続年数は男は25年以上,女は20年以上であった。これには大学や中等専門学校の在学期間も算入された。年金額は賃金の50~100%であった。法律により最低限度額と最高限度額(月120ルーブル,約3万5000円)が定められている。特別に国家に功労があった者,経済・文化・学術の面ですぐれた業績をあげた者には個人年金が与えられるが,それは一般年金の最高限度額をはるかに超えるものであり,当人の死後は家族にも与えられた。このほか,年金は廃疾者,扶養者を失った労働能力のない家族員にも与えられた。社会保険の手当としては,一時労働不能手当,婚姻・出産手当,分娩手当,埋葬手当,技能転換手当が支給された。年金と手当の決定には,すべて労働組合があたっていた。
医療は完全に国営であった。都市では4000人,農村では5000~7000人を単位に医療区を設け,総合診療所(ポリクリニカ)が置かれ,入院を要する患者は病院(ボリニーツァ)に送られた。診療所の医師は往診もするし,救急システムもある。診療や処置,手術は無料であり,入院中は薬代も食事代も無料であるが,診療所での薬代はほぼ半額が有料であった。医師は大量に養成されており,その数107万1200人(1982)は,世界の医師数の3分の1を超えていたが,社会的な評価が他の国よりも低く,給料も比較的低かった。他方でよりよい医療の質,よい医師を選ぶ患者の志向が当然に存在した。最高の医療機関はいわゆるクレムリン病院である。
教育,マスコミ,出版
ソ連では教育機関はすべて国営であった。7歳入学で10年制の義務教育が施行されていた。8年を終えたところで,そのまま残って普通総合技術学校の課程で9,10年を終える者と,職業技術学校,中等技術学校へ進む者に分かれた。普通コースに進んだ者は10年を終えると,高等教育機関を受験できる。高等教育機関は全国で891,学生数は531万5200人(1982/83)に達した。卒業には4~6年かかる。初等教育から高等教育まで無料であり,高等教育の場合は奨学金が与えられた。寮も整えられている。クラブ活動の費用もすべて国家もちである。大学入試は日本ほどではないが,モスクワ,レニングラードの両大学を中心にかなり激しいものであった。また,この2大学のほかに国際関係大学というエリート養成大学が存在した。
マス・コミュニケーションもすべて国営であった。新聞は《プラウダ》が共産党中央委員会の機関紙で,《イズベスチヤ》は最高会議幹部会の機関紙という名目上の違いがあるが,モスクワとその周辺では前者は朝刊紙で,後者は夕刊紙という程度の違いにすぎない。前者の発行部数は966万部,後者は1010万部(1989)であった。これらの新聞には,投書も取り上げられるし,ときとして地方の欠陥は鋭く批判されるが,中央政府への批判は反映されることはなかった。〈プラウダ(〈真実〉の意)はなく,ただイズベスチヤ(〈通知〉の意)だけ〉と一口話のたねになる上意下達の性格は宿命的なものであった。この点,作家同盟の機関紙《文学新聞》はときに記者の鋭い批判精神を表す記事をのせることがあった。
テレビは1975年には6000万台に達した。このうちカラー・テレビは100万台にすぎなかったが,その後急速にのびた。チャンネルはモスクワ地区では,全国共通が第1,第2チャンネルで,モスクワの地方番組が一つある。テレビはきわめて強力な政府の国民教育の手段となっており,夜9時のニュース・ショー〈ブレーミヤ〉の視聴率は全国的にかなり高かった。
ソ連では出版もまた完全に国家に独占されていた。出版にあたっては,著者と出版所との関係だけでなく,グラブリトと呼ばれる検閲機構を通さなければならないし,場合によっては関連官庁,KGB(カーゲーベー)(国家保安委員会)その他の事前検閲を経なければならなかった。したがって,出版される書物の思想は念入りにコントロールされた。
部数の決定は,需要の見込みよりは政治的配慮と計画枠とのかねあいで決定され,当局が政治的に必要と考えられるものが大量に出版される。例外的なものを除いて,売れるからといって増刷されることはなかった。したがって,大量の書物が出版されるが(1982年8万0700点,19億2500万冊),これらはパンフレットも含む数であり,全国に図書館が13万2800もあるので,個人の市民が本屋で買える本は少なかった。そのため,文学作品を中心とする評判の書物に対しては飢餓状態が存在した。本の闇市が立っているが,一般に探しているものを買うことはほとんど不可能で,友人間での貸借とタイプライターによるコピーが盛んに行われていた。
社会団体
1977年憲法第51条には〈共産主義建設の目的にしたがい,ソ連邦市民は政治的積極性および自発性の発展ならびに多様な市民の利益の充足を促進する社会団体に結集する権利をもつ〉とあり,この〈社会団体〉の性格は同第7条で〈労働組合,ソ連邦共産主義青年同盟,協同組合組織およびその他の社会団体は,それぞれの規約上の任務に照応して,国家的および社会的事業の管理に,政治的・経済的および社会的・文化的問題の解決に参加する〉と規定されていた。非国家的・非政府的な団体はソ連では自発的・自立的結社として存在しえず,国家のコントロールを強く受け,国家機構と結びついた団体としての性格をもっていた。
そのようなものとして労働組合が典型的である。労働組合は労働者・職員のほか,学生を含むが,1970年代後半にはコルホーズ農民まで含むようになった。82年に組合員数1億3120万,うち労働者・職員1億1020万,コルホーズ農民1190万,学生910万という内訳である。労働者・職員はほぼ100%の組織率である。労働組合は企業,事業所,機関,学校,コルホーズといった単位に基礎組織がつくられ,その執行部として地域委員会ないし支部委員会(メストコム)が選ばれた。この基礎組織は全国25の産業別組織にまとめられ,その上に全連邦労働組合中央評議会が立っていた。労働組合と並んで,ソビエト連邦作家同盟をはじめ,美術家,音楽家,映画人,演劇人,ジャーナリストら創造家の団体があるが,これらの団体も労働組合と共通する性格をもっていた。労働組合と創造家団体でソ連の全市民はほぼすべて組織されたことになり,これらの団体が年金,各種手当の算定から各種のサナトリウム,〈休息の家〉(保養所)への旅行の割当て,コンサートの切符の配布など,国家の与える利益,サービスの分配伝達の機構となっていた。成員の苦情を取り上げ処理する機能も果たしているが,その要求を下から結集して交渉を行うという機能は弱かった。
このほか,社会団体の中には,ソ連平和委員会や各国との友好団体などの政治的団体,医学者や科学技術者の団体,戦争に参加した元兵士の会,それからスポーツ団体,趣味の団体などがあった。この中で,1966年に創立された歴史文化記念物保存協会はロシア・ナショナリズムを基礎に,下からのイニシアティブでつくられたもので,急速にひろまり,77年には1200万人の会員を擁するにいたり,古いロシアの教会や美術品の修復・保存などの活動を行っていた。
ソ連では,憲法上,良心の自由が認められていた。個人がある宗教的信仰をもち,そのために教会で祈ること,教会で説教し,宗教的儀式を執り行うことは認められた。しかし教会堂の外で信者・非信者を問わず,不特定の人々に対し,宗教的働きかけを行う活動,布教の行為は禁止された。逆に不特定の人々に対し反宗教的宣伝を行うことは良心の自由の内容の一つとして憲法上認められた。したがって,信教の自由は制限されていたといわねばならない。信仰者の共同体としての教会は,外に向かって,国家・社会に働きかける主体ではなく,信仰者に許された避難所としてのみ存在していたのである。その限りで教会は国家により土地・建物の提供を受け,国有財産たる教会堂の使用を許されるなどの便宜を与えられていた。国家は閣僚会議付属宗務会議を通じて教会を監督した。
科学アカデミー
ソビエト連邦科学アカデミーは帝政時代からの伝統に立つ特殊な学術機関である。会員,準会員はともに,空席の生じた場合にのみ,現会員,準会員だけの選挙によって補充される。この選挙にあたっては,各種機関より候補者が推薦されるが,投票はまったく自主的・自立的に行われるもので,共産党のコントロールが及ばなかった。こうして選ばれる正・準会員は終身きわめて名誉ある地位を保証され,この会員と準会員からなる総会が科学アカデミーの方針を決定するのだが,この決定には当然,党中央委員会科学教育機関部の指導が加わる。いずれにしても,この総会の管轄下に多数の国立研究機関が存在しており,これがソ連の科学研究の主力であった。科学アカデミーはその成員の選出原理によって,非国家機関としての自立性を有していた。
祭日,休暇
祝日として休みとなっているのは,1月1日の新年,3月8日の国際婦人デー,5月1~2日のメーデー,5月9日の戦勝記念日(第2次大戦でのドイツに対する勝利を記念するもの),10月7日の憲法記念日,11月7~8日の革命記念日であった。このうち国際婦人デーが休日となったのは1964年からであり,憲法記念日は77年新憲法施行よりこの日に移されたものである。政府はこれらの祝日の前夜には食品を大量に放出し,お祭り気分を盛り上げた。政治的には,戦勝記念日と革命記念日が最も重要であるが,前者は戦没者の墓地,慰霊碑に各人が詣で,戦友たちが集まる。それに対して,後者は政府,党,軍のパレードが行われた。新しい祭日である3月8日には,当局は南の地より花を運んで売り出し,町に春の到来を告げる気分をつくり出し,また日ごろ世話になっている女性に贈るようにカードを売り出した。反対に,その直前の有給休日にならない記念日,2月23日の陸海軍記念日が男性の日となって,女性から男性へ贈物が贈られるようになっていた。
1967年の革命50周年記念日を期して,週5日労働制,土・日の2日休日制が全国一律に採用された。このほか年間の有給休暇は15日と定められている。したがって,メーデーと革命記念日の前後は土・日曜日とつなげると,長い休暇となる。休日の前日は慣習的に午前中までしか仕事が行われない。長い休暇は人々を公的生活から解放し,私生活の比重を高めることになった。
女性
ソ連では〈働かざる者食うべからず〉という原則と,戦争の影響からもくる絶対的な労働力不足の双方に基づいて,男女の別なく労働能力ある成人は必ず社会に出て働くことになっていた。このことは低い賃金の面からも必然化された。女性は全人口中で52.7%(1989)を占めているが,高等教育機関の学生の52%,中等専門学校の学生中の57%を占めており(1981/82),教育の面でほぼ男子と対等である。就業者総数に占める比率も,50.3%(1970)でほぼ対等である。女性の就業者の3分の2は肉体労働に従事しているが,しばしば建設業や道路保全のような単純重労働にも女性の姿がみられた。
女性が圧倒的な比重を占めている職業としては,看護婦,保母,秘書,出納係,店員などであるのはふしぎではないが,この国の特徴は,図書館員の95%,医師の74%,学校教師の72%が女性であり,経済専門家の82%,物理学者の74%も女性であることにあろう。管理職では商店の店長の64%,中学校の副校長の65%が女性である。最高級の知的水準を表すものとして,博士号保持者をとると13.1%が女性であり,ソ連邦科学アカデミーの正・準会員と正教授の9.9%が女性である。かなり進出しているが,ここでは男性に大きく水をあけられている(以上は1970年の数字)。政治面でみると,共産党員中の比率が1971年には22.2%であったものが,82年には27%に上がってきている。党中央委員会,中央統制委員会には第24回共産党大会(1971)の段階で21人の女性が出ている。このように,ソ連の女性は社会に出て男性と対等に働いていた。しかし,そのことは仕事と家事と出産・育児の三つをともに行わねばならない義務を課するために,女性の負担をきわめて過重なものにする結果となった。
家族
家族は1930年代に社会の基礎細胞として重視され,37年以後は,忠誠の連帯保証を行う装置としての意味を与えられていたが,スターリン批判以後は,保護政策のみ残され,束縛からは解放された。まず独身者には本給の6%にも上る独身税がかけられ,結婚が奨励された。産休は産前56日,産後56日と定められ,社会保険によりふつう給料全額分の手当が保証されている。子どもの扶養手当,多子の者に対する追加手当も定められ,とくに14歳未満の子どもの病気看護のための7日間までの有給休暇も認められている。保育所が整えられていることはいうまでもない。これらは職業をもつ女性に出産を奨励するための方策であった。平均的にはソ連では1夫婦当りの子ども数は1人ないし2人であり,3人以上の子どもの出産は60年には全体の出産の35%であったものが,82年には23%に下がっている。このため出生率(人口1000人当りの出生児数)は全ソ連邦では60年の24.9より87年には19.8に下がった。この点,中央アジアの4共和国ではなお30以上の出生率を保ち,際だった対照をなしていた。
さらに大きな問題は離婚である。スターリン時代の離婚制限などは撤廃され,1966年初めより1回の裁判による離婚手続が導入され,68年改革では裁判ぬきの離婚も認められるにいたった。この結果,1960年には人口1000人当りの離婚件数は1.3であったものが,87年には3.4とほぼ3倍に増えている。この年の1000人当り結婚件数が9.8であるので,結婚3組に対し,離婚1組の割合である。大都市ではこの比率は高く,2対1程度とみられている。この高い離婚率が女性の社会進出,地位向上と結びつき,私生活の自由とも結びついていることは否定できない。
私生活
家族の解放とともに,ブレジネフ時代のソ連に確立したのは私生活の自由である。これには,住宅建設の進展による間借生活の解消,各家族への独立住居の保証,電話の普及などの物質面の改善も影響しているが,やはり政府の側でも,国民の側でも,公と私の区別の原則が受け入れられたためである。公的には,あるいは公の場,職場や社会的会合では,公式のイデオロギーや政策路線を踏みはずすことは許されないが,私生活,自分の住居の中,親しい友人同士の仲ならば,いかような考えも表明しうるし,いかような書物も読むことができる。外国のロシア語放送(VOA,BBC,〈ドイツの波〉)も短波放送で聴くことができるし,短波付きラジオが売られている。また外国人を自宅に招くことも可能である。私生活に対する権力の介入の最大のものは同性愛の弾圧である。これはなお刑法上の犯罪とされている。もとより私生活をこえて,非公式的な見解をもった文書を流布させるとなると,当局の監視を受け,最後には抑圧された。中間的に精神病院への強制入院措置がとられることもあった。したがって,私生活の自由には外から枠が強くはめられていた。内部的には,問題化しているのは,子どもの教育の問題である。子どもは家庭と社会の双方で教育されるものであるために,公私の使い分けは子どもを混乱させることになる。
日ソ関係
シベリア戦争
十月革命によってソビエト政権が出現すると,日本は早くから干渉の動きを示し,1918年8月,アメリカとの共同出兵の形で1個師団を派遣した(シベリア出兵)。しかし,たちまち3個師団(7万2000)に増派され,アメリカが20年1月撤兵したのちも,シベリアに居座り続けた。結局,ロシア革命に干渉した列強の中で,最大の兵力を最長期間ロシアの国土に侵入させたのは日本ということになる。日本軍は22年10月まで4年2ヵ月とどまり,さらに北サハリン占領は25年5月まで続いた。日本は侵略した側であったが,1920年春,ニコラエフスク市の日本人居留民虐殺事件,いわゆる〈尼港事件〉は〈過激派〉の恐ろしさを日本国民に印象づけるために十二分に利用された。
日ソ基本条約
シベリア戦争に結着をつけ,日ソ国交を開いたのは,25年1月20日調印の日ソ基本条約と付属議定書であった。日本はソ連に1905年のポーツマス条約を認めさせ,北サハリンにおける油田の50%の利権供与を約束させた。日本国内ではコミンテルンの指導下に生まれた日本共産党が活動を続けており,知識人の間にソ連への関心がしだいに高まった。とくに第1次五ヵ年計画の開始は,昭和恐慌にあえぐ日本にも強い印象を与えた。
満州事変より日ソ中立条約へ
日本は31年満州事変を引き起こし,翌年満州国をつくり上げた。満州を通る中東鉄道は中ソの合弁経営であったため,ソ連の態度が注目されたが,ソ連は33年5月,満州国に同鉄道の売却を申し出て,宥和的な態度をみせた。ナチス・ドイツの登場によって西に危険をかかえるソ連としては,日本が次にどう出るかが最大の関心事であった。当時のソ連の新聞には毎日のように日本の記事がのった。日本の側も,満鉄調査部と参謀本部を中心にソ連の国力,抗戦力の分析を進めていた。36年11月25日の日独防共協定の締結はソ連を恐怖させた。37年7月日本は日中戦争を起こし,侵略の方向を南にとったが,その後に,38年7月には朝ソ国境で張鼓峰事件,39年5~8月には満州・モンゴル国境でノモンハン事件と,2度にわたりソ連軍との本格的衝突を起こした。このうち,とくに後者において日本軍はソ連軍の機甲兵力の前に完敗した。このことは,39年8月28日の独ソ不可侵条約の締結の衝撃とともに,対ソ冒険派を後退させた。その結果が41年4月13日に結ばれた日ソ中立条約であった。
日ソ戦争
独ソ戦争が始まったなかで,日本がドイツに呼応して対ソ攻撃に向かう可能性があらためて生まれた。このときソ連のスパイ,ゾルゲと尾崎秀実の諜報工作が行われた。結局,日本は41年12月対米英戦争に踏み切った。いまや世界中が敵味方に分かれ戦争していたとき,日本とソ連は奇妙な平和的友邦であったのである。45年2月,アメリカはヤルタ会談でソ連から対日戦参戦の約束を取り付け,その代償として,南サハリンはもとより千島列島をもソ連に与えることを約束した。ソ連は45年8月8日の準備完了と同時に,9日未明より対日戦争を開始した。戦闘は満州,サハリン,千島で,ほぼ8月18日まで続いた。日本軍の死者は8万,捕虜は59万4000と発表された。ソ連は同年4月5日,1年後に期限のくる日ソ中立条約を延長しないと事前通告していたが,もとより開戦時には条約は有効であった。したがって,ソ連の参戦が中立条約に違反するものであるのは明らかであるが,広島への原爆投下によってもポツダム宣言の受諾を決めえなかった日本政府は,ソ連参戦の報に驚き,8月14日,初めてその受諾を決めたのである。
戦後処理
ソ連は南サハリン,千島列島に加え歯舞(はぼまい),色丹(しこたん)両島を占領し,これらの島に住む日本人を日本に立ち退かせた。サハリンの朝鮮人はそのままとどめられた。さらに60万の戦争捕虜はすべてシベリアに送られ,厳しい労役につかせられた。この捕虜の帰還は49-50年になされた。またハバロフスクでは731部隊の細菌戦準備の責任を問われて関東軍首脳の戦争犯罪裁判が行われた。ソ連の代表デレビャンコ中将Kuz'ma Nikolaevich Derevyanko(1903-55)は対日理事会に参加し,しばしばマッカーサー司令部を批判して,日本の民主化,非軍事化を強めるように影響を与えた。復活した日本共産党に対しては,50年にコミンフォルムが批判を行い,活動を急進化させるように促したが,かえって占領軍の抑圧を招いた。しかし,戦後の日本の知識層,学生の間では,ソ連社会主義の権威と文化的影響は決して小さくなかった。
日ソ共同宣言
ソ連は対日講和条約の準備からは疎外され,日本はアメリカ陣営の一員として,51年9月,サンフランシスコ講和条約と日米安全保障条約を結んだ。しかし,スターリン死後の国際情勢の変化の中で,日ソ国交回復交渉が始まった。日本は歯舞,色丹両島の返還をミニマムな妥結条件として交渉にのぞんだが,ソ連が早々にこれらの島の引渡しを表明すると,国後(くなしり),択捉(えとろふ)両島も含めた4島返還の要求を出し,交渉は行きづまった。結局,56年10月19日,訪ソした鳩山一郎首相が日ソ共同宣言に調印した。これは領土問題を棚上げにした国交樹立であったが,共同宣言の中でソ連側は平和条約調印の際には歯舞,色丹両島を日本に引き渡すことを約束していた。
関係の冷却化
60年6月日米安全保障条約改定がなされると,ソ連は反感を強め,グロムイコ外相が,沖縄,小笠原諸島が返還され,外国軍隊が撤退しない限り,歯舞,色丹両島の引渡しは行わないと言明した。一方,日本では,72年沖縄返還がなされると,次は〈北方領土〉問題だという議論が台頭した。73年10月,田中角栄首相は,デタントの雰囲気と日ソ経済協力拡大の展望の中で,訪ソし,懸案問題の扱いでの多少の歩みよりを得て,文化交流面での拡大を果たした。しかし,70年代後半になると,米中,日中の接近は,かえって北方領土問題をよりクローズアップする方向に働いた。ソ連側は,米中日の反ソ連合の成立を警戒した。その中で生じたアフガニスタンへのソ連軍の侵攻は,西側に強い反発を引き起こし,80年のモスクワ・オリンピックのボイコットにいたった。81年,ついに日本政府は2月7日を〈北方領土の日〉として制定するにいたるのである。70年代はソ連社会主義の知的権威が低下した時期であり,かつ高度経済成長時代が去って,日本の経済界からは日ソ経済協力への意欲が失われていた。このような条件のもとで,領土問題による両国関係の緊張の膠着(こうちやく)化ともいうべき最悪の状況が続いた。
対話の開始
しかしながら,ゴルバチョフが登場して,ペレストロイカと〈新しい思考〉外交が開始されると,日ソ関係にも変化が生じた。86年1月シェワルナゼ外相が訪日して,外相の定期協議が復活した。5月には安倍晋太郎外相が訪ソして,はじめての日ソ文化交流協定が調印され,新方式で北方墓参が復活することになった。日本国内の専門家からは2島(歯舞,色丹)返還入口論,2島返還プラス4島(歯舞,色丹,国後,択捉)非軍事化・共同開発論が出され,論争が起こった。88年7月になると,ソ連側からもさまざまな観測気球的な提案が出されるなかで,中曾根康弘元首相が訪ソして,ゴルバチョフと領土問題を語り合った。ここにおいてソ連側の姿勢の変化が確認された。
88年12月末シェワルナゼ外相が再度訪日し,宇野宗佑外相は日本側の領土要求の根拠を体系的に説明した。このとき,平和条約締結のための作業グループを常設し,〈両国関係に存在する困難の除去〉のために討議を進めることで合意が成った。もっとも領土問題では,日本側が4島一括返還の主張に固執しているもとで,ソ連側も89年初めより,自らの主張を行う番になると,領土問題解決ずみの主張をまとめて展開した。このなかで日本外務省も89年に入ると,〈政経不可分〉論から少し変えて,領土問題と平行して,ソ連側の各種協定締結の提案も検討していく,領土問題で少し歩み寄りがあれば,経済協力もその分進めるという〈拡大均衡〉の考え方をとるようになった。しかし,ペレストロイカの進展とともに,共産党の権威がさがり,ナショナリズムが高まったソ連では,かえって領土問題での譲歩がむずかしくなるという事態が発生した。
首脳の訪日
91年4月日本に来たゴルバチョフは2島返還を約束した56年共同宣言の再確認にも踏み切ることはできなかった。彼ができたことは4島について日本との間に交渉をおこなうということと,4島へのビザなし渡航を認めることであった。海部首相との長時間にわたる交渉で視察の時間が短くなったが,日本国民は彼に好意を示した。
→ロシア →ロシア帝国
執筆者:和田 春樹
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「ソビエト連邦」の意味・わかりやすい解説
ソビエト連邦【ソビエトれんぽう】
→関連項目社会主義|民族自決|モスクワオリンピック(1980年)
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...