デジタル大辞泉 「塩」の意味・読み・例文・類語
しお〔しほ〕【塩】
2 塩味の加減。しおけ。「
3 苦労、辛苦。
「まだ世の中の―を深く味わわざる
[下接語]
[類語]食塩・食卓塩・粗塩・焼き塩・胡麻塩
えん【塩〔鹽〕】[漢字項目]
[学習漢字]4年
 〈エン〉
〈エン〉1 しお。「塩害・塩分/海塩・岩塩・山塩・食塩・製塩・米塩・無塩」
2 塩づけにする。「塩蔵」
3 酸類と金属の化合物。「塩基/正塩」
4 塩素。「塩化・塩酸」
 〈しお(じお)〉「塩辛・塩気・塩水/甘塩・粗塩・
〈しお(じお)〉「塩辛・塩気・塩水/甘塩・粗塩・[難読]
翻訳|salt
 〈エン〉
〈エン〉 〈しお(じお)〉「塩辛・塩気・塩水/甘塩・粗塩・
〈しお(じお)〉「塩辛・塩気・塩水/甘塩・粗塩・塩は食塩とも呼ばれるが,化学的には塩化ナトリウムNaClと呼ばれ,ナトリウムイオンと塩素イオンとが規則正しく配列した無色透明の正六面体の結晶で,へき開性もある。製法により結晶の外形も不定形になり,色相も種々の色を呈する。比重は2.2程度,モース硬度は2~2.5,融点は800℃付近,沸点は1440℃,飽和食塩水の氷点は-21℃である。水に対する溶解度は,温度によりほとんど変わらず,20℃で26.4%,100℃で26.9%である。純粋な塩化ナトリウムは,関係湿度75%以上で吸湿するが,一般の塩はマグネシウム塩類などの夾雑(きようざつ)物のため,これより低湿度で吸湿する。塩は独特のからみがあり,その閾値(いきち)(味覚最小濃度)は水溶液で0.01~0.1%程度といわれている。
食塩は,直接エネルギー源とはならないが,人体に必要な無機質の一つである。体液にナトリウムイオンNa⁺および塩素イオンCl⁻という形で溶けており,他の物質では置き換えができない。食塩の働きは,人体の組織内外の体液の浸透圧を一定に保つ働きをするほか,神経や筋肉の働きの調整,食物の消化(胃酸)に関してタンパク質の溶解と唾液(だえき)アミラーゼの活性化の働きをする。塩の1日の最小必要量は10g程度でよいといわれているが,食欲のための調味料としての働きがあるので,摂取量はこれより多くなる。食塩の過剰摂取と高血圧症の関係は疫学的にも明らかにされており,食塩摂取の多い地方あるいは集団は,あきらかに高血圧症の発生率が高い。血圧の調節はかなり複雑であるため,食塩と高血圧との関係は解明しつくされているわけではないが,減塩食は高血圧症に対して,明らかに有効である。
塩の資源は,地球上いたるところに存在するが,大別すると,岩塩,天然鹹水(かんすい)などの地下資源と海水資源とに分けられる。現在,利用されている塩は,図1のとおり分布し,地下資源によるものが約2/3,海水資源によるものが約1/3である。このため,塩を鉱物資源と分類することが多い。岩塩は,太古の海水が蒸発して層状に堆積したもので,地殻変動により褶曲したり,ドーム状になって存在する。それを固形のまま採掘することもあるが,省力化をはかるため,塩層に水を圧入し,鹹水(濃い塩水)として汲み上げる(溶液採鉱)のが普通である。岩塩層は,ドイツのシュタスフルト,ロシアのオレンブルグ,アメリカのオハイオ,ミシシッピなどのヨーロッパやアメリカ大陸のほか,世界各地に存在する。天然鹹水は,遮断された海が鹹湖や塩池となったり,地下に埋没して塩泉などの地下鹹水になったもので,鹹湖としてはアメリカのグレート・ソルト湖,西アジアの死海,地下鹹水としてはドイツのリューネブルク,イギリスのノースウィッチ,アメリカのシラキュースなどが有名である。
海水中に含まれる約3%の塩を太陽エネルギーと風とを利用して海水から水分を蒸発させ塩結晶を得る方法を天日製塩といい,紅海沿岸,地中海沿岸,中国黄海沿岸,メキシコ,西オーストラリアなどで行われている。天日塩では,蒸発池を段階的に設けて,濃縮を行い,その過程で夾雑物を除去し,さらに塩結晶を晶出させる。好条件では塩化ナトリウム98%程度,悪条件でも同じく80%程度の塩が得られる。メキシコのブラック・ウォリアー(カリフォルニア半島の太平洋岸)には年産500万tという世界最大の天日塩田があり,スペインのトレビエハの天日塩田,1960年代に開発された西オーストラリアの天日塩田,中国の黄海沿岸の天日塩田などとともに一大産地をなしている。日本では岩塩が見いだされていないので,海水を資源として塩を得ているが,自然条件の制約から塩田で結晶が析出するまで濃縮することが難しく,塩田で濃縮(採鹹)を行い鹹水を取り,これをさらに平がまあるいは真空式の多重効用蒸発缶で煮つめて(煎熬(せんごう))塩の結晶を得てきていた。しかし,1972年度から,塩田を使用しないイオン交換膜製塩法に全面的に転換して現在に至っている。このほか,量は少ないが,天日塩を溶解した鹹水を原料に夾雑物を除き,これを煮つめて純度の高い塩結晶(精製塩)を得ている。
イオン交換膜法とは,日本で開発,実用化された優れた鹹水採取技術で,塩化ナトリウム3%程度の海水から同じく20%程度の鹹水を採取する方法である。その原理は,図2に示すように,ナトリウムイオン,カリウムイオン,マグネシウムイオンのような陽イオンのみを通す膜(陽イオン交換膜)と塩素イオン,硫酸イオンのような陰イオンのみを通す膜(陰イオン交換膜)を交互に並べた槽に海水を入れ,両側から直流電気を通すと,電気によりイオンが膜を通って運ばれて一つおきに濃い海水と薄い海水とができる(これを電気透析という)。この20%程度の濃い海水(鹹水)を集めて,真空蒸発缶で煮つめて塩の結晶を得る方法である。この方法の特徴は,ボイラーから発生する蒸気で発電し,その電気を電気透析による濃縮に用い,余った廃蒸気を真空蒸発缶の塩の晶出エネルギーに用いることにより,少ないエネルギーで海水から直接塩の結晶を採取できることである。この方法によると,1tの塩を製造するため約200lの石油が必要であるが,エネルギー費が製造コストの大部分を占めるため,安価なエネルギー源が求められる。
日本で市販されている塩の種類と品質規格は,表1のとおりであり,並塩(なみえん),食塩,原塩(げんえん),粉砕塩などがある。このほか,特殊用途塩(グルタミン酸ナトリウム添加塩,家畜用塩),薬事法に基づく日本薬局方塩,日本工業規格(JIS)に基づく試薬塩などがある。市販塩の内容成分の例を表2に示す。
塩は生理的に必要不可欠の物質であるばかりか,古くから信仰に結びついた物質であるが,現今では,むしろ化学工業の基礎原料として重要物質であるといえる。塩の用途をその物理・化学的諸性質から分類すると表3のとおりとなる。塩の成分からみると,ナトリウムは,苛性ソーダ,ソーダ灰,重炭酸ナトリウムなどの原料となり,塩素は塩酸,有機塩素化合物,無機塩化物の原料となり,これらの薬品はさらに多くの二次製品の原料となるので,ひじょうに重要な原料であることがわかる。このほか,道路の除雪・融氷用として欧米では相当量使用されている。日本では,一般家庭用のほか,漬物,みそ,しょうゆ,水産物塩蔵などの食品工業用と,染料,顔料,化学薬品,合成ゴム,イオン交換剤再生などの一般工業用などの用途があるが,最大の用途はソーダ工業用で,総需要の80%を占めている。
世界の塩の生産量はおよそ1億9600万t(1995)と推定されており,1965年の1億1000万tから年々増加してきた。世界の主要生産国はアメリカ,中国,カナダ,ドイツなどである。おもな輸出国はオーストラリア,メキシコ,カナダ,オランダ,ドイツであり,またおもな輸入国は,日本,アメリカ,スウェーデンなどである。なおカナダは輸出入とも多い。人間1人の生活上の最低必要量は,年間約3~4kgといわれているが,実際の食料用の使用量は,生活習慣の違いにより上下するが,年間10kg程度である。塩は,ソーダ工業を主とする工業用に使用される化学工業の基本原料である。この使用量により工業化の進展を判断できるほどである。
日本での塩の需給をみると,1996年度は,931万tが消費されている。そのうち170万tが食料用を含む一般工業用,742万tがソーダ工業用に使用された。一方供給の方は,イオン交換膜法による国内生産塩136万tおよび天日塩を主とする輸入塩798万tでまかなわれた。諸外国の例をみると,アメリカにおける用途別の使用量は,ソーダ工業用と道路融氷雪用が圧倒的に多く7割以上を占める。
塩は人間生活に不可欠の物質であるから,製塩の歴史は古い。日本には,岩塩,地下鹹水などの資源がまったく存在しないため,日本の塩業の歴史は製塩には恵まれない自然条件を克服して,海水から塩を採取する歴史でもあった。上古の時代は,土器製塩あるいは海藻類を利用した藻塩焼(もしおやき),海浜の砂に付着した塩分の浸出などの原始的な方法によっていたが,9世紀ころからしだいに塩浜(しおはま)の形態が整い,入浜式(いりはましき),揚浜式(あげはましき)の塩浜が出現した。とくに入浜式では,17世紀初めに大規模な入浜式塩田が開発され,立地条件の恵まれた瀬戸内海沿岸を中心に発達し,いわゆる〈十州塩田〉を形成した。一方,揚浜式は日本海や太平洋の沿岸に発達した。明治年間に入っても生産状況は大きな変化がなかったが,日清戦争後は,塩価の高騰と芽生えつつあったソーダ工業用に対する安価な輸入塩の需要が急増したため,国内塩業の存立が危うくなった。これに加えて日露戦争の戦費調達のため1905年から塩の専売制が施行された。第2次世界大戦から戦後にかけて,深刻な塩不足の時代に見舞われたが,その後,国内塩の増産対策が進められ,1952年ころから枝条架併用の流下式塩田により,生産能力は飛躍的に増大した。しかし,生産費は輸入塩に対抗できなかったので,59年には〈塩業整備臨時措置法〉により,生産性の低い塩田を廃止し需給の均衡がはかられた。一方,このころから工業化試験を開始したイオン交換膜法は,昭和40年代に至って一段と進展をみせ,その特性を生かして大規模に統合することにより大幅なコスト・ダウンの見通しが得られるようになったので,71年には〈塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法〉により,従来の塩田を整理して大規模なイオン交換膜製塩法への全面転換をはかった。これにより,日本の製塩が農耕的産業から近代的な化学工業へ転換した意義は大きい。
専売制下の塩の流通経路について述べると,買い入れた塩は,公社から問屋である卸売業者(元売人)に,さらに販売業者(小売人)を経て,一般消費者へ売り渡される。卸売業者への売渡し価格は,公社により全国一本建てに決められており,消費者価格は,これに手数料を加えた価格(制限価格)となっている。ソーダ工業の主原料である塩は,当初から安価な輸入塩を使用している。この塩には1917年から自己輸入制度が適用されている。自己輸入制度は,ソーダ会社が専売経費を納めて,自己の責任において,塩を直接輸入できる制度である。この制度は,戦争のため24年に廃止されたが,56年に再開された。
塩専売制度の制度改革問題については,95年2月に閣議決定された〈特殊法人の整理合理化について〉において,〈塩専売制について,所要の措置を講じて廃止し,塩専売事業を民営化する。そのため,今後の塩事業のあり方について早急にたばこ事業等審議会の結論を得る〉こととされた。95年11月には,大蔵省たばこ事業等審議会の答申がなされ,〈塩専売制度を廃止し,原則自由の市場構造に転換する〉との方向が示された。96年に塩事業法が成立し,97年4月1日,塩専売制度は廃止された。廃止にともない,現在は塩事業法にもとづき塩の製造・販売を行う各事業者が販売を行っているが,これまで日本たばこ産業(株)が小売店を通じて販売してきた〈専売塩〉と同規格品の塩については(財)塩事業センターが取り扱う。
→塩田
執筆者:増沢 力
縄文時代すでに関東,東北では,海浜の集団が土器によって生産した塩を,内陸部の他集団と交易していたことが推定される。弥生時代には西日本において,首長の統率または指示に従って,海浜集団は農,漁のかたわら自給以上の塩を作り,他集団に搬出していたようである。古墳時代にはこのような集団内分業がより明確化し,その後期には備讃瀬戸・淡路・紀伊・若狭から畿内へ,能登から北陸・東国へ,知多・渥美から東海・信濃・関東へ,天草からは九州へ流通したと推定される。律令時代には製塩集団は海人(あま)部に編入され,政府が塩流通の中枢となるが,これは前代の流通形態の完成といえよう。奈良時代より塩田法が展開し,貢租塩とは別に農民的な流通もみられるようになる。平安中期以降は荘園本所の寺社,貴族が流通の機軸となるが,その剰余部分は代官,豪民により自由に交易され,また都では年貢塩の余剰が市へ放出された。
鎌倉時代になれば,荘園の貢納塩も本所分のみ現物納とし,他は市で売却し銭納するようになる。したがって本所から交通自由の権利を保証された廻船による交易が一般化し,港から都市へは馬借(ばしやく)が,内陸部へは塩座商人が運送販売の特権をもった。室町時代の流通は塩座を中心に独占的に行われた。塩座は諸座の中心をなしたが,奈良,京都,山城木津,近江保内,近江八幡などの塩座が著名である。塩座には若狭,伊勢,瀬戸内から塩が搬入されたが,瀬戸内からの塩が量的に他を凌駕(りようが)していた。1442年(嘉吉2)兵庫北関を通過した塩の量は10万石余を数えうる。室町末~戦国時代における京都への流通ルートは,瀬戸内→淀川→淀魚市→京都,北陸→敦賀・小浜→近江→京都,東海→不破関・八風街道・千種街道・日野など経由→近江→京都であったが,この時期になると,本所と座の関係は形骸化し,地方の座は戦国大名の御用商人的位置へ変質していく方向がみられる。また楽市・楽座政策は,むしろ塩座すなわち御用商人の特権を新たに確認するような作用を及ぼした。
→塩売
江戸時代にはいると,寛文年間(1661-73)には全国海上交通網の整備によって,瀬戸内塩が全国市場に流通し,全流通量の90%を占めるようになり,恒常的に塩廻船が需要地に直送した。生産地からの出荷は,貢租を納めたあと自由搬出される型と,藩専売制によるものとがあった。後者は金沢,仙台などのように自領産塩を貨幣または米をもって藩に収納し,一定価格で特定の民間販売機関によって領民に配給する型と,赤穂,徳島のように生産塩を領内または大坂,江戸などの塩会所で,藩札をもって買い上げ,これを仲買に落札払いにし,塩代銀の正貨収納を企図した型とがあった。流通手段の中心は廻船であり,内陸部へは高瀬舟,駄馬・牛,人の背が利用された。江戸時代の塩の流通路はほぼ図3のようになる。
→塩専売制度
塩の流通は明治初年一時混乱し,1890年ころまでに旧来の塩問屋,仲買などの80%は新勢力と交替した。1890-1900年には汽船,鉄道が発達し,全国的塩配給経路は大きく変わり,また1893年の〈取引所法〉によって,数ヵ所の塩取引所が設置され,塩価の動揺をもたらした。また日清戦争後の労賃・燃料の高騰,安価な台湾塩の移入は塩業界を混乱させた。日露戦争勃発にあたり,政府は1905年塩を財政専売の対象とし,当初は塩の収納のみを政府がやり,販売は塩商の自由にまかせた。当然塩価の高騰をきたしたため,13年遂に回送費のすべてを政府負担とすることによって価格の低減と均一化を実現することができた。専売制施行によって塩問屋ないし流通関係者は窮地に陥ったが,この救済策として塩回送会社の設立を指導し,19年赤穂,尾道,三田尻,坂出,撫養(むや),味野の6社を合併して日本食塩回送(株)を作らせた。この機関が各地の塩を各地の元売さばき人に配給し,これを小売人が消費者に販売するという流通ルートが確立した。31年以降,工業用塩の需要が急速に増大するが,一般用塩は近海(関東州,華北,台湾)塩を主とし,工業塩は自己輸入制度によってソーダ工業会社が,世界各地から買い付け,最寄りの港湾や駅に臨時の塩引渡場所を特設して引き渡した。輸入塩の回送は前述の回送会社と大日本塩業(株)が分担した。第2次大戦中と戦後の混乱期を経て,49年専売局は日本専売公社となるが,輸入塩の需要はますます増大する。政府は原則として直輸入せず,輸入委託業者を限定し,無用の買付競争を排除した。輸入塩は指定された港で1船を単位に公社に引き渡される。輸入塩の増加に対して,メキシコ,オーストラリアに日本商社が現地資本と合弁で,塩業開発を行った。現在輸入塩はソーダ工業用塩と再生加工塩となっている。
→専売
自然物雑食の段階においては,動物の臓器を食べることによって塩分補給はできたろうが,獣魚肉の保存や薬用,儀礼用の塩は必要であったと思われる。農耕生活が開始されると,獣魚は肉のみを食べ,植物質食料の摂取が多くなり,食用塩の需要は増大したであろう。古代になると塩の利用の実態がかなり明らかになる。塩の種類としては,舶載塩,固型焼塩,粒状焼塩,生塩,鹹水などが推定される。舶載塩は儀式または薬用に,固型焼塩はそのままでは儀式用に,また給料や神祭・祓・供養・修法・写経・弔慰などの報酬として固型のまま,あるいはつき砕いたものが与えられ,これは最終的には食用となったであろう。粒状焼塩も同様であり,生塩は庶民の食用に,鹹水は薬用,調味料などに利用されたと思われる。食用としては,そのまま調味料として,また調味料であったひしお・未醬(みそ)類の原料として,また保存用としては生菜・魚介・鳥獣肉などの塩蔵,塩辛・鮨,あるいは索餅(むぎなわ)(そうめん)製造,楚割(すわやり)(乾蔵)にも用いられ,薬用としては内服・外用・保温に利用されている。ほかには鉛酢(えんさく)料,金焼料,染色,石灰製造,鍛冶などに使われたことがわかる。以上のごとき利用は基本的には中世まで大きな変化はなかったようである。
近世における生産過剰にいたる塩生産の発展は,食用以外に多方面の利用を展開させた。すなわち医療用として,(1)内服 焼塩または食塩を産婦に,また悪酔予防・下痢止め・カイチュウ駆除などに服用,塩水(湯,茶)を便通・下剤・泥酔・宿酔・胃薬中毒に際しての催吐剤,保温・風邪・喘息に飲用した。(2)外用 傷口消毒・霜焼け・雪焼け・虫歯予防・歯磨き・虫歯痛止め・打身・くじき・あかぎれ・口中止血・やけど・皮膚病・神経痛などにそのまま,あるいは塩水・塩湯として洗眼・うがい,塩湯で赤子の入浴,婦人病・神経痛・保温・皮膚病・疲労回復などの治療に用いた。(3)罨法(あんぽう) 腹痛・痔疾・打身・くじき・やけど・頭痛・腰痛などの罨法に,また氷囊に塩を入れ熱さましに利用した。また動物の治療にも同様な利用がみられた。また保存用としては食料のほかに,獣皮保存,死体保存などにかなりの量が使用され,家具の保存や手入れに,瀬戸物・象牙・金物・木製品・竹細工・真鍮・鉄器などを磨くために使われ,洗濯にも油あか,血痕をおとすために,色物の防褪(ぼうたい)にも利用した。
執筆者:広山 尭道
ナトリウムが,生物,水,土,石などから補給されるならば,人にとって塩そのものの採取は生理的にはかならずしも必要でない。旧石器時代や中石器時代に製塩の痕跡がみられないのはそのためである。しかし,塩の用途はきわめて多方面にわたり,調味料としての塩味,家畜用,皮革なめし,医薬,保存防腐用などの効用が早くから知られている。これらの効用のすべてが同時に発見されたわけではないにせよ,生活の発達の中でしだいにそれらが認識され,安定した供給が要求されるようになり,海水,塩泉,岩塩などの自然資源をひかえた集団が製塩を開始した。それは日本では縄文時代,ヨーロッパでは新石器時代に入ってからのことである。
考古学的に証明されている最古の製塩法は土器製塩法であり,土器に塩水をいれ煮沸して塩をとる方法で,原初的な製塩法として原始から古代にかけて世界の各地で行われた。現在知られている地域は,日本,メキシコ,アメリカ,ヨーロッパ各地,黒海東岸などである。日本では平安時代,ヨーロッパではローマ支配の時代にほぼ終焉(しゆうえん)した。煮沸(煎熬)にともなって,製塩土器の器壁中にも食塩などの各種結晶が生じ,また長時間にわたる塩水の加熱継続や結晶塩の取出しなどのため,容易に剝離,亀裂,破砕が生じる。したがって繰り返しての使用ができないため,消耗品的生産用具として莫大な量の土器が製作,使用,廃棄された。そのため,器形は特殊的に単純化し,文様などの装飾的要素をもたないのが普通である。
日本では縄文時代後期後葉に関東地方の茨城県霞ヶ浦沿岸で初現し,やがて東北の宮城県松島湾岸を中心に青森県下北半島・津軽半島にまで広がったが,西日本では弥生時代中期中葉に,岡山県児島地方を中心に出現した。東日本と西日本との系譜関係は今のところ知られていない。
弥生時代後期には,岡山県,香川県,徳島県,和歌山県,兵庫県,大阪府など瀬戸内東部に広がり,ついで古墳時代を通じて九州天草地方から太平洋岸では,愛知県知多・渥美地方,日本海岸では能登・佐渡にまで拡大し,最盛期を迎えるとともに,製塩土器の器形や遺跡構造などにおいて地域的特色を形成する。
7世紀ころから,新しい大型煎熬容器が出現したとみえ,土器製塩はしだいに衰退していくが,福井県若狭地方や愛知県知多地方などでは8世紀,東北地方では9~10世紀にかえって盛行する。瀬戸内などの地域では,奈良時代に鉄製の塩釜の記録がみえ,また塩浜を思わせる記事が知られていることから,いち早く土器製塩法を脱し,原初的な塩田採鹹法と結んだ大型容器による煮沸煎熬が開始されたと考えられる。
土器製塩遺跡の構造は,香川県直島町喜兵衛島遺跡を例にとると,遺跡のほぼ中央に炉があり,その回りに作業面が広がり,ついでその外方に莫大な使用ずみの製塩土器,灰,炭などの捨て場が形成される。炉は石組みのもの,石敷きのもの,灰土で壁をつくるものなどあり,大は福井県おおい町の旧大飯町船岡遺跡の長径約5m,短径約1.8mの石敷炉,小は香川県坂出市ナカンダ浜の長径約1.0m,短径約0.7mの灰土炉などがある。製塩土器でつくられた塩が,さらに加熱固型化され,いわゆる焼塩にされる場合もあり,古代の文献にみえる顆(か)あるいは果という計量単位は,こうした固型焼塩の存在を示すものであろう。したがって,製塩土器が内陸で炭灰とともに発見されることがあるのは,単に運搬容器としてだけでなく,搬入先で焼塩が行われたことをも示す。
執筆者:近藤 義郎
塩が調味料ならびに栄養にとって必要な食物であることは,ひじょうに古い時代から知られていた。しかし原始時代の人間が塩を製造していたかどうかについては,はっきりしたことは知られていない。しかし彼らも塩けのものを必然的に要求していたに相違なく,おそらく塩けを多くふくんでいる食物を摂取することによって栄養のかたよりを防ぎ,あるいは死海のように天然に塩が露出している地方ではこれを採取していたのであって,彼らはまだ塩をつくるにはいたっていなかったであろう。事実また肉食をしている地方では,肉を生のままや,あぶり肉にして食っている場合にそのうちの塩けは失われないから,とくに塩を求める必要がない。したがって古代においても塩をぜんぜん知らない民族があり,新大陸の一部やインドでも塩はヨーロッパ人によってはじめて紹介されたのである。アフリカの奥地では現在でも塩は一般人の食物でなくて,富者のみが利用しているぜいたく品にとどまっている。前1世紀のローマの歴史家サルスティウスもヌミディア人が塩を決して用いていなかったことをあげている。
しかし塩が調味料以外に食物の保存のために必要であることが理解されるようになってから,塩に対する需要はひじょうに高まった。この利用が最初に起こったのは主として海岸や塩湖の岸辺で,そこでは大漁のあった場合に不漁にそなえ,その漁獲物の一部を乾魚にするか,塩漬にして保存した。ときにはこの沿岸住民は,平地や山地に住んでいた狩猟民に,彼らの武器や野獣や装飾品と交換に乾魚や塩を供給した。そしてまた狩猟民も大きなヤギュウや大シカを狩猟によって手に入れたときは,不猟のときの用意にその肉の一部分を保存する必要があったから,塩を必要とするにいたった。一方内陸の農耕民にとっては,元来植物性食物は塩けが不足し,肉食をしている人間以上に塩は不可欠な栄養物であった。したがって原始時代においては塩が産出される沿岸地方から離れた内陸に住んでいた人間のほうが,より多く塩を要求し,ことに農耕文化の発展が塩をまったく日常的な食物に高めていったのである。その結果,塩の産地である沿岸地方(後には岩塩の出る地方)と,狩猟民や農耕民の住所たる平地・山地地方の間に塩の交易が行われた。かくして古くからヨーロッパ,地中海沿岸地方,さらに近東諸国やアジアを通じて塩の交易路がリレー式にのびることになった。しかし塩は,コハクや火打石や真珠やその他の装飾品とちがって,個人で持ち運びするのに適しないものであるから,一定量の貨物として運搬されたに違いなく,古い時代においては道路が発達していなかったから,主として河川が利用され,あるいはその沿岸にそって家畜の背にのせて塩の荷が運ばれた。こうしてすでに青銅器時代の末期ころには,塩は西アジアからドナウ川の舟運をかりて中央ヨーロッパへ運ばれ,歴史時代になってもヨーロッパやアジアの塩のできない地方にあっては,この塩の交易路に塩の供給をあおいでいた。このような事情のために古くから,塩は生活の必需品のために交換の媒介をする一種の貨幣の役目を果たすようになり,ときには塩を固めたものが貨幣として使用されていた。ローマ時代には役人や軍人に塩が支給され,帝政時代にはこの塩の代りに貨幣が支給されるようになったが,こんにち俸給を意味する英語のサラリーsalaryは塩の支給を意味するラテン語のサラリウムsalariumに由来している。チベットでも13世紀ころに塩が貨幣として使用されていたことがマルコ・ポーロによって報告されている。古代ギリシア時代においてもギリシア人やトラキア人は,奴隷と交換に塩を売っていた。中世にはスラブ人は中央ヨーロッパの岩塩を手に入れるために,奴隷や家畜や武器や蠟を交換のためにもってきた。また中世ヨーロッパのユダヤ人は,これらの塩の交易路を利用して,彼らの商品を売りさばき,それによって巨利を博していた。ベネチアの海港都市も6~7世紀ころにはまだ小さい漁村であったが,そのころから海岸で塩をとり,その塩をビザンティンその他の東方諸国に船で売り広め,その利益によってしだいに繁栄した。
塩はまた古くから支配者がその人民から取り立てる貢ぎ物のおもな対象であって,最近までエチオピアでは塩が税金として支払われていた。ときにはまた領主は人民の塩の使用に対して課税したこともあったが(塩税),これは人民,ことに貧乏人にとっては大きい苦痛であり,不平や反抗がしばしば生じた。
古代における塩の製法には,より古くは海水あるいは鹹湖の水を蒸発させて採取する方法があり,塩田法もその一つであって,ゲルマン人は木を燃やしてそれに海水をかけ,塩けを多く含んだ灰を処理して塩を得ていた。他の方法は岩塩をそのまま採掘する方法であり,のちには岩塩の産出する場所に水をそそいで飽和溶液をつくり,それをポンプで吸い上げてから,これを蒸発させた。この両者の製造法は少なくとも先史時代にさかのぼり,中央ヨーロッパでは岩塩の採掘は鉄器時代にすでに行われ,ハルシュタットの岩塩鉱山では25度から60度の角度で入口から立坑が掘られ,岩塩のある場所では横坑が各方向にうがたれていた。そしてその最も長いものでは水平に390m,地表からは100mもあり,そのなかには幅12m,天井までの高さ平均1mの部屋ができていて,支柱も盛んに使われていた。
先史時代以来これらの塩の生産地は重要な交易の中心地として早くから人口が集中し,文化が開かれていた。今日でもそのなごりは地名のうちに残っていて,ドイツではハルあるいはハレ,アングロ・サクソン語ではウィッチは塩水を蒸発させて塩をつくる家をしばしば意味していて,ドイツの都市や町の名前であるハル,ハレ,ハルシュタット,ライヘンハル,イギリスではドロイトウィッチ,ナントウィッチ,メースウィッチなどは,少なくとも鉄器時代にそれらの場所で製塩が行われていたことを物語っている。さらにスペインでも古代に大きい岩塩層が発掘され,西アジアでは砂漠のオアシスにおいて塩が産出し,アフリカでもリビア砂漠には大きい塩の堆積層があり,古代エジプトの塩の重要な供給源をなしていた。またナイル川三角州では海水から塩が採取され,調味料以外に魚類の保存に用いられた。また少量であったが金の精錬,ガラスの製造,治療剤にも用いられ,ときには油灯の炎を黄色にし,もっと明るい快適な照明を行うために使用され,またその防腐性を利用してミイラをつくるときにも死体を塩水に浸していた。
執筆者:加茂 儀一
錬金術における硫黄・水銀・塩の〈三原質〉のうち,塩は硫黄と水銀の中間項として,両者を媒介する運動と考えられ,それを通じて水銀(質料)が硫黄(形相)に結びつくとされる。そのため,硫黄を王,水銀を王妃で表す婚姻図において,塩を僧侶の姿で描き,両者を結びつける役割をもつことを示す場合もあった(B. ウァレンティヌス《哲学の十二の鍵》)。ただし,この中間項は他の2項ほどの重要性をもたず,硫黄・水銀の二分法が取られることも多い。錬金術における他のシンボル同様,塩も多義的で,その特性規定は一定せず,〈可溶塩〉〈赤い塩〉〈賢者の塩〉など,多種類に区別されている。
塩はまた,とりわけ聖書において高い象徴性をもって語られている。そこでは神と人との間に不壊(ふえ)にして聖なるきずなが〈塩の契約〉ということばで表され(《民数記》18:19,《歴代志》下13:5など),ヤハウェ自身が供物に塩を加えることを命じ(《レビ記》2:13,《エゼキエル書》43:24),さらに塩によって悪しき水を清め,死と流産の穢(けがれ)をはらう(《列王紀》下2:20)ことが述べられている。新約聖書の有名な一句〈汝らは地の塩なり〉も以上のような旧約における不変の契り,神の食物,浄化力の象徴としての塩のイメージが重層的に内面化されたものとして読むことができよう。ところで,古代ギリシア・ローマ世界でも塩は変わらぬ友情の象徴で,〈パンと塩〉は歓待のしるしとされたが,前述の錬金術における対立物の媒介者としての塩と考えあわせれば興味深い。一方,塩は荒廃,不毛,死の象徴ともされ,聖書には破壊した町に塩をまく話(《士師記》9:45)や,滅びゆくソドムとゴモラの町をふり返ったため塩の柱と化したロトの妻の話(《創世記》19:26)などがある。
なお,スタンダールの《恋愛論》は,塩の比喩が文学において最も印象的に語られたものの一つであろう。ザルツブルク(ドイツ語で〈塩の町〉)の塩坑に投じられた小枝がつける美しい塩の結晶を,恋愛心理(結晶作用crystallization)と結びつけた個所は,比類のないイメージをわれわれに喚起してやまない。
執筆者:有田 忠郎
味かげんを意味する塩梅(あんばい)の語が《書経》にみえ,〈酒は百薬の長〉という有名なことばの対句に〈塩は食肴(しよくこう)の将〉と《漢書》で使われるように,中国でも塩は当然民族の歴史とともに古く,またきわめて重要視されてきた。黄河文明が発生した地域には山西省の大塩池があり,これを握ることが権力者の一条件で,〈禹貢(うこう)〉が冀(き)州(山西)を帝都とし,周や秦がそこに近い陝西を根拠とするのも当然であった。漢民族の支配領域の拡大につれ,山東,淮南(わいなん)など海岸線の海塩や,四川の井塩(せいえん)などが登場する。しかし,海岸線は広大な中国全体からみれば,むしろ短くかつ東に偏し,それ以外の内陸塩産地は限定されていた。こうした地理的条件と貧富貴賤(きせん)を問わず誰もが一定量を必要とする条件,そして皇帝の全国支配が結びつき,紀元前の漢代から塩の専売が出現する。とりわけ唐代8世紀半ば以後は,塩は単に食卓上の問題だけでなく,政治,経済,社会と深く関係する重要な要素となった。
〈金持ちは白い粉の塩,中層は茶色,貧乏人は黒い石ころのような塩〉という朱徳のことばは,旧中国における塩と中国人の食生活の関係を端的に表している。白い美しい塩は貴重で,薬品としての価値も古くから高く,粗悪な塩は調味料に姿を変えたり,塩漬や加工食品に使われたりして,食生活を結果的に豊かにしてゆく役割をも果たした。古来,中国の塩は,池塩,海塩,井塩,土塩などに分類される。池塩は山西省南西端の安邑(あんゆう)・解両県にまたがる東西40km,幅6kmの大塩湖から産出し,陝西,山西,河南の消費をまかなうことができた。また陝西の長城線以北には,唐代に名を知られるものだけで13の塩湖があり,良質の青白塩を産した。海塩は末塩とも呼ばれ,東部海岸で生産される塩だが,専売法とも関係して,北から長蘆(ちようろ)(河北),山東,淮南,両浙(りようせつ),福建,広南の産塩区に分かれる。井塩は四川の嘉陵江流域,金沙江と岷江(みんこう)の合流点や雲南の地下塩泉から,特殊な井戸を使って濃厚塩水を汲みあげて作る。土塩は山西省の北部各地に多く,硝土と呼ぶ塩分を含む土から精製する。このほか湖南に岩塩,湖北省の応城県にはセッコウ塩という食塩鉱があるが量は少ない。塩の品質は同じ場所でも時代によって違いがあるが,天日製塩の海塩や解池塩は結晶状で,解塩は茶色を帯びている。蒸煎した海塩や井塩の上質のものは純白だが,多くは不純で,おまけに専売下の旧中国では,運搬の途中で不純物が添加水増しされるため,末端消費になると朱徳のいうようになる。
製塩法は天日製塩と蒸煎製塩があり,晒(曬)(さい)と煎の2字をあてる。晒法は主として長蘆,山東や福建,広南の海塩と解州塩池や土塩精製で行われ,煎法は淮南,両浙の塩産地と井塩でみられる。天日製塩は広い塩田を使うものが普通だが,両浙地方の一部には板晒(ばんさい)という板を使う方法もある。塩田に海水を導入し,海水溜,蒸発池,結晶池へと濃度をあげて塩水を導き結晶させる方法は日本と同様だが,長蘆塩田のように,地形の関係で揚水に風車を使うなど,地域による差異はある。解池の塩田も基本的に同じだが,田畝のように (うね)や塍(あぜ)をつけ,4月になると池塩水をそそぎこみ,濃縮を繰り返して結晶を作るが,とくに夏,南の中条山から塩南風が吹くと2~3日で塩が結晶する。煎熬の方法は全国ほぼ同じで,海岸の塩田に砂や灰などをまき,海水を導いて塩分を付着させる。それを集めて水をそそいで濃い滷水(ろすい)を作り,平らで大きいなべで煮て水分を蒸発,塩を精製する。滷水の濃度を計るのにはハスやモモの実が使われた。煎熬の燃料はアシなどの草で,天日製塩にくらべて経費がかさんだ。四川で塩井を掘って,地下の塩水層から採取する方法は古くからあり,後漢時代の画像塼(せん)にもその工程が描かれている。おもな井戸の数は唐代に639とされるが,掘削井は深さに限界があり,大量の塩をとることは困難であった。11世紀半ば,北宋の皇祐年間(1049-53),太い楠竹(なんちく)を使い,水鉄砲の原理を応用した卓筒井(たくとうせい)の技術が開発され,地中深い塩水層の汲出しが可能になった。地上高くやぐらを組み,頂点に滑車をつけ,長いひもをつけた竹筒(大量の竹を使って作る)を下げ,これを土中深く塩水層まで落としこみ,塩水を吸入して引き上げ,それを蒸煎して塩とする。清代から民国の自流井では,井戸の深さは800m以上にも達し,林立する高さ5mのやぐらから轟音とともに落下し,また巻き上げられる卓筒井の数は1000もあった。なおここでは蒸製燃料に天然ガスをも使っていた。
(うね)や塍(あぜ)をつけ,4月になると池塩水をそそぎこみ,濃縮を繰り返して結晶を作るが,とくに夏,南の中条山から塩南風が吹くと2~3日で塩が結晶する。煎熬の方法は全国ほぼ同じで,海岸の塩田に砂や灰などをまき,海水を導いて塩分を付着させる。それを集めて水をそそいで濃い滷水(ろすい)を作り,平らで大きいなべで煮て水分を蒸発,塩を精製する。滷水の濃度を計るのにはハスやモモの実が使われた。煎熬の燃料はアシなどの草で,天日製塩にくらべて経費がかさんだ。四川で塩井を掘って,地下の塩水層から採取する方法は古くからあり,後漢時代の画像塼(せん)にもその工程が描かれている。おもな井戸の数は唐代に639とされるが,掘削井は深さに限界があり,大量の塩をとることは困難であった。11世紀半ば,北宋の皇祐年間(1049-53),太い楠竹(なんちく)を使い,水鉄砲の原理を応用した卓筒井(たくとうせい)の技術が開発され,地中深い塩水層の汲出しが可能になった。地上高くやぐらを組み,頂点に滑車をつけ,長いひもをつけた竹筒(大量の竹を使って作る)を下げ,これを土中深く塩水層まで落としこみ,塩水を吸入して引き上げ,それを蒸煎して塩とする。清代から民国の自流井では,井戸の深さは800m以上にも達し,林立する高さ5mのやぐらから轟音とともに落下し,また巻き上げられる卓筒井の数は1000もあった。なおここでは蒸製燃料に天然ガスをも使っていた。
旧中国では塩の直接生産者は竈戸(そうこ)(海塩),畦戸(けいこ)(池塩)などと呼ばれ,とくに専売法下では一般民戸と区別され,きわめて重い労働に従事させられるのが普通であった。四川の井塩では,とくに明代以後,多数の零細労働者を集め,奴隷労働的な経営が行われてきた。塩の収益は国家財政と深くかかわるが,専売塩が高く粗悪なのに比し,密売塩(私塩)は安く良質で,やみ塩は全国消費量の半分にも達し,さまざまの問題をひき起こした。また専売に寄生した特許商人(塩商)たちが,その利益を文化,芸術へ投入する現象なども清代に顕著にみられた。
→専売[中国]
執筆者:梅原 郁
塩は日本人にとっては精神的・信仰的生活のなかで多様な機能をもってきた文化要素の一つである。したがって,塩の流通網は古くから組織されていた。富山県から長野県へは歩荷(ぼつか)と呼ぶ徒歩の運搬業者により,愛知県三河地方から長野県にかけては中馬(ちゆうま)という制度によって運ばれたし,東北の南部地方へは野田ベコと呼ばれるウシを使った業者があたった。こうした業者のいなかったところは,塩売という行商的な小売商人がいて,専売法施行までその流通を支えてきた。塩を運搬したり売り歩く人に対しては,彼らが呪術(じゆじゆつ)的な霊力をもつ者として畏敬しており,きげんをそこねないように気を使った。九州地方では弱い子がいると,塩売の人と仮の親子関係を結ぶとじょうぶに育つという習慣もあった。その背景には塩が不浄や穢をはらうという,日本人の間にみられる呪術的観念がひそんでいると考えられる。祭りのときの供え物から,神社など聖地の清め,神輿の清めをはじめとして,年中行事や冠婚葬祭などにあたって塩を清めとして使うことは多く,力士が土俵に塩をまき,料理屋などで盛り塩をする風習もある。また,海に近い所では海水や海藻,石や砂そのものを用いている。これらは,海が陸地から川を通じて送られてくるあらゆる汚いものを浄化し,人間に多くの幸を与えるという,海の清浄性と豊饒(ほうじよう)性の象徴を塩に求めたためといえる。したがって,塩を生活物資として重要視するだけでなく,塩が神から贈られたものとして尊重する観念が強く,〈塩を粗末にすると罰があたる〉と各地でいってきた。生理的に塩を要求するのは人間だけでなく,牛馬をはじめとする動物にも見られる。夜間に塩を移動することを禁じ,夜間に塩の名を口にするときには〈波の花〉といい換えるのは,ヤマイヌとかオオカミなど危険な動物に気づかれぬよう心をくばった古代の人々の習慣のなごりとみることができる。
執筆者:坪井 洋文
料理の塩分濃度はほぼ1%が基本である。これは人間が適当な刺激として感じる塩の濃度が1%程度であるためで,汁物のそれも1%前後である。煮物は塩分を1.5~2%加えるが,材料の成分で煮汁の塩分が薄められ,料理そのものは1%以上にならない。味の濃い塩辛,つくだ煮は少量ずつしか食べられないし,同時に食べる飯や唾液によって薄められる。塩を他の味成分と混合使用すると,対比効果または抑制効果が現れる。対比効果としては砂糖との混用が代表的なもので,濃度0.1%で単独ではほとんど味が感じられない程度の塩でも,濃度12%前後の砂糖液に加えると,砂糖の甘みが強まる。汁粉に少量の食塩を加えたり,シソの塩漬をつけるのは対比効果を期待したものである。だし汁に少量を加えてうまみを引き立てるのも対比効果である。食酢に塩を加えると,刺すような酸味が穏やかになるのは抑制効果であり,食酢10,塩2の割合に混ぜて作る二杯酢や梅干しの例がこれにあたる。食品貯蔵に利用されるのは,加塩によって浸透圧が高まり,微生物の発育が阻害されるためである。また,塩にはタンパク質変性作用があり,例えば卵を加熱調理する場合,食塩を入れると熱凝固が促進され,身じまりのよい卵焼きやオムレツができる。同じく卵をゆでるとき食塩を加えておくと,殻が割れても卵白がすぐ凝固し,内容物の流出を防ぐ。漬物では,塩が材料に作用して脱水し,防腐性を与えると同時に材料をしなやかにし,発酵作用を調節して,漬物特有の風味を作り出す。パンやめんを作る場合,食塩を加えるのはグルテンに粘性,弾性を増加させ,生地の形成をよくするためであり,練製品製造時の加塩は魚すり身の弾力を増す。青菜をゆでるときに加えるのは,緑のクロロフィルの退色を防ぎ色を美しく仕上げるためであり,リンゴを食塩水に浸すのはポリフェノール酵素作用を阻害して褐変を防止するためである。果実や野菜のジュースを作るときに加えると,ビタミンCの酸化を防止すると同時に味をよくする。そのほか,サトイモのぬめりを取るときにも使われるなど食塩と食品のかかわり合いは深い。
執筆者:菅原 龍幸
金属または塩基の陽性成分(たとえばNH4⁺,C6H5NH3⁺など)と,酸の陰性成分とから成る化合物の総称。たとえば,NaCl,KH2PO4,K2HPO4,K3PO4,MgCl(OH),MgCl2,TiCl4,CrCl3,CrCl3・6H2O,[Co(NH3)6]Cl3,K4[Fe(CN)6],KAl(SO4)2・12H2O,NH4Cl,C6H5NH3Clなどがそうであり,無機化合物で広くみられる。酸と塩基との中和反応あるいは塩の複分解その他によって得られるが,中和では一方が多塩基酸または多酸塩基のときには何種類かの塩が得られる。たとえば三塩基酸のリン酸H3PO4の反応は,
H3PO4+KOH─→KH2PO4+H2O
KH2PO4+KOH─→K2HPO4+H2O
K2HPO4+KOH─→K3PO4+H2O
のように3段階で進み,3種の塩が得られるし,同じようにたとえば二酸塩基の水酸化マグネシウムMg(OH)2では,
Mg(OH)2+HCl─→MgCl(OH)+H2O
MgCl(OH)+HCl─→MgCl2+H2O
のように2種の塩が得られる。このとき,途中で得られるKH2PO4,K2HPO4などは完全に中和されていないという意味で酸性塩acidic salt(KH2PO4,K2HPO4そのものが酸性であるということではない。正しくは水素塩hydrogen saltという),同じくMgCl(OH)を塩基性塩basic salt(MgCl(OH)が塩基性だというわけではない。正しくは水酸化物塩hydroxide saltという)ということもある。これらに対しK3PO4やMgCl2などのように完全に中和された塩を正塩normal saltという。また,たとえばCH3COONa・CH3COOHのような塩も拡張して酸性塩といい,BiCl(OH)2のような形式のものから水分子のとれたBiClOも塩基性塩といっている。ただ1種類の単純な塩,たとえばNaClなどを単塩というのに対し,2種以上の塩が成分として含まれている,たとえばKAl(SO4)2・12H2Oのような塩は複塩といっている。また錯イオンを含む塩は錯塩という(〈錯体〉の項目参照)。遷移金属の水和物には形式上は単塩(たとえばCrCl3・6H2O)でも,水分子が金属原子に配位したアクア錯塩(たとえば[Cr(H2O)6]Cl3)であるものが多い。
塩のうちイオン結合性の強いもの(たとえばNaClなど)は,いわゆるイオン結晶をつくり,水溶液はイオンに解離し,固体では融点が高い。これに対し,共有結合性の強いもの(たとえばTiCl4,CrCl3など)は,水に不溶性であることが多い(TiCl4は分子からなり,加水分解するが,CrCl3は巨大分子からなり反応しない)。
執筆者:中原 勝儼
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
塩化ナトリウムNaClを主成分とする物質で、動物体にとっては生理的に不可欠のものである。食料用以外に工業用として多量に用いられており、食料用の約5倍の使用量である。そのほか、医薬用としても少量使用されている。食料用としては、調味以外に、塩のもつ腐敗防止、発酵調節、脱水作用などの性質を利用した用途も多く、塩蔵(えんぞう)といって肉や魚など腐敗しやすい食品を塩漬けにすることによって保存するために用いられている。とくに食用として使用できるものを食塩という。工業用としては、ソーダ、塩素の原料としてソーダ工業に多量用いられるほか、多くの化学工業にとって重要な原料となっている。そのほか窯業におけるうわぐすり(食塩釉(ゆう))、せっけん、染料製造における塩析剤など、種々の工業において用途がある。血液と浸透圧が等しくなるように食塩を溶解した水溶液が、生理的食塩水として医療用に用いられる。
[平嶋克享]
塩には原塩、粉砕塩、並塩(なみえん)、食塩、精製塩、特級精製塩、食卓塩、漬物塩(えん)などのほか、特殊用塩として各種加工塩(えん)がある。原塩、粉砕塩、並塩は、塩化ナトリウムの純度が95%以上で、おもに業務用に用いる。原塩には、岩塩、天日塩(てんぴえん)、海水よりつくる粗製塩などが含まれる。食塩は塩化ナトリウム純度99%以上で、料理の下処理、調味、漬物など広く一般に使用される。精製塩は塩化ナトリウム純度99.5%で、1キログラム袋のものでは防湿剤として塩基性炭酸カルシウムが0.15%以上含まれている。食塩に比べさらさらしており、料理の味つけに用いられる。精製塩にはこのほか塩化ナトリウム純度99.8%以上の特級精製塩がある。食卓塩は塩化ナトリウム純度99.0%以上で、防湿剤として塩基性炭酸マグネシウムが0.4%以上含まれている。名称のとおり食卓に置いて、できあがった料理の上からふりかけて、味をととのえるのに用いられる。防湿に加えられている炭酸マグネシウムは、非水溶性のため、澄まし汁などに用いると汁が白濁し、きれいな吸い物にはならない。漬物塩は、漬物専用につくられた塩で、輸入原塩を基に、リンゴ酸、クエン酸などを添加したもので、塩化ナトリウム純度は95%以上である。このほか各種の加工をした特殊用塩がある。これらには、ごま塩、焼き塩、グルタミン酸ナトリウムをコーティングしたもの、うま味調味料をコーティングしたものなど食卓塩の一種として用いるもの、パパイン酵素と混ぜて肉を柔らかくするために用いるもの、ガーリックソルト、オニオンソルト、セロリーソルトなどのように料理の調味に使われるものがある。にがり分などを加えた塩も特殊用塩の一つである。
[河野友美・林 正寿]
岩塩のない日本の製塩は、端的にいって、海水から97%の水分を除いて3%の塩をとることである。『万葉集』などに「藻塩(もしお)焼く」と表現している古代の製塩法は、海水の付着した藻を乾かし、それに海水を注いで濃厚な塩水をとり、それを製塩土器に入れて煮沸して塩をとったものと推測されている。塩浜(しおはま)(塩田)の語句が初めて文献にみえるのは875年(貞観17)『三代実録』の記事であるが、海水を濃縮する方法が、藻から砂(塩浜)利用に変わるのは奈良時代と推測されている。日本の古代・中世の塩浜には二つの様式があった。一つは揚浜(あげはま)であって、塩浜は満潮面より高い所につくられ、海水は人力でくみ上げて、砂面に撒水(さんすい)する方式である。いま一つは、潮が満ちると海になり、引くと干潟になる場所で、塩分のついた砂をかき集めて、海水を注ぎ濃い塩水をとる方法で、自然浜とよばれるものである。江戸時代になると入浜塩田(いりはまえんでん)が発達してくる。入浜塩田は堤防によって囲まれており、塩田面の一部を掘って溝をつくり、樋門(ひもん)から入ってきた海水は、溝から毛細管現象によって塩田面に浸透して砂に付着し、これが太陽熱と風力によって蒸発し、濃い海水のついた砂ができる。これを集めて海水をかけて濃い塩水をとる。この入浜式塩田も1953年(昭和28)以降、枝条架(しじょうか)を併設した流下式塩田(りゅうかしきえんでん)に転換した。その後、イオン交換膜を用いた製塩法が出現し、1972年にはこのイオン交換膜法に全面的に転換され、塩田製塩は消滅した。以後、日本では、イオン交換膜法によって、新日本ソルト(福島県)、赤穂(あこう)海水(兵庫県)、錦海(きんかい)塩業(岡山県)、ナイカイ塩業(岡山県)、鳴門(なると)塩業(徳島県)、讃岐(さぬき)塩業(香川県)、ダイアソルト(長崎県)の七つの製塩工場で塩がつくられるようになった。1995年(平成7)度の国内生産高は約135万トン、同年の輸入塩はメキシコ、オーストラリアを中心として約800万トンである。国内産塩は主として食料塩、輸入塩は化学工業用に使用されてきた。その後、1997年の塩事業法の施行により塩専売制は廃止されることになったが、塩専売制は廃止によって、一気に自由な市場構造へと全面転換するのは混乱が予想されたので、5年間の猶予期間が設けられた。
なお、世界の塩事情をみると、全世界の塩の生産高は約1億9600万トン(1995)で、1位アメリカ(4200万トン)、2位中国(3000万トン)、3位カナダ(1100万トン)、日本は19位で140万トンである。製塩法(塩資源)は岩塩がもっとも多く、ついで天日製塩、そのほか、地下鹹水(かんすい)(塩水)、鹹湖(塩湖)などがある。岩塩は、鹹湖が乾固してできたもので、大陸には各地に存在する。天日製塩は、日射が強く蒸発が盛んで降雨量が少なく、また塩田築造に適した地形と土質の地域で行われている。まず、いくつかの蒸発池に海水を入れておくと、海水の塩分濃度が高くなる。それをいくつかの結晶池に入れておくと底に塩の結晶が沈殿する。それをかき集めたものが天日塩である。インド、オーストラリア、メキシコ、エリトリア、エチオピアなどで天日製塩が行われている。
[渡辺則文]
生理的必需品である食塩は、これの供給源を押さえたものが天下をとることができる。そこで塩の専売制度が生まれた。歴史的にみると、ヨーロッパでは早くも紀元前6世紀に古代ローマで塩の販売権を政府がもつようになり、一般民衆は製塩に従事するのを禁止された。
日本でも江戸時代の藩専売制の対象品の一つとされてきたが、明治時代には日露戦争の戦費調達を目的として1905年(明治38)に国による専売が始められた。第二次世界大戦後の日本では1949年(昭和24)6月1日から実施された塩専売法により塩の製造、輸入、販売の権能は国に専属するという専売制がとられて、日本専売公社が専売権を実施していた。しかし、臨時行政調査会の答申にこたえて日本専売公社が民営化され、日本たばこ産業株式会社が創設されたのに伴い、1985年(昭和60)からは塩の専売事業は日本たばこ産業株式会社に委託された。その後の規制緩和要求の高まりに対応して、塩の専売制度も1997年(平成9)4月1日施行の塩事業法により廃止された。塩専売制度の廃止後においても、塩は国民生活に不可欠な代替性のない物資であるがゆえに、塩事業の適切な運営による良質な塩の安定的な供給の確保と、日本の塩産業の健全な発展を図るために、塩事業法は必要な措置を規程している。財務大臣は毎年塩の需給見通しを策定、公表し、塩事業センターを指定して、生活用塩の供給や備蓄、塩産業の効率化促進のため助言、指導をさせている。また塩製造業者、販売業者、卸売り業者は、財務大臣の登録を受けなければならない。
[河野友美・林 正寿]
塩は人間の生命維持に不可欠な物資であり、しかも代替品もなく、またその生産が地域的に限定されたところから、もっとも早く地域間流通のみられた物資の一つと考えられる。日本の製塩の歴史は、縄文時代後期末、関東地方の霞ヶ浦(かすみがうら)周辺においてその痕跡(こんせき)が認められるが、そのころ、すでに関東奥地との塩の流通が推測される。律令(りつりょう)制下、古代帝都における塩の供給は、おおむね調塩(租税制度。租・庸・調・雑徭(ぞうよう)のうち、調として中央政府に貢進された塩)・庸塩(庸として年ごとに宮都(みやこ)に徴発される力役(りきえき)である歳役(さいえき)の代納物として納められた塩)によった。そして、中央官人層には季録(きろく)、月料(げつりょう)などとして支給され、不足分は京の東西市や難波市(なにわいち)で購入されたようである。奈良・平安時代、瀬戸内海地域を中心として塩荘園(しょうえん)が成立してくると、瀬戸内で生産された塩は、魚とともに盛んに中央へ運ばれたようで、その陸揚げ地である淀(よど)川の要津(ようしん)山崎の津は「魚塩の利」で栄えた。中世でも塩は利潤の多い商品で、1292年(正応5)東寺領伊予(いよ)国弓削島(ゆげしま)荘の年貢塩が淀魚市で京都七条坊門の塩屋(しおや)商人に1俵200文で売却されたが、2、3日のうちに塩屋商人は1俵400文で売っている。1445年(文安2)『兵庫北関入船納帳(ひょうごきたせきいりふねのうちょう)』によると、この年、兵庫北関を通過した船1960艘(そう)のうち約47%が塩船であり、積載塩の総量は10万7841石である。これらの塩は、京都や奈良に搬入されたが、その地ではおもに塩座を通して一般に販売された。「舞の本」の人買い伝説「信田(しのだ)」には塩と子供を交換した話があり、『文正草子(ぶんしょうぞうし)』にも塩を焼いて産をなした話がある。これらによって中世商業における塩の地位をうかがうことができる。
江戸時代、1人1日の塩の使用量は約3勺といわれ、牛馬の飼育の盛んな地方では4勺とも計算されている。18世紀前半ごろ、日本の人口は約3000万人といわれているが、塩の需要は少なくとも320万石から330万石に達している。その多くは瀬戸内で生産され、塩廻船(しおかいせん)によって東海・江戸方面、あるいは北国筋(ほっこくすじ)へ輸送された。広島藩を例にあげると、1825年(文政8)当時、領内塩浜軒数は238軒、生産高は80万俵(5斗入)、その供給先と販売量は、領内13万俵(16.25%)、北国40万俵(50%)、山陰1万俵(1.25%)、九州2万俵(2.5%)、江戸・清水・名古屋24万俵(30%)となっている。江戸への入津(にゅうしん)塩は18世紀の1720年代には167万俵に達している。これらの塩は江戸市中のみならず、関東各地に輸送され、ことに下総(しもうさ)(千葉県)銚子(ちょうし)などのしょうゆ醸造地帯には大量の塩が搬入された。江戸に入津する瀬戸内産塩を扱うのは、廻船下り塩問屋(下り廻船塩問屋ともいう)と塩仲買である。下り塩問屋は、江戸北新堀町(きたしんほりまち)の秋田屋、長島屋、渡辺屋、松本屋の4軒に限定され、塩廻船を一手に引き受けた。口銭(こうせん)利益は莫大(ばくだい)で、塩問屋株は、文化年間(1804~1818)に千両株と称せられ、十組(とくみ)問屋の最高株値段をよんだ。明治維新後、流通組織は一時混乱したが、1878年(明治11)には東京食塩問屋組合と東京食塩仲間組合に組織された。当時、1か年の平均入津塩は船数330艘、俵数210万俵であった。1889年には両者は合併して東京廻船食塩問屋仲間組合東京塩問屋組合と改称された。
1905年(明治38)塩専売法が施行されることによって、塩の収納は政府の手で行われることになったが、運搬販売は、旧来の塩商人による販売機関がそのまま利用された。しかし、1907年には官費廻送販売制が実施され、さらに翌年には塩売捌(うりさばき)制が制定され、塩売捌人が指定された。これによって塩は、元売捌人―小売人の販売機関を通して消費者に売り渡されることになった。ところが、90年余年の長い歴史を持つ塩専売法が、1997年に制定された塩事業法によって廃止され、これまでの製造、輸入、流通を包括的に管理する塩専売法下での市場構造から、大きく転換することになった。
[渡辺則文]
動物にとって食塩は生理的に必要不可欠のものである。食塩は、体内とくに血液に存在し、そのナトリウムは、細胞中のカリウムとバランスをとり、浸透圧の維持という重要な役割を果たしている。人間は、健康時の血液中には0.9%程度の塩が含まれている。食塩のとり方が不足すると、消化液の分泌が減り、食欲が落ちる。長期にわたって食塩が不足すると、全身の脱力、倦怠(けんたい)、疲労、精神的不安などがおこる。さらに、ナトリウムは植物性食品のなかに多いカリウムとつねに体内でバランスをとっている。200年ほど前、奥羽地方で大飢饉(ききん)(天明(てんめい)の飢饉)のあったとき、多くの人々が山野に野菜や木の芽などを求め、それをむさぼり食べた。そのためカリウム摂取量が多く、そのうえ食塩を食べなかったので、食塩の欠乏による死亡者が続出したという。一方、食塩の過剰摂取は高血圧症の一因となる。また、急性の食塩過剰摂取は、腸における水分の吸収を妨げて下痢をおこす。食塩をとりすぎると、のどが渇く。血液中の塩分濃度が高まり、体液の浸透圧を亢進(こうしん)するので、水分を増し、食塩濃度を下げて浸透圧の力を和らげようとするためである。汗をかいて体内の水分が減少したときも同じである。成人1人1日当りの塩の摂取は、日本では10グラム以下が、WHO(世界保健機関)では5グラム以下が望ましいとされている。
[河野友美]
食塩はすべての食品に対し、そのもっている味を引き立てる役目をする。一般に料理を調味することを「塩加減」というのにもこの意味が含まれている。塩味は、溶液の温度が高くなるにしたがって味が弱く感じるようになる。冷めた料理が塩辛く感じるのは、味の感じ方の弱い高い温度で味つけしたため、冷えるにしたがい塩味が強く感じられるようになるからである。塩味は酸味を加えることで味をやわらかくすることができる。昔から「あんばい(塩梅)」ということばが使われているが、これは食塩を梅酢でまるくするという意味である。また逆に、酸味の強いものを、食塩を加えることで和らげることもできる。したがって、酢の物、すしなどの合わせ酢に食塩は欠かせない。一方、食塩は味を強める働きもする。だし汁に食塩を加えると、だしの味が際だってくる。また、甘味に対しては甘味を強めるように働く。砂糖量に対し食塩が0.2%のとき甘味の強さは最高となる。汁粉の甘味はこれを利用したものである。
塩は浸透圧の作用が強く、材料にしみ込みやすい。浸透圧の作用により、生物体の水分を強く外に吸い出す働きもある。「青菜に塩」というのはこの状態を表現したものである。なますをつくるとき、刻んだダイコンやニンジンに塩をふり水けを絞るのも、塩の浸透圧の作用を利用したもので、水けを絞ることで調味液がよくしみ込む。このように食塩は料理の際、味以外に各種の物理的な作用を食品に及ぼす。コムギや魚肉のタンパク質に対しては、塩分の濃度が低いときには溶解させるように働く。魚のすり身では、食塩を少量加えることで滑らかなすり身ができる。小麦粉では、粘りの強い生地(きじ)になる。食塩はタンパク質を固める作用もある。とくに塩分があって熱が加わると、熱によるタンパク質の凝固温度が低くなり、それだけ早く固まる。魚や肉を焼くとき、表面に食塩をしてから焼くと、表面だけが早く固まり、中の液汁は出てこない。落とし卵をつくるとき、魚をゆでるときも湯の中に食塩を入れておくと、卵や魚肉の表面が早く固まるため、形がくずれたり、うま味成分の抜けるのが防げる。
食塩には防腐作用があるが、塩分の濃度が12%以上ないと効果がないから注意を要する。濃度が低いとよく繁殖する菌もあり、とくに食中毒菌の一つ腸炎ビブリオ菌は3%の食塩水をもっとも好む。青菜をゆでるとき、ゆで湯に1.5~2%の食塩を加えると、青菜の葉緑素が安定してきれいな緑色にゆで上がる。また、リンゴなどを褐色にするポリフェノールオキシダーゼなどの酵素の働きを止め、褐変を防止する働きや、ビタミンCの空気酸化を防ぐ働きがある。サトイモ、ヤツガシラ、タコ、アワビなどのぬめり取りにも食塩は有効である。食塩には寒剤としての働きもあり、食塩に氷を加えると低温が得られる。もっともよく冷えるのは氷3に対し塩1の割合のときで、ほぼ零下20℃まで下がる。これを利用し、アイスクリームをつくるなど食べ物を凍らせることができる。
[河野友美]
塩は精神生活にも大きな意義をもっており、日本では清めのため神事の祭場や祭具、神棚に使用され、また、炉、かまど、井戸などの清めや、相撲(すもう)の土俵で力士に用いられている。葬式の場合、塩で身を清めることは全国一様の習俗である。瀬戸内海周辺から九州にかけて、オシオイといって毎朝竹の手桶(ておけ)に海水をくんできて家の内外を清める風習がある。この手桶を門口にかけておく所もあるという。客商売をする飲食店などでは、店を掃除すると店先に盛り塩と称して一握りの塩を置いておくのは全国的にみられる。全国各地の祭礼に潮水を神前に捧(ささ)げる例がある。東京・府中市の大国魂(おおくにたま)神社の祭礼に、品川の海水を持参することが行われている。神輿(みこし)を海中に担ぎ入れる祭りもあり、遠方の神社から海浜にまで行列をつくって神幸(しんこう)する祭礼もある。正月の初宮詣(もう)でに浜から海草をとって神前に捧げる例もある。
塩についての伝説に塩井伝説がある。弘法大師(こうぼうだいし)が旅先で塩気のない小豆粥(あずきがゆ)を出されたので、塩のないことを気の毒に思い錫杖(しゃくじょう)で地を突いて塩井を湧出(ゆうしゅつ)したという。塩がもっとも貴重な商品であったことは、諸国の市場にこれを求めて人々が集まり、一方、塩売りが遠い山間の地にまで入り込んで行ったことでもわかる。これは「塩の道」と称して交通経済上よく知られており、塩売りは文化の移入者の役をも務めていた。九州の鹿児島湾の東、高隈(たかくま)山中腹の山村では生児の養い親に塩売りを頼む風習があり、子供に名をつけてもらい、籠(かご)に入れた塩が塩売りから子供に贈られたという。また塩が貴重なものであったので、塩断ちといってこれをとらないことを約束して神仏に祈願することが行われている。
[大藤時彦]
塩は、ほとんどすべての民族がそれぞれなんらかの方法で入手し、使用している。ただし、塩をまったく知らない、あるいは使わない民族もあった。台湾のタイヤル族が塩を知ったのはタバコよりずっとあとであったという。植物、動物の肉や内臓、また乳製品などに含まれる微量の塩分で、必要量を十分に得ていた民族もあったと考えられる。
[板橋作美]
人工的に塩を製造するのではなく、天然の塩、つまり岩塩や干上がった塩湖などの塩をそのまま採集、採掘することが、古くから、また現在でも行われている。オーストリアのハルシュタットでは、すでに鉄器時代に岩塩が採掘されていた。これは斜坑と300メートル以上の水平坑をもつ本格的なもので、内部には採掘に使った道具が捨てられていた。カルパティア山脈の岩塩も有史以前から採掘されていた。砂漠地域、たとえば中国西部などでは、塩分を含んだ湖が干上がった跡に残った塩を利用することが多い。イランのナマキ砂漠もそうであり、ナマキは塩の意で、またこの砂漠という語もペルシア語のキャビール(塩砂漠)の訳である。次に、海、塩湖、塩井の水を火や天日で蒸発させて塩をとる方法も広く行われている。コロンビアのエル・ポルテテ近くでは、カリブ海に面した塩田で、グアヒロ人が1年のうち2か月間塩をとっている。メキシコ南部のマヤ人地域には、塩井から塩をとる所がいくつもある。ほかに、特殊な製塩法として、植物を利用する方法がある。ニューギニアのダニ人は、バナナの幹の外皮を乾燥させ、これを山中のイルエカイマ塩湖に浸す。この塩水をしみ込ませた樹皮を村に持ち帰り、2日間屋根の上で乾かす。それを焼き、塩分を含んだ灰をつくり、水をあわせてこねて固め、乾燥させる。使用するときは削って料理にかける。同じニューギニアのモニ人は普通の草の束でこれを行う。類似の方法は古代ゲルマン人が行っていた。
[板橋作美]
塩がとれる場所は比較的限られているため、古くから世界各地で塩の交易が行われた。ヒマラヤ地方ではボーチア人が交易商人として活躍し、チベット高原の塩と羊毛を、ヒマラヤ山脈中腹や山麓(さんろく)の住民に売り、そこの穀物をチベット高原に運んだ。北西アフリカではサハラ砂漠の遊牧民トゥアレグ人が隊商交易を行い、アルジェリア南部産の塩やアジア、ヨーロッパの物資をサハラ砂漠を通ってニジェール、マリなどに運び、黄金、象牙(ぞうげ)、奴隷などを地中海地域に運んだ。交易品としての塩の重要性は、しばしば塩に一種の貨幣の役割をさせることになった。ローマ時代に役人、軍人への給料の支払いが塩によって行われた時期があったこと、そして英語のサラリーsalary(俸給)が、ラテン語のサラリウムsalarium(塩の支給)に由来することはよく知られている。アフリカのソマリア半島やチベットでも同様のことがあった。マルコ・ポーロの『東方見聞録』には、チベットのガインドゥ(建昌路)地方で塩が小額貨幣として用いられていたことが記されている。塩水を煮つめた糊(のり)状の液体を型に入れて固め、表面に皇帝の印を刻したこの塩貨は、80個が金1サジオに相当したと書かれている。
[板橋作美]
塩は清める力、聖なる力をもつとする信仰がよくみられる。『旧約聖書』には塩に関する記述が多く、「列王紀」には、塩が悪い水を清め、死と流産の穢(けがれ)を祓(はら)うと述べられている。「エゼキエル書」のなかに、ヤーウェに犠牲の動物を捧(ささ)げる際、犠牲の牡牛(おうし)と牡羊に祭司が塩を振りまくよう指示している。また「出エジプト記」の聖なる薫香(くんこう)の作り方のなかで、材料を混ぜ合わせたあと塩を入れ、清く聖なるものにせよ、と指示している。カトリック系社会では、洗礼のとき、子供の口に塩を入れることが多い。メキシコの高地マヤ人はこのときの塩によって子供の魂は初めて固定するといわれる。カトリックの洗礼との関係は不明だが、フィリピンのネグリトは、新生児の口に塩を入れる。
このような、穢を祓う塩は、また魔除(まよ)けや病気治しにも使われる。東南アジアのラオ人やタイ人では、出産後の女性は妖術(ようじゅつ)を防ぐために塩水で体を洗った。かつてユダヤ人は邪視(じゃし)除けに子供の舌の上に塩を置いた。魔物が入らないように戸口に塩をまく慣習がシリアにみられた。メキシコの高地マヤ人のシナカンタン村では、塩はさまざまな妖怪、魔物を撃退する力をもっていると考えられている。ヨーロッパで魔女のサバト(宴会)の料理は塩抜きであると考えられていたのも、塩のもつこのような力の信仰の反映である。古代ギリシアでは塩は神聖なもので、神にかかわるものであるために、病気を治したり、力をつけることができると考えられていた。呪術(じゅじゅつ)師やシャーマンが体を燃えている状態にするため塩を多量に摂取することがある。たとえばメラネシアの妖術師にあっては、ヨーロッパの魔女とは逆に、塩水を飲み香料が多量に入った食物をとって体を熱くすると信じられている。また病気治しではないが、塩を美容のために使うこともよくある。エジプトのクレオパトラ、中国の楊貴妃(ようきひ)は入浴のとき塩を使ったといわれ、古代ローマでも美顔術に塩を用いたといわれる。塩はさらに、人と神、人と人の固い結び付きを象徴するものとされる。『旧約聖書』の「民数記」では、神と人の永遠に変わらぬ聖なるきずなを「塩の契約」と言い表している。古代チュートン(テウトニ)人は、誓いをたてるとき、塩に指を浸して誓った。古代ギリシア、ローマ、またはヨーロッパ、アラブで、塩とパンの共食は友情と歓待のしるしであり、しばしば「塩の交わり」を意味することばがある。ギリシアの哲学者アリストテレス、ローマの政治家・文人キケロなどが、塩のそのような力について述べている。
他方、これらとは逆に、塩を忌避する場合がある。古代エジプトの神官は塩をタブー視していた。アフリカのテソ人の社会では儀礼のときの料理には塩を使わない。同じアフリカのンデンブ人は割礼儀礼のときは塩も塩辛いものも食べてはいけない。メキシコの先住民ウィチョルのシャーマンは修行中は塩をとらない。またウィチョルはペヨーテという幻覚作用のあるサボテンを食べる宗教儀礼を行うが、ペヨーテをその自生地までとりに行く巡礼の旅の間、またペヨーテを食べて恍惚(こうこつ)状態で神と交流する儀礼の間も塩を食べず、儀礼の最後に一つかみずつ塩を食べ、儀礼の終了が示される。このような宗教的理由による塩の禁止、塩断ちはかなり多くの社会にみいだせる。社会によっては塩を穢と結び付けることすらある。アフリカのチェワ人やヤオ人は、塩は穢を伝達すると考えている。さらにイスラエルの死海という名が示すように、塩が死や不毛を表すものとしてとらえられることも少なくない。
このようなシンボルとしての塩の多義性また二面性は、最近の文化人類学の考えを応用すると、ある程度理解できる。ヨーロッパの錬金術で、16世紀のパラケルススとその一派は、水銀と硫黄(いおう)と塩を3原理とした。そのうち塩は水銀と硫黄を結び付けると考え、そのことを水銀は王妃、硫黄は王、塩は僧侶(そうりょ)の姿で描くことがあった。このことと、塩が神と人、人と人を結び付けるとする信仰は、ともに塩が、異なる二つのもの、対立するものを仲介、媒介する力をもつことを示している。塩が僧侶に類比されることはきわめて象徴的であり、僧は神と人の中間にたつ存在である。そもそも塩は自然物である食料を人工的、文化的な食物に変える料理の過程で用いられる。そのような媒介者的存在、中間的位置のものは一般に異常な力をもつとされる。そしてその力は、ある場合には善なる神聖な力と解釈され、またある場合には逆に危険な、邪悪な力と解されるのである。
[板橋作美]
『日本専売公社総務部編『専売事業の概要』(1953・日本専売公社)』▽『日本専売公社総務部編『専売法規の解説』(1954・日本専売公社)』▽『渡辺則文著『日本塩業史研究』(1972・三一書房)』▽『渋沢敬三編『塩俗問答集』(「日本常民生活資料叢書4」1973・三一書房)』▽『平島裕正著『ものと人間の文化史7 塩』(1973・法政大学出版会)』▽『日本塩業体系編纂委員会編『日本塩業体系』(1974~1982・日本専売公社)』▽『亀井千歩子著『塩の民俗学』(1979・東京書籍)』▽『広山尭道著『塩の日本史』(1990・雄山閣出版)』▽『加茂詮著『近代日本塩業の展開過程』(1993・北泉社)』▽『網野善彦著『海の国の中世』(1997・平凡社)』▽『富岡儀八著『塩の道を探る』(岩波新書)』
酸と塩基との中和反応によって生ずる化合物で、酸の陰性成分と塩基の陽性成分からなるものをいう。たとえば、塩酸と水酸化ナトリウムとが反応して中和すると、水と塩である塩化ナトリウムを生ずる。
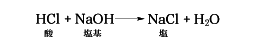
[中原勝儼]
酸と塩基の中和は、酸および塩基の強さに応じて反応が完全に進行し、酸のすべての水素原子が陽性成分(金属イオン)で置換される場合と、一部の水素原子だけが陽性成分によって置換され、一部の水素原子がそのまま残っている場合、およびその逆に塩基の水酸化物イオンあるいは酸化物イオンが一部中和されずに残っている場合とがある。たとえば、硫酸にアンモニアを通ずると、始めは、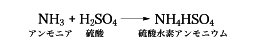
のように、二つある水素のうち一つだけが置換され、さらにアンモニアを通じていると、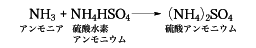
のように完全に置換される。全部の水素原子が陽性成分で置換された塩を正塩あるいは中性塩といい、塩化ナトリウムや、この場合の硫酸アンモニウムがそうである。これに対し、陽性成分の中に水素イオンが残っている硫酸水素アンモニウムなどは、酸性塩といっている。
三塩基酸では2種類の酸性塩(たとえばリン酸二水素ナトリウムNaH2PO4とリン酸水素二ナトリウムNa2HPO4)ができる。また一塩基酸でも、たとえばCH3COONa・CH3COOHのように酸成分の付加化合物ないしは分子化合物を酸性塩といっている。
塩基性塩とは、酸性塩とは逆の場合で、陰イオン成分として水酸化物イオンまたは酸化物イオンを含むものをいう。たとえばCuCl(OH)やBiClOのような化合物をいう。ただし酸性塩とか塩基性塩とかいっても、これはあくまでも化学式における形式的なものであって、塩そのものの酸性あるいは塩基性を表すものではない。したがって酸性塩がかならずしも水溶液中で酸性を示し、塩基性塩の水溶液が塩基性を示すとは限らない。
[中原勝儼]
通常の塩、すなわち陽性成分、陰性成分ともに1種類ずつの塩を単塩というのに対して、少なくともどちらかの成分が2成分以上の場合を複塩という。たとえば三フッ化マグネシウムカリウムKMgF3(KF・MgF2とも書く)などがそうである。その意味では酸性塩あるいは塩基性塩も一種の複塩である。これに対し錯イオンを含む塩を錯塩という。たとえばK2[PtCl4]、K4[Fe(CN)6]、[Co(NH3)6]Cl3などのように錯イオン[PtCl4]2-、[Fe(CN)6]4-、[Co(NH3)6]3+を含む塩であるので、これらは錯塩である。これを古く2KCl・PtCl2、4KCN・Fe(CN)2のように書いて複塩としたこともあるが、これは誤りである。ミョウバンは典型的な複塩の一つであり、これはKAl(SO4)2・12H2Oと書かれるが、実際は[K(H2O)6][Al(H2O)6](SO4)2のような錯塩の複塩である。
[中原勝儼]
『水町邦彦著『酸と塩基』(2003・裳華房)』

 (いにしへ)、宿沙、初めて
(いにしへ)、宿沙、初めて
 鹽を作る」という事物起源説を記している。
鹽を作る」という事物起源説を記している。 字鏡〕鹽 閻羅、閻なる者は之保(しほ)〔名義抄〕鹽 シホ 〔字鏡集〕鹽 ヲフ・シホ・ヒロシ
字鏡〕鹽 閻羅、閻なる者は之保(しほ)〔名義抄〕鹽 シホ 〔字鏡集〕鹽 ヲフ・シホ・ヒロシ ▶・塩
▶・塩 ▶・塩車▶・塩絮▶・塩場▶・塩神▶・塩人▶・塩井▶・塩政▶・塩税▶・塩籍▶・塩泉▶・塩酢▶・塩
▶・塩車▶・塩絮▶・塩場▶・塩神▶・塩人▶・塩井▶・塩政▶・塩税▶・塩籍▶・塩泉▶・塩酢▶・塩 ▶・塩宗▶・塩霜▶・塩竈▶・塩池▶・塩丁▶・塩鉄▶・塩梅▶・塩票▶・塩民▶・塩冶▶・塩酪▶・塩利▶・塩鹵▶
▶・塩宗▶・塩霜▶・塩竈▶・塩池▶・塩丁▶・塩鉄▶・塩梅▶・塩票▶・塩民▶・塩冶▶・塩酪▶・塩利▶・塩鹵▶ 塩・鬻塩・運塩・花塩・海塩・
塩・鬻塩・運塩・花塩・海塩・ 塩・官塩・魚塩・漁塩・羌塩・苦塩・形塩・畦塩・虎塩・
塩・官塩・魚塩・漁塩・羌塩・苦塩・形塩・畦塩・虎塩・ 塩・紅塩・山塩・散塩・私塩・煮塩・戎塩・食塩・新塩・井塩・製塩・
塩・紅塩・山塩・散塩・私塩・煮塩・戎塩・食塩・新塩・井塩・製塩・ 塩・石塩・赤塩・
塩・石塩・赤塩・ 塩・茶塩・甜塩・梅塩・白塩・米塩・卵塩
塩・茶塩・甜塩・梅塩・白塩・米塩・卵塩出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
一般に,酸と塩基との中和反応によって生じる化合物であるが,中和反応以外でも生じうるので,形式的には酸の陰性基と塩の陽性基からなるイオン性化合物をいう.塩の組成中に,酸のHを含む塩は酸性塩,塩基のOHを含む塩は塩基性塩,HもOHも含まない塩は正塩とよばれる.1種類の単純成分のみからなる塩は単純塩,2種類以上の成分が含まれる塩は複塩,錯イオンを含む塩は錯塩とよばれる.
出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報
出典 シナジーマーティング(株)日本文化いろは事典について 情報
…塩は食塩とも呼ばれるが,化学的には塩化ナトリウムNaClと呼ばれ,ナトリウムイオンと塩素イオンとが規則正しく配列した無色透明の正六面体の結晶で,へき開性もある。製法により結晶の外形も不定形になり,色相も種々の色を呈する。比重は2.2程度,モース硬度は2~2.5,融点は800℃付近,沸点は1440℃,飽和食塩水の氷点は-21℃である。水に対する溶解度は,温度によりほとんど変わらず,20℃で26.4%,100℃で26.9%である。…
…地球上の陸地以外の凹所に水をたたえ,全体がひとつづきになっているところが海(海洋)である。それを満たす水が海水で,その塩分の組成率は,世界中ほぼ一定している。海岸近くの入江や,浦,潟(かた)を海とするか湖沼と呼ぶかは,多分に従来の習慣によっている。…
…日常生活に必要な道具も,生産に必要な道具も,可能なかぎり自分の手で作り出す。そのさい多くの農村で自給できないものは,生産・生活に用いる道具のうち鉄製の部分であり,食生活に必要な塩も,製塩しうる海岸村以外では外部に求めなければならない。このような鉄製の道具や塩は藩主の手に集めたうえで,初期専売と呼ばれる形で農民の手に渡され,その代価は農産物で払われる。…
…室町時代,奈良興福寺の大乗院を本所とし,同院所属の正願院塩座問屋から仕入れた塩を奈良で振売していた塩の小売商人集団。文明年間(1469‐87)には,元興寺郷中院・紀寺・脇戸・浄土・井上・高畠・丹坂・廊ノ辻子・池ノハタ・今窪・鵲・福院などに分散居住しながら,ひとつの座衆として行動していた。…
…また物質それ自体は生物と同様に増成するという観点から,男性的原理と女性的原理の拮抗・融和によって物質の変化をとらえるという考えが定着し,水銀が女性原理を,硫黄が男性原理を代表するという硫黄―水銀の原素論がアラビア世界を通じて登場した。これがさらには,三位一体のキリスト教的発想も手伝い,塩という中性要素を加えた硫黄―塩―水銀の三原素説が四元素に優先する考えになった。特にこれは,パラケルススによりほぼはっきり体系化されるに至った。…
…彼らは同一職種による座組織を結成し,営業独占権を行使した。例えば京の南の港町,淀に着岸する塩,塩魚については〈淀魚市問丸中〉としていっさいの営業を独占し,着岸強制権さえもったのである。同じころ,地方村落にも市場が群生したが,この市に立つ小売商人は仕入れ,運送,小売に従事し,市座の営業独占権を主張している。…
…この場合には,国民はその物品の購入に際して,政府の決定した価格による対価の支払を強制されるため,実質的には消費税を課したのと変わらない結果になる。後者は,社会政策,公衆衛生,治安維持,産業保護などの公益的な目的をもって行われるものであって,塩,アルコール,麻薬等の専売がこれである。 日本においては,塩およびアルコールについて専売制度がとられている。…
…みそ玉醸造方式は現在の愛知,三重,岐阜の3県における豆みそ醸造に発展し,さらに米こうじあるいは麦こうじを加えて日本独自の米(麦)みそを創造することになった。工業的に生産されるようになったのは,江戸時代に入ってからで,1645年(正保2)に仙台伊達藩の〈御塩噌蔵〉で製造が開始された。豆みそはこれよりも早く1625年(寛永2)三河で製造が開始されたとされる。…
…
[里甲制と税制]
民政関係について述べるならば,まず人民は戸籍上,軍,民,匠,竈(そう)の4種に分けられているが,これは負担する徭役(ようえき)の違いによる分類である。すなわち,軍戸は兵役,民戸は一般行改の運営上必要な労働,匠戸は技術労働,竈戸は製塩労働を負担する者であった。数の上からいえば,民戸が圧倒的多数を占めていたので,以下は民戸を中心として解説する。…
…そのほかに,狭義の料理にとりかかるまえにあらかじめ食料に手を加えて食べやすい形に変えたり,保存性を高めるための一次的加工(食品加工)を経た加工食品がある。穀類の精白,豆腐,湯葉,納豆つくり,塩つくり,乾魚(干物(ひもの)),薫製,ベーコン,ハムの製造,乳製品つくり,練製品つくり,めん類やパンの製造などがそれである。前に述べたように,これらの食品加工はかつては広義の料理として家庭で行われたものであったが,現在では工場でつくられるものに変わった。…
※「塩」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...