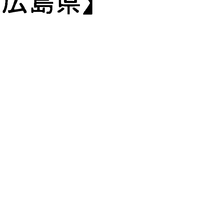精選版 日本国語大辞典 「広島」の意味・読み・例文・類語
ひろしま【広島】
- [ 1 ]
- [ 一 ] 広島県南西部の地名。県庁所在地。太田川のデルタ上に発達。天正一七年(一五八九)毛利輝元の築城に始まる。のち福島氏が入封し、江戸時代は浅野氏四二万六千五百石の城下町として発展。明治以後軍都としての性格が強く、日清戦争時には大本営が置かれ、第二次世界大戦までは旧日本陸軍第五師団司令部の所在地であった。第二次世界大戦では昭和二〇年(一九四五)八月六日に原子爆弾を投下されて壊滅的な打撃を受けた。戦後は国際平和文化都市として復興。現在は自動車・造船・産業機械・工作機械などの重工業と食料品・家具などの軽工業が発達し、カキ・ノリを養殖。明治二二年(一八八九)市制。昭和五五年政令指定都市。八行政区をおく。
- [ 二 ] 「ひろしまけん(広島県)」の略。
- [ 2 ] 〘 名詞 〙 「ひろしまやかん(広島薬鑵)」の略。
- [初出の実例]「『手めへせんどもって来たひろしまはどうした。』『アイおいらんのひばちへ湯をわかしておきいした。』」(出典:洒落本・青楼夜世界闇明月(1789‐1801)数有間勤傾契)
日本大百科全書(ニッポニカ) 「広島」の意味・わかりやすい解説
広島(県)
ひろしま
中国地方のほぼ中央にある県で、瀬戸内海に面した山陽地方に位置する。東は岡山県、西は山口県に接し、北は中国山地を介して鳥取県、島根県に続き、南は瀬戸内海を隔てて愛媛県と対している。瀬戸内海沿岸は瀬戸内工業地域の中心の一つで発展が著しいが、北部の中国山地では過疎化などの問題点を抱えている。県庁所在地は広島市。
2020年(令和2)の国勢調査による県の人口は279万9702人、面積は8479.65平方キロメートルで、人口は全国第12位、面積は全国第11位である。1872年(明治5)の人口は92万5962人、その後順調な伸びをみ、1920年(大正9)の第1回国勢調査の人口は154万1905人、1940年(昭和15)には187万人に達した。第二次世界大戦中はいくらか減少したが、戦後の1950年(昭和25)には208万人になった。広島市の人口が約120万人を数え、県人口の約43%を占める。
2020年10月現在、14市5郡9町からなる。
[北川建次]
自然
地形
県域の大部分は中国山地中央部の南斜面を占め、平野に乏しい。山地は脊梁(せきりょう)山地の高位面、吉備(きび)高原の中位面、瀬戸内海の低位面と三つの侵食面に分けられる。脊梁山地は1000~1300メートル、道後(どうご)山などの山々が連なり、山頂には高位平坦(へいたん)面がみられる。吉備高原は400~600メートルの緩やかな高原で、世羅(せら)台地などもこれに含まれる。低位面は100メートル前後の緩斜面で、瀬戸内沿岸や島嶼(とうしょ)部からなる。瀬戸内海の備後灘(びんごなだ)、安芸(あき)灘には芸予(げいよ)諸島など100を超える大小の島々が点在する。
河川は瀬戸内海に注ぐ河川と、日本海に注ぐ河川に分かれるが、分水界が南に偏っているので瀬戸内海側に流入する河川はあまり大きくない。東から芦田(あしだ)川、沼田(ぬた)川、黒瀬川、太田川、小瀬(おぜ)川などが瀬戸内海に注ぐが、山口県境に近い冠(かんむり)山に発して広島湾に注ぐ太田川のほかは中・小河川である。瀬戸内沿岸には太田川のつくる広島平野、芦田川下流の福山平野のほか、沼田川下流の三原市、賀茂(かも)川下流の竹原市、小瀬川下流の大竹市などの市街がのる小規模な沖積平野がある。日本海に注ぐ中国地方最大の河川江の川(ごうのかわ)の上流可愛川(えのかわ)は、島根県境の阿佐(あさ)山に発して東流し、三次(みよし)盆地で西城川、馬洗(ばせん)川、神野瀬(かんのせ)川と合流、江の川となって北西に流れ島根県境を越え江津(ごうつ)市で日本海に入る。江の川流域の三次盆地のほか、吉備高原上には庄原(しょうばら)盆地、東広島市ののる西条盆地などの山間盆地がある。
瀬戸内海は第四紀更新世(洪積世)の終わりごろ瀬戸内盆地が部分的に沈下し、また海面の上昇により形成されたものである。東から因島(いんのしま)、大崎上(かみ)島、大崎下(しも)島、上蒲苅(かみかまがり)島、下蒲刈島など芸予諸島の島々や、広島湾の江田島、倉橋島、厳島(いつくしま)(特別名勝・特別史跡)などが点在し、多島海の景観は瀬戸内海国立公園の一部となっている。なお県東部の山地は比婆道後帝釈国定公園(ひばどうごたいしゃくこくていこうえん)に、西部の島根・山口県境の阿佐山(1218メートル)、深入(しんにゅう)山などの山々は西中国山地国定公園に指定されており、前者には帝釈峡(たいしゃくきょう)(国の名勝)、後者には三段峡(特別名勝)の峡谷がある。県立自然公園に南原(なばら)峡、山野(やまの)峡、竹林寺用倉山(ちくりんじようくらやま)、仏通寺御調八幡宮(ぶっつうじみつぎはちまんぐう)、三倉岳(みくらだけ)、神之瀬峡の六つがある。
地質は、県土の約40%が花崗(かこう)岩類から形成され、これに流紋岩類を加えた火成岩類が約70%に達している。このほか広島市可部(かべ)付近や呉(くれ)市広、蒲刈上島、蒲刈下島、大崎上島、大崎下島、高根(こうね)島、因島にかけて部分的に古生層が残存し、三次盆地や庄原市付近には第三紀層が広く分布している。
[北川建次]
気候
瀬戸内海沿岸と中国山地では気候にかなりの差がある。沿岸部は瀬戸内式気候で、概して温暖で、年間を通じて晴天の日が多い。夏の夕凪(ゆうなぎ)現象は蒸し暑さで知られる。2017年(平成29)では、広島市の年平均気温は16.3℃、年降水量は1619.5ミリメートルである。四国山地で遮られるため台風の襲来も少ない。中国山地では冬季の冷え込みは厳しい。積雪も多く、スキー場が開設される所もある。中国山地の高峰に囲まれた標高の高い庄原(しょうばら)市高野町地区の年平均気温は10.8℃、年降水量は2268.5ミリメートルとなる。
植生は、沿岸部ではシイ、カシなどの常緑広葉樹を主とする照葉樹林帯(暖帯林)で、山間地域はナラ、ブナなどを主とする落葉樹林帯(温帯林)から形成されている。沿岸部や島嶼部ではアカマツの二次林が多いが、近年松くい虫の被害が多い。
[北川建次]
歴史
先史・古代
県の北東部から岡山県に及ぶ帝釈峡遺跡群は縄文時代を中心とする遺跡であるが、馬渡岩陰(まわたりいわかげ)遺跡からは先土器時代のものも出土している。縄文時代に入ると、県下各地に遺跡があり、縄文中期の大田貝塚(尾道(おのみち)市)からは多量の人骨が発掘されている。弥生(やよい)時代になると、中山貝塚(広島市)、松江遺跡(三原(みはら)市)、亀山遺跡(福山(ふくやま)市)などがある。4世紀後半になると、中小田(なかおだ)古墳(広島市)が出現し、東広島市の三ツ城古墳(みつじょうこふん)(国の史跡)は5世紀後半の安芸(あき)国最大の前方後円墳であり、三次盆地には浄楽寺・七ツ塚古墳群など多くの古墳がみられる。
7世紀には安芸国と備後国(びんごのくに)が成立し、安芸国の国府は当初東広島市西条に置かれ、のち安芸郡府中町に移された。備後国府は府中市に置かれた。また山陽道は畿内(きない)と大宰府(だざいふ)を結ぶ重要な官道となった。11世紀ごろから荘園(しょうえん)が増加し、大田荘(世羅(せら)郡)などが知られる。尾道は大田荘の年貢米積み出し港から発展した地である。平清盛(きよもり)は安芸国を知行(ちぎょう)国とし、厳島神社を厚く崇敬し、社殿を造営、荘園を寄進し、厳島は内海文化の中心となった。
[北川建次]
中世
平家滅亡後、鎌倉幕府は武田氏を安芸の守護に、土肥(どい)氏を備後の守護に任じた。その後、安芸の守護は今川、山名、大内各氏、備後の守護は長井、細川、渋川、今川、山名の各氏が任ぜられ、一方関東の小早川(こばやかわ)氏、吉川(きっかわ)氏らも地頭(じとう)としての勢力をもった。戦国時代は山陰の尼子(あまご)氏のほか、大内、武田、山名各氏が拮抗(きっこう)した。戦国時代末期に毛利氏(もうりうじ)が台頭し、守護の武田氏を滅ぼし、さらに大内氏の後を継いだ陶(すえ)氏を滅ぼし、内海一帯に実権をもち、3代輝元(てるもと)のときには豊臣(とよとみ)秀吉から中国地方一帯の9か国112万石を得た。瀬戸内海では海上交通が盛んで、因島の海賊衆村上氏の名が知られている。
[北川建次]
近世
関ヶ原の戦い(1600)後、毛利氏は周防(すおう)・長門(ながと)(山口県)2国に封じられ、安芸・備後は福島正則(まさのり)が支配したが、正則の改易で1619年(元和5)広島城には紀州から浅野長晟(ながあきら)が入り、安芸全域と備後の8郡を治める42万石の広島藩主となった。備後7郡は福山藩水野氏10万石が統治し、1698年(元禄11)水野氏が断絶すると、翌々年松平氏が入り、1710年(宝永7)以降は阿部氏の治下となった。
なお、1632年(寛永9)広島藩主浅野光晟(みつあきら)は庶兄長治(ながはる)に5万石を分与し三次藩が成立したが、三次藩は1720年(享保5)廃絶し、藩領は広島藩に返された。
江戸時代、芸・備両国で約100件の百姓一揆(いっき)が記録されている。1717年(享保2)年貢軽減を求める福山藩の惣(そう)百姓一揆や、翌年広島藩で起きた百姓一揆、1786年(天明6)福山藩全域で起きた百姓一揆が知られている。
一方、広島、福山両藩とも沿岸部では新田化が進み、一部は塩田となり、竹原や松永は製塩業で栄えた。中国山地では藩経営によるたたら製鉄が行われ、また、イグサ栽培と備後表の製造、備後絣(かすり)、安芸木綿、太田川流域のアサ栽培などが奨励された。
[北川建次]
近・現代
1871年(明治4)廃藩置県により広島県と福山県が誕生し、福山県は深津(ふかつ)県、小田県、岡山県を経て1876年広島県へ編入された。1889年の市町村制施行で広島市のほか464町村が誕生した。その後瀬戸内海沿岸に人口が増加し、明治から大正にかけて尾道市(1898)、呉市(1902)、福山市(1916)が次々と生まれた。
1872年広島城内に広島鎮台が置かれ、のち第五師団となった。1894年の日清(にっしん)戦争の際は広島市が臨時首都となり大本営、帝国議会も開かれ、宇品(うじな)港は軍事輸送に重要な役割を果たした。以後、広島市は軍都として発展の歩みを進めた。一方、呉には1889年鎮守府が置かれ、海軍工廠(こうしょう)も設けられて、軍港として重要な役割を担うこととなった。文教面では明治30年代までに県下に多くの中等学校、女学校が設立され、1902年(明治35)には高等教育機関として広島市に広島高等師範学校が置かれた。
昭和に入り、日中戦争、太平洋戦争と戦時色が濃くなり、1945年(昭和20)4月には第二総軍司令部が広島市に置かれた。1945年8月6日には広島に原爆が投下され、20万人近い死者を出す惨状となった。なお米軍の空襲により、呉市は市民だけで約2000人の犠牲者を出し、福山市も約350人の死者を出す被害を被った。
昭和30年代に入って生産県構想が出され、重化学工業を中心に工業が発達し、広島、呉、大竹、三原、福山各市を中心に多くの工業が立地した。1963年には福山市を中心とした備後地区が工業整備特別地域となった。
1973年(昭和48)の石油ショック以降、高度成長型の工業にもかげりがみえる。広島中央テクノポリスの指定を受けたこともあり、エレクトロニクスやバイオテクノロジーなどの先端工業の発展が期待されている。
1994年(平成6)にはアジア競技大会が広島市をはじめ、広島県下各地で開催され、さらに1996年には「ひろしま国体」が開催された。
[北川建次]
産業
広島県の産業別就業者人口を全国のそれと比べると、第一次産業と第三次産業が少なく、第二次産業がかなり多い。第二次世界大戦後は軍需工場が壊滅したこともあって農業人口が増大した。戦後の復興が進む1950年ごろから第三次産業が増え、1955~1960年にかけては第二次産業の急激な増加をみた。反面第一次産業は減少の一途をたどっている。2010年の国勢調査によると、第一次産業就業者の割合は3.4%、第二次産業26.6%、第三次産業70.0%である。
[北川建次]
農業
総農家数は7万8410戸(2002)で第二次世界大戦後減少を続けている。耕地面積も6万1500ヘクタールで、同様の傾向を示している。専業農家は1万2260戸で総農家数の15.6%に過ぎず、兼業農家が大部分を占める。経営規模は1ヘクタール未満が全体の47.9%を占め、広島県の農業が零細小規模であることを示している。
作付延べ面積では水稲がもっとも多く全体の54%、ついで果樹、野菜、飼肥料用作物、豆類などである。果樹の栽培面積は約6880ヘクタールで、柑橘(かんきつ)類が全体の60%を占め、ナシ、ブドウ、モモ、カキ、クリなども栽培される。
地域別にみると、広島市やその近郊町村では蔬菜(そさい)、生乳、卵などの生産が盛んで、とくに広島市の川内(かわうち)地区の広島菜の生産、東区小河原(おがわら)を中心とした養鶏が知られる。島嶼部では柑橘類(かんきつるい)栽培が盛んで、とくに瀬戸内のレモン、大崎下島の大長(おおちょう)ミカン、高根島の高根ミカンなどは有名である。このほか大長のネーブル、因島のハッサクなどが知られたが、主産地は他県に移っている。また世羅台地では赤ナシである幸水の栽培が盛んである。中国山地は古くから牧牛地帯で、とくに比婆(ひば)牛、神石(じんせき)牛などはよく知られている。三次(みよし)市に家畜市場があり、阪神方面からの買付けも多い。東部の神石高原は古くからコンニャクイモや葉タバコの栽培が有名であり、備後の沿岸では水田の裏作としてイグサ栽培があり、畳表の備後表として知られた。しかし近年では岡山県下、さらに熊本県に主産地が移った。東広島市西条を中心とした賀茂郡、世羅郡一帯のアカマツ林はマツタケの産地として知られている。中国山地では酪農のほかに、気候の冷涼性を利用して庄原市高野(たかの)町地区では暖地リンゴやダイコンの栽培が行われ、県西部の廿日市(はつかいち)市吉和(よしわ)などではワサビの栽培も行われている。
[北川建次]
林業
広島県の林野面積は約62万ヘクタールで、県総面積の約70%を占める。天然林が大部分で優良な人工林は少ない。林家数は5万0455戸(2000)、所有林1ヘクタール未満が約半数で、零細林家が多い。おもな用材としては、沿岸部のアカマツ、中国山地のスギ、ブナ、ナラ材などがあるが、量は少ない。
[北川建次]
水産業
県下の漁業経営体数は3536(2002)。年々減少している。漁船所有者のうち5トン未満の漁家が約半数を占め、零細な一本釣り、沿岸漁業が多い。漁獲物はタイ、ヒラメ、カレイなど沿岸魚が多い。江戸初期から行われているカキ養殖は広島湾を中心に全国生産の55%を占め、阪神・東京方面へ出荷している。ノリの養殖は減少しているが、ハマチ、タイ、ヒラメ、エビ、フグなどの養殖も行われ、養殖漁業では日本有数の県となっている。
[北川建次]
鉱業
従来中国山地の砂鉄を利用したたたら製鉄が盛んであったが、現在は芸予諸島や帝釈峡を中心とする石灰岩採掘や庄原市付近のろう石採掘が行われるにすぎない。
[北川建次]
工業
広島県の近代工業は、1881年(明治14)広島市瀬野川に官営広島紡績所が設置されたことに始まる。紡績所は完成と同時に士族に払い下げられたが、業績はあがらなかった。1889年、呉に海軍工廠が設けられたのが県の工業発展の基礎となった。広島市に日本製鋼所、三輪トラック製造の東洋工業(現、マツダ)、三菱(みつびし)造船、三菱機械(現、三菱重工業)、福山市に帝国染料(現、日本化薬)、三菱電機、因島の大阪鉄工所(のちに日立造船。現、カナデビア)などの工場が立地、発展した。第二次世界大戦後は呉市に造船、製紙、鉄鋼、大竹市に石油化学、紙・パルプ、福山市に製鉄など大企業が次々と立地し、瀬戸内工業地域の重要な拠点となった。2002年(平成14)の製造事業所総数は1万1041、従業員数は21万7000人を数える。製造品出荷額等は6兆6024億円で、中国地方第1位、全国で14位の高位にある。業種別では、輸送用機器が24.0%、以下、一般機械13.1%、鉄鋼12.7%、食料品7.6%、金属製品4.7%、電子部品4.7%となっていて、鉄鋼、機械など粗材生産、高度成長型の業種に偏していることがわかる。なお、かつて全国一を誇った造船業は、オイル・ショック以後不況が続き、さらに1985年(昭和60)の円高により決定的なダメージを受けた。現在、人員削減などの合理化が進んでいる。
地域別では広島地区の自動車、造船、機械、食料品、木材家具、雑貨、大竹市の紙、石油、電機工業、呉地区の鉄鋼、造船、機械、パルプ、三原市の電子、車両、機械、福山市の鉄鋼、電機、機械、化学工業などがある。内陸では中国自動車道沿いに鉄鋼、機械、電機、バイオテクノロジーなどの産業が立地している。
伝統工業としては、広島市の針、熊野町の筆、呉市の砥石(といし)、やすり、東広島市西条の酒造、福山市の琴、伸鉄、いかり、府中市のたんすや備後絣(かすり)などがそのおもなものである。
[北川建次]
開発
広島県は第四次長期総合計画(1995~2005)を進めたが、その中心に、中・四国地方の中心県としての管理中枢機能の強化、広域交通体系の整備、行政の広域的対応をあげた。広島市を中心に機能の集積を図り、メッセ・コンベンションシティとして国際的に開かれた都市を目ざしたのである。このための広域交通体系として、中国自動車道、本州四国連絡橋尾道―今治(いまばり)ルート(西瀬戸自動車道=瀬戸内しまなみ海道)、山陽自動車道、南北路として広島自動車道と浜田自動車道が開通、さらに広島空港も開港した。これらの基盤のうえに、瀬戸内海の開発と環境保全、広域観光開発の推進、中国山地中山間地域の農林業の活性化なども図られた。また広島県の工業が高度成長型の粗材生産に偏っていることから、広島中央テクノポリスを拠点に、エレクトロニクス、臨空工業の開発も指向している。また備北では中国自動車道沿いに大学が設置され、また工場などの立地を目ざした備北新都市圏開発を打ち出している。
[北川建次]
交通
国土縦貫的な幹線交通と、これに直交し、域内相互を結ぶ南北交通に分けられる。また広域交通と、都市間や域内を結ぶローカル交通とに分けられる。広域交通では瀬戸内沿岸部の都市を結んで、山陽自動車道、JR山陽本線、JR山陽新幹線、国道2号がある。内陸では中国山地を縦貫する中国自動車道がある。南北交通としては、広島と浜田を結ぶ広島自動車道と浜田自動車道、西日本旅客鉄道(JR西日本)の芸備(げいび)線、福塩(ふくえん)線、可部線などがあり、芸備線は山陽と山陰の連絡鉄道の役割を果たしている。なお、広島県(三次(みよし)市)と島根県(江津(ごうつ)市)を結ぶJR三江(さんこう)線があったが、沿線の過疎化等による利用者減少のため2018年(平成30)に廃線となった。ほかに松江、尾道、西瀬戸などの自動車道がある。道路では広島―松江を結ぶ国道54号があり、大竹から江津に至る186号、尾道―松江間の184号、福山―新見(にいみ)間の182号などがある。本州四国連絡橋の今治―尾道ルート(西瀬戸自動車道=瀬戸内しまなみ海道)は、1999年(平成11)5月に全線開通した。
空路は広島空港があり、国内線では東京、札幌、仙台、沖縄、成田、国際線ではソウル、大連(だいれん)、北京(ペキン)、上海(シャンハイ)、台北(タイペイ)、香港(ホンコン)と結ばれている。かつて存在した広島西飛行場は2012年に廃港。施設は「広島ヘリポート」となり、公共用ヘリポートとして使用されている。海運は、国際拠点港湾の広島、重要港湾に呉、尾道・糸崎、福山の四つがあり、これらを拠点に四国や内海の島嶼(とうしょ)を結んでいる。
[北川建次]
社会・文化
教育文化
広島藩5代藩主浅野吉長(よしなが)は、1725年(享保10)藩儒寺田臨川(りんせん)に命じて講学館を設立、藩の子弟の教育を行った。藩の最初の学問所であるが、享保(きょうほう)末年ごろ閉鎖。1782年(天明2)7代藩主重晟(しげあきら)は城内に藩校を設け、頼春水(らいしゅんすい)らを登用した。1870年(明治3)修道館と名づけられ、庶民の入学も許したが、1871年廃止。広島藩では家老が設立した講学所、朝陽館、明義堂、蒙養(もうよう)館などの学問所もあった。福山藩では、1786年(天明6)に藩校弘道館(こうどうかん)がつくられ、菅茶山(かんさざん)も教えている。庶民の聴講も許された。1854年(安政1)文武総合の藩校として誠之館(せいしかん)が設立された。菅茶山は神辺学問所とよばれる廉塾(れんじゅく)を開き、入門者は全国から集まったという。頼山陽も一時塾頭を務めたことがある。
2012年(平成24)現在、広島大学、県立広島大学など、国立大学法人1、公立4、私立16の大学がある(学生の募集を停止した大学を除く)。短大は公立1、私立5、高専は2を数える。
マスコミでは、広島県下をはじめ山口・島根県にも多くの購読者をもつ『中国新聞』がある。1892年『中国』の名で創刊されたもので、朝刊の発行部数は約61万(2016)。放送では、中国放送、広島テレビ、テレビ新広島、広島ホームテレビ、広島エフエム放送などがあり、NHK広島は中国地方の基幹局となっている。
[北川建次]
生活文化
東部の備後と西部の安芸では、県民性もやや異なる。備後は安芸よりも早くから開け、岡山県西部地方と似た方言もあり、京阪神の影響をより強く受けている。中央の動静に敏感で、進取的であるといわれるが、同じ備後でも城下町の福山は質実な気風を残し、港町の尾道は開放的で経済の動きに敏感だとされる。安芸地方は山口県東部と似た方言を用いる。瀬戸内海の主要航路からやや外れ、他地方からの影響を受けることが遅れ、大藩の城下町だったこともあって、おっとりして積極性に欠ける面があるといわれる。全体的には温和な気候、豊富な食物に恵まれ、第二次世界大戦前から退職者が多く住む所であった。したがって一般に保守的である。浄土真宗を信仰する人が多く、安芸門徒とよばれ、北陸と並んで真宗王国といわれている。他方、畿内(きない)と北九州を結ぶ廊下的な地域であるため進取の気性にも富み、移民が多かった地域でもある。1885年県民156人がハワイへ渡航したのを最初に、その後10年間に約1万1000人がハワイへ渡った。これは全国渡航者の約3分の1にあたる。
年中行事をみると、旧暦正月14日、県下各地で小(こ)正月の火祭「とんど」が行われる。三原市などではとんどを神明祭(しんめいまつり)といい、竹、松、笹(ささ)などを藁(わら)で長く巻いて「お山」とし、これを焼いて1年の無病息災を願う。旧暦3月3日の雛(ひな)の節供には実家から雛人形が贈られるが、三次(みよし)や三原の土人形(でこ)が用いられることが多い。またこの日を花見節供といって、弁当をもって花見に行く風習がある。5月5日の端午(たんご)の節供は全国各地と同様に鯉幟(こいのぼり)を立て、ちまきをつくるが、芸予諸島の漁村では若者たちによる櫂伝馬(かいでんま)の競漕(きょうそう)が行われる。厳島(いつくしま)神社の管絃祭(かんげんさい)は旧暦6月17日の夜に行われる。神体をのせた御座船が管絃を奏して夕刻本土の地御前(じごぜん)神社に渡り、夜半還御(かんぎょ)する。西日本各地から集まった大小の漁船が幟を立て、灯明をあげるさまは壮観である。お盆は各地で盆踊りが行われ、三原のやっさ踊りは阿波(あわ)踊りに似た激しい動きの踊りである。安芸門徒の墓地には美しい盆灯籠(ぼんどうろう)が数多く供えられる。
秋祭の神楽(かぐら)は、安芸では石見(いわみ)系、備後では出雲(いずも)系のものが演じられる。旧暦10月には、子供を中心とした亥の子(いのこ)が行われる。町内会ごとに亥の子駄屋という祭壇をつくり、子供たちが太鼓をたたいて町内を回る。また、亥の子石という数十本の引き綱に石をつけたもので地面をたたいて回る。秋の収穫祭の一つである。旧暦11月27日は親鸞上人(しんらんしょうにん)の命日にあたり、おたんや(逮夜(たいや))といって寺に参り、お通夜をしたり煮込み田楽(でんがく)を食べる風習がある。
[北川建次]
文化財
古くから開けた瀬戸内沿岸を中心に厳島(廿日市(はつかいち)市)、尾道、福山などに多くの文化財が分布する。これらを、国指定重要文化財を中心にみていくと、神社建築では、厳島神社には本社(本殿・幣殿など)、摂社客(まろうど)神社(本殿・幣殿など)、廻廊(かいろう)の国宝建築物のほか、海中の大鳥居、五重塔、多宝塔などがある。このほか、呉市の桂浜(かつらはま)神社本殿、北広島(きたひろしま)町の竜山八幡(たつやまはちまん)神社本殿、福山市新市(しんいち)町の吉備津(きびつ)神社本殿、同市鞆(とも)町の沼名前(ぬなくま)神社の能舞台など。
寺院建築では、尾道市浄土寺(じょうどじ)の多宝塔、本堂(以上国宝)、阿弥陀(あみだ)堂、山門、露滴庵(ろてきあん)など、西郷(さいごう)寺の本堂、山門、西国(さいごく)寺の金堂、三重塔、天寧(てんねい)寺塔婆など。禅宗の優れた建築として広島市不動院金堂(国宝)、庄原市の円通(えんつう)寺本堂、三原市の仏通(ぶっつう)寺地蔵堂、福山市安国(あんこく)寺釈迦(しゃか)堂などがある。このほか国宝建造物に福山市明王(みょうおう)院本堂・五重塔、尾道市向上(こうじょう)寺の三重塔がある。
民家建築には、廿日市市宮島町の神職林(はやし)家住宅、東広島市の豪商旧木原家住宅があり、三次市吉舎(きさ)町の奥家、同三良坂(みらさか)町の旙山(はたやま)家、同小田幸町の旧真野(しんの)家はいずれも江戸時代の豪農住宅である。
彫刻では、広島市不動院の木造薬師如来坐像(にょらいざぞう)、三滝(みたき)寺の木造阿弥陀如来坐像、尾道市浄土寺の木造十一面観音立像など、福山市明王院の木造十一面観音立像、三原市御調八幡宮(みつぎはちまんぐう)の木造狛犬(こまいぬ)などの重要文化財があり、絵画では尾道市持光寺の絹本著色普賢(ふげん)延命像(国宝)などがある。厳島神社は文化財の宝庫で、建築物以外に平家納経、紺糸威鎧(おどしよろい)、銘友成の太刀など国宝だけでも11件を数える。考古資料では、広島市福田の木ノ宗山(きのむねやま)出土の青銅器(重要文化財)、安芸高田(あきたかた)市甲田(こうだ)町荒神(こうじん)古墳から出土した副葬品などが知られている。
有形民俗文化財としては、中国山地のたたら製鉄、瀬戸内沿岸の製塩、造船などの資料などがとくに重要である。国指定の重要有形民俗文化財としては、三段峡上流にあり、ダム建設のため水没した「樽床(たるどこ)・八幡山(はちまんやま)山村生活用具および民家」、「芸北の染織用具および草木染コレクション」「川東(かわひがし)のはやし田用具」(以上、北広島町)などがある。
中国山地の村々では囃田(はやしだ)という共同の田植行事があり、壬生(みぶ)の花田植(北広島町)、「安芸のはやし田」(安芸高田市高宮町、北広島町)、塩原の大山供養田植(庄原市東城町)は国指定重要無形民俗文化財。神楽は、庄原市東城町の比婆荒神神楽が重要無形民俗文化財に、府中市上下町の弓神楽、広島市沼田(ぬた)の阿刀(あと)神楽が選択無形民俗文化財になっている。
このほか、「御神酒献備(ごしんしゅけんび)の古式」とよばれる奇習「久井稲生神社の御当(くいいなりじんじゃのおとう)」(三原市)、「安芸備後の辻堂の習俗」「安芸備後の水車風俗」が選択無形民俗文化財である。
なお、1996年(平成8)に厳島神社と広島市の原爆ドームが世界文化遺産に登録された。
[北川建次]
伝説
安芸門徒の名で知られるように、安芸は念仏信仰が深い。東広島市の長善寺の本尊「阿弥陀仏(あみだぶつ)」は、もと四国川ノ上八幡(はちまん)の御神体だったもの。この仏像が安阿弥(あんあみ)の作と聞いて海賊が盗んで船で運ぶ途中、暴風にあい海に投げ捨てた。長善寺の僧がそれを夢にみ、引き上げて寺に迎えたという。安芸郡坂町の沖に「六字岩」とよばれる暗礁がある。大坂石山合戦のとき、本願寺方を支援した毛利(もうり)勢の船が嵐(あらし)にあうが、親鸞上人(しんらんしょうにん)から授けられた六字の名号(南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ))を海中に投ずると、たちまち波が静まって無事に帰ることができた。名号がひっかかった暗礁を六字岩の名でよぶようになったという。厳島神社のある宮島は古くから神の島としての信仰が厚い。主峰の弥山(みせん)は三鬼(さんき)が擁護する神山で、弘法(こうぼう)大師が開いた「三鬼堂」には、消えずの火が燃え続けている。信仰に怠りがあるときは、三鬼が変化(へんげ)や妖怪(ようかい)の姿を借りて現れて戒めると伝えている。宮島の浜に「涙岩(なみだいわ)」という岩がある。厳島詣(もう)での徳大寺実定(さねさだ)という公卿(くげ)が、神社の内侍(ないじ)に心をひかれたが、帰京の命を受けて別離の涙を流した所という。一説には、実定の後を追った内侍が摂津(せっつ)住吉の沖合いに投身したとある。厳島神社の祭神「市杵島姫(いちきしまひめ)」は安産・子授けの神として信仰されているが、その一面嫉妬(しっと)深くて、夫婦そろって参詣(さんけい)すると縁を切るといわれている。広島市の周辺には狐(きつね)の伝説が多い。「江波のおさん狐(えばのおさんぎつね)」は京参りや伏見(ふしみ)詣での旅をしたこともあるという。祠(ほこら)は丸子山不動院の境内にある。広島市三滝(みたき)町の岩上稲荷(いわかみいなり)の主は白狐で、藩主池田公夫人に生き血を捧(ささ)げてから厚い信仰を寄せられるようになったと伝える。音戸(おんど)ノ瀬戸に架かる音戸大橋の下に「清盛塚」がある。平清盛は厳島神社の市杵島姫に思いを寄せて、姫の歓心を買うために音戸ノ瀬戸を1日で開削しようとした。工事なかばで満潮になったが、清盛がひとにらみするとたちまち潮が引いた。いまも満潮時にいっとき急潮が収まることがあり、「清盛の睨み潮(きよもりのにらみしお)」という。沼田川と西野川の間の沼地を干拓し潮止堤防を築くが波に壊される。人夫甚五郎(じんごろう)が自ら進んで人柱になった。近くに甚五郎社があり、その霊を弔って植えた松は「甚五郎松」といって樹齢約300年の大樹になっている。
[武田静澄]
『『広島県史』全27冊(1968~1983・広島県)』▽『後藤陽一著『広島県の歴史』(1972・山川出版社)』▽『藤井昭著『日本の民俗 広島』(1973・第一法規出版)』▽『若杉慧・村岡浅夫著『広島の伝説』(1977・角川書店)』▽『『広島県大百科事典』上下(1982・中国新聞社)』▽『『日本歴史地名大系 広島県の地名』(1982・平凡社)』▽『北川建次・渡辺則丈編著『広島県風土記』(1986・旺文社)』▽『『日本地名大辞典 広島県』(1987・角川書店)』

広島県章

大崎下島と大崎上島

深入山

帝釈峡

三段峡

三倉岳

広島城

入船山記念館(旧呉鎮守府司令長官官舎)

原爆ドーム

県立広島大学

頼山陽史跡資料館

広島県立美術館

広島平和記念資料館

浄土寺〈尾道市〉

西国寺

不動院

円通寺

明王院

壬生の花田植

熊野筆

備後絣

広島県位置図
広島(市)
ひろしま
広島県のやや西寄り、広島湾に面した市。県庁所在地。1980年(昭和55)全国で第10番目の政令指定都市となり、中国地方の中心をなしている。
1889年(明治22)市制施行。1929年(昭和4)安芸(あき)郡仁保島(にほじま)、矢賀(やが)、牛田の3村、佐伯(さえき)郡己斐(こい)、草津の2町と古田(ふるた)村、安佐(あさ)郡三篠(みささ)村、1955年安芸郡戸坂(へさか)村、1956年安芸郡中山村、佐伯郡井口(いのくち)村、1971年安佐郡沼田(ぬまた)、安佐の2町、1972年安佐郡可部(かべ)、祇園(ぎおん)の2町、1973年安佐郡安古市(やすふるいち)、佐東(さとう)、高陽(こうよう)の3町と安芸郡瀬野川町、高田郡白木(しらき)町、1974年安芸郡安芸町と熊野跡(くまのあと)村、1975年安芸郡船越(ふなこし)、矢野の2町をそれぞれ編入。1980年政令指定都市となり、中、南、東、西、安芸、安佐南、安佐北の7区に分かれ、1985年佐伯郡五日市(いつかいち)町を編入し佐伯区が成立。2005年(平成17)湯来町(ゆきちょう)を編入。面積906.69平方キロメートル。2020年の人口120万0754。なお、1889年の市制施行時の人口は8万3387、面積27平方キロメートルであった。
[北川建次]
自然
北部は中国山地が広がり、市域の約70%は山地、丘陵地が占める。太田川が山地を穿入蛇行(せんにゅうだこう)しながら東流し、県東部から西流してきた三篠川と合流して向きを南方向に転じ、広島平野を形成して広島湾に注ぐ。市の中心街は太田川とその分流の6河川のデルタ上に形成されている。なお、南部の広島湾に点在する島のうち似島(にのしま)などが市域に含まれる。気候は温暖な瀬戸内式気候である。
[北川建次]
歴史
広島湾岸には縄文期の貝塚などが発掘されており、弥生(やよい)期の遺跡は海岸沿いだけでなく太田川流域にもみられる。東区の木の宗(きのむね)山からは銅剣・銅鐸(どうたく)(国指定重要文化財)が発見されている。
1589年(天正17)毛利輝元(もうりてるもと)は太田川のデルタの寒村であった五ヶ庄(ごかしょう)の地に築城し、郡山(こおりやま)城(安芸高田市吉田町)から移り広島城下町を建設したが、関ヶ原の戦い(1600)に敗れ、広島城主は福島正則(まさのり)にかわった。続いて1619年(元和5)浅野長晟(ながあきら)が紀州から入封し、以後12代250年間浅野氏広島藩の治下にあった。1871年(明治4)の廃藩置県後、広島県の県庁が置かれ、1872年には広島城内に広島鎮台(のち第五師団)が設置、1889年県知事千田貞暁(せんださだあき)によって宇品(うじな)港が完成するなど近代都市としての歩みも始まった。1884年山陽鉄道が兵庫から広島まで開通、同年日清戦争(にっしんせんそう)が起こると、広島は対大陸向けの一大兵站(へいたん)基地となり、大本営が置かれ、広島臨時仮議事堂で第7回帝国議会が開かれた。以後広島は軍都として発展し、日露戦争、第一次世界大戦、太平洋戦争と戦乱のたびに拡大していった。これに伴い軍需工業をはじめ各種工業がおこった。
一方、1902年(明治35)に広島高等師範が、大正から昭和にかけて広島高等学校、広島文理大、広島工専、広島女専などの高等教育機関が設置され、文教都市ともなった。第二次世界大戦前、広島市は六大都市(「六大都市行政監査ニ関スル法律」で定められた、東京市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市)に次ぐ地位を占めていた。
1945年(昭和20)8月6日、史上最初の原子爆弾が太田川と元安(もとやす)川の分岐点に架かる相生(あいおい)橋を目標に落下、爆心地から半径2キロメートル以内は全壊全焼し、20万人余の死者を出した。戦後、焼土のなかから復興の歩みが始まり、1949年「広島平和記念都市建設法」が制定された。爆心地の中島(なかじま)地区は平和記念公園となり、市街を東西に貫く幅員100メートルの平和大通りが建設された。以後「ノーモアヒロシマズ」の精神にのっとって、国際平和文化都市としての歩みを続けている。
[北川建次]
産業
広島市は工業都市的性格が強い。都市化が進むなかで、市の北部の安佐北区、安佐南区や佐伯区では野菜や花卉(かき)栽培が行われる。とくに安佐南区の川内(かわうち)は漬物の広島菜の産地として知られる。また広島湾一帯では古くからカキ、ノリの養殖が行われるが、ノリは井口・草津地域の開発が進み、養殖漁場が消失したため、大幅に減少している。
第二次世界大戦中まで軍需工場が多かったが、戦後は三菱(みつびし)重工プラント建設(現、MHIプラント)、自動車メーカーのマツダ、日本製鋼所などによる機械工業が中心となっている。このほか食品、木工家具、ゴム、製針工業などがある。工業地域は市南部の臨海工業地帯や東郊に多い。
商業面では、卸売業は広島駅前、西部流通団地などに集中し、小売商店街は都心の中区八丁堀、本通り、紙屋町のほか、広島駅前、西区の横川、己斐、さらに郊外の安佐北区可部、佐伯区五日市などに形成されている。都心の紙屋町、基町(もとまち)一帯は中国地方の管理中枢機能が集中し、オフィス街、官庁街となっている。
[北川建次]
交通
JR山陽新幹線、山陽本線のほか、呉(くれ)線、芸備(げいび)線、可部線や、広島電鉄、広島高速交通(アストラムライン)が通じ、交通の要衝である。広島空港は三原(みはら)市にあり、広島市との間にバスの便がある。また、西区の広島湾沿いにある広島ヘリポートは、公共用ヘリポートとして使用されている。道路交通では中国自動車道、山陽自動車道、広島自動車道、広島高速道路が通じる。国道はかつての山陽道を踏襲する国道2号や191号、陰陽連絡道として重要な国道54号、261号のほか31号、183号、433号、487号、488号などがある。海上では広島港(宇品港)から四国の松山を結ぶ高速船、フェリーなどがある。
[北川建次]
文化・観光
原子爆弾が投下された都市として平和記念公園には広島平和記念資料館(原爆資料館)、平和祈念館、平和都市記念碑(原爆慰霊碑)などが設置されている。公園の北西には原爆ドーム(旧、産業奨励館)が被爆当時のまま保存されている。1996年(平成8)原爆ドームは世界遺産(文化遺産)に登録された。広島城跡(国指定史跡)には天守閣が再建(1958)され、内部は郷土博物館となっている。藩主の別邸庭園の縮景園は1620年(元和6)の築造で国指定名勝。京橋川東側の比治山(ひじやま)(71メートル)は市内の眺望に優れ、サクラの名所。比治山公園として整備され、園内には放射線影響研究所、現代美術館、まんが図書館などがある。広島城跡東方にある頼山陽(らいさんよう)居室は山陽が幽閉されていたところで国指定史跡、同地に頼山陽史跡資料館がつくられている。
東区の不動院は安土(あづち)桃山時代に安国寺恵瓊(えけい)が再建した寺で、金堂(国宝)のほか鐘楼、楼門、薬師如来坐像(にょらいざぞう)などの国指定重要文化財がある。西区の三滝寺(みたきでら)は紅葉の名所で多宝塔や、藤原時代の阿弥陀(あみだ)如来坐像(国指定重要文化財)で知られる。広島駅北側の二葉山南麓(なんろく)には東照宮、国前寺(こくぜんじ)、饒津(にぎつ)神社の社寺がある。民俗文化財には、安佐南区の阿刀(あと)明神の祭礼に奉納される阿刀神楽(かぐら)(選択無形民俗文化財)がある。文化施設は、中区に広島県立美術館、こども文化科学館、ひろしま美術館、映像文化ライブラリーなどがある。安佐北区に安佐動物公園、佐伯区に市立植物公園、東区に広島市森林公園がある。また南区にはプロ野球広島東洋カープの本拠地広島市民球場がある。広島湾内の似島の安芸小富士や、宇品築港の際に陸繋島(りくけいとう)となった宇品島にはシイの原生林があり、ともに瀬戸内海国立公園の一部になっている。
[北川建次]
『『広島市史』全5巻(1922~1925・広島市)』▽『『図説広島市史』(1989・広島市)』

広島県広島市位置図

広島市の行政区

明治時代の宇品港

原爆ドーム

広島市の原爆被災図

相生橋〈広島市〉

平和大通り

広島電鉄5100形

広島高速交通(アストラムライン)

平和記念公園

広島平和記念資料館

広島城

縮景園

不動院

広島市現代美術館

広島市まんが図書館

頼山陽史跡資料館

広島県立美術館

ひろしま美術館
広島(島)
ひろしま
香川県北西部の備讃(びさん)瀬戸に点在する塩飽(しわく)諸島最大の島。丸亀(まるがめ)市に属す。面積11.66平方キロメートル。島の南部、江の浦(えのうら)港と丸亀港とを結んで定期船が通う。塩飽七島の一つで、江戸時代には人名(にんみょう)とよばれる自治制度があった。花崗(かこう)岩からなり、青木、甲路(こうろ)地区では青木石とよばれて採石が盛んで、石材業従事者が多く、活気がある。対照的に市井(いちい)、茂浦(もうら)地区は過疎化が著しい。海岸部は瀬戸内海国立公園域で、岡山側からの海水浴客も多い。人口の減少が続いており、2009年(平成21)の人口は373。
[坂口良昭]
広島(旧町名)
ひろしま
北海道南西部にあった旧町名(広島町(ちょう))。北広島市の町制時代の名称で、1996年(平成8)広島町が市制施行して広島市となり、即日北広島市と改称。
[編集部]
改訂新版 世界大百科事典 「広島」の意味・わかりやすい解説
広島[県] (ひろしま)
基本情報
面積=8479.58km2(全国11位)
人口(2010)=286万0750人(全国12位)
人口密度(2010)=337.4人/km2(全国18位)
市町村(2011.10)=14市9町0村
県庁所在地=広島市(人口=117万3843人)
県花=モミジ
県木=モミジ
県鳥=アビ
中国地方の中央部に位置する県。東は岡山県,西は山口県,北は中国山地を境に島根県,鳥取県に接し,南は瀬戸内海をはさんで愛媛県に対する。
沿革
かつての安芸・備後両国の全域にあたる。江戸時代末には広島藩,福山藩に天領および豊前中津藩領の飛地があった。1868年(明治1)5月神石郡1村と旧天領の甲奴(こうぬ)郡12ヵ村が新設の倉敷県に編入され,71年の廃藩置県の実施に伴い各藩はそれぞれ同名の県となって,芸備両国は広島県,福山県,中津県の一部,倉敷県の一部に分かれた。同年11月の府県統廃合に際し,中津・倉敷両県下の甲奴郡は広島県へ移管され,それ以外の地域は福山県と合併して新置の深津県(1872年小田県と改称)となった。75年小田県はいったん岡山県に編入されたが,翌76年備後国6郡が広島県へ移管され,現在の県域が確定した。
広島県の遺跡
帝釈峡(たいしやくきよう)遺跡群(庄原市,神石郡神石高原町)は馬渡(まわたり)岩陰,寄倉(よせくら)岩陰,観音堂洞穴など多数の石灰岩の岩陰や洞穴からなり,先土器時代以降の文化層がみられる。大田貝塚(尾道市)は69体もの人骨を出土した縄文前期~後期の貝塚。中山貝塚(広島市東区)は瀬戸内海沿岸における縄文晩期から弥生中期にわたる文化の推移を示しており,弥生土器編年の標式となっている。西山貝塚(広島市東区)は弥生中期末から後期終末の,広島湾を一望する典型的な〈高地性集落〉である。標高258mの貝塚では巴形銅器,銅鏃,丁字頭の土製勾玉などが採集されている。青銅器といえば,銅鐸,銅剣,銅戈が大石の下から伴出したことで著名な福田遺跡(広島市東区)がある。
石鎚山(いしづちやま)古墳群(福山市)は,古墳時代前期(4世紀後半)の円墳群で,墳裾列石をもち,二神二獣鏡も出土している。浄楽寺・七つ塚古墳群(三次市)は前期から中期にかけての前方後円墳4基を含む172基が集中する。三ッ城(みつじよう)古墳(東広島市)は全長86m,高さ13mと安芸最大の前方後円墳。葺石(ふきいし),円筒・形象埴輪のほか副葬品も豊富で,5世紀後半である。尾市(おいち)古墳(福山市)は1辺12mほどの終末期の方形墳。
歴史時代では,安芸国分寺址(東広島市)のほか,奈良時代前期の寺町廃寺址(三次市)がある。《日本霊異記》にみえる三谷寺に比定され,完全な法起寺式伽藍配置を示す。塔・金堂址の塼(せん)積み基壇は日本最古の例で,瓦とともに百済の軍守里廃寺址などと類似する。初期の仏教文化が直接,地方に伝播した姿をよく示している。下岡田遺跡(安芸郡府中町)は礎石をもつ建築址,掘立柱建築址,素掘り井戸址などからなる。奈良時代後期末から平安時代と考えられ,806年(大同1)の勅にみる〈安芸駅館〉に比定されている。草戸千軒(くさどせんげん)遺跡(福山市)は芦田川の中州にある平安~江戸時代の遺跡として有名。明王院(旧,常福寺)の門前町でもある港町が旧芦田川のたびたびのはんらんで水没したもので,最盛期は鎌倉時代後半から南北朝時代にかけての時期である。遺構は掘立柱建物からなる町並みで,陶磁器,木製品,土器,金属製品など各種膨大な遺物が出土する。近年,尾道市でも同様の中世以来の港町の大規模な遺構が調査されつつある。
→安芸国 →備後国
執筆者:坂本 一登
平地の乏しい自然
北と西の県境に標高1000~1350mの中国山地の脊梁部が東西に走り,その南側に標高300~700mの神石高原,高田高原や世羅台地,賀茂台地を含む吉備高原が続いている。高原と台地を刻む江(ごう)の川水系(可愛(えの)川,西城川,馬洗(ばせん)川)の谷は浅くて幅広く,谷頭まで水田がみられる。その中心が三次(みよし),庄原の盆地であり,これより流れ出た江の川は中国山地を西(芸北山地)と東(備北山地)に分断して島根県を経て日本海に注ぐ。瀬戸内海に注ぐおもな河川は西から太田川,沼田川,芦田川などがあるが,いずれも中小河川で,高原や台地の南縁を深く刻み込み,太田川上流には名勝として知られる三段峡がある。平地は太田川下流の広島平野と芦田川下流の福山平野ならびに三次,庄原,西条の3盆地に限られ,県面積のわずか5%にすぎない。島嶼(とうしよ)部は東から東部芸予諸島(向(むかい)島,因島(いんのしま),生口(いくち)島など),中部芸予諸島(大崎上島,大崎下島,上蒲刈(かみかまがり)島,下蒲刈島など),西部芸予諸島(倉橋島,江田島,西能美(にしのうみ)島,東能美島,厳(いつく)島など)に区分され,島嶼の間に備後灘,安芸灘,広島湾が分布する。このような島嶼部の水陸分布は沖積世に元来は谷であったところに水が浸入して形成されたものである。本土沿岸部と島の海岸線は屈曲に富み,入江には内海航行の要港や小型漁船の集まる漁港がある。
気候は一般的には瀬戸内気候に属し温暖少雨であるが,沿岸・島嶼部と内陸部とでは冬季の温度や夏季の降水量でかなりの違いを示す。1月の平均気温は沿岸・島嶼部で5~6℃,内陸高原部で2~3℃,中国山地で0~-2℃である。一方,8月の降水量は呉~福山間の沿岸部で90mm以下でときおり深刻な水不足に襲われるが,芸北山地は200mmを超す中国地方最大の多雨域であり,これに隣接する広島湾岸も120mm前後を記録する。
兼業依存の農業
農家1戸当りの耕地面積はわずか76a(1995),同農業粗生産額は151万円(1995)であり,著しく零細である。零細経営は藩政期以来の特徴で,例えば明治初期の記録でも農民1人当り耕地は,全国73ヵ国の中で安芸国が下から2番目,備後国が6番目となっている。このため,早くから商品作物の導入を積極的に進めたほか,諸国への行商・出稼ぎ,海外移民が勧められた。第2次大戦後は沿岸部の工業化・都市化に伴って兼業化が進み,1995年までの10年間の兼業率は8割前後である。かつて農家経済を支えてきたものの中で,内陸部の砂鉄,和紙,沿岸・島嶼部のワタ,ジョチュウギク,塩は衰滅した。イグサ,タバコ,コンニャクなどの工芸作物は根強く残っているが,かつての盛況はない。94年の農業粗生産額1376億円の内訳は米39.8%,野菜15.8%,果樹11.8%,畜産25.1%であり,最近15年間の変化は畜産の減少分が野菜と果樹の増加となっている。野菜栽培は従来,広島市および福山市周辺の都市近郊型に限られ,特産品としては広島市北郊で生産される広島菜漬ぐらいであったが,最近は内陸高冷地でのキャベツ,ダイコン,キュウリ,ピーマンなどの特産地形成が進んでいる。果樹の主体はウンシュウミカンであり,温暖な中部島嶼では90%以上の栽培農家率を示す町村もある。近年は需給不安定の対策としてネーブル,オレンジ,ハッサクなど高品質かんきつ類への転換を進めている。神石牛,比婆(ひば)牛の名で知られる中国山地の和牛は,放牧と舎飼いによって1戸平均3~4頭を飼育するが,最近は乳牛と豚の出荷が漸増しているのに対し,肉牛出荷は一進一退を繰り返し,県内14ヵ所あった常設家畜市場も三次,庄原の2ヵ所に統合された。水産業は沿岸漁業を中心とするが,零細なうえに工業化の進展に伴って後継者を奪われ,老齢化が著しい。広島県の水産業の特色はカキ,ノリなどの養殖漁業にあり,とくにカキは全国の70%,全国一の生産をあげている。
高水準の工業生産
零細な農業経営と早くからの商品貨幣経済の浸透によって,県内各地にいろいろな伝統工業が興っていた。砂鉄生産(たたら製鉄)に結びついた広島市の縫針とふろ釜,呉市のやすり,福山市鞆(とも)の船釘,いかり,芦田川下流域のワタを原料とした備後絣(かすり),府中市の桐だんす,福山市松永の下駄,熊野町の筆,呉・三原両市および東広島市西条の酒造などであり,明治以降の近代工業発展への基盤となった。その端緒は官営広島紡績所(1881創設)と呉海軍工厰(1894創設)の設立であり,日清・日露両戦争と2度の世界大戦を通じて機械・金属,造船,繊維・紡績,食品などの近代工業が飛躍的に発展した。第2次大戦後は旧軍時代の優秀な技術と戦災から免れた施設を活用し,おりからの朝鮮戦争と輸出船ブームにのっていちはやく回復した。自動車,造船,一般機械などの加工組立型産業の発展である。さらに広島県は1952年に生産県構想を打ち出し,臨海部に鉄鋼(福山),化学(大竹)など最新鋭の大規模工場を積極的に誘致した。この結果,高度成長期には全国を上回る経済成長を遂げた。しかし,1973年の第1次石油ショックを契機に,広島県のこれらの重厚長大型の産業構造は深刻な不況に陥り,電気機械への転換など産業構造の多角化や高度化に後れをとった。さらに85年の円高は輸出依存度の高い広島経済を大きく停滞させ,減速傾向はバブル崩壊によって90年代もなお続いている。県全体の製造品出荷額等(1995)は全国第13位という比較的高い水準にあるが,その内容をみると輸送用機械が26%で,これに一般機械15%,鉄鋼12%と続く。電気機械の工場が東広島,福山に進出したが,いまだ全体の7.7%を占めるにすぎない。
瀬戸内の流通拠点
広島県は近畿と北九州の中間にあり,内海および山陽筋の交通に恵まれているので,古くから商業活動が活発であった。広島藩浅野氏の城下町広島,福山藩阿部氏の城下町福山,内海随一の要港尾道には多くの問屋が集まり,背後に広い商圏をもっていた。1979年の商品販売額は卸売で全国の2.4%(7位),小売で2.3%(11位)であるが,中国5県の実に54.2%を占め,実質的な流通拠点である。ちなみに91年のシェアは52.4%を示し,拠点性が若干低下している。なかでも広島市は福岡市,仙台市,札幌市と同じく広域中心都市として位置づけられ,行政・経済機能において他の3都市と遜色ないが,広範な地域との連係を指示する卸売,広告,情報,サービス業などの業種でははるかに劣っている。これは,瀬戸内沿岸の東西交通の発達のわりには,県内および山陰・四国方面との南北交通の整備が遅れているためである。
交通
瀬戸内海沿岸を東西に走る山陽道(中国路)は,古くから近畿地方と九州地方とを結ぶ幹線道路として重要な役割を果たしてきた。また石見(いわみ)街道,出雲(いずも)街道,伯耆(ほうき)街道はそれぞれ山陰と山陽とを結ぶ連絡路としての機能を果たしていた。現在の国道もほぼ同じルートに沿っており,旧山陽道沿いの2号線をはじめ,54号線(広島~三次~松江),184号線(尾道~三次~松江),186号線(大竹~浜田),261号線(広島~江津)などがある。このほか中国縦貫自動車道(1983開業),中国横断自動車道広島浜田線(91全線開業),本州四国連絡橋尾道~今治ルート(99開業),山陽自動車道(97本線が全線開業)などの高速交通体系の整備が進められた。鉄道は山陽新幹線,JR山陽本線,呉線が沿岸部を東西に走り,芸備線,木次(きすき)線によって広島と松江が結ばれ,三次からは三江線が江津に,福塩線が福山に通じている。また広島~三段峡間(2003可部~三段峡間廃止)には可部線が通じている。海上交通は広島~松山,呉~松山,三原~今治,尾道~今治(後2者は休止・廃止)などの主要航路のほか,沿岸各地と各島嶼間を結ぶ多くの航路があり,広島~別府間の航路も開設されている(現在は廃止)。1993年開港の広島空港(三原市南西部)と従来からの広島西空港(広島市。現,広島西飛行場)の2空港があり,北海道,仙台,東京,宮崎,沖縄などへ定期航空路がある。
広島,備後,備北の3地域
県内は自然条件,歴史的背景,そして現在の都市と周辺農村との経済的結びつきによって,広島,備後,備北の3地域に区分される。これは新全国総合開発計画に基づき1969年に設定された地方生活圏の圏域に合致する。
(1)広島地域 県域の西半部を占め,広島市を中心に呉,竹原,大竹,東広島,廿日市,江田島,安芸高田の各市と安芸,山県(やまがた),豊田3郡の全域からなる。県面積の52.3%,人口の3分の2強を占める。地形高峻で冬季積雪をみる芸北地方は過疎地域であるが,最近は中国縦貫自動車道の建設その他によって若干改善された。一方,島嶼部は交通,農漁業基盤,生活環境が改善されつつあるが,本土との格差は依然大きい。海域ではカキ養殖をはじめ,〈育てる漁業〉が盛んである。
(2)備後地域 県東部の南半部を占める。福山市を中核とし,三原,尾道,府中という個性的な3市と,世羅,神石の両郡全域からなる。県面積の23.7%,人口の3分の1弱を占める。行政上は西への傾きを示すが,歴史的・文化的には東の岡山県との結びつきが強く,方言上も同一性を示す。商品作物のいち早い導入,各種伝統工業の育成にみられるように京阪地方の動きに敏感であり,進取的である。日本鋼管の福山市進出,本州四国連絡橋尾道~今治ルートの段階的架橋などによって,この地域の社会経済は大きく変貌しつつある。
(3)備北地域 県東部の北半部を占め,三次・庄原両市からなる。県面積の23.9%を占めるが,人口は20分の1に満たない。2004年・05年の合併以前の三次・庄原両旧市以外は過疎地域で,1960-75年には人口が26.6%も激減し,廃村状態に追い込まれた集落も多い。零細な稲作主体の農業で,これに和牛やタバコ,コンニャクを組み合わせているが,瀬戸内沿岸のような有利な商品作物や兼業の機会は得られなかった。近年,減反政策への対応や中国縦貫自動車道など交通網の整備により,畜産や野菜の特産地形成の動きがあり,また三次市を中心に企業進出も目だつ。島根県と似た方言が話され,また神楽や囃子田など全国的に有名な民俗文化財も多い。
執筆者:藤原 健蔵
広島[市] (ひろしま)
広島県西部に位置する県庁所在都市。2005年4月旧広島市が湯来(ゆき)町を編入して成立した。人口117万3843(2010)。
広島
広島市中東部の旧市で,県庁所在都市。1889年市制。人口112万6239(2000)は中国地方最大規模。1980年4月に全国10番目の政令指定都市となり,中,東,南,西,安佐南,安佐北,安芸の7区を設置。85年には隣接する五日市町を合体して佐伯(さえき)区を置き,現在の8区となる。市域は中国山地を背に太田川中・下流域に広がり,南は瀬戸内海に面する。中心市街地は太田川三角州上にあり,市内を6本の川が分流し〈水の都〉といわれる。しかし反面,標高50m以下の土地は全市域の16.8%にすぎず,およそ4分の1は標高100m以上の丘陵地,山地であり,市街地拡大の阻害要因となっている。
城下町広島は明治に入ると紡績所の設置,宇品の築港など県都としての整備が進められた。とりわけ日清戦争が始まると大本営が置かれ,大陸向け兵員や物資の輸送基地となりにわかに軍都としての性格を強めた。一方,現在の広島大学の前身である広島文理科大学,広島高等学校などが創設され,中国地方の文教の中心として発展した。第2次大戦前には人口42万に達し,六大都市に次ぐ規模となった。
ところが1945年8月6日,一発の原子爆弾によって壊滅。20万をこす死者を出し,向こう75年間は草木も生えぬといわれ,人口も8万余に激減した。しかし〈広島平和記念都市建設法〉を中核に被爆からの復興に取りかかり,平和公園を中心に幅100mの平和大通りを東西に通じ,広島城を含む旧軍用地を中央公園と官公庁地区として整備し,その南側にある紙屋町,八丁堀の業務中心地区と本通り商店街に一体化させて中心機能を高めた。高度経済成長期には,軍港時代に蓄積した技術と施設を土台に三菱重工業,東洋工業(現,マツダ)などの機械工業が活気を取り戻し,さらに呉,大竹,岩国などの工業地帯の発展を背景に,広島市に金融機関,商社などの経済機能が集積した。都市の基盤整備も広島空港(1993年広島西飛行場へ名称変更)の開港,太田川放水路の完成,新広島国道の開通,山陽新幹線の全線開通など順調に進んだ。現在,中国自動車道から分岐した広島自動車道が山陽自動車道に接続している。都市づくりの最高目標を〈世界平和に貢献する国際平和文化都市〉におき,原水爆禁止運動を中心に世界の恒久平和を希求して積極的に発言した。
政令都市移行後は各区の文化・社会機能の整備拡充を進めるとともに,広島の戦後を象徴する基町地区再開発事業,海域埋立てによる西部開発事業,21世紀に向けた都市づくりを先導する西風新都の建設など積極的に都市基盤の拡充が図られている。しかし一方,1993年に広島空港(三原市),95年広島大学(東広島市)の相次ぐ移転といった広域中枢都市にとって不可欠な機能の喪失,基幹産業の輸送用機械工業の業績不振による地域経済の沈滞などがあり,その成り行きは見逃せない。市中心部には96年に世界文化遺産に登録された〈原爆ドーム〉を含む平和記念公園のほか,原形復元された表御門のある広島城跡(史),旧藩主浅野氏の庭園縮景園(名),市内を展望できる比治山公園などがある。
執筆者:藤原 健蔵
広島城下
1589年(天正17)4月から毛利輝元の島普請とよばれる広島城の建設が行われ,以後毛利,福島,浅野の各大名の城下町として発展した。毛利時代は,枝状に分かれた太田川本・支流と,平田屋川・西堂川(せいとうがわ)両運河に堤防を築き,大規模な城郭を中心として周辺に広く武家屋敷を配置し,町人町は城郭の南西に区画したが,皮屋・材木両町のほかは町名も明らかでない。しかし,1600年(慶長5)福島正則の入城とともに,近世城下町として急速に整備される。
福島正則は城下東端の岩鼻(いわのはな),西郊の佐西郡草津村,および比治山近傍の3ヵ所に大門を設けて町在の境と定めるとともに,武家町を大幅に縮小して,職人・商人町の拡大をはかり,領国経済の要の役割を果たさせようとした。城北を通っていた山陽道(西国街道,中国路)を城下に引き入れて東西に貫通させ,また,山陽道から分岐する雲石路を北に向けて走らせ,その両沿道に町人町を配置したのも,そのあらわれである。このほか,城下町商業の繁栄のために山陽道北筋に胡(えびす)社を移すとともに,市の町を設けて月4回の市立てを許可し,城下の河川・運河に架橋して交通の便をはかり,各町並みの整備にも努めた。なお,城下の北西に仏護寺とその末寺の寺々を移転させて寺町をつくり,白島(はくしま)を城下と陸続きにし,城郭をとりまく河堤のかさ上げを行ったのもこの時代である。こうして広島城下は,町はずれ372石,町新開1329石余を除き,武家町と50余町の町人町で構成された。武家町は原則的にそれぞれ所属の組頭の支配下におかれたが,町人町は町奉行の支配下に,新町組,中通組,白神組,中島組,広瀬組の5町組に分かれ,各町組に1人ずつ大年寄,各町に町年寄以下の町役人がおかれ,町行政をつかさどった。
1619年(元和5)入封の浅野長晟(ながあきら)以降も,ほぼ前代の町づくりを継承したが,22年町奉行を東西に分け,寺社・町両奉行支配に改めたこと,武家町と町人町を厳重に区別し,武家町に侍町惣門,町人町に町門(木戸)を設けて通行制限,夜間通行の禁止などを定めた。町門は109を数えたが,1758年(宝暦8)の大火以後,69に減少した。城下の町数は,1625年(寛永2)の55町が77年(延宝5)に68町に増え,1757年新開奉行の創設とともに新開組に編入された町もあり,64町に減少した。新開組35町村は,ほとんどが近世前期に干拓された高付地であるが,町組の外延的拡大によって一体的機能を果たすようになった。町家数は,1619年に2000軒,63年(寛文3)3504軒,1715年(正徳5)4928軒,1822年(文政5)6432軒(1万2624竈)と増加するが,町組は1715年を境に停滞し,新開組が急増を示した。また,町方人口は,1677年3万7406,1715年4万8010,92年(寛政4)4万8790,1819年4万7228であった。ただし,新開組では1677年を100とすれば,以下それぞれ175,340,362と年を追って増加している。
広島城下町は近世を通じて規模の拡大をみたが,同時に広島藩の経済政策は,城下町商業・金融機能の発展を促した。18世紀以降になると中国地方最大の都市に成長し,藩領支配の中枢はもとより,領域・領外市場の結節点となって頻繁な交易・交流が行われ,政治・経済・文化的機能の拠点的役割を果たすようになった。なお,明治維新後は,広島県の中心として城内本丸に県庁(のち水主(かこ)町に移る)や,鎮西鎮台第1分営が設置された。のち第5軍管広島鎮台,ついで第5師団が置かれ,広島の町は軍都としての性格を強めた。
執筆者:土井 作治
湯来
広島市西部の旧町。旧佐伯郡所属。人口7895(2000)。中国山地の山間にあり,中央を太田川の支流水内(みのち)川が北東流する。東は旧広島市に接する。町域の大部分を占める山林には植林が進められ,シイタケ,ワサビの栽培が行われる。〈山フグ〉と呼ばれるコンニャクの刺身は名物として知られる。酪農や養鶏が盛んで,生乳は旧広島市へ出荷される。冠山(1004m)東麓の渓谷に湯来温泉(放射能泉,35℃),水内川沿いに湯ノ山温泉(放射能泉,24℃)がある。湯ノ山温泉は江戸時代中期に湯治場として開かれ,藩主をはじめ多くの文人墨客も訪れた。湯坪,湯舎など当時の姿をよくとどめ,湯ノ山明神旧湯治場として国の重要有形民俗文化財に指定されている。近くの水内川支流には景勝地の石ヶ谷峡がある。花コウ岩の渓谷で,約7kmにわたって名号岩,屛風岩など奇岩の岩壁が連なり,峡中には多数の滝がある。
執筆者:清水 康厚
広島 (ひろしま)
香川県北西部,瀬戸内海の塩飽(しわく)諸島最大の島。丸亀市に属する。面積11.82km2,人口374(2010)。花コウ岩を基盤に上部に安山岩を頂く溶岩台地で,最高点は大戸山(312m)。島の西端で採掘される良質の黒雲母花コウ岩は青木石と呼ばれ,青木や甲路(こうろ)から出荷される。南岸の江の浦港には丸亀港からのフェリーが寄港し,付近は海水浴場として知られる。一方,島の裏側に当たる北岸の茂浦(もうら)や市井,東岸の田浦などは過疎化が著しい。
執筆者:坂口 良昭
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「広島」の意味・わかりやすい解説
広島[県]【ひろしま】
→関連項目山陽地方|中国地方
広島[市]【ひろしま】
→関連項目可部|祇園(広島)|広島[県]|広島[駅]
広島[駅]【ひろしま】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
日本歴史地名大系 「広島」の解説
広島
ひろしま
- 香川県:丸亀市
- 広島
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「広島」の意味・わかりやすい解説
広島
ひろしま
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
デジタル大辞泉プラス 「広島」の解説
広島
事典・日本の観光資源 「広島」の解説
広島(王頭山)
「香川のみどり100選」指定の観光名所。
出典 日外アソシエーツ「事典・日本の観光資源」事典・日本の観光資源について 情報
世界大百科事典(旧版)内の広島の言及
【北広島[市]】より
…北海道中央西部,札幌市の南東にある市。1996年9月札幌郡広島町が市制,改称。人口5万3536(1995)。…
【北広島[市]】より
…北海道中央西部,札幌市の南東にある市。1996年9月札幌郡広島町が市制,改称。人口5万3536(1995)。…
※「広島」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...


 広島県南西部の市。
広島県南西部の市。