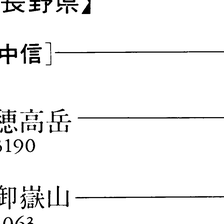精選版 日本国語大辞典 「長野」の意味・読み・例文・類語
ながの【長野】
- [ 一 ] 長野県北部の地名。県庁所在地。善光寺の門前町にはじまり、市場町も兼ね、近世初期、北国街道の開通後は宿場町として発展。信州リンゴ栽培の中心地。川中島の古戦場や松代城跡、飯縄高原、善光寺などがある。明治三〇年(一八九七)市制。
- [ 二 ] 「ながのけん(長野県)」の略。
ながの【長野・永野】
- 姓氏の一つ。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「長野」の意味・わかりやすい解説
長野(県)
ながの
本州の中央部に位置し、中部地方の東部を占める県。面積は1万3561.56平方キロメートルで全国都道府県中の第4位である。周囲を新潟、富山、岐阜、愛知、静岡、山梨、埼玉、群馬の8県に囲まれた内陸県である。古来畿内と東国を結ぶ交通路にあたり、東西の文化・技術の影響を受けてきた。県域の80%は山岳地で、これに火山山麓(さんろく)などの高地6%を加えると、生活の中心となる平地と台地は約14%にすぎない。県域は、中央部をほぼ南北に走る筑摩山地(ちくまさんち)と八ヶ岳火山連峰(やつがたけかざんれんぽう)によって東西に二分される。東部は、北流する千曲(ちくま)川の流域で、上流から佐久(さく)、上田、長野の3盆地が連なり、佐久盆地、上田盆地を東信、長野盆地を北信とよぶ。西部は、犀(さい)川、天竜川、木曽(きそ)川などの流域で、松本、諏訪(すわ)、伊那(いな)の3盆地と木曽谷に分かれ、松本盆地を中信、ほかを南信とよんでいる。県庁所在地は長野市。
1920年(大正9)第1回国勢調査時の人口は156万2722人であったが、2020年(令和2)の国勢調査では204万8011人になった。本県の人口は第二次世界大戦前後に一時疎開・海外引揚げなどのため急増したが、以後1970年(昭和45)まで一貫して減り続けた。1970年からは、しばらく自然増加・社会増加が続いたものの、2005年調査からはふたたび減少に転じている。本県人口現象の特色は全国の特色と同様である。第一の特色は高齢化で、2000年には65歳以上の人口が県総人口の21.4%で全国平均より4%ほど高くなった。山間地の町村では30~40%に達している。第二の特色はいわゆる核家族化の傾向が強まり、1世帯当り1950年(昭和25)の3.58人から2000年には2.89人になっている。第三の特色は、死亡率・出生率ともに低下し、自然増加ではあるが、その増加率は第一次団塊の世代といわれる1947年(昭和22)の16.6%から2000年には1.0%と10分の1以下に減少している。なお県下77市町村のうち、2000年頃まで人口増加が続いていたのは高速道路インターチェンジ周辺である。1958年西筑摩郡神坂村(みさかむら)、2005年木曽郡山口村がそれぞれ岐阜県中津川市に越県編入されている。
2020年10月現在、19市14郡23町35村からなる。
[小林寛義]
自然
地形
日本の中央部を南北に横切る大地溝帯フォッサマグナの西縁は、糸魚川‐静岡構造線(いといがわしずおかこうぞうせん)によって明瞭(めいりょう)にくぎられ、この大断層線を境にして県の西側と東側では、地形的にも地質的にもかなり異なっている。西側には日本の屋根と称される飛騨山脈(ひださんみゃく)(北アルプス)、木曽山脈(中央アルプス)、赤石山脈(あかいしさんみゃく)(南アルプス)が雁行(がんこう)して南北に走る。3000メートル級の山々が連なり、頂上近くに氷食地形をもつ山々もみられ、日本アルプスの呼称にふさわしい。東側には標高2000~2500メートルの三国山脈(みくにさんみゃく)、関東山地があって関東地方との境界をなしている。これらの山地・山脈から流れ出る千曲川、天竜川、木曽川などの流域に形成された6盆地が県民生活の中心地をなしている。また県域には浅間山、飯縄(いいづな)山、焼(やけ)岳、乗鞍岳、御嶽(おんたけ)山、八ヶ岳などの火山も多い。これらの火山の裾野(すその)は広大な高原をなし、近年観光地や農業地に開発されている。県内の盆地と木曽谷は山地や山脈で分離されていることもあって、相互の連絡に障害があり、これが県の統一性を妨げている。
県域の大部分が山地のため、九つの国立・国定公園のすべてが山岳地や山地に指定されている。中部山岳、上信越高原、妙高戸隠連山、南アルプス、秩父多摩甲斐(ちちぶたまかい)の5国立公園、妙義荒船(みょうぎあらふね)佐久高原、八ヶ岳中信高原、天竜奥三河、中央アルプスの4国定公園、国営アルプスあづみの公園のほか、県立自然公園に、御岳、三峰川(みぶがわ)水系、塩嶺王城(えんれいおうじょう)、聖山(ひじりやま)高原、天竜小渋(こしぶ)水系の5公園がある。
[小林寛義]
気候
南北に長い地形なので、太平洋気候、日本海式気候の両方の気候が現れる。県北部は冬季降雪量が多く北陸地方の気候に近く、上田、松本、佐久、諏訪の各盆地は夏と冬、日中と夜間の気温の差が大きく、降水量は少ない内陸型をなし、南部の木曽谷や伊那盆地は比較的温暖で夏季に降水が多く、冬季は晴天の太平洋型である。標高800~1500メートルの地帯は高冷地気候で、これより高くなると寒冷気候に移り、植物も亜高山性や高山性の樹種にかわる。これらの多様な気候はそれぞれの地方の生活様式にも密接な関係を及ぼしている。
[小林寛義]
歴史
原始・古代
信濃(しなの)の歴史は火山の裾野の高原から始まった。1952年(昭和27)諏訪市の茶臼山遺跡(ちゃうすやまいせき)から黒曜石の石刃や石鏃(せきぞく)が発見されて以来、八ヶ岳・蓼科(たてしな)火山裾野では旧石器時代文化の遺跡が次々に発見された。原始時代の居住は狩猟に便利な高原から始まったことがわかる。縄文時代もこれらの高原のほか菅平(すがだいら)高原などにも居住範囲が広がり、さらに、天竜川沿岸や諏訪湖岸など漁労に好都合な地域も居住地になった。縄文遺跡は県下全体で4000余りに及び、なかでも八ヶ岳山麓の標高1000メートル地帯にある竪穴(たてあな)住居群の尖石遺跡(とがりいしいせき)(国の特別史跡、茅野(ちの)市)や、160戸の竪穴住居跡をもつ井戸尻遺跡(いどじりいせき)(国の史跡、諏訪郡富士見(ふじみ)町)、平出遺跡(ひらいでいせき)(国の史跡、塩尻(しおじり)市)などは縄文期の代表的遺跡である。
弥生(やよい)期になると、生活の場所は高原からしだいに盆地へと下るが、これは狩猟から稲作へと生活様式が変わったためである。弥生遺跡は約1300で、縄文遺跡よりかなり少ないが、これは居住地が稲作の可能な地域に限定されてきたためと推定されている。古墳時代に入ると信濃の生活舞台は明らかに盆地に移る。千曲川東岸の森将軍塚古墳(千曲(ちくま)市)は対岸の川柳将軍塚古墳(せんりゅうしょうぐんづかこふん)(長野市)とともに、県最大・最古の前方後円墳であり、松本市の弘法山古墳(こうぼうやまこふん)とともに国の史跡に指定されている。長野、上田、伊那の各盆地を中心に県全体では約3000の古墳が確認されている。同時に鉄製農具など稲作に必要な道具も発見されているが、木曽谷のような稲作に不適当な地方には現在までに古墳は発見されていない。
大化改新(645)後、信濃国が成立したが、古代信濃の開発は、善光寺の存在や信濃国府の場所から考えて、長野、上田の両盆地から始まったものと思われる。善光寺は白鳳(はくほう)期に大陸からの渡来者たちによって建立されたとみられ、国府も当初は上田市郊外にあった。『和名抄(わみょうしょう)』(934ころ)に記されている信濃67郷のうち、半数以上が長野、上田地方にあり、『延喜式(えんぎしき)』所載の式内社も48座中36座がこの地方に集中している。なお諏訪地方の開発も早く、8世紀の一時期諏訪国が設置されていた。諏訪大社は大化改新前の草創と推定される。
平安時代に入ると、官道である東山道(とうさんどう)は伊那谷を北上し、国府所在地の現松本市を経て上田を通り、碓氷(うすい)峠を越えて前橋(群馬県)へ向かった。東山道の支道は松本で分かれ、北進して直江津(なおえつ)(新潟県)へ向かった。この官道によって、伊那谷南部は京都方面の影響を強く受けた。信濃は牧馬の重要な産地でもあり、火山山麓には官牧が設けられ、全国32か所のうち16か所が信濃に置かれた。
[小林寛義]
中世
平安末期から信濃でも中央貴族の荘園(しょうえん)化が進み、その数は60か所に及んだ。国内各地に豪族が発生したが、なかでも木曽谷を根拠地とする木曽義仲(よしなか)(源義仲)はその代表的存在であった。義仲は1180年(治承4)木曽で挙兵するが、1184年(元暦1)源頼朝(よりとも)に討たれた。鎌倉幕府成立後、信濃の豪族はその支配下に入った。信濃守護職には比企(ひき)氏、のち北条氏が任ぜられた。鎌倉幕府滅亡後、諏訪氏らが北条氏を擁して中先代の乱(なかせんだいのらん)を起こし、鎌倉を攻めたが失敗に終わった。建武(けんむ)新政で信濃守護には小笠原氏(おがさわらうじ)がなり、守護所は現長野市に置かれた。
南北朝時代には、信濃の豪族は北朝、南朝に分裂して争ったが、北朝の足利(あしかが)氏に味方した小笠原氏が勢力を得、諏訪氏や安曇(あずみ)の豪族は一時衰えた。戦国時代に入ると、甲斐(かい)の武田氏の進攻で長野盆地以北を除きほとんど武田の支配下に入り、長野盆地の支配をめぐって、武田、上杉が抗争を続けた。その後、織田信長が信濃を攻略し、1582年(天正10)信長が本能寺の変で倒れると、信濃は上杉、徳川、北条3氏の抗争の場となり、さらに関ヶ原の戦い後は徳川氏の支配を受けた。
[小林寛義]
近世
徳川政権確立後、信濃には小藩が分立した。1624年(寛永1)には真田(さなだ)氏松代藩(まつしろはん)10万5000石を最高に、飯山(いいやま)、長沼、須坂(すざか)、松本、上田、小諸(こもろ)、高島、高遠(たかとお)、飯田の諸藩があったが、その後、藩主の改易や交代、石高(こくだか)の変化などさまざまな推移があった。また、木曽谷をはじめ信濃国以外の藩の所領や幕府の直轄地が至る所にあり、それらが複雑に入り組んで、これが明治以後の県内の統一を妨げる原因にもなった。
一方、産業面はこの時期に大いに進んだ。その一つは用水路の開削で、各盆地の稲作が目覚ましく発展した。ことに浅間、蓼科、八ヶ岳火山山麓や松本、長野盆地などの扇状地、伊那谷の河岸段丘など水不足に悩んだ所の開発が進んだ。1598年(慶長3)の豊臣秀吉の検地のおり、信濃の石高は40万8000石であったが、1832年(天保3)には76万7000石に増えた。近世中期からは養蚕業が各地に普及し、また手工業もおこった。飯田の元結(もとゆい)(現在は水引)と傘、諏訪の鋸(のこぎり)と寒天、木曽の漆器と櫛(くし)、松本の家具と菓子、上田の紬(つむぎ)と蚕種、長野盆地の和紙や鎌など、現在まで存続しているものはいずれも近世に始まったものである。
信濃には五街道のうち、中山道(なかせんどう)と甲州街道が通過し、沿道には宿駅が整備された。これ以外に、隣接諸国からの物資搬入の役目を果たした野麦(のむぎ)、糸魚川(いといがわ)、三州(さんしゅう)、武州などの各街道があった。
[小林寛義]
近・現代
1869年(明治2)伊那谷の天領を対象にして伊那県が設置された。翌年伊那県の一部が中野県となり、1871年長野県と改称した。一方、同年の廃藩置県で、飯山、須坂、松代、上田、小諸、岩村田、松本、高島、高遠、飯田の10県が成立。信濃国外に本領のある椎谷(しいや)、尾張(おわり)の2県とあわせて14県が存在した。同年11月に長野に県庁を置く長野県と、松本に県庁を置く筑摩県(ちくまけん)の2県に統合された。筑摩県には飛騨国の一部も含まれていた。現在の長野県域が成立したのは1876年で、県庁は長野に置かれ、同時に飛騨は岐阜県域になった。
行政上の近代化とともに産業、交通、教育などの分野も大きな変化を遂げた。産業上では、近世末から普及した養蚕業が発展を続け、明治中期には全国一の養蚕県となった。県下各地に製糸工業がおこり、諏訪地方はその中心であった。また現在全国第2位の生産量をあげているリンゴも明治10年代に栽培が始まった。しかし昭和初年の経済不況は長野の製糸工業や養蚕業に大きな打撃を与えた。第二次世界大戦後は桑畑にかわって、リンゴ、ナシなどの果樹や野菜作が畑作の主流を占め、工業も内陸型の機械工業にかわった。
近代は、信州教育の確立した時期でもある。これは、明治前半における県政の努力と、幕末以来の県民の教育への関心の高さのためで、当時、義務教育の就学率は全国一を誇った。
1888年直江津線(現、JR信越本線およびしなの鉄道)の長野―軽井沢間が開通し、明治末までに中央東線・西線が全通した。また大正から昭和10年代にかけて、飯田、大糸、小海(こうみ)、飯山の各線が開業し、この結果、旧街道による交通は衰退し、宿場集落は大きな打撃を受けた。
第二次世界大戦時、長野県は山がちであり、空襲の対象となる大工場もないため、戦災はほとんど被らなかったが、国および県の満州移民政策により、大戦後1万5000人の命が大陸で失われた。移民は満州事変直後から始まり、県の満州分村計画などもあって農民を中心に約2万5000人が渡満し、「満州移民送出日本一の県」といわれた。
[小林寛義]
産業
農林業
1995年(平成7)2月現在、県下の農家総数は14万9000戸余りで、このうち専業農家は14%にすぎない。農業従事者も1995年現在で、65歳以上の高齢者が全就農者の50%に達し、耕地面積は、都市化による宅地化や工場団地造成、交通網の整備などのため、1990年から1995年の5年間に約1万ヘクタール減少し、総じて農業は不振である。
耕地は県面積の10%にすぎず、この大部分は県下の6盆地に集中し、地形的には扇状地、火山山麓(さんろく)、河岸段丘などで営農条件としてはあまりよくない。農家の平均耕作面積は約60アールで全国平均を下回る。
耕地は水田と畑がそれぞれ50%で、畑は野菜など普通畑が約5万6800ヘクタール(1995)、果樹など樹園地が2万0800ヘクタール、牧草地が4600ヘクタールを占める。
農産物を販売する農家数からみた県農業の中心は稲作4万2000戸、野菜7500戸、果樹1万7300戸、花卉(かき)2200戸、酪農と肉用業は2800戸(以上1995)で、これらの部門が長野県農業の中核をなしている。
水稲の生産力は高く、県単位では全国でつねにベスト5に入っている。水田も畑も耕作方法は近年かなり変わり、稲作では耕うん、田植、収穫はほとんど機械で行っている。またビニルでの保温育苗が発達し田植期は従来より1か月も早く、5月中旬が全盛期で、このため収穫量も増大しているが、山間地では機械も効率的な利用ができないし、過疎化で労働力も不足しているので耕作地の放棄が目だっている。全体的に一筆(土地登記簿上の一区画)当りの水田面積が小規模なので所要労働量が多いのも信州の米づくりの特徴になっている。
一方、畑作農業は、信州の冷涼な気候を生かした高冷地での野菜栽培に特色がある。標高800~1000メートルの軽井沢高原では大正期から高原野菜を東京方面へ出荷していたが、自動車交通の発達に伴って、いまでは県内各地の高原野菜が、京浜、阪神などの大都市圏へ盛んに出荷されている。野辺山(のべやま)や浅間山麓のレタス、キャベツ、ハクサイ、八ヶ岳山麓蓼科(たてしな)高原のセロリ、パセリ、菅平(すがだいら)の短根ニンジンは代表的な高冷地野菜である。
果樹栽培はリンゴをはじめ、ナシ、ブドウ、モモなど多様であり、昭和初年までの桑園から転換した所が多い。リンゴは青森県に次ぎ全国第2位の生産量を上げ、長野盆地を中心に佐久、松本、伊那の各盆地に広がっている。1980年(昭和55)ごろからは品質の向上に重点が置かれ、ふじ、津軽(つがる)などの品種が中心である。ナシは伊那盆地の段丘上で栽培され、1990年(平成2)に品種登録された南水(なんすい)の評価は高い。巨峰ブドウは長野盆地の中野市を中心に全国一の生産量を上げ、1970年以降は初冬から加温栽培を始め、4月下旬には出荷する促成栽培も進められている。このほか松本盆地南部、桔梗ヶ原(ききょうがはら)、佐久盆地のブドウなどもあり、ここではワイン生産も行われている。昭和初期は耕地面積の約半分が桑畑で占められ、養蚕農家13万6180戸、収繭(しゅうけん)量4万8833.5トン(1930)で全国一であった。近年は養蚕農家540戸、収繭量170.5トン(1996)と最盛時の0.3%に激減しているものの全国では上位にある。
火山山麓の裾野は第二次世界大戦後、乳牛放牧地になった。乳牛飼育頭数は3万7102頭(1995)で、中部地方では愛知県に次ぐ。八ヶ岳周辺や長野市北方の飯縄高原などは集約酪農地に指定されている。また肉牛飼育は4万1924頭(1995)で、中部地方では第2位である。
林業は、森林が多いにもかかわらず振るわない。林野面積は102万7874ヘクタールで、北海道、岩手県に次ぎ、そのうち国有林が3分の1を占める。国有林のなかでも木曽のヒノキは日本三大美林の一つに数えられるが、近年は資源の枯渇を防ぐため年伐採量は3万5000立方メートル程度に抑えられている。おもな林産物にはクリ、キノコ、シイタケ、ワサビがあり、ワサビ、エノキダケ栽培は全国一である。
[小林寛義]
工業
信州の近代工業は明治初年の器械製糸工業で始まった。1872年(明治5)諏訪に深山田(みやまだ)製糸場が設立され、翌年には高井郡に雁田(かりた)製糸場などがつくられ、全国有数の製糸工業県となった。明治末期には製糸業者たちが工場の動力化を図って発電所を建設し、電力を利用してカーバイドなどの化学工業の立地をみたが、全体としては製糸工業の比重が大きかった。昭和初年の養蚕の不況は長野県の製糸工業に大打撃を与え、休業、倒産する業者が多かった。第二次世界大戦中に京浜、中京方面から疎開してきた工場を受け入れたことが、現在の長野県の機械工業発展のきっかけとなった。1995年(平成7)製造業事業所数の割合からみた本県の工業の特色は、電機16.5%、産業機械15.0%、金属9.7%、食料9.7%など機械工業と食料品工業が中心である。出荷額等からみると電機のウェイトはいっそう高く、全工業製品出荷額等の42.6%を占めている。このように全般的に機械工業が盛んなのは、工場敷地が少ないことと、交通輸送の関係からで、内陸傾斜地における宿命であろう。以前全国有数の精密工業地区となっていた諏訪地区は工場拡張・新設用の土地取得難から、既存の工場も漸次地区外へ移動し、精密工業の出荷額等は県全体の5.4%で電機とは大きな差を示している。
県の工業のもう一つの特色は、工場規模がきわめて零細であることで、従業員9人以下の工場が実に全体の71.7%(1995)を占め、300人以上の工場は0.6%にすぎない。
最近道路網が整備されるに伴い、新設工場は高速道路のインターチェンジ付近に集中する傾向があり、松本、長野、佐久、伊那北部などへの立地が多い。
信州の風土に適した工業に、木工木材と食料品工業がある。地元のヒノキ、トチ、ブナ材などを利用した家具製造、アスパラガス、トマトなどの缶詰工業、ワイン製造、酪製品などいずれも県内産原料によるものである。
[小林寛義]
開発
昭和30年代から菅平、蓼科、斑尾(まだらお)、黒姫、飯縄の各火山山麓の高原は別荘地に開発され、志賀(しが)高原、白馬(しろうま)山麓などではスキー場の開発が進み、1997年現在県下には110か所ある。また、ゴルフ場は64か所(1997)あり、首都圏に近いため利用者が多い。高原観光地へ通じる志賀草津道路、霧ヶ峰ビーナスラインなどの道路も敷設された。昭和50年代に入ると、多目的ダムの建設や都市再開発が活発になった。高瀬川上流の新高瀬川発電所は最大出力128万キロワットの地下発電所であり、奈良井川上流には奈良井ダムが完成した。戦災を受けなかった都市の再開発が1980年代から盛んになった。松本駅前、長野電鉄の一部地下化などが図られ、佐久市中込(なかごみ)駅前などは地方都市再開発の典型である。新幹線の玄関口になる長野駅周辺では大規模な開発がなされ、新設駅となった佐久平駅前も近代的な駅前商店街が造成されている。
[小林寛義]
交通
おもな鉄道はJR北陸新幹線とJR中央本線で、前者は東京から上田、長野を経て日本海側方面へ、後者は東京から諏訪・塩尻を経て名古屋へ通ずる。このほか、小海(こうみ)、飯山、飯田、大糸、篠ノ井のJR各線がある。新幹線の敷設により、長野―東京間の所要時間は約90分になり大幅に短縮された。中央自動車道西宮線(にしのみやせん)が県内を全通したのは1981年3月で、東京から岡谷市を経て小牧市(愛知県)へ至る。1991年(平成3)長野冬季オリンピック開催が決定されてから、従来「陸の孤島」とまで酷評されてきた県都長野市を中心に高速交通機関をはじめ、オリンピック競技会場までのアクセス道路の新設改良が急速に進んだ。高速道路では、名古屋―岡谷―東京までの中央道のほかに、岡谷―松本―長野の長野道が1993年に、群馬県藤岡―佐久―更埴(こうしょく)―長野―信州中野―新潟県上越までの上信越道が1999年に開通し、このほか長野―白馬村、長野―志賀高原、大町―白馬村のアクセス道なども新設改良され県北部の道路事情はきわめてよくなった。一方、1997年10月からは、フル規格の北陸新幹線の長野駅まで開業により、県内には軽井沢、佐久平、上田、長野の4駅が設置された。これに伴い、信越線の篠ノ井駅―軽井沢駅の区間はJRから分離され、第三セクター方式の「しなの鉄道」になり、長く親しまれてきた軽井沢駅―横川駅間の碓氷(うすい)峠の区間は鉄道が廃止され、バスが代行することとなった。2015年3月には北陸新幹線が金沢まで延伸し県内にはさらに飯山に新幹線の駅が置かれた。その一方で長野以北の県内の信越本線は第三セクターのしなの鉄道に移管され北しなの線となった。空港は松本市に信州まつもと空港があるが、新千歳、福岡の2空港間に定期便が就航するだけである。県域が山がちであり、交通整備が後れていたが、冬季オリンピック開催のため国道や主要地方道の改善が進んだ。しかし積雪・凍結をみる冬季の道路事情は悪い。自家用車の保有率は貨物自動車も含めて1世帯当り2.2台(1995)で、全国平均の1.8台より多い。これは山間僻地(へきち)が多いため、公的交通機関ではカバーしきれないからである。
[小林寛義]
長野オリンピック
1998年(平成10)2月7日より22日の16日間、第18回「冬季オリンピック競技大会」が長野市、白馬村、山ノ内町、軽井沢町、野沢温泉村の5市町村で開催された。日本では1972年(昭和47)の札幌大会以来、二度目の冬季オリンピック開催である。
今回の冬季五輪大会の第一の理念は、「自然に優しく、自然との共生」である。元来長野県は自然美を売物にしてきた。しかし冬季五輪の主競技の一つであるスキーは大規模な屋外施設が必要になるため、五輪計画当初から自然の保護と競技施設の建設をどのように両立させるかが大きな課題になり、動植物の保護のため当初の競技予定地は二転三転した。そしてこの課題を象徴したのが、白馬村八方尾根のアルペン滑降地点をめぐって、国立公園地域を避けるかどうかで国際委員会と長野委員会が対立し、開催日1か月ぐらい前まで決定できなかったことである。
第二の理念は「愛と参加」であった。愛には平和という意味をもたせた。元来オリンピックは平和のスポーツといわれてきたが、長野五輪ではこれを具体化するため、五輪開催中は世界で武力を使わないよう国連総会で訴えて採択された。同時にノーベル平和賞受賞者で対人地雷禁止国際キャンペーン代表であり、自らもベトナムの地雷撤去作業中に片方の足を失ったイギリス人を聖火ランナーに起用し、大きな感動を呼び起こした。そしてすべての人が参加する意味で、性別、年齢別、職業、身体状況を問わず多くの人々が聖火ランナーとなり、長野市内の小学校が一校一国運動としてそれぞれの国旗で応援し、各国選手との交流を深めた。
第三には、大会の理念ではなく、性質ともいうべきだが、国の主導性は少なく、もっぱら県と長野市など自治体主導色が濃かった。26年前の札幌大会のときは、施設建設費の約80%、運営費の25%を国が補助したが、長野の場合は建設費に50%、運営費は0であった。県と長野市はこのオリンピック招致段階で知名度のアップと、これを機とする高速道路や新幹線の建設を意図した。
長野冬季オリンピックが長野県にもたらしたものの第一は経済的影響である。この内容はメリットの部分とデメリットの部分があり、地域的にまた業種によって明暗が分かれた。メリットの部分としては、交通基盤が飛躍的に整備されたことである。長野冬季オリンピック開催が1991年に第97次IOC(国際オリンピック委員会)総会で決定されるまでは、全国の県都のなかでも長野市は数少ない、高速道路がない都市であった。ところが開催決定後、1992年から1997年までの5年間で、長野道と上信越道の県内部分が全通し、首都圏、中京のいずれへも通じることになった。さらに1997年10月からは新幹線が東京―長野間に開業し、従来上野―長野間が最短3時間要したものがこの半分の所要時間に短縮され、鉄道交通も面目が一新された。東京への時間短縮の効果は今後も計り知れないものがあり、オリンピック期間中の乗車人員は信越線特急時代の40%増、期間外でも5%内外の増加を示している。道路も、主会場の長野市を中心に、白馬村、志賀高原方面へのアクセス(連絡)道が全面的に改良された。またホテルなどの新設や民間の建築、市の長野駅周辺の開発などで建設業界が潤った。しかし、五輪期間中は一切工事がなくなり、五輪後の工事も急減した。長野市は五輪のため、今後14年分の工事を先行したといわれ、これからの建設業界の不況が心配された。
またホテル業界は大会開催中こそ満室であったものの、大会終了後は空室が目だち始めた。このような業界にとって五輪大会のメリットは一過性のもののようである。
商店街では人波はあふれたが、買う商品は五輪関連のバッジや「スノーレッツ」(フクロウをモチーフにした大会マスコット)のぬいぐるみといった大会のスポンサーになった会社の品物が大部分で、地元商店街で売上げを伸ばしたのは飲食店・写真関連ぐらいといわれている。つまり既存商店街の活性は見かけ上にすぎないようである。
他方、白馬村、山ノ内町(志賀高原)、野沢温泉村のような代表的スキー場は五輪開催地になり、新聞などにより混雑が予想されたため一般スキーヤーは敬遠し、白馬村のペンション、民宿客は例年の50%減、志賀高原、野沢温泉付近は20~30%減でデメリットが目だった。また広い長野県内では県中・南部には経済的な波及効果はほとんどなく、不公平感を訴える自治体、企業人も多かった。
第二は経済以外の分野への影響で、長野市の知名度の上昇、学校教育のうえで生徒児童の目が海外に向けられ、一般市民もボランティアを中心に国際親善の気風が高まり、県内外を問わず競技の観客に大きな感動を与えたことなどメリットの部分が大きい。また善光寺の知名度もいっそう広まった。総じて経済的には明暗が分かれたが、文化、教育あるいは精神的にはメリットが大きかった。
[小林寛義]
社会・文化
教育文化
18世紀末から幕末にかけ江戸での半季稼ぎが盛んになると、読み書き算盤の能力が農民の間にも必要とされ、庶民の教育機関である寺子屋が各地に育った。その数は約4000といわれている。また各藩の藩校では朱子学を中心に、漢学、国学、心学から、なかには洋学を教えたところもあり、藩の中核となる人材の養成を目ざし、このなかからは明治の近代教育に活躍した人たちも輩出した。
幕末からの気風を受け継いで、明治の新しい学制下でも全国屈指の教育県をなした。1876年度(明治9)の就学率は63.2%で全国一であり、翌年も全国第2位であった。教師は研究、教育に力を注ぎ、帰宅は夕食時を過ぎ、「ちょうちん学校」ともよばれるほどであった。当時としては近代的な洋風木造校舎が山間の村々にも建てられた。現在も松本市の開智学校(かいちがっこう)(1876年造・国宝)や、地元住民が私財を投じて建築した佐久市の旧中込学校(きゅうなかごみがっこう)(1875年造・重要文化財)が残る。
小学校教師の教育への熱意も大きく、全県的組織をつくり、1886年には信濃教育会が創立された。その機関誌『信濃教育』は現在も発行されている。人道主義を掲げて明治末期に創刊された雑誌『白樺(しらかば)』は、信州人、とくに青年や教師に大きな影響を与え、「白樺教育運動」として実践された。このほか山本鼎(かなえ)の自由教育運動、農村の青年たちが農閑期を利用して学ぶという信濃自由大学の設立などがあり、昭和初期の教員赤化事件や第二次世界大戦後いち早く設立された教員組合なども特筆すべきものである。
高等教育機関には、1949年(昭和24)に旧制松本高等学校、上田蚕糸専門学校、長野工業専門学校、長野師範学校などを統合して設立された国立信州大学(8学部)のほか、県立の長野県看護大学、私立の松本歯科大学、長野大学、松本大学、清泉女学院大学、佐久大学、諏訪東京理科大学があり、短期大学に県立長野県短大、県立長野県工科短大、農業大学校のほか、私立の8校がある(2012年現在)。また国立長野工業高等専門学校がある。『信濃毎日新聞』は1873年発行の『長野新報』を前身とする。1890年以降主筆に山路愛山(やまじあいざん)、桐生悠々(きりゅうゆうゆう)、風見章(かざみあきら)、町田梓楼らを迎え、自由・進取の論調で知られた。『長野日報』は1901年諏訪で『諏訪新報』として発刊され、1905年『南信日日新聞』と改称、1942年(昭和17)の新聞統合で解散、1945年に再刊、1992年(平成4)に現在名に改称した。放送機関にはNHKのほか、信越放送(SBC)、テレビ信州(TSB)、長野放送(NBS)、長野朝日放送(ABN)、長野エフエム放送(FMNAGANO)などがある。
文化施設には、信州の風土にかかわる大町山岳博物館、小諸市立郷土博物館、岡谷蚕糸博物館などをはじめ、県下の多くの市町村に歴史、民俗、美術、工芸、考古、文学などに関係する博物館、歴史民俗資料館、美術館などがある。
[小林寛義]
生活文化
県歌に「信濃の国は十州に境つらぬる国にして」とあるように、長野県は越後(えちご)、甲斐(かい)、上野(こうずけ)など10国に囲まれ、歴史時代からこれらの国々との交流が盛んであり、影響を受けてきた。また風土の多様性もあって県内各地にさまざまな生活文化がみられる。長野市近辺や木曽の高原では昭和30年代までアサ栽培が盛んで、内織(うちおり)(自家織)の麻布を自家栽培のアイで染めた着物を用いたが、一般には近世から昭和初期までの庶民の衣料は木綿であった。仕事着は各地の風土にあわせてつくられた。もんぺ、かるさんなど股引(ももひき)状のものを着け、これに半纏(はんてん)を羽織れば、普段着にも労働着にもなった。半纏は、冬は綿を入れ、作業がしやすいように袖(そで)なしにした。山仕事で丸太などを担ぐときには肩の痛みも和らげられた。県北の豪雪地ではもんぺに似た雪袴(ゆきばかま)に、藁沓(わらぐつ)を履き、蓑(みの)と菅笠(すげがさ)を着ける。藁沓に雪踏み用のかんじきをつけることもあった。
食生活も地方色豊かである。木曽や佐久の高冷地は水田が少なく、そばやうどんを常食とした。そば粉でつくった皮の中に甘みそなどを入れ、いろりの熱い灰の中に入れて焼いた焼き餅(もち)(お焼き)は御馳走(ごちそう)の部類で、そば粉も十分でない所では、トチの実の粉を水にさらしてあくを抜き焼き餅をつくった。ほうとうは小麦粉を練って太めに切り、ダイコンや菜とともにみそ汁仕立にしたもので、寒い夜は体が温まると喜ばれた。おにかけはほうとうよりやや細めに切って熱湯でゆで、しょうゆ汁につけて食べる。伊那谷や木曽谷では米の粉を小判形にして竹串(たけぐし)にさし、甘みそやごまみそをつけて焼いた五平餅(ごへいもち)が祭りなどの御馳走になった。野沢菜漬けは塩分が少なく、冬の茶うけには欠かせない食べ物である。伊那谷の悪食(あくじき)は、ハチの子や天竜川でとれるザザムシをあぶって味つけをして食べることをいい、ときにはヘビも食べた。山国で動物性タンパクが不足するのを防ぐ生活の知恵である。また諏訪や佐久などの冬の保存食には、豆腐を凍らせた凍豆腐(しみどうふ)や、餅を外気で乾燥した氷餅などがある。
豪雪地の家屋は、建てのぼせ造りといって、豪雪の重みに耐えうるように2階まで1本の通し柱を用いる。諏訪では霧ヶ峰で産出する板状の安山岩の鉄平(てっぺい)石を屋根瓦(がわら)の代用にしたり、寒さが厳しいので、母屋(おもや)の奥座敷を土蔵造りにした建てぐるみとよぶ様式もみられる。木曽谷のように木材が豊富な所は、板屋根上に石をのせる石置き屋根がみられた。伊那や諏訪の養蚕農家では、雨風を避けて屋外作業をするため軒を長く突き出している。
[小林寛義]
民俗芸能
信州の伝統的行事は年末年始と8月に多い。前者は1年を無事に過ごした喜びと新年への祈願を込めた行事が多く、また8月は春から夏にかけての激しい農作業から解放された人々の憩いの行事が多い。年末の伝統芸能の圧巻は、県の南端赤石山脈の山懐に抱かれた遠山(とおやま)郷に古くから伝わる遠山霜月祭の芸能(とおやましもつきまつりのげいのう)(国指定重要無形民俗文化財)である。江戸時代に相続争いと百姓一揆(いっき)によって滅びた領主遠山家の怨霊(おんりょう)を慰めるもので、熱湯のたぎる湯釜(ゆがま)の周りで夜を徹して湯立神楽(ゆだてかぐら)を舞う。娯楽に乏しい隔絶山村の慰安的要素をももっている。最高潮になると釜の熱湯を素手ではねて人々にかけ、これで穢(けがれ)を払う。遠山郷の近くの伊那谷阿南町(あなんちょう)新野(にいの)の12月から翌年1月にかけての「雪祭の芸能」(選択無形民俗文化財。「雪祭」は重要無形民俗文化財)も広く知られている。雪は豊年のしるしというわけで神前に供え、新年14日夜から伊豆神社の神楽殿でさまざまな舞が奉納される。伊那谷ではこのほか「坂部の冬祭りの芸能」「和合の念仏踊」(以上、選択無形民俗文化財)、「新野の盆踊」(重要無形民俗文化財)など伝統的芸能が多い。諏訪湖では厳冬期に湖の氷が南北方向に割れ目を生じる現象がおこる。「御神渡り(おみわたり)」といい、諏訪大社上社の男神が下社の女神のもとへ通うときに生じるものと伝えられ、神官たちは割れぐあいを見てその年の農作物の豊凶を占う。千曲川上流の川上村では、1月14日に村の子供たちが前の年に嫁入りのあった家を太鼓(たいこ)をたたき、御幣(ごへい)を振りながら回って祝福する「オカタブチ」の行事がある。佐久の山村北相木(きたあいき)村では、子供たちが3月3日の節供に紙細工の雛(ひな)人形を川に流す「カンナバレ」とよぶ素朴な行事がある。人間の罪や穢も同時に流し去るという。夏は県下各地で盆踊りが盛んであるが、その代表は木曽節による盆踊りである。木曽節の起源については諸説があるが、木曽川の筏(いかだ)下しの舟乗りたちの歌ともいわれている。8月15日、佐久市望月(もちづき)の榊祭り(さかきまつり)は青年たちが褌(ふんどし)一つで榊の神輿(みこし)を担ぎ、松明(たいまつ)を手に山から駆け下りてそれを川に投げ込み、神輿で町内を暴れ回る勇壮な祭りである。伊那谷の各地に伝わる「今田(いまだ)人形」「黒田人形」(飯田市)、「早稲田(わせだ)人形」(阿南町)は、江戸時代に盛んであった文楽系統の人形芝居の名残(なごり)で、「伊那の人形芝居」として選択無形民俗文化財である。また「下黒田の舞台」(国指定重要有形民俗文化財)は操り人形専用のもので、人形も多く残されている。松本市立博物館は国指定重要有形民俗文化財の「七夕人形コレクション(たなばたにんぎょうこれくしょん)」「民間信仰資料コレクション」などを展示する。
[小林寛義]
文化遺産
信州を代表する建造物は善光寺である。境内には本堂(国宝)、二層入母屋(いりもや)造の三門(国指定重要文化財)、仏教美術品を多数所蔵する大勧進(だいかんじん)、大本願のほか39院坊が配置されている。本堂は1707年(宝永4)の再建、撞木(しゅもく)屋根造は全国有数の規模である。上田市西方の青木村の大法寺三重塔(国宝)は純和風形式の美しさを示す。正慶(しょうけい)2年(1333)の銘文があり三間四方檜皮葺(ひわだぶ)きで、どっしりとした安定感がある。帰途にかならず振り返って見るほどなので「見返りの塔」ともいわれる。上田市別所温泉の安楽寺(あんらくじ)の八角三重塔(国宝)は純粋な禅宗様で、一層に裳階(もこし)をつけ、八角様式の異色な建物である。松本城の大天守、渡櫓(わたりやぐら)、乾(いぬい)小天守(いずれも国宝)は1592年(文禄1)から1600年(慶長5)のころの建造で、五層の天守は全国最古である。俗に烏城(からすじょう)ともよばれ、全体の構造物が直線的で素朴な美しさを備えている。神社建築では、大町市の仁科神明宮(にしなしんめいぐう)の本殿・前殿が伊勢(いせ)神宮様の建築様式で国宝に指定されている。国の重要文化財に指定されているおもな建築物には次のようなものがある。後醍醐(ごだいご)天皇の皇子宗良(むねなが)親王が拠(よ)った伊那谷大鹿(おおしか)村の福徳寺本堂は、鎌倉期の建立になる入母屋造、杮(こけら)葺きの阿弥陀(あみだ)堂で、静寂な山中に素朴なたたずまいをみせている。このほか、鎌倉時代の建造物に中禅寺薬師堂(上田市)、釈尊寺観音堂宮殿(小諸市)など、室町時代の建造物に筑摩神社(つかまじんじゃ)本殿(松本市)、前山寺(ぜんさんじ)三重塔(上田市)などがある。旧小笠原家書院(きゅうおがさわらけしょいん)(飯田市)は桃山時代の豪族屋敷の代表的建造物で、崖(がけ)上に突き出した懸(かけ)造の書院と唐破風(からはふ)造の玄関など貴重である。竹村家住宅(駒ヶ根(こまがね)市)は伊那谷の代表的豪農建築で、茅(かや)葺き寄棟造で、土間は10頭の馬が飼える広さがある。
おもな仏像彫刻に以下のものがある。上田市長福寺の銅造菩薩(ぼさつ)立像は奈良時代の特徴をもつ信濃最古の仏像といわれる。長野市清水寺(せいすいじ)の聖観音(しょうかんのん)立像も藤原時代の特色をもつ優れた立像である。鎌倉時代のものでは、飯田市光明寺の阿弥陀(あみだ)如来像、松本市牛伏寺(ごふくじ)の十一面観世音立像と脇侍(きょうじ)、善光寺境内の世尊院の銅造釈迦涅槃(しゃかねはん)像などがあり、いずれも国の重要文化財に指定されている。佐久市の福王寺には鎌倉初期の地方作風を示すといわれる阿弥陀如来坐像(国の重要文化財)があり、大町(おおまち)市覚音寺(かくおんじ)の胎内木札をもつ藤尾観音堂仏像群、上田市安楽寺惟仙(いせん)・恵仁和尚(えにんおしょう)坐像(国の重要文化財)、同市常楽寺(じょうらくじ)の「板絵着色三浦屋図」(国の重要美術品)なども信州では著名な作品である。木曽谷の中山道宿場景観は全国的に知られている。南木曽(なぎそ)町妻籠(つまご)は木格子、出し梁(ばり)造の低い二階家の旅籠(はたご)や民家20数戸が復原修理され、塩尻市奈良井(ならい)も宿場景観が保存されて、両地区とも国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。また、北国街道沿いに築かれた宿場町の東御(とうみ)市海野宿(うんのしゅく)、農村景観を伝える山間部集落の白馬村青鬼(あおに)、戸隠神社の参詣道沿いに発達した宿坊群を中心とした門前町の長野市戸隠や、近世末期から近代にかけて、生糸や繊維製品の集散地として繁栄した商家町の千曲市稲荷(いなり)山もそれぞれ重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。
[小林寛義]
伝説
信州は伝説の宝庫といわれる。山国だけに「デイラボー」という巨人伝説が至る所に分布し、池や窪(くぼ)みの地形に結び付いている。姨捨山(おばすてやま)は善光寺平(だいら)の南西にそびえる山で、冠着山(かむりきやま)ともいう。親を山に捨てる「姨捨」の伝説は『大和(やまと)物語』『今昔(こんじゃく)物語』『打聞集(うちぎきしゅう)』などにも記されているが、原話はインド、中国から渡来したものといわれている。千曲(ちくま)市の長楽寺境内にある「姥石(うばいし)」は、山に捨てられた老婆が石に化したものと伝えている。長野市の往生寺(おうじょうじ)にある親子地蔵は、刈萱(かるかや)道心と石童丸父子の物語にちなむ。出家した父の刈萱を慕って石童丸が高野山(こうやさん)に行くが、父はすでに善光寺へ出発し、信州に訪ねると父は往生したあとであった。子は地蔵尊を刻んで父を弔ったというのが親子地蔵の由来である。長野市の戸隠(とがくし)山の南方にある荒倉山には鬼女伝説がある。平維茂(これしげ)が「鬼女紅葉(もみじ)」を討った地で、この伝説から謡曲『紅葉狩』や近松の浄瑠璃(じょうるり)『栬狩剣本地(もみじがりつるぎのほんじ)』が生まれた。梓(あずさ)川の右岸新村(にいむら)(松本市)に「ものぐさ太郎」という希代の無精者が住んでいたが、領主の命令で京に上り、才能をみいだされて信濃の中将に任ぜられた。安曇野市の式内社穂高神社は太郎を祀(まつ)り、新村にはものぐさ太郎がいつも腰をかけていたという「腰かけ桜」がある。諏訪大社の諏訪明神の本地として、中世以後語り継がれたものに「甲賀三郎(こうがさぶろう)」の伝説がある。近江(おうみ)国の地頭(じとう)の子三郎が、行方不明になった妻の春日(かすが)姫を捜して全国を旅した。蓼科山(たてしなやま)の穴底で妻を発見するが、兄次郎のたくらみで三郎だけ地上に出ることができず、ついに蛇体となって妻に巡り会うという。三郎は諏訪上社に、春日姫は下社に祀られたが、末弟の三郎がさまざまな困難に打ち勝って最後に成功するという末子成功譚(たん)でもある。諏訪社の神人たちの語りを経て、御伽草子(おとぎぞうし)の『諏訪の本地』として諸国に流布された。伊那谷の駒ヶ根市光前寺(こうぜんじ)に早太郎犬の塚がある。遠江(とおとうみ)の府中(静岡県磐田(いわた)市)の天満宮に大狒々(おおひひ)が住み着き、田畑を荒らし子供をさらったりした。この大狒々を早太郎が退治したが、早太郎も重傷を負って寺に戻ると息を引き取った。塚は早太郎を弔ったもので、この伝説が縁となって駒ヶ根市と磐田市は姉妹都市となっている。
[武田静澄]
『『信濃史料』全32巻(1952~1972・信濃史料刊行会)』▽『浅川欽一・大川悦生著『信州の伝説』(1970・第一法規出版)』▽『『長野県史』全38巻70冊(1971~1992・長野県)』▽『荒井勉著『信州の教育』(1972・合同出版)』▽『塚田正朋著『長野県の歴史』(1974・山川出版社)』▽『向山雅重著『日本の民俗 長野』(1975・第一法規出版)』▽『小林寛義・市川建夫著『ふるさと地理誌』(1977・信濃毎日新聞社)』▽『『長野県の地名』(1979・平凡社)』▽『『長野県百科事典』補訂版(1981・信濃毎日新聞社)』

長野県県章

八ヶ岳

焼岳

乗鞍岳

御嶽山

菅平高原

志賀高原

霧ヶ峰

諏訪湖

旧開智学校校舎

旧松本高等学校本館

遠山祭(遠山の霜月祭)

雪祭(新野の雪まつり)

御神渡り

大法寺三重塔

安楽寺八角三重塔

松本城

中禅寺薬師堂

釈尊寺観音堂

前山寺三重塔

南木曽町妻籠宿

奈良井宿

東御市海野宿

青鬼の山村集落

穂高神社

木曽の櫛

上田紬

お焼き

蜂の子料理

長野県位置図
長野(市)
ながの
長野県北部、長野盆地に位置する市。県庁所在地。1897年(明治30)市制施行。1923年(大正12)吉田町と三輪(みわ)、芹田(せりた)、古牧(こまき)の3村、1954年(昭和29)古里(ふるさと)、柳原(やなぎはら)、浅川、大豆島(まめじま)、朝陽(あさひ)、若槻(わかつき)、長沼、安茂里(あもり)、小田切(おだぎり)、芋井(いもい)の10村を編入、1966年篠ノ井(しののい)市と川中島、若穂(わかほ)、松代(まつしろ)の3町、七二会(なにあい)、更北(こうほく)、信更(しんこう)の3村と合併。2005年(平成17)豊野町(とよのまち)、戸隠村(とがくしむら)、鬼無里村(きなさむら)、大岡村(おおおかむら)と合併。2010年(平成22)信州新町(しんしゅうしんまち)、中条村(なかじょうむら)を編入。面積834.81平方キロメートル、人口37万2760(2020)。
市域は、北部を新潟県と接し、善光寺平(ぜんこうじだいら)ともよばれる長野盆地の大部分を占める。東部を千曲川(ちくまがわ)が北東流し、更北地区で西方から東流してきた犀川(さいがわ)と合流する。北部や西部は山地や丘陵地が占める。長野市街は南北方向には犀川の支流裾花(すそばな)川の扇状地上を中心に、盆地南端部の篠ノ井まで市街化し、また東西方向には、千曲川左岸一帯は連続して市街化し、おもな街道に沿って各種大型店が進出した。交通は、1998年(平成10)開催の冬季オリンピックおよびパラリンピックの開催地となった影響もあって、北陸新幹線が1997年10月に長野駅まで開通(通称長野新幹線)したのをはじめ、高速自動車道の長野自動車道(岡谷―更埴(こうしょく)間)と上信越自動車道(群馬県藤岡―新潟県上越間)も開通した。新幹線の開通で、従来の信越本線のうち、軽井沢―長野市篠ノ井間は第三セクターの経営になって、しなの鉄道と呼称がかわった。新幹線はその後2015年に金沢まで延伸し、長野―妙高高原間もしなの鉄道に移管された。このほか、オリンピックの競技場になった山ノ内町の志賀高原や、白馬(しろうま)岳山麓(さんろく)の白馬(はくば)村へのアクセス道は新設や改良で大幅に改善され、市は新幹線、高速道路、JR信越・篠ノ井線・飯山線の各線や、しなの鉄道、長野電鉄、さらには国道18号、19号、117号、403号、406号などの交通路の一大中心地になった。
[小林寛義]
歴史
千曲川右岸には古墳の分布が多い。長野市のシンボルともいうべき善光寺は、1953年(昭和28)に発掘された瓦(かわら)から白鳳(はくほう)時代に創建されたものと推定される。戦国時代、長野市全域は甲斐(かい)の武田氏に攻略され、徳川政権確立後の1622年(元和8)松代を中心とする地は真田(さなだ)氏松代藩の所領となったが、そのほかは幕府領、旗本領など多様であった。善光寺門前の大門町(だいもんちょう)は近世に入って北国(ほっこく)街道の宿場として発展し、明治になると土産(みやげ)物屋が常設され門前町を形成した。1871年(明治4)には千曲川流域一帯を県域とする長野県の県都に、1876年には現在の長野県全域の県都になり、県の中枢機関だけでなく、中央官庁の出先機関、新聞社、学校、銀行などが集中するようになった。1999年(平成11)には中核都市の指定を受けた。また、冬季オリンピックの開催地になったため、国際的な知名度も向上した。戸隠地区は、戸隠神社を中心として典型的な宗教集落が形成され、宿坊、飲食店、土産物店が並ぶ。鬼無里という地名は、平維茂(たいらのこれもち)が鬼女を退治した「紅葉狩(もみじがり)」の伝説にちなむ。戸隠と鬼無里の間にある荒倉山には鬼女の紅葉(もみじ)が棲んだといわれる岩屋があり、一帯は謡曲『紅葉狩』の舞台とされる。新町地区では近世後期から明治にかけて松本まで犀川の通船があった。また同地区は明治、大正時代には養蚕と麻の取引で栄えた。
[小林寛義]
市街
市街は第二次世界大戦の被害をほとんど受けなかったため、街路は改良が進まなかったが、オリンピックの開催を機に市街地の道路整備が進み、これに伴って新しい商店街が旧中心部の北・東・南の3方面に形成された。近世宿場町当時からの市街地中心部であった善光寺門前町と長野駅を結ぶ中央通りは商況が停滞し、市はこの活性化に努めている。JR長野駅は善光寺を模してつくられた旧駅舎を、新幹線開通とともに橋上駅に改築した。同時に駅前も整備され、これまで市の玄関口となっていた善光寺口(西口)のほか、新しく発展している市街東方への東口を改良・整備した。東口側からは、県民文化会館、NHK放送局、県立図書館をはじめ大型スーパー店、信州大学工学部、保健所などへのアクセスがよい。駅周辺にはホテルが集中し、オリンピック以前の景観は一変した。
[小林寛義]
産業
県全体の比率からみると長野市の農業人口は少ないが、周辺部の信更地区、更北地区、新町地区を中心に米作、リンゴ、モモ、ブドウなどの果樹栽培、高原野菜やタマネギ栽培、中条地区ではクワ、芋井、信里、戸隠、鬼無里(きなさ)などではタバコなどの工芸作物の栽培や畜産が行われる。長野市街北方の往生地(おうじょうじ)は信州リンゴの発祥地の一つであり、長野市は県下のリンゴ栽培の中心地になっている。長芋、キノコ、ソバは特産。山間部では森林の育成・保存を推進している。また、善光寺や妙高戸隠連山国立公園をはじめ、観光資源に恵まれ、観光開発にも力を入れている。工業は、明治以来県都のため各種印刷物などの発注もあって印刷工業が発達し、技術水準が高かった。市の発展は、善光寺や県庁に依存してきた傾向があり、工業より商業の中心地であった。1997年現在、商品販売額は県全体の30%、商店数は18%を占める。工業も、昭和40年代から三菱(みつびし)電機、富士通、新光電気などの工場が立地し、テレビ組立て、半導体、コンピュータ、セラミックなどの電気機器工業が盛んになり、県下第一の工業地を形成するようになった。製造品出荷額は県総額の12%を占め、年間7700億円を超える(1996)。とくに目だつ工業は電機で、ついで食品、出版・印刷などである。
[小林寛義]
文化・観光
善光寺の境内には国宝の本堂をはじめ大本願、大勧進(だいかんじん)のほか山内の36の宿坊が並び、全国の善男善女の参拝が絶えず、年間700~800万人に達する。東隣の城山(じょうやま)公園には県立美術館・東山魁夷(ひがしやまかいい)館などがある。真田氏の城下町松代には、松代城跡、松代藩藩校の旧文武学校(ともに国指定史跡)、藩主真田信之霊屋(のぶゆきたまや)、旧横田家住宅(ともに国指定重要文化財)などがあり、象山(ぞうざん)記念館は佐久間象山(しょうざん)の遺品などを展示する。若穂地区の清水寺(せいすいじ)は国指定重要文化財の聖観音(しょうかんのん)立像、千手観音像などを蔵する。鬼無里地区の白髯神社本殿(しらひげじんじゃほんでん)は国指定重要文化財。また篠ノ井の川柳将軍塚古墳(せんりゅうしょうぐんづかこふん)・姫塚古墳は国の史跡に、泉平(いずみたいら)の素桜神社の神代ザクラ(そざくらじんじゃのじんだいざくら)は国の天然記念物に指定されている。
千曲川と犀川の合流点は、「川中島の戦い」が行われた川中島古戦場として名高い。北部の戸隠地区には円錐(えんすい)火山の飯縄山(いいづなやま)がそびえる。南麓(なんろく)の飯綱(いいづな)高原には大小の湖沼が点在し、別荘地、ゴルフ場などに開発されている。戸隠山(1904メートル)は、戸隠連峰の主峰で、山岳信仰に発した神仏混交の霊場であり、平安時代から山伏の修験場(しゅげんじょう)として知られた。また、戸隠高原には高原植物が豊富で、戸隠森林植物園がある。裾花川の源流近くには、ブナの原生林やミズバショウの群生地があり、奥裾花自然園となっており、紅葉もよい。これらの山岳地や高原一帯は妙高戸隠連山国立公園に含まれる。ほかに聖(ひじり)高原、北野美術館、真田宝物館、戸隠そば博物館、スキー場、キャンプ場、牧場などがある。犀川沿いの新町には水内(みのち)ダムに堰き止められた琅鶴(ろうかく)湖、県歌「信濃の国」にも歌われている久米路(くめじ)橋などの景勝地がある。
[小林寛義]
『小林計一郎著『わが町の歴史――長野』(1979・文一総合出版)』▽『『長野市誌』全16巻(1997~2005・長野市)』
長野
ながの
秋田県中東部、大仙市(だいせんし)の一地区。旧長野町は1955年(昭和30)に周辺3村と合併して中仙町となり、中仙町は2005年(平成17)大曲(おおまがり)市などと合併して大仙市となった。雄物(おもの)川水系の玉川東岸に位置する。江戸時代はこの地まで通船可能で、雄物川舟運の陸揚げ場として栄えた。JR田沢湖線羽後長野駅があり、国道105号が通じる。サクラの名所の八乙女公園がある。「東長野・長野ささら」は県指定無形民俗文化財。
[編集部]
改訂新版 世界大百科事典 「長野」の意味・わかりやすい解説
長野[県] (ながの)
基本情報
面積=1万3562.23km2(全国4位)
人口(2010)=215万2449人(全国16位)
人口密度(2010)=158.7人/km2(全国38位)
市町村(2011.10)=19市23町35村
県庁所在地=長野市(人口=38万1511人)
県花=リンドウ
県木=シラカバ
県鳥=ライチョウ
中部地方の中央東部に位置し,群馬,埼玉,山梨,静岡,愛知,岐阜,富山,新潟の8県に囲まれた内陸県。
沿革
県域はかつての信濃国全域にあたる。江戸末期には松本藩,飯田藩,高遠(たかとお)藩,高島藩(諏訪藩),田野口藩(後に竜岡藩と改称),松代藩,須坂藩,飯山藩,岩村田藩,小諸藩,上田藩の諸藩が分立しており,木曾は尾張藩領で,そのほかにも天領,旗本領,寺社領などが入り組んでいた。1868年(明治1)伊那県が置かれて,尾張藩の所管となっていた旧天領,旗本領などを支配下に置き,翌年三河県を併合(1871年額田県に編入),70年には一部を割いて中野県を設けた。71年廃藩置県によって各藩は県となり(竜岡藩は直前に廃藩して伊那・中野両県へ分属),同年伊那,松本,飯田,高遠,高島の5県と高山県(飛驒)は筑摩県に,長野(中野県を改称),松代,須坂,飯山,岩村田,小諸,上田の7県は長野県に統合された。76年筑摩県の廃県に伴い信濃国分を長野県に編入,現在の県域がほぼ確定した。
長野県の遺跡
長野県には,先土器・縄文時代を中心に,多くの遺跡がある。先土器時代では,ナイフ形石器や局部磨製石斧の出土した茶臼山遺跡(諏訪市)が関東地方以外で初めて発掘調査されたこの期の遺跡として,また矢出川遺跡(南佐久郡南牧村)は日本で初めて細石器を出土した遺跡として,ともに学史的にも重要。ナイフ形石器を主とする遺跡としては,杉久保型ナイフで知られる野尻湖底の杉久保遺跡(上水内郡信濃町)がある。柳又遺跡(木曾郡木曾町)では,A地点でケツ岩製ナイフ形石器と黒曜石製細石刃石器群が層位的に出土し,B地点では柳又ポイントと呼ばれる縄文草創期の幅広の有舌尖頭器と隆線文土器が伴出している。神子柴(みこしば)遺跡(上伊那郡南箕輪村)では押圧剝離による月桂樹葉形尖頭器や断面三角形の円鑿(まるのみ)風石斧など五十数点の石器が土器を伴わずに発見された。諏訪湖底の曾根遺跡(諏訪市)は各種石鏃など多量の石器と爪形文土器片などが発見され,珍しい湖底遺跡として古くからその性格,成因などが論じられたが,先土器時代末~縄文草創期の湖畔遺跡だったと考えられている。栃原(とちはら)岩陰(南佐久郡北相木村)は押型文土器を伴う縄文早期の遺跡。縄文前期では大集落址の阿久(あきゆう)遺跡(諏訪郡原村)がある。ここでは,馬蹄形集落とその中央の広場に方形に配列された土壙群,それに大環状集石群など,従来の縄文時代のイメージを破る遺構が発見され注目されている。中期の井戸尻遺跡群(諏訪郡富士見町)は井戸尻,曾利など中期を主とする遺跡群の総称。土器に優品が多く,また約200の竪穴住居址の編年研究や集落の復原が試みられている。尖石(とがりいし)遺跡(茅野市)でも中期の中央広場をもつ馬蹄形集落が調査されている。茂沢南石堂(もざわみなみいしどう)遺跡(北佐久郡軽井沢町)には中~後期の竪穴住居址や後期の敷石住居を含む配石遺構などがある。晩期では前半の大洞C式を伴い,佐野式の標式遺跡である佐野遺跡(下高井郡山ノ内町),同じく後半,網状浮線文をもつ氷(こおり)式の標式遺跡である氷遺跡(小諸市)がある。庄ノ畑遺跡(岡谷市)は縄文晩期後半~弥生中期初頭(いわゆる庄ノ畑式土器)の遺跡。
弥生時代では,中期前半,阿島(あじま)式の標式遺跡である阿島遺跡(下伊那郡喬木村),中期の石鏃工房をもつ北原遺跡(下伊那郡高森町),中期後半の栗林式の標式遺跡である栗林遺跡(中野市)がある。平出遺跡(塩尻市)では古墳時代~平安時代を中心とする住居址などが調査され,古代農村の研究の好材料。
高塚古墳では,4世紀代の前方後方墳弘法山(こうぼうやま)古墳(松本市),前方後円墳の川柳(せんりゆう)将軍塚古墳(長野市),やや遅れるやはり前方後円墳の森将軍塚古墳(千曲市),6世紀代の円墳で積石塚の金鎧山(きんがいさん)古墳(中野市),積石塚を主とする小円墳500余基からなる7世紀代の大室古墳群(長野市)などが重要。歴史時代では信濃国分寺址(上田市)がある。
→信濃国
執筆者:狐塚 裕子
日本の屋根
長野県は日本列島で最も幅の広い中央高地にあって,高い山並みが連なっているため,江戸時代から〈日本の屋根〉といわれていた。県の北北西から南南東にかけて糸魚川-静岡構造線が走り,この西側に,北から飛驒山脈,木曾山脈,赤石山脈の日本アルプスと通称される3山脈が雁行して走っている。いずれも標高3000m級の高い壮年期の褶曲山脈であるが,圏谷やU字谷などの氷食地形が各所に発達している。
県の東部には標高2000~2500mの秩父山地,関東山地や浅間山,白根山などの火山があって,県境をなしている。これらは日本アルプスほどけわしくなく,碓氷(うすい)峠,内山峠,十石峠など多くの峠道があって,関東平野との交流は早くから盛んであった。糸魚川-静岡構造線の東側がフォッサマグナの地域にあたり,ここには八ヶ岳,霧ヶ峰,美ヶ原,妙高火山群が噴出し,丘陵性の筑摩山地がある。これらの山地の間には長野盆地(善光寺平)のほか,上田盆地,佐久盆地(佐久平),松本盆地(松本平),諏訪盆地,伊那盆地(伊那谷),木曾谷などの細長い盆地や谷がほぼ南北方向に連なっている。この盆地や谷には〈日本の屋根〉に源をもつ信濃川の源流の千曲(ちくま)川・犀(さい)川,天竜川,木曾川などの大河が流れ,周辺の山地から流入する諸河川は,複合扇状地をつくって盆地の大部分を埋めている。また伊那盆地などでは河岸段丘の発達が著しい。この扇状地の卓越は長野県の土地利用を特色づけている。扇状地のとくに扇央部では地下水位が低いために,その開発は江戸時代の用水堰の建設や,第2次大戦後の深井戸の開削とともに進んだところが多い。県内にはこう配の急な河川が多く,とくに昭和初期から電源開発が進み,犀川,千曲川,木曾川,天竜川水系などで多くのダムが建設された。1960年代以降,奈川渡(ながわど)ダム(1968),高瀬ダム(1981),牧尾ダム(1961)など規模の大きなダムが建設され,その水資源は,愛知用水をはじめ発電,灌漑,工業用水,上水道などとして用いられている。
長野県の南北の長さは212kmもあって,緯度では2°に近いため,南端と北端では気候に大きな違いがある。また県域は全体的に標高が高く,山地帯,亜高山帯に属している地域が広い。県北部では標高650m以上,それ以外では800m以上の地域がいわゆるシラカバ気候の高冷地で,県内の高原の大部分はこの高冷地に属している。標高1400~1500m以上はダケカンバの自生する亜高山帯,2500~2600m以上はハイマツの生える高山帯である。南部の飯田市以南の伊那盆地と南木曾地方は,東海型気候区に属し,夏季を中心に降雨が多く,温暖なために照葉樹林帯になっている。一方,中綱湖と高社(こうしや)山を結ぶ線より北の信越国境は,北陸型気候区に属し,世界でも有数の深雪地帯である。これらの間が中央高地型の気候区で,長野などの諸盆地は典型的な内陸性気候を示し,年降水量は900~1200mmと,日本ではきわめて少なく,果樹農業に適している。
風土とのかかわりが深い農林業
かつて長野県では蚕糸業が産業の大部分を占め,日本一の産額を上げていたが,昭和恐慌後から産業構造が大きく変わり,農業では果樹,野菜などの園芸農業,工業では電子,精密などの機械工業が中心となっている。県の農家人口は全人口の約4割を占めているが,兼業率も高く全農家の88%(1995)にも達している。農業は日本列島のほぼ中央部にある位置的な有利さと,各地域の自然条件を有効に利用した集約的な園芸農業が高度に発展している。長野,上田,松本,伊那などの盆地ではリンゴ,桃,ブドウなどの栽培が盛んで,県全体の収穫量(1996)ではリンゴが全国の22%(2位),桃が13%(3位)を占めている。
八ヶ岳山麓,浅間山麓,菅平高原をはじめとする高冷地では,レタス,ハクサイ,キャベツなどの高原野菜の栽培が発展し,県全体の収穫量ではレタスが全国の35%(1位),ハクサイが18%(2位)を占めている。また松本盆地や伊那盆地北部は県の穀倉地帯をなし,稲作の生産性が高いことで知られ,近年長野盆地の北部などでエノキダケやアスパラガスの生産が急増している。
林業では木曾のヒノキ,伊那の杉,佐久のカラマツが有名であるが,ヒノキは資源が急減しており,また第2次大戦後全県的に植林がふえたカラマツは,価格が低落して,収支がとれない状況にある。
内陸部の工業地帯
第2次大戦中,京浜地方から戦禍を避けて,諏訪地方など製糸業の盛んだった地域に疎開した工場がその施設と労働力を利用してそのまま定着し,戦後大企業に成長したものが少なくない。しかし内陸にあって,工業発達のための交通条件に恵まれていないため,原料や製品の輸送にあまり負担がかからないコンピューター,テレビなどの電気機械工業が第1位で,県の全出荷額(1995)の43%を,またカメラ,時計などの精密機械工業が第2位で,15%を占めている。これらの部門は労働集約的であって,付加価値の大きい点で共通している。このほか農林業と結びついた食品工業,木工業が盛んで,清酒,みそ,凍豆腐,家具,漆器などの特産品は全国的に知られている。
山岳と高原の観光
長野県は日本を代表する観光県の一つで,県内には飛驒山脈全域にわたる中部山岳国立公園,浅間山,菅平,志賀高原,妙高火山群を含む上信越高原国立公園,甲武信ヶ岳(こぶしがたけ)を中心とする秩父多摩国立公園,赤石山脈の大部分が含まれる南アルプス国立公園,荒船山を中心とする妙義荒船佐久高原国定公園,美ヶ原,霧ヶ峰,蓼科(たてしな)山を含む八ヶ岳中信高原国定公園などの自然公園があり,山岳,高原,渓谷,湖沼などの自然美に恵まれている。また善光寺,松本城をはじめ文化遺産が多く,数多くの温泉が湧出し,スキー場,避暑地などの観光施設も充実している。
交通の発達
長野県では明治期に日本の産業経済の主体をなしていた蚕糸業が盛んであったため,鉄道の敷設は比較的早く,1893年に全通した信越本線をはじめ,中央本線,篠ノ井線などの幹線が明治時代に開通している。幹線道路の開削は明治初期に始められたが,山間部の道路は昭和初期になってから開通したものが多く,山間部の道路の中にはいまだに車道が開通していない国道も存在する。
高速自動車道は,中央自動車道西宮線(1982年全通),長野自動車道(1993年全通),上信越自動車道(1997年県内全通)によって県内のみならず,東京,名古屋,新潟などとの交通事情は大変便利になった。また松本空港は1993年10月ジェット化に伴う工事が完了し,札幌,仙台,大阪,広島,福岡などと結ばれている(2008年現在,札幌,大阪,福岡の3路線)。
北信,東信,中信,木曾,諏訪,伊那北部,伊那南部の7地域
長野県は自然条件,歴史的背景,中心となる都市との結びつきなどから七つの地域に分けられる。長野県では旧国名の信濃,信州の呼称が現在も多用され,地域区分にも北信,東信などの称が一般的である。
(1)北信地域 県の北東部,県庁所在地の長野市のほか,飯山市,中野市,須坂市,千曲市と周辺の町村を含む。千曲川に沿って長野・飯山両盆地が開け,長野新幹線,JR信越本線,飯山線,篠ノ井線の実質的な分岐点で長野電鉄の起点でもある長野市は,善光寺の門前町として発展したところで,北信のみでなく,全県域と新潟県上越地方にも影響力をもつ。農業では長野盆地南部の果樹,北部のエノキダケの栽培が盛んで,工業では電子工業が発達している。志賀高原をはじめ上信越高原国立公園に含まれる範囲が広く,山ノ内温泉郷,野沢温泉など温泉も多い。
(2)東信地域 県の東部,上田市,小諸市,佐久市,東御市と周辺の町を含む。千曲川沿いに佐久盆地,上田盆地が開け,長野新幹線,しなの鉄道線(旧,JR信越本線),小海線,上田電鉄が通じる。中心をなす上田市は,古代,当時の小県(ちいさがた)郡に信濃国の国府が置かれ,平安初期まで信濃国の中心だったところで,16世紀末には真田氏の城下町となった。この地域は農業では八ヶ岳および浅間山麓における高原野菜が全国一の特産地となっている。工業では磁気テープ,自動車部品などの生産が中心をなす。東京からの交通の便がよいため,国際的避暑地である軽井沢町をはじめ,菅平など高原の観光地が発展している。
(3)中信地域 県の北西部,松本市,塩尻市,大町市,安曇野市と周辺の町村が含まれる。中央に県内最大の松本盆地が開ける。JR大糸線,篠ノ井線,松本電鉄の集中する松本市は,平安初期に国府が上田市から移されて以来,信濃国の中心となったところで,中信地域だけでなく,木曾,諏訪,伊那北部地域などにも影響力をもつ。農業では松本盆地での稲作のほか,ワサビやブドウの特産がある。工業では電子,食品などの部門が発達している。
(4)木曾地域 県の南西部,木曾谷と周辺の山地を占める。中山道(国道19号線)とJR中央本線に沿う地域であるが,市はなく中心である木曾町の旧木曾福島町も都市機能が弱いため,中信の松本市や岐阜県中津川市の影響を受けている。江戸時代には尾張藩の支配を受けていたことから,名古屋市の影響も強い。古くから林業の盛んな地域で,経済の発展が遅れた反面,妻籠(つまご)宿をはじめとする町並みや,漆器などすぐれた伝統的工芸品の生産が維持されている。
(5)諏訪地域 県の中央東部,諏訪盆地と八ヶ岳山麓からなる。諏訪市が中心をなすが,JR中央本線,中央自動車道に沿って隣接する下諏訪町,岡谷市とともに連続した都市を形成している。諏訪大社の存在で示されるように早くから開けた地域で,明治以降は日本一の製糸業地域となった。第2次大戦から戦後にかけて時計,カメラなどの精密機械工業が発展し,最近では電子,産業ロボットなどの工業ものびている。下諏訪などの温泉や霧ヶ峰などの高原に恵まれて観光も重要な産業である。
(6)伊那北部地域 県の南東部,伊那市,駒ヶ根市と周辺の町村を含む。中心は伊那盆地北部の伊那市で,近世の城下町の高遠町(現,伊那市)に代わって明治以降発展した。JR中央本線,中央自動車道に沿い,工業用地にも恵まれて県下で最も工業生産の伸びが著しく,電子,精密機械などの工業が発達している。駒ヶ岳千畳敷カール,桜の名所高遠城跡などの観光地がある。
(7)伊那南部地域 県の南部,伊那盆地南部とその周辺の山地を含む。都市は飯田市のみで,その影響力は大きい。工業では電子などの近代工業のほか,水引・紬などの伝統工業は日本でも有数の産地である。人形浄瑠璃や霜月祭のような民俗芸能が数多く伝承されている。
執筆者:市川 健夫
長野[市] (ながの)
長野県北部の市で県庁所在都市。2005年1月旧長野市が豊野(とよの)町と大岡(おおおか),鬼無里(きなさ),戸隠(とがくし)の3村を編入して成立し,10年1月信州新町(しんしゆうしんまち)と中条(なかじよう)村を編入した。人口38万1511(2010)。
大岡
長野市南西端の旧村。旧更級(さらしな)郡所属。人口1544(2000)。筑摩山地に位置する山村で,村面積の7割を山林・原野が占める。村域は南東部の聖(ひじり)山(1447m)から西縁を北流する犀(さい)川の谷までほぼ北西に傾斜し,山間部に集落と耕地が点在する。稲作中心の農業が主産業であるが,昭和30年代から若年労働力の流出が著しく,農家人口は減少している。昭和40年代から聖山(聖ヶ岡)高原の観光開発が進み,キャンプ場,スキー場,別荘地などが造成されている。西縁を国道19号線が通じる。
鬼無里
長野市北西端の旧村。旧上水内(かみみのち)郡所属。人口2333(2000)。北は新潟県に接し,周囲は標高1000m以上の山地に囲まれる。鬼女紅葉伝説でも知られる山村で,中央を犀川支流の裾花川が南流し,川沿いの小平たん地に集落が散在する。南部を国道406号線が横断する。古くは〈木那佐〉と記されたが,戦国末期以降〈鬼無里〉の字があてられるようになった。米作,タバコ栽培,酪農,畜産を中心とした農業が主産業であるが,耕地の多くが山間急傾斜地にあり,生産性は低い。奥裾花渓谷,奥裾花自然園などの観光地があり,品沢高原では別荘地が開発されている。奥裾花自然園には樹齢300年以上のブナ原生林と日本有数の規模を誇るミズバショウの大群生地があり,訪れる観光客は多い。日影に平維茂の祈願所といわれる白鬚神社があり,桃山時代の様式を伝える本殿は重要文化財に指定されている。
信州新町
長野市南西部の旧町。旧上水内郡所属。人口5535(2005)。筑摩山地にあって,犀川沿岸に低地がみられるほかは山林・原野が広い面積を占める。中心集落の新町は江戸時代には松本と結ぶ犀川通船の起点であり,物資の集散地としてにぎわい,2・6・9の日の九斎市が開かれていた。山間傾斜地を利用した農業が主産業で,養蚕,酪農,果樹栽培が盛ん。犀川に並行して国道19号線が走り,隣接する旧長野市への通勤者が多いが,近年は精密機械,弱電,繊維を中心に工場の進出が目だつ。
戸隠
長野市北西部の旧村。旧上水内郡所属。人口4938(2000)。東を飯縄(いいづな)山,黒姫山,北を戸隠山に囲まれた戸隠高原にあり,北部は冬季の積雪が2mをこえる豪雪地帯である。中社,宝光社は古くから修験道場として知られた戸隠神社の門前町として栄えた。近年,周辺にキャンプ場,スキー場,森林植物園などの設備が整って観光地化が進み,バードラインの開通(1964年。97年無料開放)以後,旧長野市経由の観光客も増加している。戸隠そばと竹細工が名物で,戸隠そば博物館,竹細工センターなどの施設もある。国道406号線が横断する南部は平たん地をなし,豊岡,栃原,祖山地区ではタバコ,水稲,高原野菜などの栽培が盛ん。鬼女紅葉伝説が伝わる荒倉山の近くには,紅葉の岩屋とされる洞窟がある。戸隠神社の写経紙本墨書法華経残闕(ざんげつ)・牙笏(げしやく)は重要文化財。
豊野
長野市北東端の旧町。旧上水内郡所属。人口1万0005(2000)。長野盆地中央部に位置し,南は旧長野市,東は中野市に接する。町の北西部は標高300~500mの山地が占めるが,東部を北流する千曲(ちくま)川の沿岸には低地が広がる。中心集落の浅野は近世には北国脇往還の宿駅で,1888年に信越本線,1926年には飯山線が開通し,交通の要地となった。小規模な食品加工工場も立地するが,主産業は農業で,稲作と果樹栽培が行われ,特にリンゴは県下でも有数の生産量を誇っている。国道18号線沿線にはリンゴの直売所などが林立し,アップルラインとよばれる。テクノハイランド構想のもとで近年,工場の誘致が進む。
中条
長野市西部の旧村。旧上水内郡所属。人口2525(2005)。大部分が犀川支流の土尻川流域にあり,一部は北の裾花川流域にまたがる。一帯は起伏の激しい筑摩山地で,北にそびえる虫倉山(1378m)の山腹にも集落が分布する。養蚕,畜産のほかリンゴ,タバコなどを栽培する。傾斜地が多く水田はきわめて少ない。過疎化が進むが,旧長野市への通勤者は増えている。1997年に開通したオリンピック道路(長野~白馬ルート)は村域の南部を横断する。日下野(くさがの)の大内山神社にあるスギは県天然記念物。
執筆者:柳町 晴美
長野
長野市中東部の旧市で県庁所在都市。1897年市制。1966年篠ノ井市のほか川中島,松代(まつしろ),若穂の3町,信更,更北,七二会(なにあい)の3村と合体。人口36万0112(2000)。市域は千曲川に沿う長野盆地南西部と,支流の犀川沿いなど周辺の山地からなる。善光寺の門前町として発達した市街地は,犀川の支流裾花川の谷口集落的な性格をもっていたため,周辺の薪炭や,盆地内のワタ,綿布などを扱う定期市が早くから開かれていた。近世には北国街道が開設され,善光寺の門前に宿がおかれていっそう発展した。このように近世まで門前町,市場町,宿場町の複合的な性格をもっていた長野は,1871年(明治4)県庁所在地となって政治・経済・文化の中心地となり,国や県の出先機関,会社などが数多く進出した。明治~昭和初期にかけては蚕糸業の発展が著しかったため,鉄道の敷設は早く,1893年には信越本線が全通した。1997年10月には長野新幹線が開通,飯山線,篠ノ井線の始発駅で長野電鉄の起点でもある長野駅付近や北の権堂(ごんどう)付近を中心に商業が盛んで,商圏は北信地域だけでなく,新潟県上越地方にも及んでいる。工業ではみそ,凍み豆腐の食料品,家具などの地場産業のほか,コンピューター,テレビなどの電子工業が立地している。農業では犀川扇状地(川中島平)での米作,周辺の山麓部でのリンゴ,ブドウ,桃など集約的な果樹園芸農業が盛んである。千曲川西岸の川中島平は16世紀武田信玄と上杉謙信の川中島の戦で知られる。東岸の松代は近世,真田氏10万石の城下町として栄えたところで,海津城跡(史),藩校文武(ぶんぶ)学校(史)など史跡が多い。川中島平南部の篠ノ井は1959-66年篠ノ井市だったところで,信越本線(97年篠ノ井~軽井沢間はしなの鉄道となる)と篠ノ井線の分岐点をなす交通の要地として明治以降発達した。上信越自動車道,国道18号線,19号線が通じる。長野市は道路交通の中心であり,市域に飯縄高原,周辺に志賀高原,戸隠高原(現,長野市)などがあるため,観光基地ともなっている。98年2月には長野市を中心に冬季オリンピックが開催された。
執筆者:市川 健夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「長野」の意味・わかりやすい解説
長野[県]【ながの】
→関連項目中部地方|長野オリンピック(1998年)
長野[市]【ながの】
→関連項目川中島|篠ノ井|長野[県]|松代|松代藩
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「長野」の解説
長野
ながの
百済 (くだら) 伝来と伝えられる阿弥陀如来を本尊とする善光寺が7世紀にでき,中世に至って,その門前町として発展した。江戸時代まで善光寺町と呼ばれ,北信濃の政治・経済の中心となる。1897年市制施行。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の長野の言及
【中仙[町]】より
…散村が多く見られる純農村地帯で,中仙米で知られる米の産地である。中心集落の長野は近世初期に佐竹北家が居城し,また雄物川舟運の遡航終点の河港にあたり,角館(かくのだて)方面への物資の荷揚地,市場町として発達したが,北家の角館移転に伴い衰退した。扇端部には湧泉が多く,これを農業用水として水田が開かれていたが,湧泉帯以東の原野は,近世初期の用水池の開削とともに開墾が始められた。…
【信楽[町]】より
…古代には木津川の河谷を経由して大和との関係が深く,町の北東部に紫香楽宮(しがらきのみや)跡があり,国の史跡に指定されている。中心の長野は信楽焼の主産地で,第2次大戦前は火鉢,茶壺の生産が多かったが,近年は植木鉢に主力が注がれ,ほかにタイルや庭園用の陶器のテーブルセット,灯籠などがつくられており,県立窯業試験場,信楽伝統産業会館がある。町の西部の朝宮を中心とする山間地は〈信楽茶〉の産地。…
※「長野」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...


 長野県北部の市。
長野県北部の市。