デジタル大辞泉 「山口」の意味・読み・例文・類語
やまぐち【山口】[地名]
 中国地方西部の県。もとの
中国地方西部の県。もとの 山口県中央部の市。県庁所在地。中世、大内氏が京都を模した町を建設し発展。幕末に萩から毛利氏の藩庁が移された。常栄寺庭園・瑠璃光寺などの史跡や湯田温泉がある。平成17年(2005)に徳地町・
山口県中央部の市。県庁所在地。中世、大内氏が京都を模した町を建設し発展。幕末に萩から毛利氏の藩庁が移された。常栄寺庭園・瑠璃光寺などの史跡や湯田温泉がある。平成17年(2005)に徳地町・ 中国地方西部の県。もとの
中国地方西部の県。もとの 山口県中央部の市。県庁所在地。中世、大内氏が京都を模した町を建設し発展。幕末に萩から毛利氏の藩庁が移された。常栄寺庭園・瑠璃光寺などの史跡や湯田温泉がある。平成17年(2005)に徳地町・
山口県中央部の市。県庁所在地。中世、大内氏が京都を模した町を建設し発展。幕末に萩から毛利氏の藩庁が移された。常栄寺庭園・瑠璃光寺などの史跡や湯田温泉がある。平成17年(2005)に徳地町・中国地方の西部を占める県。東は島根・広島両県に接し、北は日本海、西は響灘(ひびきなだ)、南は瀬戸内海に面し、三方を海で囲まれている。南西部は狭い関門海峡を隔てて九州と相対し、響灘、玄界(げんかい)灘を越えて朝鮮半島へも近く、北九州とともに大陸への門戸的位置を占め、また西日本における海陸交通の要地として重要な地域的機能を果たしてきた地方である。面積は6112.5平方キロメートル、県庁所在地は山口市。
古代、周防(すおう)、長門(ながと)2国からなり、中世は大内氏、近世は毛利(もうり)氏によって統治され、明治以降もその領域は変わらず比較的まとまった地域として発展してきた。長く農水産業が中心で、産業の近代化はやや遅れたが、大正期以降、下関(しものせき)や宇部(うべ)、小野田の工業化が進み、さらに昭和10年代以後、内海沿岸各地に重化学工業の立地をみた。一方、日本海沿岸は農水産業への依存度が高い。海底トンネルや関門橋などによって関門海峡を隔てた北九州と直結しているため、文化、経済、産業上も北九州圏との関係が深い。
明治以降の人口の趨勢(すうせい)をみると、1876年(明治9)の84万は1925年(大正14)に109万、2000年(平成12)には152万7964となった。120年間に約2倍の増加であるが、全国人口が3倍以上の増加であるのに比べると低調で、人口流出県である。1958年(昭和33)には162万に達したが、以後1970年に151万まで減少し1971年からわずかながら上昇に転じて1985年には160万まで回復したが、その後は減少している。2005年の人口は149万2606。人口分布は内海沿岸に集中し、山陽本線沿いの市部の人口が総人口の78%を占めていた。2015年の人口は140万4729、2020年(令和2)の人口は134万2059。
2002年4月の時点で、14市11郡37町5村からなっていたが、平成の大合併を経て、2020年10月時点では、13市4郡6町に再編されている。
[三浦 肇]
中国山地は西へ向かうにつれて高度を減じ、県域の大部分は高原状の山地や丘陵地である。
広島、島根県境には中国脊梁(せきりょう)山地の一部をなす1000メートル級の寂地(じゃくち)山や平家岳、莇(あざみ)ヶ岳など起伏の大きい山地があり、その延長に600~700メートルの鳳翩(ほうべん)山などの分水界山地が連なる。分水界山地よりやや低い300~500メートルの周防山地、長門山地などは中国地方の吉備(きび)高原面に相当し、侵食谷によってさらに小さく分かれる。瀬戸内沿岸に広く発達する100~300メートルの周南(しゅうなん)丘陵や長門丘陵は、瀬戸内面とよばれる侵食小起伏面に相当する地形で、長門丘陵のうちでもとくに宇部・厚狭(あさ)丘陵はその標式地として知られる。長門丘陵の内陸には約130平方キロメートルにわたってカルスト地形が発達する日本最大の石灰岩台地秋吉台(あきよしだい)がある。
自然公園は、県南東部の多島海景観を中心に関門海峡付近までの地域が瀬戸内海国立公園の一部をなし、県北東部の大起伏山地と渓谷美に優れた寂地山、小五郎(こごろう)山などが西中国山地国定公園に、日本海沿岸北端の須佐湾一帯から萩(はぎ)海岸を経て青海(おうみ)島、油谷(ゆや)半島、角(つの)島にわたる海食景観が北長門海岸国定公園に、カルスト高原秋吉台と鍾乳洞(しょうにゅうどう)の秋芳(あきよし)洞(ともに特別天然記念物)を含む地域が秋吉台国定公園に指定されている。なお、県立自然公園には石城(いわき)山、長門峡(ちょうもんきょう)、豊田(とよた)、羅漢(らかん)山の四つがある。
[三浦 肇]
中国地方に一般的な山陰型、中国山地型、山陽型の気候上の特徴が、山口県ではそれぞれ漸移的に北九州型の気候へ移り変わる。三方を海に囲まれ、高い山地もないので、気温も降水量も沿岸から内陸山間地へ向かって温暖少雨から冷涼多雨へと高度に応じて同心円状に変化する。日本海沿岸は山陰型に属し、概して冬の季節風が強く、曇天や雨雪が多いが、対馬(つしま)暖流の影響もあって気温の較差は小さく温暖で、年平均気温は15~16℃。内海沿岸は山陽型に属し、東部ほど冬季の日照時間が多く温暖で季節風の影響も少ない。平均気温15~16℃。山間部は中国山地型に属し、高地ほど冷涼で年平均気温は15℃以下である。夏季には台風による風水害も多い。
[三浦 肇]
県内の数か所から旧石器時代の石器が出土しているが、確かな居住開発は新石器時代に入ってからで、縄文時代の土器や石器の発見地は40か所以上あるが、遺跡の規模は小さい。主要遺跡は平生(ひらお)町岩田、山口市美濃ヶ浜(みのがはま)などいずれも海岸にあり、出土遺物の特徴から瀬戸内系と九州系の両方の縄文文化が交錯していることがわかる。大陸に近いこの地方では稲作農耕文化は響灘沿岸にまず定着し、しだいに内陸へと展開した。弥生(やよい)前期の大集落址(し)が発掘された綾羅木郷(あやらぎごう)と、多紐(たちゅう)細文鏡や細形銅剣を出土した梶栗浜(かじくりはま)の両遺跡は下関市北郊にあり、弥生人骨300体余が発見された下関市豊北(ほうほく)町の土井ヶ浜遺跡(どいがはまいせき)は日本人の起源や当時の生活、習俗を知る重要な遺跡である。大和(やまと)政権による統合が進むにつれ、古墳は瀬戸内沿岸に多く築造された。主要な前方後円墳には、日本最大級の単頭双胴怪獣鏡を出土した柳井(やない)市茶臼山古墳(ちゃうすやまこふん)、県下最大の全長125メートルの平生町白鳥古墳(しらとりこふん)、天王日月四神四獣鏡を出土した周南(しゅうなん)市竹島の御家老屋敷古墳(ごかろうやしきこふん)、被葬者が百済(くだら)王子琳聖(りんしょう)太子との伝承をもつ防府(ほうふ)市大日古墳(だいにちこふん)などがある。また1975年(昭和50)から発掘され、弥生期から古墳期の墳墓形態をもつ山口市朝田墳墓群(あさだふんぼぐん)は畿内(きない)型古墳の影響がみられるものの、在地性の濃い西日本に珍しい大墳墓群として注目される。
奈良時代の律令(りつりょう)制下に山口県域には周防と長門の2国が成立し、周防国府は沙麼県(さばのあがた)の置かれていた防府市佐波令(さばりょう)に、長門国府は仲哀(ちゅうあい)天皇穴門豊浦宮(あなとのとよらのみや)の地である下関市長府に置かれた。条里型地割の遺構は、小規模であるが約40か所の条里区が知られている。防長両国は銅産国でもあり、鋳銭司(じゅぜんのつかさ)が置かれた。710年(和銅3)ごろ長門国府に付設した鋳銭工房で和同開珎(わどうかいちん)を鋳造したが、827年(天長4)ごろ周防国に移し、山口市陶(すえ)の地で約150年間に皇朝十二銭のうち8種が鋳造された。また、古代の銅産地の美祢市美東町(みとうちょう)長登(ながのぼり)には銅製錬の遺跡があり、奈良東大寺の大仏の鋳造用の銅を産出したことが近年の発掘調査でわかった。平安末期、内海海賊の鎮圧に功をあげ、西国一帯に多くの所領を有して中央に強大な勢力を誇った平家一門は、源氏によって京都を追われ、1185年(文治1)瀬戸内海の西端の壇之浦(だんのうら)で滅亡した。
[三浦 肇]
1186年周防国は東大寺の造営料国となり、大勧進重源(だいかんじんちょうげん)がくだり、以後長く東大寺領として大勧進が国司上人(しょうにん)として国務を管理した。南北朝期、大内氏が国府在庁官人から台頭して周防守護職となった。1355年(正平10・文和4)大内弘世(ひろよ)は長門守護職厚東(ことう)氏を滅ぼし、防長2国を領有し、山口に守護所を設けて京都に模した街づくりをした。その子義弘(よしひろ)はさらに石見(いわみ)、豊前(ぶぜん)、筑前(ちくぜん)にも勢力を伸ばし、義興(よしおき)のときには和泉(いずみ)、紀伊をも領有して7国の大守となり、室町幕府の管領代(かんれいだい)として中央にも進出した。大内氏は海外貿易を独占して経済的基盤を培い、その府下山口は「西の都」とよばれるほどの繁栄を極めた。1550年(天文19)山口を訪れたスペインの耶蘇(やそ)会士フランシスコ・ザビエルは、1553年大道寺に教会堂を建てて布教に努めたが、このころの山口は戸数1万以上を数えたと伝えられている。小田原と並ぶ中世城下町であり、堺(さかい)や博多(はかた)とともに西日本有数の貿易都市であった。1551年大内氏は家臣の陶晴賢(すえはるかた)の反逆によって滅び、陶氏もまた毛利元就(もとなり)に敗れて自刃した。やがて中国8か国の大守となった毛利氏も関ヶ原の戦い以後、防長2国に減封された。
[三浦 肇]
1604年(慶長9)広島から山陰沿岸僻陬(へきすう)地の萩に移った毛利輝元はここに城下町を建設し、防長両国の経営に腐心した。毛利秀元(ひでもと)を西境の豊浦(とよら)郡の豊浦藩(長府(ちょうふ)藩)に封じ、吉川広家(きっかわひろいえ)を玖珂(くが)郡に配して東境の押さえとし、藩体制の整備を進めた。藩法「万治(まんじ)制法」の制定、藩治職制の確立を急ぎ、地方行政に関しては本藩領を18の宰判(さいばん)に分け、藩府からは郡奉行(こおりぶぎょう)のもとに代官が派駐された。藩は殖産興業に深く意を用い、荒蕪(こうぶ)地の開拓、沿岸低地の干拓地造成が盛んに行われた。その結果、藩領総高は宝暦(ほうれき)検地(1761)では86万石余に達した。とくに内海沿岸では大規模な干拓が行われたが、そのなかには塩田も多く、なかでも三田尻塩田(みたじりえんでん)は防長塩業の中心をなした。西廻(にしまわり)航路の発達に伴い、各地に港町の発展をみ、下関、中関(なかのせき)、室積(むろづみ)などの港は廻船(かいせん)の出入りでにぎわった。米や塩のほか防長四白として有名な生蝋(なまろう)や紙も山間農村で盛んに製造された。一方、藩は各地の特産物を買い上げる「御内用産物方」を設け、専売制の強化を図ったが、これに反発する農民たちにより1831年(天保2)一揆(いっき)が頻発した。
幕末、長州藩は開国と攘夷(じょうい)をめぐって揺れ、馬関攘夷戦の敗退、京都蛤御門(はまぐりごもん)の変(1864)での敗戦から二度の長州征伐を経て、1869年(明治2)長薩(さつ)土肥4藩の版籍奉還に至った。明治維新の大変革を推進した高杉晋作(しんさく)、伊藤博文(ひろぶみ)ら多くの人材が萩の松下村塾(しょうかそんじゅく)から輩出したことは特筆さるべきであろう。
[三浦 肇]
1871年の廃藩置県で山口、岩国、豊浦(とようら)、清末(きよすえ)の4県が置かれ、やがて統合されて山口県が成立した。
明治前期に岩国に製糸工場、小野田にセメント工場や化学工場が設立されるなど近代工業の萌芽(ほうが)がみられたが、大正期までは農業県として推移した。その後、沿岸各地の工業化が進展するにつれて、農家数も大正初年の13万5000戸を最高に減少傾向をたどった。江戸期に商品作物として各地にみられたナタネ、ワタ、アイなどの栽培や養蚕は昭和期に入って減少し、一方、士族授産によっておこった萩地方の夏ミカンや、すでに江戸後期に始まった大島地方の温州(うんしゅう)ミカンの栽培が盛んになった。第一次世界大戦を機に、内海沿岸には大工場が進出し、下関、宇部、防府、徳山、下松(くだまつ)、岩国などが工業都市として発展した。とくに江戸期から石炭産地であった宇部、小野田では明治後期に海底炭田の開発に乗り出し、1940年(昭和15)には423万トンの石炭を採掘した。大正末年ごろを境として工業生産額が農業生産額を上回るようになり、昭和期に入ってとくに化学工業を中心に工業県へと産業構造の近代化を遂げてきた。第二次世界大戦中には石油、金属、機械の工業部門も強化され、昭和30年代のエネルギー革命期にはいち早く、岩国や周南(しゅうなん)に石油化学コンビナートの形成をみた。近年、宇部、小野田にも石油化学工業が加わり、山口県は全国有数の石油基地となっている。
[三浦 肇]
県の産業の中心は、大正期まで稲作主体の農業であったが、昭和期に入って工業化が急速に進展した。1930年(昭和5)の農業人口は全就業者人口の50%、工業人口は12%であり、農業が依然県の重要産業であった。農業人口と工業人口が同率を占めるようになるのは高度経済成長期の1970年代である。
一方、海に囲まれた山口県では江戸末期に内海漁民が対馬(つしま)近海へ出漁しており、鯨組も組織されていた。明治以降も朝鮮近海の漁場開発に乗り出し、朝鮮半島沿岸に移住漁村をつくったのも山口県漁民が多かった。仙崎におこった日本海捕鯨も発展して日本捕鯨業の中心となって、南氷洋捕鯨に活躍した。西日本における近代漁業の発達のなかで、水産県山口の果たした役割は大きいものがあった。
山口県産業の特質は伝統的な農業県から明治・大正期を経て農水産県として発展し、石炭や石灰石を利用し、北九州工業地帯の影響下に、昭和期を通じて工業県として大きく変貌(へんぼう)を遂げてきたといえるであろう。
[三浦 肇]
平野の少ない山口県は藩政期に造成された干拓地などを含めても、平野(台地、低地)面積は県総面積の16%程度である。2000年(平成12)の『世界農林業センサス』によると農業関連の土地利用は以下の通りである。なお( )内は1995年の数値を示している。耕地面積は4万1200ヘクタール(4万5700ヘクタール)、耕地率は6.7%(7.5%)で、水田3万5000ヘクタール(3万8000ヘクタール)、普通畑3200ヘクタール(3700ヘクタール)、樹園地2900ヘクタール(3500ヘクタール)、全国的には畑地の少ない県である。農業産出額は1994年に1164億円であったが、2003年には777億円に減少している。内訳は米が42%を占め、ついで畜産27%、野菜18%、果樹6%の順となっている。農家数は減少を続けていて、1995年の6万3000戸から2000年にはさらに5万2000戸に減少、また農業就業人口も1995年の8万4000人から、2000年は5万8000人と減少している。農業従事者の老齢化、経営規模の停滞などもあり、農業所得の伸びも鈍化している。
米作はかつて沿岸の小平野や小盆地が良質の防長米の産地として知られたが、第二次世界大戦後は土地改良や栽培技術の革新によって、内陸山間盆地の下関市豊田(とよた)町地区、美祢市秋芳(しゅうほう)町地区などが安定した米産地となっている。下関市はもっとも早く近郊農業の発達をみた所で、ネギ、レタス、ホウレンソウ、ナス、トマトなど全県第一の生産をあげている。そのほか山口市のイチゴやメロン、タマネギ、宇部市のキュウリ、キャベツ、岩国市の蓮根(れんこん)、ゴボウ、萩市のスイカなどがよく知られている。果樹は作付面積が減少傾向にあり、大島地方の温州ミカンも萩地方の夏ミカンも生産過剰で、とくに温州ミカンは1979年(昭和54)から3回にわけて生産抑制計画が実施され、イヨカンやハッサクなどへの転換が進められている。
林野面積は43万6000ヘクタール(2000)で、34万3000ヘクタールが私有林である。林家数は3万3000戸(2000)であるが、経営規模5ヘクタール以下の戸数が76%を占め零細である。竹林は日本海沿岸にわずか分布するが、全国2位の竹材生産県である。林野副産物のマツタケは山口市と岩国市の花崗(かこう)岩地が主産地。
[三浦 肇]
屈曲に富んだ海岸線をもつ山口県の沿岸には多くの漁港が発達している。現在日本海側に約50、内海側に約60の漁港あるいは漁業地があり、下関のほか、かつては萩、仙崎も遠洋漁業の基地ともなっていた。しかし、沿岸の魚族資源の減少、若年労働力の流出と漁民の老齢化、沿岸の工業都市化に伴う漁場汚染などにより水産業は厳しい状況にあり、養殖漁業への転換が図られつつある。海面漁業の漁獲量は2003年では5万3000トン(1994年は約12万トン)で、東シナ海区がその70%以上を占めている。漁業生産額は2003年では249億円(1994年は496億円)に達する。瀬戸内海区の漁業は、周防灘でのエビやカレイ、ナマコ、貝類を漁獲する小型底引網がもっとも多く、東部の島嶼(とうしょ)沿岸ではタイ、タチウオ、アジなどの一本釣りやイワシの船引網が盛ん。おもな漁港に久賀(くか)、安下庄(あげのしょう)、上関(かみのせき)、室積(むろづみ)、粭島(すくもじま)、防府、宇部などがある。東シナ海区では下関漁港を基地とする巻網や以西底引網、沖合底引網などにより、アジ、サバ、フグなどが水揚げされ、韓国輸入魚も増えている。ついで萩と仙崎が日本海漁業の二中心をなし、沖合底引網、揚操(あぐり)網、棒受(ぼううけ)網、敷網などが行われ、アジ、イワシ、ブリ、イカ、シイラなどの水揚げが多い。内海沿岸の秋穂(あいお)はクルマエビ養殖の発祥の地といわれ、いまでも盛んである。ここには1963年に日本最初の種苗センターとして開設された県内海栽培漁業センターがある。日本海側では青海(おうみ)島に県外海栽培漁業センターが、阿武町に外海第二栽培漁業センターがある。水産加工は萩、仙崎、防府、下関でかまぼこ製造が盛んであり、下関のふく料理は山口県の味覚として全国に知られている。
[三浦 肇]
山口県の採鉱の歴史は古く、古代の防長2国は銅産出国として知られた。近世も藩営の一ノ坂銀山、阿川山(あがわやま)砂鉄、白須山(しらすやま)製鉄場などがあり、舟木(ふなき)・宇部地方の石炭は製塩などの燃料用に採掘された。明治以降近代技術が導入されて各種鉱山の本格的開発が始まったが、埋蔵量が少なく小規模なため盛衰が著しい。鉱山数は1995年の24から、2004年には16に減少している。タングステン、セメント用の珪石(けいせき)、石灰石、鋳物用の珪砂、耐火煉瓦(れんが)用のろう石、石炭などが主要な鉱産物である。山口県化学工業の基礎原料として重要だった硫化鉱の河山鉱山は1978年閉山し、また宇部の石炭系化学工業を生み出した宇部炭田や無煙炭の大嶺(おおみね)炭田もエネルギー革命によって1970年代にすべての炭鉱が閉山した。
[三浦 肇]
山口県の工業は重化学工業に特色がある。1994年の製造出荷額は4兆8100億円で全国の22位、1993年以降は伸び率は停滞しているが、2003年には5兆1415億円となり、全国20位と順位が上昇している。出荷額のうち化学工業が28%を占め、ついで輸送機械18%、石油製品15%、鉄鋼業10%の順で、いずれも高能率の大工場が多い。事業所数では食品、金属、窯業、木材の順となっている。地域的にみると、1964年に工業整備特別地域に指定された周南工業地域(しゅうなんこうぎょうちいき)が全県工業出荷額の36%を占め、県を代表する重化学工業地域を形成している。この地域は第二次世界大戦前に豊富な塩と石炭を利用してソーダ工業がおこり、戦後は徳山市(現、周南市)の石油精製工場を中心に石油化学コンビナートが成立した。光(ひかり)市は鉄鋼と薬品、下松市は鋼板、車両、石油精製の工場があり、防府市は化学繊維や肥料工場に加えて、近年自動車工場が進出した。宇部・小野田工業地域は化学肥料、ソーダ工業、美祢(みね)市産出の石灰石を利用するセメント工業が中心で、新しく石油精製工場も加わった。下関地域は造船業や、水産加工を中心とする食品工業が盛んで、金属、ゴム、鉄鋼、化学工業などの工業も発達している。岩国・和木(わき)地域は広島県大竹市の化学工場と結ばれ、日本最初の石油化学コンビナートが成立した所で、早くから錦(にしき)川の水を利用するパルプ工業、化学繊維工業が発達した。日本海沿岸にはみるべき近代工業はなく、阿武地方の耐火煉瓦工場、近世以来の伝統工業である萩焼などのほかは萩市や長門市の水産加工業がおもなものである。
地場産業として特筆すべきものに赤間硯(あかますずり)と萩焼がある。赤間硯は下関市から宇部市にかけて産出する輝緑凝灰岩を原石とし、現在は宇部市万倉(まぐら)の岩滝で採掘している。色彩の美しさと彫刻の巧緻(こうち)さで知られている赤間硯の創始は鎌倉時代ともいわれるが、江戸時代、長府藩御用硯師に大森家があり、西国の要港として赤間関(下関市)が発展するとともにしだいに下関商人によって全国に広まった。萩焼は一楽(らく)二萩三唐津(からつ)といわれ、茶陶として珍重されてきた。江戸時代初期萩藩御用窯として始まり、萩市松本の坂窯や三輪(みわ)窯、長門市深川(ふかわ)の坂倉窯、坂田窯が江戸時代からの古窯で、明治になって山口市宮野の松緑(しょうろく)窯が定着した。蹴(け)りろくろを使う伝統的な技法が受け継がれているが、重油窯による製品も増えている。現在100以上の窯元があり、高級品の抹茶器、煎茶(せんちゃ)器のほか、置物、花瓶、日常雑器も生産されている。
[三浦 肇]
県の産業、経済構成は瀬戸内側に偏在している。これからは内外の変動に対して適応性のある、国際競争力をもった産業複合体をつくることが必要である。近年、8地域からなる広域生活圏構想や県土交流一時間圏構想、ハイテク産業技術の集積を目ざす宇部テクノポリス構想などが推進され、その一部は実現しつつある。この圏域内には各種工業の集積があり、基幹資源型工業開発のモデル地域でもあり、先端技術産業の開発と導入を図り、ファインケミカルズ(医薬品)、コンピュータ産業、新素材、複合材、IC産業などの生産額が増加しつつある。圏域を山陽新幹線、国道2号、中国自動車道が貫通し、県営山口宇部空港も近く、交通網は整っており、山口大学工学部、山口東京理科大学、山口県メカトロ技術センターなど研究機関も充実しつつある。
なお、県では1998年から新しい開発計画「やまぐち未来デザイン21」を進めている。
[三浦 肇]
九州と近畿を結ぶ海陸交通の要地にあたるため、古代から山陽道と山陰道が合流し、瀬戸内や西海の諸航路の集まる所であった。1901年(明治34)山陽本線(当時は山陽鉄道)が開通し、1905年関釜(かんぷ)連絡船が就航して下関市は大陸への門戸となった。大正末年には山陰山陽連絡の山口線、美祢線などが通じたが、山陰本線の全通はようやく1930年(昭和5)であった。第二次世界大戦中の1942年には関門海峡の海底を関門鉄道トンネルが貫通、1958年(昭和33)に関門国道トンネルが開通した。九州と本州が結ばれたことは日本交通史上のみならず、世界的にも画期的なことであり、西日本における産業、流通圏に大きい影響を与えることになった。1973年、吊橋(つりばし)の関門橋を含む関門自動車道が完成した。1975年には山陽新幹線が新設され、新関門トンネル(延長18.7キロメートル)も貫通した。続いて1983年、中国縦貫自動車道が県内陸部を貫いて全通し、1992年(平成4)には、山陽自動車道県内全線(山口―岩国間)が開通し、高速時代の新しい交通網の整備が進んだ。
県営山口宇部空港はジェット機が就航、東京―宇部間を1時間30分で結んでいる。港湾は国際拠点港湾2、重要港湾4、地方港湾23を数え、下関、宇部、徳山下松、岩国、三田尻中関、柳井、萩の各港が入港船舶数、貨物輸送量とも大きい。
[三浦 肇]
藩校には本藩の長州藩に明倫館(めいりんかん)があり、各支藩にも岩国の養老館、長府の敬業(けいぎょう)館などがあったが、吉田松陰(よしだしょういん)の私塾であった萩の松下村塾からは明治維新や明治新政の推進に活躍した人材が多く育った。学制公布直前の山口県下の教育施設の普及率は長野県と並んで高く、庶民教育が広く浸透していた。藩校山口明倫館は1870年(明治3)に山口中学、のちに県立山口中学校となり、1894年に山口高等学校と改称された。初代校長は後の文部大臣岡田良平、教授の一人に西田幾多郎(にしだきたろう)がいた。
2017年(平成29)時点の県内の大学は、国公立等では山口大学、山口県立大学、下関市立大学、山陽小野田市立山口東京理科大学、水産大学校、私立では徳山大学、梅光(ばいこう)学院大学、東亜大学、宇部フロンティア大学、至誠館大学、山口学芸大学、放送大学山口学習センターがある。ほかに、大島商船・宇部工業・徳山工業の3高等専門学校や、私立の4短大などがある。文化社会教育施設としては明治・大正期から全国的にその活動を知られた県立山口図書館、全国初の公文書館である山口県文書(もんじょ)館をはじめ、山口博物館、県立美術館、岩国徴古(ちょうこ)館、萩市の萩博物館、美祢市の秋吉台科学博物館、下関市の土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム、宇部市常盤(ときわ)公園の緑と花と彫刻の美術館(ときわミュージアム)など特色あるものが多い。放送機関にはNHK山口放送局とKRY山口放送、TYSテレビ山口、YAB山口朝日放送の4局のほかにエフエム山口などがある。
[三浦 肇]
山口県の方言は西日本方言圏に含まれ、九州方言圏と区別される。古来北九州と畿内(きない)を結ぶ文化廊下の役割を担ってきた地域であり、近畿との交流が深い。県内の分水界山地も低く、人文交流上の障壁性は少なく、山陽・山陰間の言語上の南北差はあまりない。大内氏、毛利氏の統治を通じて共通性の広い「長州弁」あるいは「山口弁」といわれるお国ことばが形成された。「おいでませ」「のんた」「であります」に象徴される山口方言は、九州方言に比べて明らかに柔らかい響きをもち、京ことばの影響があるともいわれる。近畿と共通する方言として、から(体格)、おおこ(天秤棒(てんびんぼう))、おいど(尻(しり))、こける(倒れる)、ごつい(大きい、武骨)など多くのものがあげられ、中国地方共通の方言には、たお(峠)、いたしい(気の毒)、はぶてる(すねる)、くじをくる(しかる)などがある。山口県内でもたとえば、稲むらの語形も「のう」「ぐろ」(周防)と「としゃく」(長門)に分かれ、「たくさん」を意味する語形も「えっと」(周防)、「じょうに」(長門)、ていねいな表現の「見せなさい」も「見せさんせー」(周防)と「見せさん」(長門)となり、東部と西部の小方言区に分かれる。
伝統的な農家の基本形は寄棟造整型四間取りである。かつては藁葺(わらぶ)きであった屋根も明治以降内海沿岸で黒瓦(がわら)が多く用いられ、内陸から山陰側ではほとんどが赤い光沢のある耐寒性の石見(いわみ)瓦にかわった。現在でも山陽と山陰を結ぶ山口線や美祢線沿いでは、こうした風土を反映した民家景観の変化を見ることができる。農家の間取りも藩政時代は厳しい規制があって、本百姓は四間取り(田の字型)であった。玄関(入(はい)り口)を入った土間を「にわ」といい、表の間、上(かみ)の間、台所(よこざ)、奥の間(ねま)の4間からなり、さらに六間取りではそれに、中の間、納戸(なんど)が加わったもの(サの字型)になる。
正月を迎える風習には各地にさまざまのものが伝えられている。大晦日(おおみそか)の夜、氏神に餅(もち)を持って参詣(さんけい)する「年の夜参り」が東部の島々や周防各地にあり、周防大島町屋代(やしろ)の志度石妙見(しどいしみょうけん)社のように籠(こも)り堂の炉を囲んで元旦(がんたん)を迎える所もある。小正月(こしょうがつ)にはどんど焼(左義長(さぎちょう))が行われ、正月飾りなどを集めて焚(た)き、餅を焼いて食べると風邪(かぜ)をひかない、書初(かきぞ)めをくべて高く舞い上がると字が上手になるといい、神社の境内や学校の校庭を利用する子供たちの行事となっている。熊毛群島の祝(いわい)島や八(や)島では長く切替畑(きりかえばた)と牛の放牧が行われてきたが、明治以降切替畑は廃れて、放牧だけが1992年(平成4)廃止されるまで続けられてきた。八島ではこれを「牧畑(まきはた)」とよんでおり、1月4日には正月飾りを山の牧場で焼いて、餅を牛に食べさせる「ねがり」という風習を伝えていた。
春から夏への行事では田植祭があり、花笠(はながさ)をつけて踊る華やかな「囃田(はやしだ)」の行事はわずかに岩国市平田や萩市須佐の上三原(かみみはら)などで伝えられているにすぎない。下関市住吉神社のお田植祭は下関市農業祭に組み入れられ、典雅華麗な祭典として復活した。古くからの夏越(なごし)の行事として、内海沿岸の農村で7月中・下旬に牛を海に引き入れて水浴させる「さばら」とよぶ伝統的な行事がある。一方、漁村の行事では萩市玉江浦(たまえうら)の和船競漕(きょうそう)「おしくらごう」が6月に行われる。4組の青年宿の若者たちが4隻の五丁櫓(ろ)の和船に乗り組み、海上8キロメートルの勝敗を争う雄壮な海の祭礼である。旧暦6月17日には県下各地の厳島(いつくしま)神社で安芸(あき)の本社と同様の管絃祭が行われる。漁民休息の日で、豊漁祈願の祭礼が行われる。7~8月は県下各地で多彩な夏祭が繰り広げられる。約10万個の紅提灯(ちょうちん)が火のトンネルをつくる山口ちょうちん祭、600年伝承された鷺舞(さぎまい)が奉納される山口八坂(やさか)神社の祇園(ぎおん)祭、神功(じんぐう)皇后の故事にちなむ下関忌宮(いみのみや)神社の数方庭祭(すおうていさい)、藩主御座船を模した山車(だし)や神輿(みこし)が繰り出す萩住吉神社のお船謡祭(おふなうたまつり)など地方色あるものが多い。国東(くにさき)半島伊美(いみ)別宮八幡宮の神輿の海上13里の渡御を迎えて、4年に一度行われる上関(かみのせき)町祝島宮戸八幡宮の神舞(かんまい)(県無形文化財)では古式ゆかしい24種の岩戸神楽(かぐら)が奉納される。盆踊りは島嶼部に素朴な形でよく残り、都市では観光化される傾向がある。宇部市居能(いのう)の盆踊りは古い口説(くどき)や振が伝承された優れた郷土芸能である。11月の農村行事に「いのこ」がある。大島郡や周防各地、萩市や旧阿武(あぶ)郡、下関市などにみられ、旧暦10月最初の亥(い)の日に子供たちが「いのこの歌」を歌いながら、収穫感謝と無病息災を祈願して、亥の子石を縄で結んで農家の庭をついて回る。こうして冬に向かい、正月の準備が始まる。
[三浦 肇]
重要なものをあげると、国指定重要文化財のうち、社寺建築では大内時代の山口市瑠璃光(るりこう)寺五重塔、鎌倉時代の下関市功山(こうざん)寺仏殿、大内時代の下関市住吉神社本殿は国宝として文化史上貴重である。山口市には平清水(ひらしみず)八幡宮本殿、今八幡宮の本殿・拝殿・楼門、八坂神社本殿、洞春寺(とうしゅんじ)の観音(かんのん)堂・山門など鎌倉時代や大内時代のものが集中している。そのほかには下松市の閼伽井坊(あかいぼう)多宝塔、光市の石城(いわき)神社本殿、山口市の月輪(がちりん)寺薬師堂などが注目される。住宅建築では旧厚狭(あさ)毛利家萩屋敷長屋や熊谷(くまや)家住宅など特色ある武家・商家の住宅が、城下町であった萩市に多く、萩市堀内地区・平安古(ひやこ)地区・浜崎・佐々並市(ささなみいち)は柳井市古市金屋とともに、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。彫刻では防府市阿弥陀(あみだ)寺の木造重源坐像(ちょうげんざぞう)、下関市国分寺の木造不動明王立像、萩市大照院の木造赤童子立像、山口市神福寺の木造十一面観音立像、防府市国分寺の木造四天王立像などは傑出した逸品である。
国指定重要有形民俗文化財としては、周防大島町久賀と山口市徳地岸見に残る石風呂(ぶろ)、防府市三田尻塩田の製塩用具、長門市の北浦捕鯨用具、防府市阿弥陀寺の湯屋、長門市赤崎神社楽桟敷(がくさじき)などがあり、それぞれの時代の生活文化を伝える貴重なものである。
[三浦 肇]
山口県西部には至る所に「神功皇后(じんぐうこうごう)」の伝説がある。熊襲(くまそ)討伐のために九州に遠征した仲哀(ちゅうあい)天皇は、新羅(しらぎ)を先に誅(ちゅう)せという神託に従わず、神罰により橿日宮(かしびのみや)(福岡市)で急死した。遺体は神功皇后が華山(げさん)(下関市)の西の嶽に葬り、その地を伏拝(ふくはい)の峰と名づけた。皇后は豊浦宮(とようらのみや)(下関市豊浦町)という斎宮(いつきのみや)を建てて、喪に服していると、新羅を討つべしと重ねて神託があった。皇后は壇之浦の海神に七日七夜戦勝を祈願し、「干珠・満珠(ひたまみつたま)」の宝珠を借りて出陣した。干珠は潮を干し、満珠は潮を満たす秘宝で、そのおかげで無事に凱旋(がいせん)することができた。壇之浦北部にある干珠島(かんじゅしま)、満珠島(まんじゅしま)の二つの美しい島は宝珠ゆかりの島と伝えている。平家一門が最期を遂げた壇之浦を指呼の間に見る長府(下関市)から彦島にかけて、「平家落人(おちゅうど)」に関する哀話や伝説が多く残る。『吾妻鏡(あづまかがみ)』には「先帝(安徳(あんとく)帝)つひに浮ばしめたまはず」とあるが、下関市の赤間神宮社地に「安徳天皇阿弥陀寺陵(あみだじりょう)」が存在する。この陵に納められた遺体は、漁師の網にかかったものと伝承されている。平家武将たちのしかばねを集めたという平家七盛塚も同神宮の一隅にある。
周防・長門2国を支配した大内義隆は家臣の陶晴賢(すえはるかた)に謀られて自刃したが、陶軍が攻め込んだとき、義隆は能『田村』を楽しんでいた。大内氏滅亡後、居宅だった築山館(つきやまのやかた)跡でこの曲を謡うと、庭園の古井戸から白馬に乗った装束姿の武士が現れると伝えられ、いまでも山口ではこの曲を謡うことを禁じている。現在の山陽小野田市には昔、「寝太郎」という怠け者がいた。その寝太郎があるときにわかに働きだし、厚狭川に堰(せき)をつくって湿地の千町ヶ原を美田にかえ、大長者になったといい、寝太郎権現(ごんげん)、寝太郎稲荷(いなり)に祀(まつ)られている。
[武田静澄]
『『山口県文化史』(1963・山口県)』▽『山口県編・刊『山口県政史』上下(1971)』▽『三坂圭治著『山口県の歴史』(1971・山川出版社)』▽『宮本常一・財前司一著『日本の民俗35 山口』(1974・第一法規出版)』▽『松岡利夫・古川薫著『山口の伝説』(1979・角川書店)』▽『『日本歴史地名大系36 山口県の地名』(1980・平凡社)』▽『『山口県百科事典』(1982・大和書房)』▽『小野忠凞著『山口県の考古学』(1985・吉川弘文館)』▽『『角川日本地名大辞典35 山口県』(1988・角川書店)』▽『川村博忠・小杉健三監修『山口県の地理』(1994・山口県刊行物普及協会)』▽『八木充責任編集『図説山口県の歴史』(1998・河出書房新社)』▽『山口県歴史散歩編修委員会編『山口県の歴史散歩』(2006・山川出版社)』

山口県章

錦帯橋

青海島の海食景観

秋吉台

秋芳洞「百枚皿」

長門峡

綾羅木郷遺跡公園

柳井茶臼山古墳

松下村塾

関門橋

瑠璃光寺五重塔

功山寺

住吉神社〈下関市〉

閼伽井坊塔婆

旧厚狭毛利家萩屋敷長屋
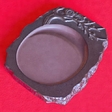
赤間硯

萩焼

山口県位置図
山口県のほぼ中央に位置する県庁所在都市。椹野(ふしの)川流域とその河口の山口湾(小郡(おごおり)湾)沿岸の平野部、および北部の佐波(さば)川の中・上流域、最北部の阿武(あぶ)川の中・上流域などからなり、北は島根県に接する。1889年(明治22)山口町として県庁所在地となったが、その後長く産業の近代化に立ち後れ、1929年(昭和4)吉敷(よしき)村と合併してようやく市制施行(当時の人口3万3522)、県都としては埼玉県の浦和(現、さいたま市)とともに全国でもっとも遅かった。1941年宮野村、1944年平川、大歳(おおとし)、陶(すえ)、名田島(なたじま)、嘉川(かがわ)、佐山、秋穂二島(あいおふたじま)の7村と阿知須(あじす)、小郡の2町を編入したが、1947年阿知須地区、1949年小郡地区は分離独立、1956年鋳銭司(すぜんじ)村、1963年大内(おおうち)町を編入。2005年(平成17)徳地(とくぢ)、秋穂(あいお)の2町と、かつて山口市に含まれ、のちに分離した阿知須、小郡の2町とをふたたび合併し、2010年には阿武郡阿東町(あとうちょう)を編入。市域は1023.23平方キロメートルと県下第1位であるが、農村地帯を広く含む。人口19万3966(2020)。
JR山陽本線・山陽新幹線新山口駅(旧、小郡駅)が市の玄関にあたり、ここからJR山口線や宇部(うべ)線が分岐している。また山口盆地の南縁を中国自動車道が貫通し、これに山陽自動車道が結び付いて山口ジャンクションとなり、市内には小郡、山口、徳地、山口南のインターチェンジがある。沿岸部を国道2号と190号が走り、その西側には山口宇部道路も走る。陰陽連絡路の国道9号と262号、376号、435号が山口盆地で交差し、県都に集まるバス交通網はよく発達している。市の北東山間部には315号、489号が走る。
[三浦 肇]
市域の中北部には中国山地西端にあたる物見ヶ岳(746メートル)や西鳳翩(にしほうべん)山(742メートル)などがそびえるが、その南東側は低く、北東方向の構造線に沿って沈降した宮野盆地や山口盆地、大内盆地が高度10~60メートルの地溝性の埋積盆地を形成し、ここを流域とする椹野川は南西流して周防灘(すおうなだ)に入る。その河口は深く湾入して三角江をなし、その両岸の名田島、江崎、深溝(ふかみぞ)の低地には江戸時代に造成された干拓平野が広がっている。北東から南西に大きく広がる市域の気候は沿岸と内陸の盆地では対照的で、穏やかな瀬戸内式気候の沿岸からわずか十数キロメートル入った山口盆地では気温較差が大きく、霜日数や霧日数が多く、典型的な盆地性気候を示す。とくに北東―南西の海陸風が年200日以上も出現し、地理的に特徴ある地方風が認められる。また、北部の山間部は多雪、高冷地である。
[三浦 肇]
縄文後・晩期の遺跡として知られるのは山口扇状地や仁保(にほ)川の段丘、秋穂半島の美濃ヶ浜(みのがはま)などで、発見例は少ない。山口盆地周辺の山麓(ろく)帯には弥生(やよい)・古墳期の遺跡が多く、とくに朝田墳墓群(あさだふんぼぐん)(国指定史跡)は弥生期から古墳期にかけての大規模な埋葬遺跡群、集落址(し)群として西日本における代表的遺跡である。さらに盆地床一帯は河畔の氾濫(はんらん)原を除いて、500町以上に及ぶ古代条里制の遺構が広く分布し、その開発の早いことをうかがわせ、ほぼ市域に相当する古代吉敷郡には八田(やた)、宇努(うの)、仲河(なかがわ)、浮囚(ふしう)など10郷が『和名抄(わみょうしょう)』に記されている。室町時代には対明(みん)貿易で栄えた守護大名大内氏の城下町(正確には屋形(やかた)町)として、京都に模した町がつくられ、戸数1万(宣教師報告)を数え、東の小田原(おだわら)と並ぶ中世都市として発展した。また小郡地域の津市(ついち)は河口港で、山口の外港として発達した。近世には地方的商業町にすぎなかったが、幕末毛利(もうり)氏が藩庁を萩(はぎ)からここに移し、明治以降は県政の中心都市として行政、教育、文化的諸施設の集中をみた。
[三浦 肇]
工業化のほとんど進んでいない山口盆地や沿岸の平野部は県下最大の穀倉地帯で、市の農地は9000ヘクタール(2017)に及ぶ。また山口盆地ではイチゴ、ブドウ、南部の名田島、深溝などの干拓地ではタマネギ、トマト、秋穂や嘉川、佐山の台地ではダイコン、キャベツを主とする近郊園芸農業が、北部の阿東地区では米作、果樹栽培、肉牛(阿東牛)の飼育など盛ん。秋穂や阿知須では漁業も盛んで、クルマエビの養殖も行われている。商業活動は、卸売業は弱く、小売業、飲食店が中心で、県中央部に比較的まとまった買物圏を形成し、中心商店街は旧石州街道に沿う市場町に起源をもつ大市、中市、米屋(こめや)町、道場門前と並ぶ単線型の一筋町を形づくっている。工業では、県内の臨海工業都市に比べるときわめて弱体であった。そのため、山口テクノパーク、山口物流産業団地、小郡インター流通団地などがつくられ、工業の発展が図られている。
[三浦 肇]
「大内氏遺跡、附凌雲寺(りょううんじ)跡」(国指定史跡)、瑠璃光(るりこう)寺五重塔(国宝)、常栄(じょうえい)寺庭園(国指定史跡・名勝)をはじめ大内氏ゆかりの史跡に富む。八坂神社本殿、古熊(ふるくま)神社本殿・拝殿、洞春(とうしゅん)寺観音(かんのん)堂・山門、今八幡(いまはちまん)宮本殿・拝殿・楼門、龍福寺本堂など室町時代の建築物や、山口県旧県庁舎および県会議事堂は国重要文化財に指定されている。また萩藩主毛利家墓所、大村益次郎(ますじろう)墓(ともに国指定史跡)など明治維新時の史跡も多い。日本に初めてキリスト教を伝えたザビエルを記念するサビエル記念聖堂もある。1952年完成の旧聖堂は1991年(平成3)焼失したが、信者や一般市民らの寄付により1998年に新聖堂が再建された。祇園(ぎおん)祭の鷺舞(さぎまい)や七夕提灯(たなばたちょうちん)祭りなどの歴史的祭事もある。市街地南西の湯田温泉(ゆだおんせん)は山陽路随一の湯量を誇り、秋吉(あきよし)台や萩城下町観光の基地となっている。椹野川の河畔は国指定天然記念物ゲンジボタル発生地で有名。阿武川の中流、阿東地区から萩市にかけての渓谷は、長門峡(ちょうもんきょう)とよばれる景勝地で、国の名勝となっている。なお、山口駅前から早間田(はやまだ)交差点を経て県庁前に至るパークロード沿いにはカエデやケヤキの並木が続き、地方合同庁舎、県立美術館、児童公園、県立図書館、博物館、15階建ての県庁舎などがある。吉敷(よしき)地区には維新百年記念公園と陸上競技場があり、平川地区には国立山口大学の7学部(吉田キャンパス)がある。そのほか、秋穂地域の秋穂正八幡宮(しょうはちまんぐう)の社殿、徳地地域の月輪(がちりん)寺薬師堂が国の重要文化財に指定されている。
[三浦 肇]
『『山口市史』(1982・山口市)』
長野県南西部、木曽郡(きそぐん)にあった旧村名(山口村(むら))。現在は岐阜県中津川市東部を占める地域。1958年(昭和33)長野県西筑摩郡(にしちくまぐん)神坂村(みさかむら)が中津川市に編入した際、馬籠(まごめ)、峠、荒町(あらまち)の3地区は山口村に編入。山口村は生活圏としては中津川市に属していたため、2005年(平成17)長野県から岐阜県中津川市に越県編入した。旧村域は木曽谷の南端にあり、国道19号(中山道(なかせんどう))が通じ、JR中央本線中津川駅からバス便で結ばれている。気候は温暖で、太い竹の林や茶畑があり、木曽川左岸の傾斜地は水田化している。旧中山道に沿う馬籠は近世の木曽十一宿の馬籠宿で、島崎藤村の出身地として知られる。藤村記念館、島崎家の墓所永昌(えいしょう)寺、清水屋資料館、馬籠脇本陣史料館、東山魁夷(かいい)のリトグラフなどを展示する東山魁夷心の旅路館などがある。
[小林寛義]
『『山口村誌』全2巻(1995・山口村)』
基本情報
面積=6113.95km2(全国23位)
人口(2010)=145万1338人(全国25位)
人口密度(2010)=237.4人/km2(全国28位)
市町村(2011.10)=13市6町0村
県庁所在地=山口市(人口=19万6628人)
県花=ナツミカン
県木=マカマツ
県鳥=ナベヅル
中国地方の最西部を占め,北は日本海,西は響灘,南は瀬戸内海に臨む県。
山口県はかつての周防,長門の2国に当たり,幕末には長州藩(山口藩)とその支藩である徳山藩,岩国藩,清末藩,長府藩(1869年豊浦(とよら)藩と改称)の5藩があった。1871年(明治4)6月徳山藩は山口藩と合併し,同年7月の廃藩置県の実施により山口,岩国,清末,豊浦の4藩はそれぞれ同名の県となった。つづく同年11月の府県統廃合によって4藩は統合され,現在の県域が確定した。
先縄文時代の遺跡はあまり多いとはいえないが,たとえば美濃ガ浜遺跡(山口市)で縄文時代の遺構,古墳時代の集落に伴う土器製塩址,それに中期の兜山古墳群などとともに,旧石器の包含層が知られている。
岩田遺跡(熊毛郡平生町)は縄文時代中期~弥生時代の集落址で,ことに晩期のどんぐり類を収納した貯蔵穴群や甕棺墓群など初期農耕の問題にかかわる遺跡としても重要である。島田川流域遺跡群は県東部を流れる島田川流域に分布するが,なかでも天王,岡山,石光の3遺跡(周南市)など弥生時代の高地性集落址が有名。綾羅木郷(あやらぎごう)遺跡(下関市)はおびただしい弥生前期土器や石器を伴って,多数の袋状竪穴群や溝状遺構が検出され,アズキその他の植物遺存体と,珍しい陶塤(とうけん)が出土したことでも知られる。中ノ浜遺跡(下関市)は弥生時代前期~中期初頭の埋葬遺跡。前期前半には土壙墓,前期中葉から末葉には配石墓,前期後半から中期初頭には箱式石棺墓がそれぞれ盛行し,甕棺墓や集骨葬もある。副葬品には細形銅剣,銅戈(どうか)などがある。梶栗浜(かじくりはま)遺跡(下関市)も弥生時代前期末~中期初頭の埋葬遺跡。組合せ箱式石棺が主で,その上に積石や列石を伴う。副葬品には朝鮮半島からの舶載と思われる多鈕細文(たちゆうさいもん)鏡と細形銅剣,それに碧玉製管玉などがある。土井ヶ浜遺跡(下関市)は,これまでに200余体の人骨が出土したこともあって,こうした弥生時代の埋葬遺跡としては最も著名であろう。被葬者の成人男性人骨の身長が縄文人より高く,朝鮮半島南部の住民に近いことが注目されている。東向きの仰臥屈葬や伸展葬で抜歯例も多い。副葬品には弥生土器のほか玉類や貝釧(かいくしろ),指輪などがある。
竹島古墳(周南市)は古墳時代前期の前方後円墳。舶載の四神四獣鏡や銅鏃などが出土している。白鳥(しらとり)古墳(平生町)は県下最大の前方後円墳で全長125m。埴輪列をもち,神獣鏡や巴形銅器などを副葬する5世紀前半ごろの古墳である。長光寺山古墳(山陽小野田市)は全長約62mの前方後円墳で二つの竪穴式石室をもつ。三角縁神獣鏡などの副葬品がある。赤妻古墳(山口市)は高さ約6mの円墳で,かつて墳頂から箱形石棺2,刳抜式舟形石棺1が出土している。各種鏡,玉類などの副葬品がある。見島(みしま)古墳群(萩市)はジーコンボ古墳群とも呼ばれ,約200基の後期の積石塚古墳からなる。柳井茶臼山古墳(柳井市。茶臼山古墳)からは仿製(ぼうせい)の鼉竜(だりゆう)鏡が出土している。
石城山神籠石(いわきさんこうごいし)(光市)は7世紀ごろの朝鮮式山城。土塁がめぐらされ,門址,水門をもつ(山城)。周防国衙址(防府市)は,方2町の古代地方政庁。周防鋳銭司址(山口市)は平安時代の官営鋳銭所の跡で,工房址,井戸址などの遺構,鋳損じの銭貨,緑釉陶器,木簡等々の遺物が出土した。
→周防国 →長門国
執筆者:坂本 一登
本州の最西端に位置し,中国山地の西部を占める山口県は,あまり高い山も広い平野もない低山性の半島県である。北は日本海に面して大陸に近く,南は瀬戸内海をひかえ,関門海峡を隔てて,古代文化の先進地北九州と相対しており,早くから大陸・九州と中央とを結ぶ交通上の要衝であった。弥生時代人骨を出土した土井ヶ浜遺跡,西日本最大級の弥生時代集落址として有名な綾羅木郷(あやらぎごう)遺跡の存在も,この地域の文化が先進的であったことを示している。《日本書紀》に見える仲哀天皇の穴門豊浦(あなととよら)宮は,大和朝廷による九州経略の基地となったところで,下関市長府の忌宮(いみのみや)神社境内がその故地と伝えられている。さらに古代の終焉を告げた源平最後の壇ノ浦合戦の舞台となったのも,下関市の関門海峡であった。室町時代には,山口盆地に本拠をもつ大内氏が朝鮮や中国との貿易によって経済的基盤を築き,中央へも進出したが,この大内氏の繁栄も,防長両国の地理的条件に負うところが大きい。近世になって防長2国を領有した毛利氏は瀬戸内海沿岸の浅海を干拓して農地を開発し,米,塩の増産をすすめ,また内海航路の発達に伴って,赤間関(あかまがせき),三田尻,室積(むろづみ),上関(かみのせき),柳井などの港町が開け,なかでも赤間関(現在の下関)は長崎とともに西日本屈指の商港として繁栄した。
明治以降,山陽本線の下関までの開通(1901)によって,大陸への西日本の門戸としての地域性を強め,また北九州工業地帯の延長として,下関をはじめ内海沿岸各地に,重化学工業の展開をみた。さらに関門鉄道トンネル(1942)につづいて,第2次大戦後,関門国道トンネル(1958),中国自動車道の関門橋(1973),山陽新幹線の新関門トンネル(1975)が次々に完成して,九州と結ばれ,東西の文化・経済交流の地として発展している。
山口県は中国山地の西部にあたる低山性・丘陵性の地形が大部分を占め,海岸線も沈水性のところが多い。平野も狭小であるが,農業は内海沿岸部の岩国,柳井,下松(くだまつ),防府(ほうふ)などの小三角州や干拓地,内陸の玖珂(くが),鹿野(かの),徳佐,山口など多くの小盆地において,稲作が卓越し,山間地のすみずみまで農業土地利用がゆきとどいている。近郊農業では下関市や宇部市周辺の台地における花卉,野菜の栽培が盛んで,屋代(やしろ)島(周防大島)は山口ミカン,萩市付近はナツミカンの特産地として知られている。全県の農家数は6万3000戸(1995),耕地面積は4万5700ha(1995)で,10年前に比べるとそれぞれ16%程度減少しており,全国傾向と同じように停滞的である。米の生産は19万1700t(1994)で,農業粗生産額の50%を占め,首位である。畜産が乳牛,養鶏を中心に近年伸びてきたものの,まだ農業全体の1/5を占めるにすぎない。林業は私有林が80%を占め,農家の副業としての性質が強く,その経営も零細である。滑山(なめらやま)国有林のアカマツ,錦川上流や阿武川中流のヒノキ,杉やシイタケ,ワサビが知られている。
三面海をめぐらし,出入りに富む沈水海岸の発達した山口県は,沿岸に多くの漁村が分布する。日本海沿岸は対馬海流に洗われ,漁場条件に恵まれているため,古くから海女漁業や長州藩鯨組の捕鯨業で知られたところで,萩と仙崎(長門市)の漁港を中心としている。一方,瀬戸内海側の漁業は日本海側に比べて兼業が多く,著しく零細なうえ,重化学工業の発展に伴って漁場が狭まったことなどにより,漁獲量は日本海側の1/4(2万3000t。1994)にすぎない。沿岸漁業は年々不振となり,養殖漁業の振興がはかられ,クルマエビやハマチ,タイなどの養殖が秋穂(あいお),仙崎,大島などで行われている。
山口県を代表する重要な漁港は下関で,全県の漁獲量の1/4はここに水揚げされる。明治以降朝鮮近海に山口県漁民が多く出漁したが,下関漁港はその水揚港として急速に発達した。さらに昭和に入ってからも,捕鯨船や底引網,巻網漁船の基地となり,西日本における重要な水産物の流通拠点となってきた。しかし近年では漁場の遠隔化などが原因となって,市場への水揚量は減少傾向にあり,1994年の2.8万tは5年前の1/2である。かつては西日本随一の規模をほこった下関漁港も,長崎や福岡,境港に比べてその地位はかなり低下している。
山口県の工業は,すでに近世から各地に織物や醸造,陶業などがあり,明治初期にも民間では日本最初のセメントや化学の近代工業が起こっている。県の産業構造が本格的に工業化へ進展したのは,干拓地の多かった内海沿岸に臨海工業が立地した大正期からで,第1次大戦を契機として,下関に造船や金属精錬,宇部・小野田に鉄工,セメント,火薬,製薬,徳山・下松にソーダ,造船,鉄板の諸工場が設置された。さらに昭和に入ってから,海底炭田の開発で知られた宇部・小野田にソーダ,耐火煉瓦,化学,防府に紡績,ゴム,徳山・下松に石油,鋼板,セメント,岩国に人絹,紡績,パルプ,石油など各種の工場が進出した。山口県は瀬戸内工業地域の一中心として急速に発展し,工業生産額も広島・岡山両県をしのぐに至った。第2次大戦後は岩国,徳山,光の旧軍用地に鉄鋼や薬品,石油精製および石油化学の大工場が建設され,とくに全国的にも重要な石油化学コンビナートが形成されている。
山口県工業の特色は,ソーダ,肥料,薬品などの化学工業,石油精製と石油関連工業,鉄鋼業の3業種による出荷額(1994)が全体の約49%を占め,基幹資源型工業が中心となっていることである。これらの多くが臨海の装置型工業であるため,関連産業が少なく,したがって地域への波及効果が低い体質をもっている。工業の分布は地域的に偏り,内海沿岸に全県の事業所の60%(1994),出荷額の93%が集中し,なかでも徳山市,新南陽市(ともに現,周南市),下松市,光市を含む周南地区が,事業所数は15%であるが,出荷額では39%を占めている。近年,宇部・小野田地区の埋立地に新しく石油化学工業,防府地区の塩田跡地に自動車工業が進出し,下関市長府の海岸埋立地にも新工業団地が形成されつつある。
山陽と山陰の変化に富む海岸線をあわせもつ山口県は,多島海の風光にすぐれた内海沿岸の主要部が瀬戸内海国立公園に含まれ,日本海側の須佐湾から青海(おうみ)島・油谷半島まで海食景観の卓越する沿岸や島嶼が,北長門海岸国定公園となっている。また深山と高原の魅力をもつ県境の寂地山は西中国山地国定公園の一部をなし,日本で最も広い石灰岩台地の秋吉台は日本最大級の鍾乳洞と特異なカルスト景観をもつ国定公園として有名である。これら多彩な自然景観とともに,歴史的・文化的観光資源も多く,とくに中世の大内氏の遺跡と明治維新期の史跡にすぐれたものがある。山口市の瑠璃光寺五重塔や常栄寺の雪舟庭園などは大内文化を代表するもので,市内湯田温泉を宿泊基地として,山口市と秋吉台,萩市,島根県津和野町を結ぶ巡回型観光ルートが形成されている。萩市は近世毛利氏の城下町景観をよく保存し,松下村(しようかそん)塾や萩城跡,伊藤博文旧宅など明治維新期の史跡の多い町である。茶器として全国に知られる萩焼は,萩藩御用窯の伝統を伝えるすぐれた陶芸で,多くの窯元があって,近年は食器,花器,置物など多種の製品がつくられ,山陰の城下町にふさわしい観光産業となっている。県の東端岩国市にある錦帯橋は錦川に架けられたアーチ型5連の木橋で,江戸時代から日本三奇橋の一つとして知られた貴重な文化財であり,錦川の鵜飼いとともに多くの観光客をよんでいる。一方,山口県西端の下関市の関門橋は関門海峡をまたぐ全長1068mの自動車道路橋で,直下の関門国道トンネルや火ノ山公園とともにユニークな観光地となっている。
山口県はその自然条件とそれぞれの地方小都市の生活圏の広がりから,次の4地域に区分される。
(1)県央 県の中央部を占め,面積で37%,人口で38%を有する。山口,防府,周南,下松,光の5市からなる。山口盆地や防府平野,下松平野は古代条里制の遺構が県内で最も広く残っており,開発の古い地方で,現在も県下の重要な稲作地域をほとんど含み,米生産量の40%を占め,県内の水田農業の中心をなす。防府市は周防国府の置かれたところであり,内陸盆地の山口市は中世大内氏の城下町として栄え,近世には衰えたが,明治以降は県庁所在地となって,県の行政・文教の中心として発展してきた。周防灘沿岸には石油化学コンビナートに鉄鋼業や自動車工業も加わって,県工業生産のほぼ半ばをあげている周南5都市があり,重化学工業に特色をもつ県の工業の中核的存在となっている。
(2)県東 県の東部を占め,周東とも呼ばれる地方で,面積で21%,人口で17%を有する。岩国市,柳井市と周辺の町を含む。北半の西中国山地,内陸中央の玖珂盆地と丘陵地帯,南半の周防大島や熊毛半島など地形的に複雑な構成をもち,岩国平野,柳井平野,玖珂盆地のほかは平地に乏しい地方である。岩国市は周防国東端の錦川河口に位置する吉川(きつかわ)氏の城下町として起こり,近世に開発された広い干拓地に,大正以降紡績,パルプなどの大工場が進出し,第2次大戦後いち早く石油化学コンビナートが成立し,工業都市として発達した。アメリカ軍岩国基地をもつ基地の町でもある。屋代島をかかえた柳井市は海陸交通の要地を占め,近世以来製塩と柳井縞で知られた商都として栄えた。近年塩田跡地を利用して工業化が進んでいる。沿岸島嶼は明治以降多くの海外移民を送り出したが,現在は山口ミカンの主産地となっている。
(3)県西 県西部を占め,面積23%,人口38%を有する。下関,宇部,山陽小野田,美祢(みね)の4市からなる。全般に丘陵性の地形で,厚東(ことう)川,厚狭(あさ)川,木屋(こや)川,綾羅木川の河川に小三角州平野と干拓地が発達し,内陸にも船木,厚狭,田部,豊田など小盆地が多い。西部を占める下関市は県内一の都市で,古代から海関として重視された。明治以降,化学,金属,機械の諸工業が起こり,大陸貿易や近海漁業の基地となって,水産商工都市として発達した。宇部市,山陽小野田市はともに海底炭田の開発に伴って一寒村から化学工業を中心とした新興工業都市に成長した。ここには山口宇部空港があって,県の空の玄関口となっている。内陸の美祢市も石灰石と無煙炭の開発によって都市化が始まった鉱業都市で,沿岸の宇部市と結びついて工業化が進んでいる。県西部地域は山陽本線・新幹線,山陰本線,中国自動車道の交通幹線がここに集まり,海底トンネルと高速道路橋で九州と結びつき,交通革命の進行するなかで,大きく変貌しつつある。
(4)県北 県北部を占め,面積19%,人口7%を有する。萩市,長門市と周辺の町からなる。山陰側の日本海に臨む地方で,人口密度が低く,開発の遅れた農漁業地域である。この地方の中心都市萩市は,近世に毛利氏36万石の城下町として発達したが,明治以降は停滞的で工業化も進まず,山陰の水産商業都市にとどまっている。萩は明治維新期の史跡に富む城下町景観をよく保存している観光都市として,全国的に知られている。
執筆者:三浦 肇
山口県のほぼ中央部に位置する県庁所在都市。2005年10月旧山口市と秋穂(あいお),阿知須(あじす),小郡(おごおり),徳地(とくじ)の4町が合体して成立し,10年1月阿東(あとう)町を編入した。人口19万6628(2010)。
山口市南端の旧町。周防灘に面する。旧吉敷(よしき)郡所属。人口7941(2000)。町域は半島状をなし,東は大海(おおみ)湾,西は秋穂湾に臨む。中央を南北に山地が走るため町域は二分されている。東側は中世以来長講堂領であった秋穂二島荘に属し,近世には盛んに干拓が行われた地域で穀倉地帯となっている。ミカン,タマネギ,キャベツの栽培が盛んで,ヒューム管,コンクリート製品の製造工場もあり,周防灘沿岸部の山では花コウ岩の採掘が行われている。クルマエビの養殖が盛んで,大海湾には大規模な養殖場が多い。また秋穂湾の塩田跡地には内海栽培漁業センターがあり,養殖・放流用として稚魚を供給している。西部の天田は大村益次郎の生地で屋敷跡に生誕碑がある。
執筆者:清水 康厚
山口市南西端の旧町。旧吉敷郡所属。人口8823(2000)。椹野(ふしの)川河口の山口湾西岸にあり,宇部台地の北東部を占める。町域の西半は低い丘陵地で,貝殻山に弥生中期の貝塚遺跡がある。中世末には白松庄,近世以後は井関村と称した。1940年阿知須町となり,一時山口市に合併したが,47年分離独立。国道190号,山口宇部有料道路,JR山陽本線,宇部線が通り,工業都市宇部の東隣にあって通勤者の多い地域である。広い台地ではダイコンの栽培が多く〈山口たくあん〉の産地として知られる。阿知須漁港は小型底引網・刺網・釣りの漁船が多く,遠浅の沖合ではノリ養殖が盛んである。西の丘陵地にはラドン含有量の多いラジウム温泉で泉温22℃の阿知須温泉があり,付近はミカン園や牧場として開発され,万年池一帯はゴルフ場となっている。
山口市北部の旧町。旧阿武郡所属。日本海に入る阿武川の上流部を占め,島根県津和野町に接する山間農村地域。1955年嘉年(かね),徳佐,地福,篠生(しのぶ),生雲(いくも)の5村が合体,改称,町制。人口7620(2005)。町役場所在地の徳佐は近世の石州街道に沿う市場町として発達した所で,国道9号,JR山口線が通り,阿武郡東部の中心をなした。県境の野坂火山群による堰塞(えんそく)湖盆だった徳佐盆地は県北部最大の稲作地域であり,果樹栽培や酪農も盛んで,鍋倉のリンゴや長門峡付近のナシは観光農業としても成功している。嘉年は阿武川の源流にある小盆地で県下で最も雪の多い所である。県境に秀麗な山容を見せる十種(とくさ)ヶ峰(989m)は長門の名峰として知られ,山口線に近い船平山とともに中国地方西端のスキー場として人気がある。阿武川中流に長門峡県立自然公園があり,紅葉の季節に観光客が多い。
執筆者:三浦 肇
山口市南西部の旧町。旧吉敷郡所属。人口2万3107(2000)。椹野川の河口付近の沖積平野を占める。古代~中世は東大寺領椹野荘に属し,早くから開発が進められた。中心の津市(ついち)は山陽道の宿場町で,近世は本陣,天下御物送場番所などが置かれ,小郡宰判の勘場(代官所)もあった。現在も山陽新幹線,JR山陽本線,山口線,宇部線,国道2号,9号線が通じ,中国自動車道小郡インターチェンジもある交通の要衝で,県都山口への西の玄関になっている。椹野川の下流部は古くから干拓が進み,米や野菜の栽培が行われる。弥生時代の中郷遺跡,百谷須恵器窯跡などがある。
山口市東部の旧町。旧佐波郡所属。人口8375(2000)。中国山地にあり,中央部を佐波川が南流する。この地方は鎌倉時代に東大寺再建のための造営用材の採取地に定められ,佐波川上流の山地から多くの用材を奈良へ送ったところで,現在も滑(なめら)国有林など杉,松,ヒノキの造林地が多く,山林が町域の大部分を占める。佐波川沿いでは,米作を中心に野菜や果樹栽培,酪農が行われ,特産にワサビ,シイタケ,ツクネイモ,マツタケがある。佐波川上流には多目的の佐波川ダム(大原湖)があり,1980年には南部に中国自動車道徳地インターチェンジが完成した。野谷石風呂,佐波川関水などの史跡があり,出雲神社には天然記念物のツルマンリョウ自生地がある。
執筆者:清水 康厚
山口市中南部の旧市で,県庁所在都市。1929年市制。人口14万0447(2000)。瀬戸内海に流入する椹野川の流域とその河口(山口湾)沿岸の平野部を占め,356.9km2に及ぶ県下最大の市域をもつが,水田農村地域を広く含み,人口は全国県庁所在都市の中で最少である。市域は椹野川上・中流の山口盆地を中心とした北部地区と山口湾岸の吉南(きちなん)平野を占める南部地区に分かれる。市街地は山口盆地の北東隅にあって,14世紀後半,大内氏が館を置いて京都を模した街をつくり,約200年間城下町として栄えた。その後,陶(すえ)氏,次いで毛利氏の支配下に置かれたが,近世には萩に毛利氏の本拠が移されたため,山口はさびれた。幕末の1863年(文久3)藩庁が萩から山口に移転して政治中心地として復活し,明治以降も県庁所在地となって発展してきたが,山陽新幹線の小郡駅(現,新山口駅)からJR山口線で約25分の内陸にあり,鉄道幹線から離れているため,近代産業の定着を見ず,行政・文教面の中心機能をもつにすぎない。中心の亀山周辺には,市役所から県庁に至るパークロード沿いに図書館,美術館,博物館,教育会館などの文教施設が並び,旧石州街道沿いの大市,中市,米屋町,道場門前が中心商店街を形成している。市街地の南西端,国道9号沿いの湯田温泉が秋吉台,萩,津和野などへの観光基地となっている。市内にはザビエル記念聖堂,瑠璃光(るりこう)寺五重塔(国宝),八坂神社,常栄寺の雪舟庭園など大内氏時代をしのぶ遺跡が多く,山口祇園祭や七夕ちょうちん祭は異色の夏祭として知られる。一の坂川のゲンジボタルは天然記念物である。市東部の大内に中国自動車道山口インターがあり,南部鋳銭司(すぜんじ)を山陽自動車道が通じる。また,市北部の仁保にはKDDの山口衛星通信所(現,KDDIの山口衛星通信センター)があり,さらに宇宙通信や日本国際通信も進出し,情報通信機能が集積しつつある。
市の南部地区は名田島(なたじま),江崎,深溝など近世に成立した干拓地が広く,タマネギ,イチゴ,トマトなどの栽培を中心とした近郊農業が盛んで,佐山の台地は山口沢庵用のダイコンの特産地である。周防鋳銭司址のある南東部の鋳銭司には住宅産業の新工場がある。
執筆者:三浦 肇
山口湾岸,山口盆地に縄文時代の遺跡が若干ある。弥生時代には各所に水田が開け,集落がつくられた。中世都市のつくられた一の坂川流域の扇状地でも弥生時代の土器類が発見されており,耕地と集落が存在したことは明らかである。盆地ではその後条里がつくられ,一の坂川流域も同川のはんらんで変形しているものの,その跡は現在も明らかで,大内氏が京都を模してつくったと伝える山口の町はこの条里遺構に規制された都市である。この地域は律令行政区画としては周防国吉敷郡宇努(うぬ)郷であったと見られ,現在も宇野の地名が残っている。山口の地名は円政寺(現,萩市)の1254年(建長6)の金鼓に刻まれたのが初見であるが,円政寺町の位置から考えて,この時には山への入口という一般名詞からかなりの広がりをもつ地名になっていたとも思われる。山口の町の中心部は石見国へ抜ける石州街道に面した大市,中市,米屋町で,大市と中市の境に直交する竪小路を約400m北上したところに大内氏の館(現,竜福寺)があり,その周辺および南部に家臣の居住区があった。大内氏の館から南西に約2km離れた所に湯田があり,湯治場として利用されていた。これらを核として中世都市山口は形成されており,大内氏家臣の居住区,商工業地区,湯治場,それに大内氏が勧請した今八幡宮,八坂神社,北野天神社,円政寺,平蓮寺,瑠璃光寺,国清寺などの社寺が町内と郊外に立ち並び,近世城下町の原型ともいうべき観を呈していた。
石州街道に接し,竪小路から峠越えで長門への道,盆地を貫く椹野川から港湾小郡,瀬戸内海への道,故地大内から峠越えで南下する周防国府への道が通じるという条件のもとで,大市,中市などが既にある程度形成されていたのではないかと思われることから,大内氏がこの地を本拠とした理由を想定することができる。また町に対する大内氏の支配は1459年(長禄3)の禁制が初見で,夜間の大路往来,辻相撲,路頭において女をとること,大内氏家臣やその被官が夜に湯田の湯へ入ることを禁止している。1486年(文明18)には薦僧(こもそう),放下(ほうか),猿引を山口およびその近在から追放し,職人でも武家被官でもない者や他国者の山口での止宿禁止,路上での夜の念仏の禁止,巡礼者の止宿期間の制限,異相不審の者への制止など,町への介入がきびしくなっていることがわかる。1551年(天文20)のフランシスコ・ザビエルの書簡によれば,山口は大市街で,みな材木の構家であり,戸数1万以上とあるので,この時の人口は5万~6万を数えたと思われるが,この年8月に陶(すえ)隆房ら大内氏重臣の反乱で大内義隆は自害し,山口の町は8日間にわたって焼けたという。大内氏を継いだ大内義長は,宣教師たちに大道寺の造営を認め,山口に南蛮寺が建立されたが,57年(弘治3)大内氏は毛利氏に滅ぼされ,同時にこの時戸数1万を数えたという山口はふたたび焼亡,中国地方の政治中心としての地位も失った。17世紀初頭の調査で,山口とその周辺をあわせて市屋敷数2702戸とかつての1万戸へはついに回復しなかった。
執筆者:木村 忠夫
大内氏の滅亡と戦乱によって町はほとんど焼失した。関ヶ原の敗戦後,防長両国に移封された毛利輝元が萩に築城したため,山口は大内氏時代の繁栄を失い,山間小盆地の町となり,街路も大内氏時代の6間幅から4間幅に狭まった。しかし長州藩が城下町と山陽道を結ぶ萩,山口,三田尻の間を参勤交代の通路(御成道)として重視したため,山口は交通の拠点として復活した。萩街道(御成道)と石州街道が通っていたため,藩は中市,道場門前に本陣を置き,竪小路に宿駅を設けて人馬継立てを行わせた。中河原と湯田には御茶屋(藩の公邸)があり,藩主の休泊所となっていた。長州藩は激動する内外の情勢に備えるため,1863年(文久3)藩庁を山口へ移し,64年(元治1)上宇野令の亀山北方を新藩庁の地と定めて築造に着手した。築造工事は第1次幕長戦争(長州征伐)に敗れたために中断したが,66年(慶応2)藩庁新館が完成した。1863年以後,山口は藩政の中心地となり,明治維新と深いかかわりをもつこととなった。
1813年(文化10)長州藩は上田鳳陽を儒役に任じ,中河原の御茶屋(公邸)の前に山口講堂を設置して山口在住諸士の教育を開始した。45年(弘化2)同所は山口講習堂と改称し,萩明倫館,三田尻越氏塾に次ぐ学問所となった。60年(万延1)山口講習堂は萩明倫館の直轄となり,翌年中河原から亀山の東麓に移転し,重要な藩の人材養成機関となった。63年藩庁の山口移転後,山口講習堂は山口明倫館と改称し,文学寮と兵学寮をもつ藩校となった。1862年に帰国した村田蔵六(大村益次郎)は兵学寮の教授となり,西洋兵学を教えて優秀な士官を養成した。70年(明治3)山口明倫館は山口中学校と改称し,山口県近代教育の母体となった。
執筆者:小川 国治
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
宝永三年(一七〇六)の小県郡房山村指出帳(上田藩村明細帳)には「枝郷山口村」と記されている。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
出典 日外アソシエーツ「事典・日本の観光資源」事典・日本の観光資源について 情報
字通「山」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…群馬県北西部,吾妻(あがつま)郡中之条町の北部にある温泉。四万川上流部の渓谷に臨む,温泉口,山口,新湯(あらゆ),日向見(ひなたみ)の4温泉の総称で,四万温泉郷とも呼ばれる。開湯の歴史は古く,源頼光の四天王の一人碓井貞光の発見とか,坂上田村麻呂が奥羽征討のおり湯宿を設けたとかいわれ,伊香保,草津とともに北関東の名湯として知られた。…
…東西を急峻な山地に囲まれ,中央を北流する只見川上流の伊南(いな)川流域に集落が点在する。中心集落の山口は,只見や田島から奥会津へ向かう沼田街道と田島街道(国道289号線)の分岐点として発達した。就業人口の30%が農林業に従事するが,村域の大部分は山地で国有林が多く,耕地は伊南川沿岸に限られ,しかも冬季の積雪量が170cmにも及ぶため農業条件は厳しいが,生食用の〈南郷トマト〉は首都圏にも出荷されている。…
※「山口」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...