大島〔愛媛県八幡浜市〕
愛媛県八幡浜市南端の頃時鼻(ころどきばな)の西方約3.5キロメートルに位置する宇和海諸島の島。面積約0.75平方キロメートル。南側の三王島(さんのうしま)、地王島(じのおおしま)とは橋で結ばれている。これらと周辺の属島、粟ノ小島、貝付小島をあわせた5島を総称して「大島」ということもある。ハモやウニ、アワビなどの漁業、ミカン栽培などの農業が行われる。島南西部では“地震の化石”の異名を持つシュードタキライト(国指定天然記念物)が観察できる。
大島〔和歌山県〕
和歌山県東牟婁郡串本町、潮崎の東に位置し、熊野灘に面する有人島。面積約9.68平方キロメートル。明治時代にトルコの軍艦エルトゥールル号がこの島の樫野埼沖で悪天候のため遭難・大破し600名近い犠牲者が出たが、この際島民が生き残りの遭難者たちを献身的に救出・介護したことで知られる。1999年開通の「くしもと大橋」により本土と陸続きになった。
大島〔愛媛県新居浜市〕
愛媛県新居浜市(にいはまし)、黒島港の沖約2キロメートルに位置する島。「新居大島」ともいう。面積約2.14平方キロメートル。伊予水軍の頭領であった村上義弘の出身地とされ、島内には水軍関係の史跡が多い。島に伝わる伝統行事の「とうどおくり」は市の無形民俗文化財に指定されている。
大島〔長崎県壱岐市〕
長崎県壱岐市、壱岐島の南西、郷ノ浦港の西沖約3キロメートルに位置する島。面積約1.17平方キロメートル。近接する原島(はるしま)、長島とあわせ、“渡良三島(わたらみしま)”と呼ばれる。3島のうち最北に位置し、南側にある長島との間は珊瑚大橋で結ばれる。北部に海水浴場がある。
大島〔長崎県小値賀町〕
長崎県北松浦郡小値賀町(おぢかちょう)、五島列島の北にある平戸諸島の島。小値賀島の南西約3.5キロメートルに位置する。面積約0.71平方キロメートル。近接する宇々島に生活困窮者世帯を3年を限度に移住させ、生活を再建させる独特の風習が昭和時代まで続いていた。
大島〔愛媛県今治市〕
愛媛県今治市、今治港の北東約5キロメートルに位置する。「越智大島」とも呼ばれる。面積約41.97平方キロメートル。北東の鵜島との間にある能島は能島村上水軍の本拠地で、城跡が残る。標高230メートルの亀老(きろう)山からは瀬戸内海の眺望が楽しめる。
大島〔長崎県西海市〕
長崎県西海市、太田和郷の西沖約2キロメートルに位置する島。寺島を経由し、呼子ノ瀬戸を跨ぐ大島大橋で本土と結ばれている。面積約12.15平方キロメートル。昭和初期には炭鉱で栄えたが、1970年代に閉山。その後、企業誘致により造船所ができた。
大島〔宮城県〕
宮城県気仙沼市、気仙沼湾内にある東北地方最大の有人離島。「気仙沼大島」「陸前大島」ともいう。面積約9.05平方キロメートル。屈曲した海岸線による自然景観が美しく、北部には海抜235メートルの亀山がある。三陸復興国立公園に指定されている。
大島〔大分県〕
大分県佐伯市、鶴見半島の先端から北へ約0.6キロメートルに位置する豊後諸島の島。面積約1.63平方キロメートル。江戸時代には佐伯藩が往来する船を監視するための御番所が置かれた。サバ、アジ、ブリなどの好漁場として知られる。
大島〔香川県〕
香川県高松市、屋島湾の庵冶(あじ)港の北西約2.5キロメートルに位置する島。面積約0.73平方キロメートル。屋島の合戦に敗れた平家方の墓に植えられた樹齢800年の「墓標の松」、国立ハンセン病療養所「大島青松園」がある。
大島〔北海道〕
北海道松前郡松前町の西方約56kmに位置する無人島。「渡島(おしま)大島」ともいう。面積約9.7km2で、無人島としては日本最大。かつてはオオミズナギドリの繁殖地として知られた。
大島〔宮崎県〕
宮崎県日南市、目井津漁港の南東約3キロメートルに位置する南那珂群島の島。面積約2.08平方キロメートル。幕末までは飫肥(おび)藩の馬牧場。島南部にある鞍埼(くらさき)灯台は日本初のコンクリート製灯台。
大島〔千葉県〕
千葉県いすみ市の釣師海岸沖にある無人島。2009年に政府の総合海洋政策本部が策定した「海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針」に基づき、名称付与された離島のひとつ。
大島〔茨城県〕
茨城県日立市河原子町沖にある無人島。2009年に政府の総合海洋政策本部が策定した「海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針」に基づき、名称付与された離島のひとつ。
大島〔長崎県佐世保市〕
長崎県佐世保市南部、大村湾にある島。面積約0.4平方キロメートル。本土とは江上大島橋で結ばれる。大正時代には煉瓦の製造工場があった。島南部にはサン・レモ リハビリ病院がある。
大島〔高知県〕
高知県宿毛市、宿毛湾にある島。本土の片島地区と、ごく短い橋で結ばれている。面積約1.02平方キロメートル。威陽島を見下ろす高台に、温泉つきの国民宿舎がある。
大島〔三重県紀北町〕
三重県北牟婁郡紀北町の長島港の南東、熊野灘にある無人島。暖地性植物が多く自生。島の南部に、長島大島灯台がある。
大島〔徳島県〕
徳島県海部郡牟岐(むぎ)町、牟岐港の南東約6.3kmに位置する無人島。磯釣りやダイビングの名所として知られる。
大島〔岡山県〕
岡山県笠岡市、笠岡諸島の真鍋島の北約2kmに位置する無人島。先大島、前大島の2島が砂州で結ばれ1島をなす。
大島〔青森県〕
青森県夏泊半島北端の夏泊崎の北方約200mに位置する無人島。陸奥大島灯台がある。
大島〔三重県志摩市〕
三重県志摩市の熊野灘にある無人島。「和具大島」ともいう。ハマユウの群生地がある。
大島〔岩手県〕
岩手県下閉伊郡、船越半島付近に位置する花崗岩の島。「船越の大島」ともいう。
大島〔兵庫県〕
兵庫県美方郡新温泉町、三尾地区北に位置する無人島。「三尾大島」ともいう。
大島〔熊本県〕
熊本県天草市、黒島の西約4kmに位置する無人島。牛深大島灯台がある。
大島〔山口県〕
山口県長門市、青海島の東約0.5kmに位置する無人島。
大島〔石川県〕
出典 小学館デジタル大辞泉プラスについて 情報
Sponserd by 

 東京都、伊豆諸島中最大の火山島。大島支庁に属する。中央に三原山がある。昭和61年(1986)に大噴火し、全島民が島外に避難した。面積91平方キロメートル。伊豆大島。
東京都、伊豆諸島中最大の火山島。大島支庁に属する。中央に三原山がある。昭和61年(1986)に大噴火し、全島民が島外に避難した。面積91平方キロメートル。伊豆大島。 和歌山県南部、潮岬の東方にある島。串本節で知られる。面積9.5平方キロメートル。紀伊大島。
和歌山県南部、潮岬の東方にある島。串本節で知られる。面積9.5平方キロメートル。紀伊大島。 山口県南東部、瀬戸内海にある島。ミカン栽培が盛ん。昭和51年(1976)完成の大島大橋で本土と結ばれる。面積129.6平方キロメートル。
山口県南東部、瀬戸内海にある島。ミカン栽培が盛ん。昭和51年(1976)完成の大島大橋で本土と結ばれる。面積129.6平方キロメートル。 鹿児島県、
鹿児島県、 北海道南西部、日本海にある島。松前町の西方60キロメートルにある火山島で、日本最大級の無人島。面積9.73平方キロメートル。オオミズナギドリの繁殖地。
北海道南西部、日本海にある島。松前町の西方60キロメートルにある火山島で、日本最大級の無人島。面積9.73平方キロメートル。オオミズナギドリの繁殖地。 福岡県宗像市にある島。宗像大社の中津宮と沖津宮
福岡県宗像市にある島。宗像大社の中津宮と沖津宮 「
「
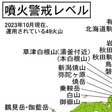

 田史名倉(同書同六年四月一一日条)などが流されており、伊豆島が流刑地とされていたことがうかがえる。神亀元年(七二四)伊豆は安房・常陸・佐渡・隠岐・土佐とともに遠流の地に定められている(「続日本紀」同年三月一日条)。文武天皇三年(六九九)五月二四日、役小角(役行者)が「伊豆嶋」に流されているが(続日本紀)、「扶桑略記」同日条には「仍配伊豆大島」とあり、小角の配流地は大島と考えられる。永久元年(一一一三)には山城醍醐寺の仁寛(真言立川流の祖)が罪科を得て「伊豆大島」に流されている(「殿暦」同年一〇月二二日条)。保元の乱に敗れた源為朝は近江国
田史名倉(同書同六年四月一一日条)などが流されており、伊豆島が流刑地とされていたことがうかがえる。神亀元年(七二四)伊豆は安房・常陸・佐渡・隠岐・土佐とともに遠流の地に定められている(「続日本紀」同年三月一日条)。文武天皇三年(六九九)五月二四日、役小角(役行者)が「伊豆嶋」に流されているが(続日本紀)、「扶桑略記」同日条には「仍配伊豆大島」とあり、小角の配流地は大島と考えられる。永久元年(一一一三)には山城醍醐寺の仁寛(真言立川流の祖)が罪科を得て「伊豆大島」に流されている(「殿暦」同年一〇月二二日条)。保元の乱に敗れた源為朝は近江国 命
命
 島
島 墅截)には「穴井浦之内大島之儀、近年新浦に申付、百姓召付候処、小網一帖仕出度之由、去年も申出」とある。漁場(網代)は「八幡浜十人網と相定」めて認可された。享保三年(一七一八)八月一一日には、「穴井浦之内大島、近年人数多罷成有来候、元網計にてハ渡世難成候ニ付、古網等取合新網壱帖仕出度」(大島井上文書)とあり、新網(結出網)一帖の操業を認可されている。
墅截)には「穴井浦之内大島之儀、近年新浦に申付、百姓召付候処、小網一帖仕出度之由、去年も申出」とある。漁場(網代)は「八幡浜十人網と相定」めて認可された。享保三年(一七一八)八月一一日には、「穴井浦之内大島、近年人数多罷成有来候、元網計にてハ渡世難成候ニ付、古網等取合新網壱帖仕出度」(大島井上文書)とあり、新網(結出網)一帖の操業を認可されている。



