時の概念は、過去から現在へ、さらに未来へと連続して止まることなく過ぎていく現象、すなわち経過していく「時間」と、たとえば一昼夜を区分した時計や十二辰刻(とき)のように定められた「時刻」に分けられる。時の流れを1本の直線に対比して考えるならば、直線のくぎりが点であり、点と点との間の距離が長さであるように、時の流れのある瞬間が時点、つまり時刻であり、その時点と時点との間隔が時間である。いいかえると、時間とは時の流れを測る物差しであり、時刻とはその物差しの目盛りであるといえよう。
[渡辺敏夫]
時間は、古来、哲学の対象として、空間とかかわりをもちながら論じられてきた。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは、時間を「より先」と「より後」とを考慮した場合の運動の数として位置づけており、ニュートンは、外力の作用のない運動物体は一つの直線上を等速運動をする、つまり一直線上の等しい長さの距離は等しい長さの時間に対応するという法則に基づいて、時間を空間から独立した変量として扱っている。また、相対性理論では、時間は、空間とともに四次元の時空世界を形成し、空間から独立したものではないとしている。このように時間は物体の運動、つまり空間における位置の変化としてとらえられているのである。
時間は、方向性、均一性および不可逆性などの特性を有する。一般に時間の流れは、過去から現在へ、そして未来への流れとしてとらえられているが、われわれが時間の流れを認識するのは、われわれの住む世界に変化があって前後の感覚を生ずることによるものである。しかし、感覚上の自然的な時間の長さは不均等にならざるをえない。ニュートンは、時間を感覚から解放する意味で、真に数学的時間、すなわち「絶対時間」を提唱、「真の数学的時間は外界の何物とも関係なく均一に流れる」としている。また、時間の流れは瞬間的であって、一度過ぎ去ればふたたび元に戻ることはできないという不可逆性を有する。つまり、時間の流れには、現在という瞬間がただちに過去として消え去り、ほんの一瞬前までは未来であった瞬間が現在になるという一定の方向があり、その方向を逆転して、過去を現在に手繰り寄せることはできない。この不可逆性に当面して、われわれは時間の存在に気づくことが多いのである。
[渡辺敏夫]
時の流れの長短を知るためには、物の長さを測ると同じように、基準となるようななんらかの「時」の原器を得る必要がある。そのためにわれわれが考えうる方法は、この基準となる時間と同じように繰り返しおこる自然現象を探し出すか、あるいはこの基準となる時間と同じようにしかも精確な時間で繰り返し運動する機械、すなわち時計をつくることである。
人類の文化がまだ幼稚な時代には地球の自転運動からおこる昼夜の交替する1日が、もっとも初歩的な時間単位であった。しかし人間が生活していくには、さらに細分した区分法が必要となり、太陽の高さや方向から1日を大ざっぱな時刻に区分し、さらに太陽の日周運動が季節によって変わることや、1日のうち太陽の高さや方位がどのように変わるかということがわかってくると、それにしたがって日時計のような測器が発明されて、時間を測るようになった。日時計や星時計は曇天や雨天には使用できないため、晴雨にかかわりなく時間測定するために考案されたのが水時計や砂時計である。水時計や砂時計は、1日の長さが季節によって変わることを教えてくれた。
さらに精密な時間測定を必要とした人類は、水時計よりもはるかに精密な時間を保ち、時間の測定に役だつ周期的現象を発見し、それによる時を測る機械を生み出した。すなわち振り子時計の発明である。振り子時計は重力による振動現象であるが、弾性による振動を利用した、もっとも進歩した精緻(せいち)な時計が時辰儀(じしんぎ)(クロノメーター)である。
しかし、振り子時計にしても時辰儀にしても空気の抵抗や摩擦などの影響を受けており、絶対に精確であるとはいえない。これらの多くの時計は、その循環過程がいずれもみな同じ物理的条件の下で行われるということが厳密にいえるとき、この循環過程は同一時間に営まれるという仮定が成り立つのであるが、いかに精巧につくられた時計でも完全に同じ物理的条件を満たすことはありえない。その場合、どの時計を標準とするか、さらに長期にわたって一定不変の正しい時間の物差しをどうするかといった問題が生ずる。
世界中のすべての時計に精確に、しかも長期にわたって一定不変の正しい時間を与えるものと考えられるのは、自然界で理想的な周期現象を示す地球自転による回転運動である。しかし、地球表面には海があり、また太陽や月などの引力による潮汐(ちょうせき)作用があって、地球の自転に一種のブレーキをかけるような潮汐摩擦とよばれる作用が働き、100年間に1000分の1秒ずつ自転の周期が長くなる。その量はわずかであるが、長い時間を経ればその時間は無視できなくなる。さらに、この地球自転の長年加速を取り除いても、なお地球自転の不規則な変動があることがわかったため、地球自転速度から定義される「自転時」にかわって、地球が太陽の周りを回る公転から定義された「公転時系」が採用されて、「暦表時」という考え方が生じたのである。
暦表時は、太陽・月・惑星などの位置を表示するために必要な力学的時系で、天体暦に使用される。暦表時は太陽のニューカム表に基づくもので、太陽の位置を暦表時で観測した場合には太陽表に一致する時系であるが、実際には自転時系の世界時で観測されるため、世界時と暦表時の違いに相当するだけ太陽の観測位置はずれるはずであるが、このずれは、太陽の運行速度が1日わずか1度にすぎないために、太陽観測からは精確に決定できないという困難がある。月はその運行の角速度が太陽の13倍にも達するので、各国の天文台で行われる月の観測を総合して世界時に対する修正値を求めて暦表時が算出されるのであるが、この値が最終的に決定されるのは数年先のことで、現在の用には役だたないという難点がある。そこで、暦表時にかわるものとして原子時が設定された。
20世紀に入って量子力学の発展に伴い、原子が吸収したり放出する電磁波の振動数が、その原子固有の一定不変の値を示すことがわかった。原子のこの性質を利用した「原子時」によって暦表時とは異なった別の一様の時の単位が得られる。現在は、セシウム原子の基底状態の二つの超微細準位の間の遷移に対応する固有振動数91億9263万1770ヘルツの時間間隔を1秒とすると定義されている。この振動数ごとに1秒を刻む時計がセシウム原子時計で、この時計の示す時刻目盛りを原子時、または積算原子時という。このように定義された1秒の原子秒は、1967年パリでの第13回国際度量衡総会で、暦表時の1秒にかわる時間の単位として決定された。原子時計は人工の時計であるから、時間を測定することはできるが、これだけでは時刻の決定ができないため、1958年1月1日世界時0時を原子時0時として出発して、現在使用されている。
[渡辺敏夫]
暦法が1日を単位として長い歳月を規定するのに対し、1日を定め、これを細分する規定が時法である。暦法が人類の生活に重要であるように、時法もまた日常生活に欠くことはできない。1日を昼夜に二分することはもっとも初期の段階であり、さらに白昼を太陽の南中によって二分することは容易に理解できよう。人類の文化が進み、生活が複雑化するにつれて、時の細分化も進み、1日は一二分あるいは二四分される。
エジプトでは、紀元前3000年ころ、すでに昼夜をそれぞれ12時に分けたという。ところが昼夜の長さは、赤道以外では季節によって違うから、この細分によれば、北半球では昼の1時間は夏に長く、冬に短い。反対に夜の1時間は夏に短く、冬に長い。このような、昼夜で1時間の長さを異にする時法を「不定時法」という。この時法はギリシアからローマに伝わってローマ帝国の各地に広まり、中世まで用いられたもので、4000年にわたって人間の日常生活を支配した。
これに対し、昼夜を通して等分した時法を「定時法」という。定時法は、古代の天文学者が計算に使用したもので、2世紀ごろのアレクサンドリアの天文学者プトレマイオスも使用している。14世紀ごろ時計が発明されてからしだいに定時法が用いられるようになった。現在のように1日を24等分する制度は、バビロニアに由来する。バビロニアでは初め1日を12等分した時法が用いられた。この時法を二重時間という。1日を12等分または24等分した1時間だけではまだ不十分であり、さらにこれを細分した時の単位が必要となった。中国や日本などでは1日12辰刻(とき)をさらに分割した刻・分が、ヨーロッパでは六十進法による今日用いられている分・秒の単位が生まれた。
六十進法の分・秒制はどのように発生したか。バビロニアでは、4000年前、十進法と六十進法が併用されていたといわれる。十進法が指の数に由来したことは異論はないが、六十進法についてははっきりした説はないようである。古代バビロニア人は、1年を360日とし、太陽は全円周の360分の1を毎日運行するものとしていた。円周は半径の6倍にほぼ等しいことを知っていたらしく、これから360度の6分の1から60という数字が暗示され、60という数を一種の神秘的な数とみ、1度の60分の1を1分、さらにその60分の1を1秒とした、と一般に信じられていた。しかし、この細分化は数列発達の一般原則である低位から高位に進むということにもとるという理由から、バビロニアの六十進法は、それ以前に行われていた十進法と六進法の折衷であろうといわれる。またバビロニアに限らず、十二進法が世界各地で、主として測定と関連して採用されていたと考えられる理由がある。1年がほぼ12朔望(さくぼう)月であり、一方、この数は2、3、4で割り切れ、したがって分割が容易にできるということが人の心をひいたといわれる。フィートにおけるインチの数、ポンドにおけるオンスの数、シリングにおけるペンスの数、ダースにおける個数などはそのよい例である。これが60となれば、さらに5で割り切れるという利点がある。
[渡辺敏夫]
1日の始めをどこに定めるかは、時を数える基準として必要である。1日の始めの選び方は民族によって違っている。これは、それぞれの民族の生活に密接に関係するもので、一般に人は太陽により生活するから太陽の出没に関係することはもちろんであるが、月によって日を数える民族は太陽が沈む夕方を1日の始めとした。エジプトでは1日の始めを薄明としたようである。アラビア人、トルコ人、ユダヤ人は日没をもって1日の始めとし、ローマ人は夜半から1日を始めた。
天文学のほうでは、天体の南中を基準として時の経過を数える。その天体が太陽であるときには太陽日、恒星であるときには恒星日といい、これを細分した時間が太陽時、恒星時である。太陽時も視太陽か、平均太陽かによって、視太陽時、平均太陽時に区別される。太陽は天球上、黄道を毎日不等の速さで運行するから、視太陽日の長さは1年間、毎日同じではない。1年を通じていつも等しいような時間単位に分割した時法が平均太陽時である。いいかえると、赤道上を毎日等速度運動する平均太陽とよぶ仮想太陽の南中に始まる平均天文太陽時に12時を加えた夜半に始まる時法が平均太陽時である。夜半に始まる平均太陽時は今日、日常生活に用いられている時法で、常用時ともよばれる。18世紀から19世紀にかけて、ヨーロッパでは平均太陽時がしだいに採用されるようになった。これは機械時計が発明され、その精度が向上してきたからである。
地球の自転に基づいて決まる時系を自転時といい、地球の自転の不整がわかってきて、地球の公転から決まる時系の公転時が、1956年に採用された。これが暦表時である。天文学的に決まるこの両時系を天文時と称する。
[渡辺敏夫]
日常生活上、正しい標準時刻を知る必要から、時計により保持された精確な時刻を一般に知らせることを「報時」といい、ラジオやテレビにより時刻を知らせることを時報という。天文台では、晴夜には恒星の子午線観測により恒星時を得、これを計算することによって平均太陽時を換算する。直接、太陽の観測から視太陽時に均時差を補正して平均太陽時を求めることは、太陽の大きさのために精確に子午線経過時刻を測定することが困難であるためである。また日時計による日影から求められる視太陽時はなお不精確なものである。このようにして求め得た時刻を保つための器械が時計であり、この目的のため長く天文時計として時辰儀や、種々の振り子時計が使用されたが、第二次世界大戦後は天文台から姿を消して、水晶時計がこれにかわった。水晶時計は水晶の圧電効果と弾性を利用した水晶発振器を用いるもので、地球自転の不規則性をつきとめるほどの精密さを有する。これにより時辰儀は天文時計として用いられなくなり、現在では航海用、野外観測用として用いられている。
報時は、古くは鐘や太鼓で、あるいは午砲で行われたが、無線電信がマルコーニにより発明されて、20世紀に入ると、各国は無線による報時を1日数回行うようになった。第二次世界大戦中、アメリカでは毎秒の信号を送信する連続報時を行うに至り、大戦後、各国もこれに倣った。日本も1948年(昭和23)から実施して今日に至っている。現在、発信される標準電波秒報時は時刻としては世界時を示し、時間としては原子時の1秒を刻むもので、このように管理された人工的時系を協定世界時(UTC)とよんで、各国で標準時として採用されている。1975年1月1日以降、協定世界時と世界時(UTI)との差はプラスマイナス0.9秒以内に管理されているが、もしこの制限を超えるおそれが生じたときは、1秒のステップで調整が行われる。これを閏秒(うるうびょう)といっている。
[渡辺敏夫]
日本の古い時代のことは明らかではないが、『日本書紀』に、斉明(さいめい)天皇6年(660)、初めて漏刻(ろうこく)(水時計)をつくって民に時を知らせたとあり、これが日本で歴史上最初の時計であり、報時の始めである。また天智(てんじ)天皇10年(671)に、この漏刻を新しくつくった新台に置いて、太鼓と鐘で時を報じたことが記載されている。この時代が時制の確立した最初と考えられるが、その内容については不明である。
10世紀前半(醍醐(だいご)天皇時代)に編修された『延喜式(えんぎしき)』によると、8~9世紀ころには視太陽時による定時法が使用されていたと推定される。当時は1日を昼夜通して12辰刻(とき)、48刻(こく)に分け、夜半を子(ね)として12辰刻を順に、子・丑(うし)・寅(とら)……亥(い)とし、1辰刻を4刻、1刻は10分に分けていた。したがって1刻は現在の30分に相当する。この時刻法を現在に割り当てると、子刻(ねのこく)は午後11時から翌日午前1時まで、子1刻は午後11時から11時30分まで、子2刻は11時30分から12時まで、子3刻は午前0時から同30分まで、子4刻は0時30分から午前1時まで、ここで丑1刻となり、以下同様である。この時刻法では初刻がなく、ただちに1刻となる。『延喜式』には、時刻のあとに、「諸時撃鼓」の見出しで、太鼓や鐘の打ち方が記してある。それによると、子刻、午(うま)刻から9・8・7・6・5・4という順序で辰刻ごとにその数だけ太鼓を打ち、辰刻間には1・2・3・4と刻の数だけ鐘を鳴らした。つまり子刻・午刻を九つにあて、それから順に1辰刻ごとに八つ、七つ、六つ、五つ、四つと逆に数えたのである。以上は宮廷で使用された時刻法であるが、当時の具注暦の「宣明(せんみょう)暦」では、1日を12辰刻、100刻とし、また8400分としている。すなわち1刻は84分、1辰刻は700分=8刻28分という定時法を使用している。これは日・月食の観測・記録に用いられた時刻法であるが、同じ具注暦に日の出・日の入りの時刻が記載されていて、前記の日・月食の時刻法とは別の異なった時刻法が採用されている。また夜間を日暮れから夜明けまでとし、これを5等分して、これを1更とし、1更を5点とする更点法が文人などの間で用いられた。
奈良時代、時刻を保持するために漏刻が用いられた。宮廷には漏刻博士という官が2人置かれ、この下に20人の守辰丁がいて、漏刻の時刻を読み取って鐘鼓を打つことをつかさどった。行幸の際などには漏刻を持って漏刻博士が供奉(ぐぶ)したもので、それほど漏刻は貴重なものであった。しかし中世に入り、しばしばの戦乱や宮廷の衰微などで漏刻が一時廃止されることもあった。その結果、定時法の基礎を失い、時刻法は原始的な不定時法に逆行することになった。夜明け・日暮れ、日の出・日の入りやその方位などによって、大略の時刻を知るよりほかに方法がなかった。この状態は江戸時代に入っても続き、一般庶民の使用する時刻法は原始的な不定時法で、明治に至るまで日常生活に使用された。
徳川家康の時代には、江戸では明け六つ、暮れ六つに太鼓を打って時を知らせたが、2代将軍秀忠(ひでただ)の代になって、五つ、四つ、九つ、八つ、七つを報ずるようになり、同時に鐘に改まったという。江戸時代にはオランダを通じてヨーロッパの精確な機械時計が輸入され、多くの時計師がこれを模造して、時の観念も広く行き渡ったが、定時法を使用するまでには至らなかった。しかし暦家は、不定時では計算に不便であるので、相変わらず定時法を採用し、暦面にこれを記載したため、一般民間で使用された時法と相違するという不都合な状態が天保(てんぽう)の改暦まで続いた。民間で用いられた不定時法の呼称は、夜明け、日暮れを、それぞれ明け六つ、暮れ六つとし、昼九つ、夜九つ、暁五つ、晩六つというように夜・昼・暁・晩という字を冠して昼夜のいずれかを区別する必要があった。一方、十二支による子刻、丑刻のように1日を通して数えるほうが便利なことから十二支による唱え方も用いられた。しかし、この十二支による唱え方は暦面記載の定時法の十二辰刻を意味するものではなく、明け六つ、暮れ六つの唱え方にかわって用いられた不定時法であった。すなわち子刻は夜九つであり、卯(う)刻とは明け六つのことである。十二辰刻はさらに上刻・中刻・下刻に三分されたが、この定めがはっきりしていなかったため、時を知らせる鐘が上野と芝で違っていて問題がおきたことがあった。天保暦になって暦面に民間使用の時刻も記載することになり、両者が相違するという事態は消滅した。時刻制度の発達からみると退歩したといわざるをえない。
1873年(明治6)太陽暦が施行されると、江戸時代の時刻法が廃され、昼夜平分24時に分けられた太陽時による定時法が用いられることになった。1884年アメリカのワシントンで開催された「本初子午線並に計時法万国公会」で、イギリスのグリニジ天文台を通る子午線を本初子午線とすることが定められ、1886年7月12日、勅令第51号をもって、1888年1月1日から東経135度の子午線(明石(あかし)市通過)の地方時を日本の標準時に定め、現在に至っている。また主として経済上の理由で、法律により標準時を1時間進ませる夏時法(サマータイム)が、1948年(昭和23)日本でも採用されたが、4年後に廃止された。
[渡辺敏夫]
 〈ジ〉
〈ジ〉 〈とき(どき)〉「
〈とき(どき)〉「
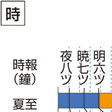
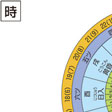








 (つつし)んで民に時を授く」は農時暦の意。古文の字形は中山王鼎にもみえ、之(し)と日とに従う。之にものを指示特定する意があり、〔書、舜典〕「百揆(き)時(こ)れ敍す」、〔詩、大雅、緜〕「曰(ここ)に止まり 曰に時(を)る」のような用法がある。また〔石鼓文、
(つつし)んで民に時を授く」は農時暦の意。古文の字形は中山王鼎にもみえ、之(し)と日とに従う。之にものを指示特定する意があり、〔書、舜典〕「百揆(き)時(こ)れ敍す」、〔詩、大雅、緜〕「曰(ここ)に止まり 曰に時(を)る」のような用法がある。また〔石鼓文、 (吾)車石〕に「
(吾)車石〕に「 ち
ち と通じ、よい。
と通じ、よい。 と通じ、まつ。
と通じ、まつ。 時 カクノゴトク
時 カクノゴトク (蒔)・塒の二字を収める。
(蒔)・塒の二字を収める。 のとまり木で、みな蒔く、植える意がある。時はもと農耕に関する字であったかもしれない。
のとまり木で、みな蒔く、植える意がある。時はもと農耕に関する字であったかもしれない。 は同声。是・
は同声。是・






 時・花時・嘉時・及時・旧時・救時・今時・近時・計時・済時・祭時・歳時・暫時・四時・失時・殊時・瞬時・順時・少時・乗時・常時・食時・酔時・随時・寸時・盛時・聖時・夕時・戦時・即時・多時・奪時・抵時・適時・天時・当時・同時・年時・農時・曩時・非時・不時・平時・餔時・明時・夜時・幼時・良時・臨時・歴時
時・花時・嘉時・及時・旧時・救時・今時・近時・計時・済時・祭時・歳時・暫時・四時・失時・殊時・瞬時・順時・少時・乗時・常時・食時・酔時・随時・寸時・盛時・聖時・夕時・戦時・即時・多時・奪時・抵時・適時・天時・当時・同時・年時・農時・曩時・非時・不時・平時・餔時・明時・夜時・幼時・良時・臨時・歴時