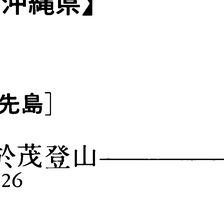精選版 日本国語大辞典 「沖縄」の意味・読み・例文・類語
おき‐なわ‥なは【沖縄】
- [ 1 ] 〘 名詞 〙 魚を捕えるのに使う縄。
- [ 2 ]
- [ 一 ] 「おきなわじま(沖縄島)」の略。
- [ 二 ] 「おきなわしょとう(沖縄諸島)」の略。
- [ 三 ] 「おきなわけん(沖縄県)」の略。
- [ 四 ] 沖縄県沖縄島中南部の地名。那覇市の北東二〇キロメートルにあり、米空軍嘉手納(かでな)基地がある。昭和四九年(一九七四)コザ市と美里村が合併し改称市制。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「沖縄」の意味・わかりやすい解説
沖縄(県)
おきなわ
日本最西端、有人島域としては日本最南端に位置する県で、「琉球(りゅうきゅう)」の別称もある。アジア大陸の東縁を九州の南から台湾島の手前の与那国(よなぐに)島まで、弓状にカーブを描いて伸びる1200キロメートルに及ぶ南西諸島(琉球列島)のほぼ南半分を占める。沖縄島をはじめとする島嶼(とうしょ)だけで形成される日本本土にない唯一の県である。面積2282.59平方キロメートル。
県域は、北端の硫黄鳥島(いおうとりしま)から南端の波照間島(はてるまじま)まで南北約400キロメートル、東端の北大東島(きただいとうじま)から西端の与那国島まで東西約1000キロメートル、北緯24度2分~27度53分、東経122度55分~131度20分に位置する。試みに、県庁所在地の那覇市(なはし)を東京に置いて県域を本州に重ねると、北端の硫黄鳥島は福島県に、西端の与那国島は香川県に位置する広大な県域となる。鹿児島県の南端与論(よろん)島と沖縄島は北緯27度線を挟んで約28キロメートルであり、与那国島と台湾島の間は約100キロメートル、晴れた日に毎年数度は肉眼で台湾島を遠望できる。県域の東側に太平洋があり、西側に東シナ海を挟んで中国大陸が存在する。北側は琉球列島の北半分の島々を経て日本本土に連なり、南西は台湾から東南アジアにつながっている。地理的位置を象徴するものとして、1月中旬から5月下旬にかけて、南十字星の上部を観察することができる点にも注目したい。
琉球列島の島々は行政上南西諸島の名で総称され、198島から構成される。北半分の38島が薩南(さつなん)諸島(鹿児島県)、残り160島が琉球諸島(沖縄県)である。琉球列島は古く「南島(なんとう)」と称され、そのなかの喜界島(きかいじま)以南の島々は歴史的に「琉球」とよばれてきた。
琉球諸島は沖縄島を主島とする沖縄諸島(116島)、宮古(みやこ)島を主島とする宮古列島、石垣島を主島とする八重山列島(やえやまれっとう)に区分され、宮古・八重山両列島を総称して先島諸島(さきしましょとう)ともいう。沖縄島が最大で県総面積の53%を占め、ついで西表島(いりおもてじま)、石垣島、宮古島、久米島(くめじま)の順となり、前記5島で県総面積の85%に達し、残りはいずれも狭小な島々ばかりである。有人島は45島で残りは無人島であるが、人口の8割は沖縄島に集中し、宮古・石垣両島を除くと残りはいずれも過疎性の強い離島となっている。2020年(令和2)10月時点で、11市5郡11町19村からなる。2020年の国勢調査では人口は146万7480で、このうち約77%は市部に集中している。沖縄島は北部(別名国頭(くにがみ)・山原(やんばる))、中部(中頭(なかがみ))、南部(島尻(しまじり))に3大別され、那覇市は南部の北端に位置する。
沖縄はかつて琉球ともよばれ、日本文化の一環に属する文化をもつ人々が居住し歴史を形成してきた。15世紀初期から約450年間「琉球王国」とよばれる独自の国家が存在したが、1879年(明治12)に「沖縄県」が設置され、日本社会の一員に編成された。だが、第二次世界大戦後に日本社会から分離されアメリカ合衆国の直接統治下に置かれた。しかし、住民の日本復帰の要求が強く、1972年(昭和47)5月15日に日本復帰が実現して今日に至っている。地理、自然、歴史、文化、社会のあらゆる面でユニークな特徴をもつ県の一つである。
[目崎茂和・高良倉吉]
琉球の呼称
「琉球」の呼称は中国人による命名で『明実録』洪武(こうぶ)5年(1372)の記事が初見。以後、この名称は喜界島以南から与那国島までの島嶼地域をさすことばとして定着し、同時にまた、琉球王国の成立(1429)から1879年(明治12)の琉球処分により王国が廃止されるまでの約450年間、沖縄の公称として用いられた。一方、「沖縄」はすでに8世紀の文献『唐大和上東征伝(とうだいわじょうとうせいでん)』に「阿児奈波(おきなわ)」の名で登場し、古謡集『おもろさうし』にも「おきなわ」と明記されているが、「沖縄」と明記したのは新井白石(あらいはくせき)の『南島志(なんとうし)』(1719)が最初である。ただし、沖縄はもともとは沖縄島とその周辺離島をさす地域名でしかなく、琉球処分の結果「沖縄県」が設置されるに及んで初めて、現在の県域全体を包括する公称になったものである。ところが、第二次世界大戦後のアメリカ統治下において政治的目的により「琉球」の公称が復活し用いられた。しかし1972年の日本復帰により「沖縄県」がふたたび復活したのに伴い、沖縄という公称もまた復活するに及んだ。琉球、沖縄ともにその語源はいまのところ明らかではない。
[高良倉吉]
自然
地形
大東・尖閣(せんかく)両諸島を除くと、沖縄県の島々はすべて、琉球海溝と沖縄舟状海盆(トラフ)とに挟まれる海底山脈状の高まりに形成された弧状列島(島弧)である。その一般的特徴である火山帯の存在は、九州から吐噶喇(とから)列島を経て、県最北端の硫黄鳥島まで明瞭(めいりょう)に認められる。火山島列の太平洋側には屋久(やく)島、奄美(あまみ)大島、沖縄島など非火山島列が並び、二重弧の性格を有する。そのため火山島列を内弧、非火山島列を外弧ともいう。しかし先島諸島にはこの関係はない。そのほか、地震や地殻構造など典型的な島弧の特徴があり、地殻変動の顕著な島々となっている。
琉球列島の成立は約500万年前の新生代新第三紀鮮新世といわれ、それより古い基盤の地質構造は西南日本外帯と類似する帯状構造をもつが、やはり先島諸島ではそれは不明瞭となる。すなわち外弧では大陸側から古生代岩塊を含む中生代、中生代、新生代古第三紀と地質が順に新しくなるように、帯状の配列構造を示す。
島の地形は、この島弧の特徴や地質の帯状構造と密接に関連している。巨視的に島の地形をみると、山地のある「高島(こうとう)」と台地状の低平な「低島(ていとう)」の2種に大別できる。内弧の火山島はもちろん高島に属し、古生代~新生代古第三紀の地質は大半が山地をなす高島となる。一方、新第三紀~第四紀の新しい地質の島は台地をなして低島となる。高島は久米島、石垣島、西表(いりおもて)島などであり、低島は宮古列島、黒島、波照間(はてるま)島などである。なお沖縄島だけは、北部の高島タイプと中南部の低島タイプが残波(ざんぱ)岬―石川の地帯で接合したものである。高島・低島の分類は薩南諸島にも有効で、南西諸島全体に適用できる。
また、高島と低島の2大別は地形分類であると同時に、島の地学上の判別にもきわめて有用な分類である。地質的に高島は火山あるいは古第三紀より古い地層から構成されるのに対し、低島は新第三紀の島尻(しまじり)層群の泥岩類と、それを覆う第四紀の琉球石灰岩からなる。この地質的な差異のため高島の土壌は酸性の赤黄色土(国頭マージ(くにがみまーじ)とよぶ)となるのに対し、低島では一般に中性から弱アルカリ性の石灰岩土壌(島尻マージとよぶ)と泥岩未熟土壌(ジャーガルとよぶ)とが主体をなす。地形、地質の相違は水文条件にも影響を与え、高島は河川を中心とするのに対し、低島は地下水主体の水文環境である。高島と低島との地学上の差異は、当然のことながら植物、動物あるいは土地利用、集落立地などにも現れる。
[目崎茂和]
気候
一般に、亜熱帯気候とよばれる。だが、気候的には西日本と同じ温帯多雨帯(ケッペンの気候区分Cfa)に属す。長い夏と四季の不明確な点で西日本とは異なるが、その他は気候学的によく類似する。すなわち、本土より1か月早く始まる梅雨(つゆ)(沖縄で小満芒種(スーマンボースー)という)が6月下旬に明けると、小笠原(おがさわら)高気圧に覆われ、南風の高温多湿の夏が10月中旬まで4か月近く続く。その期間の安定した晴天は、毎年平均4個の台風の襲来で乱される。夏季の終了は、北東季節風の吹き出し(この風をミーニシとよぶ)とそれに伴うサシバの渡りで告げられ、梅雨期前までこの北東風が卓越する。この点では西南日本と同じモンスーン気候といえる。冬季はこの北東風のため曇天が多く、日照率は日本海側と同じ30~40%である。だが、1、2月でも最低気温が10℃以下になることはまれで、氷雪をみることはない。島によって若干異なるが、年平均気温は21~24℃、年降水量は1600~3000ミリメートルで、その47%は梅雨と台風によってもたらされる。しかし梅雨や台風期の降水は年の変動が大きいため、干魃(かんばつ)も少なくない。水の器としては小さい島が多いことも干害を助長する。
気候上は西日本と類似するが、地形、地質や動植物には熱帯的要素が顕著に認められる。たとえば黒潮の北上と関係して、沖縄の島々はサンゴ礁の発達が良好である。大半は裾礁(きょしょう)タイプであるが、久米島や石垣―西表島間には堡礁(ほしょう)が存在する。また、河口には熱帯特有のマングローブ湿地(ヒルギの群生林)があり、とくに西表島の仲間川(なかまがわ)、浦内川(うらうちがわ)に顕著である。島の地形にも、日本本土にはない熱帯性の地形がある。その代表的なものが沖縄島の石灰岩地域に発達する円錐(えんすい)カルストや石灰岩堤の地形であり、これらは熱帯性カルストに分類される。また地質的には、第四紀のサンゴ礁に起源をもつ琉球石灰岩の広大な分布(県面積の約3割)も日本本土にない熱帯的な特徴である。このように地形、地質の面から沖縄の自然は、「島弧の島」「亜熱帯の島」という二重の性格をもつユニークな環境として位置づけられる。
[目崎茂和]
生物相
沖縄島を中心とする南西諸島は、亜熱帯海洋性気候、地理的な位置、島々の成り立ちの地史など特色のある自然環境である。そのため、日本のほかの地域にはみられない特異な生物相を呈している。したがって、生物地理学的にも南西諸島の全体にわたって記述するのが都合がよく、ここでは「動物」についてはその方向で記述する。「植生」は、奄美(あまみ)諸島については「奄美諸島」の項目を参照のこと。
[池原貞雄]
動物
南西諸島は、暖帯から熱帯性の動物が主体をなしている。すなわち、動物地理学的には東洋区系の生物が豊富な地域である。そして、東洋区系の生物の分布北限あるいは旧北区系の生物の分布南限が、それぞれこの地域内で区画されるものが多い。たとえば、鳥類などでは蜂須賀(はちすか)線(沖縄島と宮古島間)、哺乳(ほにゅう)類・爬虫(はちゅう)類・両生類などでは渡瀬(わたせ)線(屋久島(やくしま)・種子島(たねがしま)と奄美諸島との間)、昆虫類や高等植物の一部では三宅(みやけ)線(薩南諸島と九州南端との間)に、それぞれ境界があると提唱されている。
固有種が多く、高等動物の固有種のなかには近隣地域の対応種に比べて、はるかに古い時代の生き残りとみなされるものが多いのも特色の一つである。たとえば沖縄産の甲虫類875種のうち298種が固有種であり、陸産貝類の70%以上が固有種で占められている。奄美諸島のアマミノクロウサギ、沖縄島のノグチゲラ、西表(いりおもて)島のイリオモテヤマネコなどが、古い時代の生き残りとみなされている。これらの古い種は、南西諸島がアジア大陸から海で隔離された古い時代から、島に取り残されて現在に至っていると考えられている。
海を越えて伝播(でんぱ)できない動物たちに、亜種に分化したり変種に移行したものが多いことも特色である。たとえば、沖縄諸島産のオオコウモリは、オリイオオコウモリ(沖縄島)、ダイトウオオコウモリ(大東諸島)、ヤエヤマオオコウモリ(八重山(やえやま)列島)の三つの亜種に分化している。種の成立や亜種・変種への分化には、地理的な隔離が大きな要因となることはよく知られている。奄美諸島や沖縄諸島に亜種や変種が多いのは、生物が海で隔離された島々に、長年の間封じ込められてきたためであると考えられる。
絶滅種や外来種が多いことも特色である。前者の例では、哺乳類のオキナワオオコウモリ、鳥類ではリュウキュウカラスバト、ダイトウハシボソウグイス、ダイトウミソサザイなどは、近年まったくみられなくなったことから、絶滅してしまったと考えられている。南西諸島は島の面積が比較的小さいので、島の自然環境の変化はある種の生物に致命的な影響を及ぼすのである。外来種でありながら沖縄で繁栄しているものでは、哺乳類のマングース、両生類のシロアゴガエル、淡水魚のティラピア、グッピー、陸産貝のアフリカマイマイなどがあげられる。昆虫類では、南方地域から人為的(意図的あるいは無意図的)に移入されたものや渡り昆虫などの侵入によって、この地方の昆虫相を複雑なものにしている。
海の生物相は、熱帯海域の生物相ときわめて似ており、日本のほかの海域ではみられないほど、造礁サンゴを主体とする造礁生物の種類が豊富なことも特色である。サンゴ礁海域には熱帯系の多種多様な生物がみられ、沖縄地方の生物相の一大特色となっている。1970年代以降のオニヒトデの大量発生、1990年代以降の海水温上昇による白化現象など、サンゴ礁をめぐる環境の悪化が問題となっている。
[池原貞雄]
植生
沖縄県の植生は、石灰岩と非石灰岩という母岩の相違によって大きく分けられる。非石灰岩上では大部分はスダジイの優占する常緑広葉樹林で占められ、沖縄島ではオキナワシキミ‐スダジイ群集にまとめられる。また石垣島、西表島にはオキナワウラジロガシ群集が、内陸の渓谷沿いの適潤地に発達している。一方、古生代の石灰岩上では、ナガミボチョウジ、リュウキュウガキなどの石灰岩特有の植物で特徴づけられるガジュマル‐クロヨナ群集などの植生がみられるが、自然林としては山地部やドリーネの窪地(くぼち)に残存するだけで、大部分は二次林である。また、ヤシ科植物のビロウ林やヤエヤマヤシ林(西表島星立(ほしだて))などは亜熱帯植生を特徴づけている。さらに海岸の急傾斜地のウバメガシ林やソテツ群落などもよく発達している。
亜熱帯植生を代表するもう一つの植生にマングローブ(紅樹林)があり、各島の河口部や遠浅な湾部に分布している。メヒルギ、マヤプシギ、オヒルギ、ヤエヤマヒルギなどを主要な群落構成種としている。西表島の仲間川、沖縄島慶佐次(けさじ)湾などにまとまったマングローブ林がみられる。マングローブ林の背後の低湿地に広がるサガリバナ群集や、巨大な板根(ばんこん)を有するサキシマスオウノキの森林は特異である。
海岸植生も本州から九州にかけての植生とはかなり異なる。海岸隆起サンゴ礁上には、波打ち際よりイソフサギ群落、イソマツ‐モクビャッコウ群集、モンパノキ‐クサトベラ群集の植生配分がみられる。砂丘上ではハマアズキ‐グンバイヒルガオ群集、クロイワザサ‐ハマゴウ群集、アダン群集の植生配分となっている。
琉球諸島は古くから人々が住み着き、ほとんどが代償植生(人為的な植生)に覆われている。山地部はスダジイ萌芽(ほうが)林やリュウキュウマツ植林で覆われ、一部にススキ草原、リュウキュウチク群落がみられる。隆起サンゴ礁上の平坦(へいたん)地は草地(スズメノコビエ‐チガヤ群集)やパイナップルの耕作地(シマニシキソウ‐ハリビユ群集)と化している。
[奥田重俊]
歴史
時代区分と特徴
歴史は大づかみに五つの時代に区分してとらえられている。〔1〕先史時代、〔2〕古琉球、〔3〕近世琉球、〔4〕近代沖縄、〔5〕戦後沖縄である。「先史時代」はいまから数万年前から紀元後12世紀ごろまで。続く「古琉球」は12世紀ごろから1609年(慶長14)の薩摩(さつま)島津氏による武力征服事件(島津侵入事件)までの約500年間。「近世琉球」は1609年から1879年(明治12)の明治政府による琉球王国の廃止=沖縄県の設置(琉球処分)までの270年間。「近代沖縄」は1879年から1945年(昭和20)の沖縄戦までの70年弱の期間。「戦後沖縄」は1945年からアメリカ統治時代の27年間を経て1972年(昭和47)5月15日の日本復帰以後今日まで、である。
前記の時代区分に象徴されるように、沖縄の歴史は日本社会の他の地域に類例をみない独自の歩みをたどっていることがわかる。その基本的な特徴をあげると、3点に要約できる。
(1)日本文化を所有する人々が沖縄の島々に住み着いて創造した歴史であるが、やがて人々はしだいに独自の歴史的な歩みをたどるようになり、古琉球の時代にはついに日本社会の枠外で国家(琉球王国)を形成するほどの独自性を発揮したこと。
(2)そういう独自の歩みをたどった地域が、近世初頭の島津侵入事件、近代初頭の琉球処分という二つの事件を契機に段階的に日本社会の一員として編成されたこと。
(3)しかし沖縄戦の結果ふたたび日本社会の枠外に置かれてアメリカの直接統治を受けるようになり、そういう状況のなかで県民が主体的に日本社会への復帰を要求、やがて日本社会の一員に復帰して今日に至っていること。
このように、沖縄のたどった歴史はきわめてユニークなものであり、沖縄のもつ地域的特質の主要な背景をなしている。以下、各時代順に歴史の推移を述べてみよう。
[高良倉吉]
先史時代
歴史の起源は、現在確認されているところでは旧石器時代にまでさかのぼる。那覇市の山下町第一洞穴遺跡から出土した人骨(山下洞人)は3万2000年前、八重瀬(やえせ)町の港川(みなとがわ)遺跡から出土した人骨(港川人)は1万8000年前という古さを示している(いずれもカーボン測定法(炭素14法)による年代)。ただし、旧石器と断定しうるものはまだ確認されていない。当時の人々は島々に広く生息していたシカを狩り、その角(つの)、骨を加工して利器として用いる、いわゆる骨角器文化を所有していたことがわかっている。だが、調査、研究は始まったばかりで不明の点が多く、いかなる文化的系譜をもつものであるかもわかっていない。
旧石器時代は約1万年前に終了したが、その後しばらくの間人類居住の痕跡(こんせき)を確認できない空白期が続き、やがて貝塚時代(新石器時代)と称される新しい時代が登場する。最新の研究によれば、読谷(よみたん)村の渡具知東原遺跡(とぐちあがりばるいせき)出土の爪形文(つめがたもん)土器にみられるように、貝塚時代は約7000年前、つまり縄文時代草創期にその起源をもち、文化内容としては九州地方の縄文文化と深い関連をもちながら展開したとみられている。九州地方とはその後も文化的接触が継続した模様だが、しかし、貝塚時代前期(縄文時代後期にほぼ相当)を代表する荻堂式土器(おぎどうしきどき)や伊波式土器(いはしきどき)以後は類似の土器が沖縄以外の地域からは出土せず、したがってこの時期から沖縄の先史文化もしだいに土着化・個性化を強めていったと考えられている。やがて貝塚時代後期には、沿岸の浅い礁湖(ラグーン)を舞台とする漁労に支えられた単位集団が海岸付近の低地に成立した。この間、北九州の弥生(やよい)文化の影響も一定程度は及んだが、社会的変化を促すほどの大きなインパクトは及ぼさなかったとみられている。
貝塚時代は12世紀ごろには終了し、引き続いてグスク時代と称される新しい段階が登場する。グスク時代遺跡は炭化した米や麦、それに鉄製品を出土することから、すでに穀類農耕、鉄器使用の段階に入りつつあったことがわかる。また、須恵器(すえき)や陶磁器の出土にみるように、日本および中国の文化的影響がこの時代から顕著になり始めた状況も確認されている。グスク時代の終末をいつとみるかについては、研究者の間で諸説があり一定しないが、15世紀初期の琉球王国の成立あたりを下限とみたほうが妥当だという見解が提示されている。
[高良倉吉]
古琉球
グスク時代は重要な転換期であった。農耕・鉄器文化の進展と外来文化のインパクトが及び始めたため、それまで緩やかに推移してきた先史社会を大きく変容させることになり、やがて按司(あんじ)と称される首長層の動きが各地で活発となり始めた。按司は自己の共同体・地域集団を率いて互いに抗争し、13世紀ごろにはグスクを築き始め、各地に小さな勢力圏を形成するようになったらしい。やがて、強大となった按司を主体とする広域的な勢力圏が出現し、14世紀に入ると沖縄島を中心に三山(さんざん)とよばれる小国家が鼎立(ていりつ)する形勢(三山時代)となった。沖縄島北部地方には今帰仁(なきじん)城を拠点とする山北(さんほく)(または北山(ほくざん))が、中部地方には浦添(うらそえ)城(のちに首里(しゅり)城)を拠点とする中山(ちゅうざん)が、南部地方には島尻大里(しまじりおおざと)城(南城市)を拠点とする山南(さんなん)(南山(なんざん))がそれぞれ登場した(山南の拠点は内紛の結果しばしば島添(しまそえ)大里城に移ったともいう)。
1372年、中山王察度(さっと)は明(みん)の太祖洪武帝(こうぶてい)の招諭を受けて初めて入貢し、中国との間に密接な外交、交易関係を樹立した(以後この関係は琉球処分までの500年間続く)。これに対し山南・山北もまた同様な関係を樹立したので、三山の抗争は一段とエスカレートする状況となった。1406年、中山王武寧(ぶねい)は山南の一按司尚巴志(しょうはし)に敗れ、尚巴志が中山の覇権を手中にする。1416年、尚巴志は兵を率いて山北王攀安知(はんあち)を攻めこれを滅ぼした。1429年、彼は山南王他魯毎(たろまい)をも倒し、ここについに念願の統一王朝樹立に成功する。尚巴志の手で建設されたこの統一王朝を一般に第一尚氏(しょうし)王朝と称し、この王朝の出現を画期に琉球王国が名実ともに成立したことになる。だが、この王朝の支配はかならずしも安定したものではなく、按司層の勢力はなお各地に温存されたままであった。1453年には王位継承をめぐる内乱(志魯・布里の乱(しろふりのらん))が発生し、1458年には有力按司の反乱(護佐丸・阿麻和利の乱(ごさまるあまわりのらん))も惹起(じゃっき)し、王朝の屋台骨は大きくぐらついた。そして1469年、有力者金丸(かなまる)はクーデターにより王権を奪い、翌年即位して尚円(しょうえん)と号し新しい王朝を始めた。これが第二尚氏王朝である。
第二尚氏王朝は3代尚真(しょうしん)の治世期(在位1477~1526)に最盛期を迎える。国家行政機構を整備するとともに、位階制を制定し、また、各地に割拠する按司層を首里に集住させ、国王を頂点とする国家機構に編成した。さらにまた、隠然たる勢力をもつ神女(しんじょ)層を聞得大君(きこえおおぎみ)を頂点とする組織に編成してそれを国王の配下に置き、その一方で地方、島嶼(とうしょ)に役人を置いて地域支配を強化した。こうして、北は奄美(あまみ)諸島から南は八重山(やえやま)列島に至る琉球弧の島々を版図とし、国王を頂点とする国家機構をもつ琉球王国が16世紀初期に確立したことになる。国王はティダ(太陽)あるいは世の主(よのぬし)と称されて、その統治拠点であった王都首里には王宮首里城をはじめとする幾多の建造物が建立され栄華を極めた。
按司の抗争から尚真治世期に至る歴史は琉球王国の形成史と理解することができ、尚真治世期の転換を経た以後の歴史は、琉球王国が東アジアにおいて独自の国家としての展開をみせる時期と理解することができる。琉球王国の形成、展開史に相当する12世紀から16世紀までの時期を沖縄歴史では古琉球と称する。
古琉球にはいま一つ次のような重要な動向があった。それは、三山の末期から第一尚氏・第二尚氏両王朝を通じて展開された対外交易である。中国(明(みん))との進貢貿易(朝貢貿易ともいう)を主軸に、北は日本、朝鮮、南はシャム、マラッカ、ジャワなど東南アジア諸国との間に活発な交易が繰り広げられている。対外交易は国家が主体に行う官営貿易である点に第一の特徴があった。交易品のなかには琉球産の品も含まれてはいたが、大半は異国産のものによって占められ、諸国の産物を巧みに組み合わせて取引する典型的な中継貿易であったことがわかる。これが第二の特徴であった。交易を中心とする諸国との交流が琉球文化の形成に大きな影響を与えたことはいうまでもなく、同時にまた王国発展の経済的基盤としても重要な意義をもった。東アジアの代表的な交易国家として琉球王国は発展したが、しかし、隆盛を誇ったこの対外交易も、ポルトガル勢力の進出、中国商人・日本商人の発展などにより16世紀中ごろから急速に衰退していった。
[高良倉吉]
近世琉球
16世紀末期の日本における統一国家形成の動きは、琉球にもさまざまな波紋を投げかけた。やがて徳川幕府が成立すると、局面は一挙に変転した。かねてから琉球征服の野望を抱いていた薩摩(さつま)藩主島津家久(いえひさ)は徳川家康の承諾を得て、1609年(慶長14)春、兵3000を送り琉球を攻略した。当の琉球側には戦意がなく、若干の抵抗を示しただけで無条件降伏を余儀なくされた(島津侵入事件)。この事件を契機に琉球は幕藩体制の一環に編成されると同時に、島津氏によって管理される政治的地位に置かれることになった。しかし、王国体制や中国との外交関係はそのまま温存されるなど「異国」としての形式は存続した。こうした状態を「幕藩体制のなかの異国」と評する研究者もいる。
近世琉球は、大づかみにいって三つの要点を中心に推移している。一つは、幕府・薩摩藩の規制下で幕藩体制的秩序をいかに国内において実施するかという問題、二つ目は伝統的な中国との関係をいかに安定的に維持していくかという問題、三つ目は以上の2点を前提に琉球社会をいかに振興していくかという問題である。この三つの要点を政策課題に掲げて登場した代表的な政治家が向象賢(しょうしょうけん)と蔡温(さいおん)であった。彼らの施策により琉球の近世体制はほぼ確立し、王国の直接的な統治主体である首里王府の機能も強化された。この施政の安定を背景に18世紀は琉球文化(沖縄文化)の一大高揚期を迎える。蔡鐸(さいたく)や鄭秉哲(ていへいてつ)らによる修史事業の展開、玉城朝薫(たまぐすくちょうくん)らによる組踊(くみおどり)の創作、識名盛命(しきなせいめい)・平敷屋朝敏(へしきやちょうびん)らによる和文学の隆盛をはじめ、琉歌・三味線音楽・芸能あるいは美術・工芸、漢詩文・学問などの各分野に優れた人材を輩出し、琉球文化の花を開かせた。
だが、薩摩、首里王府への重い貢租負担を課せられた民衆の疲弊化がしだいに進行し、18世紀後半になると行政単位である間切(まぎり)や村が貢租負担能力を失って倒産するという異常事態が頻発した。この傾向は19世紀に入るとますます深刻となり、王府財政も極度に逼迫(ひっぱく)するようになった。これに加えて、1816年(文化13)のイギリス軍艦アルセスト号、ライアラ号の来航を皮切りに異国船の来航が相次ぐようになり、1853年(嘉永6)にペリー艦隊は琉球側に強い態度で諸要求を突きつけ、翌1854年(安政1)には琉球側もペリーとの間に琉米修好条約の締結を余儀なくされている。内外の多難に対して、琉球内部でも対応策をめぐる路線争いが生じた。牧志・恩河事件(まきしおんがじけん)(1858~1859)で守旧派が勝利を収めたものの、有効な手だてを得ぬまま幕末・維新期の激動を迎えることになった。
[高良倉吉]
近代沖縄
明治維新により日本は近代国家の歩みを開始したが、その際領土確定の問題が重要案件の一つとしてクローズアップされた。明治政府は1872年(明治5)から琉球王国を近代日本の版図に正式に編入する手だてを練り始めるが、その前に基本的に二つの障害が横たわっていた。一つは琉球側の統合反対の動きであり、他の一つは、伝統的な琉球との関係を盾に明治国家の琉球併合に反対する中国(清(しん))の存在であった。この両者の反対をしり目に1879年春、明治政府は軍隊、警察を投入して王宮首里城の明け渡しを迫り「沖縄県」の設置を宣言した(琉球処分)。この事件により琉球王国は解体したが、琉球の支配層は明治政府に対する不服従運動を展開し、また、旧臣の間には密命を帯びて中国に渡航し中国政府を動かして王国復旧を実現しようとする動きが激増した(脱清運動)。これを受けて中国側も強く抗議したため、明治政府は1880年に宮古、八重山を中国に割譲するのと引き換えに、中国内で欧米並みの特権を得るという分島増約案を示したが、土壇場で実現をみなかった。琉球側の不服従、中国側の抗議は最終的に日清(にっしん)戦争における日本の勝利によって終止符が打たれる。
置県後、明治政府は沖縄県政に慎重な態度をとり、急激な本土並みの近代化を避け、王国時代の旧制度を基本的に踏襲する旧慣存続策を選んだ。このため沖縄の近代化は本土に比べて大幅に遅れることになり、その不満が宮古島人頭税廃止運動(1892~1894)や謝花昇(じゃはなのぼる)らの運動(1899~1900)となって現れた。これらの動きと日清戦争の勝利を踏まえて、政府は土地整理(1899~1903)を皮切りに本土並みの制度への転換を本格的に推進したが、その作業は大幅に遅れ、1921年(大正10)の首里、那覇への市制の施行によって初めて達成される。
本土への一体化は沖縄の日本資本主義への実質的な編成を意味したが、これに伴い沖縄社会もしだいに変容の度合いを強め、海外移民や本土工業地帯への出稼ぎ者が増加するなど新たな矛盾を抱えることになった。ことに大正末期から昭和初期にかけての不況は、脆弱(ぜいじゃく)な県経済に打撃を与え「ソテツ地獄」と称される窮乏を招き、大量の移民や出稼ぎ者が発生した。経済を中心とする苦境の一方で、沖縄が日本社会に占める位置のあり方を歴史的・文化的に考えようとする伊波普猷(いはふゆう)らの沖縄学の運動も台頭する。だが、解決されないさまざまな矛盾を抱えたまま、やがて悲劇的な沖縄戦を迎えることになった。
[高良倉吉]
第二次世界大戦後の沖縄
本土進攻作戦の一環として、アメリカ軍は、後方支援部隊をあわせて延べ54万の兵力を沖縄戦に投入した。これを迎え撃つ日本軍は約10万といわれるが、その3分の1は沖縄現地で非常徴集された補充兵力にすぎなかった。戦力の劣勢を補うため日本軍は老幼婦女子・生徒までも戦力化することにし、また、一日でも戦闘を引き延ばしてアメリカ軍の本土進攻を遅らせる持久戦をとった。1945年(昭和20)3月下旬から開始されたアメリカ軍の進攻作戦に対し、日本軍の組織的戦闘は6月中旬にはほぼ終了したが、なおも沖縄島南部などで残存兵力によるゲリラ戦的抵抗を続け、牛島満(うしじまみつる)司令官の自決(6月23日)後もなおアメリカ軍は掃討戦を展開し、アメリカ軍が作戦終了を宣言したのはやっと7月2日になってのことである。
沖縄戦は住民をも巻き込んだ日本唯一の国内地上戦であり、県民生活の場がそのまま戦場となったところに特徴がある。しかも、短期決戦を目ざして物量戦を展開するアメリカ軍と、出血戦を前提に引き延ばしを図る日本軍がぶつかりあったため多数の犠牲者を出すことになった。日本軍将兵(沖縄県出身者を除く)6万5908人、アメリカ軍将兵1万2281人に対して、県出身軍人軍属2万8228人、一般住民9万4000人(沖縄県援護課調べ)の戦死者が出ている。兵士よりも住民死者のほうが多いというこの事実に、沖縄戦の性格が集約されている。しかも、住民戦死者数はまだ推定の域を出ておらず、実数はさらに多いといわれている。住民の集団自決、日本軍による住民虐殺などの異常事態も多発しており、沖縄戦の特徴の一つをなしている。沖縄戦は近代沖縄の「結論」であるといわれるが、同時にまた戦後沖縄の「起点」にも位置していたといえよう。
[高良倉吉]
アメリカ統治
アメリカ軍は早くも沖縄戦中に太平洋艦隊司令長官ニミッツの布告に基づいて軍政府を樹立(4月5日)して占領地行政を開始していたが、翌1946年1月に連合軍西南太平洋方面司令官であるマッカーサーは、日本と南西諸島の行政分離を宣言してアメリカによる沖縄確保の意向を打ち出した。冷戦の激化と中華人民共和国の成立(1949)および朝鮮半島における情勢の急変は沖縄の戦略的重要性を高め、アメリカは軍事目的のために沖縄を確保することを明確に決定するようになる。1949年から本格的な基地建設を開始し、1951年9月のサンフランシスコ平和条約(対日講和条約)により沖縄・奄美(あまみ)を日本から分離し自己の施政権下に置いた(奄美は1953年末に日本に返還)。こうして西太平洋におけるアメリカの戦略拠点としての基地オキナワが着々と形成されていったが、その一方でアメリカは基地機能の安定的維持のため各種の民政・復興事業を展開している。琉球政府の設立(1952)、基地依存型経済の創出などの諸施策が次々と実施されたが、しかしそのいずれも最終的には基地機能の確保を目ざす軍事目的の延長線にすぎなかった。したがって、基地優先主義のアメリカ統治は、住民生活との間にしばしば摩擦を生じた。基地建設に伴う土地の強制収用、基本的人権の抑圧・規制などをめぐる幾多の事件が頻発し、あるアメリカ軍高官は「ネコの許す範囲内でしかネズミは遊べない」と豪語したほどである。
[高良倉吉]
本土復帰運動
こうした状況下で住民の権利意識、政治意識が高揚し、1950年代中ごろの土地闘争を画期にしだいに諸要求は祖国復帰運動へと収斂(しゅうれん)していった。1960年に復帰協(沖縄県祖国復帰協議会)が結成されると、復帰運動は人権擁護・反戦平和運動へとしだいに発展し、住民の大多数の声を結集する一大県民運動にまでなった。1965年の佐藤‐ジョンソン共同声明は、沖縄のもつ戦略上の意義とアメリカの施政権の保持を日本、アメリカ双方で了承するにとどまったが、しかし県民の強い要求の前に、1969年の佐藤‐ニクソン会談では1972年の返還を実施する旨声明せざるをえなかった。
この間、ベトナム戦争の前進基地として沖縄が使われたため社会的にさまざまな問題を惹起(じゃっき)し、復帰運動の反戦平和運動としての性格をますます強めることとなり、教公二法闘争(1967)、屋良朝苗(やらちょうびょう)公選主席の誕生(1968)など革新勢力の相次ぐ前進を生み出している。1972年5月15日、沖縄は日本に復帰したが、基地オキナワを温存したままでの復帰だったため、その後になお多くの問題を残すこととなった。
[高良倉吉]
復帰後の諸問題
復帰後、政府による沖縄振興開発事業によって社会資本の整備は著しく進展をみせ、またこれに連動する民間企業の開発も観光・リゾート分野を中心に急速な展開をみせた。その結果、県経済は順次拡大し県民生活は以前にはみられない豊かさを享受するようになった。この意味で、復帰後の沖縄は「経済の時代」だったといえる。しかし、基地経済の比重は小さくなったものの、それにかわって政府の財政支援などに依存する経済体質が顕著となり、「自立経済」の構築を目ざす新たな目標が力説されている。本土との経済格差は依然として横たわったままであり、自立経済への具体的な展望も十分にみいだせないまま推移しているのが現状である。
その一方で、政治、行政、経済など多くの分野で本土社会との系列化が進行し、地元マスコミには「本土化」「ヤマト化」の危機を訴える記事がしばしば掲載された。また、経済開発などに伴う自然・環境の破壊も進行しており、伝統的な景観も急速に失われつつある。だが、生活の豊かさは伝統文化の見直し、新しい文化の創造に拍車をかけた。とくに音楽・文学・スポーツ分野の隆盛は目覚ましく、沖縄ポップスの本土展開、芥川賞受賞作品の登場、沖縄尚学(しょうがく)高校による選抜高等学校野球大会優勝(1999)は文化現象とみなされた。
だが、1995年(平成7)9月に起こった沖縄米兵少女暴行事件は、基地オキナワの現実が厳然と横たわり県民生活を圧迫していることを改めて明らかにした。当時の県知事大田昌秀(おおたまさひで)は在日アメリカ軍基地の約75%が沖縄に偏在している不公正を強く主張するとともに、沖縄戦体験に基づく県民の平和意識を力説して、基地の整理・縮小を強く求めた。1996年には当時の首相橋本龍太郎との会談から沖縄政策協議会が設置され、大田県政は政府との対立を含みながら沖縄の主張を続けたが、1998年11月の知事選挙において政府との協調関係の保持、基地問題の漸進的解決を主張する稲嶺恵一(いなみねけいいち)に敗れた。
なお、2000年7月に先進国首脳会議(九州・沖縄サミット)が開かれ、クリントンが沖縄を訪れたが、これは復帰後初めてのアメリカ大統領の沖縄訪問であった。
[高良倉吉]
産業
経済の特質
第二次世界大戦後の沖縄経済は、27年間に及ぶアメリカの統治と日本復帰後に大きく区分される。前者は、戦後沖縄経済の形成過程であり、米軍基地需要を中心に主要な産業や企業を創出してきた。とくに、アメリカ・ドルを通貨としたため生産による供給よりは輸入による供給が卓越し、工業の立ち遅れと流通・サービス業の進展を促進し、第三次産業中心の経済が形成された。
復帰後は、政府支出と観光収入を両輪に経済が進展し、一段と第三次産業中心の性格が強まった。沖縄国際海洋博覧会の開催(1975.7~1976.1)、沖縄海邦国体の開催(1987)という二大イベントをテコに経済は大きく成長したが、反面、財政依存度が構造的に高く、自立化を妨げる要因となっている。
また、戦後一貫して県人口は増加し続け、1940年(昭和15)は57万4579であったのが、1960年88万3122、1980年110万6559、2000年(平成12)131万8220、2010年139万2818人、2015年143万3566人、2020年146万7480人を数え、人口増加率は全国的にもトップグループに属し、自然増加率は日本一である。人口の増加を反映して県経済は着実に成長している。しかし、失業率は3.3%(2020年平均、総務省)と全国平均(2.8%)の1.2倍近くもあり、雇用機会の創出と経済の自立化が直面する大きな課題となっている。
[真栄城守定]
産業構造
産業構造は第二次世界大戦後大きく転換した。戦前と比較すると、第一次産業と第三次産業の占める比重がまったく入れ替わっている。戦前が「農業社会」であったのに対し、戦後は「三次産業社会」、つまりサービス経済が圧倒的に卓越する社会となった。この産業構造の一大転換はアメリカ軍基地の建設が引き金となっており、三次産業化が促進される一方で、一次産業は急速に低下の過程をたどった。戦後の一時期、食糧の自給化を目ざして一次産業が大きなウェイトを占めたことがあるが、しかし、アメリカ軍基地の建設により新たな需要が生じると、農村地域から基地周辺地域への人口移動が急速に進み、三次産業化が実現する。この基地建設によって戦後沖縄の産業構造の骨格がつくられたが、その後、B円(B型円、アメリカ軍票のこと)から米国ドルへの通貨の切り替え(1958)による貿易の自由化、あるいは砂糖生産を主軸とする農業のモノカルチュア化、ベトナム戦争による特需ブーム、日本復帰、海洋博、海邦国体開催などの諸要因によって産業構造は多様化している。
概して、日本復帰以前は基地依存型の経済であり、復帰後は財政主導型の経済にそのリーディング・セクターが移行した、といえる。とくに復帰後に特徴的なことは、公共投資の増大に連動して建設業のシェアが拡大したことであろう。海洋博開催に伴う公共工事をはじめ、本土との格差是正のための社会資本への投資、あるいは住宅建設等の増大が建設業拡大の要因となっている。また、海洋博の開催は、その効果として観光の驚異的な伸長を促進し、観光が第三次産業の支柱としての役割を果たす契機となった。近年、産業構造は依然として第三次産業に偏重しながらも、その内部で基地関連から観光関連へと比重が入れ替わる大きな変化をみせている。「沖縄振興開発計画」(1972年12月閣議決定)は、そのねらいとして産業構造のバランスを掲げ第二次産業化を図ったが、実勢はむしろ第三次産業が根強く定着した。また、意図した第二次産業の拡大も、製造業は停滞気味に推移、建設業だけがそのシェアを広げたにすぎない。
[真栄城守定]
部門別の状況
以上、産業構造についてマクロの面からみたが、次にミクロの面から部門別に解説すると、まず第一次産業、とくに「農業」は次のような特徴と変化をもつ。作目構造としては現在サトウキビ単作が定着しているが、実はサトウキビは1960年代以降の沖縄農業を根底から変化させた作物である。第二次世界大戦後、食糧自給を余儀なくされたため甘藷(かんしょ)、水稲が長く作目の主座を占めていたが、沖縄産糖特恵措置の閣議決定(1959)を契機に糖業振興策が展開され、サトウキビ作への傾斜が急速に進行した。甘藷畑、水田などの甘蔗(かんしょ)畑への転換、原野の開墾が行われた。このサトウキビへのモノカルチュア化は、サトウキビが価格保証された安定的な作目であったこと、主食である米を安価なアメリカのカリフォルニア米の輸入によって供給できたこと、さらにはキューバ革命による国際糖価の急上昇があったこと、などを背景に進行したものである。
サトウキビ単作構造の出現は戦後沖縄農業の一大変革であり、兼業農家の増加への大きな引き金となり、農業構造や社会構造の各面にまで深く影響を及ぼすほどのものであった。しかし、1990年(平成2)以降、サトウキビの生産は価格の低迷、従事者の高齢化などを反映して減少し、精糖工場の統廃合が始まっている。なお、サトウキビと並んでパイナップルも換金作物として戦後定着をみせたが、近年国際競争の面からしだいに衰退しつつある。野菜は日本復帰後に県外出荷が実現し、全国市場へ進出するようになったが、特産のゴーヤー(ニガウリ)は増加したものの、県外出荷量は伸び悩んでいる。一方、キクを中心とする花卉(かき)類、マンゴーなどの果樹類は急速な伸びをみせている。サトウキビ単作の農業構造から作目の多様化へと向かいつつある。肉用牛の飼養頭数は増加を続け、2010年には8万5000頭にのぼっている。
第二次産業については、建設業と製造業の盛衰が特徴的である。公共投資と民間建設活動に依存して建設業は大きな伸びを示しているが、他方、製造業は低迷・停滞を続けている。復帰前、県産品保護策のもとで成立していた県内製造業も、復帰後の本土商品の攻勢を受けて淘汰(とうた)されたものが多い。製造業内部の変化も大きく、基本的には建設関連業種と食品関連業種に限られてきている。しかし、食品関連では特産品開発と連動して、多様な製品が生産され、アンテナショップを全国主要都市、台湾、シンガポールに展開し、全国的に注目されている。なお、CTS(石油備蓄基地)建設に伴い石油精製業等の石油関連業種が、生産額および輸出額で大きなシェアを有していることも特徴的であろう。
水産業は、おもに鮮魚生産を中心とした日帰り操業で、同時に、1970年代後半ごろから、クルマエビやモズクなどの養殖業が盛んになっている。林業は未発達で、わずかにパルプ用材や特用林産物を生産している。また鉱業も資源に恵まれず、セメント原料や路盤材の産出がみられる程度である。
伝統工芸は、琉球王国時代の遺産として継承され、琉球絣(がすり)、久米島紬(つむぎ)、宮古上布(じょうふ)、八重山上布、芭蕉布(ばしょうふ)などの織物をはじめ、陶器、漆器、染物(紅型(びんがた))などきわめて多様である。また第二次世界大戦後、ガラス工芸も定着している。伝統工芸は年間57億6000万円(1982)の生産実績をあげるなど、観光の進展と相まって土産(みやげ)品としての魅力と地歩を築いてきたが、近年は漸減傾向にある(2010年41億円)。
観光産業は沖縄の重要な産業となっていて、近年では国際的な観光・リゾート地としての発展をみせている。西表石垣国立公園(いりおもていしがきこくりつこうえん)、沖縄海岸国定公園、沖縄戦跡国定公園があり、自然、文化遺産、伝統芸能などの観光資源に恵まれ、2010年には572万人の観光客が訪れている。
復帰前は基地依存、復帰後は財政支出依存という県経済の体質は他律型という点では変化がない。所得水準も全国平均の約70%であり、産業開発の課題は大きい。なお、復帰後、第一次(1972~1981)、第二次(1982~1991)、第三次(1992~2001)にわたる沖縄振興開発計画が国によって策定され、それに基づいて自立的発展のための基礎条件の整備等が推進された。2002年には新たな「沖縄振興計画」が策定された。また沖縄振興開発特別措置法により、特定免税店制度、自由貿易地域制度など沖縄独自の制度が設けられている。
[真栄城守定]
交通
広い海域に分布する島嶼だけで形成され、しかも日本の最西端、最南端に位置するという特性が交通の特性をも大きく規定している。交通網は沖縄島を中心に編成されており、県外および県内主要離島は那覇市を拠点とする航空機や船舶によって結ばれている。かつては県営鉄道が走っていたが第二次世界大戦後の陸上交通は自動車に依存している。2003年(平成15)8月10日那覇市内12.9キロメートル(那覇空港―首里間)に沖縄都市モノレール(ゆいレール)が開通した。なお、宮古列島は宮古島市、八重山列島は石垣市をそれぞれ拠点に、那覇市および列島内各離島と航空機、船舶で連絡している。
[真栄城守定]
航空路
航空路は国内線、県内線、国際線が開設されている。国内線は日本航空と全日空を中心に日本トランスオーシャン(JTA)が就航し、東京、大阪、福岡、名古屋をはじめ、東北、北陸、中・四国、九州のほぼ国内全域と結び、観光の伸長とともに輸送能力の増加が著しい。なお、宮古、石垣は東京、大阪、福岡、中部便が毎日就航している。県内線はJTA、全日空、琉球エアーコミューター(RAC)が担当し、宮古島、石垣島、久米島、南大東島、北大東島、与那国島が那覇と直接結ばれ、宮古島からは石垣島と多良間島へ、石垣島からは与那国島へそれぞれネットされている。また、RACは鹿児島県の与論島と那覇を結んでいる。国際線は、那覇から台北(チャイナエアラインなど)、ソウル(アシアナ航空など)、香港(ホンコン)(香港航空など)、上海(シャンハイ)(中国東方航空など)へは毎日、北京(中国国際航空)、シンガポール(ジェットスター)などへは週数便の割合で就航している。
[真栄城守定]
航路
船舶も、航空機同様、国内、県内、国際の各航路がある。国内は奄美諸島、鹿児島、阪神、東京と結んでいる。おもな県内航路は那覇市、宮古島市、石垣市をそれぞれ拠点に編成されているが、そのほかにも各地、各離島にサブ拠点があって航路がネットされており、離島住民の生活航路、観光客輸送、物資輸送に大きな役割を果たしている。
[真栄城守定]
陸上交通
第二次世界大戦後、長く鉄軌道がなかったため、全面的に自動車に依存しているのが特徴的である。公共交通はバス、タクシーが担当しているが、個人交通としての自家用車の普及がかなり進んでいる。自動車の普及は2人に1台の割合に達し、この急速な増加に道路整備が追いつかない状況下で、那覇市をはじめとする既成市街地で交通渋滞が大きな社会問題となっている。沖縄島ではバス路線網がかなり発達しているが、自家用車の普及に伴ってバス離れ現象が生じ、路線網の再編成や企業経営の立て直しが課題となっている。なお、沖縄自動車道(名護市―那覇市間)は1987年に全面開通し、2000年に那覇空港自動車道も一部開通、2003年には那覇市の沖縄都市モノレールが開通した。宮古島、石垣島、西表島でもバス路線がある程度整備されている。
[真栄城守定]
社会・文化
伝統文化の推移
奄美諸島から沖縄諸島、先島諸島に至る島々には古くから琉球文化(あるいは沖縄文化)と総称される独自の文化圏が形成されていた。この文化は日本文化の明確な一環であり、日本文化の源流と深い結び付きをもつ文化であると同時に、たとえば日本語が本土方言と琉球方言(琉球語)に2大別されるように、日本本土の文化(狭義の日本文化)に対して強い独自性を発揮する文化として知られている。そのことは言語の面だけでなく、宗教、民俗、芸能、文学、美術工芸などのあらゆる面で顕著である。琉球文化のもつ、こうした独自的な性格を生んだ背景として考えられる点は三つある。
一つは、これらの島々が一方では広大な海域に分布するため、他と隔絶された孤立的な環境下で歴史、文化を形成したこと。二つ目は、他方では東アジアに独自の地理的位置を占めるため、日本本土はもとより中国、朝鮮、東南アジアなどの文化的影響をさまざまな形で受けたこと。そして三つ目は、15世紀初期から琉球処分(1879)までの450年余にわたって独自の国家(琉球王国)をこれらの島々が生み出したこと、であろう。
以上の背景をもって形成された琉球文化は、大づかみにみると二つのレベルに区分してとらえることができる。一つは村落共同体レベルで形成されたものであり、言語、宗教、祭祀(さいし)、芸能、民俗など琉球文化の基盤、根幹をなすものである。いま一つは首里の王朝を中心に開花したもので、共同体レベルの文化のうえに海外の文化を取り入れて形成され、美術工芸、文芸、音楽、舞踊、建築などの分野で洗練され様式化された文化として発展した。しかし、王朝レベルの文化は、琉球処分により王国が崩壊するに及んで多くは消滅し、そのなかの一部のもの(たとえば三線(さんしん)=琉球三味線、音楽、舞踊、漆芸など)が民衆生活のなかに受け継がれ存続したにすぎない。一方、村落共同体レベルの文化も、琉球処分後の近代において日本本土への一体化政策が推進されたため、しばしば遅れた野蛮なものとして排斥された。たとえば、方言の使用を禁じて標準語の普及を強制するために、学校教育で「方言札(ふだ)」を常用して方言を使う生徒を罰することが行われた。しかし、こうした規制、禁圧の波にさらされながらも、共同体レベルの伝統文化の根幹は沖縄の各地で着実に受け継がれていった。
[大城将保・高良倉吉]
第二次世界大戦後の社会変動とその特徴
伝統文化を根底から揺り動かしたのは、沖縄戦とそれに続くアメリカ統治下での戦後の激動であったといえよう。戦争は幾多の人命を失わせたばかりでなく、文化遺産や生活基盤をも灰燼(かいじん)に帰した。しかも沖縄は日本本土から分離され、アメリカの直接統治下に置かれることになり、広大な軍事基地が建設されて多数のアメリカ兵が至るところに氾濫(はんらん)する状況となった。人々はこうした激しい時代の変転を「ヤマト(日本)世(ゆー)」から「アメリカ世」への「世替り」と称した。「アメリカ世」はそれまでにない状況を沖縄の社会にもたらした。
(1)まず「基地オキナワ」の出現である。農地や宅地、墓地が接収されて広大なアメリカ軍基地が各地に建設されたばかりでなく、多くの住民が基地労働者や基地関連サービス業に従事するという基地依存のいわゆる「基地経済」が成立した。
(2)それに伴い基地の集中する沖縄島中南部に地方、離島からの人口の流入がおこり、「基地の街」化あるいは都市化が急激に進んだ。旧コザ市(沖縄市)などは基地のゲート前面に発達した典型的な「基地の街」である。
(3)他方、農村、離島では深刻な過疎化がおこり、伝統的な村落共同体の維持さえ危ぶまれる状況となった。このことは、「基地経済」を中心とする第三次産業(サービス経済)が肥大化を遂げる一方で、第一次産業、とくに農業は衰退するという経済構造の変化に連動するものであった。
(4)また「アメリカ世」は、アメリカ型の消費生活、物質文化、価値観をもたらしたので、世相、人心も大きく変化し始めた。戦前までの貧困を相対的に脱しつつあった県民の間で、日本式の生活様式とともにアメリカ式の生活様式も生活の一部に浸透し始めた。
このように、「アメリカ世」は、県民にとってまさしく異質な文化的・社会的衝撃であったといえよう。
こうした状況のなかで、県民の意識構造に大きな変化が現れ始めた。そのもっとも基本的な点は、「アメリカ世」という一種のカルチャー・ショックに遭遇したことにより、自らのアイデンティティの回復を求めて伝統文化への回帰とウチナーンチュ(沖縄人)意識を強烈にもち始めたことだろう。そのことは、たとえば基地の街として形成された旧コザ市において、伝統的な地縁・血縁によって結ばれた人間関係が濃密に成立し、精神的には戦後社会の情感を歌い上げるおびただしい数の民謡が生まれ歌われたことによく象徴されている。つまり、「アメリカ世」に直面して自分たちの文化的伝統を見つめ直し、そのことによって、自らのアイデンティティを回復する営みが随所に展開された。
[大城将保・高良倉吉]
アメリカ世からヤマト世へ
「アメリカ世」に対置するアイデンティティの回復は、一方では民族的自覚の問題につながっていた。第二次世界大戦後の一時期、「琉球独立論」などもささやかれたが、しかし大多数の県民は自らが日本人であり、沖縄もいずれ早い時期に日本社会に復帰すべきであると考えていた。たとえば、学校教育において教師たちの熱意により日本語による教育、日本の教科書による教育、つまり「日本国民としての教育」が早い時期から意識的に推進された。こうした民族的自覚の高揚が、日本復帰運動の支柱の一つとなったのである。
「アメリカ世」の政治的現実は、アメリカの軍事優先主義、県民の無権利状態であった。県民の側の政治的要求がしばしばアメリカ側によって強権的に圧迫されたばかりでなく、アメリカ兵の理不尽な犯罪が治外法権を盾に無罪もしくはうやむやにされた。こうした現実下で当然のことながら政治的権利の回復、基本的人権の確保が切実な課題となり、この要求が復帰運動の二つ目の支柱となった。沖縄の歴史始まって以来といわれるほどに県民の政治的意識が高まり、それが復帰運動の大きなうねりとして発現したのも戦後の基本的な特徴の一つである。また、復帰運動の三つ目の支柱として、沖縄戦における過酷な戦場体験とその反省にたつ平和への希求があったことも忘れてはならない点だろう。
こうした3本の支柱に支えられた復帰運動は、多くの県民を結集して1960年代以後活発となり、1972年(昭和47)5月15日、ついに宿願の日本復帰は実現した。「アメリカ世」から「ヤマト(日本)世」への世替りである。
[大城将保・高良倉吉]
復帰後の特徴
復帰後の特徴としては次の点があげられる。
(1)「アメリカ世」時代には保障されなかった政治的権利、基本的人権が制度的に保障されるようになったこと。
(2)しかしその一方で、全国の米軍専用基地の75%が集中する「基地オキナワ」で当初約束された基地の整理・縮小は進まず、軍用地の強制使用、実弾演習や爆音による被害、米兵犯罪などの多発のほか、地域開発の障害にもなり、基地は諸悪の根源といわれた。
(3)本土社会との格差を是正するために国庫による大規模な投資が行われ、生活基盤、社会資本が飛躍的な充実をみせ、本土並みの水準に急速に近づきつつある点も特徴の一つである。
(4)消費生活水準も全体として急速にレベルアップし、経済生活の面でこれまでにない豊かな状況が現出した点も見逃せない。
(5)しかし一方では、日本復帰によって本土社会との間に各分野で急速な系列化が進み、県民意識、生活の面で「本土化」とよばれる変動が進行している。
(6)これに対し、県民の間で文化的伝統への積極的な関心も高まり、自らのアイデンティティの確立を求める気運も強まってきている。そのことは、伝統文化とそれに立脚する文化創造の隆盛ぶりによく現れている。
[大城将保・高良倉吉]
伝統文化の隆盛
有形の文化遺産の多くは、沖縄戦で灰燼(かいじん)に帰した。戦前までは琉球王国時代の粋を伝える21件もの国宝指定文化財が存在したが、そのすべてが砲弾で破壊された。しかし、戦火を免れた史跡、名勝などが各地にまだかなり残っており、歴史や文化を語りかける素材として重視されている。1992年(平成4)には沖縄戦で焼失した首里城が復元された。一方、無形の技術、技能を生かした文化遺産は戦争や戦後の激動をくぐり抜けてますます盛んとなっている。たとえば、琉球舞踊、三線(琉球三味線)を中心とする芸能分野では、各地におびただしい数の私設の研究所があって後継者を養成しており、発表会、演奏会がしきりに開かれている。しかも、舞踊、音楽は専門家が演じるだけでなく、家庭、宴席および酒席など日常生活のあらゆる場面で一般の県民によって演じられており、広い裾野(すその)に支えられている。こうした文化的土壌に支えられる形で、1980年代末期から、りんけんバンドや喜納昌吉(きなしょうきち)などによって代表される沖縄ポップスが台頭し、全国的に知られるようになった。なお、2004年1月には、おもに琉球舞踊など伝統芸能の保存振興を目的とした国立劇場おきなわが開場した。
観光客の急増に伴い、土産品としても脚光を浴びている伝統工芸は、種々の問題をはらみながらも盛んに生産されている。陶器や漆器あるいは紅型(びんがた)に代表される織物をはじめとして、ガラス工芸、菓子類などが着実に生産されている。沖縄を代表する酒泡盛(あわもり)も各地で生産されており、また、琉球料理も家庭だけでなく専門の料理店で賞味することができる。空手(からて)は各地に多くの道場があり、その鍛錬にいそしむ人が多い。沖縄独特の年中行事、民俗芸能も各地で盛んであり、ウヤガン(宮古島)、アカマタ・クロマタ(八重山)などの神秘的な神行事もなお受け継がれている。
[大城将保・高良倉吉]
沖縄研究と文学・芸術
伝統文化の隆盛に加えて、沖縄では沖縄学=沖縄研究と称される学問研究も盛んである。地元の琉球大学(国立大学法人)、県立芸術大学、県立看護大学、名桜大学(公立)、沖縄国際大学、沖縄大学、沖縄キリスト教学院大学、沖縄科学技術大学院大学(以上4校私立)などの大学をはじめ(2018)、公立の試験研究機関や学会、研究会に所属する多くの研究者によって推進されており、県外の研究者、県内のアマチュア研究家も多く、県民もまたこの学問に対して強い関心を払っている。1980年代からは諸外国との学術交流も活発化し、外国人研究者も沖縄をテーマとする研究に取組みはじめた。とくに中国や台湾との交流は目覚ましく、アジアの視野で沖縄の歴史・文化を検討する動きが盛んとなった。そのことを反映して出版も隆盛を極め、県内外で出版される沖縄関係図書は年間300点前後に及ぶといわれている。
文学、芸術分野の活動も活発である。共通した傾向は、沖縄をテーマとし沖縄のなかから素材をみつけるという態度であろう。芥川(あくたがわ)賞受賞作である大城立裕(おおしろたつひろ)『カクテル・パーティー』(1967年受賞)、東峰夫(ひがしみねお)『オキナワの少年』(1971年受賞)、又吉栄喜(またよしえいき)『豚の報い』(1995年受賞)、目取真俊(めどるましゅん)『水滴』(1997年受賞)は戦後沖縄の現実を題材とした代表的な作品である。
[大城将保・高良倉吉]
県民意識と生活
(1)新聞・報道の役割 文化活動に対する『沖縄タイムス』『琉球新報』の地元2紙の役割はきわめて大きい。新聞購読者の大半のシェアを占めるこの2紙は、文化活動に対して戦後一貫して牽引車(けんいんしゃ)的な役割を発揮してきた。テレビ、ラジオはNHKのほかに琉球放送、沖縄テレビ、琉球朝日放送、ラジオ沖縄、FM沖縄などがあり(2018)、いずれも沖縄に関する自主企画番組を編成して地域文化の振興に一役買っている。
このように郷土の文化的伝統への愛着・執着、あるいは「県人意識」(ウチナーンチュ=沖縄人意識)の強烈さという点で他県にはみられない状況を呈している。この傾向は本土に居住する県出身者、ハワイ、南米など海外諸国に居住する県出身移民の間にも共通にみられる点で、郷土愛の強い県民性としてしばしば指摘されている。
(2)信仰形態と門中(もんちゅう) 信仰は伝統的な祖霊、祖先神信仰を中心にいまなお根強く保持されており、とくに祖先崇拝とこれに支えられた各種の年中行事はたいせつにされている。また、独特の造型をもつ大きな亀甲墓(かめこうばか)に代表されるように、墓には金をかけ供養を怠らない伝統をもつ。仏教の影響は他県に比べてかなり少なく、寺院の数も限られている。王国時代における中国との交流を反映して道教的習俗がみられ、第二次世界大戦後のアメリカ統治時代の影響もあってキリスト教もいくぶん定着している。しかし、全体としてみると固有信仰が社会的に大きな比重を占める点が、特徴の一つである。また、血縁・地縁に基づく交際が重視される点も特徴の一つで、門中とよばれる独特の親族集団内での交際や都市地区における出身地ごとの郷友会、村人会活動が活発である。民間金融としての役割をもつ模合(もあい)(頼母子講(たのもしこう))も盛んで、しばしば交際、親睦(しんぼく)を目的とする集会手段として活用されている。
社会的には農村地区、都市地区を問わず公民館を中心とする伝統的なコミュニティ活動が盛んであり、とくに都市地区以外ではシマとよばれる集落(字(あざ)に相当)が生活母体として強固に維持されており、シマ単位の各種の活動(年中行事、PTA活動など)が展開されている。
[大城将保・高良倉吉]
沖縄の神話
総じて「沖縄」は地域名、「琉球」は文化圏として用いるため、「琉球神話」とよぶべきであろう。琉球神話は、文献に記載された王朝神話と、民間に伝承された祝詞(のりと)、巫歌(ふか)、歌謡、伝説などに現れる民間神話とに大別される。文献上の初出は、袋中和尚(たいちゅうおしょう)の『琉球神道記(しんとうき)』(1605)で、それによると、「アマミキュ」「シネリキュ」という男女2人が天降りして波間に漂う島から沖縄の国土を形成し、往来の風によってはらんで3子を産み、長子は所々の主(ぬし)、次子は祝(のろ)、三子は土民の始めとなったと記されている。また『おもろさうし』第10巻(1623)にはテダ(日神)が「アマミキヨ」「シネリキヨ」を召して島造りを命じたとあり、かつては太陽信仰が絡んでいた様相がうかがえる。さらに『中山世鑑(ちゅうざんせいかん)』(1650)に至ると、日本の記紀神話や漢籍の影響が強くなる。それによると天帝は阿摩美久(あまみく)を下界に降し、土石(どせき)を用いて島造りをさせ、その要請により天帝の男女の御子を降し、風によってはらんで生まれた3男2女が、国々の主(天孫子(てんそんし))、諸侯、百姓、君々(きみ)、祝女(のろ)の始めとなったと記されている。これに穀物起源神話も加わって、阿摩美久が天上から五穀の種をもらい受け、麦、粟(あわ)、菽(しゅく)(豆)、黍(きび)を久高(くだか)島に、稲を知念(ちねん)・玉城(たまぐすく)(南城市)に播(ま)いたという。これらの神話の共通要素は、天界出自の男女2人の始祖神による人類起源、波間に漂う島からの国土生成、王朝の政治・宗教的支配による階層秩序の呈示、王朝の収穫儀礼の行われる聖地と穀物起源を結び付けて語ること、などである。
一方、文献にみえる神話に対し、民間に伝承された神話によれば、東方の海上の島にいる女神の漂着による始祖の話や、古宇利(こうり)島などに伝わる近親相姦(そうかん)による兄妹始祖伝説、アマンチューという巨人の天地分離による世界創造の伝説などがあり、別系統の創世神話を伝えている。これらは包括的な神話体系を形成するまでには至らず、奄美(あまみ)から、沖縄、宮古(みやこ)を経て八重山(やえやま)に至る琉球諸島各地では、さまざまな系統の神話が混ざり合っている。
琉球神話の特徴を神話学者大林太良(おおばやしたりょう)(1929―2001)の見解に基づいて整理すると、(1)なんらかの形での兄妹始祖神話はこれらの地域に共通して存在する。(2)モチーフは北部の奄美・沖縄と、南部の宮古・八重山に大別され、流れ島、風によってはらむ、世界分離巨人は北部から、犬祖(けんそ)伝説、地中よりの始祖の出現は南部から、それぞれ報告されている。(3)琉球の王朝神話は共通した要素を持ち伝えているが、そのうち流れ島、風によりはらむというモチーフは、沖縄でも後世には凋落(ちょうらく)し、宮古・八重山へは伝播(でんぱ)していない。(4)民間神話のモチーフは始祖漂着、生み損ない、犬祖、地中よりの始祖、世界分離巨人などである。これらは一複合体を形成せず、したがって王朝文化に対する民間の基層文化にはかなりの地方差や系統差があったことが指摘される。総じてこれらの神話や伝説は、日本、朝鮮、華南などの文化系統を比較する際の指標とされ、生業や社会集団との結び付きを通して相互の文化伝播(でんぱ)の様相を明らかにしうるものと考えられている。沖縄の神話は、その結節点として重要である。
[鈴木正崇]
伝説
沖縄本島や先島(さきしま)諸島は亜熱帯に位置するだけに、竜宮、大魚報恩、漂流、津波、島の成立など海に関する神話、伝説が豊富である。津波伝説は南太平洋の島々にも伝承されているが、多良間(たらま)島では、兄妹が津波に遭難して生き残っていっしょになり、この島で栄えた。その子孫から土原豊見親(んたばるといみや)のような勇士が生まれたという。来間(くりま)島では、敗残の兵に追われて無人島に泳ぎ着いた兄妹が、やはり夫婦になって村建てをしたという。沖縄では村をシマというが、その神事をつかさどるのは祝女(のろ)で、他人のうかがうことを許さぬ御嶽(うたき)には、独特の伝説を生む要素をもつ。八重山(やえやま)列島のアカマタ・クロマタは海のかなたから豊穣(ほうじょう)をもたらしてくる神々の秘儀で、常世(とこよ)信仰のニライカナイに裏づけられた伝説によっている。沖縄の神々の信仰には洞窟(どうくつ)を宮としたものが多くある。那覇市首里桃原(しゅりとうばる)の女が芭蕉布(ばしょうふ)の糸を紡いでいるところを見られ、糸巻きの管(くだ)をくわえて去り、普天間(ふてんま)(宜野湾(ぎのわん)市)の洞窟に消えた。女は洞窟の神となったという。洞窟の中は神秘をはらむ神域であって、みだりに入ることを許されない。これなども洞窟に対する沖縄人の信仰からきた伝説ということができる。英雄伝説には、為朝(ためとも)、百合若(ゆりわか)、カニカマド、目黒盛豊見親(めぐろもりといみや)、サカイイソバ(サンアイイソバ)など多い。為朝は伊豆を逃れて沖縄に上陸し、豪族の女(むすめ)をめとったが、その子は琉球王統となったと伝える。北九州の巨人百合若説話が沖縄水納(みんな)島に根づいている。百合若のかわいがったタカの墓と称するものまであり、日琉同根の伝説となっている。巨人カニカマドは八重瀬城(やえせぐすく)に、勇士目黒盛豊見親は宮古島に、女酋(じょしゅう)サカイイソバは与那国(よなぐに)島に、いずれも怪力の巨人、もしくは知謀武略の英雄伝説になっている。沖縄にも「真玉橋(まだんばし)の人柱」など、いくつかの人柱伝説がある。真玉橋の主人公は七色の元結(もとゆい)をした女性で、自ら人柱になったが、死後その女性の子供は口がきけなくなったというモチーフは、本土の影響が濃厚である。八重山列島の島民は人頭税や島分けという過酷な政策を課せられ、その悲劇から石垣島の「野底(のそこ)マーペー」などの悲しい伝説を生んでいる。
[武田静澄]
『鳥越憲三郎著『琉球の神話』(1966・淡交社)』▽『沖縄タイムス社編・刊『沖縄の証言』上下(1971、1973)』▽『大城立裕著『内なる沖縄』(1972・読売新聞社)』▽『新里恵二他編『沖縄県の歴史』(1972・山川出版社)』▽『大林太良著『琉球神話と周囲諸民族神話との比較』(『沖縄の民族学的研究――民俗社会と世界像』所収・1973・民族学振興会)』▽『新崎盛暉著『戦後沖縄史』(1976・日本評論社)』▽『『講座 日本の神話10 日本神話と琉球』(1977・有精堂出版)』▽『高良倉吉著『琉球の時代』(1980・筑摩書房)』▽『木崎甲子郎編『琉球の自然史』(1980・築地書館)』▽『大田昌秀編著『総史沖縄戦』(1982・岩波書店)』▽『嶋津与志著『沖縄戦を考える』(1983・ひるぎ社)』▽『『沖縄大百科事典』本巻3・別巻1(1983・沖縄タイムス社)』▽『上野英信著『眉家私記』(1984・潮出版社)』▽『目崎茂和著『琉球弧をさぐる』(1985・沖縄あき書房)』▽『木崎甲子郎編『琉球弧の地質誌』(1985・沖縄タイムス社)』▽『外間守善著『沖縄の歴史と文化』(1986・中央公論社)』▽『『角川日本地名大辞典47 沖縄県』(1986・角川書店)』▽『鹿野政直著『戦後沖縄の思想像』(1987・朝日新聞社)』▽『鹿野政直著『沖縄の淵――伊波普猷とその時代』(1993・岩波書店)』▽『高良倉吉・田名真之編『図説・琉球王国』(1993・河出書房新社)』▽『牧野浩隆著『再考沖縄経済』(1996・沖縄タイムス社)』▽『『沖縄を知る事典』(2000・日外アソシエーツ)』▽『『日本歴史地名大系48 沖縄県の地名』(2002・平凡社)』▽『『沖縄を深く知る事典』(2003・日外アソシエーツ)』▽『新崎盛暉著『沖縄現代史』(岩波新書)』▽『高良倉吉著『琉球王国』(岩波新書)』
沖縄(市)
おきなわ
沖縄県沖縄本島中南部にある市。1956年(昭和31)6月中頭(なかがみ)郡越来(ごえく)村がコザ村と改称し、7月市制施行。1974年美里(みさと)村と合併して沖縄市と改称。越来の方音はグイク。「コザ」は、第二次世界大戦後、アメリカ軍が呼称していたキャンプ「コザ」に由来する。市域の地形は、おおむね丘陵状の台地からなり、中央部は標高100メートルの台地で、その両側に谷を挟んで60~70メートルの台地が続く。東側の台地は40メートルの落差をもつ段丘で、海岸に沿って低地を形成。国道329号、330号が走り、沖縄自動車道が市域を縦貫する。第二次世界大戦前の越来村は人口8000人程度の純農村。アメリカ軍上陸後、沖縄で初めての難民収容所が設けられ、人口が急増した。越来村北部は嘉手納基地(かでなきち)などに接収され、村の63%が軍用地になった。基地の恒久化に伴って基地周辺の都市化は著しく、基地依存の強い「基地の町」として成長した。市域の34.0%(2022)が基地。基地都市のイメージから脱却するため「国際文化観光都市」を宣言、国際色豊かなリゾート拠点づくりが進められている。市街地周辺の農地ではサトウキビ、花卉(かき)が栽培され、酪農が行われている。知花城跡(ちばなじょうあと)の旧跡のほか、東南植物楽園やレジャーランド「沖縄こどもの国」、市立郷土博物館がある。闘牛も名物。旧盆明けに行われる沖縄全島エイサー祭りは県下最大のエイサー祭りとしてにぎわう。面積49.72平方キロメートル、人口14万2752(2020)。
[堂前亮平]
『『コザ市史』(1974・コザ市)』▽『『沖縄市史』全13巻(1984~ ・沖縄市)』
改訂新版 世界大百科事典 「沖縄」の意味・わかりやすい解説
沖縄[県] (おきなわ)
基本情報
面積=2276.15km2(全国44位)
人口(2010)=139万2818人(全国30位)
人口密度(2010)=611.9人/km2(全国9位)
市町村(2011.10)=11市11町19村
県庁所在地=那覇市(人口=31万5954人)
県花=デイコ
県木=リュウキュウマツ
県鳥=ノグチゲラ
日本の最南西に位置し,沖縄島(本島)ほか160の島々からなる島嶼(とうしよ)県で,そのうち40島が有人島,他は無人島である。明治以前の沖縄は琉球国という小独立国で,特に中国からは冊封を受け,臣の礼をつくして貿易を守り,その文物を輸入した。1609年(慶長14)薩摩藩に征服されてからのちも中国との通交は持続し,日中両属の形が続いた。明治政府は琉球と中国との関係を断絶させ,いわゆる琉球処分によって1872年(明治5)琉球国を琉球藩とし,79年藩を廃して沖縄県を設置した。こうして沖縄県は,明治・大正・昭和の県政時代を経て,第2次世界大戦の終了まで存続した。戦後,沖縄県はアメリカ軍の統治下に置かれ,27年間におよぶアメリカの統治後,1972年5月15日,日本への復帰が実現した。なお2000年に〈琉球王国のグスク及び関連遺跡群〉が世界文化遺産に登録されている。
先史時代の沖縄
琉球諸島で現在知られている最古の人類は,那覇市山下町出土の山下洞人で,炭素14法の年代によると約3万2000年前にさかのぼり,具志頭村発見の港川人とともに東アジアにおける確実な洪積世人類として重要な意義をもつといわれる。利器としての確実な石器は未発見だが,鹿角骨を利用した製品は若干検出されている。しかし,シカの長管骨などを利用した,いわゆる叉状骨器はシカ同士による咬傷痕であって,人工品ではないという見解もある。
新石器時代文化は沖縄諸島と先島諸島とでは起源を異にする。沖縄諸島は早・前・中・後の4期に編年される。早期は縄文時代の中期までを一括するが,将来は細分が必要であろう。前期は縄文後期,中期は同じく晩期にほぼ比定される。早期中ごろまでは九州の土器文化の延長にあるが,早期後葉に九州の文化圏から離脱したものと思われ,前期の段階では沖縄独自の土器文化を展開させた。ところで,弥生文化が沖縄に及んだかどうかはまだわかっていない。しかし近年,弥生土器,板状鉄斧,ガラス小玉,箱式石棺墓,炭化米など弥生関係の資料は増加しており,またすぐ北の奄美諸島では弥生前・中期文化の定着したことが確認され,沖縄諸島への波及も十分考えられる。弥生期以降に対比される石器時代終末期の文化が後期で,10世紀ころまで存続する。その次は〈ぐすく〉時代で,〈ぐすく〉の性格についてはいまだ定説がなく,初期のものについては支配者居城説,葬所説,高地性集落説などがある。終末は15世紀ころといわれる。
南の先島諸島の土器文化は南方起源といわれているが,系譜の確認は今後の課題である。南端の八重山では先史~歴史時代を4期に編年する。第1・2期が先史時代で,打製・磨製石器文化で始まる。第2期に土器出現,炭素14法によると約3000年前である。第3期は外耳土器の時代で〈ぐすく〉時代に対比され,第4期はパナリ焼の時期である。宮古列島はすべて新しく,八重山の第3期以降の遺跡である。
執筆者:高宮 廣衞
風土と産業
沖縄県の自然は本土と大きく相違し,亜熱帯風土の特色を有している。県域は,九州南端から台湾にいたる海域に飛石のように連なる南西諸島のうち,北部の薩南諸島(大隅諸島,奄美諸島)を除いた琉球諸島,すなわち沖縄諸島,先島諸島(八重山列島,宮古列島),尖閣諸島と琉球海溝をへだてて大東諸島などの島々から構成される。琉球弧(琉球諸島)の地体構造は,次のように分けられる(1965,小西健二)。琉球地背斜区(沖縄島,宮古島,石垣島,西表(いりおもて)島の脊梁山地)の新第三系の基盤岩類は,東シナ海側から太平洋側に向かって,(1)石垣帯(古生代のトムル層と琉球火山帯が重なる),(2)本部(もとぶ)帯(古生代の本部層,与那嶺層),(3)国頭(くにがみ)帯(中生代の名護層,嘉陽層),(4)島尻帯(第三紀層)が,古いものから新しいものへと雁行状に配列する。そのうち沖縄県の面積の過半を占め,県の政治,経済,文化の中心をなす沖縄島は北東から南西にのびる細長い島で,北端の辺戸(へど)岬から南端の荒崎までおよそ120kmである。沖縄島の石川・仲泊地峡を境に,以北は山岳の多い地域で,島軸の脊梁山地は標高300~500mの山地が島状に連続し,そのまわりに台地(海岸段丘)が広く発達する。最高点の与那覇岳(503m)から南下するにつれて高さを減じ,山地南端の読谷山(よみたんざん)岳(236m)に達する。地峡以南の中・南部地域は第三紀層島尻層の泥岩を基盤に,上部を琉球石灰岩が被覆し,丘陵・低地の波浪状の地形やカルスト台地の地形などの特徴がある。また海岸は裾礁,堡礁などサンゴ礁地形がみられ,サンゴ礁独特の青い海,白い砂浜,強烈な陽光はいかにも南国的である。
亜熱帯海洋性気候に属する沖縄県は東アジア季節風の影響を受けるが,全体としては長い夏と短い冬型の季節が特徴で,四季の変化は明確でなく,降雪はまったくない。5月下旬から6月下旬の梅雨期に最も雨が多く,夏には台風が数回襲来する。台風はしばしば猛烈な暴風雨を伴い,農作物などに大被害を与えることがある。また多くの離島からなるため,古くから離島苦(島チャビ)をかかえて,つねに自活の道を歩まねばならなかった。この島嶼性,離島性と本土を遠く離れた隔絶的な環境は,沖縄の地域性に大きな影響をおよぼし,独自の歴史・文化を生み出す要因となった。
第2次大戦前は農業県で,産業構造上農牧業の占める比重は高く,農家率は73%(1940)を占めていたが,戦後はアメリカ軍基地の恒久化に伴って農業の地位と特色が変容した。復帰後かなりの経済成長率を示し,1人当りの県民所得は1986年に全国平均の75.7%にまで格差が縮まったが,その後は低下し,94年には全国平均の71%となっている。沖縄県の総生産の割合(1994)を産業別にみると,第1次産業3%,第2次産業21%,第3次産業76%で,全国と比較すると第3次産業に特化している。94年の農業粗生産額の総額は1009億円で,その構成は,耕種部門ではサトウキビ19%,野菜17%,花卉16%,果実4%,葉タバコ4%,いも2%,米1%,その他2%,畜産部門では豚16%,肉用牛8%,鶏6%,乳用牛5%,その他畜産1%となっている。耕種と畜産の比率は65:35で,耕種農業を主として畜産を加味した経営となっている。原料農産物に比べて,米・いもはわずかに18億円に過ぎず,稲作はまったく不振である。全体として,基幹作物であるサトウキビから花卉や畜産への転換が図られている。
沖縄の糖業は1623年(元和9)儀間真常が製糖を試み,その成功以来のことである。およそ350年余の歴史的背景をもつ糖業の沖縄経済上に占める地位は高いものがある。戦前は移出額の65%内外が砂糖で,また戦後の1953年の総輸出額の36%が砂糖であった。しだいにその比重は低下傾向にある。戦前の砂糖生産は分蜜糖(ざらめ糖)に比べて含蜜糖(黒糖)が29:71の割合(1938年期)で多かった。戦後は農家はサトウキビ栽培だけを行い,県全体で101万3000t(1995),全国の62%を産し,製糖は工場で行うという分離方式をとっているため,分蜜糖が圧倒的に多く,95%を占めている。県下の大型工場11社では分蜜糖,小型工場7社では含蜜糖を生産している。その他昭和初期に栽培が始められたパイナップルは戦後沖縄の復興産業と位置づけられ,おもに沖縄北部と石垣島で栽培が盛んであったが,年々減少している。これに代わり急激に生産量を増加してきた花卉は,主として沖縄島各地で盛んに行われるようになってきた。また,肉用牛を中心とする畜産も盛んになってきた。伝統的な特産品工業の泡盛,紅型(びんがた),陶器,漆器などは首里,那覇に生産地がある。南風原(はえばる)町の絣,大宜味(おおぎみ)村の芭蕉布,久米島のつむぎ,宮古・八重山の上布などは特産品である。
27年間にわたるアメリカ統治の影響は,沖縄の政治,経済,社会など各面におよんでいる。1950年ころから始まったアメリカ軍の基地恒久化に伴って,莫大な予算を投じて築きあげた軍事基地の存在は,直接・間接に沖縄経済に結びついている。96年のアメリカ軍基地面積は2万4306haで,全県の10.7%を占めている。とくに沖縄島北部,中部,それに伊江島において広大な面積を占めている。〈沖縄に基地があるのではなく,基地の中に沖縄がある〉と誇張されるように,軍事基地の存在は,基地と政治,基地と経済,基地と生活というように,基地の周辺地域に大きな影響をおよぼしている。したがって基地密度の高い沖縄島中・南部の基地周辺地域に,顕著な地域的変容がみられる。那覇市の過密化や,中部の都市化が進み,石川市(1945),宜野湾市(1962),具志川市(1968),浦添市(1970),沖縄市(1974)が成立した(2005年合併により石川,具志川両市はうるま市となる)。これらの都市は程度の差こそあれ,いずれも基地の存在と無関係ではなく,卸売業,小売業,サービス業などを中心とした消費的性格の強い基地的都市を出現させている。沖縄島には戦前,那覇から与那原(よなばる),嘉手納,糸満,那覇港へ沖縄県営鉄道(1914創業,全延長48.03km)が通じていたが,沖縄戦で破壊された。以後全国で唯一,鉄道をもたない県となり,自動車交通の発達が著しいが,交通渋滞など交通問題は深刻化している。その対策として,道路の立体化などの整備を進める一方,2003年沖縄都市モノレールの那覇空港~首里間が開通。沖縄自動車道は1975年に名護市の許田インターチェンジと石川市(現,うるま市)の石川インターチェンジの間が国道329号沖縄自動車道として開通。87年石川インターチェンジから那覇インターチェンジまでが開通し,高速自動車国道に編入された。沖縄島を中心に他の主要な島々へは海上交通が発達するが,航空路も発達していて,那覇空港(1933開設)から宮古,石垣,粟国,南大東,久米などの各島へは航空路が通じる。また東京,大阪,神戸,福岡,鹿児島などへは定期航路,東京,名古屋,大阪,福岡,鹿児島などへは定期航空路が通じる。香港,台北,ソウルなどへの国際線の定期航空路もある。
沖縄島北部,中南部,先島
ここでは沖縄県域のうち自然や人文環境の相違により,石川地峡を境にして沖縄島の北部と中南部,それに先島の3地域について述べる。
(1)沖縄島北部 名護市と国頭郡の範囲で,山岳地形をなすことから山原(やんばる)の呼称がある。緑の山地を背景にしたサンゴ礁の海岸は美しく,恩納(おんな)から辺戸岬までの海岸は沖縄海岸国定公園に指定された。また海洋博記念公園をはじめ真栄田(まえだ)岬,万座毛(まんざもう),辺戸岬,海水浴場のあるビーチなど,名勝地,行楽地が多い。名護市は北部の中心都市である。
(2)沖縄島中南部 石川地峡以南の範囲で,県人口の80%がこの地域に集中しており,都市地域を形成している。那覇市は表玄関として歴史的に栄え,1881年首里にかわって県庁所在地となり,名実ともに沖縄県の主都となった。これに比べて歴史都市の首里は首里城跡(史)付近に県立芸術大学,守礼門(県史跡),園比屋武御嶽(そのひやんうたき)石門(重要文化財),玉陵(たまうどん)(史)などの集まる閑静な文教住宅地に変わった。南部の糸満市は漁業の町として知られ,沖縄戦最後の激戦地となった摩文仁(まぶに)岳一帯は沖縄戦跡国定公園となっている。
(3)先島 宮古島市,石垣市,宮古郡,八重山郡の範囲である。宮古列島は宮古島など八つの島嶼からなる。宮古島は全島琉球石灰岩で被覆され,平たんな地形で,太平山(島)とも呼ばれた。サトウキビ単一栽培の砂糖の島であったが,復帰後から園芸農業が盛んになった。宮古漁民の南方漁場への進出は目覚ましい。宮古上布,サンゴの加工は特産。宮古島の旧平良(ひらら)市が中心都市である。八重山列島は石垣島,西表島など19の島嶼からなる。石垣島は,中央部に沖縄県で最も高い於茂登(おもと)山(526m)がそびえ,山々が連なる。山地に続く緩斜面の台地,沃野は広く未開地もあり,人口密度は低い。かつてはマラリア地帯もあったが,今はない。八重山は詩の国,歌の国といわれ,島々には古謡があり,民謡も豊富で,伝統的な祭り行事を保存している。西表(いりおもて)島は沖縄県第2の面積をもつ島であるが,全般的に山がちで低地が乏しく,熱帯・亜熱帯の原生林が繁茂し,秘境を残している。イリオモテヤマネコ,カンムリワシ,セマルハコガメなど国指定の天然記念物がある。西表島と周辺海域は西表国立公園(2007年石垣島などとともに西表石垣国立公園となる)に指定されている。
執筆者:田里 友哲
近代の歴史
人頭税廃止運動
ここでは琉球処分(1872-81)以後について述べる。それ以前については〈琉球〉の項を参照されたい。
明治前期における琉球処分の政治過程は,明治政権の中央集権体制の完成を期す連続的な事業であった。それが10年という期間にわたっていることは,国内の政治状況が流動的であり,日清の国際環境が緊張していたことに大きく規定されている。琉球処分の直後から,明治政府は清国の国内の通商権と引換えに宮古・八重山を割譲するという内容の秘密外交交渉(改約分島交渉)を進めていた。初期明治政権が日本民族の独立確保を重要な課題として,欧米諸国に対等に伍そうとする外交政策は,国権を確立しその伸張をはかることにあった。それゆえに,条約改正の先鞭として開始した改約分島交渉は,内容的に琉球処分における統合を否定するものであった。この交渉は〈琉球分割条約〉まで構想したが,その後,清国はロシアとの対立抗争を解消することに成功したので,必ずしも日本との対立を解決せねばならぬという緊急性を失い,分割条約案は流産することになる。また明治政府は,沖縄県を設置しても,すべての諸制度を統合化,一体化する施策をとらなかった。むしろ沖縄の旧支配層を懐柔し,脱清行為を鎮めるために,旧慣を存置する政策がとられた。そのため土地制度,租税制度,地方制度などの改革は大きく遅れることとなる。と同時に当時の日本政府は,自由民権運動の高揚の対応に全力を注ぎ,沖縄に深く関わるだけの余力をもっていなかった。
日本政府の旧慣存置の政策によって,沖縄社会はその発展を抑制された。当時の農民は巨額の負債を背負いこんで疲弊しきっており,まったく返済のあてもなかった。《上杉県令巡回日誌》(1881-82)は農民の貧困と悲惨な現実にふれ,県政改革を模索しはじめている。上杉茂憲は県庁役人の人員整理・縮小による財政再建をはかり政府に建白したが,政府は拒否して上杉改革案を葬り去った。先島の農民の場合は,もっと緊迫していた。それは人頭税制に直接的に苦しめられていたからである。琉球政府の収入を一定ならしめるためとも,他の地への移住を禁止するためにともいわれている人頭税は宮古・八重山で典型的に見られ,反布で上納されていた。宮古の人頭税撤廃に立ち上がった農民を支援したのは,製糖指導員城間(ぐすくま)正安と新潟県人中村十作である。2人は人頭税の納期に縊死や身投げが続発するのをみて農民に同情し,運動に尽力することになった。農民は宮古島役所長に対し人頭税の廃止を要求したが,役所長および県当局は要求を認めようとはしなかった。農民は政府との直接交渉を決意し,平良真牛,西里蒲を代表に選んで上京させた。1893年11月に〈沖縄県宮古島島費軽減及島政改革請願書〉を提出し,翌年には内務省に県政改革建議書を提出した。この運動を契機に政府の旧慣存置の政策の再検討が行われ,人頭税は1903年沖縄県土地整理法の施行によって廃止された。
沖縄自由民権
明治10年代の自由民権運動の基本綱領は,国会開設(国家構想),地租軽減,条約改正であった。明治30年代の謝花(じやはな)昇とその同志によって推進された県政改革運動は,特に〈沖縄の自由民権運動〉と位置づけられ,評価されてきた。謝花昇の運動と本土の自由民権とは,当然のことながら内容,質的に差違がある。後者が国会開設をめぐって抗争していることに対し,前者は形式的には開設された国会に代表者を参加させるという要望をしている。これは歴史的落差の顕著な例であろう。当時の沖縄県知事は鹿児島出身の奈良原繁で,彼は士族の救済対策として杣山(そまやま)の開墾事業に着手し,尚家一族や鹿児島商人,上級官僚らに開墾を許可した。開墾事務にたずさわっていた謝花は開墾予定地を視察し,農民の反対の声に接して奈良原知事と対立する。入会地の一方的払下げは,農民の生活を根底から破壊するのも同然であった。謝花は上京し,〈杣山慣行取調書及び其官民有利陳述書〉を議会に提出した。また田中正造,星亨,高木正年らの協力を得て奈良原の暴政を指摘し,その更迭を訴えた。謝花らの運動原理の中には,沖縄のかかえる課題を,市民的自由という政治参加の方式を通じて地域住民の意思を広く国会の場に反映させ,国民的課題として解決をはかることこそが重要であるとの立場があった。したがって,参政権の必要性は最も重大な政治課題になりえたのである。謝花は同志とともに沖縄俱楽部という政治・学習結社を作り,政治宣伝のために機関誌《沖縄時論》(1899-1902)を創刊した。しかし奈良原ら反対派の激しい攻撃で運動は挫折して同志は離散し,謝花もついには発狂した。県民が参政権を獲得して形式的に国政に代表を送ったのは,帝国議会が開設されて22年目の1912年であり,それも宮古・八重山を除く差別的な制度であった。
奈良原県政の1899年から1903年にかけて,〈土地整理〉が実施された。これは沖縄社会の一大変革で,古琉球以来つづいた地割制度が廃止され,土地の私的所有権が認められた。かくして村落共同体社会の秩序は,上から資本制的社会に改変させられていった。土地整理の意義は,土地の私的所有権が確定したことで,租税が間切(まぎり)や村に課されていたのが,所有者個人に課されるようになる。したがって行政全般が本土と一体となり,諸制度(徴兵,選挙)の実施が可能となった。それ以後政府は,県庁や公教育機関を通じて国策の浸透をはかり,より一層の本土との一体化を積極的に推進した。これに迎合する風潮も見られたが,啓蒙思想家伊波普猷(いはふゆう)のように,沖縄の歴史的地域的個性を主張して,政府の一方的な政策に抵抗したものもいた。この文化運動はのちに沖縄学と称され,大きく発展した。今日の沖縄研究の基礎は,この時に構築されたものである。
ソテツ地獄
明治・大正の沖縄で,唯一の換金作物は黒糖であり,その生産と価格は沖縄経済全体に大きな影響を与えていた。60万人ほどの人口のほとんどが農業生産に従事しており,農業経営の規模も1戸当り平均耕地面積が約7反,5反未満農家が全体の半数以上を占めていた。しかも農家戸数全体の6割以上がサトウキビ栽培に従事する零細農業県で,高い租税の支払にはサトウキビ作以外に換金作物を見いだすことができなかった。またサトウキビ作面積の増大は自給食糧であるサツマイモの栽培面積を縮小させ,同時に水田をも畑に変えていき,主食糧を他に依存する形態をとるようになる。この生産構造は第1次大戦後の不景気をまともに受けて,県民の生活を恐慌の中におとしいれた。1920年黒糖は那覇相場で10斤につき24円であったが,翌年には12円台と大暴落し,26年には9円台に落ちこみ,以後8~9円台を低迷した。もともと貧困な県民生活はこの恐慌によりいっそう窮迫し,三度の食事のうち1回は,野生のソテツの実や幹を食べたという。しかしソテツには有毒成分サイカシンが含まれているので製法を誤ると中毒し,そのために死者がでるというありさまだった。それはまさにソテツ地獄と呼ばれる状況であった。そこで貧農だけでなく中農層の子弟も身売りに出された。
沖縄県の海外移民は,〈謝花民権〉の挫折後に始まり,しだいに激増した。1907年の対米移民禁止後ハワイへの移民は減少した。不況の時代に入って多くの人が,北アメリカ,南アメリカ,フィリピン,南洋諸島に出かけた(特に農村地域からの流出が大きい)。実際には,不況で農村の〈口べらし〉のために移民となり,故郷をはなれた人たちではあったが,彼らは苦労して稼ぎためた金を実家に送った。不況の県下に有効な救済策もなく,海外からの送金は県経済を大きく支えていた。移民に出ない者は,安い労働力として県外に流出していった。
戦時体制下の沖縄
第1次大戦終了後の恐慌と不況の影響を受けた沖縄社会の疲弊ぶりは,実に深刻であった。その救済対策としてにわかに浮上した沖縄県振興計画(1932)は,産業基盤の整備・拡充を基本的な柱とし,産業各分野における生産力の増強をはかるというものであった。しかし振興計画策がようやく軌道にのりはじめたころに,戦時体制へと没入していくことになる。この間の沖縄社会の動向を象徴的に示す史料に沖縄連隊区司令部の報告書《沖縄防備対策》(1934)がある。報告書は国防の観点から,沖縄社会の性格をこう分析している。(1)憂いの最大は県民の事大思想である。(2)依頼心が強く他力本願である。(3)一般に惰弱の気風がある。(4)古来任俠の伝統がなく,団結,犠牲の美風に乏しい。(5)武装の点でほとんど無力である。青年訓練所,在郷軍人においてすら銃器を有せず,有事の際の郷土防衛はきわめて困難。以上の軍の対沖縄観には,沖縄に対する不信と偏見,差別意識が表出している。こうした認識を基盤にして具体的な施策が政府と軍の指導の下で,国防教育,愛国運動として精力的に展開されていくことになった。これは沖縄県民を自発的・自主的に戦争体制に協力させ,ひいては動員および調達していくことを目的としていた。政府は1937年〈国民的思想動員運動〉を策定し,さらに〈国民精神総動員計画実施要綱〉を発表した。〈挙国一致,尽忠報国,堅忍持久〉のスローガンのもとに,言論,思想の弾圧,国民統制の強化がはかられ,しだいに県民生活の細部に干渉し,物理的強制力を発動していった(国民精神総動員運動)。特に標準語使用,方言撲滅の運動は,方言の使用をスパイ行為とみなし,戦争中には軍の指令でスパイ嫌疑として虐殺している。地方文化を無視した防諜取締りのきびしい一面である。また38年4月には国家総動員法が公布され,同法にもとづいて〈長期持久戦時体制の確立〉をはかるため,(1)物価統制,(2)消費節約,(3)輸出振興,(4)廃品回収,(5)貯蓄徹底,(6)生活簡素化などの方策が掲げられ,〈沖縄県振興計画〉ももはや例外を許されなくなった(国家総動員)。
太平洋戦争開戦を画期として,戦時色は沖縄県下をぬりつぶし,大政翼賛会が決定した〈必勝生活訓〉が県民のスローガンになっていく。(1)強くあれ,必勝の信念をもって職域を守れ,(2)家庭も戦陣,生活を挙げて御奉公の誠をつくせ,(3)国土防衛は協力一致,隣組の力で持場を固めよ,(4)流言に惑うな,当局の指示を信頼して行動せよ,(5)国運を賭しての戦だ,沈着平静最後までがんばれ,と。新聞も一県一紙の方針のもとに,1940年《琉球新報》《沖縄朝日新聞》《沖縄日報》の3紙が統合して《沖縄新報》のみとなった。検閲もきびしく,自主性は失われ,政府や軍部の代弁機関となった新聞からは,真実を聞かされることはまったくなくなってしまった。情報回路は上意下達の回覧板にゆだねられ,民衆を相互に監視する隣組組織が強められた。民衆の意識は戦争に協力する画一的な様相をますますこくしていった。このような状況下で45年3月,太平洋戦争最後の戦闘であり,日本国内で唯一の地上戦である沖縄戦が沖縄島ならびに周辺諸島で展開された。
→沖縄戦
日本復帰運動
数ヵ月間にわたる日米両軍の戦闘の結果,約20万人の死者を出し,焦土と化した戦後沖縄の出発は,すでに苦難を背負っていた。戦災で生活基盤のすべてを徹底的に破壊された住民は各地の収容所に幽閉され,居住地に帰ることすら禁止された(1945年10月29日以降原住地への帰村は許されたが,原住地がアメリカ軍に接収されたままいまだに帰れない住民もいる)。戦場となった農耕地も軍事施設としてアメリカ軍に囲いこまれた。中華人民共和国の成立(1949)後,アメリカ軍の土地政策は土地接収の方向に転換した。朝鮮戦争の勃発でアメリカ軍は沖縄基地の重要性を認識し,基地機能を集中化した。そして1952年4月28日の対日平和条約の発効によって,法的にも沖縄は日本より分断され,沖縄基地はアメリカ軍における極東の軍事的かなめ石となった。アメリカによる統治は当初,陸・海軍の軍政府(米軍政府)によってなされていたが,1950年12月5日の〈琉球列島米国民政府に関する指令〉で,アメリカ政府の出先機関である米国民政府United States Civil Administration of the Ryukyu Islands(略称USCAR)が設置された。この結果,沖縄の統治は司法,立法,行政の全般にわたって,琉球列島米国民政長官の指揮下で行われた。また52年4月1日には,米国民政府布告〈琉球政府の設立〉に基づいて,沖縄住民側の中央政府としての琉球政府Government of the Ryukyu Islandsが,米国民政府のもとに設立された。その機構は,行政主席官房,行政主席情報局,総務局,警察局など1房13局81課3委員会(人事委員会,中央選挙委員会,中央教育委員会)よりなっていた(同年9月,奄美,宮古,八重山に各々地方庁が置かれた)。琉球政府は〈琉球における政治の全権を行うことができる〉との権限をもってはいたが,あくまでも米国民政府の指揮下においてであった。しかし三権分立,司法権の行使など,国家的作用もある程度認められていた。
対日講和の構想が明らかにされるころから,沖縄では日本復帰運動の組織的活動が開始される。1951年4月,沖縄社会大衆党(社大党,1950年10月結党),沖縄人民党(人民党,1947年7月結党)を中心に〈日本復帰促進期成会〉が初の超党派的復帰運動体として結成された。50年代の沖縄の民衆運動は軍用地問題をめぐる島ぐるみ闘争に象徴されるが,その爆発的契機となったのは,56年6月のプライス勧告である。アメリカ軍の土地強制接収に対抗するため,琉球立法院は(1)一括払い反対,(2)適正補償,(3)損害賠償,(4)新規収集反対の四原則を決議していたが,勧告はこれを否定するものであった。運動組織は強化され,四者協議会(琉球政府,立法院,市町村長会,軍用土地連合会により1954年4月に結成)による,島ぐるみの土地闘争は爆発的高揚を示した。四者協の闘争方針や四原則をささえた思想の根底には,生活権の擁護(デモクラシー),領土主権の防衛(ナショナリズム)が流れており,土地闘争で提起された課題は復帰運動に引きつがれる。復帰運動は三つの要素からなっており,(1)異民族支配からの脱却(復帰),(2)民主主義の確立(人権と自治),(3)戦争反対,平和の擁護(反戦・平和)である。これは沖縄民衆の占領支配に対する権利要求の集約的表現となっている。60年4月28日,沖縄県祖国復帰協議会(復帰協)が結成され,運動の母体となり,復帰協に参加した各種の団体は対日講和条約の発効した4月28日を〈屈辱の日〉として,この日を中心に統一と団結のスローガンの下に統一戦線的性格を堅持し,運動を深化させていった。
復帰運動の理念は日本国憲法の民主主義と平和主義の精神を異民族支配下の特殊政治状況の中で実現化するところにあり,それは復帰協に結集する沖縄民衆の闘争の蓄積によって支えられていた。68年には屋良朝苗を初の公選主席に当選させるほどに運動は高揚し,72年5月15日の施政権返還というかたちで,日米両政府間における沖縄返還が歴史的事実となったのである。しかし,その時点でアメリカ軍基地の存続が認められ,一部自衛隊の使用に供されて,軍事基地の問題は未解決のまま残されたために,沖縄戦を思いおこし,戦争への危機感をうえつけている(この点を歴史的に第三の琉球処分と評価する視点もある)。一方,異民族支配下の政治風土である住民自治の制約,基本的人権の抑圧などは大きく変貌をとげた。復帰実現は沖縄県民に多くの夢を与えたが,その反面,本土との系列化の進行,急激な開発による自然破壊をもたらした。しかし,県民に日本国民としての精神的な余裕を与えた点は大きな変化であろう。
返還・復帰後の沖縄
沖縄の人々は,日本国憲法の下での人権も,参政権も,米軍基地の存在も〈本土並みに〉保障されることを祈願して,〈島ぐるみの〉祖国復帰運動をくりひろげ,1972年に復帰を実現させ,国政に参加することができたが,日本・アメリカ両政府の沖縄政策は,日米軍事協力の強化を目的にした沖縄返還でしかなかったことが,復帰後にますますはっきりしてきたといえよう。復帰後の沖縄県知事は,革新・保守から屋良朝苗(1972-76),平良幸市(1976-78),西銘順治(1978-90),大田昌秀(1990-98),稲嶺惠一(1998-2006)等が選出されて行政を担当し,政府とわたりあってきた。
1972年の本土復帰当時,沖縄の米軍基地は287km2,87施設であったが,四半世紀後の96年には243km2,47施設である(2001年には237.53km2,38施設)。日本全土の米軍基地314km2の実に4分の3を沖縄が占め,しかも沖縄本島に集中しており,本島面積の約18%に及ぶ。基地の存在の〈本土並み〉縮小という切実な願いは,完全に裏切られた。
日本政府は,アメリカ合衆国との間で日米安全保障条約を結んでおり,その目的はアメリカと日本との相互の安全とアジアの平和維持だとされている。この条約によって日本はアメリカに基地を提供する約束をしたのであるが,沖縄の米軍基地は,日本の安全を守るためにアメリカに提供しているのだから大幅に縮小することはできないと,日本政府は主張しつづけてきた。
沖縄の人々の反発を抑えるために,政府は復帰後に軍用地使用料を6倍に引き上げ,基地所在市町村には基地周辺整備事業費を交付してきた。また,復帰の年の12月から政府は3次にわたり沖縄振興計画を実施し,沖縄と本土の格差是正をはかり,自立的な発展の基盤をつくるべく港湾,空港,道路,下水道,学校校舎等の整備を行った。しかし,それら沖縄の人々への〈懐柔策〉ともとれる政策は,沖縄の経済を公共投資依存型の構造を強める方向に押しやってきた。
本土では米軍基地の9割が国有地であるが,沖縄では基地面積の7割弱を民有地が占める。沖縄の人々の多くは,これ以上自分たちの土地を基地に提供することはできないと,拒否する立場をとっており,とくに〈反戦地主〉たちはその前面に立っている。1990年に革新系の大田知事が登場し,基地の整理・縮小を掲げて日米の政府と交渉を進めてきたが,その間95年9月に起きた米兵による少女暴行事件は沖縄県民の怒りを爆発させ,基地縮小の要求が拡大した。95年11月に日米政府は〈沖縄基地特別行動委員会(SACO)〉を設置して基地の整理・統合計画を検討し,96年12月には普天間など一部の基地返還に伴う代替へリポート建設などの報告を出した。また96年9月〈基地の整理・縮小,日米地位協定の見直し〉に関する県民投票では投票率約6割のうち,賛成が9割近くを占めた。次いで97年には,同年5月で契約期限切れとなる嘉手納など12施設の扱いをめぐり,政府は沖縄県の意向を押し切って〈駐留軍用地特別措置法〉を改正し,暫定使用を可能とした。
政府は,安保体制に協力する沖縄に対して,その引替え条件に地域振興策としての国際都市構想の実現を約しているが,その実態は明確でなく,沖縄の人々の支持を取り付けているとはいいがたい。97年末,代替へリポート建設をめぐり沖縄本島北部の名護市で行われた住民投票で,地元世論を二分したうえで反対派が上回った事態は象徴的であろう。基地問題の解決を地方交付金の空中散布的な配分方式,大型予算の投入等で図る政府の態度は,かつてのアメリカ軍政といかほどの差異があるであろうか。
こうした新しい状況の中で,戦後沖縄に重くのしかかってきた日米安全保障条約体制を見直す運動(人権,平和,自立)が高揚してくるが,その背景に〈安保再定義〉論議があることはいうまでもない。また他方では,平和憲法を持つ国家への期待がうすれていくなかで,沖縄では,かつて〈一国家を形成していた琉球王国〉の歴史を想起し,アジアに開かれた沖縄を志向する動きも見られる。
執筆者:我部 政男
民俗
沖縄の民俗は地理・歴史的背景が本土とかなり異なるため独特のものがあり,おおざっぱに沖縄島とその周辺,宮古島とその周辺,八重山地区に大別される。全般に仏教の影響が少なく血忌が重視されないことや,清明祭や火の神などに中国的要素が色濃く認められることのほか,琉球王府の政策によって各種の規制が加えられ,その独自性を強めたことも考慮すべきである。一方で,日本の古語,古俗を残すと思われる民俗が見いだされ,沖縄は〈古代日本の鏡〉ともいわれている。
衣食住
琉球に木綿が伝来したのは17世紀初めで急速に普及したが,それまでは今日夏だけに用いられる芭蕉布が一般住民の通年の衣料であった。身分的服装規定が16世紀にはじまり明治中期ころまで残存しており,一般には紅型,藍型(えーがた)はじみなものが礼装に許されるのみで,平織に限られていた。縞柄,模様も身分,性,年齢によって規定され,身分の低いものは高いものより,男は女より,老人は若いものより細かくなっていた。ハレの衣服は祝儀で黒地,不祝儀で白地で,女性は祝儀に色ものも用いた。食物は,現在は米中心だが,近年まで主食としては通年収穫可能なサツマイモ,副食としては豚肉,ヤギ肉を用いる点に特徴がある。豚は魔物を追い払うと考えられていることから,驚いてマブイ(霊魂)が落ちたと思われる時には,豚小屋に行って供物して拝むこともある。正月準備に正月豚といって豚を殺し,塩漬けにして赤肉から順次調理して食べるほか,清明祭や葬式,年忌にも豚肉を用いる。調理法は煮たり,いためることが発達し,焼くことはほとんどなく,魚の調理法はあまり発達していない。住居は,周囲をサンゴ礁で築いた石垣で囲まれ,一般に南向きに建てられ,主屋は4部屋ある。南面東側を一番座と呼び神をまつる祭壇が設けられ,南面西側を二番座と呼び仏壇がおかれており,死に関する儀礼が行われるほか,日常の社交の場となる。主屋の西側に台所があり,主婦が管掌する火の神がまつられる。これは炉を象徴する三つの石を神体とし,分家の際にはこの灰を分け,主婦が死亡すると石をとりかえる風があった。家族レベルの儀礼は屋敷の南東部で行われ,便所と豚小屋は北西隅におかれることが多い。
→琉球料理
信仰
15世紀以降,沖縄では国王の宗教政策によって神女組織がつくられ,〈聞得大君(きこえおおぎみ)〉と称する国王の姉妹または王妃が,最高の女祭司官として頂点に立ち,その下に大アムシラレという女祭司が3人いて全地域のノロ(祝女)を統轄させた。〈聞得大君〉は高級神女三十三君の上位に位する大君であり,聞補君(ちふじん)ともあてられ,名高い意でキコエを冠するという。また国王のオナリ神として,その霊力をもって国王の安泰と国の隆昌を保障するものであったとされ,国家泰平,航海安全,五穀豊穣,稲麦の穂祭,干ばつの祈願などがなされた。オナリ神信仰は,兄弟に対して姉妹が霊的に優位にたつというもので,国家から村落レベルに至る神女組織をささえる信仰の一つであった。久米島にあって〈聞得大君〉に直属し,同島のノロを統轄していた神官は〈君南風(チンベー)〉と呼び,八重山のオヤケ・アカハチの反乱征伐(尚真王24年,1500年)に功ありとして恩賞に君南風御殿を授かったことで知られ,三十三君の一つである。国王および〈聞得大君〉と深い関係をもつ久高(くたか)島は開闢(かいびやく)伝説でも名高く,知念(ちねん),玉城(たまぐすく)とともにカミグニとされた。南城市の旧知念村久手堅にある斎場御嶽(さいふあうたき)は開闢降臨の地とされ,久高島への遥拝所でもあり,聞得大君の〈御新下(おあらおり)〉という就任儀礼では参籠が行われた。聞得大君はトヨムセダカコとも呼ばれる。セジは霊力を意味し,村落レベルの神女でもその適格者はセジ高い女でなければならないという。セジを身につけ,これを国王に奉り,兄弟をまもり,またこれで仇敵を呪詛することもした。
村落レベルの祭祀をつかさどるノロは,王国の神女組織の末端を担っていた。ノロ以上の神官は国王から辞令を受け,特別に土地を給せられ,賦役も免除されていた。彼女らは官人でその職責は世襲であるが,その継承にあたっては種々の違いが認められる。ノロは〈ノロ殿内(どんち)〉に住んで,担当の祭祀管轄区域内の祈願儀礼を行い,御嶽(おたけ)/(うたき)や拝所でオモロをうたい,オタカベ(お崇べ)を唱えた。オタカベは祭礼のよき日と神の出自をたたえた神への祈願の言葉をいう。各村落の御嶽は村の守護神としてノロの執行する祭祀や共同祭祀の中心となる。御嶽は小高い丘に森をなしているものが多く,いずれも名前をもち,神話伝説も伝えられている。各村落には御嶽のほかに〈拝所(うがんじよ)〉と呼ばれる聖地があり,祭りの時にここでも儀礼が行われる。御嶽の中には神アシアゲという神殿があるが,これはノロ殿内や村の草分けの家の近くにあることもある。祭礼の日にはここに神が降臨し人々の祝福をうけ,その前の広場では神遊び,オモロ,臼太鼓などが行われる。こうした信仰生活を律してきた王国から村落に至るヒエラルヒー的な神女組織は17世紀の薩摩の侵入以後,さまざまな社会変化や旧体制への圧迫によって,明治期以降国レベルでは崩壊し村落祭祀の執行者としての地位はかなり形骸化した。
沖縄的信仰の基盤はシャマニズムの中に位置づけることができる。霊的職能者とされるユタはモノシリともいわれ,〈門中〉と不可分のタブーの判断や運勢,病気祈禱などを行う。歴史的には庶民を惑わすものとして取締りをうけてきたことが,ユタの存在を隠微なものにしてしまったことも考えられる。ユタが霊的能力を備えるとされる現象をカミダーリ(憑依(ひようい)現象)といい,これを経ることがユタたる一つの特徴である。系譜関係の当否の判断をはじめとして近親の死者との橋わたしをするので,〈生きた祖先崇拝の維持者〉であり,〈神意診断役〉ともいえよう。ユタは全琉球に分布するが,沖縄島の中部に偏在し,位牌祭祀に関して男系をたどる継承を推進するため,女性の立場から社会問題化している一方,その存在はますます隆盛をきわめている。
社会
琉球王国末期の百姓地は村の共有であって,一定年限ごとに持地の割替えを行った。先祖が占有した土地を住民に均分に分割相続させ,耕地は共同作業で耕作し収穫物は平等に分配した。これが制度化されたのが地割制度で,1899-1903年の土地整理まで続いた。
親族関係を特徴づける用語にはウェーカ,ハラウジ,門中,チュチョーデーなどがある。門中は男系系譜をたどり,長男を優先するのが特徴で,沖縄島中南部でこの観念が強い。息子のない場合には,たとえ娘がいても婚出させ,自分の男系系譜内から養子を組み入れることにしている。庶民の間ではこれに抵触する〈他系混淆(たちーまじくい)〉〈兄弟重合(ちよーでーかさばい)〉〈嫡子押込(ちやつちうしくみ)〉〈女先祖(いなぐがんす)〉などの言葉があるが,これらはユタの活動によるところが大きい。ハラウジは男女双系にわたって血縁をたどり,個人を中心におおむね従兄弟姉妹までを含む関係を指している。沖縄島北部,久米島,本部(もとぶ)半島,先島の一部に分布し,日常的な互助共同や通過儀礼において機能する。地縁集団は〈組〉と呼ばれ,労働力交換を指すユイの仲間を構成することが多い。
通過儀礼
出産は裏座に〈地炉(じろ)〉を作って,その脇で行い,夏でも産後は火をたいて暖めていた。えな(胞衣)は火の神がまつってある台所裏手の雨だれの下に埋めたが,近所の婦人や子供たちに大声で笑ってもらい,生児が健康に育つよう祈った。命名までの間,子供の性の反対に男児は〈大女〉,女児は〈大男〉と呼んだ。農村の結婚は男女の交際が自由でモーアシビ(毛遊び)で結ばれることも多かった。他村落との通婚は少なく,その場合は女方の村落の青年へ〈馬手間(うまでま)〉という酒または酒代を出さねばならなかった。嫁の引移りにあたって,仏壇と火の神を拝み,男方では台所から入ってその火の神を拝んでから披露宴をした。婚約成立の時点で男方で行う親類へのひろめを〈門中開き〉といった。沖縄では自分の干支が来るごとに正月に年祝を行う風習がある。すなわち13,25,37,49,61,73,85,97歳を祝うが,とくに13歳の祝は実家での最後の祝いとして成年式の意味もかねて女子のある家では盛大に行った。このほか,88歳の祝いは〈トカキ祝〉と称し,8月8日に大だらいに米を盛り斗搔(とかき)をさしておいて参会者にそれを配った。また97歳の祝いは〈カジマヤー祝〉という。
墓ははじめは天然の洞穴を利用していたが,やがて横穴を掘るようになり,のちに平地に築造するようになった。本格的な墓の築造は13世紀末の〈ヨウドレ〉(国王の墳墓)にはじまるとされ,先祖崇拝の厚い沖縄では立派な墓が多いが,墓の形としては,〈亀甲墓〉と〈破風墓〉の二つがよく知られている。亀甲墓は亀の甲の形に似ていることにその名が由来し,築造は堅固である。破風墓は人家に似せてつくられている。埋葬後3年程度たつと遺骨を洗い清める〈洗骨〉が行われ,骨壺に入れて墓に納める。これにより子孫は先祖に対する義務を果たしたとされる。
年中行事
沖縄の気候は本土とかなり異なるため,作物の収穫時期が早く,同じ行事でも本土とは日時がずれることが多く,また琉球王府の政策によって行事の日時が統一されたと思われるものもある。年中行事はほとんど旧暦で行われ,同じ沖縄でも沖縄島と先島(宮古・八重山)地方とでは行事の名称や内容にかなりちがいがみられる。農耕に関連するおもな行事には,2~3月の麦の収穫祭,5~6月のアワや稲の収穫祭,11月のいもの収穫祭のほか,4月のアブシバレー(畦払い)という害虫駆除の儀礼や,立冬ころの〈種取り〉という稲の播種祭などがある。沖縄では年末に豚をころし,正月は餅をつかずに豚で祝った。沖縄島では元旦に若水をくみ,神棚,仏壇,かまどに若水をあげ,家族はその水で〈お水撫で〉をする。若水はスディミズともいわれ,生命を新しくする水という意味がある。マブイ込めやはしかの時にも水をつけた指先で額をなでる行為を行う。先島では夏季のシチ(節)にこの水をくむが,これは正月よりも稲やアワの収穫祭のほうが1年の折り目としてより重要視されていたためであろう。盆行事も沖縄島では本土と同じように行われるが,仏教の影響が少ない先島では盆を行わない所もある。
3月3日には〈浜下(はまおり)〉という一種のみそぎが行われ,蓬餅(よもぎもち)を作って先祖に供したり,親戚知人などに配る。また3月の清明節には墓前で清明祭(シーミー)という盛大な先祖祭が行われる。5月4日には,おもに糸満漁民の村でハーリー(爬竜)と呼ばれる船競漕が行われる。4月のアブシバレーにハーリーを行う所もある。6月には六月ウマチー(祭)といって稲の大祭が行われ,村によってはこのとき沖縄相撲や綱引きなどを行う。八重山各地では6月にプールと呼ばれる稲やアワの収穫祭が行われ,西表島古見など4ヵ所ではこの祭りに豊穣をもたらす仮面仮装神であるアカマタ・クロマタが登場する。沖縄島北部の沿岸では7月20日以後の亥の日または6月中の亥の日に〈海神(うんじやみ)祭〉が行われる。これは海神を迎えまつって海の幸を祈る祭りである。また7月の盆の前後の亥の日には豊作豊猟の予祝祭である〈シヌグ祭〉が行われ,海神祭と隔年で交互に行っている所が多い。7月7日には墓掃除や洗骨がなされ,盆を行う所ではその準備が始まる。盆には,遊び念仏,盆踊とも呼ばれるエイサーが沖縄島中部で盛んに行われる。7月15日の晩に精霊送りをすますと,村の男女はエイサーを踊りながら各戸をまわって酒を求めた。10月1日には〈竈(かまど)回り〉といって,火の神をまつったかまどを掃除し,村の頭役が見まわった。沖縄島などでは10月は〈アキハテ(飽き果て)十月〉といってほとんど祭りらしい行事はないが,宮古の伊良部島佐良浜では〈ユークイ(世乞)〉という豊年祈願祭が行われ,神女たちを中心に村の婦人たちがみな参加し,各拝所を踊りながら健康と豊漁を祈願して歩く。冬至には各家で〈冬至雑炊〉というサトイモ入りの雑炊を作って火の神や仏壇に供えるが,沖縄島北部の村々ではいもの収穫祭が行われる。12月8日には〈鬼餅(むーちー)〉といってビロウの葉に包んだ餅を作り,年の数だけ食べる。この行事には鉄の入った餅で人食い鬼を退治したという伝説が伴っている。年末にはカイルガマという悪魔払いの儀礼が行われる。また12月24日には,かまどの火の神が昇天し,正月の初旬に下界に戻ってくるといわれている。このほかに時期は不定だが,〈井泉詣(かーめー)〉といって井泉を拝み,水への感謝と健康祈願をする行事や,門中ごとに沖縄島北部の東方霊地を巡拝する〈東(あがり)回り〉や北山への〈今帰仁(なきじん)拝み〉といった行事もある。玉城村百名(ひやくな)の海岸にある〈受水走水(うきんじゆはいんじゆ)〉は東回りの第1の霊地で,この水でアマミキョ(始祖神)がはじめて稲作を行ったといわれている。
執筆者:饒平名 健爾
琉装
現在は沖縄でもおおかたの人々の衣生活は洋服である。しかし本土における和服同様に,沖縄でも伝統的な衣服が日常生活にも使用されており,沖縄特有の衣装姿(琉装(りゆうそう))は本土の和服姿とほぼ同じくらいの比率で見受けられる。和服の長着(ながぎ)(小袖,単(ひとえ),帷子(かたびら))に相当する琉装の衣服は〈衣(ちん)〉で,これは本土の小袖や単や帷子が男女,階級,地域に関係なく,伝統的に基本衣服として使用されてきたと同様,沖縄でも男女,階級に関係なく,ほとんどの地域で着用されてきた。形態は本土の小袖の類と一見したところほとんど同形である。ただ,袖が平袖(広袖)で,袖口は袖下の縫目の位置まで大きく開いており,袖付下に襠(まち)が入っている。これは本土以上に高温多湿の土地柄から,袖口をいっぱいに開けて少しでも風通しのよい衣服にした形であり,袖付下の襠は腕の動きを楽にし,また補強のために付けられた布である。単仕立てとあわせ仕立てとがあり,季節に合わせて着用する。この沖縄の伝統的かつ各階級共通衣服の〈衣〉も,基本的な形態は変わらないながら,士族以上と庶民とでは袖丈など多少長さが異なるなどの違いはあった。また地質,色柄,模様,着装法に至っては,王家,士族,庶民の階級別にかなり厳しいきまりがあった。たとえば,庶民は芭蕉布の場合上等品の煮綛(にーがしー)は着られない。柄も庶民は絣模様は禁じられているが縞はよい。紅型・藍型の模様染は士族以上のもので,それもその中での身分によって模様の大きさ(大きい柄ほど身分が高く,一幅に一つの模様がある一玉柄は王家専用,二玉,三玉は士族用)や色(金(黄)が最高,次いで赤,水色,茶色の順の地色)にきまりがあるなどである。また沖縄衣装のきれ地は,芭蕉布,苧麻(ちよま)布,木綿が主で,上流者の間に絹や桐板(とんびやん)が時に用いられた。
衣服の着装法は,庶民の場合,男子はふんどしの上に〈衣〉を着て,織帯(幅が10cm前後のミンサー帯)を締め,女子も腰布の上に〈衣〉を着て,織帯を締めるだけの簡単なものが基準であった。しかし士族以上は相当厳格に姿容を整えていたようで,古くは中国の属国であったところから上流階級の衣服は中国系であり,近世以降薩摩藩の統治下になってからも士族以上の正装は男女ともに中国系の濃厚なものであった。したがって近世以降明治にいたるまでの沖縄上流者の服装は,本土風が入ったとはいうものの男子はほとんど中国系の服装,女子は多分に本土風が取り入れられた服装という様相であった。明治になってから上流階級の男子は本土同様急速に洋服化するが,女子は近世以降に入った本土風が明治になったからといってそれ以上は入らなかったようである。ただ,夏季の女子のくつろぎ着としての着装法押衣(うしんちー)が,しだいに士族婦女子の一般的な夏季服装になってきたことが注目される。もともと押衣は,ごく内々の非常にくつろいだ時の服装である。士族以上の女性は常に下着としての袴をつけているが,押衣の時はふくらはぎくらいまでの丈の四布袴(よのばかま)で,その袴の腰の位置に小帯(ミンサー帯)を締める。その上から〈衣〉を着て,合わせた上前(うわまえ)の右腰部分を,下袴に締めてある小帯に,上から押し込むようにして挟み込む着装法である。1920年代ころまでは士族の女性は家居の場合でも威儀を正した服装で,夏季も〈衣〉の上に帯を締め,その上から田無(たなし)という絽地花織(花倉織)の夏季用打掛を着ていたという。明治時代の沖縄の絵画や大正時代から現代にいたる沖縄の写真資料にしばしば〈衣〉の前の打合せが左前(左衽(さじん))になっているのがあるが,中国の服装文化と日本の服装文化とのなんらかの影響が,現代にこういう現象となって残されているのだと思われる。
執筆者:神谷 榮子
美術工芸
資源の乏しい沖縄では,古くから中国,日本,朝鮮,南方の諸外国との交易によって文化を摂取しながら,亜熱帯特有の気候風土の中で独自の美術工芸をつくり育てた。それらを歴史的にながめると,1609年(慶長14)の薩摩藩の琉球征服以前と以後でその性格を異にしているといえる。慶長以前は海外貿易による豊かな財源を背景に,石造建築や彫刻を中心とする大規模な建造物群がつくられたのに対し,慶長以後は薩摩の支配の下,対外交易権を奪われて財源が困窮し,小規模の工芸品制作が行われた。慶長以後は琉球王府に〈貝摺奉行所〉や〈瓦奉行所〉が設置され,漆器や染織,陶器などの工芸品を王府が保護育成したため,工芸技術が一段と進歩した。それらの多くはかつて王家や士族用のものであったが,伝統技術は今も継承されている。
絵画
記録にのこる最古の絵画は察度(さつと)王(1395没)の肖像画(16世紀末)といわれるが,今では不明である。その後,尚円王以来歴代国王の肖像画が極彩色で描かれているが,いずれも画家の名は判明しない。王府時代の画家では欽可聖(きんかせい)(城間(ぐすくま)清豊,1614-44)が天才自了(じりよう)と呼ばれ,中国の陳元輔や日本の狩野安信らに推称されたという。17~18世紀には呉師虔(ごしけん)(山口宗季)とその弟子殷元良(いんげんりよう)(座間味庸昌)を生んだ。このころはおもに中国の技法を学びながら琉球独特の絵画を生み出し,琉球絵画が最も栄えた時期である。その後尚元瑚(小橋川朝安,1748-1841),呉著温(屋慶名政賀),慎思九(泉川寛永)らが輩出したが,総体として絵画は工芸ほどには振るわなかった。それは,絵画が工芸に従属し,絵師は工芸の下絵などで働いたからである。琉球絵画は日本にはあまり影響を与えず,殷元良や呉著温などは日本の画法を取り入れて《雪中雉子の図》や《雪中山水図》を描いている。
建築
沖縄の建造物は第2次大戦でことごとく灰燼(かいじん)に帰した。戦前における沖縄の代表的な建築物には,首里城内の守礼門,歓会門,瑞泉門,白銀門,正殿,首里円覚寺内の総門,左・右掖門,三門,仏殿,竜淵殿,鐘楼,獅子窟,那覇崇元寺内の総門,正廟,首里の園比屋武(そのひやん)御嶽,弁ヶ嶽,末吉宮,那覇の沖宮(おきのみや)などがあった。これらは大半が琉球の黄金時代といわれた尚真王(1477-1526)時代,あるいはそれ以前の創建になるものである。これらの建造物には唐様,天竺様,和様と種々の様式が認められ,中でも多くの城や石橋は技術的・造形的に優れたものであった。石造建築には石を切る鉄器をはじめ種々の高度の技術が必要であり,それを可能にしたのは尚真時代の経済的繁栄であったといえる。高度な石彫技術を示す遺品には15世紀の第一尚氏王統時代の世持橋の勾欄の羽目がある。砂岩に魚貝や海波模様が力強く彫り込まれているのは,海外貿易に挑んだ当時の人々の精神の現れとも見られる。また尚真時代の円覚寺放生池石橋の勾欄羽目や玉陵の屋根獅子などには珍しいセン緑岩が使用され,中国の石工との合作による琉球石造彫刻中の最高のものである。しかし慶長以後は薩摩産の花コウ岩による日本式雪見灯籠や三重塔灯籠のような優美なものにかわった。
木彫は沖縄に良質の木材が少なかったため,石彫に比べて劣っているが,円覚寺竜淵殿鳳凰板戸透彫や欄間竜彫刻,総門の仁王像などが作られ,また梅帯華(田名宗経,1798-1863)の《竜頭観音像》や《十六羅漢浮彫椰子合子》などが残っている。
陶芸
沖縄最古の瓦は中部の浦添(うらそえ)城跡から出土したおよそ13世紀初期の高麗瓦である。記録では15世紀中期に中国人が南部の国場で瓦を初めて焼いたとある。15世紀初期の陶器は南方系の素焼が多く,中部の知花(ちばな)や読谷(よみたん)村の喜名,北部の古我知(こがち)でおもに酒がめや水がめがつくられた。16世紀初期には喜名や知花の窯が王府によって那覇の壺屋に移された。そして17世紀初期に王府は薩摩から高麗人陶工張献功(一六),一官,三官らを招聘(しようへい)して朝鮮式陶法を伝授させ,さらに17世紀中期には陶工平田典通を中国に派遣して赤絵の技法を習得させた。18世紀初期には仲宗根喜元が初めて白土を陶土に使用し,さらに仲村渠致元(なかんだかりちげん)も薩摩で陶法を学び大型製陶に成功した。このように沖縄の陶器には南方系,中国系,朝鮮系,日本系があり,これらはいずれも壺屋で制作された。そして現在も魔よけの屋根獅子や置物の獅子,抱瓶(だちびん),碗,皿,壺などが,灰釉,飴釉,黒釉,呉須などを用いて焼かれ,魚文に代表される大らかな文様を施した温かみのある陶器が作られている。なお新城(あらぐすく)島(現,竹富町)で19世紀中ごろまで作られたパナリ焼は土器で,製法は古く中国人が伝えたともいわれる。つる草やタブノキの粘液を土に混ぜてこね,手で成形してカタツムリや貝肉の粘液を塗り,露天で焼いた。パナリ焼についての古謡も伝えられ,素朴で美しいフォルムが今日も喜ばれている。
漆器
古い記録に1429年に明より漆を買いに来たとあるので,このころには沖縄でも漆を使用していたと思われる。また,北部今帰仁(なきじん)の百按司(ももじやな)墓内の朱塗りの木製厨子や首里円覚寺扁額の漆絵などからみても,そのころすでに漆芸が相当発達していたと思われる。漆芸の技法はおもに日本から学び,ろくろの技術も1629年(寛永6)に日本の漆工が沖縄に漂着し,那覇の若狭町で塗物と一緒に伝えたという。その後王府は漆工芸に最も力を注ぎ,中国の技法も取り入れて,沖縄の夜光貝を使用して作った螺鈿(らでん)(青貝摺)や中国の堆朱(ついしゆ)の技法を応用した琉球漆器独特の堆錦(ついきん)が生み出された。また明治以降は木地に特産のデイゴが用いられ,木肌の粗いデイゴへの下地塗りにキリ油や泥岩に豚血(とんけつ)を混ぜる豚血下地が行われ,廉価で堅牢なため今日も伝承されている。そのほかにも彫りの線が太く重厚な沈金や漆絵などがある。これらの漆器はいずれも王府によって日本や中国へ献上あるいは輸出された。
染色
沖縄の代表的な染色工芸である紅型(びんがた)染は,近世初頭に南方の更紗や日本の友禅染の影響を受けて発達した。もっぱら王家や上流士族の間で使用され,制作も王府の監督のもとに首里の特定の紺屋,城間,知念,沢 (たくし)家で行われ,世襲であった。型紙を用いる型付には藍型(えーがた)もあり,藍型は琉球藍一色で染め,紅型は多色で染めたものをいう。型付に対して,手がきによる筒引(つつびき)の技法も行われる。これは筒袋からのり(糊)を出しながら描く糊引法で,おもにふろしきや舞台幕に用いられた。色彩は植物染料のほかに顔料や動物性の醒臙脂などを使用し,生地は,芭蕉布,苧麻,羽二重などもあるが,主として綿布を用いる。
(たくし)家で行われ,世襲であった。型紙を用いる型付には藍型(えーがた)もあり,藍型は琉球藍一色で染め,紅型は多色で染めたものをいう。型付に対して,手がきによる筒引(つつびき)の技法も行われる。これは筒袋からのり(糊)を出しながら描く糊引法で,おもにふろしきや舞台幕に用いられた。色彩は植物染料のほかに顔料や動物性の醒臙脂などを使用し,生地は,芭蕉布,苧麻,羽二重などもあるが,主として綿布を用いる。
織物
古くは一般に芭蕉布や苧麻が織られ,上流階級には木綿や絹が使用された。絹は14世紀に中国から,木綿は17世紀初めに薩摩から伝えられた。これらの織物は草木で糸を染めて織った。機織は古くはもっぱら地機で,後に高機の手機織を使用した。織物の種類は平織や絽織,綾織,ロートン織,浮織その他たいへん多い。王府時代は芭蕉布の最上品や麻の首里上布,絹織物の高級品は首里で最も盛んに織られた。高級品は王族や上流階級しか着用が許されなかったからである。一方,宮古上布や八重山上布,久米島紬,読谷花織,大宜味村の喜如嘉(きじよか)や今帰仁村の芭蕉布など,地域によって特色ある織物もつくられた。織柄には絣,縞,格子などがある。特に絣の技法は15世紀ころ南方から伝えられ,独特の清楚な琉球絣を完成し,さらにこれは日本本土の絣にも影響を与えた。
執筆者:外間 正幸
文学
沖縄文学は,奄美諸島(現,鹿児島県),沖縄諸島,宮古列島,八重山列島にまたがる地域で生まれた文学の総称で,古代文学と近代文学の二つに分けることができる。古代文学とは,沖縄が歴史的出発(3世紀ころ~6世紀ころ)をしてから,19世紀後半ころまでの間に琉球方言で表現された文学を指し,近代文学とは19世紀後半以後,主として日本的標準語で書かれた文学を指す。古代文学と近代文学の間には,歴史の変革に伴う文学の〈場〉の構造的な変質と,文学意識,および意識の媒体となる言語のあらたまり(琉球語→日本語)が明らかであり,それらをもって区別の基準とする。
→琉球語
古代文学
古代文学の内容は,その形態と発想の側面から呪禱文学,叙事文学,抒情文学,劇文学の四つに分けられる。呪禱,叙事,抒情の三つは,そのほとんどが唱えものか謡いもの,あるいは歌謡として韻文的に口承されてきたものであり,劇文学も韻律を伴ったせりふに,音楽,舞踊が組み合わされたもので韻文的である。このようにそのほとんどが韻文で構成されており,散文形式のものはかろうじて狂言などに見られる程度で,呪禱,叙事性を基層にした呪詞,歌謡中心の文学であることと,その言語が,ほとんど島ごとに異なった姿をみせていることが大きな特徴である。したがって,それらをそのまま日本文学の中に包みこむことはむずかしい。ただ,両者は言語も文化も源を同じくするものであり,文学の形態,発想そのものも本質的には同質で,日本文学の古形,あるいは独自に変成したとみられるものである。日本文学の歴史には痕跡しかとどめない原始的過程を暗示するものとして注目したい。
(1)呪禱文学 呪禱文学は言霊信仰に基づいた呪言によって唱えたり謡われたりするもので,奄美のクチ(口),タハブェ(崇(たか)べ),オモリ,マジニョイ(まじない),沖縄のミセセル,オタカベ(お崇べ),ヌダティグトゥ(宣立言),ティルクグチ(照るく口),ティルル(照るる),マジナイグトゥ(まじない言),宮古のニガリ(願い),マジナイグトゥ(まじない言),タービ(崇べ),ピャーシ(拍子),フサ(草),ニーリ,八重山のカンフチ(神口),ニガイフチ(願い口),カザリフチ(飾り口),ジンムヌ(まじない言)などがある。例を沖縄諸島にとれば,ここに伝わる呪詞・呪言のうち,もっとも古いと思われているものはミセセルとオタカベである。オタカベは,神を崇べ,神に対する宣立(のだて)のための祝詞(のりと)であることは,その内容と機能から明らかである。超人間的な力をもつ神にすがり,五穀豊穣の予祝をしようとする願望が,神祭りにおけるオタカベとなって発達したのである。島々の呪詞・呪言には多くの呼称があり,地域的な偏差と内容の変遷または重なりなどをもっているため,それぞれの呼称に対応した内容の区別をすることはきわめてむずかしい。中には,神々の呪縛と呪禱的な心意を離れ,集落の歴史や人事(ひとごと)を語る叙事歌的内容に変わっているものもある。ただそれらのすべてに共通することは,人と神との間をむすぶ呪詞としての機能をもっていることである。
(2)叙事文学 奄美のナガレ歌,八月踊歌,ユングトゥ,沖縄のクェーナ,ウムイ,オモロ,宮古の長アーグ,クイチャーアーグ,八重山のアヨー,ジラバ,ユンタ,ユングトゥなどがある。叙事文学もまた,歴史的変遷の中で呼称に応じた区別をしにくくなったものが多い。さらに呪禱と叙事と抒情との区別もしがたいほど内容の重複の見られるものすらある。それらの大部分は農耕儀礼にかかわりが深く,神々の呪縛の中に初源的な生命を育て,呪禱的心意や叙事性を含みこんだまま,共同体の生活の場に大きく広がっていったものである。沖縄のクェーナは,村落共同体の繁栄や幸福への願いを,対語・対句をつらね,連続・進行的に述べていく典型的な叙事的歌謡である。アマウェーダーと呼ばれるクェーナをみると,稲作のための整地から種まき,稲の生育,刈入れまでの過程を,順序よくていねいに謡いこむことによって,予祝すると同時に作業手順を正確に伝承していったことがうかがえる。このように,稲作その他の生産過程を表現することが,そのまま豊穣につながっていくのだという言霊信仰があり,それを基盤にしてクェーナ的古謡が生まれてきたようである。こういうクェーナ的古謡の形態と発想は,奄美,沖縄,宮古,八重山などの南島古謡に共通な基本的性格であるといえる。沖縄のウムイはクェーナを基盤にしながら,オモロという新しい歌形を生みだす母体になったものである。《おもろさうし》は16世紀から17世紀にかけて琉球王府が島々の古謡を採録したもので,沖縄の古代社会を研究するための大事な手がかりである。ウムイとオモロは本来同じものであるが,地方のウムイが中央で整理され,歌形をととのえていったものがオモロである。
(3)抒情文学 奄美の島歌(しまうた),沖縄の琉歌,宮古のクイチャー,トーガニ,シュンカニ,八重山の節歌(ふしうた),トゥバラーマ,スンカニなどがある。島歌,琉歌,節歌などは総括的な呼称で,それぞれの中でまた長歌形と短歌形に分けることができる。いずれも,もとは単に〈うた〉と呼ばれたものであるが,沖縄の〈うた〉が琉歌といわれるようになったのは,日本の和歌が,漢詩(からうた)に対して和歌(やまとうた)と称して区別されるようになったのと同じ事情であり,地域的変容と特性をもっている。琉歌は〈短歌形式〉〈長歌形式〉に二分し,前者は〈短歌〉〈仲風(なかふう)〉に,後者は〈長歌〉〈つらね〉〈木遣り〉〈口説(くどき)〉に分けることができる。短歌は8・8・8・6の4句30音から成る定型の短い文学形式で,普通に〈琉歌〉というときにはこれを指す。仲風は7・5・8・6の4句26音,もしくは5・5・8・6の4句24音から成る定型の短歌である。長歌は8・8・8・8と八音を連続し,末句を六音でしめくくる形式の歌である。八音の連続性が〈短歌〉より長いことが特徴であるが,長いといっても〈短歌〉に比べてという程度で,さらに長い〈長歌〉は別のジャンルの〈つらね〉に近くなってくる。八音を連ねて末句を六音でしめくくるのは,〈長歌〉〈つらね〉ともに同じであり,その点〈短歌〉も例外でない。木遣りは,建築用材を山からおろして引いていく時に歌われる労働歌である。口説は,七五音の連続を基調にし,いわゆる和文調の歌である。和語も取り入れられているし,読みも和風に読むのが正しい。もともと薩摩役人たちをもてなす宴席で歌われたという。
(4)劇文学 奄美の諸鈍芝居(しよどんしばや),狂言,沖縄の組踊(くみおどり),狂言,人形芝居,歌劇,宮古・八重山の組踊,狂言などが伝わっている。組踊は,沖縄の言語,文学,芸能をもって総合的に構成された独自の楽劇である。島々に伝わる伝説,説話を軸とし,古語を積極的に取り入れながら沖縄的な八八調の音律に調え,舞踊もまた古くから伝わる〈こねり〉〈しぬぐ〉などの祭式舞踊を組み合わせている。沖縄,宮古,八重山に伝わる狂言はそれぞれ独自であり,風土に根ざした〈笑いの文学〉である。人形芝居は,人形を操って各地を門付したもので,大和からの渡来であるという。歌劇は沖縄独特の歌舞劇である。せりふを琉歌の節(ふし)に合わせて掛けあいで歌い,しぐさや踊りをまじえながら劇を進めていくという形をとる。組踊がとかく王府や士族階層のもつ道徳律にしばられがちであったのに比べ,歌劇は庶民の生活の場にある喜びや悲しみをたくみにくみあげている。
近代文学
沖縄の文学は呪禱から叙事,抒情へと独自な形で数百年も続いてきた。しかし明治初年,幕藩体制の崩壊による日本の国家統一,近代化の過程で,沖縄もまた日本的体制の中にくみこまれることになったため,政治,経済,文化の諸面にわたって大きな変動がおこった。文学も例外ではなかった。まず言葉の面で日本的標準語が沖縄語の上にかぶさったため,沖縄語によるよりは標準語を使ったほうが,より広い場に通用し,多くの支持を得るようになった。文学環境のこのような変革を,沖縄における古代文学と近代文学のくぎりにすることができる。言語のみならず,社会の変動に伴う文学意識の変化も,はっきりとした様相を呈してくる。しかし,沖縄の島々を本土の体制の中にくみいれようとする上からの力は,さまざまな制度的差別,社会的差別を伴いつつ浸透してきたため,平和に生活してきた沖縄の人々の心に深い傷跡をとどめた側面があった。山之口貘(やまのぐちばく)の,〈お国は?〉と聞かれてひとこと〈沖縄〉といえない心の屈折を綴った〈会話〉と題する詩は,辺境“沖縄”であることの社会的被差別の痛みを表現しており,それはそのまま沖縄の近代化の歴史的苦悩を象徴するものでもあった。1879年以後,日本的標準語を使うことで近代文学への足がかりをつくった沖縄の文学は,明治30年代に〈近代短歌〉〈詩〉,40年代に〈小説〉という新しい文学形式を獲得してのち,中央の文学と同質化しようとするけんめいな努力を試みることになるが,山之口貘の独特な詩風を除いては,見るべき作品は生んでいない。沖縄の近代文学が,自覚的かつ自立的な文学として歩みだすのは,戦後の1955年以降にまたなければならない。
執筆者:外間 守善
芸能
沖縄は中国大陸にも東南アジアにも近い地理的環境から,古代日本的な民俗基盤の上に四方の国々の芸能要素を吸収して,汎東洋的ともいえる独特の芸能を発達させた。今日伝承される沖縄の芸能を大別すると,(1)琉球王国時代に王家の儀式などに演じられた宮廷芸能の芸統を伝えるもの。(2)1879年の廃藩置県後,民間に生まれた商業劇場を中心に専業の俳優や奏者によって創造され,その後,舞踊家などの参加によって舞台を中心に発展をみつつある芸能。(3)各市町村の生活の中で地域住民がみずから演奏者となって伝承してきている,いわゆる民俗芸能である。
宮廷芸能
沖縄島を統一した15世紀の第一尚氏王統の時代から第二尚氏王統の初期にかけて,宮廷では儀式舞踊として巫女集団によるコネリ(舞踊の古語。ナヨリとも)などが行われ,また,饗宴の席などでは当時全盛のオモロが赤犬子(あかいんこ)などの歌人によってうたわれたようだが,当時中国から三弦が伝来し,やがて三線(さんしん)とよばれて宮廷奉仕の士族たちがつま弾くようになるとオモロはすたれ,かわりに8・8・8・6調の短歌(琉歌と呼ぶ)を士族たちがつくって,それを三線にのせてうたうようになった。16世紀にはこの三線が本土へ渡って三味線を生むことになるが,宮廷では17世紀に湛水親方(たんすいおやかた)が出て三線歌曲の芸術化が急速に進み,18世紀には聞覚(もんかく),屋嘉比朝寄(やかびちようき)などが工工四(くんくんしい)と称する楽譜を編み,また19世紀には野村安趙が野村流を,安富祖(あふそ)正元が安富祖流を興して,近代の三線音楽を確立した。
舞踊は16世紀ころ,宮廷奉仕の若衆(わかしゆ)(未成年男児)が新国王の冊封に来琉する明国の冊封使を饗応する宴席で,華麗な扮装で踊りを披露し,17世紀にも童児の群舞が行われた。冊封使饗応の宴は宮廷最大の行事で,宴に披露する歌舞を企画・制作するのに高官の中から躍(おどり)奉行を選び,数年前から準備,稽古に入る慣行であったが,1719年,尚敬王冊封のときに躍奉行に選ばれた玉城朝薫(たまぐすくちようくん)(1684-1734)は,従来の舞踊にかえて,三線を伴奏にしながら歌とせりふで物語を展開する組踊と称する歌舞劇を創作して上演した。これが評判をえて,以後組踊が歴代創作されるようになったが,また彼は三線歌曲を伴奏にした舞踊を振付けし,のちの宮廷舞踊の基礎を固めた。この種の舞踊を端踊(はおどり)と呼ぶが,種目には老人踊,二歳踊(成年男子の踊り),若衆踊,女踊の四つがあり,それぞれで扮装と技法が異なる。演者はいずれも士族の子弟が勤め,若衆踊,二歳踊は該当年代の者,女踊は成年直後ごろの者の役割であったが,廃藩置県後はしだいに崩れ,女性も自由に踊るようになった。組踊で現存する台本は47に及ぶが,上演頻度の多いのは玉城朝薫作の《執心鐘入(しゆうしんかねいり)》《二童敵討(にどうてきうち)》《銘苅子(めかるしい)》《女物狂(おんなものぐるい)》《孝行の巻》の5番と,朝薫以後に出た平敷屋朝敏(へしきやちようびん)の《手水の縁》,田里朝直の《万歳敵討》,高宮城親雲上(たかみやぐすくぺえちん)の《花売の縁》,久手堅親雲上(くでけんぺえちん)の《大川敵討》などである。端踊では玉城朝薫が振り付けたと伝える女踊の《伊野波節(いのはぶし)》《諸屯(しよどん)》《作田節(つくてんぶし)》《綛掛(かせかけ)》《天川》《柳》などが,古いコネリの技法を歌舞伎踊の様式に融合させた点で特に優れる。二歳踊は,紋服姿の若者が本土風の七五調の口説歌などにつれて軽快に踊るもので,《上り口説》《前の浜》などの曲がある。若衆踊は,振袖あわせ衣装に引羽織をつけた若衆姿の踊手が《こてい節》などの祝賀曲をういういしく踊る。老人踊は老人姿の踊手が国や人の寿福を祝賀して踊るもので,本土の翁(おきな)に当たる。なお組踊と端踊を含め,宮廷舞踊を冠船踊(御を冠して呼ぶこともある)と総称するが,これは新国王の王冠をたずさえて来琉する冊封使の乗る船を冠船と称したことに由来する。
三線歌曲は,近世以前のものを〈昔節〉〈大昔節〉などといい,前者に《作曲節》《首里節》《諸屯節》など,後者に《茶屋節》《仲節》《十七八節》がある。すべて琉歌に三線を添えたものだが,近世になると,本土の和歌と琉歌を組み合わせた〈仲風(なかふう)〉や,口説を三線にのせるものも生まれた。三線に加えて箏,胡弓,笛,太鼓を合奏することもあるが,箏曲は18世紀初め,稲嶺盛淳が薩摩から八橋流箏曲を学んできたものの流れで,独特の独奏曲も伝承している。
近代劇場芸能
廃藩置県令施行後,禄を失った士族のうち芸に堪能な者が集まって,那覇市中の思案橋や仲毛(なかもう)にかます囲いの芝居小屋を仮設して踊興行を始めたのがきっかけで,1882年ごろにいわゆる沖縄芝居が始まった。当初は組踊,端踊をもっぱら演じていたが,大衆の嗜好に応えるため民謡,流行歌の類を三線にのせ,芭蕉衣や絣着の百姓娘と町女が軽快に踊る姉小舞(あんぐわもうい)を創作上演したり,当時隆盛の廓の遊女の風姿を描いた踊り,遊女と客の交情を描く劇舞踊などを演じて喝采を得た。現在も上演される《浜千鳥》《かなよう》《むんじゅる》《花風(はなふう)》《川平節(かびらぶし)》《金細工(かんぜいく)》などがそれで,これらは旧来の冠船踊に対して,雑踊(ぞうおどり)と総称された。当時,《むんじゅる》などを振り付けた玉城盛重は冠船踊にも熟達し,のちには踊師匠になって後継者養成に専念したので,近代沖縄芸能興隆の祖といわれる。新垣松含,渡嘉敷守良などの名優も輩出し,明治後期には3劇場に3座が鼎立して,歌の掛合で物語を運ぶ歌劇や,こっけい会話の狂言,歴史に取材した史劇などを次々に開拓し,沖縄芝居全盛期をつくりあげた。歌劇の名作《泊阿嘉(とまりああか)》や《薬師堂》《奥山の牡丹》などは今も上演されるが,それらの劇も昭和に入ると映画産業に押されて衰退し,珊瑚座などの活躍が一時はあったものの,太平洋戦争で劇場は壊滅した。戦後,ときわ座,大伸座,乙姫劇団などが出て各地を巡演,民心の鼓舞に功績があったが,テレビなどの普及で衰退した。かわって玉城盛重などの薫陶を受けた旧俳優や踊師匠によって育てられた男女の舞踊家が輩出し,冠船踊や雑踊を舞台にかけ,また創作舞踊を発表するなど舞踊家全盛の時代が到来した。芝居の衰退で伝承が危ぶまれた組踊も,1972年国の重要無形文化財に指定され,後継者養成の事業が進められている。
民俗芸能
沖縄諸島,宮古列島,八重山列島とも昔から芸能は盛んで,町や村の祭りをはじめ,婚礼,新築祝,年祝などの家庭行事,あるいは男女が集まっての野遊びなどさまざまの機会に人々はうたい踊った。大きな祭りは稲,アワの収穫期から次の年への播種期にかけて集中的に行われ,そこでは祭事をつかさどる巫女集団が古風な神歌をうたい,また遊(あそび)などと称する呪禱的な舞踊を演じたりする。沖縄島北部のシヌグや宮古島や大神島のウヤガン,あるいは12年目ごとに行う久高島のイザイホーの祭りなどは,特に古い巫女の歌舞を残している。また,村々の祭りに海のかなたのニライの国から仮装神が来訪する儀礼を伝える村が各地にあり,八重山列島の収穫祭に出現するアカマタ・クロマタや,年替りの節祭に出現するマユンガナシなどは特に名高い。芸能化したものでは,八重山列島に多い弥勒踊があるが,これはニライから稲,アワをもたらす弥勒のおとずれを歌と踊りで示すものである。また全域的にさまざまの祭りに登場する獅子舞も,遠くから来訪して災厄を払い豊穣をもたらすと信じられた神の芸で,シュロなどの繊維で編んだぬいぐるみの中に2人の踊手が入ってデイゴの獅子頭を振りまわしつつ豪快に踊る。その他祭りをにぎわす芸能で全域的に行われるものに棒術,棒踊の類があるが,棒術は真棒(まあぼう),組棒などといって,2人1組の男が三尺棒,六尺棒などを激しく打ち合わせるもの,棒踊はそれの舞踊化で,土地によって赤毛をかぶって曲技を演じたりする。これを南島(はえのしま)などというのは,南中国などから伝来したとの由来談があるからである。太鼓を打ちならす芸は沖縄,八重山にあり,沖縄島の中城(なかぐすく)村伝承の打花鼓(たあふあくう),今帰仁村伝承の路次楽は,ともに中国楽器の哨吶(つおな)(チャルメラ)を吹き,前者は太鼓,鉦,銅鑼(どら)を鳴らし,後者は小太鼓を打ちつつ道中する芸で,いずれも中国からの伝来を説く。また津堅(つけん)島伝承の大踊は本土系の太鼓踊の形を学んだもので,沖縄芸能のもつ芸能要素の多様性がしのばれる。八重山では獅子舞に添う形でペッソーと呼ぶ太鼓踊が行われ,また石垣島の川平には珍しい銭太鼓の踊りが残存する。
全域的には祭りの余興に村芝居を演じるのが盛んで,村ごとに演出を凝らした狂言や組踊を上演し,あいだに村独特の踊りを披露する。一方,島ごとでは,沖縄島にウスデークと呼ぶ女性の集団舞踊がある。琉歌調の歌につれて優雅に踊るもので,巫女の遊の舞踊化ともいえる。宮古島では祭りはもちろん,随時人が集まれば男女ともに踊るものにクイチャーがある。手を打ち,足を力強く踏み,跳ねながら踊る群舞である。八重山では祭りに踊る群舞をマキ踊といい,古風な手ぶりを伝える。盆祭の芸能では沖縄島にエイサーがあり,八重山には盆アンガマがある。前者は男女の集団が村内をめぐって念仏歌をうたい,その後民謡にのせての踊りを披露するもので,後者も覆面,仮装の者たちが各家々をめぐる。念仏は近世初頭ごろ本土渡来の念仏聖や京太郎(ちよんだらあ)と称する宗教芸能者が落とした種子とみられるが,京太郎の芸能は今も沖縄島の沖縄市などに,その演目の一部である馬舞や鳥刺(とりさし)舞などが伝承されている。人形芝居は昔京太郎にもあったが,その伝承は絶え,今帰仁村などに獅子人形の糸操りがわずかに伝わる。江戸時代,八重山在勤の士族間で行われた能囃子が,石垣島に大胴(おおどう)(大鼓)・小胴(こどう)(小鼓)の名で残っているのも珍しい。なお沖縄島で昔村の男女が月明りの晩などにうたい踊ったという毛遊びの風習は絶えたが,人々が集まればカチャーシイと呼ぶ三線の早弾きにのって,即興の手ぶり足ぶりで踊る習慣は今も生きている。
執筆者:三隅 治雄
沖縄[市] (おきなわ)
沖縄県,沖縄島(本島)中部,那覇市の北方22kmに位置する市。琉球王朝時代には越来間切(ごえくまぎり)を基盤に越来城が築かれていたが,首里王府の新政策によって,1666年(寛文6)越来間切と美里間切に分離し,1908年特別町村制の施行で,越来村,美里村に改称した。56年6月越来村はコザ村と改称し,翌月市制を施行した。美里村の一部が石川市となって分離したが,74年コザ市と美里村が合併して沖縄市と改称。人口は13万0249(2010)で,沖縄県第2の都市である。合体により沖縄市の総面積は49km2,そのうち36%が軍用地で,嘉手納基地の一部も含まれる。基地の恒久化に伴って成長してきた都市で消費都市の性格が強い。基地依存からの脱却が進み,市の東部海浜地区では中城(なかぐすく)湾開発が行われており,埋立地に工業団地の建設が進む。70年12月にはアメリカ軍支配に反発するコザ暴動が起こっている。沖縄自動車道の沖縄南,沖縄北の二つのインターチェンジがある。
執筆者:田里 友哲
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「沖縄」の意味・わかりやすい解説
沖縄[県]【おきなわ】
→関連項目九州地方|ゴーヤーチャンプルー|残存主権|日米密約|琉球諸島|琉球文化
沖縄[市]【おきなわ】
→関連項目コザ
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「沖縄」の解説
沖縄
おきなわ
沖縄史の初めは言語・文化を同じくする日本人の一部がこの列島に住みついたことに始まると思われる。伝説としては,源為朝が八丈島から沖縄島に渡り,土豪の妹を妻として一子を得,これが第1代の王となったとされるが,もとより史実とはいえない。11世紀ごろから按司 (あんじ) と呼ばれる族長が支配する部族国家が分立し,やがてそれらの上に世主 (よのぬし) が出現し,各地に割拠した。14世紀には,北山・中山・南山の3勢力にまとまり,明にそれぞれ朝貢し,特に中山朝は,アンナン・ジャワ・シャムなどを対象とする東南アジア貿易を発展させ,またその商船は博多や坊津に来航して南洋方面との貿易を中継するなどの動きをみせていた。15世紀の初め,尚氏が台頭,同世紀の末には本島を政治的に統一し,16世紀の初めまで琉球史上の全盛期を現出した。この尚王朝が明治維新まで続く。1609(慶長14)年の島津氏の侵攻は琉球王国に大きな打撃を与えた。その後は,島津氏と,中国の明・清への両属を余儀なくされた。しかも島津氏の琉球人に対する本土の風俗・言語の使用を禁じる政策は,本土人と琉球人の民族的一体化を妨げた。明治維新後,新政府は1874年台湾出兵を行い,琉球の日本帰属を諸国に黙認させ(琉球帰属問題),'79年沖縄県とした。沖縄県となってからは知事や県庁の首脳部をはじめ指導者層はすべて本土から派遣され,急速に日本化が推進されたが,本土と同じ自治制度となったのは1920年であり,本土と異なる差別的な特殊事情が存続した。また経済的にも本土の資本や商人の進出で不安定であった。太平洋戦争末期,沖縄は激しい攻防の戦場となり,住民は大きな被害をうけた。'45年アメリカ軍に占領され,以後その軍政下に置かれた。'51年サンフランシスコ平和条約締結以後も,第3条の規定によってアメリカの権力下に置かれたので,住民の自治権は限られ,生活は基地に左右された。悲願の日本復帰運動は '72年に実を結び,沖縄は新しい道を進むことになり,'75年には海洋博覧会が開催された。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「沖縄」の解説
沖縄(おきなわ)
1872年,明治政府は琉球(りゅうきゅう)国を琉球藩に吸収し,国王を藩王としたが,その帰属をめぐって中国との間になお抗争が続いていたため,79年に琉球藩の廃止と沖縄県の設置を断行した。帰属問題は未解決な課題を残していたが,日本が日清戦争で勝利したことでその問題は決着するに至った。しかし太平洋戦争末期には大激戦地となり,民間人を含む多数の戦争犠牲者を出した末にアメリカ軍に占領された。その結果,1951年のサンフランシスコ講和会議によりアメリカ施政下に琉球政府が置かれた。その後長い間の交渉と国際状況の変化により,71年に沖縄返還協定が締結され,翌年5月に日本に返還された。ただ返還後もアメリカ軍の基地移転やアメリカ兵犯罪の処置などをめぐって今なお多くの問題を抱えている。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の沖縄の言及
【琉球】より
…沖縄の別称。1372年から1879年までの約500年間,沖縄の公式名称として用いられた。…
【八重山地震津波】より
…1771年4月24日(明和8年3月10日)午前8時ころ,〈石垣島付近東南東数十粁の処を東北東西南西に走る線〉を震源地とし,マグニチュード7.4の地震が発生した。その結果,まもなく未曾有の大津波が八重山・宮古両列島(現,沖縄県)の島々村々を襲った。津波の被害が甚大で,〈明和の大津波〉とも呼ばれる。…
【琉球処分】より
…沖縄の廃藩置県のこと。明治政府は王国体制のまま存続しつづける琉球の処遇について画策し,1872年(明治5)9月,琉球王国をひとまず〈琉球藩〉とし外務省の管轄とした。…
※「沖縄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
「歓喜の歌」の合唱で知られ、聴力をほぼ失ったベートーベンが晩年に完成させた最後の交響曲。第4楽章にある合唱は人生の苦悩と喜び、全人類の兄弟愛をたたえたシラーの詩が基で欧州連合(EU)の歌にも指定され...

 日本最南端の県。
日本最南端の県。 沖縄県、
沖縄県、