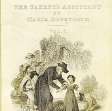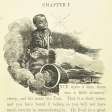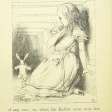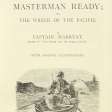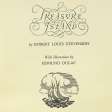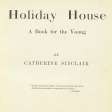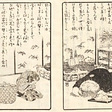精選版 日本国語大辞典 「児童文学」の意味・読み・例文・類語
じどう‐ぶんがく【児童文学】
- 〘 名詞 〙 児童を読者対象として、その情操を豊かにするためにおとなが書いた文学の総称。読者の年齢による、幼児童話・幼年童話などの分類のほかに、ジャンルによって童話・少年少女小説・童謡・少年少女詩・児童劇などの分類もある。
- [初出の実例]「小波さんのわが児童文学の上に印せられた足跡はこの上もなく大きい」(出典:書物(1944)甲〈森銑三〉二五)
日本大百科全書(ニッポニカ) 「児童文学」の意味・わかりやすい解説
児童文学
じどうぶんがく
概説
大人が子供をおもな読者と想定して創作した文学。形式上、絵本、童話、小説、童謡、詩、戯曲などの純創作に、神話、伝説、昔話などの再話、『ロビンソン・クルーソー』のような本来大人の文学で子供によってこの分野に含まれたものの再話や、広く知識の本までをも含み込む。
[神宮輝夫]
大人の文学との違い
1960年代末以降、年齢の高い子供や若者を読者とした作品は内容的に大人の文学と近いため、改めて違いが問われた。児童文学に含まれて生き続けている昔話などの伝承文学は本来口誦(こうしょう)文学であったため、表現の簡明、形式の共通性、大きな主題などの特質をもつ。さらに、伝えられる主題は語り手個人のものではなく、多数の人間の知恵の結晶として代々伝えられたものである。児童文学は小説を含めてほぼ前述の特質と共通する性質をもっている。だから、児童文学とは、筋の展開と結末についてほぼ一定の形式(あるいはパターン)があり、個人のというより人類の知恵が発見した、人間についての基本的主題を伝達する文学だともいえる。これが児童文学の中心部分を形成し、その周辺に大人の小説と性質の同じ作品が同心円的に存在している。だが、それらにしても、登場人物と状況はあくまで少年少女・若者の立場と視点から描かれているという点で、やはり大人の文学とは異なっている。
[神宮輝夫]
外国
18世紀以前は、とくに子供を読者とする本はほとんどなかったから、子供たちは神話、伝説、昔話や『イソップ』の寓話(ぐうわ)(イソップ物語)などを語り聞かされた。もっとも、イギリスの歴史家ベーダの『博物の本』(8世紀)やボヘミア人の牧師コメニウスの『世界図絵』(1658)のような教科書類や、清教徒ジェームズ・ジェインウェイJames Janeway(1636―1674)の『子供への贈りもの』(1671~1672)のような宗教教育・しつけの本はわずかながらあった。また、ルイ14世の宮廷から、シャルル・ペローの『昔話集』が生まれた。
[神宮輝夫]
18世紀
市民社会の興隆と啓蒙(けいもう)主義が近代小説と児童文学を生み出した。デフォーの『ロビンソン・クルーソー』(1719)は冒険精神や明快さのゆえに、スウィフトの『ガリバー旅行記』は奔放な想像力の展開のゆえに、すぐに平均24ページの小冊子「チャップブック」となって子供に手渡された。こうした現象に新しい市場を予知したジョン・ニューベリーは、ジョン・ロックの教育論を基礎に「教育と娯楽」を目的として『かわいいポケットブック』(1744)ほかを出版し、子供の本出版に先駆的役割を果たした。セアラ・フィールディングSarah Fielding(1710―1768)もロックの教育論と方法に忠実で、兄ヘンリー・フィールディングやサミュエル・リチャードソンの助言を受け、児童文学史上最初のフィクション『少女のための小さな塾』を発表し、少女小説の源となった。
ルソーの影響も大きかった。ドイツのカンペJoachim Heinrich Campe(1746―1818)は『新ロビンソン・クルーソー』で漂流記に自然哲学思想を加味した。フランスのジャンリス夫人Mme de Genlis(1746―1830)は、フェアリー・テイル(おとぎ話)を無益と批判した書簡集『アデールとテオドール』(1782)を出し、アルノー・ベルカンArnaud Berquin(1747―1791)は『子供の友』(1782~1783)で名高い。イギリスのトーマス・デイThomas Day(1748―1789)は『エミール』の子供版『サンドフォードとマートン』(1783~1789)を出し、マライア・エッジワースは『両親への助言者』(1796)ほかで知られる。『こまどり物語』(1786)で有名なトリマー夫人Mrs. Sarah Trimmer(1741―1810)と、『ソールズベリー草原の羊飼い』(1795)を含む宗教教育パンフレットで名高いハンナ・モアHannah More(1745―1833)の2人は、昔話や冒険などを否定し、信仰、しつけ、知識の増進を主眼に活発な活動をした。
[神宮輝夫]
19世紀
想像力の所産
この世紀の子供の文学にはロマン主義の影響が強い。想像力の自由な展開の主張は、民間伝承の文学の新たな評価と収集を促した。ドイツでは、A・アルニムとC・ブレンターノが『少年の魔法の笛』(1806)を、グリム兄弟が『子供と家庭のための童話』(1812より)を出版し、ドイツ民衆の心と民族の魂を探るとともに、それらを子供に伝え、昔話・童謡収集と再話、および新しい想像力の展開へ道を開いた。以後、アスビョルンセンとヨルゲン・モウJørgen Moe(1813―1882)の『ノルウェー民話集』、アファナーシエフの『ロシア民話集』、ジョーゼフ・ジェイコブズJoseph Jacobs(1854―1916)の『イギリス民話集』などが続いた。
伝承文学の新たな評価は、デンマークの作家アンデルセンをして、昔話に根を下ろした独自な人生観や美意識を展開する『子供のためのお話』(1835)を創作させた。彼は生涯で160余に及ぶいわゆる「アンデルセン童話」を残し、子供の文学の価値の認識を大きく変えた。ドイツではE・T・A・ホフマンが、色彩豊かな幻想性と奇異な物語の展開でのちにバレエになった『くるみ割りとネズミの王さま』を、W・ハウフは形式や素材に『アラビアン・ナイト(千夜一夜物語)』の、また幻想にホフマンの影響が明らかな『隊商』ほかを創作した。
世紀後半になると、主としてイギリスで、伝承文学の内容を含みながらもその形式に縛られない想像力の所産が生まれ、それらがのちにファンタジーとよばれるようになった。聖職者で社会改良家チャールズ・キングズリーは、聖書的宇宙観と生物進化論の融合をモチーフに『水の子』を書き、オックスフォード大学の教授ルイス・キャロルは、常識と非常識の衝突から真実を明らかにしようとした『ふしぎの国のアリス』『鏡の国のアリス』を発表して、子供たちに新しい空想の楽しさを知らしめた。またエドワード・リアは、『ナンセンスの絵本』で韻文のナンセンスの楽しさを集大成した。聖職者として出発したジョージ・マクドナルドは、『北風のうしろの国』その他で神を探究してファンタジーの本流を築いた。
[神宮輝夫]
冒険小説
イギリスのロマン派の小説家ウォルター・スコットの『アイバンホー』を代表とする歴史ロマンスは、冒険と夢と英雄たちの華麗な過去のイメージで子供を楽しませ、同時に歴史物語の源流をもなした。アメリカのスコットとよばれたジェームズ・フェニモア・クーパーの『モヒカン族の最後』を含む『革脚絆(かわきゃはん)物語』五部作は、未開の大自然の冒険と高貴な自然人アメリカ・インディアンへのあこがれをかき立て、やがてドイツで『大西部』をはじめとするカール・マイの通俗西部小説や、イタリアのエミリオ・サルガーリEmiglio Salgari(1863―1911)の西部小説などを生んだ。
フランスでは、スコットの影響下にアレクサンドル・デュマが『三銃士』『モンテ・クリスト伯』など、興味深い人物と事件の絡まりから娯楽性に富む読み物を大人と子供に贈り、ジュール・ベルヌは、ロマン主義精神を基礎に、科学が開く未来を鋭く洞察した『地底旅行』(1864)、『海底二万里』などの空想科学小説の分野を創造した。
イギリスでは、『ロビンソン・クルーソー』の伝統にロマン主義精神が加わり子供向きの冒険物語の空前絶後の発展がみられた。海軍軍人だったマリアットFrederic Marryat(1792―1848)は、スイスのウィースの自由奔放で科学的事実を無視した『スイスのロビンソン』に腹をたてて、事実に忠実な子供向きロビンソン『老水夫マスターマン・レディ』(1841)を書いて子供のための冒険小説の開祖となり、『ニュー・フォレストの子供たち』で子供のための歴史小説を生み出した。バランタインRobert Michael Ballantyne(1825―1894)の『サンゴ島』はやはり少年版ロビンソンだが、主人公たちは、19世紀イギリスが求めた少年の理想像であった。こうした作品には教訓性が色濃く付きまとっていたが、それを取り除き、適確な人物創造と、巧みなエピソードの選択と筋立てにより冒険小説の模範となったのがR・L・スティーブンソンの『宝島』だった。これに刺激されてライダー・ハガードが書いた『ソロモン王の宝窟(ほうくつ)』も読者を魅了した。
[神宮輝夫]
日常生活物語
前世紀以来の教訓性を色濃く残しながら徐々に感傷性の強い興味中心の物語へと移行した。読者も登場人物も主として少女だった。イギリスでは、清教徒的宗教教育を主眼としたシャーウッド夫人Mary Martha Sherwood(1775―1851)の『フェアチャイルド家の子供たち』、シャーロット・ヤングCharlotte Mary Yonge(1823―1901)の『ひなぎくの鎖』、ドイツではクリストフ・フォン・シュミットChristoph von Schmidt(1768―1854)の『イースターの卵』、グスタフ・ニーリッツGustav Nieritz(1795―1876)の『盲目の少年』などが教訓や感傷に満ちた物語を通じて少女や少年の理想の姿を描いていた。だが全体の風潮のなかからも徐々に進歩のしるしは現れた。イギリスでは、キャサリン・シンクレアCatherine Sinclair(1800―1864)が『別荘物語』で教訓性の薄い、生き生きと子供らしい少年少女が登場する物語を発表した。世紀後半のJ・H・ユーイング(ユーイング夫人)の『ジャカネイプス』ほかの作品は冷静公平に人間を描き、真にリアリズムといえるものとなった。モルズワース夫人Mary Louisa Molesworth(1839―1921)は『キャロッツ』で幼児の内面に光をあて、さらに『カッコウ時計』で子供の空想を物語化して、日常生活のなかの魔法という新しいファンタジーを創造した。
アメリカでは、フロンティアの存在が想像力を上回る夢だったためか、本来リアリズムが本流で、メアリー・メイプス・ドッジがオランダを舞台に『ハンス・ブリンカー』で血の通った子供を描き、ルイザ・メイ・オールコットが『若草物語』ほかで生活の細部に忠実なアメリカの少年少女群像を家庭生活のなかで活写した。彼女には多少の感傷性と教訓性が残っていたが、マーク・トウェーンの『トム・ソーヤの冒険』『ハックルベリ・フィンの冒険』にはそれらはまったくなく、真の庶民の子供の目で社会を見つめる批判精神が横溢(おういつ)し、子供の大人に対する優越性を強く打ち出し、アメリカ・リアリズムの基礎を築いた。現実を基礎にアメリカ的理想を空想の物語にまとめたのが世紀の変わり目の1900年に出たフランク・バウムの『オズの魔法使い』だった。
子供は大人より優れているというロマン派的な考えは、スイスのヨハナ・シュピリの『ハイジ』やアメリカのバーネット夫人の『小公子』などで、優れた物語性とともに極度に増幅されて、以後今日に至るまで児童観に強い影響を与えている。イタリアのカルロ・コッローディの『ピノッキオ』は、本来の教訓性よりも生きた子供像が読者の心をつかみ、エドモンド・デ・アミーチスの『クオレ』も人道主義的理想が子供に感動を与えた。
[神宮輝夫]
絵本
増大する市場と印刷技術の向上、さらに子供への認識の深まりは、優れた挿絵や絵本を生み出した。ドイツのハインリヒ・ホフマンの『もじゃもじゃペーター』、ウィルヘルム・ブッシュの『マックスとモーリッツ』、イギリスでは、ナンセンス詩人リアの『ナンセンスの絵本』に始まり、ウォルター・クレーンWalter Crane(1845―1915)、ランドルフ・コールデコットRandolph Caldecott(1846―1886)、ケイト・グリナウェイKate Greenaway(1846―1901)などの諸作によって、19世紀絵本の黄金時代がもたらされた。
[神宮輝夫]
20世紀
第一次世界大戦まで
各国とも新しい世紀の動きと古い伝統の交替が始まりながらも、まだ真に20世紀的なものは生まれなかった。もっとも豊かな実りはイギリスがもたらした。ビクトリア時代(1837~1901)の余光で安定した繁栄のなかにあったため、作家たちは人生のもっともよい時としての子供時代を作品化して子供と共有した。ジェイムズ・バリーは『ピーター・パンとウェンディ』で人間の本源的な夢を語り、ラディアード・キップリングはルソーの思想の流れをくむジャングルの冒険物語『ジャングル・ブック』ほか、幼年文学、学校物語、歴史小説に新機軸を生んだ。ケネス・グレアムが美と詩と笑いとを込めた『たのしい川べ』は人々に喜びを与え、E・ネズビットは『宝さがしの子供たち』で自然な子供の姿をとらえ、『砂の妖精(ようせい)』でモルズワース夫人Mary Louisa Molesworth(1839―1921)の創(つく)ったファンタジーを完成した。ビアトリクス・ポターの『ピーター・ラビット』絵本やヘレン・バナーマンHelen Bannerman(1862―1946)の『ちびくろサンボ』も全体的な豊かさの産物といえよう。
以上の収穫に、たとえば大人数の音楽家一家の日常を扱ったアグネス・ザッパーの『愛の一家』や、蜜蜂(みつばち)を中心に虫の世界が人間について寓意(ぐうい)を込めて語られたワルデマール・ボンゼルスの『みつばちマーヤ』などドイツの作品を加えると、古いものを含みつつ新しい動きがみえてくる。スウェーデンの文部省が、祖国を子供に教えるための物語として依頼した結果である『ニルスのふしぎな旅』(セルマ・ラーゲルレーブ作)なども、各国が意識的に子供の文学を重視し始めた一つの証拠だった。
[神宮輝夫]
1920年代
アメリカは新しい国であるため当初から教育に力を注ぎ、1909年にホワイトハウスで青少年問題会議が開かれて子供への関心がさらに高まり、1922年にはニューベリー児童文学賞(ニューベリー賞)が創設され、子供の本の書評誌『ホーン・ブック』が1924年に創刊された。ヒュー・ロフティングの『ドリトル先生アフリカゆき』は、着想の新鮮さ、物語の簡明さ、反戦平和の理想など真に20世紀的な作品だった。同じ理想主義が、オーストリアの作家フェーリクス・ザルテンの『バンビ』をはじめとする動物物語にもみられる。動物をいわば内面から描いた迫真的な物語の背後に平和への強い願いがある。革命後のソビエト連邦は、浮浪児の盗みを通じて新生国家とそのなかでの生き方を描いたパンテレーエフの『金時計』や、革命と内戦の時期を生き生きと物語化したガイダールの『ボリスの冒険』などを生んだ。これらに比べイギリスは、逃避性の強い詩的ファンタジー全盛時代で、類型的な作品が数多く出た。なかでも驚異と美と人間の真実を表現しえているのは、『三匹の王子ザル』で知られるウォルター・デ・ラ・メア、『ヒナギク野のマーティン・ピピン』のエリナー・ファージョン、『クマのプーさん』のA・A・ミルンなどである。
[神宮輝夫]
1930年代
1920年代末に始まった経済恐慌とそれに続く政治危機および後半の戦争は児童文学にも大きな影響を与えた。全体的傾向は社会・生活への意識が強かった。恐慌の発端であるアメリカでは、黄金時代への回帰と、理想の再確認ともいうべき西部開拓時代が、キャロル・ブリンクCarol Ryrie Brink(1895―1981)の『キャディ・ウッドローン』やL・I・ワイルダーの『大きな森の小さな家』とその続編で描かれた。ハンガリー出身のケイト・セレディKate Seredy(1899―1975)によるハンガリー農村を描いた『よき地主』や、ブルガリアの農村に住む少年を描いたモニカ・シャノンMonica Shannon(1890?―1965)の『ドブリー』などもアメリカの理想の一表現であった。エリナー・エステスの『モファットきょうだい』と続編2冊には貧困の影が付きまとっていた。
イギリスでも、小説家ジャック・リンゼーJack Lindsay(1900―1990)や児童文学作家ジェフリー・トリーズGeoffrey Trease(1909―1998)が一時期社会主義イデオロギーを宣伝する諸作を書くなど全般にリアリズムが強く、イーブ・ガーネットの『ふくろ小路一番地』のようにスラム街の労働者一家を暖かい同情を込めて活写する作品なども生まれ、ほかにも働く子供を登場させる作品が続いた。アーサー・ランサムは、休暇中の子供たちを精密に描写しながら、冒険精神あふれる物語の楽しさを現代によみがえらせて子供の文学の地位を高めた。だが、生きた子供群像の冒険を通じて現実生活の問題に触れ、理想を掲げて時代を批判しこの時期の精神をもっともよく表現したのは、ドイツのエーリヒ・ケストナーによる『エミールと探偵たち』『飛ぶ教室』などの作品だった。
ファンタジーは、イギリスで、独創的なお手伝いさんがナンセンシカルな不思議を演じて驚異と美を伝える『風にのってきたメアリー・ポピンズ』(パメラ・トラバース)や、のちに『指輪物語』に拡大されたJ・R・R・トールキンの叙事詩的ファンタジー『ホビットの冒険』、アリソン・アトリーAlison Uttley(1884―1976)のタイム・ファンタジー『時の旅人』などの傑作が生まれた。いずれにも強い批判精神と逃避性の混合がみられる。
[神宮輝夫]
1950年代
第二次世界大戦後は、世界平和の理想、国際協調の強化、文化交流など、多くの要因が重なって、児童文学が全世界的なものになった。たとえば、スウェーデンのアストリッド・リンドグレーンは超能力少女の奇想に満ちた冒険物語『長くつ下のピッピ』(1945)、幻想的英雄物語『白馬の王子ミオ』(1956)などで、子供の内面世界と行動力を巧みな物語にした。現実味のある物語ではエディト・ウンネルスタードEdith Unnerstad(1900―1982)、ハンス・ペテルソンHans Peterson(1922―2022)らが地域性豊かに少年少女を描いてみせた。ノルウェーからはトールビョン・エグナーThorbjørn Egner(1912―1990)の、絵と曲が加わった人間味あふれるコメディー『ゆかいなどろぼうたち』と、アルフ・プロイセンの、突然スプーンほどに小さくなる癖のある主婦の話『小さなスプーンおばさん』が、フィンランドからは、最初スウェーデン語で書かれ、のち世界各国語に訳されたトーベ・ヤンソンの『ムーミン谷の彗星(すいせい)』に始まる「ムーミン」シリーズが出た。
1930年代にジャン・ド・ブリュノフの『ババール』を出した程度で振るわなかったフランスも、『ゾウのサマ』ほかの動物物語のルネ・ギヨRené Guillot(1900―1969)、『首なし馬』のポール・ベルナ、『少年と川』のアンリ・ボスコなどが出て活況を呈したが、もっとも有名になったのは、人間についての深い思索の込められたサン・テグジュペリの遺作『星の王子さま』だった。ドイツにおいても発達は目覚ましく、戦後まもなく歴史の転換点に焦点をあてた歴史小説を次々発表したハンス・バウマン、ドイツ・メルヘン的想像力により人類の理想を語ったジェイムズ・クリュスJames Krüss(1926―1997)、昔話的素材から楽しくわかりやすい物語『小さな魔女』ほかを生み、幼い子供たちに生きる喜びを伝えたオトフリート・プロイスラーなどが活発な活動を始めた。
英語圏における発達も目覚ましく、イギリスではローズマリ・サトクリフの『ともしびをかかげて』、シンシア・ハーネットCynthia M. Harnett(1893―1981)の『羊毛の梱(こり)』などの考証と想像力による精緻(せいち)な歴史小説、ウィリアム・メインの鋭い心理洞察と新鮮な筆力による『五月のミツバチたち』、ルーシー・ボストンの古い屋敷のファンタジー『グリーン・ノウの子供たち』などが続々出版された。なかでも、永遠の生と神を探究したC・S・ルイスの『最後の戦い』を中心とするいわゆる「ナルニア国物語」7巻と、トールキンの『指輪物語』3巻は、子供の文学とくにファンタジーの可能性を大きく広げ、今日も大きな影響を与え続けている。さらに、フィリッパ・ピアスの『トムは真夜中の庭で』もこの時期の傑作とされている。
アメリカのリアリズムは、オランダ系のマインダート・ディヤングの『コウノトリと六人の子供たち』によって子供の内面を探る深味をもち、スコット・オデールScott O'Dell(1898―1989)の『青いイルカの島』によって非常に高度な文学性を獲得するに至った。ファンタジーでも、ホワイトE. B. White(1899―1985)の『シャーロットのおくりもの』のように生活実感と非凡な着想が融合した佳作を生んだ。1950年代は、全体に理想主義的、楽天的であり、また児童文学らしさの枠が暗黙に守られていた時期だった。
[神宮輝夫]
1960年代以後
モラルの変化、科学技術の急速な発展とくにメディアの多様化、経済の拡大などが相まって、子供をめぐる状況が大きく変わり、児童文学も急激な質的変貌(へんぼう)を遂げた。その一つは、ゴールディングの『蠅(はえ)の王』(1954)やサリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』(1951)など、大人の小説とみなされていた作品が児童文学の外縁に位置するほどに範囲が広がったことである。象徴的な作品はイギリスのジョン・ロウ・タウンゼンドの『アーノルドのはげしい夏』で、16歳の若者の展望のない生活の実態描写が激しい論議をよんだ。以後イギリスではジル・ペイトン・ウォルシュJill Paton Walsh(1937―2020)、K・M・ペイトン、ウィリアム・コーレットWilliam Corlett(1938―2005)らがこの分野で優れた仕事を続けている。領域の広がりは、また、子供と状況をよりリアルにつかむ視点をもたらした。
ドイツでは、ハンス・ペーター・リヒターHans Peter Richter(1925―1993)がナチ政権下のユダヤ人の悲劇を『あのころはフリードリヒがいた』にまとめ、ペーター・ヘルトリングPeter Härtling(1933―2017)は『ヒルベルという子がいた』で障害児の問題を真正面から見つめた。またオーストリアのネストリンガーChristine Nöstlinger(1936―2018)は、敗戦直後のオーストリアの状況を子供の目で描いた手堅いリアリズム作品『あの年の春は早くきた』ほかで新しい魅力を生み出している。
より現実に近づこうとする流れは、必然的に、子供を取り巻く諸差別、偏見、無理解などに対する強い批判をモチーフとする作品を生み出した。イギリスは従来こうした傾向を好まなかったが、1970年代中ごろから、バーナード・アシュリーBernard Ashley(1935― )、ロバート・リースンRobert Leeson(1928―2013)、ジャン・ニードルJan Needle(1943― )らが、人種差別、階級差別に対する批判や子供に対する大人の責任などを鋭くついた作品を書き始めた。
アメリカでのこの動きははるかに早く強かったが、『バビロンまではなんマイル』でアフリカ系アメリカ人少年の夢想と現実を子供の目で適確にとらえたポーラ・フォックスPaula Fox(1923―2017)、『グローバーくん』で極限的状況下の子供の強さを描いたクリーバー夫妻Vera Cleaver(1919― ), Bill Cleaver(1920―1981)、『わたしはアリラ』でアフリカ系アメリカ人や北米先住民の歴史と夢と現実を語ったバージニア・ハミルトンVirginia Hamilton(1936―2002)などによって、問題中心、抗議第一の段階をはるかに超える高みに達している。
ファンタジーの分野も、叙事詩的ファンタジーにアラン・ガーナーの『フクロウ模様の皿』、アーシュラ・ル・グウィンUrsula Le Guin(1929―2018)の『影との戦い』などが生まれ、ドイツではメルヘンの伝統と哲学性の濃いミヒャエル・エンデの『はてしない物語』が新鮮な世界を開いた。
[神宮輝夫 2018年2月16日]
日本
明治以前
古くは鳥羽僧正(とばそうじょう)(覚猷(かくゆう))の作といわれる『鳥獣戯画』(12世紀)その他の絵巻物があり、南北朝から江戸初期にかけて成立した御伽草子(おとぎぞうし)や江戸期の絵草紙などは、いずれも同時期のヨーロッパの類似のものに比べてはるかに優れていた。また知識の本なども、中村惕斎(てきさい)による『訓蒙図彙(きんもうずい)』(1666)など、コメニウスの仕事と同様な高い史的価値をもっている。
[神宮輝夫]
明治期
19世紀後半に始まった明治維新による近代化は児童文化の意識的開拓を促し、まず総合誌『少年園』(1888創刊)、『小国民』(1889)、『日本之少年』(1889)などの雑誌ジャーナリズムがおこり、『日本之少年』の博文館が硯友社(けんゆうしゃ)系の作家たちによる『少年文学叢書(そうしょ)』32巻を始め、第1巻の巌谷小波(いわやさざなみ)作『こがね丸』(1891)が事実上日本の児童文学の第一作となった。小波は日本と外国の伝承文学を再話する一方で、『猿蟹後日譚』などいわゆる「おとぎ話」の名で創作を続けて児童文学を確立した。一方、『魯敏遜(ロビンソン)漂流記』(井上勤(つとむ)訳、1883)、『十五少年』(森田思軒訳、1896)などの翻訳は、やがて押川春浪(おしかわしゅんろう)の『海底軍艦』(1900)に始まる50余の作品や、江見水蔭(えみすいいん)の『海国男児』(1901)を生む。小波の伝承文学的文体による伝統的モラルの新時代的表現、それから春浪らの軍国冒険物語は、児童文学史的には「物語」的特質の継承とみることができる。これに比べ『女学雑誌』(1885創刊)に『小公子』(1890~1892)を翻訳した若松賤子(しずこ)の業績は、キリスト教道徳という別なモラル体系の紹介とともに、小説的性質を児童文学に導入したとみてよい。
[神宮輝夫]
大正期
明治時代に芽生えた諸要素が、経済の発展、小規模だが市民社会の形成、民主的自由主義的思想の広がりのなかで育った時期だった。雑誌は明治期に続き『少女』(1913)、『少年倶楽部(くらぶ)』(1914)、『良友(りょうゆう)』(1916)などが新たに加わり、1918年(大正7)にこの時期を代表する『赤い鳥』が鈴木三重吉(みえきち)によって創刊された。『おとぎの世界』、『金の船』(のち『金の星』)、『童話』がそれに続いた。これらのうち『赤い鳥』は、イギリス・ロマン派詩人に通じる児童観にたつ北原白秋(はくしゅう)による童謡創作と運動がもっとも大きな業績で、それに西条八十(やそ)の貢献が加わった。さらに『蜘蛛(くも)の糸』(芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ))ほかの説話系の作品、『一房の葡萄(ぶどう)』(有島武郎(たけお))のようなリアリスティックな作品、『月夜と眼鏡(めがね)』(小川未明(みめい))に代表される童話系列の作品を世に送り出した。未明は『赤い蝋燭(ろうそく)と人魚』をはじめとする作品集に、昔話的形式に独自の思想を盛り込んだものや子供の身辺スケッチ風の短編を収めて、空想と写実両面で新しい道を開拓し始めた。『良友』に拠(よ)った浜田広介(ひろすけ)は、『椋鳥(むくどり)の夢』に庶民的道徳と日本的感性のこもる短編を収め、幼年向き文学の開拓者と称された。『童話』の千葉省三は『虎(とら)ちやんの日記』で農家の子供の日常を描いた。『金の船』も多くの童話作家が寄稿したが、野口雨情(うじょう)の童謡も人気を集めた。ほかに、野上弥生子(やえこ)の『人形の望(のぞみ)』、徳田秋声の『めぐりあひ』を含む実業之日本社の「愛子(いとしご)叢書」(1913~1914)も大きな足跡である。
[神宮輝夫]
昭和・戦前期
経済不況のなかで始まるこの時期は、ヨーロッパ、アメリカ同様にリアリズムの時代といえる。注目すべき動きは、1926年(大正15)の『無産者新聞』につくられた「コドモのせかい」欄に始まるといわれるプロレタリア児童文学への歩みだった。作品らしいものは残さなかったが、子供への視点に与えた影響は大きく、必然的に子供の日常を社会全体の動向のなかでとらえたり、子供を総合的に描こうとするいわゆる生活童話を生んだ。猪野省三(いのしょうぞう)(1905―1985)、岡一太(かずた)(1903―1986)、奈街(なまち)三郎(1907―1978)、宮原無花樹(むかじゅ)(1907―1981)が思想性の強い作品を書き、槇本楠郎(まきもとくすろう)が理論を展開した。塚原健二郎、下畑卓(しもはたたく)(1916―1944)、岡本良雄、関英雄(せきひでお)、小出正吾(しょうご)らがそれぞれの子供観とモチーフをもってリアルに子供をとらえようと努めた。なかでも、傑出した作品『風の中の子供』『子供の四季』などで生活全体のなかでの子供の立場を客観的にとらえて子供の独自性を際だたせた坪田譲治はこの時期のリアリズムの頂点にたち、『ごんぎつね』ほかで庶民の物語性とモラルを伝えた新美南吉(にいみなんきち)、『風の又三郎(またさぶろう)』『グスコーブドリの伝記』が単行本で出版されてその物語性、象徴性の高い豊かな幻想性がようやく理解され始めた宮沢賢治は、ともにファンタジーとリアリズム両面で子供の文学を大きく前進させた。
[神宮輝夫]
昭和・戦後
太平洋戦争直後は雑誌文化が栄え、平塚武二(たけじ)、岡本良雄、関英雄、筒井敬介(つついけいすけ)(1918―2005)らが明確な主張をもつ短編を多く発表したが、雑誌の廃刊とともに活動も停滞した。この時期で残ったのは、西欧的モラルに裏打ちされた子供の成長の物語『ノンちゃん雲に乗る』(石井桃子)、長編の骨格をもつ『ビルマの竪琴(たてごと)』(竹山道雄)、戦中の庶民史『二十四の瞳(ひとみ)』(壺井栄(つぼいさかえ))であった。
創作がふたたび出版され始めるのは、戦後世代の書き手が育ち経済力が上昇し始める1960年代初頭である。1959年に日常生活のなかの小人の存在をアイデアに戦後の理想を語った『だれも知らない小さな国』(佐藤さとる)と『木かげの家の小人たち』(いぬいとみこ)が現れ、翌1960年に労働者一家の生活を少女を中心に入念に追ったリアリズム『赤毛のポチ』(山中恒(ひさし))と、民話を再創造した『竜の子(たつのこ)太郎』(松谷みよ子)が出て真の戦後児童文学がスタートし、以後1960年代を通じて理想主義と楽天性に貫かれた作品が輩出した。だが経済の高度成長に伴う生活の変化とそれがもたらす諸問題の子供への影響は必然的に作品にも変化を促した。象徴的な作品は奥田継夫(つぐお)(1934― )の『ボクちゃんの戦場』で、子供が初めて幻想性の衣をまとわずに描写され、リアリズムへ拍車をかけた。また反戦・平和を主題とする作品面でも、侵略戦争が『ヤン』(前川康男(やすお))によって中国少年の目で甘えなく扱われた。1970年代は、三木卓(たく)が下積みの少年・若者の生活への努力を『真夏の旗』で追究した手法にみられるように技法面の向上が目覚ましく、小沢正(ただし)(1937―2008)、山下明生(はるお)(1937― )、寺村輝夫(てるお)の幼年文学、舟崎克彦(かつひこ)、角野栄子(かどのえいこ)(1935― )らのユーモアやナンセンス豊かな作品、上野瞭(りょう)(1928―2002)、那須正幹(なすまさもと)(1942―2021)らの物語性を重視した長編など多彩な展開をみせた。
[神宮輝夫]
『神宮輝夫著『世界児童文学案内』(1963・理論社)』▽『L・H・スミス著、石井桃子・瀬田貞二・渡辺茂男訳『児童文学論』(1964・岩波書店)』▽『ベッティーナ・ヒューリマン著、野村滋訳『子供の本の世界』(1969・福音館)』▽『安藤美紀夫著『世界児童文学ノート』全3冊(1975~1977・偕成社)』▽『杉一郎編『英米児童文学』(1977・中教出版)』▽『イーゴフ、スタブス、アシュレイ編、猪熊葉子・清水真砂子・渡辺茂男訳『オンリー・コネクト』全3冊(1978~1980・岩波書店)』▽『J・R・タウンゼンド著、高杉一郎訳『子どもの本の歴史』上下(1982・岩波書店)』▽『神宮輝夫著『現代イギリスの児童文学』(1986・理論社)』▽『谷本誠剛著『児童文学入門』(1995・研究社出版)』▽『末松氷海子著『フランス児童文学への招待』(1997・西村書店)』▽『ハンフリー・カーペンター他著、神宮輝夫監訳『世界児童文学百科』(1999・原書房)』▽『菅忠道著『日本の児童文学』(1956・大月書店)』▽『鳥越信著『日本児童文学案内』(1963・理論社)』▽『上笙一郎著『児童文学概論』(1970・東京堂出版)』▽『上野瞭著『現代の児童文学』(1972・中央公論社)』▽『猪熊葉子・神宮輝夫・鳥越信他編『講座日本児童文学』8巻・別巻1(1973~1977・明治書院)』▽『日本児童文学学会編『日本児童文学概論』(1976・東京書籍)』▽『関英雄著『体験的児童文学史』上下(1984・理論社)』▽『松村武雄著『児童文学』(1987・久山社)』▽『日本童話協会編『童話史』(1987・久山社)』▽『日本児童文学学会編『世界児童文学概論』(1988・東京書籍)』▽『谷本誠剛著『児童文学とは何か――物語の成立と展開』(1990・中教出版)』▽『大阪国際児童文学館編『日本児童文学大事典』(1993・大日本図書)』▽『上田道夫・大藤幹夫ほか共編著『現代日本児童文学選――資料と研究』(1994・森北出版)』▽『長谷川潮著『日本の戦争児童文学 戦前・戦中・戦後』(1995・久山社)』▽『日外アソシエーツ編・刊『児童文学書全情報』(1998~2001)』▽『勝尾金弥著『伝記児童文学のあゆみ』(1999・ミネルヴァ書房)』▽『鳥越信編著『日本児童文学史』(2001・ミネルヴァ書房)』
改訂新版 世界大百科事典 「児童文学」の意味・わかりやすい解説
児童文学 (じどうぶんがく)
ここにいう児童文学とは,子どもたちのための文学作品を意味するが,それはもとより文学の一分野であって,文学の本筋からはなれた別のものではない。しかし,児童文学は,そうした文学性をそなえつつ,子どもたちに楽しみをあたえうるものでなければならず,生涯を通じて生きつづける経験ともいうべき深い意味の教育性をそなえていなければならない。そして楽しみと教化という児童文学の2要素から,児童文学における訓育主義と芸術主義という二つのモットーがくりかえされてきた。
児童文学の歴史は,子どもたちに対する社会の態度,つまり児童観の変遷ともみられる。子どもが,単に生物的な庇護を必要とする年少の人間であるばかりでなく,実質をそなえた社会的存在として認識されるようになったのは,日本でも西欧でも中世にまでさかのぼる。子どもという範疇(はんちゆう)の成立は児童文学の成立の第1の前提である。しかし,こうして見いだされた子どもは,まずは未開野蛮の蒙昧(もうまい)状態から一刻も早くおとなになるべき存在とされた。それより先,子どもたちは,その本来の新鮮な好奇心から,おとなにたちまじって,おとなたちが語り聞きして楽しんでいた昔話や伝説,神々や世界の始まりについての物語を,乏しい経験の許すかぎりで楽しんだものと思われる。やがておとなが絵入りの本を所有すればそれをのぞき,印刷術の発明普及によっておとなたちが本を所有するようになれば,おとなたちの本棚からこっそりと,みずから本を選びとって自分の本棚にうつしてきた。《ガリバー旅行記》や《ロビンソン・クルーソー》はその典型的な例である。
したがって児童文学の領域も,広くは,子どもたちが言語を媒介とし耳で聞いた口承の民話,神話,伝説,寓話などからの簡単なお話,民謡,童謡,絵の助けを借りる絵本,絵物語,漫画,そして文字を媒介とする童話,物語,小説,事実の本,知識の本までを含む。この領域の順は児童文学の生長過程でもある。しかし狭義には,これらのもののうち,子どもたちに共感を寄せる文学者たちが意識的に書き,本の形をとったものをいう。狭義の児童文学の成立は,教育の普及による子どもたちの読み書き能力の獲得,中産階級の成立による公教育の場とは異なる享受層と享受の場の成立,子どもの本のマーケットの成立と対応する。狭義の児童文学は,近代の中産階級の広範な出現をまって初めて安定した一つの制度となり,公教育と並存し,基本的には対峙する形でその領域を広げてきたのである。以下,〈絵本〉や〈口承文芸〉については別項にゆずり,狭義の児童文学の歴史をたどってみよう。
西洋
世界の児童文学の源流に立つのはC.ペローである。ペローの《ガチョウ小母さんのお話》(1697)は,昔話に初めて文字をあたえ,〈赤ずきん〉や〈長靴をはいた猫〉〈親指小僧〉を子どもたちの永遠の財産にした。しかし,それにつづく啓蒙主義の普遍理性の時代は,昔話を卑俗で子どもの健全な成長に有害なものとし,子どもの本は教訓としつけの目的に奉仕させられることになった。ほぼ1世紀にわたる訓育主義の跋扈(ばつこ)の後に様相は一変する。フランスの文化的優位に対する反発から始まるドイツ・ロマン主義の動きは,自国の土と血に根ざしたものの探求に向かい,そこからC.ブレンターノらの童歌(わらべうた)の収集と,グリム兄弟の《子どもと家庭のための昔話集(グリム童話)》(第1巻1812)が生まれ,つづいて,デンマークでは昔話に美しい空想の翼をあたえたH.C.アンデルセンの《童話集(アンデルセン童話)》,さらにはノルウェーのアスビョルンセンP.C.AsbjørnsenとムーJ.Moeによる民話の収集(1837~44)が現れるのである。以下,各国の歴史をたどる。
イギリス
16~17世紀は手鏡のようなホーンブックhornbook,17~18世紀は江戸時代の赤本のような行商人によるチャップブックchapbookが,子どもたちの唯一の本だった。しかし1744年にニューベリーJ.Newberyがロンドンのセント・ポール大聖堂前に,世界で初めての子どものための本屋をひらいて,小型の美しい本を発行し,伝承歌謡を集めた《マザーグースの歌(マザーグース)》やO.ゴールドスミスに書かせたと思われる初の創作《靴ふたつさん》を送り出した。しかし18世紀を支配したJ.J.ルソーの教育説はたくさんの心酔者を出して,児童文学は型にはまり,C.ラムは姉メアリーとともにこの風潮に反抗して,《シェークスピア物語》(1807)などを書いたが,児童文学が自由な固有の世界となるには,ペローやグリム,アンデルセンの翻訳をまたなければならなかった。しばしば子どもたちの実態を小説に描いたC.ディケンズは《クリスマス・キャロル》を1843年にあらわし,E.リアは滑稽な5行詩による感覚的なノンセンスの楽しみを《ノンセンスの本》(1846)にまとめた。
空想の国へ子どもをさそうファンタジーは,C.キングズリーの《水の子》(1863)を経て,L.キャロルの《不思議の国のアリス(アリス物語)》(1865)でみごとな花をさかせた。少年小説もまたT.ヒューズの《トム・ブラウンの学校生活》(1857),R.バランタインの《サンゴ島》(1857),ウィーダOuidaの《フランダースの犬》(1872),シューエルA.Sewellの《黒馬物語》(1877)のあとをうけて,R.L.スティーブンソンの《宝島》(1883)で完成した。架空世界を取り扱った物語は,J.インジェローの《妖精モプサ》(1869),G.マクドナルドの《北風のうしろの国》(1871),R.キップリングの《ジャングル・ブック》(1894),E.ネズビットの《砂の妖精》(1902),K.グレアムの《たのしい川べ》(1908),J.M.バリーの《ピーター・パンとウェンディ(ピーター・パン)》(1911),W.デ・ラ・メアの《3びきのサル王子たち》(1910)にうけつがれ,ファージョンE.Farjeon《リンゴ畑のマーティン・ピピン》(1921)は空想と現実の美しい織物を織り上げた。さらにA.A.ミルンの《クマのプーさん》(1926)が新領域をひらき,J.R.R.トールキンの《ホビットの冒険》(1937),《指輪物語》(1954-55)は妖精物語を大成する。C.S.ルイスが架空の国ナルニアの7部の物語(《ナルニア国ものがたり》1950-56)で善悪の問題を取り扱い,トラバーズP.L.Traversの〈メリー(メアリー)・ポピンズ〉5部作(1934-82)はユーモアをこめて新しい魔女をつくり出し,ノートンM.Nortonも人間から物を借りてくらす小人たちのミニアチュア世界を5部作(1952-82)で描いてみせた。
ファンタジーはイギリス児童文学の真骨頂というべく,その後もピアスP.Pearce《トムは真夜中の庭で》(1958)やボストンL.M.Bostonの〈グリーン・ノウ〉(1954-76)の連作,ホーバンR.Hobanの《親子ネズミの冒険》(1967),ガーナーA.Garnerのウェールズ伝説に根ざした諸作(1960-),メーンW.Mayneの《地に消える少年鼓手》(1966)などの秀作が生まれ,1950年代から60年代の隆盛期を現出させた。72年には動物ファンタジー《ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち》がアダムズR.Adamsによって書かれた。冒険小説もJ.メースフィールドを経て,ランサムA.Ransomeのたのしい休暇中のヨット旅行の数々の冒険(1930-47)に発展した。歴史小説ではサトクリフR.Sutcliffがぬきんでて,両トリーズG.Trease,H.TreaseやウェルチL.Welch,ハーネットC.Harnett,バートンH.Burtonらがつづく。実生活の問題を含んだ題材がガーネットE.Garnettの《袋小路1番地》(1937)からしだいに多く扱われはじめ,60年代のメーンやタウンゼンドJ.R.Townsendにうけつがれ,さらに思春期の少年小説が,ウォルシュJ.P.WalshやペートンK.M.Peytonによって書かれている。
アメリカ
アンデルセンと同じ時代に,アメリカではW.アービングが《リップ・バン・ウィンクル》(1802)を書き,J.F.クーパーがインディアンものを1823-41年につづけて出し,N.ホーソーンがはっきり子どもをめざして昔の歴史や神話を書きなおしていた。52年のストー夫人の《アンクル・トムの小屋》はむしろ社会的な事件であったが,それよりも65年のドッジ夫人M.M.Dodgeの《ハンス・ブリンカー(銀のスケート靴)》は,児童文学上の事件であった。彼女の写実的傾向はついに,L.M.オルコットの《リトル・ウィメン(若草物語)》(1868),《リトル・メン》(1871),クーリッジS.Coolidgeの〈ケーティもの〉のような,健全な家庭小説を新たに開拓し,ついにアメリカ的なマーク・トウェーンの《トム・ソーヤーの冒険》(1876),《ハックルベリー・フィンの冒険》(1884)にいたった。バーネットF.H.Burnettの《小公子》(1886),ウィギンK.D.Wigginの《少女レベッカ》(1903)はこの明るい精神の所産である。この国の昔話は黒人やインディアンの民話の粋をとりこんで,ハリスJ.C.Harrisの動物民話集《リーマス物語》(1880)に結実した。
20世紀にはいってアメリカの児童文学は,児童図書館の発達によって多彩となった。動物物語にはJ.ロンドンをはじめとして,ムカージD.G.MukerjiやターヒューンA.P.Terhune,ジェームズW.Jamesなどがおり,少年小説ではJ.ウェブスターの《あしながおじさん》(1912)やバーネットの《秘密の花園》(1910)がある。しかし,最も特色ある一分野は,アメリカ史上の栄光である開拓時代を題材とするもので,ワイルダーL.I.Wilderの8部に及ぶ開拓少女ローラに関する大河小説がその圧巻である。次に移民たちが故国の思い出をつづることで生じた諸国物語の系列がある。オランダを舞台とするデヨングD.DeJongの《あらしの前》(1943)と《あらしの後》(1944)は感動的だし,デヨングM.DeJongの《コウノトリと6人の子ども》(1954)は心理を深めて個性的である。童話はイギリスから帰化したロフティングH.Loftingの〈ドリトル先生〉の数々の愉快な物語(《ドリトル先生物語》1920-53)によってこの国に定着し,J.G.サーバーやデュ・ボアW.P.Du Boisを経て,ホワイトE.B.White《シャーロットのおくりもの》(1952)が生まれた。1960年代以降は本家イギリスのファンタジーを追う様々の試みがあるが,U.K.ル・グインが傑出し,ほかはアレゴリーの域を出ない。ほかに歴史小説のスピアE.G.Speareや冒険小説のオデルS.O'Dellがいるが,なんといっても近年のアメリカのリアリスティックな作品を特徴づけるのは,多民族国家アメリカの少数民族の経験を核にしたさまざまの作品である。ユダヤ人のカニグズバーグE.L.Konigsburg,I.B.シンガー,黒人のハミルトンH.Hamiltonがすぐれており,ほかにフォックスP.Fox,ボイチェホフスカM.Wojciechowskaらが問題作を書いている。
旧ソ連邦
かつてロシアでは,A.S.プーシキンが民話に取材して《金のニワトリ》(1834)などを書き,エルショフP.P.Ershovが《せむしの小馬》(1834)を作り,I.A.クルイロフはイソップ風の寓話を,V.M.ガルシンは童話的な寓話を書いたが,いずれも権力に刃向かう声であった。F.K.ソログープは暗い影の多い不思議な小説を作り,L.N.トルストイはおおらかな民話と小品を発表した。革命後の新しい児童文学の父はM.ゴーリキーであったが,彼はとくに子どものものを書かずに,V.V.マヤコーフスキーやS.Ya.マルシャークやK.I.チュコフスキーにその実りをゆずった。そのうちでマルシャークは第一人者として,《12の月(森は生きている)》(1943)のような劇やたくさんの童謡を発表している。ソ連の写実的な児童向きの小説は,A.P.ガイダールの《革命軍事会議》(1926)とパンテレーエフA.I.Panteleevの《金時計》(1928)あたりで形づくられた。
スターリン体制下でも,ボロンコワL.F.Voronkova,ムサトフA.I.Musatov,ノソフN.N.Nosovらが子どもの生活を描いたが,1966年のフロロフV.Frolov《愛について》に至って少年の現実生活を描いて間断するところがなくなった。空想的な物語は不調のようだが,民話のエネルギーをくんで力強く美しい文学作品に結晶させたP.P.バジョーフの《孔雀石の函》(1939)所収の《石の花》は,プーシキン以来のロシア児童文学の伝統の力を垣間見せる。民話への指向はマブリナT.Mavrinaにもうけつがれている。自然を扱う作家にはM.M.プリーシビン,V.V.ビアンキがおり,幼年ものではミハルコフS.V.Mikhalkovがすぐれ,ノンフィクションのM.イリインは国際的に評価された。
フランス
ペローの古典を幕開けとして,歴史は長いが実質がふるわないのは,この国の教育が子ども時代の固有な点を受け入れないせいであろうか。作品は太い流れを形づくることはなく,おもしろい作品が多いが散発的である。H.H.マロが《家なき子》(1878)で遍歴する孤児のテーマを流布させたが,同じころJ.ベルヌがSFの先駆といわれる作品を精力的に書いて,夢想に現実性を与えた。少年小説の古典《二年間の休暇(十五少年漂流記)》(1888)も彼の手になる。
20世紀にはいるとベルギーの詩人M.メーテルリンクが童話劇《青い鳥》(1908)を書き,1932年にはC.ビルドラックが《ライオンの眼鏡》を生んだ。同じころのショボーL.Chauveauは子どもの酷薄さと向きあった作家である。第2次大戦で死んだサンテグジュペリの《星の王子さま》(1943)は詩のように美しい傑作であった。戦後ギヨーR.Guillotが出現して,はじめてフランスにおける子ども固有の文学が世界的にみとめられたといってよい。ギヨーの作品は,ことに動物もので名高い。M.エーメの幼年物語は,奇想と機知にみちている。さらに,ボードゥイM.-A.Baudouy,ビビエC.Vivier,ベルナP.Bernaなどもいる。ドリュオンM.Druon《みどりのゆび》(1957)はサンテグジュペリを継ぎ,空想的な物語にはグリパリP.Gripariの《木曜日はあそびの日》がある。南フランスの風土の精気を昇華させて独特のファンタジーを生んだボスコH.Boscoの諸作品も見逃すことはできない。
ドイツ
ドイツではJ.B.バゼドーの主唱に呼応してコンペJ.H.Compeが1776年に《小さな子ども文庫》を出したのがはじめで,ややおくれてG.A.ビュルガーが1786年にラスペR.E.Raspeの作に手を入れた《ミュンヒハウゼン男爵の冒険(ミュンヒハウゼン物語)》をあらわし,ゲーテにつづくロマン派の人々が,民話の収集にあたっている。その所産がブレンターノとA.vonアルニムの《少年の魔笛》であり,グリム兄弟の《子どもと家庭のための昔話集》であった。ベヒシュタインL.Bechsteinの《ドイツ童話の本》(1844)がそれにつづく。一方では,L.ティーク,ブレンターノ,F.de la M.フケー,E.T.A.ホフマンが不思議な物語を手がけ,その流れから創作としてぬきんでたW.ハウフの《隊商》(1826)が生まれた。T.シュトルムやA.シュティフターにも子どもに向く作品はあるが,レアンダーR.Leanderの《フランス風暖炉のそばの夢想》(1871)とザッパーA.Sapperの《愛の一家》(1906)が大きな収穫となった。前者は童話,後者は家庭小説である。そのあいだに,1896年ウォルフガストH.Wolfgastが新しい児童文学を提唱して,ローゼッガーP.Roseggerなどを生み,やがて詩人W.ボンゼルスの《蜜蜂マーヤの冒険》(1912)が出て,第1次世界大戦にはいる。オーストリアのザルテンF.Saltenの《バンビ》(1923)とE.ケストナーの《エミールと探偵たち》(1928)が出ると,新生面がひらけるかにみえたが,第2次大戦でとざされた。しかし,わずかではあるが,ウォルフF.Wolf,ウィーヘルトE.Wiechertらのすぐれた作品がある。
第2次大戦後はケストナー以下ミューレンウェークF.MühlenwegやヘルトK.Held,シュポンゼルH.SponselやバウマンH.Baumannと歴史もの・冒険もののうまい作家がつづき,リュートゲンK.Lütgenも前代の大衆作家K.マイを顔色なからしめている。動物物語ではクナークK.KnaakやシュトイベンF.Steubenが出てレーンスH.Lönsを古くした。女流ではガストL.Gastやベナリー・イスベルトM.Benary-Isbert,ミヒェルスT.Michels,ウェルフェルU.Wölfelがいる。プロイスラーO.Preussler,クリュスJ.Krüssがさまざまの形式に挑み,エンデM.EndeやツィムニクR.Zimnikは現代の寓話を書き,ヘルトリングP.Härtlingが実験的な作品を書いている。
イタリア
イタリアはE.デ・アミーチスの《クオーレ》(1886)とコロディC.Collodiの《ピノキオ》(1880)によって新風をおくったが,ヌッチョE.Nuccioのするどい童話と,ロダーリG.Rodariの《チポリノの冒険》(1951)もめだっている。イタリアの民話を集大成して児童文学に接近したI.カルビーノの《マルコバルドさんの四季》(1963)も見逃せない。ゴッタS.Gottaの冒険小説は戦時中からつづき,マンツィA.Manziの動物物語は新しい収穫といわれる。ほかに新しいメディアを活用するアルジリM.Argilliがいる。
その他のヨーロッパ諸国
オランダでは,女流のルトヘルス夫人A.Rutgersがよく問題作を出し,ファン・マルクスフェルトC.van Marxveldtも女生徒に好まれている。デンマークは近代童話の親アンデルセンを生んだ国であり,アスビョルンセンとムーによる民話集をもつノルウェーにはヘルイE.Herjiの冒険もの,画家エーグネルT.Egnerの愉快な物語,プリョイセンA.Prøysenの幼年物語がある。S.ラーゲルレーブの《ニルスのふしぎな旅》(1906-07)を生んだスウェーデンでは,A.リンドグレーンがすばらしく,まことに多才である。この伝統はグリーペM.Gripeにうけつがれている。フィンランドのT.ヤンソンはムーミンを主人公にした不思議な世界をつくりあげた。
そのほかの諸国からひろうと,スイスのJ.シュピーリの《ハイジ(アルプスの少女)》(1881)とウィースJ.R.Wyssの《スイスのロビンソン》(1812-13),ハンガリーのF.モルナールの《パール街の少年たち》(1907),チェコスロバキアのK.チャペックの《童話集》(1932)が見落とせない。
執筆者:瀬田 貞二+菅原 啓州
カナダ,オーストラリア,ニュージーランド
カナダにはL.M.モンゴメリーの《赤毛のアン》(1908)があるが,本領はE.T.シートンやロバーツG.D.Robertsによって19世紀末から開拓された動物物語にあり,その伝統はモワットF.Mowat《ぼくのペットはふくろう》(1961),バンフォードS.Bunford《信じられない旅》(1977)に息づいている。オーストラリアの近年の児童文学の隆盛はめざましい。チョーンシーN.Chauncyのタスマニアの自然に根ざした作品が先駆け,現実生活を描いた作品にもファンタジーにも通ずる才を発揮するライトソンP.Wrightsonと,過酷な自然条件を背景に迫力のある物語を展開させるサウソールI.Southallが双璧である。ニュージーランドにはマヒーM.Maheyがいてさわやかな妖精物語をつづっている。コモンウェルスの国ということで付記すれば,インドのデサイA.Desai《ぼくの村が消える!》(1982)は感動を呼ぶ。
アフリカ
1950年代の後半から相ついで独立を果たしたアフリカ諸国の児童文学は生成期にある。西アフリカのナイジェリアや東アフリカのケニアなどに出版活動の核があって,各国に波及している。急激な近代化を迫られながら,民族のアイデンティティを,民話・伝説・神話の口承文芸の大海からくみあげることで形成しようとする志が,アフリカの児童文学を特徴づけている。回想記風の物語によって固有の生活様式を子どもたちに伝達しようとする作品も同じ志から発している。ナイジェリアにアチェベ,ケニアにグギがいる。ナイジェリアのエクウェンシC.Ekwensiのピカレスク風冒険物語も昔話の単純直截な語りの口調を保持している。
執筆者:菅原 啓州
東洋
東洋は,世界の四大文明圏の三つ(中国,インド,イスラム)を含んでおり,それぞれがはやくからすぐれた文学を生みだしたが,そのなかには後世の児童文学と直接間接に関係の深いものが少なくない。
インド
インドでは紀元前すでに,寓話集《パンチャタントラ》や経典〈ジャータカ〉がまとめられて諸外国にもつたわり,日本の《今昔物語》《宇治拾遺物語》などにも,そこから説話が採録されている。一時は世界中の昔話がみなインドに由来するという説さえ行われたほど,インドは昔話の豊富な国であり,記録も古い。しかしヨーロッパの植民地となったインドには,民族的自覚と結びついた近代のめざめが訪れるまで,新しい児童文学がそだつ基盤がなかった。ノーベル賞作家タゴールはインドの夜明けをつげるかのような,少年を描いた詩的な戯曲《郵便局》(1914)を書いたが,新しいインドが伝統を生かして児童文学をゆたかに創造することは今後に期待される。1956年にインドで開かれたアジア作家会議の中心議題の一つが児童文学であったことも象徴的である。
中国
紀元前の中国,すなわち春秋戦国時代から漢の時代にかけての古典には,後代の民衆にも親しまれた寓話が豊富であったし,隋・唐の時代には多くの説話集もまとめられ,日本につたわって文献に残された説話も少なくない。民衆の口語文学として数世紀にわたって形成されてきた《三国志》《水滸伝(すいこでん)》《西遊記》は,中国ばかりでなく日本の児童にも今日なおきわめて親しみ深い物語である。しかし,子どものための文学の意識的な創造は,第1次世界大戦後,中国に反帝反封建の運動がもりあがり,文学革命が進んでからのことである。葉紹鈞(ようしようきん)の《稲草人(かかし)》(1922)は,中国ではじめての近代童話であり,魯迅(ろじん)はこの作品を〈中国の童話のために一すじの創作の道をひらいてくれた〉と高く評価した。魯迅も,中国の児童文学の発展のために外国の作品を翻訳し,また民話・古典など民族の文化遺産の生かし方に指導的な役割を果たした。その後,林蘭(りんらん)の名による民話の収集整理,老舎の長編《小坡の誕生日》(1930)をはじめ,巴金(はきん),謝冰心(しやひようしん),茅盾(ぼうじゆん),張天翼(ちようてんよく)らの創造活動によって前進をとげた児童文学は,中華人民共和国の成立後,国家的事業として飛躍的に発展しつつある。
新中国の児童文学を代表する張天翼の小説《羅文応の話》(1954),秦兆陽(しんちようよう)の童話《ツバメの大旅行》(1950),そのほか詩,劇,伝記,科学読物などさまざまなジャンルにわたって,革命後の成果が1954年の国際子どもデーに表彰された。児童文学の創造は中国作家協会の中心的課題にすえられて大いに力が注がれ,革命闘争,抗日戦争や社会主義建設に取材した作品や民話の発掘と再創造の仕事など,多面的な発展がみられた(この点は,解放された朝鮮においても同様である)。なお,連環画(絵物語)という大衆的形式の活用がはかられていることも注目された。しかし,いわゆる文化大革命によって,児童文学も停滞を余儀なくされたため,その後の近代化路線によってもその修復は大幅におくれ,中国の児童文学の再出発はようやく再開されたばかりといえる。
アラビア
東洋が生みだした文学で,世界の児童文学に古典的地位を占める《千夜一夜物語(アラビアン・ナイト)》は,10世紀から15世紀にかけて成立したとみられるが,原型はペルシアの民話集であり,アラビア,インド,ユダヤ,エジプトなどの民話を集大成している。18世紀のヨーロッパに紹介されて,めずらしい夢みるような空想がよろこばれ,近代童話の発想にも影響するところが大きかった。
日本
日本で,子どもを対象とする童話が本格的に現れるようになったのは江戸時代の初期であり,草双紙のさかんな刊行は世界の児童出版史上でもはやく,イギリスに匹敵する。その内容は,室町時代に成立した御伽(おとぎ)草子を中心に,古浄瑠璃(こじようるり),謡曲などに取材したものが多く,その源流は古代,中世にかけて成立した説話集,軍記物語,あるいは伝説,昔話であった。これらは明治時代に巌谷小波(いわやさざなみ)によって国民童話としてまとめられ,多くは今日もなお生きつづけている。日本の近代的児童文学の道もまた,巌谷小波の《こがね丸》(1891)でひらかれた。彼自身が後に,この作品を〈《南総里見八犬伝》と《狐の裁判》をないまぜにした〉くらいのものと語っているが,これは小波を指導者として形成された明治の児童文学の本質でもある。日本人には目新しい西欧的メルヘンの空想が江戸末期の戯作調と結びついて,明治期のおとぎ話が成立した。それは全体として興味性がゆたかで教訓性もつよく,表現はやさしい説話体であったので,読んでも聞いても心をひきつけられるものであった。しかしその反面には遊戯的な態度,思想の貧困,芸術性のとぼしさが目だっていた。小川未明の第1童話集《赤い船》(1910)は,日本の児童文学に近代的文学精神と文芸形態をもたらしたさきがけである。未明と同じくネオ・ロマンティシズムに立つ鈴木三重吉も,世界童話の芸術的再話によって小波の世界おとぎ話の移植に対決した。三重吉が主宰する雑誌《赤い鳥》(1918創刊)は,新しい童話・童謡の創作をうながす文学運動のよりどころとなった。この時期は,ほとんどすべての文壇作家が童話を書いたほどの盛況であったが,その多くは再話的なもので,今日に残るすぐれた創作は少ない。その主流はロマンティックな未明童話を頂点とする物語性のゆたかなメルヘンで,子どもの現実生活をリアルに描いた作品は少なかった。代表的な作家には,秋田雨雀,芥川竜之介,有島武郎,宇野浩二,佐藤春夫,豊島与志雄たちがいる。
大正期には児童中心主義の児童観に応ずる童心文学の主張が支配的で,それが典型的に現れたのは北原白秋,西条八十,野口雨情に代表される童謡においてであるが,この近代的詩形が日本の伝承童謡の復興を詩の精神としたことは注目すべきである。童話の分野では,西欧の民話が多く再話の対象になった。また童謡では思い出が主要なモティーフになっていた。童話が,思い出をモティーフにすることでリアリティをもつようになったのは,昭和に入ってからのことで,回想的・私小説的方法でリアリズム児童文学が成立し,固定化するようになったが,これは現代の児童文学をかなりつよく特質づけている問題である。千葉省三は《虎ちゃんの日記》(1925)をはじめとする一連の作品で,酒井朝彦は〈木曾もの〉と呼ばれる作品で,郷愁と結びついたリリシズムを描き,また坪田譲治は〈善太・三平もの〉でリアルな児童像を造形して,それぞれにこの時期を代表している。
小川未明や秋田雨雀をさきがけとして社会性のある主題は児童文学のものになってきたが,それを決定的なものにしたのは昭和初年のプロレタリア児童文学運動で,槙本楠郎,猪野省三,川崎大治たちが活躍した。マルクス主義陣営からの批判は,未明童話をもふくめて童心主義の非社会性と超階級性に徹底的に向けられた。しかし,理論をうらづけるだけの実作をともなわないままに解放運動は中絶し,転向と抵抗との複雑なからみあいのなかで,社会主義リアリズムの一側面を生活主義童話の提唱としておし出した。槙本,川崎や塚原健二郎,岡本良雄らの作品で,児童の自主性と社会性が児童文学のおもな題材となる道はひらけたが,戦争の重圧のなかで平板な生活童話に変質し,スケッチ的・風俗小説的作風は現代の児童文学になお色こくみられる弱点となっている。これは,回想的・私小説的方法とともに,児童文学から物語性に富んだおもしろさをうばいとり,子どもを通俗文学のとりことして放置する結果を生んだ。その間にあって,宮沢賢治,新美南吉の童話は想像ゆたかな物語性で異色を放ち,また幼年童話における浜田広介は独特な調子で近代説話を語り,それぞれ戦中・戦後にわたって広範な読者をもった。
第2次世界大戦後,平和と民主主義という新しい価値観の到来とともに,《赤とんぼ》《銀河》《子供の広場》など文化的・進歩的な児童雑誌の創刊があいつぎ,一種熱っぽい状況のなかで,石井桃子《ノンちゃん雲に乗る》(1947),竹山道雄《ビルマの竪琴(たてごと)》(1948),壺井栄《二十四の瞳》(1952)など今日にも残る作品が生まれた。これらはいずれも短編中心だった日本の児童文学にはめずらしい本格的な長編作品だったが,その作者がいずれも未明を中心とした童話文壇の人脈でないところから現れた点は象徴的である。未明の伝統につながる児童文学界は,戦後すぐの高揚期に社会風刺性の強いメルヘンや,生活童話のわくを超えるリアルな日常的物語など,新しい時代にふさわしい模索はつづけていたものの,朝鮮戦争がおこった1950年を境に,その後約10年の慢性的不作の時代を迎えていた。その原因についてはさまざま考えられるが,結局,未明の伝統の呪縛から抜けきれず,児童文学の不振・停滞の理由をつねに外的要因にのみ求め,真に子どものための文学のあり方を追求するメスを内へと向けなかった点が最大の原因だったといえよう。
そうしたなかで,当時文学的にも社会的にも無名だった若い世代は,模索の手を未明の伝統という聖域へ伸ばし,53年の早大童話会による〈少年文学宣言〉を皮切りに,未明の伝統への否定的克服の道を歩みはじめた。60年,外国児童文学の洗礼を受けた石井桃子,瀬田貞二,渡辺茂男らのグループが《子どもと文学》を刊行したことでその動きはさらに強まり,57年,いぬいとみこの長編幼年童話《ながいながいペンギンの話》を筆頭に,神沢利子,佐藤さとる,中川李枝子,古田足日,松谷みよ子,山中恒らの新人作家がそれぞれの処女作をひっさげて登場,60年を越えた時点で日本の児童文学地図は完全に塗りかえられるに至った。以来今日まで,翻訳や評論・研究の分野を含め,また読書運動など普及の面も含めて児童文学は盛況の一途をたどっている。
現在の日本の児童文学は,一口にいって,ひとり創作に限らず,絵本,民話,ノンフィクション,漫画等々あらゆる子どもの要求にこたえる多様化現象に最大の特色がみられるが,その繁栄ぶりは必ずしも順風満帆とのみはいえず,もろもろの問題を内包している。例えば価値の多様化による思想性の喪失,その結果として小手先の面白さだけを追求する技術主義の横行にはじまり,内容的には子どもの家出・自殺から両親の離婚,さらにセックス・暴力などに至るタブーの崩壊,またとくに絵本に多くみられるアダルト化現象など,情報過剰の時代状況のなかで,児童文学が文学というより風俗的なファッション商品化してゆく傾向がみられる。それだけにかつての未明の伝統克服の時期と同様に,改めて児童文学とは何かという古くて新しい根源的な命題が問い直されている時期といえよう。
執筆者:菅 忠道+鳥越 信
児童文学の現況
1960年代の後半以降,欧米や日本などの工業先進国では,児童文学の基盤を揺るがすような変化が徐々に顕在化しはじめた。変化は10歳を境とした年長の子どもたちの緩やかな,しかし確実な児童文学からの離脱,逆に思春期・青春期の若者たちの児童文学に寄せる熱い関心という形で目にとまるようになった。作品の上では,リアリスティックな作品の中に,戦争や人種差別や家庭崩壊などの問題が正面から扱われるようになり,才能ある作家はこぞって高年齢の子どもたちを対象にするようになった。その傾向はファンタジーにもおよんで,ファンタジーには楽しみと慰めを与えるものとしてよりも,現代世界を説き明かす寓意性が求められるようになった。総じて性急にアイデンティティを問うことが中心テーマとなり,物語る精神は萎(な)えはじめた。
当初この変化は,それ以前から始まっていた児童文学の中産階級性に対する批判の延長と理解され,児童文学の領域を拡大するものとして歓迎されたが,実はそれは工業先進国の社会がこうむっている大きな変化のうねりの現れであったことが理解されはじめている。一言で管理社会化といわれるこの変化を,子どもたちと,児童文学享受の場であった家庭にかぎっていえば,自己と環境との関係を自覚的にとらえはじめる10歳前後の子どもたちにとって,将来の生活は計画しつくされていて未来は失われ,試験成績とその補完価値である特殊能力の獲得のため自由な時間をうばわれる。管理社会の論理は家庭にまで浸透して,家庭は生活と民俗の様式を維持伝達する内容を失って裸の個人が共同生活する場となりはてる。社会生活に子どもたちが参入する以前に習得すべき情報の量は増大して修学年限はいやましに長くなるばかりか,おとなもまた管理社会の部品となって,絶えず革新される技術情報を習得するための生涯学習を強いられる。つまり,様式を失って丸裸にされた十代からおとなまでが一線にならび,おとなになれない青壮年と十代にして老けた子どもたちが共存する。おとなと子どもを画する明確な一線(通過儀礼の機会)は失われる。ここでは親と子,おとなと子どもの関係とその場の全体に近代の始まりに匹敵する変化が生じはじめているのである。
こうした事態の無制約の進行は,今のところ,一方で伝統的な市民社会の制度と様式の慣性力によって,一方では自由な精神の適応拒否によってからくも押しとどめられている状態だが,近代の市民社会のエートスと不可分の狭義の児童文学はそれ自身のサイクルを終えたことはまちがいない。当面,旧来の児童文学は,10歳前後より幼い子どもたちのものへと縮小し,それ以上の子どもたちのための児童文学は,子どもたちが,青・壮年と異なることのない擬似経験の場にさらされているところからみて,文学一般の中に拡散してゆく趨勢に大きな変化はあるまい。しかし,すぐれた文学は,時代との格闘から生まれて時代を超えた普遍性を獲得するものであること,児童文学は子どもたちに楽しみと深い経験の核となるものを与えるものであることを考えれば,サイクルを終えたかにみえる児童文学の現状は,実は狭義の児童文学の歴史的制約性にもとづくものであって,そこでは児童文学の再定義と歴史の読みかえ・再編が求められていることが明らかとなる。読みかえの基軸は,狭義の児童文学の出発点には必ず昔話や神話,伝説の収集・保存・再創造があり,すぐれた創作は例外なくそこにとどく回路をもっている点に注目することである。近代市民社会の中産階級に固有のものとみえ,実際小説原理に近づく形で成長発展してきたかにみえた児童文学は,実は近代の理性万能の風潮に逆行する魔法や空想を昔話や物語やファンタジーの中に保存し,近代の小説原理が排除した物語の原理を蓄え,悪しき個性主義が退けた遊びと楽しみを横溢(おういつ)させることで形成されてきたからである。
→絵本 →子ども
執筆者:菅原 啓州
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「児童文学」の意味・わかりやすい解説
児童文学【じどうぶんがく】
→関連項目ザッパー|住井すゑ|ハイジ
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「児童文学」の意味・わかりやすい解説
児童文学
じどうぶんがく
children's literature
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...