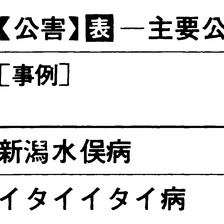精選版 日本国語大辞典 「公害」の意味・読み・例文・類語
こう‐がい【公害】
- 〘 名詞 〙 公共に及ぼす害。産業の発達、交通量の増加などに伴い、近隣の住民が精神的、肉体的および物質的にうける種々の被害、および自然環境の破壊。騒音、振動、煤煙(ばいえん)、粉塵(ふんじん)、悪臭、汚水廃液、地盤沈下、有毒ガス、放射性廃棄物などによる被害。日本において、特に公害防止の世論が高まったのは、昭和三、四〇年代で、同四二年(一九六七)八月、公害対策基本法が施行された。なお、同法は、平成五年(一九九三)の環境基本法の成立に伴ない廃止されている。
- [初出の実例]「他人の冤抑を伸べ、衆人の公害を除き、衆人の公益を興さんとするも」(出典:日本道徳論(1887)〈西村茂樹〉五)
改訂新版 世界大百科事典 「公害」の意味・わかりやすい解説
公害 (こうがい)
公害の語源は明らかではないが,日本の法制上登場するのは,明治10年代の大阪府の大気汚染規制のための府令(のちの条例)や同20年代の〈河川法〉以降である。この場合の公害は〈公益〉の反対概念であったが,やがて大正期に入ると,地方条例の中で,今日と同じように,大気汚染,水汚染,騒音,振動,悪臭などによる公衆衛生への害悪を総称して公害と呼んでいる。
現代の公害は次のように定義できよう。すなわち,公害とは,都市化,工業化に伴って大量の汚染物の発生や集積の不利益が予想される段階において,経済制度に規定されて,企業が利潤追求のため環境保全や安全の費用を節約し,また無計画にモータリゼーションや大量消費生活様式が普及し,国家(自治体を含む)が環境保全の政策を怠る結果として生ずる自然および生活環境の侵害であって,それによって人の健康障害または生活困難が生ずる社会的災害である。
公害の原因は気象などの自然条件,人口配置,あるいは安全の技術を含む生産力の水準によって変わってくるが,自然災害と違って,基本的には経済や社会のあり方から生まれる人為的なものであり,不可抗力の天災ではない。
欧米では公害とまったく同じ概念はないが,air pollution(大気汚染),water pollution(水質汚濁)などを総称して,environmental pollution(環境汚染)またはenvironmental disruption(環境破壊)ということばを使っている。
日本の〈公害対策基本法〉では,その第2条において,次のように定義している。〈公害とは事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。……),土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。……)及び悪臭によって,人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう〉。
この定義は包括的なようだが,法律上の便宜からでたもので,他の法律で規制されている原子力公害,鉱山掘採による地盤沈下などの鉱害を含まず,いわゆる典型7公害に限っている。しかし,近年では東京都の6価クロム事件やアメリカのラブ運河事件のように産業廃棄物による公害,あるいは日照・通風権侵害など,公害は多様化する傾向にある。また,〈京都府公害防止条例〉の公害概念に見られるように,自然,景観,歴史的文化財の破壊なども対象にして考える動きがある。
このように公害の概念はしだいに広くなる傾向にあるが,科学や政策の対象として,おのずから一定の領域を定めるべきであろう。例えば,薬品公害,食品公害というように,商品使用によって直接発生する被害を公害の中に入れる傾向がある。これらは社会的災害であり,とくに企業が安全の費用を節約したために発生するという意味で,公害と根は同じだが,環境破壊を媒介にしていないという点で異なっている。また石油関連工場,石油タンクや石油・LNGなどのタンカーの爆発を公害に入れる人もある。これも原因は公害と共通しているが,一時的な事故という点で,公害のように日常経済活動に随伴する社会的災害と相対的に区別されよう。
公害の歴史
欧米諸国
典型としてのイギリス
人類は社会をつくり,生産力を発展させる過程で,自然を改造し,古い環境を破壊してきた。環境破壊は有史以来繰り返されてきたことだが,それが局地的でなく,国土全体で公害として問題になり始めるのはイギリス産業革命以降のことであり,地球規模で日常的社会問題となったのは現代であろう。公害史の典型はイギリスに求めうる。
イギリスは暖房などの燃料に石炭を使用し,とくに首都ロンドンが大気汚染を起こしやすい地形であったため,早くから公害問題に悩まされていた。17世紀半ばには,有名な統計学の始祖J.グラントは,《死亡表に関する自然的および政治的諸観察》(1662)の中で,ロンドンの死亡率の高い原因を大気汚染に求めている。
産業革命は工場という〈魔法の杖〉で農村を都市に変えたが,当時の労働者の居住環境は地獄的なものであった。労働者の街は,工場と鉄道の間にあったり,工場の煙をまともに浴びる風下にあって,日光は不足し,風通しが悪かった。都市計画は工場を核にしてつくられ,河川は工場に占有され,下水道の代りとされた。労働者の住宅は狭く,多くの家族が同居しており,不潔であった。この居住環境の悪化と労働条件の過酷なこととがあいまって,結核,赤痢,チフスやコレラなどの伝染病が広がった。イギリスの公衆衛生行政の創始となったE.チャドウィックは,1842年の報告書の中で,労働者の死亡率が高く,経済的損失の大きいことを警告している。この報告に基づき,48年以降,中央政府は〈公衆衛生法Public Health Act〉によって衛生の改善に努めるが,地方団体の不熱心なこともあって事業は進まなかった。55年には〈公害防止法Public Nuisance Removal Act〉が公布される。これによって,公害対策機関を各地につくり,その所有地上に危険物ないし不潔物を堆積している土地所有者または借家人にそれらをとり除くように命じたり,販売されている有害食品を没収したりする権限を賦与した。しかし,既存の機関と錯綜(さくそう)しているために効率は上がらず,公害除去の訴訟も手続に手間をとり,訴訟費用が汚染者の隠れみのといわれた。
化学工場のばい煙に対する住民運動と,その裁判闘争の勝利を経て,63年,大気汚染防止のための〈アルカリ工場法〉が成立,また1847年以降,新興資本家たちの反対を押し切って各地方に数十の公害防止条例が出現したものの,公害問題の改善には直接は結びつかなかった。F.エンゲルスは《イギリスにおける労働者階級の状態》の中で,公害を〈社会的殺人・傷害〉と名付け,これは不作為犯であるが,犯人はこの社会の支配者である資本家階級であると述べ,また,K.マルクスは,《資本論》の中で,このようなたくさんの公害防止の法律や条例と熱意のある行政官の行動にもかかわらず,事態はいっこうに改善されていないと述べている。
イギリスの公害問題は,20世紀に入っても,1960年代後半まで基本的改善をみなかった。1914年にニュートン卿 Lord Newtonを議長とする委員会が大気汚染の調査をしたが,21年の最終調査報告書では,工場地帯の中で成育した人々は煙の存在に繁栄を見,環境の悪化を経済生活の豊かさと思い違いをし,地方団体も中央政府も環境の改善に無為であったと痛烈な結論を下している。実際に1世紀にわたり公害対策は進まず,52年12月のロンドン・スモッグ事件では約4000人の過剰死亡者を出した。そしてこの事件を契機として56年,大気汚染に関する法律が全面改正されて〈大気清浄法The Clean Air Act〉が制定され,ようやく実効が見られるようになった。河川についても,20世紀前半まで繰り返し汚染による伝染病が起こっており,近年ようやく,大都市の河川汚濁が減り浄化が進んだといってよい。
70年,イギリスは環境省をつくり,日本の建設省,運輸省,国土庁などを環境庁にあわせたような組織に集大成した。環境政策を総合的に行うためである。
イギリス以外の国々
イギリス以外のヨーロッパ諸国,あるいはアメリカ大陸の資本主義国では,イギリスと同じように,産業革命以後,公害問題の増加とともに対策がとられている。ドイツの場合,インミッシオンImmisionとしてイギリスのニューサンスと同じように,ガス,煙,熱,騒音などによって,隣地の所有や利用を侵害する行為を取り締まってきた。あるいは,アメリカの場合には,自治体の条例によって,大気汚染や水質汚濁の防止が進められた。とくに大気汚染のひどかったピッツバーグの市民ぐるみの公害対策は効果をあげたといわれる。しかし,一般的にいって,急激な工業化,都市化,とくにロサンゼルスの公害に見られるような自動車の増大や大量消費に伴う廃棄物の増大は,事態の改善を困難にした。各国が総合的な環境保全の法制と実行官庁づくりに一定の効果をあげ始めるのは,1960年代の終りから70年代にかけてである。
日本における公害の歴史
第2次世界大戦以前
日本の公害問題の記録に残る歴史は,少なくとも17世紀までさかのぼりうる。しかし,社会問題として深刻化したのは明治以後のことであろう。第2次大戦前の公害問題は大きく三つの典型に分けることができる。
第1は戦前の最大の国内資源であった銅の精錬や硫酸製造に伴う鉱山・工場公害である。足尾,別子,日立,小坂の鉱山・製錬所の公害事件や,硫酸工場の煙害に対して農民が訴訟を起こした大阪アルカリ公害裁判が有名である。足尾鉱山の足尾鉱毒事件は,銅製錬後の鉱滓が洪水のたびに大量に流出し,下流の農民の健康や農作物に被害を与えた事件で,のちのイタイイタイ病事件と同じ性格のものである。古河財閥と政府は,被害農民の反対運動を権力によって弾圧した。これに対して,別子銅山と日立鉱山の事件は製錬所の亜硫酸ガスによる大気汚染事件である。これらの事件では長期にわたる農民の反対運動が繰り返された結果,企業は公害対策をせざるをえず,今日の公害対策を考えるための主要な原則が確立したという点で重要である。すなわち,別子銅山については1910年に農民と協定を結び,汚染物の削減をしなければ増産できぬことになり,このため種々の失敗の末,発生源対策を確立した。これはばい煙中の亜硫酸ガスを回収して硫酸にするもので,34年には二酸化硫黄SO2の排出濃度は1900ppmにまで削減した。別子銅山の場合,すでに1904年には製錬所を四国本島から20km離れた四阪島に移しており,このような人家と工場をひき離す立地政策は高濃度の汚染物を排出していた時代には失敗であったが,発生源対策が進むと効果をあげることがわかった。また,日立鉱山は,14年156mの世界一の煙突を325mの山に立てることによってばい煙対策に成功した。これは拡散,希釈という自然の力による方法である。日立鉱山のケースは煙突が1本で,内陸から海へ向けて高層気流のある条件の下で成功したもので,戦後の工業地域のように,多数の汚染源のあるところで行って失敗した高煙突対策とは違っている。また,公害を発生した場合の賠償も行われており,例えば,別子銅山に関して住友鉱業が1910年以来39年の公害問題終了宣言に至るまで,848万円の巨額の賠償金を農民に支払っている。
第2の典型例は大阪府・市の公害問題である。日本のマンチェスターといわれた大阪市は,すでに明治10年代に煙害にみまわれている。このため,公害防止のための条例の制定が行われたが実効をみるには至らなかった。さらに日露戦争以降の重化学工業化と都市化は公害を発生させ,このため,大阪府は工場の許可制度を敷き,厳格な公害防止条例を用意するが,産業界に反対された。このような状況の中で大正末期,関一大阪市長は,市立公衆衛生研究所において,大気汚染の常時観測をはじめ,日立鉱山の高煙突の設立者鎬木徳二などの優れた研究者を集めて,防止対策を行わせた。大阪市の公害対策は戦争によって中断するが,戦前の先駆的な公共部門による公害対策といえよう。
第3の典型例は,八幡における八幡製鉄所の公害であろう。八幡製鉄所は官営であり,その公共性からいって,民間企業に比べてより進んだ公害対策をとらねばならぬはずであるが,実際には反対で,お上の権力で,〈企業城下町〉ともいうべき市民の発言が困難な都市をつくり上げた。このため,七色の煙といわれるようなばい煙を出し,下水道をつくらず洞海湾を下水道の代用物として漁場や海水浴場を破壊してしまった。ここでは戦前はおろか,公害防止条例のできた1955年以降ですら,67-68年まで,製鉄所の公害を訴える市民運動はなかった。
戦前,すでに公害対策の原理が確立し,一部では積極的な対策がとられたが,大部分の地域では,八幡製鉄所の場合のように,公害は野放しであり,被害者の運動は成功しなかった。とくに,恐慌から戦争にかけて,公害反対の世論や運動が終息するとともに,公害防止の技術開発や対策の発展は全国的に中断した。
第2次世界大戦後
戦後,朝鮮戦争とともに,日本の経済は復興過程に入り,1955年前後から史上空前の経済の高度成長が始まった。1950年東京都,51年大阪府,55年福岡県に公害防止条例が制定されたものの,重化学工業化と都市化は,住民の公害反対の世論や運動が立ち遅れたこともあって,このような規制を踏みにじって前進した。高度成長期の日本の都市は,史上かつてない環境悪化にみまわれることになった。例えば,56-60年の平均をとると,大阪におけるスモッグは実に年間125日,東京は年62日となった。スモッグのために昼間から自動車がライトをつけねばならず,東京から富士山が見えなくなったのも,このころである。地方においても,工業都市の汚染は空前の状況となった。水俣病,イタイイタイ病などの深刻な公害事件が発生したのは,この高度成長の初期のことであった。
戦後の公害の典型は,日本最初の石油コンビナートを建設した四日市の公害である。1958年ころから四日市港内において石油くさい魚がとれ,やがて漁業が困難となった。60年,コンビナートが完全操業を始めると,1000人に達する喘息患者が発生した。当局や企業は,石炭と違って石油を原燃料とする工場では公害はないとして責任を回避したが,三重大学や名古屋大学の調査では原因が石油コンビナートにあるとされ,裁判で確定した。四日市に続いて,1950年代後半以降,70年代までにコンビナートが三大都市圏と瀬戸内圏につくられた。これらの地域は四日市に学んだとしながらも多かれ少なかれ不完全な対策で公害問題を発生した。
1960年代後半以降,後述のように公害反対の世論や運動が行われた結果,表のように公害裁判が被害者の勝利に終わり,また革新自治体が大都市圏を中心に誕生して,厳格な公害防止対策をとるようになった。これに加えて,国際的な環境問題への関心の深まりもあって,70年,いわゆる公害国会において,公害対策関係15法(〈公害健康被害補償法〉のみ1973年)が成立し,71年には環境庁が発足した。
このように一時期進展を見たものの,石油ショック以降,不況が慢性化するとともに,環境政策の後退が始まった。78年7月,環境庁は二酸化窒素NO2の環境基準を緩和した。公害裁判は81年12月の大阪空港公害事件の最高裁判決で,夜間飛行差止めの請求が門前払いをされ,他の裁判の判決も明らかに被害者に不利となり始めた。企業の公害防止投資の推移はこの間の事情を忠実に反映している。すなわち,それは1970年の1883億円(全設備投資の5.3%)から,75年には9645億円(同17.7%)と,世論や政策に押されて世界最高水準となったが,79年には3256億円(同5.4%)に激減,物価上昇を考えれば,ほぼ10年前の水準に逆戻りしている。また,財界は,〈公害健康被害補償法〉の撤廃など,よりいっそうの環境改革の後退を公然と主張している。OECDは,1975年前後の資料をもとに,77年日本の環境政策について日本は数多くの公害戦闘に勝利を収め,今後はアメニティ(快適な環境の創造)が課題だと高い評価をした。たしかに硫黄酸化物SOxなどの一部の汚染物の削減は効果をあげた。しかし,水俣病などの過去の被害救済は行き詰まり,他方,公共事業の公害や自動車公害,ごみ・合成洗剤の公害など,消費過程の新しい問題が生じ始めている。
このような環境政策での行詰りは日本のみではない。1972年のストックホルムでの国連人間環境会議は,〈かけがえのない地球〉というスローガンの下に開かれた人類最初の国際会議としてのその意義は大きかったが,以後の世界経済の不況による各国の環境政策の後退の影響を受けて,第2回は開かれていず,82年10周年記念大会がナイロビで行われたにとどまっている。
公害問題の特徴
被害の側から見た特徴
生物的弱者への集中
公害問題を被害の側から見た特徴は,まず第1に生物的弱者から被害が始まることである。環境が汚染されると,人間に先立って,動植物に被害が発生する。次いで,人間の健康障害が生ずる場合には,病弱者,高齢者や年少者に被害が集中する。毎日,通勤,通学しているような健康な青壮年層が被害者となるときには,あらゆる年齢階層が病気で倒れているであろう。大気汚染による公害病認定患者は,14歳以下の年少者と55歳以上の高齢者で70%以上に達する。他の公害病も同様である。イタイイタイ病は中年の経産婦を被害者としているが,これは妊娠中の女性が胎児にカルシウムを摂取されるという条件の下で,カドミウム中毒が進行したと推定されるので,広い意味で,生物的弱者といってよいだろう。病弱者,高齢者や年少者に被害が集中するというのは,これらの人たちの社会的行動様式と関連している。すなわち,これらの人たちは汚染区域に24時間住んでいる場合が多く,男子の青壮年層のように行動半径が広くない。性別で見ると,大気汚染による公害病認定患者は,男子の比率が若干大きい。ところが,15歳以上54歳までの青壮年層をとると,女性が多くなる。これは,この年齢層に多い家庭の主婦が,24時間汚染地域に住むという行動様式をとっているためであろう。
病弱者,高齢者,年少者と主婦の大部分は企業に雇用されていない。このため,これらの階層が被害を受けても,企業にとっては損失にならない。長期的には年少者の健康障害は生産力を衰退させ,高齢者や主婦の公害問題は社会不安の原因となる。しかし,短期的には生産力の減退は起こらないので,被害者が活動しない限り,財界や政府も経済的損失として公害問題をとらえることはない。このことが,公害対策を遅らせて,公害を深刻化させた一因である。
社会的弱者への集中
第2の特徴は被害者が社会的弱者を主体とするということである。公害病認定患者の大部分は,低所得の勤労者,下流中産階級の市民や貧しい農漁民である。高額所得の企業家・政治家や上流中産階級は,よい環境を選択し,良好な住宅に住み,栄養のよい安全食品を食べ,高級な医療を受けているので,公害にあうことは少ない。例えば,大阪市に本社をもつ一部上場企業の重役のうち,約7%しか,日本一環境の悪いといわれる大阪市には住んでいない。残りの経営者は比較的環境のよい西宮,芦屋,宝塚,神戸などの各市に住んでいる。これはアメリカやイギリスについても同じことがいえ,公害にあうのは,低所得の少数民族が多い。低所得者は自力で公害対策をとり,高度の医療を受け,病気になっても生活を維持することはできない。なんらかの社会的救済が必要であろう。しかし,社会的弱者は個人では政治的力が弱く,このため公害対策はなかなか実行されなかった。
絶対的損失の発生
公害問題の第3の特徴は絶対的損失が発生することである。環境は市場価値をもたぬか,その効用に比べて市場価値は小さい。このために,環境が破壊されても,企業のコスト上昇とならず,コストに含めても大きな影響はなかった。公害を市場経済の尺度ではかると小さいが,人間社会に対する影響で見ると重大である。とくに,それは次のような絶対的不可逆的損失を含んでいる。(1)人間の健康障害および死亡,(2)人間社会に必要な自然の再生産条件の復旧不能な破壊(大規模な埋立てや宅地造成),(3)復元不能な文化財の損傷,(4)固有の景観の損失など。
これまでの経済現象では,開発に伴う損害は,利益を得る事業主体が被害者に補償をすれば社会的公平が保てるとされた。しかし,このような損失は貨幣で補償しても不可逆で絶対的なものである。
このため,公害問題は他の経済問題と違って予防がたいせつであり,もしも被害が発生した場合には,差止めというきびしい制裁措置が認められている。しかしながら,現実には環境保全よりも経済の優先の傾向があるため,予防措置としての環境影響事前評価制度(環境アセスメント)が不十分ながら実行されるのは,1970年代のことであり,裁判においても差止めはなかなか認容されていない。
公害の加害者
資本主義と市場の失敗
現代社会の公害の加害者の多くは企業であり,また公共事業では政府・自治体である。公害は社会的損失または社会的費用といわれるように,経済過程において,その費用を原因者が負担せず,第三者や社会に転嫁している。このような現象は,先述の三つの特徴に見られるように,資本主義経済制度の欠陥あるいは市場の失敗market failureと呼ばれている。企業が公害を発生させても市場制度の下では損害にならず,むしろ,公害対策費を節約するだけ価格が下がって,公害対策をしている企業に比べて競争に勝ち,利潤をあげ得るためである。そこで,この社会で公害を防止しようとすれば,公共的介入といって,行政や司法の手でなんらかの規制をしなければならない。しかし,現実には,企業の力は強く,政府や自治体は企業と一体になっている場合が多いので,住民が公害反対の世論や運動を起こして,公害対策をとらせるように,政府・自治体や裁判所に働きかける必要がある。公害問題は市場制度の下では他の経済問題のように放置していては解決されず,なんらかの住民の世論と運動を必要とするのである。
旧社会主義国の公害
旧社会主義諸国の場合,急速な工業化,都市化の過程で公害が発生している。例えば,チェコスロバキアとポーランドにまたがる鉄と石炭の産地シロンスク地方の工場地帯の公害などは,1960年代の北九州地域のように深刻である。社会主義国の多くは,70年代半ばに憲法を改正して環境権をうたい,また資本主義国に比べて市場の失敗の影響は少ないはずだが,なぜ,このような深刻な公害問題が起こるのであろうか。その理由は,これらの諸国の生産力が資本主義国より低く,近代化を急ぐために,企業は公害対策費を節約して,生産向上に専念し,一方,政府がコンビナート方式のような集積利益を上げる立地計画をとって汚染源を複合させた結果であろう。また,国民もポーランドの調査によると,大気清浄化より自動車の増産を望んでいるという。欧米や日本のような生活様式を理想として急速な都市化,工業化を進めれば,社会主義国といえども同じような公害が発生するといってよい。それに加えて,官僚主義が支配していると,公害反対の世論や運動を国営工場に向けて行うことは制約され,また司法権の自立や新聞などのマス・コミの独立が保障されていないと,汚染企業を告発することも困難となろう。
産業革命以来の歴史を見ると,公害問題は明らかに資本主義のアキレス腱で,今後もなお解決がむずかしいが,現代社会主義国も公害問題の解決の道を示しえていないといってよいだろう。
日本の公害問題の特徴
日本は国土が狭く,人口が密集しているので,公害を発生しやすい条件にあるが,とくに戦後の高度成長の過程で,三大都市圏に企業と人口が密集した結果,他国に例を見ない公害の発生を見た。
事実の隠ぺい
高度成長期の公害問題の特徴としては,まず,産業公害が中心で,その中には企業犯罪と呼べるような事件が起こったことをあげることができる。典型例は水俣病である。この事件発生直後,1956年,熊本県水産課は工場排水説をとり,また,熊本大学医学部水俣病研究班も当初から工場排水説をとり,59年には有機水銀説を発表,62年にはアセトアルデヒドの製造工程から原因物質が排出されることを解明している。ところが排出源のチッソはこれを認めず,68年まで有機水銀をたれ流した。この間,チッソは東京工業大学清浦雷作のアミン説を支持,1959年,工場付属病院の細川院長の猫による実験で熊本大学の有機水銀説の正当性を認めながら,それを秘密にして,患者との間に見舞金契約を結び,この事件をやみに葬ろうとした。同様なことは,阿賀野川有機水銀中毒事件(新潟水俣病事件)にあたっての昭和電工の対応にも見られる。このような企業の犯罪的な態度が被害を残酷なものにし,事件発生後30年近くたっても,根本的解決をみない原因といえよう。
政府・自治体と企業の関係
日本の公害問題の第2の特徴は,政府・自治体が被害住民の立場に立たずに,汚染企業の助成にまわりがちなことであろう。先の水俣病事件では,通産省はチッソ=清浦説をとり,厚生省は熊本大学説をとって対立,政府見解は,1968年まで水俣病の原因は不明というありさまであった。このため,有機水銀対策は遅れ,69年に第2水俣病の発生を見た。戦後の重化学工業は臨海部にコンビナートを造成することによって発展したが,これを促進したのが地域開発政策である。四日市公害は,地域開発のもたらした事件といっても過言ではない。以後のコンビナート公害も同様であって,政府・自治体は汚染企業と同じ責任をもつといってよい。
各国政府は形式的にせよ,住民の環境保全の世論と運動を支持している。しかし,日本の政府と多くの自治体は,高度成長期を通じて,住民運動を軽視してきた。その反面,公害対策では企業に対する補助政策を続けている。例えば,四日市公害裁判で,8人の原告が12年の苦闘の末手にした補償金は9619万円であるが,73年度,四日市市がコンビナート3社の公害対策設備の固定資産税を免税した額は9709万円であった。同じことは日本全国についてもいえる。76年度決算で見ると,企業が〈公害健康被害補償法〉や〈公害防止事業費事業者負担法〉で負担した額は839億円だが,公害関連減税,公害防止事業公費負担などの企業助成額は1400億円にのぼる。
絶対的損失の大きさ
日本の公害問題の第3の特徴は,絶対的損失が大きいことである。現在,公害病認定患者は10万人に達しているが,実数はこの数倍以上といわれている。戦後,三大都市圏の港湾や瀬戸内海を中心に埋立てが進み,全海岸線の60%が人工海岸となった。その他の取り返しのつかぬ自然破壊は枚挙にいとまがない。宅地開発による文化財の損傷も全国的である。高速道路などの建設によって,東京や大阪の景観も消失してしまった。これら巨大な損失は,価格ではかりえないものが多く,後代に伝承すべきストックを失ったといってよい。
このような日本の公害の深刻さの原因は,なによりも,重化学工業化と大都市化を進めた高度成長の経済構造にある。1970年代半ばまで,日本の産業構造は,鉄鋼,石油,石油化学,アルミニウムなどの素材供給型産業を中心としていたので,生産単位当りの汚染物排出量がきわめて大きかった。70年までは企業の公害対策はみるべきものはなかった。それに加えて,これらの汚染企業は三大都市圏と瀬戸内という人口密集地区に集中的に立地した。これは企業が集積利益を最大限にあげようとしたためだが,それは住民からみれば,極度の集積不利益を受けることとなった。例えば窒素酸化物NOxの1km2当りの排出量は,全国平均で1955年の0.6tから71年には17.0tに増えているが,関東臨海部では同時期に2.3tから68.3tと驚くべき増加となっている。大阪圏や名古屋圏も同じである。この期間に,史上最大の人口移動が,地方から三大都市圏へ生じた。したがって,公害病が多発したのも必然であった。
高度成長期には大量消費生活様式が導入された。とくにモータリゼーションは急激に進んだ。この結果,自動車公害は都市では工場公害に劣らぬ被害を招くようになった。また,合成洗剤による水汚染や大量のごみによる公害問題も,この大量消費生活様式の無計画な普及によっている。
戦後の日本経済を支えたのは,世界最高の公共投資である。この公共投資の半分は道路,鉄道,港湾,電信・電話などの交通通信手段の建設にまわった。そしてこの建設は効率を中心にして,短期間に行われた。このため,道路公害や空港公害などの公共事業による公害が全国的に発生した。
公害対策と公害反対運動
公害対策
公害対策は,次の四つの側面がある。(1)被害の実態把握と原因の究明,(2)被害の救済,(3)汚染源の規制,(4)公害の予防と環境の保全である。
被害がすでに発生している国や地域では,(1)から(4)へと政策や研究が進められねばならないが,これから経済開発を行う国や地域では,既発生地域の経験を参考にして,(4)から(1)へと政策を構成しなければならない。
被害の把握と原因の究明
公害問題は被害に始まり,被害に終わるといわれるが,公害対策にあたっては,なによりもまず,被害の全貌を明らかにし,その原因を究明しなければならない。これは当然なことのようにみえるが,まことに困難である。例えば,水俣病の患者は1960年代の資料には87人と断定していたが,いまでは何人いるかまったくわからない。81年3月現在,水俣湾周辺の水俣病は熊本県認定患者1042人(死亡397人),鹿児島県258人(死亡40人),認定申請者は両県で5624人,新潟県阿賀野川は認定患者588人(死亡96人),申請患者90人にものぼっている。また,遅発性患者や新しい地域の患者が発生しないとは限らない。大気汚染患者については,いまだに全国的調査は行われていないので,潜在患者はつかめない。このように,肝心の被害の全貌が不明な理由は一般的にいうと二つある。自然科学的にみるならば,疫学を中心とした被害調査が徹底して行われていないためである。とくに初期の疫学調査の不十分さがこのような事態を生んだのである。環境の科学は1970年代に前進し,研究費も増えているが,工学部門の研究費が多く,医学部門とくに被害調査は遅れている。社会科学的にみるならば,被害救済をはじめ,世論や行政が被害者を支持する社会的状況がなければ,公害は顕在化しないためである。水俣病患者は73年の第1次裁判の原告勝訴までは,名のりをあげても利益は少なかった。それよりも,患者自体はもとより家族も就職や結婚の妨げになり,損失が大きかった。大気汚染患者の場合も同様で,申請をするとアカ呼ばわりをされたり,差別をされるので,川崎市などでは,実際は1/10程度の申請であるといわれる。このように被害の実態把握も社会的なもので,被害者に対する社会的連帯が必要である。
被害の原因の究明は長年月かかる。この理由は,原因が複雑で,公害の科学が遅れていることもある。しかし,多くの場合は,汚染者が原因の究明をはばむことにある。企業の営業上の秘密,政府・自治体の行政上の機密,軍隊の軍事上の機密や研究者などの研究上の秘密などは法律や慣習で保証されているが,これが,加害者を保護する役割を果たしている。医学の秘密があってはならぬように,公害問題については,秘密は限定されねばならないだろう。とくに危険物質の使用については,すべて公開されることが望ましい。
被害の実態の把握と原因の究明は,欧米でも遅れている。とくに健康障害の調査は不十分である。例えば,カナダのオンタリオ州西部のインディアン居留地の水銀中毒事件などは一例である。
救済
被害の救済のためには,責任が明確化されねばならない。原因が究明されても,責任が確定するには長年月かかる。水俣病は17年,四日市喘息は12年かかっている。責任が確定しても,救済が完全に行われるとは限らない。大阪空港公害事件では,1964年ジェット機導入以来,17年後,欠陥空港をつくった運輸省の責任がようやく最高裁で認められたが,被害者に対して過去の慰謝料50万円が支払われたにすぎない。被害救済の原則は,原型復旧である。被害者の健康を回復し,破壊された自然や文化財を復旧し,景観を回復し,被害者が社会へ復帰して安心して生涯をおくれる地域社会を再生することである。金銭賠償をするのは当然だが,それで被害が回復するのではない。
被害の救済は,日本では伝統的に,被害者と加害者の直接交渉と行政の介入によって行われてきた。しかし,1960年代後半,企業や行政機関の不誠意に絶望した被害者は,裁判に判定を求めた。四大公害裁判によって原告が勝訴し,さらに被害者の要求によって四日市,尼崎,川崎,東京,大阪などに自治体による補償制度が確立することによって,全国的な制度化が進んだ。69年には医療費無料化を中心とした救済法が成立し,さらに73年障害補償費を中心とした〈公害健康被害補償法〉が成立した。この制度は世界で最初の行政的救済制度である。一面で民事的責任を果たす側面をもっているために,障害補償費(患者への年金)や医療費などは企業の実額負担である。他面で行政的救済という側面をもっているので,給付額は労働災害に準じて,平均給与の80%となっており,各企業の負担額は租税と同じように公開されていない。
補償法は他国に例を見ず,多くの問題点をもっている。被害者にとってみれば,裁判のように費用と年月がかからないので手続は便利になったが,加害者の責任追及は不明確となった。大気汚染についてみれば,全体の80%は主要汚染源かSOxの寄与率に応じて拠出しているが,残りの20%は自動車重量税で負担している。これは自動車企業が負担を回避しているためである。近年,SOxが環境基準を達成し始めているので,財界はこの制度をやめたいと主張している。しかし,NOxは横ばいであり,これを新しい負担の基準にすべきだといわれている。障害補償費は男女や年齢によって大きく違っている。これは労災を基準としたためだが問題があろう。
このようにたくさんの問題点があるが,これに代わる適正な補償制度が考案されない限り,廃止することは被害者が長年月かかって取得した権利の侵害である。
規制
公害の規制は大きく分けて二つある。第1は発生源対策である。日本では,汚染物質または規制対象別に環境基準を定め,それに基づいて発生源ごとに規制基準を定めている。日本の特徴は,この物質や対象が過去の公害事件を起こしたものに限定されていることである。このため,アスベストなどの化学物質や重金属物質についての規制が不十分である。また過去の健康障害をもたらした物質の環境基準は他国よりも厳格だが,水汚染中生活環境項目や騒音,振動などの規制はルーズである。とくに騒音は市民の過半数を悩ましているが,基準は現実妥協的となっている。また,環境基準は物質ごとにばらばらで,複合汚染は対象としていない。
公害の規制の第2の方法は,社会資本の造成や立地計画などによって,公害の影響を除去あるいは削減する方法である。日本では公害防止計画がとられている。これは公害の激甚地および公害のおそれある地域を対象にして,土地利用計画,生活環境施設の整備や自然の保全などの総合施策を行うものである。1981年現在,第1次から第7次まで47地域を指定し,主要な工業都市および大都市地域など43地域(対全国比,面積で9%,人口で54%,製造品出荷額66%)が対象となっている。これらの地域において環境基準達成を目標としている。
予防
公害の予防のためには,事業前の環境アセスメントが重要である。アメリカは1969年〈国家環境政策法〉によって,公共事業その他公共機関の介入する原子力事業などについて,アセスメントを行うこととなった。年間約2000件のアセスメントが行われ,うち約10%が事業計画の修正を要求されている。また,州や市町村でもアセスメントの条例が施行されている。同じような制度は,カナダ,スウェーデンや西ドイツでも行われている。日本では72年に閣議了解によって,国の公共事業について環境アセスメントを実施することが定められ,〈公有水面埋立法〉と〈瀬戸内環境保全特別措置法〉ではアセスメントが義務づけられている。このため,大規模事業については,アセスメントが行われているが,その内容に不備があり,とくに第三者機関の審査や住民参加などがなく,制度上の欠陥もある。環境庁は76年以来,毎年アセスメント法案を準備しているが,財界や政府部内の反対もあって実現していない。
実現手段
公害対策を実現する手段は,行政や司法によって直接規制をする方法と,財政や金融によって経済的刺激を与えて行う方法とがある。日本では直接規制が主要な手段である。公害反対の世論や運動が強い場合には,小型自動車排ガス規制問題や四大公害裁判に見られるように,直接規制は有効である。経済的刺激策では,補助金,財政投融資,減免税,課徴金などの手段があるが,課徴金がもっとも有効であるといわれる。課徴金を汚染者に負担させる方法をPPP(汚染原因者負担の原則)という。この方法では,結局のところ,汚染者はその負担を経済的弱者に転嫁し,多くは消費者負担となる。日本の場合,PPPとしては,先の〈公害健康被害補償法〉や〈公害防止事業費事業者負担法〉の企業負担がある。
日本では公害反対運動の歴史が長いが,とくに,戦後,市民運動として大きく広がったのは,1963-64年の三島,沼津,清水の2市1町の住民による石油コンビナート誘致反対闘争の成功以後である。これを手本とした三島・沼津型と呼ばれる公害反対運動は,徹底した共同調査と共同学習を土台にして,自治体闘争を中心とするもので,地域の各界各層が連帯するところに特徴がある。現在,数千の住民組織が活動している。ヨーロッパでは,環境保護団体が独自の政党(緑の党)をつくっている。日本では,このような動きはないが,政治上無視できぬ力をもっている。とくに,日本の特徴は,被害者団体の団結力が強く,全国的に結集していることである。
79年6月,環境政策を憂えた公害問題の研究者や弁護士が呼びかけて,日本環境会議を結成した。この会議では環境は公共信託財産であり,環境権を守る義務は政府・自治体にあることなどをうたった〈日本環境宣言〉を発表した。80年5月には,住民によるアメニティを求めた〈日本都市環境宣言〉,81年11月には,生活環境としての自然から地球規模までの自然の保全を求めた〈日本自然環境宣言〉が発表された。このような研究者,実務家の運動が大きな役割を果たしていることは,先の被害者の運動の活発なこととともに日本の特徴といってよい。
→悪臭 →地盤沈下 →振動公害 →騒音 →大気汚染 →土壌汚染 →水汚染
執筆者:宮本 憲一
公害反対運動
日本における公害反対運動は,1960年代に始まった高度経済成長政策に伴う環境破壊とともに,社会的注目を集めるようになった。全国各地で起こった公害や自然破壊,さらに歴史的環境の破壊に対し,それぞれの地域で住民は事態の解決を求めて立ち上がり,発生企業の責任を追及,破壊行為の差止要求,損害賠償の請求,さらにそのような事態の発生を黙認した行政の責任追及など,さまざまな行動を起こし始めた。それまで被害を受けても泣寝入りしがちだった住民たちが,この時期になって,すすんで立ち上がり始めたことは,日本の人権意識の確立の歴史のうえから注目すべきことである。
しかし,このような住民運動はこの時期になって,にわかに起こってきた現象ではない。日本の公害は明治の初めの足尾鉱毒事件から始まっているとされているが,住民運動の歴史もまたこのころから起こり,公害の歴史とともに今日に及んでいる。そこでまず明治以来現代までの住民運動の軌跡をたどってみよう。
初期の公害反対運動
1887年,栃木県の足尾銅山の鉱毒により渡良瀬川流域の水質汚濁による農業と漁業被害が明らかになると,流域の住民は政府に対策を請願するため東京に〈押出し〉と呼ばれる大衆行動を行った。1900年には利根川北岸の川俣で数百人の警官と憲兵が農民たちを抑制し多数の負傷者と逮捕者が出た〈川俣事件〉も起こっている。栃木県選出の衆議院議員田中正造がこの行動を支援し,議会でとり上げるとともに01年には明治天皇の馬車に直訴状をかかげて駆けよる非常手段をとっている。足尾鉱毒事件は被害の深刻さと約30年に及ぶ企業と政府に対する住民の救済要求の行動という点で,日本の公害と住民運動の原点といえよう。このほか04年には,新居浜から瀬戸内海の四阪島に移転した住友鉱業別子銅山鉱業所からの煙害に対し,農作物の被害を受けた愛媛県の農民たちによる住民運動が起こっている。14年には日立鉱山の煙害に対する住民の要求に迫られて,企業は日本で初めて高さ156mの高煙突を建設した。東京の深川の浅野セメント降灰事件(1907),岐阜県の荒田川の中小繊維工場の排水汚濁事件(1923)などでの住民運動も注目される。
公害は第2次大戦後の経済復興から高度経済成長へと向かうとともに各地で起こり始めた。川崎市の大気汚染(1950),横浜喘息(1951)が問題になり,住民の要求を受けて,49年に東京都工場公害防止条例が,51年に神奈川県事業場公害防止条例,54年に大阪府事業場公害防止条例が制定されている。公害が本格的になったのは60年になってからで,1959年には四日市喘息が注目され,62年には東京でスモッグ被害が激しくなり,熊本県の水俣市では新日窒(のちのチッソ)の排水に含まれた有機水銀中毒による悲惨な水俣病が現れてきた。1962年,不知火海沿岸の漁民3000人は対策と損害賠償を要求して工場に乱入,乱闘事件がきっかけになり,水俣病事件は全国的に注目されるようになった。1961年には富山県のイタイイタイ病の原因が三井金属鉱業神岡鉱業所から排出されるカドミウムであると解明されたのをはじめ,安中市の東邦亜鉛工場増築反対運動,八幡での小野田セメント降灰補償要求運動など各地で〈対策協議会〉という名の住民組織がつくられ,公害に反対する住民運動が活発になった。茨木市,吹田市,大宮市などで原子炉などの施設設置反対が起き,さらに各地で原子力発電所建設反対運動が起こり始めている。また岡山を中心に森永ヒ素ミルク事件,ABS洗剤の毒性問題,サリドマイド薬禍など公害と取り組む消費者運動も盛んになってきた。
こうした運動に対し,初め企業の対応は消極的で,公害の発生責任を容易に認めなかったり,住民との交渉を拒否する例が多く,行政もまた産業擁護の立場から,公害発生企業への対策も十分ではなかった。しかし,東京湾の浦安の漁民が,本州製紙の江戸川へ排出した廃液による漁業被害の対策を求めて工場に押しかけ乱闘になったのがきっかけになって,1958年に公共用水域水質保全法と工場排水等規制法のいわゆる〈水質二法〉が制定された。61年にはばい煙規制法も制定されるなど国の対応も散発的ではあるが見られるようになった。
公害反対運動の活発化
1960年代の高度経済成長による工業化と都市化の波が全国的にまき起こるとともに各地で環境破壊が起こり,それに伴って住民の公害反対運動も活発になってきた。63年から64年にかけて静岡県の三島・沼津地区で静岡県が計画した石油コンビナート建設に対し,地元の市民たちが,公害学習会を開き,反対運動を展開し,建設を中止させた。67年には新潟水俣病と四日市喘息,68年には富山県のイタイイタイ病,69年には熊本水俣病と,いわゆる〈四大公害訴訟〉が相次いで住民運動を中心にして提起された。またこのころ,横浜市新貨物線反対運動,富士市のへどろ公害反対運動,富士川火力発電所建設反対運動,大阪国際空港騒音反対運動などもそれぞれに活発になってきた。これらの運動の全国的な連絡組織もつくられ,全国公害活動者集会や総評による全国公害対策連絡会議なども開かれるようになった。これをうけて国も対策に動き始め公害防止事業団法(1965),大気汚染防止法(1968),騒音防止法(1968),公害健康被害救済特別措置法(1969)などを制定し始めた。
公害反対運動の多発期
70年,日本列島の各地で公害が噴出し,住民による公害反対運動も活発になってきた。なかでも東京の新宿区の柳町交差点付近の自動車排ガスによる鉛汚染,東京の杉並区を中心にして起こった光化学スモッグ事件など,各地で大気汚染や水質汚濁など多種多様の公害が深刻化してきた。この年の春,東京では社会科学者による公害国際シンポジウムが開かれ,人権としての環境権の存在が確認され,各地の運動に指針を与えた。年末には公害対策を集中審議する〈公害国会〉が開かれ,公害対策基本法の改正など公害関連の14の法律が制定されたり改定強化された。そして翌71年7月に環境庁が発足した。このように公害は,まず第1にこれと直面した住民が,生活環境を守るために行動を起こし,それにこたえて自治体が条例などをつくり対応する。そうした条例が各地に制定された現実をもとにして国が法律をつくって対策を立てる。日本では環境問題に対する対策は住民→自治体→国という順序をたどっているのが一般的な現象である。
71年から73年にかけて四大公害裁判の判決はいずれも原告の勝訴になり,とくに四日市喘息の判決では複数企業の共同不法行為の責任が明らかになり,公害に対する企業の責任が追及された。1972年ころから北海道電力伊達火力発電所建設をはじめ九州電力豊前火力発電所,関西電力多奈川第2火力発電所などの建設に反対する環境権訴訟が住民によって各地で提起されるようになった。すでに公害が発生してしまったあとからの事後的な損害賠償の請求運動から,将来の環境破壊を予想して事前に公害源の建設を防止しようとするものに発展してきた。このころから住民運動は企業の公害発生責任の追及から,さらに進んで道路建設や新幹線,空港騒音,ごみ処理場,埋立てなど国や自治体を相手どって,公共事業による生活環境の侵害にも対決するようになった。
経済が高度成長から低成長へ転換し開発事業が沈静化するとともに,住民運動もかつてに比べその数は減った。この現象を見て〈住民運動は冬の時代〉に入ったとする見方も出てきたが,一方で,住民運動が多様化したことも見のがしてはならない。公害と取り組むことによって環境を見つめる住民の目はきびしくなった。そうした視点からあらためて身の回りを見つめることによって人々は自然破壊の現状に気づき,1970年ころから全国各地で自然保護の住民運動を展開した。尾瀬や北海道の大雪山,妙高山,南アルプスなどで観光自動車道路の建設に反対する住民運動が各地で起こったのは,そのような人々の環境観の拡大を背景にしているといえよう。さらに70年代後半に入ると,住民は歴史的環境の破壊が現代の環境問題の重要課題であることに気づき,それとともに各地で歴史的町並みの保存・再生の運動が起こってきた。このように住民は公害,自然破壊,歴史的環境の破壊といったように,環境を幅広く総合的にとらえて保存運動を展開するようになるとともに,すすんで快適環境の創造を目ざすようになった。また琵琶湖の水質汚染に対し周辺の滋賀県の主婦たちが,リンを含む洗剤をやめて粉セッケンを使う運動を始め,それが契機になって滋賀県が富栄養化防止条例を制定したように,住民みずから環境汚染への責任はないかと自省して,すすんで生活方式の変革を試み,それを住民運動のエネルギーにするようになった。さらに住民がみずから寄金を出しあって保護すべき環境を買い取るナショナル・トラスト運動も,北海道の斜里町の知床半島の原生林復元運動や,和歌山県田辺市の天神崎買取り運動など各地で活発になってきている。住民運動が自治体をまきこんで積極的に環境創造の運動を展開していることは21世紀を目ざす新しい一つの運動の形態として注目される。
執筆者:木原 啓吉
公害に関する法律
日本では公害防止を目的とした法令は,1950年代初めころから,東京,大阪,福岡などの工業地帯をかかえた地方公共団体の条例の形で制定されはじめた(地方公共団体の条例は日本の公害法の基礎を作ったものであり,その後もそれぞれの時期に国の法律を導き出す重要な役割を果たしてきた)。
公害防止を内容とする国の法律は,1956年に制定された〈工業用水法〉に,地盤沈下の原因となる地下水の採取規制の規定がおかれたことが最初であるとされる。その後,58年に〈公共用水域の水質の保全に関する法律〉と,〈工場排水等の規制に関する法律〉(いわゆる〈水質二法〉。現在は廃止)が制定され,本格的な公害規制法の端緒となった。ただし,同法は,地域を指定して水質基準を定め,これにもとづいて排水規制をしようとするものであり,地域の事情に左右されがちであった。また当時の水質の検査技術の限界もあり,必ずしも実効性をあげなかったともいわれる。次いで60年には,〈ばい煙の排出の規制等に関する法律〉(現在は廃止)と都市における地下水の過剰な採取による地盤沈下防止のため〈建築物用地下水の採取の規制に関する法律〉が制定された。
しかし日本の公害はその後も激化をたどり,大きな社会問題となった。そこで,強い世論の後押しもあって,1967年には,公害対策を体系的に進めていくための〈公害対策基本法〉(のち1993年に〈環境基本法〉によって廃止された)が制定された。同法は,法律上の〈公害〉を〈事業活動その他人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁,騒音,振動,地盤の沈下によって,人の健康又は生活環境に係る被害が生じること〉と定義し,公害防止のための行政上の目標値である環境基準を定めることなどを規定した。ただし,同法は,生活環境の保全に関して,〈産業の健全な発展との調和を図る〉必要があるものと規定していたため,国の公害対策全体がそのような制約の下に置かれるとの誤解を生じ,批判をうける結果ともなった。ところで,この公害対策基本法をうける形で,68年に,旧ばい煙規制法が廃止され,〈大気汚染防止法〉が制定された。これによって,はじめて全国一律に大気汚染物質の排出を規制することとされ,大気汚染防止行政は大きく進展することとなった(なお,同法はその後数次にわたって改正され,総量規制や燃料規制などの新たな規制手法を積極的に取り入れていった)。また同じ68年には,〈騒音規制法〉も制定された(〈騒音〉の項目参照)。さらにこれらの公害の規制を目的とする法律のほかに,69年には,公害による健康被害者の医療上の救済を図るため〈公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法〉(現在は廃止)が制定された。またこの年には,これまでばい煙規制法などの中に取り入れられていた行政機関による公害紛争解決のためのあっせんの制度をさらに充実させた〈公害紛争処理法〉が制定された。このように1960年代の後半には,公害関係法の領域も,ある程度整備されてきた。
しかし,日本で公害関係法が本格的に整備されたのは,1970年の第64国会(いわゆる公害国会)であった。この国会では,公害対策基本法が改正され,前述の〈調和条項〉が削除されるとともに,〈土壌汚染〉と〈悪臭〉が公害の類型として新たに追加された。また旧水質二法に代えて,〈水質汚濁防止法〉が制定され,大気汚染防止法同様に,全国一律の規制基準が適用されることになった。このほか,〈海洋汚染防止法〉,〈農用地の土壌の汚染防止等に関する法律〉,〈公害防止費用事業者負担法〉,〈人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律〉が制定され,また大気汚染防止法,騒音規制法,〈農薬取締法〉,〈下水道法〉,清掃法などが改正された。この改正によって清掃法は,ごみ処理に伴う公害防止を重視した内容の〈廃棄物処理及び清掃に関する法律〉に改められた(なお典型七公害のうち,悪臭の規制は,1971年に〈悪臭防止法〉が,また振動の規制は76年に〈振動規制法〉が制定されている)。
1971年には,公害防止対策行政の一元化を図るとともに,さらに自然環境行政をも一元的に行うため,環境庁が設置された。そして,これまでに整備されてきた公害関係法の積極的な運用がなされ,これによって,工場・事業場からの大気汚染や水質汚濁の防止対策は大きく進展した。しかし,公共用水域の水質汚濁は,中小の汚染源に対する規制が十分に行えなかったことなどが理由で,必ずしも急速には改善されなかった。そこで,78年には,73年に議員立法によって制定されていた法律を改正する形で〈瀬戸内海環境保全特別措置法〉が作られ,瀬戸内海に流入する河川をもつ府県に,排水の総量規制が加えられ,あわせて東京湾,伊勢湾にも同様の規制を行うため水質汚濁防止法が改正された(さらに同年には,旧〈公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法〉が改正され,生活費用の補償を追加するなど被害者救済をより充実させた〈公害健康被害補償法〉(さらにその後〈公害健康被害の補償等に関する法律〉と名称を変更)に改められた)。また,84年には,湖沼の水質保全をさらに進めるため〈湖沼環境保全特別措置法〉が制定された。
公害対策が進まなかったもう一つの分野は自動車騒音や排気ガスによる公害であった。この分野については,1980年に〈幹線道路の沿道の整備に関する法律〉が制定され,自動車公害の激しい道路の沿道の土地利用の形態を変える等の対策を講じるものとされ,また92年には,〈自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法〉が制定され,首都圏などで最新規制車への買換えを促進させるため登録できる車種を制限する等の規制を新たに行うものとされた。また寒冷地で使用されるスパイクタイヤが道路路面を削り取ることによって生じる粉じん公害の防止のために90年には〈スパイクタイヤ粉じんの防止に関する法律〉が制定され,スパイクタイヤの使用が禁止された。
このように日本の公害関係法は,政策体系の基本を定めた公害対策基本法のもとに,各種公害の規制法をはじめ,紛争処理法,被害者救済法,刑事処罰法,公害防止事業法などの広い体系をもったものとして,1970年代前半までにほぼ体系的に整備された。そして,70年代後半からは,それらの不十分な点を補うための特別法が制定されてきたことがわかる。
しかし,前述のように規制の手法は,大規模な工場や事業場の排出する汚染物質を取り締まるためには有効であっても,小規模で多数にのぼる群小発生源(ノンポイント・リソース),とりわけ家庭の雑排水や,自家用車の排出ガスを減少させる手法としては効果がない。これらは個々の行為が直ちに目に見えて被害を発生させないために,〈公害〉として規制することは困難だからである。同様のことは廃棄物の増大に伴って,その処理に際して生じる環境汚染問題の解決に必要な廃棄物の量の削減についてもいいうることである。またさらに,地球規模での気象変動の防止のために必要とされる温室効果ガスの排出抑制やこのような目的に有効とされる省エネルギー・省資源を義務づける問題についてもいえる。1990年代に入ってくると,政策の目標を,現実の被害を想定した〈公害防止〉の段階よりもっと前に,人や事業者の活動によって人の生活環境も自然環境も含めて,これらの人の〈環境〉を悪化させるおそれ(環境への負荷)を未然に防止することに変える必要があることが広く認識されることとなった。
そこで1993年に,これまでの公害対策基本法と,自然環境保全法の一部を取り入れた新たな〈環境基本法〉が制定され,日本の環境政策の基本法は,ようやく一本化され,従来の〈公害防止〉と〈自然保護〉の2本建ての体制が改められた。そして〈公害〉は環境保全上の支障の一形態として位置づけられることになった。環境基本法は,国の環境施策の体系を示すものとして〈環境基本計画〉の策定を規定しているが,95年に策定された同計画は,政策の基本を〈循環〉〈共生〉〈参加〉〈国際的取組〉におくものとし,従来の典型公害の防止対策中心の環境政策を改め,大気環境・水環境・土壌環境とこれらの総体としての環境要素の保全と,生物の多様性の保全等を政策の目標とすべきことを明らかにした。そして,従来はあまり取り上げられなかった有害化学物質による環境や生態系への危険の防止や,省資源・省エネルギーにもつながる統合的な廃棄物対策などの新たな政策課題への取組みが始まっており,公害関係法も,広く他の環境領域の法令と連携しつつ,〈環境法〉の一部を構成する法領域にかわりつつある。
なお,1981年には〈環境影響評価法案〉が国会に提出され,公害の発生原因となり,また自然環境保全上の支障を生ずるおそれがある施設の設置等に先立って,当該事業による環境の影響を調査,予測または評価し,必要な対策を講じさせる環境アセスメント制度の導入が図られた。しかし,当時は,この制度の手続として取り入れられた〈住民への説明〉や〈住民意見の聴取〉等が,かえって反対運動を激化され,事業の遅延を招くといった理由で事業者側の反対が強く,この法案は国会で廃案となってしまった。そのかわりに,84年に,政府は〈閣議決定〉による要綱を策定し,これによって行政指導の形で環境影響評価制度が実施されてきた。ただし,これまでの要綱によるアセスメントは〈公害防止〉に重点がおかれる傾向があり,また対象となる事業種や規模,また評価対象となる環境項目も限定されていて,これに対する批判が多かった。このような状態は,環境基本法の制定をうけて,97年に〈環境影響評価法〉が制定されることによってようやく改革の方向が示されることとなった。そして,新たな環境影響評価法は,公害防止に限らず,総体としての環境をとらえたアセスメントを目指すものであり,広く〈環境法〉体系の中に位置づけられるべき法令となっている。
→公害裁判 →公害賠償制度
執筆者:浅野 直人
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「公害」の意味・わかりやすい解説
公害
こうがい
公害の意味・特色
公害の定義
普通、公害とは、企業の生産活動によって、地域住民に、健康や生活環境の損失・侵害をもたらすことをさす。さらに狭義の具体的な項目として、日本は行政上、典型7公害をあげ、「事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によつて、人の健康又は生活環境に係る被害」(公害対策基本法2条)としている。
この公害対策基本法は、1967年(昭和42)に問題の深刻化に対し施行されたものであり、当時、その第1条2項に「……生活環境の保全については、経済の健全な発展との調和が図られるようにするものとする」という、いわゆる調和条項が加えられていた。当時の現実の行政面では、事実上、日本経済の発展が第一で人の健康はむしろ二の次であり、公害もそのごく狭い範囲のものだけを「公害」とみなすといった風潮が強かった。
しかし現実には、同法施行前後に被害は全国的に拡大深刻化するとともに、人間生活の基礎をなす動物や植物とか土壌に被害が出、直接目の前で人命が損なわれなくても、それへの危険な前兆ともいうべき事態が広まってきた。たとえば、東京を例にすれば、第二次世界大戦前は当時の省線(現、JR)山手線の外側に出れば見られたホタルが、昭和30年代には、その生息する限界が西へ退行し、昭和40年代の公害対策基本法公布のころには八王子の西へ行かないと見ることができなくなった。また昭和40年代後半、光化学スモッグで、人体の異常は認められなくとも、関東の周辺県のサトイモ、タバコなどの葉が枯れるといった事態が出ている。
1993年(平成5)11月、公害対策基本法にかわる形で環境基本法が成立、施行された(公害対策基本法は廃止)。同基本法は、従来個別に行われていた公害対策や自然環境保全(自然環境保全法)の枠を超え、人類の将来を見通し国際規模で環境問題に対処しようとするものである。
[柴田徳衛]
公害に共通な特質
①公害に共通な特質の第一は、その被害が金銭で評価しにくい場合が多いことである。近代の経済現象はすべて価格に換算され、生産活動の総和たるGDP(国内総生産)の額が指標となり、また各企業は利潤を最大にするよう生産営業活動をする。ところが、大気・海洋の汚染、気温の変化といった現象は、経済的価格に反映しにくく、その日の株式価格の相場変動にも反映しがたい。一般に価格のないもの、価格に反映しない事象は、価値のないつまらないものと見捨てられがちであるが、公害は反対に重大・深刻ながら価格現象にはすぐ反映しない。さらに、いちばん身近な人体への影響については、もちろん水俣病(みなまたびょう)や四日市喘息(ぜんそく)のような深刻な病気が発生して、金額としても大きな損失をもたらしたものもあるが、それに至らぬ半健康・不快感ともいうべき形の公害の被害が広がりつつある。ごく微量の有害物質に長期にさらされて気分が優れない、騒音でいらいらする、耳には聞こえない超低周波によって圧迫感がし不快な船酔い現象がもたらされる、カラオケなどによる近隣騒音の迷惑等々は、金銭では評価できないが、大きなマイナス現象である。
②第二に、公害の被害には不可逆的損失(元に戻すことのできない損失)、換言すれば補償が不可能な類(たぐい)の損失が多い。水俣病、四日市喘息で生命を奪われた犠牲者たちはその最大の例である。そのほか一般の事象は、原因を除けば結果も消えると考えられるが、公害の場合、たとえばある程度以上の緑を失うと、原因を除去しても、その地域山林の治山治水能力は失われ、生物多様性の減少が進む事態が多い。また周辺の自動車走行や工場排煙による大気汚染が原因で、インドのタージ・マハル宮殿、ギリシアのアテネの神殿、ローマの遺跡などの大理石などが傷み始めている事態は、500年、1000年と受け継がれた人類の芸術品や文化財が、公害被害で取り返しのつかない損失を招いている例である。
③第三には、その影響・被害が、年月が経過するほど複雑・広域化していることである。複合汚染、二次汚染といった現象が広まっている。前者の例として、大気中の窒素酸化物と炭化水素が強い日光にさらされ、有害度の高いオキシダントを発生させて光化学スモッグをおこし、広い範囲の動植物に被害をもたらすことがあげられる。また生態系の営みにおいて、一つの河川汚濁が周辺の植物、さらにそれに依存する動物、流入する湖や湾内の魚類へと連鎖的に公害をもたらす。したがって、公害の被害は、かつては工場煙突の周辺に住む住民、排水口近くの魚類が受けたが、1970年代になってからは光化学スモッグのようにむしろ緑が多く光線の強い周辺地帯や、赤潮における瀬戸内海沿岸のように広範囲に広がるケースが増えている。北欧の酸性雨の場合は、ヨーロッパ大陸の工場の煙がバルト海を越えてスカンジナビア半島一帯を襲い、樹木を枯らし、多数ある湖沼の魚を殺す結果をもたらした。
このように原因と結果が複雑・広範囲になればなるほど、被害に対する責任の所在が不分明となってくる。
④第四として、公害の発生が、生産過程から流通、消費の過程に広がりつつあることである。工場の生産過程において公害の規制を厳格にしても、その大量の製品が運搬され、消費される過程で公害を引き起こす例が増えている。著しい例は空き缶公害である。このほか新しいタイプのごみ(固形廃棄物solid waste)公害が、全国的、全世界的に広がっている。河川、海岸でのペットボトル、発泡スチロールなどプラスチック製品の投棄も多い。廃棄物の焼却によるダイオキシン発生等の問題も広がっている。
⑤第五の特質として、その国際化があげられる。先の第三にあげた特質の広域化と関連し、海外ではドナウ(ダニューブ)川の上流の汚染が、ハンガリーからクロアチア、セルビア、ブルガリア、ルーマニア等と下流の流域諸国に影響を及ぼすといった例が多い。1974年3月には、バルト海沿岸諸国が初の多国間公海汚染防止協定を結んでいる。大陸諸国から離れ、孤島の形にある日本は、そうした隣接国とのかかわりが薄かったが、別の次元での公害の国際化問題に直面させられている。それは多国籍企業活動の発展である。先進国の巨大企業が、国境を越え、労働力の安く豊富に供給される地域、公害規制の緩い国で工場の生産活動をする傾向が強い。本国で厳しい公害の規制をしながら、海外とくに開発途上国で公害を発生させる、いわゆる公害の輸出現象が広まるのである。日本の企業も東南アジアへの進出に伴い、こうした問題をしばしば指摘されよう。
[柴田徳衛]
日本の特質
19世紀以来の技術進歩は著しかったが、その世界的な発展傾向を極端に圧縮し、短期間に達成させたのが日本である。戦後のいわゆる焼け野原から、1955年(昭和30)ごろを転機に、技術革新の道を突進し、世界の最先端技術を入れて、石油コンビナートを建設した。そうして利益の集中・集積を図りながら生産性向上を第一とし、そのため港湾、高速道路、新幹線、空港が急速に建設された。つまり各種公害の発生源が、特定地域に集中して設立されたのである。日本は人口の極度の集中地域に急激な公害を集中的に発生させ、被害は世界に例のない激烈な形で出てきた。
実質人口密度の低い先進国では、生産技術にそれほど公害対策を加味せずにすんだかもしれないが、日本は先進生産技術をそのまま輸入し、自国の実状に即しての公害対策をおろそかにしてきた。こうして水俣病に代表される世界に類のない悲惨な被害を大規模長期間にわたり生じさせてきた。しかも被害者が零細漁民、農村主婦といった、いわゆる低所得者層に集中したこと、また加害の側に人権を守り尊重する配慮が欠けていたところに、日本的公害の悲劇を大きく長期化させた背景がある。ここでは、公害の問題は社会的貧困の問題と深く絡んでいる。
産業革命の口火を切ったイギリスには、個人の権利を妨げ、不快・不便や損害を加える行為としての「ニューサンス」nuisanceという概念があり、とくに社会一般に危険を及ぼす可能性のあるものを公的ニューサンスpublic nuisanceと称し、19世紀後半には法律的にもいろいろ取り上げるようになった。具体的には交通妨害、有害な煤煙(ばいえん)、採光のじゃまなどがこの公的ニューサンスにあたる。しかし日本では、こうした概念に基づいて公害問題を取り上げることは大きく後れていた。
「公害」にあたる英語として、environmental pollution(環境汚染)がよく使われる。しかし、日本の公害は、環境を汚染するのみならず、それを破壊する激烈さをもつし、地盤沈下なども含まれるため、むしろenvironmental disruption(環境破壊)と表現したほうが適切である。さらに戦後の日本的公害の特色に注目すれば、むしろ原語のままkogaiと表現して海外に訴えるのがもっとも適切ともいえよう。なお公害と異なる語に事故、災害などがあるが、日本の現実ではそれらが重なる例が多い。
[柴田徳衛]
公害の歴史
公害の世界における歴史は、さかのぼれば300余年前の17世紀に求められる。ロンドン市民の健康をその死亡原因から求めたジョン・グラントJohn Graunt(1620―1674)の『死亡表に関する自然的および政治的諸観察』Natural and Political Observations Mentioned in a Following Index, and Made upon the Bills of Mortality(1662)は、「多数の人々はロンドンの煤煙(ばいえん)を、不愉快であるだけでなく、その息苦しさのため、まったく堪えられず」とし、健康への悪影響を指摘している。そして19世紀に入り、先の産業革命前後からの下水道の後れによる水質汚濁はコレラなどの伝染病を多発させ、ヨーロッパ諸都市に多くの被害をもたらした。その後、工場からの亜硫酸ガスなどで多くの被害を出した例として、1930年ベルギーのミューズや、1948年アメリカのペンシルベニア州ドノラでのケースがあり、また石炭燃焼と気象条件が重なり2週間で平常の同じ時期より4000人も多い死者を出した1952年末のロンドン・スモッグなどは、公害の歴史上有名な事件となっている。
[柴田徳衛]
戦前日本の歴史
日本においては、明治以後「富国強兵」「殖産興業」のスローガンのもと、いわゆる上からの経済発展を強行しただけに、公害の被害も早くから出た。その原点とよばれるものが、足尾銅山(あしおどうざん)鉱毒事件である。通信・軍用に必要な銅を産する古河(ふるかわ)財閥経営の足尾銅山は、明治10年代から操業を急発展させたが、それに伴って鉱毒が大量に渡良瀬川(わたらせがわ)に流入し、流域のとくに谷中(やなか)村など広範囲の田畑に被害をもたらした。明治30年代、田中正造を中心に農民たちが反対運動を重ねたが、政府はこれを弾圧し、問題の足尾銅山、同製錬所がやっと閉じたのは、1973年、1974年(昭和48、49)であった。このほか別子銅山(べっしどうざん)の公害事件、大阪市の煤煙(空中浄化)問題などが続くが、企業城下町主義――市経済を支える工場の煙がたくさん出るおかげで市民は豊かになれるとか、戦争に勝つためがまんすべしとかいった論理で、公害の規制は大きく後れた。事実こうした公害現象は日本各地にあったが、鉱山の被害にあたる「鉱害」の語はあっても、一般の辞典には昭和30年代末まで「公害」なる用語は登場してこなかった。
[柴田徳衛]
吹き荒れる公害と住民運動
日清(にっしん)・日露そして第一次世界大戦と、戦乱のたびに日本の重化学工業は大きく発展し、各種公害を引き起こしたが、第二次世界大戦中の米軍空襲などにより国土は焦土と化した。新しい生産活動が本格化するのは、朝鮮戦争を経て1956年(昭和31)経済白書の「もはや戦後ではない」の宣言から、1960年末の「所得倍増計画」発表にかけてのことである。
[柴田徳衛]
生産性向上の陰に
1950年代なかばから海浜を大規模に埋め立て(欧米ではこうした例は少ない)、世界最先端の技術を集めた工場群をもっとも能率よく配列し、大型石油タンカーで原油を搬入し、精油、発電、鉄鋼、石油化学などの生産活動を集中一貫して行うコンビナートの建設が続いた。こうしてエネルギー源が石炭から石油に大きく転換し、工場の立地も、石炭などの産出地から、近くに大都市をもつ港湾を建設しうる地が選ばれ、大阪湾の堺泉北(さかいせんぼく)や伊勢湾(いせわん)の四日市、京浜工業地帯、京葉工業地域などに数多くのコンビナートが建設された。日本の金融機関は、そうした重化学工業の設備投資に重点的にその資金を回し、また財政面では関連施設として、いわゆる産業基盤とよばれる鉄道(新幹線)、道路(高速道路)、港湾、工業用水施設などの整備・拡充工事が進められた。
こうして生産性の向上にあらゆる努力が払われたが、その過程で広がる公害への規制は軽視された。生産が本格化し、1956年(昭和31)あたりからの神武(じんむ)景気、1960年前後の岩戸景気といわれる一方で、水銀、カドミウム、亜硫酸ガス、一酸化炭素、粉塵(ふんじん)などが工場周辺の住民を襲うようになった。
[柴田徳衛]
水俣病・四日市喘息
それ以前から公害による発病はあったが、1950年代後半に入り表面化してきたものに水俣病(みなまたびょう)、イタイイタイ病がある。前者はアセトアルデヒド工場の水銀触媒から生成する微量のメチル水銀が不知火海(しらぬいかい)(熊本県・鹿児島県)あるいは阿賀野川(あがのがわ)(新潟県)に排水され、魚を経るなどして(食物連鎖を通じ)人体に吸収され、大規模な被害を生じさせた。後者は富山県神通川(じんづうがわ)中・下流で神岡鉱山から排出されたカドミウムが米に蓄積濃縮され、とくに女性に無数の骨折を生じさせる悲惨な被害をもたらしたもので、法的認定患者は100人を超えた。
先のコンビナートの操業本格化に伴い、周辺住民にもたらされた被害は発作性の呼吸困難であり、代表的なものは「四日市喘息(ぜんそく)」である。そのほか中小工場や事務所、ホテルなどから排出される有害物質が重なり、大都市はいずれも公害の中心となってしまった。その後の経過として、たとえば水俣病については、認定が棄却された多数の未認定患者により訴訟が起こされるなど大きな社会問題となったが、1996年(平成8)までには和解が成立し、かなりの数までの被害者については決着をみた。
[柴田徳衛]
以前にはみられなかった現象の頻発化
地下水汲(く)み上げによる地盤沈下も、越後平野(えちごへいや)、濃尾平野(のうびへいや)、阪神地方に広がった。東京の東部でも工業活動と正比例するスピードで沈下が進み、東の区部面積の20%以上が、満潮時には水面以下となったため、満潮時に地震・台風などが襲えば、大量の犠牲者を生じるおそれが出てきた。
こうして1960年代も後半になると、国民の多くが、不快をはるかに超え、生存への危機感すら抱くに至った。1967年(昭和42)に入り、ようやく公害対策の憲法ともいうべき「公害対策基本法」が施行されたが、先に述べたように「経済発展との調和」条項が置かれ、多くの規制は努力目標的なものにとどまって実効をあげえなかった(同基本法は、1993年環境基本法となった)。
[柴田徳衛]
自治体の努力
国の弱い公害規制に対し、その枠を破ったのは、住民の声を背景とした地方自治体が公害発生源の企業と結んだ協定である。先例は1964年(昭和39)に横浜市が開いたが、有名なのは1968年9月に東京都と東京電力とが結んだ火力発電所の公害防止協定である。その年4月に発足した東京都公害研究所(現、東京都環境科学研究所)が技術・情報の研究を進め、また協定成立に至るまで都が世論に訴えたことなどにより、亜硫酸ガスの排出量の大幅削減、低硫黄(いおう)分石油の使用、都の立入検査を認めること、情報の公表(東京都公害研究所刊行の『数字でみる公害』各年版など)など、当時としては画期的な項目を協定として結ぶことができ、成果をあげた。以後、他企業もこれに倣い、東京に青空が少しずつ戻り始めた。
さらに東京都は1969年7月に公害防止条例を公布し、その前文で、「人間は自然の資源と法則を利用して文明をつくり、自然の与える恩恵をうけてその用に供してきた。しかし、文明は、また、自然を破壊し……公害をもたらした。すなわち、公害は、人間がつくりだした産業と都市にその発生原因が内在し、あきらかに社会的災害である」とし、第一原則として「すべて都民は、健康で安全かつ快適な生活を営む権利を有するのであって、この権利は、公害によってみだりに侵されてはならない」をたてた。産業発展との調和を強く批判したものである。
[柴田徳衛]
大気汚染
自動車排出ガス規制問題
1970年(昭和45)を契機として新しいタイプの公害が広がり始めた。同年7月18日朝、東京、杉並区の立正高等学校で突然発生した光化学スモッグである。それは青天の強い太陽光線による窒素酸化物と炭化水素の複合汚染により有害オキシダントが発生し、グランドで走る生徒四十数人が倒れる被害を生じたものであり、以後、都心よりはむしろ緑の多い近郊地帯に多発した。問題となった窒素酸化物の発生源としては自動車の排出ガスが大きな比重をもつ。生産台数の急増にしたがって世界的に普及率を急増させてきた自動車が、交通事故や騒音・振動だけでなく、大気汚染の大きな要因となってきたのである。
ロサンゼルスなどで早くからこの問題に苦しんできたアメリカは、1970年に大気清浄法Clean Air Actを強化した修正法(通称マスキー法)を通じ、自動車排出ガス規制に目標年次をたて実現に乗り出した。日本も続く1972年にアメリカと同じ規制実現計画を定め、一酸化炭素、炭化水素等については成果があがった。しかし、肝心の窒素酸化物の排出量を1976年までに走行1キロメートルにつき0.25グラム以下に規制するという目標は、1974年春ごろになって日米の大手自動車メーカーがともに、達成は技術的に困難と主張し始めたために実現が阻まれた。
子どもたちにとくに集中する光化学スモッグ被害に苦悩する母親をはじめ、広く住民団体が自動車メーカーに規制実現を求める運動を展開したが、メーカー側の技術論議の前に、運動は進展を阻まれた。住民の健康を憂える東京都をはじめ川崎、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸の七大都市の首長が集まり、1974年8月には技術分野と公害行政の専門家たちによって「七大都市自動車排出ガス規制問題調査団」が結成され、10月、同調査団から規制は技術的に可能との報告書が出された。専門家による科学的解明と、それに裏づけられた自治体、住民団体の運動は事態改善の大きな圧力となった。業界筋は、こうした公害対策の強化は生産コストを高め、自動車販売台数を減らし、失業の増大、不況を招くと反対し、一時は規制が緩和されたが、やがて成果の著しい改善を示した自動車が広く生産されるに至った。この過程で排出ガス規制の技術研究が大きく進み、結果として燃料消費の少ない経済性の高いエンジンが開発された。こうして日本の自動車業界そして財界から「公害をより強く規制する製品を産出してこそ初めて市民は歓迎してその製品の販売は促進され、業界自身の真の発展が図れる」という声が出た。こうした自動車排出ガス、とくに1995年(平成7)に6万余トンもあった窒素酸化物の排出量も大きく減じ、光化学スモッグの被害もほとんど解消した。
[柴田徳衛]
大気汚染公害訴訟
住宅密集地沿いに高速道路が走り、騒音・振動や大気汚染などの被害が広がっている。工場からの有害排出物質と自動車排出ガス、それに騒音・振動の加わる都市型被害を受けた大阪西淀川の公害患者112人が、1978年(昭和53)に国、阪神高速道路公団と企業10社を相手に提訴した(大阪西淀川公害訴訟)。大阪地方裁判所は1991年(平成3)に企業側の責任を認める判決を出し、その後1995年3月に企業側が責任をとる形の和解が成立した。そこでは国と公団は非を認めず和解に応じなかったが、結局1998年7月に至り大阪高等裁判所で、原告と国・公団は和解し、国や公団は排出ガス対策の強化を約束し、原告側は賠償金の請求を放棄した。そして「あおぞら財団」が結成され、公害で荒廃した地域の再生を進めることとなった。
西の大阪に対し、東の京浜コンビナートの中心たる川崎南部では、京浜国道、首都高速道路、産業道路などが集中し、そこに昼夜を分かたずに重量トラックや大型タンクローリーなどが走り大きな騒音を発して、深刻な自動車公害が起こった。そこで1982年3月に原告119名による第一次提訴が、汚染物質排出の日本鋼管、東京電力など企業11社と、道路建設管理主体としての国、首都高速道路公団とを被告として起こされ、以後第二次から第四次の提訴が続いた(川崎公害訴訟)。その後幾多の経緯を経て、1998年8月に横浜地方裁判所川崎支部から判決が出され、環境基準を上回る二酸化窒素や浮遊粒子状物質による大気汚染が現在も続いており、自動車排出ガスのみでも健康被害を起こすとし、国・公団はその責任があるとした。
川崎公害訴訟の原告側は、裁判を機会に研究者による川崎の新しい時代の発展への道、よりよい環境創造の方向を求める川崎環境研究プロジェクト(KEP)の展開を支えることとなった。単にこれまでの苦しい過去にのみかかわらずに、新しい21世紀の地域発展の道を求めようというのである。
[柴田徳衛]
ごみ処理問題
「もはや戦後ではない」と経済白書でいわれた1956年(昭和31)あたりから、洗濯機、冷蔵庫、掃除機の電化製品が家庭に普及し始め、これらが家庭の「三種の神器(じんぎ)」とマスコミにはやされた。さらにたいへん貴重とされたテレビの受信契約数が、1958年に100万を超え、掃除機が白黒テレビにかわった。こうして従来家庭になかった「耐久消費財」が、以後爆発的に各家庭に普及した。以上に述べた耐久消費財は、普及し始めてから10年後の1970年にはすでに日本の全家庭に対し、電気冷蔵庫89.1%、同洗濯機91.4%もの普及率に達していた(経済企画庁「消費動向調査」)。
ここにさらにやっかいな化学製品が登場してきた。プラスチックである。その国内消費量が、10年ごとに倍増以上の勢いで増え続けてきた。
急増する耐久消費財は、相当期間家庭で使用された後、ごみとして廃棄される。新品として1960年前後からすさまじい勢いで各家庭に普及するとともに、10年前後を経た後にそのままごみとして同じくすさまじい勢いで排出されてきたのである。それが具体的な姿で現れたのが、1971年9月末から東京で始まった「江東(こうとう)ごみ戦争」であった。
経済の高度成長は、大量生産・大量消費の経済を招き、それまでの「節約の美徳」の考えを「使い捨て」促進へと変えてしまった。ごみ排出量は加速度的に増加するとともに、プラスチックなどの処理困難物や、冷蔵庫やベッドといったような大型耐久消費財――「粗大ごみ」の廃棄も増加してきた。焼却工場からの残灰、下水処理場の汚泥といった廃棄物処理後の都市系ごみも増えるし、建設廃材や残土の量も都市化が進むほど増大する。他方、都市化が進むほど、住宅の過密化、交通渋滞、用地難が進み、ごみ収集、運搬、処理の各段階で困難が重なっていった。
問題の根本は、経済のあり方が価格のある物の生産を増大させ、それをより多く消費(浪費)させることに重点が置かれ、価格のつかないごみをじゃま物と軽視してきたこと、自分の家からだけ早くごみを持ち去ればよいとした考え方、他人の迷惑や地域全体のことの軽視……など日本経済のあり方自体、民主主義のあり方自身に根ざしていた。
1971年東京の江東区に端を発したごみ処理問題は、全国にたちまち波及した。また焼却処理場の建設、清掃施設の整備などごみ関係の行政も進んだ。しかし家庭ごみに対して産業廃棄物の比重が大きくなり、危険な有害物質がそこに含まれていることが表面化した。1975年の東京・江東方面での六価クロム鉱滓(こうさい)投棄問題を機に、政府も廃棄物処理法を改正して国会に提出した。その後、廃棄物処理法は何度も改正され、排出事業者責任の徹底や国の役割強化などがなされている。
[柴田徳衛]
福島第一原子力発電所事故
原子力公害をめぐる問題について、1974年(昭和49)9月の原子力船「むつ」の放射線漏れ事故や、海外では1979年3月に起こったアメリカ、ペンシルベニア州ゴールズボローにあるスリー・マイル島原発事故Three Mile Island nuclear power plant accident(TMI事故)が注目を集めた。さらに世界を震撼(しんかん)させた大きな事故としては、1986年4月のチェルノブイリ(ウクライナ)原子力発電所の4号炉爆発事故がある。ここで大量の放射性物質が放出され、周辺30キロメートルの住民が退避することとなった。日本国内でも各地の原子力発電所で、規模の差こそあれ放射能汚染水漏れ、火災、故障などの原子力発電所事故が続出している。1999年(平成11)9月には茨城県東海村の核燃料工場が臨界事故を起こした。
2011年(平成23)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震によって引き起こされた福島第一原子力発電所事故は、冒頭に示した公害の定義に照らせば、公害ととらえることができる。その被害の大きさからみると、過去に類のない公害である。電力を生産する過程で事業主は起こりうる重大な事故・災害を「可能性小」だから「想定外」とし、それに必要な施設・装置(つまり必要経費)を省略し、取り返しのつかない大事故につながったと解するほかない。いまの通念としては、「公害」とは工場の煙突から黒い煤煙を排出して周辺に迷惑をかけることといったイメージが強い。マス・メディアの用法としての原子力災害は、公害とよぶのにあまりに巨大なのではないか。そのため、社会的には「公害」とよばずに、原子力発電における大事故と位置づけられてもいる。
これまで原子力発電は、地球温暖化を加速させる二酸化炭素を出さない「地球に優しいエネルギー」とされてきた。しかし「事故は起こりうる」のであり、そうした観点で今後日本として、自然界における再生可能なエネルギーの比重をできるだけ大きくしていくための議論がなされている。原子力発電に今後も依存し続けるのか、それとも太陽光発電、地熱発電、水力発電、風力発電のような自然の再生資源に重心を移すのか、選択を迫られている。ある日突然全部の原子力発電所を閉鎖廃止するのは困難だろうが、ここでは自然エネルギーの活用、具体化の研究・実現の方途を求めたい。もちろんそれらの実現には、休耕・放棄農地活用のための農地法や漁業法における水利権等々の法律的権利調整、つくられた電力の送電線設置やその買取価格の問題などの解決が大事となる。原発事故からの復興において、事故による社会的な損害をどのように補償するか、また今後の安全重視のためのエネルギー対策などについて、国(行政)の果たす役割は重要である。
[柴田徳衛]
世界に広がる公害
水俣病(みなまたびょう)をはじめとした日本における公害の教訓は、一度公害を引き起こすと回復は困難であり、問題の解決に半世紀以上も要すること、複合的な被害であるため完全な解決はありえないこと、などであった。日本は、この失敗の教訓を積極的に世界に発信し、同様の失敗が世界で繰り返されないようにすべきであった。しかしながら、被害者の視点に立った失敗の検証が不十分であったため、日本の教訓や経験が世界の公害防止に十分に役にたったとはいいがたい。
[山下英俊]
世界の水俣病
水俣病に類似した産業公害としては、中国吉林(きつりん/チーリン)省第二松花江(しょうかこう/ソンホワチヤン)の水銀汚染、カナダのオンタリオ州ケノラ地区の水銀汚染などが知られている。前者は、アセトアルデヒド工場からの有機水銀の流出により、吉林省・黒竜江(こくりゅうこう/ヘイロンチヤン)省で軽症水俣病患者が報告されている。後者は、パルプ工場付属のカ性ソーダ工場からの水銀により、先住民の居住地区の水域の魚が汚染され、それを食べた住民から水俣病にみられる神経症状が確認されている。被害を受けたカナダの先住民と日本の水俣病患者との交流が行われた。また、韓国慶尚南道(けいしょうなんどう/キョンサンナムド)温山(おんさん)コンビナートでも、環境汚染による健康被害が報告されている。原因物質が複合的であり、汚染への曝露(ばくろ)も多経路によるため、従来の公害と異なり、その因果関係を証明することが困難となっている。
[山下英俊]
公害輸出
先進国の企業が環境規制の緩い途上国に工場を立地し、そこで公害を引き起こす事例も多い。いわゆる公害輸出である。ボパール事件や、ARE事件などがその代表といえる。前者は、アメリカのユニオン・カーバイド社がインドのボパールに立地した農薬工場から、1984年に猛毒のイソシアン酸メチルが漏洩(ろうえい)し、周辺住民に重大な被害をもたらした事故である。事故直後の死者は2500人、中毒患者は20万人ともいわれている。後者は、三菱(みつびし)化成(現、三菱ケミカル)が出資してマレーシアに設立した合弁企業エイシアン・レア・アース(ARE)社が、1982年(昭和57)からイポー近くのブキメラ村で、スズの廃鉱石からできるモナザイト(モナズ石)という鉱石からレア・アース(希土類元素)の生成・抽出を開始した。その際に発生する廃棄物に放射性物質のトリウムが含まれていた。ARE社は、操業当初、ほとんどなんの対策もとらないまま、工場裏の池に捨てていた。このため、周辺環境を汚染し1980年代後半には住民への健康被害も明らかとなった。地元住民が操業停止を求める裁判を起こし、日本でも「公害輸出が裁かれた初のケース」として報じられた。こうした経緯を受け、1994年(平成6)にARE社は工場の閉鎖を明らかにした。
また、石綿産業においては、1970年前後に石綿の有害性が関係者の間で認識されるようになるのと並行して、日本の石綿企業がアジアに生産拠点を移転させる動きがみられた。たとえば、日本アスベスト(現、ニチアス)は、1971年に韓国の釜山(ふざん/プサン)に現地企業との合弁で第一アスベストを設立した。系列の奈良県の竜田工業から、石綿のなかでも毒性の強い青石綿(クロシドライト)を原料とする製品の製造技術を第一アスベストに供与し、同時に国内での生産を中止したという。現在では、竜田工業および第一アスベストの周辺に居住していた住民の間に、石綿への曝露が原因となって発病する中皮腫の患者が確認されている。また、1990年に、今度は第一アスベストがインドネシアに工場を移転した。2008年(平成20)時点で、インドネシアの工場ではいまだに石綿製品が製造されており、生産設備や環境対策は40年前の日本と大差ない状況であったという。石綿の有害性に関する情報格差と、石綿への曝露から健康被害の顕在化までの時間差が利用され、3世代にわたる公害輸出が行われた事例といえる。
[山下英俊]
軍事環境問題
軍事活動に起因する環境破壊も深刻である。軍事活動は、軍事基地建設、軍事基地での活動、戦争準備(軍事訓練、軍事演習)、実戦という四つの局面で環境破壊をもたらす。軍事基地建設による環境破壊が懸念される事例としては、沖縄の米軍普天間(ふてんま)基地の代替施設建設問題があげられる。移転先とされた沖縄県名護(なご)市辺野古(へのこ)の沖合いのサンゴ礁は絶滅危惧種のジュゴンの餌場(えさば)となっている。基地建設が強行されれば、沖縄のジュゴンを絶滅に導く危険性がある。
軍事基地は、それ自体が特殊な化学工場のようなもので、さまざまな汚染物質が大量に存在している。しかも、汚染物質に関する情報が軍事機密として秘匿される。基地内の汚染の実態が明らかになるのは、米軍基地の返還など特殊事情によることが多い。たとえば、1995年(平成7)に返還された沖縄の恩納(おんな)通信基地では、浄化槽にたまっていた汚泥に水銀、カドミウム、ヒ素、PCB(ポリ塩化ビフェニル)などが高濃度で含まれていた。返還跡地の汚染が住民に健康被害をもたらした事例としては、フィリピンの米軍クラーク空軍基地、スービック海軍基地があげられる。前者は1991年に、後者は1992年に返還され、軍事利用から民間利用への転換が進められている。しかし、地元の環境NGOの調査によると、2002年8月時点で両基地周辺の汚染被害者の総数は2457名に及び、白血病、癌(がん)、腎臓(じんぞう)性疾患、呼吸器障害など多様な症状がみられるという。
軍事演習や実戦においても、航空機騒音による公害(米軍横田基地など)や、劣化ウラン弾の使用による環境汚染と健康被害など、さまざまな被害が指摘されている。
[山下英俊]
大気汚染
大気汚染に関しては、日本など先進国においては、まず工場などの固定発生源の対策が進み、ついで自動車(移動発生源)の対策が進められている。しかし、アジアの大都市においてはいまだに深刻な汚染状況となっているところもある。たとえば、2006年の中国北京(ペキン)の二酸化硫黄(いおう)濃度(年平均値)は52マイクログラム/立方メートルとされるが、これは同時期の東京よりも1桁(けた)大きい(2006年度平均で0.002ppm。二酸化硫黄1ppm=2860マイクログラム/立方メートルで換算すると5.7マイクログラム/立方メートル)。東京の1970年代前半の濃度に匹敵する値である(1973年度の一般環境大気測定局平均で0.020ppm。換算すると57.2マイクログラム/立方メートル)。これは石炭に強く依存したエネルギー供給構造が大きく影響していると考えられる。なお、2000年代なかば以降、長崎、熊本などこれまで光化学オキシダント注意報の発令されたことがなかった地域で注意報が発令されるようになった。この原因として、中国から風に乗って運ばれてくる大気汚染物質の影響が疑われている。
[山下英俊]
廃棄物の越境移動
中国やインドなど、急速な経済成長を続けるアジア地域は、旺盛(おうせい)な資源需要を自国内の供給でまかなうことができず、天然資源だけでなく再生資源(廃棄物)も国外から大量に輸入するようになった。たとえば、2007年の統計では、中国は鉄くずを339万トン、古紙を2256万トン、廃プラスチックを691万トン輸入している。おもな輸入元は、アメリカ、ヨーロッパ、日本である。
こうした再生資源貿易に伴い、一方で、輸入品の不適正処理・不法投棄、廃棄物の不法輸出といった問題が発生している。たとえば、中国広東(カントン)省汕頭(スワトウ)市貴嶼鎮(きしょちん)は、中国における代表的なリサイクル拠点であり、年間100万トンものリサイクルが行われているとされる。しかし、小規模な私営企業や個人による家内工業が中心であるため、技術水準に問題があり、不適正処理が行われ、従業員や住民の健康被害が生じている。汕頭大学医学院教授霍霞(フオシア)の研究グループの調査によると、貴嶼の幼児の血中鉛濃度の上昇、作業従事者のポリ臭化ジフェニルエーテルによる汚染などが明らかになっている。また、廃棄物の不法輸出については、1998年12月に台湾からカンボジアに水銀を含む有害廃棄物が不正輸出された事件や、1999年(平成11)12月に日本からフィリピンに古紙の名目で医療系廃棄物が輸出された事件、2004年(平成16)4月に日本から中国に輸出された廃プラスチックに基準を上回る廃棄物が混入していた事件など、後を絶たない。
従来は、製品の廃棄段階で有害物質を適正に処理するという方針で政策体系がつくられてきた。しかし、国内でも廃棄物の不法投棄の発生を十分に抑えることができていない。加えて、再生資源貿易の進展により海外への流出が増加している。こうした現状を踏まえると、廃棄段階で適正処理を担保する制度の構築は困難であると考えるべきである。むしろ、汚染の原因となる有害物質を、製品の設計・生産段階から排除する方向へ、政策体系を移行してゆくべきであると考えられる。規制対象物質を含んだ製品の域内での販売を禁止したEU(ヨーロッパ連合)のRoHS(ローズ)指令などが、その具体例といえる。
[山下英俊]
『柴田徳衛著『日本の清掃問題』(1961・東京大学出版会)』▽『都留重人編『現代資本主義と公害』(1968・岩波書店)』▽『東京都公害研究所編・刊『公害と東京都』(1970)』▽『東京都公害研究所編・刊『数字でみる公害』(1971~1987)』▽『東京都環境科学研究所編・刊『数字でみる環境』(『数字でみる公害』を改題、1988~1994)』▽『K・W・カップ著、柴田徳衛・鈴木正俊訳『環境破壊と社会的費用』(1975・岩波書店)』▽『清水誠編『戒能通孝著作集8 公害』(1977・日本評論社)』▽『柴田徳衛著『日本の都市政策』(1981・有斐閣)』▽『田尻宗昭著『羅針盤のない歩み』(1985・東研出版)』▽『日本環境会議・「アジア環境白書」編集委員会編『アジア環境白書』(1997、2000、2003、2006、2010・東洋経済新報社)』▽『原田正純著『いのちの旅――「水俣学」への軌跡』(2002・東京新聞出版局)』▽『村山武彦著「アジアにおける公害輸出の事例――3世代にわたるアスベスト工場の移転」(『環境と公害』38巻4号所収・2009・岩波書店)』▽『庄司光・宮本憲一著『恐るべき公害』(岩波新書)』▽『庄司光・宮本憲一著『日本の公害』(岩波新書)』▽『原田正純著『水俣病』(岩波新書)』▽『田尻宗昭著『四日市・死の海と闘う』(岩波新書)』
百科事典マイペディア 「公害」の意味・わかりやすい解説
公害【こうがい】
→関連項目足尾鉱毒事件|アース・デー|煙害|環境衛生|環境科学|環境庁|環境破壊|鉱害|公害裁判|公害紛争処理法|公害防止事業団|公害防止条例|工業地域|工場排水|高度経済成長|国家環境政策法|自然改造|社会的費用|所得倍増政策|振動公害|スモッグ|地下水汚染|ニューサンス|バイオ・レメディエーション|水汚染
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公害」の意味・わかりやすい解説
公害
こうがい
public nuisance; environmental pollution
日本では足尾銅山の鉱毒が渡良瀬川に流出した足尾鉱毒事件にみられるように,明治時代から産業活動に伴う環境破壊が問題になっていた。第2次世界大戦以後,1960年代の高度経済成長期に入ると,産業の興隆のみに全力を傾けて人の生活環境を保全することを怠ったために公害が全国的に広まり,1967年には公害対策基本法 (昭和 42年法律 132号) が制定された。この法律では,公害を放射性物質による汚染,薬事や食品添加物など他の法令で対処すべきものを除外し,典型7公害に限定した。その上で,相当範囲にわたって人の健康または生活環境にかかわる被害が発生すること,生活環境の範囲は人の生活に密接な関係のあるもの,と限定的に解している。しかし一般には,日照阻害,壁面反射や深夜照明などの光害,電波障害,ビル風害,ペットの鳴き声・ピアノ・クーラーなどの生活騒音による迷惑,空地へのゴミの投棄,食品添加物,ポルノグラフィー,ギャンブルなど,社会環境で公衆になんらかの迷惑ないし撹乱を与える行為が広く含まれるものと考えられる。さらに現在では,大都市圏でヒート・アイランド現象のような典型7公害以外の大気現象が日常的にみられるようになっている。
当初の公害対策基本法では,生活環境の保全を「経済の発展と調和がはかられるようにするものとする」とした,いわゆる経済との調和条項が規定されていたが,これには強い批判があった。引続き,四日市喘息,水俣病,イタイイタイ病,スモン薬害,カネミ油症事件,川崎公害事件など数多くの悲惨な事件が起ったため被害者の救済や公害反対運動が全国的に広まった。その結果,1970年末のいわゆる公害国会で,公害対策基本法の改正により調和条項は削除され,公害を環境問題として認識する方向が明示された。 1980年代の後半になると,地球レベルでの環境保全の必要性が強く認識されるようになり,1992年には環境と開発に関する国連会議 (地球サミット) がブラジルで開催された。それを受けて日本でも 93年に環境基本法 (平成5年法律 91号) が制定された。しかし同法には,環境権,環境影響評価 (環境アセスメント) ,汚染者負担の原則,公害被害者救済制度の制度化なども盛込まれておらず,基本的には旧公害対策基本法の内容の踏襲の域を出ていない。最も問題なのは,地球サミットでもうたわれた「持続可能な発展 (ないし開発) 」という言葉を,日本では開発を持続することをにおわせる「持続的発展」という言葉に置き換えたことである。これは,ある意味では 1970年の公害対策基本法の改正によって削除された経済との調和条項の復活といえなくもない。
ともあれ両基本法が公害防止に実効性をもつようにするためには,(1) 環境政策を最優先することをうたった規定,(2) 地球規模の環境破壊ばかりに目を奪われずに,国内ですでに起っている公害対策を重視する視点を盛込むこと,(3) 原因と責任の徹底的追及と汚染者負担の原則,(4) 住民参加と情報公開の原則,(5) 環境影響評価の法制化,などを明記することが不可欠といわれる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
普及版 字通 「公害」の読み・字形・画数・意味
【公害】こうがい
 利
利 るも、之れを興すこと或(あ)る
るも、之れを興すこと或(あ)る (な)く、
(な)く、

 るも、之れを除くこと或る無し。
るも、之れを除くこと或る無し。字通「公」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「公害」の解説
公害
こうがい
公害がクローズアップされた時期は三つある。第一は産業革命の時期で,足尾銅山・別子銅山の鉱毒事件,大阪市の煤煙問題などが主要なもの。第二は,第一次世界大戦中〜戦後で,資源開発に伴うダム災害など,この時期は重化学工業を中心に独占が進み,同時に都市問題が続出した。第三は1960年代以降の高度成長の時期で,一・二の時期に比べて次の三つの特徴がある。その一つは公害の発生回数が圧倒的に多くなったこと。二つには,技術革新や都市化の進展によって現れ方が複雑となり,種類がふえたこと。たとえば目に見える黒煙や煤煙から亜硫酸ガスや悪臭などの被害にかわり,交通マヒ・清掃マヒなどの新種が登場した。三つめは,公害の影響する範囲が広域に及んでいること。すなわち工場公害から都市公害へ,さらに全国的に拡大している。こうして公害は人体への影響だけでなく,自然を破壊するものとして大きな問題となっている。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「公害」の解説
公害(こうがい)
環境破壊ともいう。15世紀以来の西洋世界の拡大は,香辛料,森林資源(船材,製鉄用燃料),農地を求めた地球環境問題の始まりであった。その後19世紀に産業革命をへて,高度工業化社会となった先進諸国は,資源・エネルギー大量消費型の生産・生活様式をとり,20世紀の地球温暖化に拍車をかけた。公害はオゾンホール,酸性雨,砂漠化・土壌汚染(ダイオキシン,ゴミ問題),海洋汚染,大気汚染など生活や生命に直結する。1956年のロンドン大スモッグでは,約4000人の死者が出た。農薬問題を警告したR.カーソン『沈黙の春』(62年)や,72年国連人間環境会議は,世界への問題提起となった。石油危機,86年チェルノブイリ原発事故後の,92年国連環境開発会議(地球サミット)では,アジェンダ21など重要議案が採択された。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
化学辞典 第2版 「公害」の解説
公害
コウガイ
public nuisance
人間の社会活動に伴う生活環境の破壊,およびこれによって生じる健康被害をいう.法律的には,公害対策基本法により次のように具体的,限定的に定義されている.すなわち,事業活動,そのほかの人の活動に伴って生じる相当広範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁,土壌の汚染,騒音,振動,地盤沈下,および悪臭によって人の健康または生活環境にかかわる被害が生じることをいう.地震,暴風のような自然災害はもちろん公害ではない.職場における労働災害,自動車事故,薬害,添加物による食品害などは公害類似現象で,公害としばしば混同されるが,上記の定義により公害とは区別される.
出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報
栄養・生化学辞典 「公害」の解説
公害
世界大百科事典(旧版)内の公害の言及
【化学工業】より
…そこで今後については,第1に販売の集約化や過剰設備の処理などで過当競争を是正すること,第2に設備近代化・合理化によるコスト削減,第3に高付加価値製品のシェアを高めること,第4に原料の安い海外へ進出すること,などが必要とされている。【富沢 このみ】
【化学工業の公害】
化学工業による公害には,生産過程で生じる廃物によるものと,生産された化学物質が使用されて生じるものとがある。前者は原理的には他産業の公害と同じであるが,使用される原料や中間製品の危険性が高い場合があるだけでなく,副反応などによりきわめて危険性の高い物質が放出されることがあり,水俣病はその典型である。…
【火力発電】より
…このほか,地域暖冷房または工場などで,総合熱経済の向上を図るため,動力と発電設備を組み合わせた熱併給発電も行われている。内燃力発電【宮原 茂悦】
[火力発電所の公害]
火力発電所は大量の燃料を燃焼させるため,大気汚染源の主要なものの一つであり,多くの事件を引き起こしてきた。歴史的にみると,すでに1890年ごろまでに日本で最初の電力会社である東京電灯会社と大阪電灯会社の火力発電所が市民の苦情を受けており,ことに煙の都とまで呼ばれるようになった大阪では第2次大戦前を通じて問題が絶えなかった。…
【鉱業】より
…鉱業の費用は主として鉱山の開発費と輸送費であり,これらは製品価格が変動してもあまり変わらないからである。(6)鉱業の社会的な問題点は,採鉱,選鉱,製錬に伴い,人体や植物に有害な物質が流出する場合が多く,公害問題を引き起こすおそれがあることである。このため近隣に人家などがあるところでは鉱業を行うのはむずかしい。…
【コンビナート】より
…しかしその効率性はまた多くの欠陥を伴っていた。日本の公害問題はコンビナートの成長ときりはなせない。せまい地域にエネルギー多消費の巨大工場が集中することは大気汚染,廃棄物問題を深刻にする。…
【住民運動】より
…また,一部の薬品や食品添加物による健康障害も顕在化するにいたった。1960年代になって住民はこれらの公害に対して連帯して抗議するようになった。公害発生企業に対する直接抗議行動,開発計画の再検討や差止めを要求する陳情や訴訟,加害企業の責任を明らかにして正当な補償を求める交渉や裁判などを行った。…
【日本資本主義】より
…ただ,財政規模は小さかったとはいえ,財政支出の内容は,財政投融資の対象とともに産業基盤向けの比重が高く,その反面福祉,民生向けの比重は低かった。
[公害の発生]
高度成長は国際水準の重化学工業を確立させ,所得水準の上昇と完全雇用を実現したが,その裏面で深刻な社会問題を発生させた。とくに〈所得倍増計画〉による1960年代の工業立地が,太平洋,瀬戸内の臨海地帯に集中したことから,いわゆる太平洋ベルト地帯を中心に空気・水質の汚濁,悪臭,騒音・震動等の公害が頻発した。…
※「公害」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...