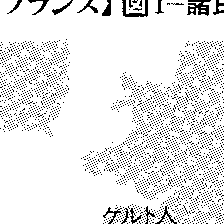翻訳|France
精選版 日本国語大辞典 「フランス」の意味・読み・例文・類語
フランス
日本大百科全書(ニッポニカ) 「フランス」の意味・わかりやすい解説
フランス(国)
ふらんす
France
ヨーロッパ大陸西部にある共和国。正称はフランス共和国République Française。面積59万9090平方キロメートル、人口6018万5831(1999年センサス)、6281万8000(2005年推計)、そのうち本土とコルシカ島のみの人口は5851万8395(1999年センサス、2005年国連年央推計6049万6000)。首都はパリ。
[日高達太郎]
総論
国土
国土はほぼ六角形で、東西および南北約1000キロメートルの間に広がる。東はライン川、ジュラ山脈とアルプス、西は北海、イギリス海峡と大西洋、南はピレネー山脈によりそれぞれ限られ、北側は明瞭(めいりょう)な自然境界なしにドイツ、ルクセンブルク、ベルギーに接する。これら本土とコルシカ島のほかに、以下の海外県や海外自治体などをもつ。
〔1〕四つの海外県がある。(1)グアドループ(カリブ海東部)、(2)マルティニーク島(カリブ海東部)、(3)フランス領ギアナ(南アメリカ北東岸)、(4)レユニオン島(インド洋西部)。合計の面積9万0874平方キロメートル、人口166万7436(1999)、180万7000(2005)。
〔2〕四つの海外自治体がある。(1)サン・ピエール・エ・ミクロン(大西洋ニューファンドランド沿岸の島嶼(とうしょ))、(2)マホレ(マヨット)島(マダガスカル島北西のコモロ諸島南東部)、(3)フランス領ポリネシア(南東太平洋タヒチなど)、(4)ウォリス・フトゥナ諸島(中部太平洋)。合計面積は4758平方キロメートル、人口はサン・ピエール・エ・ミクロンが6316(1999)、マホレが16万0265(2002)、フランス領ポリネシアが24万5516(2002)、ウォリス・フトゥナ諸島が1万4944(2003)。
〔3〕特別自治体のニュー・カレドニア(南西太平洋)は、面積1万8575平方キロメートル、人口は19万6836(1996)、23万1000(2004)。
〔4〕フランス領南極地方がある。南極周辺の諸島(インド洋)、南極のアデリー・ランドは1959年の南極条約で領土権主張を凍結し、管轄しているのみ。定住者はない。
なお、近年、海外領土の地位の見直しが進められている。
[日高達太郎]
歴史的特質
国名は「フランク人の国」を意味する。このフランク人は、5世紀末の西ローマ帝国崩壊に伴って現在のフランスの地に侵入した多くの民族のうちもっとも有力であり、パリを中心とする地域に王国を建設した。「ヘクサゴン(六角形)」l'Hexagoneとよばれるフランス本土は中緯度にあって海洋性気候が卓越し、「うまし国フランス」La Douce Franceといわれるように温和な風土で、先史時代以来きわめて多くの民族がこの地に流れ込み、そこにとどまる終着地的な存在であった。同時に、ローヌ川とライン川の谷を通じて地中海文明の北上があり、アキテーヌ盆地とパリ盆地を通じてフランドルとイギリスに至る東西方向の交流が可能になるなど、どの時代にも諸文化・産物の交差点にあたっていた。
フランク人のクロービスが建設した王国はカール1世の帝国にまで発展(800年)した。この国は以後他民族との大規模な融合を経験することはないが、多少とも独立していた周囲の諸地域をしだいに統合し、15世紀末には現在のフランスに近い領域を占める国家を形成した。異民族とその文化の吸収同化はこの国の伝統であり、現在に至るまでヨーロッパのみならず世界各地からの移民を受け入れ続けてきた。このことは、16世紀すでに他の国々に先駆けて強大な統一国家となっていたことと並んで、フランスの社会・文化の根底をなす特色である。
[日高達太郎]
国旗・国歌
フランス大革命の後に制定された国旗は、竿(さお)の側からそれぞれ正義、自由、博愛を表す青、白、赤に三分されているが、三色旗のうちではもっとも有名なものとなった。国歌は1795年制定の『ラ・マルセイエーズ』で、三色旗とともにフランス民族の国家意識と自由獲得の意欲の象徴となっている。
[日高達太郎]
自然
地質
フランスには北ヨーロッパにみられるような楯状地(たてじょうち)こそないが、カレドニア褶曲(しゅうきょく)運動を受けた先カンブリア時代の地質と古生代初期の変成岩層が、西部のアルモリカン山地に知られている。シルル紀の堆積物(たいせきぶつ)は、アルモリカン山地とモルバン山地に硬砂岩、スレート、赤鉄鉱層などとして現れる。デボン紀に形成された地向斜の厚い層は、石炭紀末のヘルシニア(アルモリカン、バリスカン、アパラチア)褶曲を受けている。その進行中あるいは前後に、花崗岩(かこうがん)の貫入による変成作用を伴っており、地質分布は複雑である。その褶曲軸には、西部の北西―南東に延びるアルモリカン方向と、東部(中央群山(マッシフ・サントラル)とボージュ山脈)の南西―北東に延びるバリスカン方向の二つがあり、アイルランド南部からウラル山脈までW字型にヨーロッパ全域に及んだ大きな褶曲運動に属している。ペルム紀(二畳紀)の褶曲による炭層の堆積や火山活動(ボージュ山脈、マッシフ・サントラル、エステレル山地)などを交えながら、この大山地の準平原化が進んだ。三畳紀の中ごろには海進が始まり、ボージュ山脈は海没、他の山地間では潟(かた)や盆地に新しい堆積層が形成され(ロレーヌ地方の岩塩など)、旧地形は化石化する。緩慢な侵食と堆積、および海進を主とする中生代には、こうして南部と南東部にきわめて厚い地向斜が形成され、第三紀のアルプス大褶曲運動を迎える。
ピレネー山脈に始まり、アルプス、ジュラ山脈、コルシカ島の山系を形成した地殻運動は、侵食の進んでいた古い山塊、その周囲の盆地をも距離に応じて多少とも変形させた。マッシフ・サントラルは数ブロックに砕かれ、アルモリカン山地もゆがみ、ボージュ山脈は傾動、東側は陥没してアルザス地溝帯となり、シュワルツワルト山地と分かれた。パリ盆地中心部、ロアール川下流地域、アキテーヌ盆地などは沈下する。マッシフ・サントラルでは、鮮新世の溶岩台地(オーブラック台地)や大火山体(モン・ドール山地、カンタル山地)の形成から第四紀(ピュイ火山)まで続く火山活動も始まる。古生代の褶曲を受けた古い地域の最南部と、新しい大造山地域の最北部が、フランスにおいて他所にもまして緊密に影響しあったのである。こうして若返った地質構造を骨格として、温暖な第三紀、寒冷期を挟む第四紀、それぞれの侵食・堆積作用を経て現在の起伏が生まれた。
[日高達太郎]
地形
東西の境界
地質構造に由来する地形特性に従って2地域に分かれる。その境界は、マッシフ・サントラルの南西にあるモンターニュ・ノアール山地(最高点1211メートル)から東縁のセベンヌ山地(最高点1699メートル、ビバレ山地南部を含めれば1754メートル)、ビバレ山地、ラングル高地(最高点516メートル)を経てボージュ山脈までS字型に走る線である。この境界は大西洋側と地中海側両水系の分水嶺(ぶんすいれい)ともなっている。西側の広い地域は、古い平坦(へいたん)面を多く残しているヘルシニア諸山塊、大盆地、小丘陵地、谷に刻まれた低台地などによって占められ、マッシフ・サントラルとボージュ山脈の山間地帯を除いては交通障害もない。モーゼル川、セーヌ川、ロアール川、ドルドーニュ川、ガロンヌ川などの諸河川が、多くの支流の水を集めて各低地を潤している。これに対し、境界線の南側と東側は、若い山地とその前衛地帯および構造谷(アルザス地方、ソーヌ川流域の低地帯)に占められ、起伏ははるかに大きく、水系は地質構造を反映する明瞭(めいりょう)なパターンを示す場合が多い。
[日高達太郎]
アルプスとピレネー
アルプスはヨーロッパの最高峰モンブラン(4808メートル)を含み、ピレネー山脈中央部では180キロメートルの間に3000メートル以上の高峰が続いていて、尖峰(せんぽう)、やせ尾根、ときにはドーム状の大山頂を示し、斜面と谷間には氷河地形がみられる。ピレネー山脈は、海岸に臨む東西両端を除いては通過困難な障壁を形成しているが、アルプスでは古来、峠道が発達し、山間の連絡は比較的容易である。西側の石灰岩質のアルプス前地にはいくつかの横谷があり、東側の山脈本体との間の低地(コンブ・ド・サボア、グレジボダン、トリエーブの各地方)に通じている。ここからは氷食を受けた広いU字谷(イゼール川上流タランテーズ、アルク川上流モーリエンヌ)が深く山中に食い込んでいて、山間地区(バノワーズ山群、最高点3852メートル)への通路となる。低高度のジュラ山脈では、規則正しく並行した稜線(りょうせん)の間を谷(バルval)または陥没低地(コンブcombe)が走り、河流は横谷を通じて隣の谷に流れ込むため大きく迂回(うかい)する一方、石灰岩層中に地下流を形成し、西方山麓(さんろく)に至って湧出(ゆうしゅつ)する(アン川、ドゥー川)。
[日高達太郎]
平野部
堆積盆地、山地前面の平野と山間の地溝帯、フランドリアン期の海岸平野など3種に分かれる。
〔1〕堆積盆地 アキテーヌ盆地と国土の25%を占めるパリ盆地は、中生代と第三紀の堆積層からなり、周囲には多少ともケスタ地形が発達している。両盆地とも粘土層または砂層に覆われ、主として森林地区として残った部分を除けば、台地、谷間などが古くから人間活動の舞台となってきた。ケスタ背後の第三紀石灰岩層の現れる乾燥した「シャンパーニュ」champagne(白亜質平野)とよばれる地域には、レス(黄土)に覆われた豊かな農業地帯と、レス層がなく森林・荒地が多い地帯とがある。ケスタ急崖(きゅうがい)の足下、古い山塊の麓(ふもと)などには、ときに沼も多い(ロレーヌ地方)湿潤な帯状の平野、台地がある。アキテーヌ盆地のケスタは不明瞭でシャンパーニュは少ないが(シャラント、サントンジュ、ペリゴールの各地方)、小起伏を示す石灰質砂岩地域に土壌が重く耕作に困難を伴う地区(アルマニャック地方、トゥールーズ市周辺)が多い。地溝帯内の堆積物は、周囲の地質構造や地質と密接に関係し、変化に富み、分布も複雑である。
〔2〕山地前面の平野 背後山地の隆起の条件、氷河、周氷河侵食などの諸要素が加わって、地形、堆積層の構成ともにきわめて多様となる(ローヌ川の谷、ソローニュ地方、ランヌムザン地方)。
〔3〕海岸平野 洪積世(更新世)の海進による海岸平野は、北海(フランドル)、イギリス海峡(マルカンテール地方、セーヌ川河口、ドル沼沢地)、大西洋(ブルターニュ、ポアチエ、シャラント、ボルドー各地方の沼沢地)などに面してポルダー地区を形成している。堤防と排水路を完備した放牧地(プレ・サレ)、耕作地、塩田あるいは貝・甲殻類養殖水域などを前面に有し、背後には泥炭質の湿地が残っていることも多く、特殊な景観を示す。ローヌ川の河口からピレネー山脈東麓まで延びる潟の連なる海岸平野は内陸性のもので、第四紀の泥灰岩質および砂質の堆積物により形成された。
[日高達太郎]
海岸線
フランスの海岸線延長は3200キロメートルで、背後の地形に応じて多様な景観を示すが、その現形は第四紀の大規模な海面昇降の跡をとどめ、沈水海岸の地形が大部分を占める。アルプスとプロバンス地方の南岸、コルシカ島西岸、ピレネー山脈東麓など山地に接する部分では、急崖の迫る出入りの多い海岸線、岬の延長上の島嶼(とうしょ)、狭い入り江、じょうご型の湾入などが交錯して美景を呈する。アルモリカン山地の沿岸も同様で、海食崖、硬砂岩の岬とその沖合いの島々、数多くの沈水した旧河口が形成する深い入り江に切られた低地部の浜辺などがみられる。堆積平野前面の海岸もその緩やかな起伏に応じて、凸部(ブローニュ、コー、シャラント各地方沖合いの島々)と凹部(セーヌ河口、ジロンド河口)を形成している。そして、潮流が砂を運び砂丘の発達する部分では、その前面に、滑らかな海岸線に沿って広い砂浜が続いている(ランド地方、ラングドック地方)。
[日高達太郎]
気候と植生
地中海沿岸部とアキテーヌ盆地の一部を除いて温帯気候に属し、西に開いた地形配置は海洋性低気圧の内部侵入を容易にし、年間を通じて降雨があり、夏冬の気温較差も小さい。典型的な海洋性気候は、西の卓越風にさらされているブルターニュ地方やノルマンディー地方にみられ、年中、とくに秋に霧雨が多く(ブレスト市、年降水量1123ミリメートル、降雨日数201日)、海洋の緩衝効果が明らかで気温の年較差は小さい(同市、10.7℃、霜日数17日)。ダンケルク市の気温年較差は12℃にとどまるが、冬の気温は4℃、霜日数38日で緯度の影響を示す。緯度は少し下がっても北海から遠ざかるリール市では、年較差14.7℃、冬季温度2.5℃、霜日数61日となる。南側のアキテーヌ盆地ではすでに西風とオータンとよばれる南東風が交互に吹き、春と秋に雨が多く、高温の夏はほとんど地中海岸を思わせ、トウモロコシの大農もみられる。植生もブルターニュのブナとカシの林相に対し、カシワとマツが多くなる。
東部では亜大陸性の気候が現れ、冬には零下25℃以下、夏には35℃以上を示すこともあり、山地を除いて雨量は減じ、夏に集中する(ストラスブール市、年降水量607ミリメートル、最大降雨月8月、80ミリメートル)。ボージュ山脈の稜線(りょうせん)付近の牧草地帯の下方に広がるモミの大森林をはじめ、ムーズ川、モーゼル川のケスタ斜面、ラングル高地などは、ブナ、ハリモミ、アカマツの美林に覆われている。一方、湿潤な西風から守られている低地では、夏の高温に助けられて地中海性植物もみられる。これら東西両地域の間は、海洋性気候から亜大陸性気候への漸移帯を構成する。
地中海性気候の特徴は、夏の高温と乾燥、低温期とくに秋に多い集中豪雨、乾燥し寒冷な強い北風(ローヌ川の谷のミストラル、ルシヨン地方のトラモンタン)などである。その直接の影響範囲は、背後の山地、ローヌ川の峡谷部などに阻まれて狭く、オリーブの生育限界にほぼ一致する。ほかにウバメガシ、マツ、イトスギが、石灰岩地帯の小低木と芳香性草本のみが生育するガリッグgarrigue(石灰質荒地)や、コルシカ島で有名な結晶岩地帯のマキmaquis(密生低木林)などとともに、南フランスに独特の景観を与えている。
他方、山地では高度が大きくなれば冬の気温が下がるのみならず、降雨をもたらす西風を受ける斜面とその陰となる部分との差が大きい(アルプス前地、ジュラ地方、ボージュ地方、マッシフ・サントラルとピレネー山脈の西部)。陥没した構造谷では海洋からの影響が減少し、雪・霜の多い厳冬や嵐(あらし)も多い高温の夏など大陸的な性格が現れる(アルザス地方、ソーヌ川の谷、リマーニュ地方)。山地の植生分布は、ピレネー山脈ではブナ、マツなどを主として比較的単純であるが、自然要素のより多様なマッシフ・サントラルのカシワ、ブナ、クリ、アルプスの各種のマツ、カシ、ブナの森林の水平・垂直方向の分布はきわめて複雑である。
[日高達太郎]
地誌
地域区分
おのおのの自然条件と歴史を背景とした小地区(ペイpays)と、その必然的あるいは人為的な地域的集合である州(プロバンスprovince)の概念は、現在なおフランス人の心のなかに生きている。これが強力なパリ中心の体制によって結ばれているのがフランスの地誌的特色である。19世紀に工業化が始まり、各地に工業都市が発展した際も、その本部はパリに集まり、経済の分野でも首都としての地位は強化された。現在なお人口100万以上の都市がパリだけ(大都市圏人口ではマルセイユとリヨンとリールも100万を超える)であることは意味深い。かくして今日、マッシフ・サントラル、南西地方などは西ヨーロッパ大工業地帯に遠く、投資削減、人口老齢化などに悩んでいる。この事実を考慮しつつ、フランスを三大地域に分けることができる。(1)アルモリカン山地からピレネー山脈までを含む西部・大西洋地域(西フランス)、(2)アルザス地方から地中海に至るライン川・ローヌ川の廊下地帯の両側地区、東部地域(東フランス)、(3)パリ盆地、ロレーヌ地方、フランドル地方を抱擁する北部平野地域(北フランス)の3地域である。
[日高達太郎]
西フランス
湿潤な海洋性気候に恵まれる伝統的な農業地域で、ブルターニュ地方がその性格を代表している。ブルターニュ半島南岸にフランス第二の漁港ロリアンがある。この地域は、缶詰工業があるとはいえ、沿岸では半漁・半農、内部では中心都市レンヌの盆地とシャトーランの台地・平野に単作の豊かな農業があるほかは、立ち木に囲まれた農家、牧場、畑など、ボカージュbocage(農牧地を取り囲む帯状の樹林)の景観がみられる多角的農業が行われる。ロアール川の河口はナントの古い造船と食品工業を基礎に、造船のサン・ナゼール、精油のドンジュを含む工業地帯に発展したが、ほかには海軍工廠(こうしょう)のあったブレストに第二次世界大戦後誘致された軽工業、レンヌに自動車工業があるにとどまる。
ロアール川下流の南に広がるバンデー地方とシャラント地方は、それぞれアルモリカン山地とマッシフ・サントラルの前面台地・平野にあたり、農業地帯を形成する。沿岸のロシュフォール、ラ・ロシェル両港をはじめとする諸漁港の重要性は減じたが、潟地区の貝と甲殻類の養殖が盛んである。農業地帯の酪農はノルマンディー地方に劣らず、ショレの繊維工業(ハンカチーフ)と靴製造は全国的に有名である。シャラント地方のブドウ栽培はコニャック地方のブランデーにより世界に知られる。マッシフ・サントラル西縁のリムーザン台地では牧畜が発達し、台地周辺の谷間には地方小炭田と水力発電により発展した小工業都市がある(リモージュ、モンリュソン、チュール)。アキテーヌ盆地には、ジロンド川河口沿岸のブドウ(ボルドー・ワイン)や段丘上の野菜栽培は例外として、伝統的な多角的農業の形態がもっとも明らかに残っている。マッシフ・サントラル南西面の厚い石灰岩層に覆われたケルシー地方は、多くの先史遺跡(クロマニョン、ラ・マドレーヌ)が古くからの人間活動を示しており、18世紀までは豊かな農業地帯でもあったが、耕作の困難、干魃(かんばつ)などによって放棄され、現在は荒地でヒツジの放牧が行われる。その逆が北側のペリゴール地方で、むしろ軟らかい砂岩地帯が多く、昔のクリの実を主食とした貧しい地区は、中世の僧院による開発も手伝って豊かな農業地帯となった。アキテーヌ盆地の工業は、航空機のトゥールーズ、天然ガス開発のポー、港湾活動と精油のボルドーに集中している。
[日高達太郎]
東フランス
西ヨーロッパの南北方向の幹線に沿う地域である。地中海沿岸の観光は特異な経済的地位を占めているが、背後の平野・台地には、ブドウ、花卉(かき)、灌漑(かんがい)による果物・野菜などを主とする商品作物の農業がある。数多い小都市がおのおのの影響圏をもって発達してきたのも地中海地域の特色であり、マルセイユやローヌ川河口の大工業地帯が南フランス全体の経済活動の中心となったのは第二次世界大戦後のことである。コルシカ島は、山中のヒツジの放牧ととくに東部海岸平野のブドウ栽培によりプロバンス地方に比較でき、1960年代以降は観光も重要性を増した。
アルプス山脈では、北部の広い谷が交通路(グルノーブル、アヌシー、シャンベリ)と耕地として、また山頂部が放牧場(アルプ)として利用され、夏冬の観光も発展した。水力の活用による山間地の工業も古くからあり、その地方中心は残った(グルノーブル)。これに対し山脈南部はコンパクトな地形と乾燥した気候でヒツジの放牧に限られ、夏冬の観光も振るわない。ジュラ山脈の森林は主として公共財産であり、歴史の古い協同組合(フルイティエール)による大型チーズの生産など酪農が活動の中心である。山間の手工業も古く、北部の時計、中部のろくろ細工など各地区の伝統を生かしている(サン・クロードのパイプ、モレーズの眼鏡レンズ、モルトーの柱時計など)。山麓(さんろく)の交通要衝ブザンソンのみが、主要な地方都市として発展した。美林で有名なボージュ山脈は、東にアルザス地方、西にロレーヌ地方の斜面を控えている。アルザス平原は古くからホップ、タバコ、ブドウ栽培など豊かな農業地帯であったが、19世紀の工業化は全国に先駆けた。ミュルーズの繊維工業はボージュ山脈東斜面の山間に及び、同時に各地に小工業の中心となる地区が発生した。コルマルの製紙、アグノーの化学工業、山麓地帯の軽金属工業は時代順応も巧みに発展を続けた。カリ塩とライン川の水力発電のみを資源とするアルザス地方では、ライン川の水運もきわめて重要である。ライン川の谷は、ソーヌ川・ローヌ川の谷とはジュラ山脈とボージュ山脈との間の狭い帯状の低地により結ばれている。この低地帯の中心都市ベルフォールと南部のモンベリアルなどは工業化に成功している。
ソーヌ川の谷の西側斜面は有名なブルゴーニュ・ワインの産地で、斜面を切り込む谷はパリ盆地への通路(ブルゴーニュ運河)である。東岸では多角的な農業が行われ、人工沼の淡水魚養殖(ドンブ地方)、酪農(ブレス地方)など比較的貧しい土地の開発に多くの努力が払われた。ソーヌ川はリヨンでローヌ川に合流し、アルプス前地とマッシフ・サントラルに挟まれたいくつかの「関門」と広い平野に向かう。バランス、モンテリマルなどの平野は、灌漑により果樹園の並ぶ豊かな地帯となった。リヨンは西ヨーロッパの一大交差点に位置する。この古代からの都市は16世紀以降ローヌ川の谷のクワを原料に絹の町となり、その下請け工業はマッシフ・サントラルの谷間に及ぶ。中世以来の資本と広い市場に企業家の活躍も加わり、化学工業、ついで鉄鋼業がおこった。
マッシフ・サントラルの山間部は、溶岩台地上または小盆地内で小麦が耕作できるが、いくつかの温泉地がある程度で、牧畜・酪農に頼る人口流出の激しい地域である。しかしこの山中にも東部のサンテティエンヌとクルーゾの石炭資源による工業地帯、北部のクレルモン・フェランを中心都市とするアリエ川の谷(リマーニュ地方)、ロアンヌを中心都市とするロアール川上流の谷に連なる小盆地など、農業・牧畜、地方的小工業の諸地区がある。
[日高達太郎]
北フランス
フランス近代工業の出発点となった地域で、豊かなパリ盆地の大農地も近代化の先端にある。東縁のロレーヌ地方は水系が北海に向かい、気候的にも地質的にも大陸性ヨーロッパに接し、歴史的には辺境地帯の性格を示す。林業と牧畜を主とするボージュ山脈西斜面、メスとナンシーの2都市を有する豊かな土地と活発な工業に恵まれた中央廊下地帯、斜面上のブドウ栽培で有名な西側ケスタ地区の三つがあり、森林資源を生かした手工業(ガラス工芸、高級家具、楽器、刃物)、繊維工業などの伝統産業に加えて、岩塩採掘による化学工業、世界第三の鉄鉱石層とザールに連なる炭田を基礎とする重工業も発展した。パリ盆地北側、狭い意味の北フランスは、アルトア、ブーロネの丘陵地とその北側に広がるフランドルの平野と内陸台地、そしてアルデンヌ山地の南西端部を含む。北海に臨み、各方向への海上連絡もパリ盆地中心部への陸上連絡もよいフランドル地方は、繊維工業を中心とする中世以来の活発な経済地域で、近代以降は炭田の存在によりその重要性が高まった。周辺地区の多様な農業も、ビール醸造、製糖、アルコール蒸留などの加工工業に結び付いている。
パリ盆地中心部の広い台地では、19世紀以来テンサイ、小麦、大麦、家畜飼料などの商業作物を、ときに600ヘクタールにも及ぶ大農園で少人数の資本集約的経営により生産している。丘陵地と谷間は大都市への野菜・果物の供給地である。そして周囲には、ケスタ斜面のブドウ栽培で有名なシャンパーニュ地方、平坦(へいたん)な台地の広がるピカルディー地方、港湾・漁業活動のシェルブールやカーンを中心とする海岸地帯、ルーアンやル・アーブルを中心とするセーヌ川下流工業地帯などが広がる。内陸の丘陵地では、酪農を主としつつ台地上で大農も発達するノルマンディー地方があり、南には「フランスの庭」とよばれるロアール川中流域の谷を挟む豊かな農業地帯が広がる。
[日高達太郎]
政治
フランス政治の歴史的特質
第二次世界大戦以降現在に至るまでのフランスの政治は、1958年5~6月を境として、第四共和政と第五共和政の2時期に分けられている。前者は、議会制の民主化を企てながら、大戦前の第三共和政の政治体制に逆戻りし、大戦の諸打撃からの回復と刷新を目ざして諸分野で成果を収めながら、植民地アルジェリアとの戦争につまずき倒壊した。それにとってかわった第五共和政は、前体制の枠組みを基本的に修正した議会制的大統領制(M・デュベルジェはこれを半大統領制と名づける)を樹立、政府の安定性と主導性を増し、対外的自主性を強めてきた。とはいえ、フランス大革命(1789~1799)以来200年を越える歴史の刻んだ諸困難をすべて整序しえたわけではない。
(1)政治体制の非永続性 第三共和政は70年続き、第五共和政も40年を超えた。しかし現体制は大革命以来16番目の体制である。それは、政府の統治力の弱さを、あるいは体制に関する国民的合意の狭さを示すものであろう。現に第五共和政も1962年、1968年、1981年そして1986年に命運を問われかけたのである。
(2)多党制のもたらす諸問題 多党制の決定的な政治問題は、多数党もしくは多数派連合の構造にあるが、第四共和政の国民議会や戦間期の代議院には単独多数党がなく、連合多数派は不安定で一貫性を欠いていた。したがってそれを基礎とする政府も不安定で弱体となるほかなかった。ことに第四共和政で、両翼に強力な反対派をもつ中央派の連合多数派の場合がそうであった。たとえ多党制でも、選挙、議会、政府を通じて、明確な政策協定にたつ連合が組織され、参加政党の院内投票規律が厳しければ、多数派、政府、ひいては議会制の諸困難も救われたであろうが、第五共和政以前のフランスには、そのような投票規律や多数派連合がまれであった。この点で、第五共和政下の政党には注目すべき進展があった。とはいえ、フランスの政党特有の政党機能にかかわる問題、すなわち市民の政党不信、弱体な政党組織などの歴史的な根本問題が解決されたわけではない。
(3)権威主義的官僚制の重み 第三、第四共和政が政治の自由化、民主化を進めてきたことは事実であるが、それは主として政策定立あるいは立法過程に関してのことで、政策実施の過程、つまり行政過程にまで拡大、浸透したわけではなかった。政治家が行政分野に立ち入り、官僚を監視し、制御しえたわけではなく、政治家や大臣のなしえたことは、地方的利益や中小企業の利益のための調整であった。これに対して官僚は国家的利益の擁護者を自任し、国家の永続性の名において行政過程を支配してきた。しかもこの支配は、中央行政ばかりでなく地方にまで行き渡っていて、多年強固な官僚的中央集権制を維持してきた。政府の任命する県知事は、中央の出先機関を監督して、県を管理する。市民が選出する県議会や市町村議会はあるが、その議決権限の範囲は狭く、市町村は県知事によって後見監督される。したがって地方政治あるいは地方自治の内容もごく限られていた。1982年の左翼政権は、地方分権化改革に取り組んだ。これにより、県知事は共和国委員(1988年知事の名称は復活)となって、地方における国の職務のみを行い、市町村への事前統制権を失う。また地域、県、市町村は自治体として大幅な権限を有するようになった。
こうして、民主化されてきた中央の立法過程に対して、権威主義的官僚団の支配する行政過程が自立性をもって併存してきたのである。両者の関係はそれだけではない。長期的にみれば、立法過程に対してさえ官僚は重要な役割を果たしてきた。議会多数派権力や政府権力の一貫性の欠如や安定性の不足を補って、政治の連続性を保証してきたのは官僚である。大臣は去るが官僚は残り、政府は短命にして交替するが行政は永続するのである。それに加えて戦後、経済・社会に関する問題が政治問題として増加するにつれ、政策の立案定立に関してテクノクラート(専門家)官僚が政治的影響力を増してきた。ディリジスム(国家主導型経済体制)や経済計画に加わる官僚がそうであった。中央官庁の上級官僚ばかりでなく、首相や各大臣の政治的スタッフである大臣官房への出向官僚も同じ理由で政治的影響力を増してきている。これらのエリート官僚の多くは、歴史的にグラン・コール・ド・レタgrands corps de l'État(国家基幹官僚団)とよばれてきたが、第二次世界大戦後は、1945年設立の国立行政学院l'École Nationale d'Administration(略称ENA(エナ))によって供給され、その出身者はエナルクとよばれている。エナルクの多数は専門家的合理主義を奉じつつも、中・上級階層の出身であるうえに、卒業後の公私部門のポストやときに婚姻関係を通じて、上級階層や大企業の立場に結び付きやすい。このナポレオン帝政以来の伝統をもった権威主義的官僚制は1981年に就任した大統領ミッテランの左翼政権下でも基本的には変化しなかった(いわゆるエリート・ローズの出現)。
[横田地弘・井上すず]
政治権力の構造
第五共和政の成立
第四共和政の不安定な多数派連合政権の下では、内外の課題への対応に十分な強力さを欠き、現状凍結的保守政策(イモビリスム)が目だった。とくに旧植民地諸地域との関係の再編問題、とりわけアルジェリア問題の処理は困難を極め、まもなくこの政府の不決断は軍の反抗を招いた(一九五八年五月十三日事件)。そこでこの危機を救うべく再登場したのが将軍ドゴールである。ドゴールは6月3日議会から全権委任されて、憲法改正にとりかかる。新憲法は当然、強力な政府と威信ある国家の確立というドゴールの憲法思想を反映したものであった。
[横田地弘・井上すず]
半大統領制
ドゴールは、国民投票(1958年9月、1962年10月)に訴えて承認を得た1958~1962年の憲法によって、議会制とは異なる論理とメカニズムをもついわゆる半大統領制を創出した。それは、アメリカ型の大統領制に、議会による政府抑制という議会制的メカニズムを併せ備えていた。明らかにそれは、当時の危機的状況に対するドゴールとドゴール党による、伝統的議会制に対する折衷的反応であった。政府権力の核心は多くの特権を備えた大統領にある。大統領を独裁者としない政治的歯止めとして、彼の任命する政府に対して政治責任を問いうる国民議会(下院)が設けられるが、その手続は限定される。大統領が多くの権限を実質的なものとし、その優越的地位を保持するためには、市民の直接選挙によって民主的正統性を与えられなければならない。この選挙は2回投票式多数得票制による。つまり第1回投票で有効投票の絶対多数を得た者がなければ、2週間後に、第1回投票の上位者2名について決選投票が行われる。なお任期は7年(2000年任期を5年に短縮)と長く、再選禁止などの規定もない。大統領は首相の任免権(ときにより閣僚の実質的任免権)、国民議会の解散権、非常事態対処権限などをもつ。また閣議を統裁し、政府と共同で国民投票付託権(1995年シラク政権下では付託しうる法案の範囲は拡大された)、文武官任命権、政令・特別政令(デクレ・オルドナンス)の署名権、憲法改正発議権などをもつ。対外政策を指導し、軍の首長として戦略核戦力の使用決定権をもつことが注目される。
[横田地弘・井上すず]
国民議会の地位
第四共和政までのグベルヌマン・ダサンブレgouvernement d'assemblée(議会優越体制)に慣れた人々は、その低下に驚きまたは憤った。確かに、議会はその立法審議権を制限され、政府の責任追及権も制約されている。会期は年170日以内(1995年シラク政権下で通常会期1期制9か月に改正)とされ、議事日程の自主性を失い、常任委員会の数を19から6に減らされ、法律案、予算案の審議・採決に介入され、法案の修正権を制限されている。ことに、政府が国民議会でこの法案に責任を賭(か)けると宣言し、これに対する問責動議(いわゆる不信任案)が可決されなければ、法案そのものが審議なしに可決となる手続さえある。また、立法の範囲そのものも明示的に限定されている。政府の責任追及の主要手段である問責動議についても、提出者、表決時期、賛成票などについて厳しい条件がつけられている。しかし、これらは、議会の審議をより効率的にする技術であり、政府の行動の麻痺(まひ)を防ぎ、さらには政府を安定・強化させる技術であり、議会制の民主化に逆行するかにみえてそれを「合理化」する技術である。市民によって直接選出され、同じ民主的正統性にたつ国民議会と大統領という2権力を均衡させている、ともいえよう。なお、国民議会の議員の任期は5年で、単記2回式多数得票制によって選出される。これに対する元老院(上院)は、任期9年(2003年任期を6年に短縮)で、3年ごとにその3分の1が間接選挙で改選される。その選挙人団は県ごとに、県選出代議士と県会議員に市町村会議員の代表を加えて構成される。国会議員の兼職禁止規定は種々あるが、第五共和政特有の制度として注目すべきものは、元老院、国民議会の議員はいずれも首相以下の政府構成員との兼職は許されない。このため、すべての候補者は選挙に際して、当選後入閣する場合、自分にかわる議員となるべき補充者を伴って立候補する。ところが地方議員(市長なども含む)との兼職については、第五共和政以前から行われてきたように、国会議員のみならず首相以下政府構成員にも認められている。このフランス独自の兼職制度は、中央―地方関係が政党組織よりも政治家の個人的影響力により動かされる傾向を強め、不透明な政策過程、ひいては政治家の汚職問題とからめて、近年批判が絶えない。とくに地方自治の進展は、この問題をより深刻にしている。また議会の欠席率増大とこうした兼職との関連が指摘され、1985年の法律により、ヨーロッパ連合の議員を含めて、地方議員と国会議員との兼職は二つまでに制限された。
[横田地弘・井上すず]
半大統領制の政治権力の構造
第五共和政特有の半大統領制という政治体制における諸権力の関係は、どのようなものであるか。憲法によれば、政府が国の政策を決定、実施し、首相がこの政府を指導する。他方、国民から直接選出された大統領は、この首相を任命し、大統領が統裁する閣議を通じて政府を指導する。この入り組んだ大統領・政府関係を解く鍵(かぎ)は、大統領と議会多数派との関係にある。もし議会多数派が大統領支持であれば、大統領は意のままに首相を任免し、行政府の主導権を掌握できる。しかし、一度議会に大統領に対立する多数派が成立すると、大統領は首相以下政府構成員をこの敵対する多数派から選任しなければならない。いかに議会の地位が低下したとはいえ、議会は政府を不信任にできるからである。この場合は、外交・国防政策の相当部分を除いて実質的主導権は、首相・政府の側に移行する。いわゆるコアビタシオン、保革共存政権(1986―1988、1993―1995、1997―2002)である。
このうち最初の保革共存政権で初めて表面化した、人事をめぐる大統領と首相の間の紛争は、むしろそれまでの大統領と政府の多数派が一致していた政権においては、国家枢要の地位の任命権を多数派が容易に独占し、政治の司法への介入すらありうることを示唆していた。
確かに、多数派権力に対するチェック機能の必要性は、いまだ国民的合意を得たとはいいがたいが「少数意見の尊重」「法治国家」の要請が論議される1980年代末の時代状況もあって、かつてジスカール・デスタン政権下で、憲法院に法律の合憲性審査を付託する権利を両院の少数派(議員60名以上)にも与えたことが(1974年憲法改正)この観点からも再評価されてきた。ただし、この合憲性審査は立法の最終段階での審査であって、通常いわれる違憲立法審査とは異なる。
[横田地弘・井上すず]
政党制の発展
第五共和政に入って、政党制は伝統的な形態を残しながらも、しだいに組織化され、4党二極化の方向をとった。まず注目されたことは、右翼の連合による議会多数派の発展であり、単独多数党の出現である。それはいずれも新議会の成立から次の総選挙まで安定した多数派(党)を構成した。例外は1958~1962年の議会で、ここでは、大統領ドゴールがアルジェリア戦争収束政策によって多数派の結集と維持を強いた。
1962年以降、ドゴール派の新共和国連合(UNR)を中核とし独立共和党(RI)を加えた右翼多数派が形成され、大統領ドゴールの権威と声望の下に維持されるが、UNRがドゴールに忠実な人格的政党であるのに対して、RIのほうはしだいに条件付き支持政党となる。1968年には、ドゴール派の共和国民主連合(UDR)の単独多数党を生むが、連合は維持されて72.7%の議席率を占める。だがこれは、1968年5月の重大危機に対するドゴール以下のすさまじい反撃の成果で、「かつてない議会」と称された。大統領ポンピドー、次の大統領ジスカール・デスタンの下でも、しだいに中央の諸派を取り込むことにより右翼多数派が維持される。1978年には、ドゴール派の共和国連合(RPR)とネオ・リベラルのフランス民主連合(UDF)との連合をみた。後者は、大統領ジスカール・デスタンの党である共和党(PR)を中心に、中央派の民主社会中央党(CDS)、急進党主流、独立・農民派(CNIP)その他を結集した政党連合で、優勢なRPRとの均衡をねらった大統領ジスカール・デスタンの戦略の成果であった。
この1978年の総選挙までに、右翼多数派を逆転させ、左翼多数派が実現されるはずであったが、社共2党の連合はその前年に破綻(はたん)して、1971年以来の左翼の健闘は実を結ばなかった。左翼は1965年から左翼連合を企てたが、1968年の惨敗の衝撃で解消。1971年、旧社会党(SFIO)にかわった新生社会党(PS)は、第一書記ミッテランの下に新左翼連合の戦略をとるに及んでようやく勢力を伸長し、1981年の大統領選でミッテランが勝利を得た直後に、急造の左翼連合の勝利と社会党の単独多数を実現し、左翼連合の画期的な「大交替」が達成された。しかし左翼多数派はその大胆な社会・経済改革の試みにもかかわらず、1986年にはふたたび右翼多数派にとってかわられた。この選挙は、予想される社会党の敗北を最小限にとどめるため比例代表制で行われたが、結果として極右の国民戦線(FN)の議会進出を生むことになる。その後、選挙制度は旧に復し、国民戦線は議会では勢力を失うが、大統領選挙では、得票率が1988年14.4%、1995年15%、2001年17.79%と上昇の傾向にある。激しい人種差別的言動で知られるルペンを党首とするこの政党は、移民の増大、都市治安の悪化、失業などに不安を抱く民衆に支持を拡大してきた。他方1980年代後半にエコロジストがもう一つの新勢力となって現れた。この派は、都市、青年、高学歴給与生活者などを支持基盤とし、1989年ヨーロッパ議会選挙で初めて得票率が10%を超えたが、党派としての一体性に欠け、各種選挙での得票率も安定していない。これら二つの新勢力は、選挙制度ゆえに4党二極化の政党体制を崩壊させたわけではないが、この体制を弱める要因となった。なお、1988年の大統領選挙でミッテランは再選を果たすが、1993年の総選挙での社会党の惨敗もあって、2期目の統治は活力を欠いた。1995年の大統領選挙では、RPRのシラクが勝利し、14年ぶりに右翼の大統領の誕生となった。シラクは、ヨーロッパ通貨統合への参加の条件を満たすため緊縮政策を行うが、この政策が国民の不満を高めていくことを懸念して、1997年4月に任期前議会解散に踏み切った。その結果は、左翼の勝利で社会党の首相ジョスパンが誕生し、またしても、保革共存政権となった。しかし、2002年5月の大統領選挙では、シラクとの一騎打ちが予想されていたジョスパンが第1回投票でFNのルペンに敗れ3位となり、ルペンとシラクの決選投票となった。結果はシラクが再選を決めたが、ジョスパンは第1回投票の敗退をうけて辞表を提出。シラクは、新たな首相に自由民主党(DL)副党首ラファランを任命。6月の総選挙では保守連合が単独過半数を獲得して圧勝。これによりシラクとジョスパンの下で5年続いた保革共存政権に終止符が打たれた。11月に保守連合は、RPRを中心として、DLやフランス民主連合の一部を加えて国民運動連合(UMP)を発足させている。ラファラン内閣は社会保障制度改革などに取り組んだが、高い失業率や格差拡大などで国民の支持率が低迷し、2004年3月の地方選挙で惨敗した。さらに2005年5月にヨーロッパ連合(EU)の基本法となるヨーロッパ憲法批准承認を問う国民投票では、賛成が45.33%にとどまり、否決された。その結果、首相ラファランが辞任、6月に内相であったドビルパンDominique de Villepin(1953― )が首相に就任し、内閣が発足、UMP党首ニコラ・サルコジが国務相兼内相に就任。2006年3月、若年層の雇用促進を目的としたCPE(初期雇用契約)の導入を巡り、これに反対する学生や労働者たちによるデモやストライキがフランス全土に拡大、4月ドビルパン首相はCPE撤回を表明、支持率を下げた。
2007年5月に任期満了を迎えるシラクは、次回大統領選挙の不出馬を正式表明。UMP党首ニコラ・サルコジと社会党のセゴレーヌ・ロワイヤルSégolène Royalの決選投票(5月6日)の結果、保守派のサルコジが当選した。同16日の就任演説でサルコジは「過去との決別」と「改革」を掲げ、市場原理と競争に基づく英米型社会への転換を示した。17日に側近のフランソア・フィヨンFrançois Ⅰ Fillonを首相に指名、18日に内閣が発足した。外相として国際緊急医療援助団体「国境なき医師団」創設者の一人ベルナール・クシュネルBernard Kouchnerを起用、また、移民・同化・国家アイデンティティ相が新設された。
[横田地弘・井上すず]
第五共和政の対外関係
第五共和政におけるドゴール外交の目標は、実質的には中級国家となったフランスが、いかにして世界的影響力をもつ大国としての地位を確保するかということにある。第四共和政期と同様、東西対立の基本的枠組みでは、西側に帰属しながらも、彼の信念である「国家独立」「フランスの偉大さ」のための自主独立外交の可能性を追求した。1960年代のデタント(緊張緩和)の国際状況ゆえにこのような外交努力が実を結んだことも否めない。この独自外交の不可欠の手段が、何よりも核戦力保有であり、全方位抑止戦略理論を採用して、フランスは1966年NATO(ナトー)(北大西洋条約機構)の軍事機構から離脱した。ほぼ時を同じくして、東への開放政策(中国承認1964、ソ連訪問1966)、アラブより政策への転換(1967)、ベトナム戦争批判(1966)などいずれも対米追随を非とする外交を展開する。ヨーロッパ経済共同体(EEC)については、ドゴールにとってもフランスの経済力強化のために推進すべきであったが、国家主権の縮小には断固反対した。なお、旧植民地、とくにアフリカ諸国との関係は依然として重視され、多方面にわたる二国間協定を結んで、これらの国々との関係を統轄する協力省を置いた。
このようなドゴールの対外政策は、その後の国際環境の変化や後継諸大統領の個性によりいくぶん手直しされるものの、冷戦終結(1989)に至るまでは、フランス外交の基本型であった。社会党出身の大統領ミッテランの場合も、就任当初、第三世界重視外交が目をひいたが、とくにこれまでの対外政策の型を逸脱するものではない。ところが、ミッテランが大統領再選を果たしてまもなく、ベルリンの壁崩壊(1989年11月)、湾岸戦争(1990年8月―1991年3月)、東西ドイツの統一(1990年10月)、ソ連解体(1991年12月)というように国際環境が激変する。この戦後の国際政治の基本的枠組み崩壊後のミッテランの外交戦略は、ヨーロッパ統合の強化であった。湾岸戦争は、アメリカの軍事力、日本とドイツの経済力を見せつけた。もはやフランス一国では経済はもとより軍事、外交においても指導的地位は得られないとすれば、強いドイツをヨーロッパの枠の中に封じ込め、ドイツに対するフランスの軍事的外交的優位(核兵器所有、人権大国の声望)を利用して統合の主導権を握り、アメリカの世界支配に立ち向わざるをえない。通貨統合、政治統合への批判の高まるなか、ヨーロッパ連合条約批准の可否を国民投票に問い、条約成立に導いたことはミッテラン外交の成果であった。
1995年5月、大統領となったシラクは、前任者の政策を引き継いで通貨統合への努力を続けたが、1996年2月、重大な国防政策の転換を行った。1997~2002年の国防力整備計画のための新方針で、次の3点を柱とする。(1)地上発射核戦力全廃。1995年9月、世界世論の批判を浴びつつも強行された核実験は1996年1月をもって終了。ただし核抑止力は維持。(2)2002年までに徴兵制を廃止し、現存50万の兵力を35万に削減。(3)国防産業再編成、競争力強化。新政策は国防費削減(現行計画より年間予算を200億フラン減じて1850億フランにとどめる)を図るとともに、テロ、人道援助への対応の必要という冷戦後の新状況に備えて、職業軍人による高度の装備と機動力をもつ軍への転換を意図したものである。この結果、2001年に徴兵制は廃止され、志願兵制度が導入されている。
なお、フランスは、1995年12月NATO内の軍事委員会に出席したのを皮切りにNATOの軍事機構に復帰しつつある。ただしNATOを内側から改革するとして、ヨーロッパにおけるアメリカの指揮権存続には異をとなえている。2003年のイラク戦争に際しては、アメリカ主導の戦争開始には反対の立場を表明。シラク大統領は在任中、ドイツのシュレーダー首相としばしば会談し、ヨーロッパ連合(EU)の主要国同士として対独強調路線を図った。
2005年5月、フランスでEUの基本法となる欧州憲法(EU憲法)条約批准の是非を問う国民投票が行われ、反対54.87%で否決された。この結果、対外的にヨーロッパ統合を推進する主要国としてのフランスの指導力が問われ、EU内での影響力が低下し、ユーロ導入に続くEUの政治的統合が停滞した印象は否めない。なお、シラク政権は、歴史的につながりのあるアフリカ、中東、アジア各地域の開発途上国との関係も重視した。
2007年5月16日に第五共和政6人目の大統領に就任したサルコジは、就任直後ドイツを訪れメルケル首相と会談、改めてEU体制の再生と強化をアピールした。また、市場原理と競争に基づく英米型社会への転換を示し、米英協調路線を打ち出した。
[横田地弘・井上すず]
経済・産業
混合経済の体制
フランスは資本主義国家であり、経済の仕組みも私企業の自由な経済活動を前提にしてつくられている。つまり、基本的には「営業の自由」を原則にし、国家の干渉や独占の形成を否定する自由主義経済の体制が基調になっている。しかし、他方において、フランスでは歴史的に早い時期から企業の国有化が進行しており、今日では他の資本主義諸国家に比べると国有企業のウェイトがもっとも高い国になっている。これは自由主義経済の新たな局面を示すもので、経済発展をめぐり国家が重要な役割を果たすようになったことの結果である。一般に、こうした状況における私企業と国有企業との共存を「混合経済」の体制とよんでいるが、その典型例がフランスである。なお、フランスの場合には、自由主義経済を踏まえつつも、政府が国有企業の活用によって国民経済の全体を指導し発展させるという考え方(ディリジスムdirigismeの思想)が強く、私企業もそれと協調する体制になっているので、官民の「協調経済」と表現されることも多い。
[遠藤輝明]
国有化の進展
企業の国有化は、1929年大恐慌にみられた自由放任経済の破綻(はたん)や、現代における社会主義経済圏の出現と拡大を経験するなかで、経済計画の導入と絡み合いながら進展してきた。それは深刻な経済不況のたびごとに経済振興策の一つとして主張され、フランス労働総同盟(CGT(セージェーテー))など労働組合の強力な支持によって実現されたものである。鉄道と軍需産業が国有化されたのは、1936年に成立した人民戦線内閣によってである。また、一連の基幹産業部門(石炭、ガス、電気)とフランス銀行(中央発券銀行)や四大預金銀行(商工国民銀行、パリ国民割引金庫、ソシエテ・ジェネラル、クレディ・リヨネ)など有力な金融機関、さらに各種の保険会社、ルノー自動車などが国有化されて混合経済の大枠がつくられたのは、第二次世界大戦で反ナチ・レジスタンス運動を経た直後、1944~1946年における労働運動の国民的な高揚期においてであった。さらに、1982年には、社会党に足場を置く大統領ミッテランのもとで、国有企業の新たな拡大が図られた。こうして、前記のほかに航空(エールフランス)、海運(トランス・アトランティク、メッサジュリー・マリティーム)、鉄鋼(ユジノール、サシロール)、化学(ローヌ・プーラン)、航空機(アエロ・スパシャル、ダッソー)、同エンジン部門(スネクマ)などで国有化が進んだ。しかし、こうした動きに対して、資本家諸団体を中心にする自由主義経済の擁護者たちの間から、国有化は経済の国家管理をもたらし「営業の自由」を侵害するという反論が絶えず強力に提起されていた。その結果、1947年以降は国有化の推進案が出されつつも1982年まで実現されなかったし、1986年ごろからは石炭、鉄鋼などの国有企業が収益性を失ったことも重なり、国有企業の民営化(私企業化)がミッテラン政権に対抗する諸党派の主張になった。なお、国有企業の経営には、(1)関係大臣が指名した関連業界の代表者、(2)組合選出の従業員代表、(3)専門職、または消費者代表などが取締役として参加できる「三者協議」方式を採用しており、いわゆる「国営」とは異なることにも注意すべきであろう。
[遠藤輝明]
経済成長と経済計画
戦後フランスの経済復興は、有名なモネ・プラン(第一次経済計画、1946~1952)によって推進され、電気、石炭、鉄鋼、セメント、運輸、農業機械の6部門が重点的に復興された。この成果を踏まえ、第二次(1954~1957)、第三次(1958~1961)のプランでは製造業一般の設備近代化=合理化が計画され、国際経済力の増強が図られた。また、第四次(1962~1965)、第五次(1966~1970)、第六次(1971~1975)では、公共施設(学校、病院、文化施設)や国土開発(道路、地域開発)へもプランの対象が拡大され、「社会・経済の発展計画」とよばれるようになった。これらのプランはそれぞれに成果をあげ、1960年代から1970年代の前半にかけては、国民総生産の伸び率が年平均では5%となり、1973年には6.6%というヨーロッパ諸国で第1位の経済成長率を示した。1976年以降は、石油ショックに伴う世界的な景気後退のなかで、失業の増大や貿易収支の赤字幅拡大などにより経済の悪化がみられたが、それだけに経済計画の重要性も高まり、第七次プラン(1976~1980)のもとでは年平均3%台の経済成長を保った。1980年代に入ってからは、第二次石油ショックの打撃を受け、マイナス成長の年もみられたが、平均すれば1.1%の伸び率を示している。経済計画については、第八次プラン(1981~1985)がミッテラン政権の成立により1982~1983年の中間計画に変更されたあと、第九次プラン(1984~1988)で企業の国有化政策が強調されるが、1986年に成立した保守連合のシラク政権により公企業の民営化が打ち出された。そして、1989~1992年の「第十次経済社会文化発展計画」から以降は国家の介入に一定の限度を設け(規制緩和)、民間企業の自助努力による経済発展の方策を強めるようになっている。1986年には約3500社あった国営公共企業は、2002年末には約1600社にまで減少している。
[遠藤輝明]
産業構造
2004年における各種産業への就業人口は2472万人(総人口の40%)であり、その産業別構成比は、第一次産業(農業、漁業など)4.0%、第二次産業(製造業、建設業など)24.5%、第三次産業(商業、サービス業など)71.0%になっている。これをイギリスやドイツと比較すると、第一次産業の比重が高く、それだけ農業国としての特徴を残していることになるが、他方で第三次産業の占める割合はドイツやイタリアよりも大きく、世界的にみてもヨーロッパにおいても上位に位置する。これは成熟した先進工業国としての特徴を示すものである。第二次産業の就業人口比は1977年まで増加を続け、その後はしだいに低下する傾向にある。その理由は、成長産業の主軸が鉄鋼、造船など重工業部門から、宇宙、電子、化学など知識集約的なハイテク産業へ移行していることに由来している。サービス業を中心にした第三次産業の就業人口が増加してくるのは、こうした製造業における新たな編成替えを踏まえてのことであるが、フランス経済を全体としてみれば「脱工業化」(産業社会の成熟度指標)の進行を示している。
[遠藤輝明]
産業組織
他の先進工業国に比べて、経済集中度は低いほうであり、小規模零細企業の多数存在がフランスの伝統的な特徴になっている。各種企業を雇用従業者数によって規模別に分類すると、1983年に、小売・卸売業の94.8%が10人以下の零細企業であり、製造業の場合でも、10人以下の企業および職人的家族営業が84.4%を占め、500人以上の大企業は0.4%にしかすぎない。また、従業者の分布状況でみると、一般に大企業が支配的とみられる鉄鋼業でも、1979年の従業者数45万5500人のうち、500人以上の大企業で働く者は27%であり、20~499人の中小企業で57%、19人以下の小規模零細企業で16%という割合になっていた。紡績・織布業も同様で、従業者数53万6000人のうち、500人以上に30%、20~499人に59%、19人以下に11%という分布になっている。こうしたなかで、500人以上の大企業が従業者数の大半を雇用している業種は、石炭業(100%)、電気・ガス・水道業、鉄鋼業(90%台)、自動車産業、石油・天然ガス産業、金融機関、海運業、非鉄金属、保険業(80%台)、電気機械産業、化学産業、ガラス工業(70%台)などであり、いずれも国有企業が進出している部門である。また、フランスの経済成長に大きく貢献してきたのも、これらの業種であった。こうして、フランスの産業組織においては、公共的な性格をもつ業種や先端技術を導入した産業のもとで、国有企業を軸にした限られた数の大企業が上部に形成され、その下部に国民経済の豊かな消費を支える伝統的な在来産業(繊維、食品、皮革、流通、サービス業など)の幅広く層の厚い中小零細企業が存在する形になっている。なお、大企業の場合には、経営陣に高級官僚やテクノクラートの養成機関である理工科大学校(エコール・ポリテクニク)などグランゼコールの卒業生が参加し、経済変化へ革新的に対応していく進歩主義がみられるのに対して、中小零細企業では企業所有者による家族的経営が一般的であり、企業行動においても保守的であるのが特徴になっている。
[遠藤輝明]
工業地帯
19世紀の初頭から始まる産業革命の展開によって、諸産業の地域的な集中が進んだ結果、次の五大工業地帯が形成され現在に至っている。
〔1〕北フランス 消費財から生産財に至る各種の産業が相互に連関をもちながら多面的に展開しており、工業化と社会的分業とがもっとも進んだ地域である。とくに、広範な農村工業から出発し産業革命の母胎になった繊維産業は、リール―トゥールコアン―ルーベー―アルマンティエールの一帯で発達し、亜麻(あま)、綿、羊毛を素材とする紡績、織布、染色、捺染(なっせん)、仕上げなど多様な諸工場の密集地帯をつくりだしている。また、採掘量でフランス最大を誇る炭田がアンザンAnzinからパ・ド・カレー地方に広がっており、フランス石炭公社の有力な炭鉱やコークス工場、火力発電所が展開しているほか、バランシェンヌ、ドゥエ、ダンケルクなどに大規模な製鉄所が立地し、それをめぐって大小さまざまの鉄加工業(車両、造船、鋼管、製缶、機械など)が発達している。
〔2〕東部フランス ロレーヌはフランス第一の鉄鋼生産地(銑鉄と鉄鋼の60~70%を生産)であり、ロンウィLongwy、エアンジュHayange、ティオンビル、オメクールHomécourt、メス、ポンタ・ムーソンPont-à-Mousson、ナンシーなど多数の著名な鉄鋼都市がド・バンデル社やシデロール社、ユジノール社系の大型銑鋼一貫工場を中核にして形成されている。しかし、北フランスと異なり、鉄加工業の発達はみられない。アルザス地方では、ミュルーズがリール―トゥールコアンやルーアンと並んで綿織物工業三大中心地の一つであり、とくに高級捺染綿布の生産が著名である。また、ベルフォールとモンベリアルでは機械工業の展開を踏まえてプジョー社が自動車を生産している。
〔3〕ノルマンディー地方 産業革命の発祥地であるが、その担い手となった独立自営の家族的小経営が、中小零細企業として根強く生き残っている。この特徴は、とくに金物と綿布の生産でみられる。工業地帯形成の起点になったのは、フランスのランカシャーといわれ綿織物工業で富を築いたルーアンであり、ここからセーヌ川の河口にある工業港ル・アーブルへかけて各種の工業都市が連なっている。ヤンビルYainville(火力発電と化学製品)、グラン・クビリLe Grand-Quevilly(造船)、デュクレールDuclair(金物、ボルト、銅加工)、ル・トレLe Trait(造船)、ポール・ジェロームPort-Jérôme(石油精製、プラスチック、合成ゴム)、ゴンフルビルGonfreville(石油精製の臨海基地)などである。また、ルーアンより上流には毛織物の工業都市エルブーフElbeufとルービエLouviersがある。ノルマンディーの西部では、カーンを中心に、鉄鋼、機械、家電器具の生産が行われている。
〔4〕パリ地域 パリは商業・金融の中心であるほか、人口集中による豊富な労働力の集積があり、最新技術の研究・開発機関も多いので、冶金(やきん)・製鉄業を除き、すべての工業生産がパリと周辺の郊外地に立地している。製造業の就業人口は全体の22%をこの地域で占めており、フランス第一の工業地帯である。もっとも重要な産業部門は、自動車(ルノー、シトロエン)、航空機(スネクマ)、および、電気機械、電子機器、カメラ、工作機械、工具類などである。これらの生産工場は、大部分がパリを取り巻く衛星都市に立地しており、新たな人口集中をもたらしている。たとえば、パリ北部のサン・ドニ、オーベルビリエAubervilliers、サントアンSaint-Ouen、アニエールAsnières、南西部のビヤンクール(ブローニュ・ビヤンクール)、イシーIssy-les-Moulineaux、南東部のイブリーIvry-sur-Seineなど。ルノー工場はビヤンクールにあり、従業者数3万8000人を擁する巨大企業であるが、工具類などは5人前後の小企業であることが多い。また、伝統的産業では、生地(きじ)加工、縫製、食品、印刷などが、パリ市内や周辺部で盛んである。
〔5〕ローヌ―アルプ地方 リヨン、サンテティエンヌ、グルノーブルの3都市を拠点にする工業地帯である。19世紀のなかばごろから、リヨンの絹織物とサンテティエンヌの石炭・鉄鋼とが二大推進力になり、各種の関連産業を急速に発展させた。現在、絹織物業は主要な生産地をリヨン地域から低ドフィーネや南ジュラの農村へ移し、織物業における地位も相対的に低下したが、染色や仕上げ加工の部門はリヨンに残り、それとの関連で、高度な化学技術を利用する染料や化学繊維の生産が発達している。サンテティエンヌはリヨンから南西へ走る国有鉄道で1時間たらずの距離にあるが、この間に、ジボルGivors(ガラス、各種機械)、リーブ・ド・ジエRive-de-Gier(鋳鉄、特殊鋼)、サン・シャモンSaint-Chamond(特殊鋼、金物、化学製品)などの工業都市が並び、煙突が林立している。サンテティエンヌは、これらペイ・ノアールpays noir(英語の「ブラック・カントリー=黒郷」と同じ意味)と通称されてきた地域の中心であり、特殊鋼の生産と並んで銃砲、自転車、工具・金物、工作機械、起重機などの製造で著名である。一般に工場の規模は小規模であるが、企業組織としては大部分が二つの大会社(コンパニー・デ・ザトリエ・エ・フォルジュ・ド・ラ・ロアールとエタブリスマン・シュネーデル)にグループ化されている。グルノーブル地域では北アルプスの豊富な水と水力発電を基盤にして、製紙業、電気精鋼、アルミニウムの生産などに労働力が集中している。
以上の五大工業地帯のほか、地域開発による地方都市の工業化(トゥールーズの航空機産業、クレルモン・フェランのゴム、医薬品など)や、港湾都市の臨海工業地帯化(ボルドーの石油製精、セルロース、リン酸塩、食品、マルセイユの石油化学、造船など)も進んでいる。
[遠藤輝明]
農業
農林水産業の就業人口は1977年の201万3000人から1984年の165万9000人、2003年の78万1000人になった。また、農家戸数も70年の158万8000戸から2000年には66万4000戸になった。この推移は「小農経営の国」と特徴づけられてきたフランスでも大規模経営への集中が進んだことを示している。農業経営の規模別分布によると、20ヘクタール以下の小経営が急速に減少し、100ヘクタール以上の大経営が増加している。農地の利用面積でみると、2000年に20ヘクタール以下の経営はわずかに6.6%を占めるのみで、100ヘクタール以上の経営が45.6%を占めている。しかし、資本家的借地農による大規模経営の形成は歴史的に主として北部の穀倉地帯でみられ、ナントとスイスのジュネーブを結ぶ線の南側と東部フランスとでは伝統的な小規模零細経営が依然として支配的である。こうした北と南の格差は産業構造の近代化が進むなかで広がっており、その是正が農業政策の最大の課題になっている。農産物の生産高(基準価格)は2003年に643億ユーロであった。内訳は生産高の多い順に家畜(18.4%)、穀物(14.9%)、牛乳・その他の動物性農産物(13.2%)、果実・野菜・ジャガイモ(12.3%)、飼料・植物・花(12.0%)などである。この年に小麦の生産量は全世界の5.4%を占め、中国、インド、アメリカ、ロシアに次いで第5位であった。農業生産の地理的分布をみると、小麦と大麦の生産高がもっとも大きいのは、ボースとパリ盆地を主力とする北部の大農経営地帯である。150から600ヘクタールに及ぶ大農場があり、農業機械化も進んでいる。また、パリや北フランスの製糖業へ供給するテンサイの栽培もこの地方に集中している。世界に誇るワイン生産国としてブドウは重要な農作物であり、ナントからシャルルビル・メジエール(アルデンヌ県)へ斜めに結ぶ線を北限にして全県で栽培されている。ブドウの栽培耕地面積は2002年に85万2000ヘクタール(農用地総計の4.6%)であり、2000年には595万キロリットルのワインを生産した(全世界の39.2%)。しかし、主要山地は南部フランスにあって、作付面積はアキテーヌ盆地のジロンド県と、地中海沿岸のオード、エローの両県とが最大である。牧畜はブルターニュ地方を中心にした大西洋沿岸地帯と中央山岳地帯とで盛んである。
[遠藤輝明]
鉱工業
鉱業では、ロレーヌの鉄鉱石(ミネット鉱)、プロバンスのボーキサイト、リムーザンの亜鉛などが世界的に名声を得てきたが、総じて鉱物原料の自給率は低く海外への依存度が高い。ただし、ニューカレドニアのニッケル鉱は生産が多い。1995年に鉱物原料の輸入額が73億6800万フランに達したのに対して輸出額は15億7200万フランであった。工業では、石油ショック(1973)までの高度成長を踏まえ、生産量で世界の10位以内に入る部門が鉄鋼、化学、機械、繊維などの分野で出現した。しかし、これらの諸部門も1985年を100とする指数でみると、1994年における鉱工業全体の伸び率116.0を鉄鉱石・鉄鋼(90.8)、繊維(80.8)などが下回り、平均を超えたのは化学製品(154.6)、自動車(122.9)、建築業(123.6)であった。主要な企業として、化学ではローヌ・プーラン、ペシネイ、エア・リキード、ロレアル、コダック・パテ、クリスチャン・ディオール、サノフィ、自動車ではルノー、プジョー・シトロエン、鉄鋼ではユジノール・サシロール、クルーゾ・ロワール、ユージヌ・アシエ、電気ではジューモン・ジュネデール、繊維ではプルボスト、ブサック、ルベなど。
[遠藤輝明]
エネルギー
国内のエネルギー資源は全般的に不足しており、経済発展の大きな足かせになってきた。1980年におけるエネルギーの総生産量は石油換算100万トンの単位で34.6、総消費量は163.2であった。したがって、エネルギーの輸入依存度は79%になっていた。同じころに日本は90.2%、旧西ドイツが53.5%であった。すでに石炭と天然ガスの生産はしだいに減少しており、エネルギー消費の52%は石油であるが、その国内生産量は消費の2%を補う程度であった。こうしたなかで、エネルギーの節約強化と原子力発電の推進がエネルギー開発政策の基本となり、1990年度を目標にして輸入依存度を50%にまで引き下げる政策がとられた。その結果、1980年以降、工業生産指数のなかで電力生産が毎年1位の高い伸び率を示し、1993年には総消費量2億1860万トンのうち1億1340万トンを生産し、輸入依存度を48.1%とした。同年に日本が80.2%、ドイツが54.9%の輸入依存度になっていることと比較すれば、フランスにおけるエネルギー政策の成功を読み取ることができる。しかしその後は輸入依存度は上昇し、2002年にはエネルギー総消費量は2億4442万トンで、輸入依存度は66.1%となっている。
その後、エネルギー自給率は50%前後が続いたが、2005年には自給率が49.8%となっている。2005年のエネルギー総消費量は2億7650万トン、電力総生産量は5754億キロワット(石油換算で1億2270万トン)で、そのうち原子力発電が79%、水力・風力・太陽光発電が10%、火力発電が11%となっている。原子力発電の割合が高く、原子力発電が一次エネルギー総生産量に占める割合は、1973年には9%だったのに比べ、2005年には85.5%にまでになっている。
[遠藤輝明]
運輸・通信
鉄道はフランス国有鉄道会社SNCFの経営で、2001年の従業者数は18万2800人、営業キロ数は2万9352キロメートルであった。路線は、パリから四方へ放射状に延びる五大幹線を軸にして、支線が網目のように敷設されている。1981年にはパリ―リヨン間を超高速列車TGV(テージェーベー)が最高時速270キロメートルで営業を始め、その後も路線網を広げている。在来線乗り入れを含めると、南東へニース、西へはブレスト、西南へはボルドー、北はリール、カレーなどの国内のおもな都市をパリと結び、2001年にはバランスとマルセイユを結ぶ地中海線が開通している。さらにブリュッセル、スペインのイルン、ミラノ、ジュネーブなど近隣諸国へも乗り入れている。また、1994年、英仏海峡トンネルの開通に伴い、パリ―ロンドン間を直通専用列車ユーロスターが走り出した。道路は経済計画で高速道路の建設が促進され、パリを中心にフランス縦断や横断の道路がつくられた。1992年における高速道路の延べキロ数は7000キロメートル(1974年=100として255の伸び)であり、国道総計2万8000キロメートルの25%に相当する。河川と運河は、鉱石、石油、肥料、農産物などの輸送に利用されており、とくに五大工業地帯で重要な役割を果たしている。輸送船が航行可能な延べキロ数は8500キロメートル(うち、3000トン以上は1647キロメートル)であり、鉄道の4分の1強にあたる。海運は世界第9位の規模で、1986年の船舶所有数は311隻(うち、客船27、貨物船221、タンカー63)、総トン数は583万トンであるが、1981年にタンカー108隻を含む424隻の船舶を保持した時点と比べ、海運不況の影響を強く受けている。航空輸送は、エール・フランスとUTAが世界へ路線を開き、エール・アンテールが国内路線を担当していた。しかし国際路線の合理化と競争力促進のため、エール・フランスは1990年にUTAを買収した。また同年、エール・フランスはエール・アンテールの株式を約74%取得し、実質的にフランス航空業を独占した。1997年にはエール・フランスにエール・アンテールの運行業務が統合されている。1998年度のエール・フランスの航空機所有数は209幾、従業員数5万4000人。さらに、エールフランスは2003年にKLMオランダ航空と経営統合し、エールフランス・KLMグループとしてヨーロッパ第1位の航空グループとなった。通信では、1981年に電話網の大規模な整備計画が実施された結果、1000人当りの電話普及率は、1975年の235から2004年には560に上昇した。また移動電話の契約数は2004年で4455万で、1000人当り737となっている。テレビの保有世帯率は95.1%、インターネットの利用者数は約2500万人で、ヨーロッパではドイツ、イギリス、イタリアに次ぐ第4位を占めている。
[遠藤輝明]
貿易
2004年の輸入総額は3743億1300万ユーロ、輸出総額は3607億6800万ユーロであり、貿易収支は135億4500万ユーロの赤字であった。輸入額と輸出額の合算による貿易規模は、アメリカ、ドイツ、中国、日本に次いで世界第5位である。また、国内総生産の貿易依存度は、輸入、輸出ともに21%であり、ドイツに比べれば低いが、アメリカ、日本よりも高い。貿易収支が黒字基調であったのは1992年からの数年間であり、石油ショックを境にして1970年代の後半からは赤字が恒常化していた。1982年には過去最高の1515億フランの赤字を記録している。このように貿易収支が悪化した主要な原因としては、エネルギー資源の対外依存度が高いフランスにとって石油価格の高騰が大きく影響したこと、それに伴って製造業の経営内容が悪くなり、国際競争力が低下したことなどをあげることができる。その後、エネルギー開発政策の推進により、1990年代からエネルギー資源の輸入量が大幅に急減し、貿易収支の改善をもたらした。各種物品の輸出額を輸入額で除した輸出入カバー率をみると、1994年に100%を超えているのは、上位から順に、陸運関係車両・部品136.4、農産加工・食品126.8、農水産物124.0、生産設備機械112.7、自動車・部品108.6などである。なお、100には満たないが、化学製品99.0、金属・加工品98.0、消費財96.7などが注目される。これらの数値はフランスが農業国としての伝統を保持しつつ機械、自動車、化学など近代的な科学技術のセクターで世界経済のなかへ進出していく姿を示唆している。貿易規模の地域別構成比は、EU(ヨーロッパ連合)45.0%、OECD(経済協力開発機構、EUを除く)16.6%、アフリカ5.3%、アジア(日本を除く)5.2%であり、国別ではドイツ19.6%、イタリア9.6%、イギリス8.9%、アメリカ7.7%の順になっている。日本は2.8%を占めている。
[遠藤輝明]
金融・財政
1970年代の前半期まで設備投資の年平均伸び率は7.5%であり、旧西ドイツの4%を大きく上回っていた。しかし、その結果はインフレの高進をもたらし、その継続のなかで貿易収支の悪化に伴う深刻な経済不況を迎えた。これに対して、1981年にフランを3%切下げ(マルク5.5%切上げ)輸出の振興を図ったが失敗に終わり、1982年にふたたびフランの5.75%切下げ(マルク4.2%切上げ)を実施するとともに、財政収支の赤字幅を国内総生産(GDP)の3%以内に収める均衡財政を目ざしてインフレを抑制する政策をとった。また、規制緩和、自由化による国際化への対応も打ち出されるようになった。こうして、フランスの経済動向が示すように、1986~1991年に財政の健全化が進み、鉱工業生産指数の向上により1988年には経済成長率が4.5%に達するなど、景気も明るさを取り戻した。失業率も1989~1991年には9~8%台に落ちている。しかし、そのころ、景気の過熱により公定歩合が高騰しており、それとともに1991~1993年に鉱工業生産指数が低下し、経済成長率も下降、1993年にはマイナス1.3になった。その結果、1992年から税収の伸び悩みによって財政赤字がふたたび増加し緊縮財政が求められている。1995年の財政規模は歳入1兆4952億6000万フラン、歳出1兆8365億8000万フランであり、国庫特別会計を合算すると3445億2000万フランの赤字であった。この歳出は国内総生産の23.3%を占め、イギリスの28.6%より低いが、ドイツ15.5%、アメリカ21.8%よりも高い。なお、1996年度の主要な歳出の構成比は文化・教育費22.4%、国防費15.6%、産業・運輸通信費5.3%、保健・雇用費10.8%などである。また、主要な歳入の構成比は、直接税35.8%(うち所得税17.7%、法人税10.4%)、間接税64.2%(うち付加価値税46.0%)である。
ヨーロッパ統合にむけての経済政策上の重要な課題である通貨統合が行われた。それにより、2002年1月から通貨がフランからユーロに変更となった。また、2002年の財政収支は、歳出2801億ユーロ、歳入は2301億ユーロで、500億ユーロの赤字となった。この結果、財政赤字が国内総生産(GDP)比で3.3%となり、ヨーロッパ連合(EU)の財政安定成長協定の基準違反となったため、財政改善が重要な課題となっている。
[遠藤輝明]
社会
地域構造
パリ(大都市圏)は964万4507(1999年国勢調査、2005年推計で985万4000)の人口を擁し、政治、経済、文化の一大中心地をなしている。これに次ぐ大都市としてはリヨンとマルセイユ‐エクサン・プロバンス、リールが100万を超え、ボルドー、トゥールーズ、ニース、ナント、トゥーロン、ドゥエ‐ランスが50万以上を数えるが(いずれも大都市圏人口)、パリには遠く及ばない。このように極度の中央集中のため、地方の経済活動や文化生活は活発とはいえず、あらゆる面でパリと地方(プロバンス)との格差がつねに問題となっている。とくに地図上でル・アーブルとマルセイユを結ぶ線を境にして南西にあたる諸地方は、パリを含む北東部に比べて経済開発が進まず、生活上の格差も大きい。所得の面からみると、たとえばブルターニュ地方やラングドック地方はパリ首都圏の60%程度にすぎない。また、これらの地方からの離農、人口流出はかなりの勢いで進んできた。
こうした中央集中の地域構造を是正するため、1964年、いくつかの県をまとめて広域化した計画化地域(レジオン・ド・プログラム)が全土で21(のち22)設けられ、その枠組みのなかでそれぞれの地域の開発計画を策定して開発が進められ、ある程度の成果をあげている。しかし、長い歴史をもつ中央集権の体制は一朝一夕に変更しうるものではなく、課題は今後に残されている。工業の中心は、多くがル・アーブルとマルセイユを結ぶ線の北東、すなわちパリ首都圏、リールを中心とする北部、アルザス・ロレーヌ、ローヌ川の谷などにあるが、1960年代以降は南西地方でも、ナント、ボルドー、トゥールーズなどを中心にいくつかの工業地域が生まれている。西欧先進国のなかでは高かった農民人口の割合も著しく低下し、1984年には7%、1993年には4.5%、1997年には4.0%、2003年には2.9%にすぎなくなった。
[宮島 喬]
人口
フランスは久しく人口に関しては増加の鈍い停滞的な国であった。さまざまな原因があるが、やはり二度の世界大戦で多くの青年人口を失い、そのために著しい出生減を経験してきたことが大きく作用しているといえよう。1932年以来、家族手当が制度化され、子供の数に応じて支給されてきたのも、この人口政策の観点からであった。しかし、第二次世界大戦後は人口増加に転じ、1946年に約4050万であったのが、第四、第五共和政のもとでの経済成長に伴い、1990年に5807万4215、さらに1999年には6018万5831、2005年(推計)では6281万8000と推移している。
1999年の資料によると、20歳未満の人口は24.6%、20~39歳の人口は28.1%、40~59歳の人口は26.0%、60~74歳の人口は13.6%、75歳以上の人口は7.7%となっている。人口の都市集中は著しく、首都圏(パリとその周辺地域)は全人口の16%を占め、それを除く都市圏人口10万以上の都市の人口が28%に達している。その一方で、人口500以下の農村の人口は1%に満たず、減少の一途をたどっており、こうした小コミューヌ(町村)は過疎化の悩みのなかに置かれている。
また、今日のフランスでは外国籍居住者の人口が326万3186(1999)の多数に上り、人口全体の5.6%となった。その大部分を占めるのは、南ヨーロッパ、アフリカおよび開発途上国からの移民労働者とその家族である。これは、二つの世界大戦によって人口の減少ないし増加の停滞が生じ、労働力不足をきたした結果、これを補うべく計画的に移民を導入してきたことによるもので、ポルトガル人(57万3000)、アルジェリア人(54万5000)、モロッコ人(44万5000)などの順で多くなっている。これらの移民は、主として単純労働、一部は半熟練労働に携わっており、フランス経済にとって不可欠の役割を果たしているが、その労働条件、生活条件は本国人労働者に比べてかなりの差があり、社会的な問題にもなっている。1980年代以降これら移民労働者の定住化が進んだが、2005年10月末、パリ郊外の移民ら低所得者が多く住む地域で、アラブ系を中心とした移民の若者らによる暴動が発生した。暴動はフランス全土に広がり、11月には政府が非常事態宣言を発動する状況となったが、暴動拡大の背景には、移民層の失業、差別、貧困などに対する不満があったと考えられる。
すでに述べたように農業人口は5%を割り、他方、カードル層(管理職、専門職、技術職)や事務員が増加し、いわゆる「新中間層」に該当する層が50%近くを占めるようになっている。また経済の脱工業化に伴い、サービス業従事者も増加している。なお、有業人口に占める女子の割合も高まり、1984年の42%から1999年の57%へと増加をみている。結婚し、出産してのちも仕事を続けるという女性が増え、30歳代の平均の有職率が77%を超えるに至っている点は、女子の社会参加の増大を示すものとして注目されてよい。
[宮島 喬]
国民生活
国民1人当りの平均年間所得は2万4431ドル(2003)であり、ヨーロッパの国々のなかではスイス、スウェーデン、デンマーク、ドイツなどに次いで高い。しかし、すでに述べたように、パリ首都圏を含む北東地方と、後進的な南西地方の間には所得格差がある。また、高所得層と低所得層との開きも欧米先進国のなかでは大きいほうに属する。これを職業階層別にみると、経営者、自由業および上級のカードルの所得がとくに高く、中間層をかなり引き離し、生産労働者のそれの平均4倍前後にも及んでいる。これは、上層への資産の偏在を意味するとともに、のちに述べるこの国の一種のエリート養成の教育制度をも反映している現象である。この所得の不平等の是正が政策の重要な課題とされ、法定最低賃金の引き上げ、最低所得補償制度の実施、税制改正の努力が進められている。上級カードルと生産労働者の所得の倍率は、1970年4.5倍、1975年3.9倍、1980年3.6倍と、1970年代にやや縮小の傾向がみられた。なお、所得の面で事実上最下層をなすのは、すでに述べた移民労働者層(フランス国籍をもつ者も多い)である。彼らの多くは法定最低賃金に近い所得に甘んじている。加えて、熟練水準が低く、社会的差別も重なり経済的不況期には真っ先に雇用不安にさらされる存在であり、社会経済的不平等はここにいちばんしわ寄せされているといってよい。
生活様式の面で今日のフランス国民を特徴づけるものの一つは、バカンスの名でよばれる長い有給休暇とそれを楽しむ習慣である。バカンス制度は1936年のいわゆる人民戦線内閣に始まるといってよく、同内閣は週40時間労働と年に15日の有給休暇を定めた。この有給休暇は以後しだいに延長され、1969年には4週間近くとなり、さらに1982年には5週目が認められるに至った。ことに「グランド・バカンス」grandes vacancesとよばれる夏季休暇は、一般の勤労者はもとより、カードル、経営者、自営業主などにも広く普及しており、夏のバカンス出発率は国民全体で60%に達し、1人当り休暇の平均利用日数も27日強に及んでいる。この時期、地中海岸、大西洋岸、あるいは国境を越えてスペイン、ポルトガル、イタリアなどに向けて大きな人口移動がおこり、都市生活は活気を失い、政治、経済の動きも鈍りがちである。国民のうちには、夏のバカンスで1年の貯えをほとんど使い果たし、秋からまた翌年の夏のバカンスのために働き始めるという者も少なくない。ただし、この長期有給休暇の制度化は、1980年代から「雇用の分かち合い」、高失業率への対応のために必要と認識されるようになっており、雇用政策との関連が無視できなくなっている。
[宮島 喬]
労働
フランスでは、労働組合の法的承認は19世紀後半とかなり遅く、それに加え、いくつかの労働組合センターが分立しているため、労働者の組合への組織率はかならずしも高くない。1895年結成というもっとも長い歴史をもつ「労働総同盟」(CGT)は、共産党と緊密な連携関係を保ってきた。このCGTから1948年に分裂した非共産党系の労働組合センターとして「労働者の力」(FO)がある。また、その前身がカトリック系の労働組合組織であった「フランス民主労働連合」(CFDT)は、現在では社会党と密接な関係を保っている。このほか、教員は以上とは別個の組織をもっており、「全国教員連盟」(FEN)を結成している。これら労働組合の活動の力によって、労働条件、労働時間はしだいに改善されてきた。1936年の人民戦線内閣のもとで労働時間は週40時間と定められたことはすでに述べたとおりであるが、ミッテラン社会党政権下の1982年にはさらに週39時間となり、今日では週5日制も広く普及し、年次有給休暇も拡大の一途をたどっている。さらに2000年にはジョスパン内閣によって週35時間労働制が導入された。しかし、経済競争力の低下を招くとして、2005年に就業時間延長を認める法が成立している。また1952年以来職種を問わず定められた最低賃金については、労働組合はその引き上げに熱意を注いでいる。
他方、政府も、第二次世界大戦後、雇用問題や労使関係の調整を自らの責任とみなすに至った。それは、たとえば従業員100人以上の事業所に「企業委員会」の設置を法によって義務づけるといった点に現れている。これは、従業員から選出された代表と経営側との間で労働条件の改善等について協議を行うための機関である。また、1950年の法律では、雇用主と被雇用者の間の団体協約の締結が義務として定められ、採用、解雇、給与などに関する条件がその対象とされた。なお、1945年から1946年にかけて、のちに述べるように諸種の社会保険が整備・確立されてきた。しかしEC(ヨーロッパ共同体)からEU(ヨーロッパ連合)へとヨーロッパの統合が進むなかで、一国のなかでの雇用、労働政策には限界が生じており、共通社会政策の推進、EU社会憲章の法制化などが望まれている。
1980年代から、欧米全般での景気後退のなかで失業者が増大し、失業率は1997年には12.4%に達したが、その後はやや低下し、2004年には10.0%となっている。とりわけ若年層において失業率は高い。このため労働者の雇用防衛の運動も強いものがあり、1990年代に課題となった国有企業民営化、企業の整理、統合に伴う合理化には、激しい抗議行動が起きた。なお、こうした景気後退のなかで事実上移民労働者の導入は停止されているが、現にフランスに滞在中で失業の状態にある移民の数はかなり多く、社会問題ともなっている。また2006年3月に、若年労働者を雇用から2年以内なら無条件に解雇できるようにした「若年向け雇用制度(CPE)」をめぐって、大規模な反対デモが発生した。そのため、制度の導入は撤回され、シラク体制に大きな打撃を与えた。
[宮島 喬]
社会保障
フランスの社会保障の諸制度は、すでに述べたように1945~1946年にかけて整備・確立されているが、さかのぼれば、1930年の社会保険法(勤労者、農業労働者の廃疾、退職、死亡など)や1932年の家族手当法がその基礎となっているといってよい。社会保険については、その原理がすでにヨーロッパの主要国に普及し終えた時期に初めて制度化されるなど、立ち遅れをみせたが、家族手当の面では、この国特有の人口問題の解決という強い要請もあって、ヨーロッパのなかでも制度化は早かった。
1946年の法律によって明確化された社会保障の諸原則は、イギリスのビバリッジ・プランから部分的に影響を受けているといわれ、古くからある保険の観念を保障の観念に置き換え、賃金とは別個に、国民的連帯性により拠出される社会的所得を設けようとするものであった。保険は義務的であり、老齢、廃疾、死亡などの保険が定められた。受益権は当初は賃金生活者に与えられたが、全フランス人に拡大されるべきものとされ、1968年からは手工業者や独立自営業者にもこれが適用されていく。
社会保障支出費は、約1兆5000億フラン、国内総生産の30%近くを占める。その財源構成は、使用者50.6%、被保険者23.4%、国、地方公共団体23%となっている(1992)。一般保険の財源は使用者と被保険者によって負担されるが、労災補償と家族手当は使用者のみによって負担される。老齢年金の受給年齢は60歳からで、この時までに37.6か月の被保険期間があれば、完全年金が保証され、被保険期間がこれに満たない場合には比例年金が適用される。支給額はもっとも所得の多かった(退職直前の、ではない)10年間の平均賃金年額の50%に相当する額とされる。なお、2004年の社会保障給付金は4804億4200万ユーロとなっている。
特色があるのは、きわめて多種に及ぶ家族手当である。この制度は1939年の家族法典のなかに盛られ、戦後は社会保障制度のなかの主要なものの一つとなった。子が1人の場合には支給されないが、2人以上の子をもつすべての家庭(外国人家庭も含めて)に所得制限なしに適用される。支給額は算定された基礎月額に対する一定の割合で決められるが、3子、4子、5子以上と増えるごとにその割合は大きくなり、子供の加齢に応じても割増しが行われる。この他、家族給付としては、家族補償手当、遺児手当、単親手当、乳幼児手当、さらに住宅手当などがあるが、このなかで乳幼児手当などには出産奨励という給付のねらいが強く現れている。
[宮島 喬]
教育
大革命のさなかに布告された一七九一年五月三日憲法は、「すべての人間にとって不可欠な教育を無償とし、すべての市民に共通であるような公教育が創設されるであろう」と述べ、あまねく国民に教育を受ける権利があることを宣言した。しかし、公教育をその根幹とする現在の教育制度が確立されるのは第三共和政の時期である。その理念とするところは、教育の自由、すなわち公私両教育の併存(ただし、比重は公教育が大きい)、公教育の無償と非宗教性(ライシテ)、そして公開試験による選抜と資格付与、などである。なお、この最後の点は、激烈な試験を勝ち抜いてきた少数の者に英才教育を施すこの国独特の高等教育制度の存在と結び付いている。第二次世界大戦後、ランジュバン‐ワロン教育改革案などによって進学制度の民主化の努力や、大学進学者の増大にこたえての諸改革が行われてはきたが、高等教育のあり方はつねに論議の的となっている。
義務教育は6歳から16歳までの10年間で、小学校から中学校(コレージュ)を経て高等中学校(リセ)または職業高校(LEP)の1年次修了時までがこれにあたる。高等中学校の3年次修了後、大学入学資格(バカロレア)を取得して高等教育に進む者もあれば、また職業教育高校を卒業して実社会に出る者もある。近年、バカロレアの取得者は増え、同年齢層の60%前後を推移している。ただしここには比較的最近設けられた科学技術バカロレア、職業バカロレアの取得者も含まれていて、彼らの場合、高等教育に進む者は少ない。これを差し引いた普通バカロレアの取得者は同年齢層の約35%である。大学(ユニベルシテ)は、標準的には18歳からの3年間で、一般教育的な第1課程と専門の第2課程に分かれる。従来、大学では応用的な科学や技術教育が比較的軽視され、純粋科学と人文教育の偏重の傾きがみられた。また、大学卒業生の就職難は1970年代から強まった。このため、1970年代、1980年代には幾度か実社会、産業界の要請にこたえるように専門課程の改革が行われてきたが、反面これは大学の職業教育機関化であると学生の反発も招いた。
バカロレア取得者には門戸が開かれる一般の大学に対して、厳しい試験の結果入学を許される高等専門学校(グランゼコールgrandes écoles)が別にある。したがって、フランスの高等教育は二元化しているといってよい。後者に進学するためには、バカロレア取得後、通常、有名リセのなかに設けられた「受験準備級」で2年間勉強し、入学試験を受けることになる。有力なグランゼコールでは、高度に専門的でありまた実際的でもある教育が行われ、卒業後はその席次順に、官庁、企業などでそれぞれに高い地位が与えられていく。このようにグランゼコールはいわゆるエリート養成機関としての性格を濃厚にしており、それだけに、一般の大学との勉学条件や教育条件における大きな格差がしばしば論議の的となるのである。
[宮島 喬]
文化
「フランス文化」への疑い
フランスは世界の国々のなかでもとりわけその文化によって注目される国であり、またフランス人の間でも自国の文化を誇りたいせつにする気風が強いことは確かであろう。フランスの社会では伝統的に文化に大きな役割と高い価値が与えられており、そのことは国家のレベルにおいても当てはまる。文化省が設立されたのはたかだか50年前(1959)にすぎないが、フランスには国家らしきものが成立して以来つねに有形無形の「文化政策」が存在していた。こうしてフランスが文化の国であり、フランス文化が優れた文化であることは、パリを中心としたいわゆる高級な文化(ハイ・カルチュア)を問題にする限り、一見、自明なことのように思われる。だがそれは、はたしてフランスの文化なのであろうか。また文化の定義を個々人の生活様式に深くかかわるものとして考えるとき、そもそも「フランス文化」なるものは存在しうるのであろうか。これまでフランス文化の存在が自明のこととして論じられることが多かっただけに、われわれはそれを疑うことから出発してみよう。
実際、一つの文化の単位を国境によってくぎることが可能であろうか。パリの文化はフランスのブルターニュ地方やマッシフ・サントラル地方の農民の文化よりも、むしろロンドンやニューヨークの文化に近いし、同じパリであっても知識人の生活と労働者の生活の違いは大きい。しかもパリ在住の知識人にしても労働者にしても、かなり大きな部分を外国人や移民が占めており、それらの異質な要素を排除すれば、フランスの社会そのものが崩壊するだろう。都市と農村の文化的な差異は別としても、フランスの地方にはパリと異なったさまざまな異質な文化が存在している。フランスは人種の混合体であって、特定の人種の特徴からフランス文化を論じることはできない。フランス語は一つの目安となるだろう。だが19世紀のなかばころには、まだフランスの地方の住民の半数はそれぞれの方言を用いていて、いわゆるフランス語が使えなかったことを忘れてはならないだろう。それにこの場合、海外諸県や海外自治体、カナダ、スイス、ベルギーあるいはアフリカにおけるフランス語圏の文化との関係をどのように考えればよいのであろうか。たとえばカナダのケベック州の文化は、フランス語を話す住民による文化の、フランスとは異なったもう一つの可能性を示している。
こうして単一不可分の共和国に見合った単一不可分の均質な「フランス文化」の存在は一種の神話であり、中央集権的なイデオロギーの生み出した一つの幻想にすぎないのではないかという疑いが強くなる。だがここで注意すべきは、かりにそれが幻想にすぎないとしても、そのような幻想自体もまたすでにフランス的な文化の特徴的な一側面をなしているということである。現在フランスとよばれている国の文化の特徴を観察するためには、文化を変化の相のもとにとらえて、その多様性と普遍性に注目しつつ、対立と葛藤(かっとう)、そして局地的な均衡と調和を繰り返しながら形成されつつあるダイナミックな文化のモデルを考える必要があるだろう。以下そのような文化モデルを思い描いた場合に、重要だと思われる特徴を要約的に記しておこう。
[西川長夫]
多様な民族、多様な文化
近代国家の形成という観点から眺めるとき、すでにみたように、フランスは地理的にきわめて恵まれた条件を備えていた。農用地率は55%を超えており、「うまし国フランス」の呼び名にふさわしいこの豊かな土地には、古来さまざまな人種が住み着き、また通り過ぎていった。南フランスのドルドーニュ地方で発見された人骨(クロマニョン人)は旧石器時代後期に属するものとされ、ラスコーの洞窟(どうくつ)の壁画は1万7000年前、ブルターニュの巨石文化は紀元前2000年ぐらいのものと推定されている。だが現在のフランス文化に直接かかわる歴史的事件としては、前9世紀におけるケルト人のガリア移住以後を視野に収めればよいであろう。
ドナウ川流域からガリアの地に移動してきたケルト人の社会は、貴族(武士)、平民、僧侶(そうりょ)に分かれ、優れた鉄器文化と樹木や泉を崇拝し、霊魂の不滅を信じる信仰(ドルイド教)をもっていた。ローマとキリスト教による支配ののちも、ケルト文化は民間伝承や習俗として残り、フランス文化の祖先を求めれば、多くの場合、900年にわたってガリアの地を支配したケルト文化に行き着くようである。
前2世紀の末から南ガリアに進出していたローマの勢力は、前58~前51年にかけてカエサルに率いられた軍勢によってガリア全土の征服に成功した。当時のガリアの状況やガリア気質とでもいうべきものを、われわれは今日カエサルの残した『ガリア戦記』によって知ることができる。以後500年にわたるローマの支配は言語(ラテン語)、法律、行政制度、宗教、建築などの領域にきわめて大きな影響を残した。現在も残されているニームやアルルの神殿や闘技場、ポン・デュ・ガールの水道橋、パリのクリュニー美術館の庭にある浴場跡など、当時の雄大なローマ文化をしのばせる遺跡がフランス各地に散在している。今日に至るラテン系文化の最初の特徴はこの時期に深く刻まれた。
紀元後4世紀に始まったゲルマン人の大移動はガリアの地にさまざまな部族を送り込んだが、最終的な支配者としてこの地に定住したのは、ライン川の下流から移動してきたフランク人であった。476年の西ローマ帝国滅亡後、フランク人の首長クロービスが王となって481年フランク王国が建設される。だがゲルマンの支配と影響力がとくに強かったのはロアール川以北であり、ロアール川以南にはローマの影響が残存した。こうして北フランスと南フランスの風土的な差異に重ね合わされて、今日にまで続く南北の文化的な違いが形成される。北のゲルマン法に対する南のローマ法、北の単婚家族・均分相続に対する南の拡大家族・長子相続制、北のウマを中心とした三圃制(さんぽせい)と南のウシによる二圃制、さらにはオイル語とオック語といった言語の違いなど、対照的な文化が存在したのであった。最初に高度な宮廷文化が誕生したのは南フランスのほうであったことも忘れてはならないだろう。
ガリアの地に展開された諸民族の移動と定住の跡をたどることは、この地が諸民族にとっていかに開かれた土地であり、ヨーロッパにおける民族の交差点をなしていたことを証明することになる。地中海と大西洋の二つの海に面しているフランスでは、縦横に走る河川を通じて二つの海が容易に結び付く。自然国境のように存在するピレネー山脈やアルプスの山岳地帯、あるいはライン川などの大河も、交流を妨げる大きな障壁とはなりえなかった。フランスの自然的な条件はその地にいくつかの文化圏や政治権力を成立させる程度には変化に富んでいたが、それらを孤立させ交流を妨げるほどの決定的な障壁は存在しない。こうして多様な人的構成と多様な文化の存在を許したこの土地は、国民的な文化の成立以前に、すでにある種の普遍的な文化への志向と可能性を秘めていた。
[西川長夫]
普遍的な文化への志向
フランク王国の最初の王であったクロービスが496年にランスの聖(サン)レミの洗礼を受けてカトリックに改宗したことは、それ以後のフランスにおける王権とカトリックの密接な関係の端緒として重要な事件であるばかりでなく、普遍性を目ざす国民的な文化におけるカトリックの役割を考えるうえでも興味深い。クルティウスが『フランス文化論』で指摘しているように、フランスにおける文化意識(したがって国民的な感情)の高揚期には、つねにキリスト教が大きな役割を果たしている。11世紀の後半から12世紀のなかばに至る武勲詩(シャンソン・ド・ジェスト)やゴシック芸術、あるいは十字軍などは、いずれも国民的な使命をキリスト教に結び付けるものであった。13世紀初頭の南フランスにおけるアルビジョア十字軍の背後にあったのは、異端討伐の名を借りた北による南の支配と統一の意志である。15世紀中葉のジャンヌ・ダルクの出現は、国民的な感情と宗教的な感情の融合に特色が認められる。その二つの感情のいずれが歴史の主流であったかは、フランス全土に支配を及ぼすような強大な王権の成立とともにおのずと明らかになるだろう。シャルル8世やフランソア1世のイタリア遠征は、領土拡大の野心とともにフランスの文化的な覇権の願望を秘めていた。国民的な感情と普遍的な文化への志向が合体してそれにふさわしい表現形式をみいだしたのは、ようやくルイ14世時代の古典主義においてであろう。文化的な普遍主義が政治的な統一と拡大のイデオロギー的な表現でありえたことはいうまでもない。
18世紀の啓蒙(けいもう)主義は、ブルジョアの時代にふさわしい、キリスト教にかわる新しい普遍的な文化の理念を提供する。人類の歴史を進歩の相のもとにとらえ、万人が享受しうる普遍的な価値を想定する「文明」という概念は、しかしながらフランスの国民的な文化が普遍的なものであるという確信に支えられていた。フランス大革命のナショナリズムはこの「文明」概念に支えられており、イギリスを除く全ヨーロッパを席捲(せっけん)したナポレオン軍は、その意味では一種の近代的な十字軍である。現在のフランスにも根強い中華思想は、この「文明」概念に深くかかわっている。
[西川長夫]
フランス語にみる普遍性と多様性
フランス精神の具現として、フランス的なものの第一にあげられるフランス語にも、この普遍性と多様性の対立葛藤(かっとう)の歴史が深く刻まれている。フランス語の母胎はガリアの地に広がって変形していった俗ラテン語であった。フランク人のゲルマン語はゲルマン的な生活や制度にかかわる数多くの語彙(ごい)を残し、音韻体系にも大きな変化をもたらしたが、それ自体がラテン語にかわることはできなかった。北フランスのオイル語が南フランスのオック語を放逐してゆく過程は、北フランスの政治的な支配の確立と対応しているが、しかしその間フランス語は統辞法の確定を進める一方で、近接の言語から多くの単語を導入して豊富な語彙を形成する。国語の統制が強力に推進されるのは17世紀の絶対王政の成立とともにであり、辞書の編纂(へんさん)を通じて国語に強力な規範を与える公的な機関としてアカデミー・フランセーズが設立されたのは1635年のことであった。18世紀におけるリバロールの「明晰(めいせき)でないものはフランス語でない」という有名なことば(『フランス語の普遍性について』1783)はまさしくフランスの文化的な覇権の宣言であったが、それが言語の明晰性の主張として述べられているところに特色がある。フランス語が明晰でなければならぬのは、それが普遍的な理性の実現を目ざすものだからであるが、他方この普遍的な理性は学者の科学的な研究や高邁(こうまい)な精神の働きにではなく、サロンの会話や市民の日常生活のなかに求められたところにフランス的な特色が認められよう。
フランス大革命はジャコバン派とジロンド派の対立によって中央集権的な普遍主義と地方分権的な個別主義の対立を浮き彫りにしたが、言語の問題がもっとも劇的な様相を示したのも革命期のフランスにおいてであった。唯一不可分の共和国の理念は、いわゆるフランス語の法令を地方のことばに翻訳することを義務づける一方で、国語としてのフランス語の支配と方言の抑圧にかつてない強い力を発揮したからである。ジャコバン的なデモクラシーと文明の理想は、地方の伝統的で多様な文化の破壊に導いたのであった。だがそうした中央政権の意図がかならずしも成功しなかったことはその後の歴史が示している。フランスの地方の農民が国民的な統合のなかに組み入れられる時期はきわめて遅く、ようやく20世紀初頭においてであるとする説(ユージン・ウェーバー『フランス人になった農民』Peasants into Frenchmen――The Modernization of Rural France。1976)もあるほどである。またパリにおいても規範的なフランス語と大衆によって実際に使われることばの差異は大きく、「ビラング(2国語)の国」といわれていることを付け加えておきたい。
[西川長夫]
「国民性」といわれるもの
フランスの国民性についてもっともみごとに述べているのは、おそらくモンテスキューの次のことばであろう。「社交的な気質、開いた心をもち、生活を楽しみ、自分の考えを伝えることを好み、またそれをやすやすと行い、活発で人当たりがよく、陽気で、ときには軽率で、しばしば不謹慎だが、それらに加え勇気があり、寛大・率直で、なにほどかの誇りさえもっている国民」(『法の精神』)。シーグフリードはイギリス人の不屈性とドイツ人の規律に対してフランス人の知性を強調した。マダリアーガはスペイン人の美的受動性やイギリス人の行動性に対してフランス人の思考と享楽への志向を指摘する。だがパリ中心のフランス文化の説明としては説得的なこうした性格特性に対しても、ドフィーネ地方の農民の非社交的なはにかみと頑固さ、ブルターニュの農漁民の冒険心と瞑想(めいそう)性、等々地方的な特色をあげた反論が可能である。むしろフランスの文化も個人も普遍性と多様性との矛盾と葛藤のなかでときに引き裂かれ、ときに調和的であるというべきだろう。フランスの個人主義は国家権力や社会の全体主義的な流れには強固に抵抗するが、ときに独裁者を容易に受け入れる。フランス人の自由の感覚はきわめて無政府的で享楽的であるが、ナショナリズムの波に飲まれやすい。フランス人は外国人と外国の文化を寛大に受け入れるが自らは外に出て行こうとしない、等々。
[西川長夫]
国家の時代の文化
フランスの国家予算のなかで、教育・文化部門の占める割合は、他の諸国と比べて例外的に高い(ミッテラン政権下では22%を超えた)。フランスは普遍的な文明の概念を通して、中央集権的な高度の文化の形成に成功した国である。コレージュ・ド・フランス(1530)、アカデミー・フランセーズ(1635)、コメディ・フランセーズ(1680)、中世に起源をもつユニベルシテ(総合大学)やフランソア1世の王室図書館に始まる国立図書館、さらに時代は下るが、ルーブル美術館(1791)、オペラ座(1875)なども含めて、大部分はパリに存在するこれらの古い文化的機関は、そうした国民的な高い文化を代表するものとして現在も機能している。またそうした古い文化装置と並んで、ポンピドゥー芸術文化センターや新オペラ座など、新設のさまざまな文化機関や建造物がパリの街を彩っている。これらの諸制度を通じて生み出された文化の輝かしさは、それらに活力を与えてきたフランスの地方の文化的な豊かさと多様性を覆い隠すように作用してきた。だがパリに代表される文化は国家の時代の文化であって、もしそのような強力な国家の時代が終わりを告げようとしているとすれば、フランスの文化的な未来はどうなるのであろうか。1970年代に入ってから目だち始めた地方分権によるフランス活性化の試みと地方文化再興の運動はその点でも興味深い。この点でとくに注目されるのは、ヨーロッパ統合がECからEUへと展開されるなかで生じている文化変容の動きである。ヨーロッパ共同体の実現は、ヨーロッパ人やヨーロッパ市民という理念の追究でもあり、内包する多様性や差異への権利が認められるようになってきた。しかし、それは一方で、民族や伝統に執着する極右的ナショナリズムを導き出し、フランスの国民文化の概念に深い動揺をもたらしている。たとえば、多言語・多文化主義が論じられ、外国語の学習が推奨される一方、フランス語の擁護が叫ばれたり、ヨーロッパ内で人と物の移動の自由が実現しつつある一方、マグレブ地域(アフリカ北西部)からの移民が排除されたり、ユダヤ人墓地が荒らされるなど、反ユダヤ主義の根深い動きもある。また、ヨーロッパ統合に伴う地域的な再編は、かっての中央と地方、中核と周辺の関係に変化をもたらし、アルザスのように新たな照明をあびる国境地帯もあれば、コルシカやブルターニュのようにいっそうの周辺化をおそれる地域もあり、地域文化の位置と意味にも変化が現れている。
[西川長夫]
新聞・テレビ・ラジオ
最後にフランスの新聞・放送事情について簡単に触れておこう。日刊紙は全国に81紙あり、うち10紙がパリ発行の中央紙、経済やスポーツなどの専門紙が10紙で、残りが地方紙である。パリで発行される中央紙の代表的なものには、『フランス・ソワール』(夕刊紙、7万7400部)、『ル・モンド』(同、36万部)、『ル・パリジャン・リベレ』(36万部)、『フィガロ』(34万5000部)などがある。地方紙ではレンヌの『ウエスト・フランス』(76万5000部)、リヨンの『ル・プログレ』(25万9000部)、ボルドーの『スッド・ウエスト』(32万部)、グルノーブルの『ラ・ドフィーネ・リベレー』(25万3000部)などの有力紙がある(数値はいずれも2002)。
テレビ放送は地上波テレビ、衛星テレビ、ケーブルテレビからなる。おもなチャンネルはティー・エフ・ワン(TF1)、フランス・ドゥ(France 2)、フランス・トロワ(France 3)、カナル・プリュ(Canal Plus)、ラ・サンキエーム(La Cinquième)、エム・シス(M6)、アルト(Arte)の7局である。
[西川長夫]
日本との関係
日仏交流の先駆者たち
フランス人が日本を最初に知ったのはマルコ・ポーロの『東方見聞録』(1298)の記述を通じてのことであった。一方、日本人は1549年(天文18)に来日した宣教師フランシスコ・ザビエルによってフランスのことを初めて知ったものと考えられる。だが、最初にフランスの地に足を踏み入れたのは、伊達政宗(だてまさむね)がローマ教皇に使節として派遣した支倉常長(はせくらつねなが)とその一行である。1615年(元和1)10月、常長一行は暴風雨を避けるためにスペインのバルセロナからイタリアのジェノバに向かう途中で南フランスのサン・トロペに上陸し、3日間ほど滞在した。現在、ボークリューズ県カルパントラのアンギャンベール図書館に常長一行に関する記録(羊皮紙6葉)が残されている。これにはサン・トロペの領主たちがみた日本人の印象が綴(つづ)られている。一方、最初の来日フランス人は、トマゾ・サント・ドミンゴというスペイン風の名を用い、ドミニコ派の僧服をまとってマニラ経由で琉球(りゅうきゅう)に潜入したギヨーム・クールテ神父であった。だが、クールテ神父はただちに捕らえられ、1年後には長崎に送られて拷問(ごうもん)のすえに斬首(ざんしゅ)処刑された。1637年(寛永14)9月29日のことである。キリシタン禁制下のクールテ神父の殉教のあと、日仏の直接の交流は絶えたが、オランダ商館を通じて間接的な交流は行われた。アンブロアーズ・バレの『外科学概論』(1551)、ノエル・ショーメルの『百科事典』(邦訳名『厚生新編』)などがオランダ語訳本から日本語に翻訳されてフランスの科学が紹介された。モンタヌスが1680年(延宝8)にアムステルダムでフランス語による『日本皇帝のもとに遣わされたオランダ連合州東インド会社の使節団』を著し、クラッセ神父の『日本教会史』(同『日本西教史』)、シャルルボア神父の『日本史』(1725)などが刊行され、日本の地図も出回る。1787年(天明7)8月、ラ・ペルーズは宗谷海峡を探検し、これを「ラ・ペルーズ海峡」と命名した。
[富田 仁]
日本文化のフランス流入
17、18世紀リヨンの絹織物は中国物をモデルにしたが、日本の錦(にしき)もオランダ経由で入手、珍重された。牡丹(ぼたん)のモチーフが長いこともてはやされた。18世紀には日本から輸入した漆塗りのパネルで家具を飾ることも流行し、マリ・アントアネットまでが日本の漆器を集めるほど日本趣味が深まった。19世紀、ポール・サバティエは日本の植物を採集し、フランシェとの協力でフランスに紹介し、『花彙(かい)』と題する著作を刊行した。また、1867年のパリ万国博覧会で浮世絵が展示されるが、それに先だってゴンクール兄弟が1851年に初めて日本の美術品を購入し、『北斎(ほくさい)』『歌麿(うたまろ)』を出版し、印象派の人々に反響をよぶというように、日本趣味(ジャポニスム)が芸術界に一大旋風を起こした。後のオートビーユ派、ナンシー派などの美術家にもその感化が及んでいる。パリの社交界では日本の扇が使われ、サン・サーンスは日本に取材したオペラ『黄色い王女』(1872)を発表するなど、日本趣味は広がった。ロダンが日本の舞踊家ハナコのデッサンや彫刻を制作し、ポール・クローデルが二度来日して、『繻子(しゅす)の靴』など日本の影響をみせる作品を書いた。日本語の研究も、1863年にレオン・ド・ロニーによって東洋語学校に日本語講座が開かれたことで本格化した。ロニーは多数の日本語研究の書を残し、新聞『よのうはさ』も刊行した。
[富田 仁]
フランス語辞書の編纂
19世紀に入ると、日本でもフランス語の学習の機運が兆す。フランソア・ハルマの蘭仏(らんふつ)辞書に基づいたいわゆる『ハルマ辞書』がつくられ、江戸時代の蘭学者に大きく貢献するが、1817年(文化14)ごろには、フランス系オランダ人のピーテル・マリンの仏蘭辞書から、長崎のオランダ通詞本木正栄(もときまさひで)が中心になってオランダ商館長ドゥーフの指導下に『拂郎察辞範(ふらんすじはん)』『和仏蘭対訳語林』を編纂(へんさん)する。1854年(安政1)ごろ、村上英俊(むらかみひでとし)が佐久間象山(さくましょうざん)に頼まれて、独学でフランス語を学んだ知識を生かして仏英蘭3か国語対照辞書『三語便覧』を刊行する。『五方通語』『仏語明要』などの辞書の編纂に加えて、私塾・達理堂におけるフランス語教育によって村上英俊は幕末・維新のフランス学の第一人者となる。その功労で晩年には東京学士会院会員に推され、フランスからレジオン・ドヌール勲章の「シュバリエ」(勲五等)を叙勲された。
[富田 仁]
技術・文化交流の活発化
日本とフランスの外交折衝も琉仏条約締結(1855)を経て、1858年に日仏修好通商条約が結ばれることで本格化し、1864年(元治1)に横須賀(よこすか)製鉄所設立が建議され、大尉シャノアーヌCharles Sulpice Jules Chanoine(1835―1915)を団長とするフランス軍事顧問団の来日、横浜仏語伝習所の開校、さらには1867年(慶応3)パリ万国博への将軍の名代・徳川昭武(とくがわあきたけ)(1853―1910)の派遣など、幕府とフランスの結び付きは密接になった。明治維新後も、1872年(明治5)に開業した最初の官営工場・富岡製糸場へのフランス式製糸技術の導入、生野鉱山(いくのこうざん)に技師コワニー、ガス事業にプレグランHenri Auguste Pélegrin(1841―1882)の雇い入れなど技術面でフランスに多くを負っている。日本からも西陣(にしじん)の織工がリヨンに研修に赴き、山梨県勝沼の2青年がぶどう酒の技術を学びにトロアに留学するというように日仏の技術交流が盛んになる。また、法律顧問として活躍したボアソナードの法典編纂、明法寮などでのフランス法の教育の功績も見落とせない。明治期では、ジャン・ジャック・ルソーの思想の移植者・中江兆民(なかえちょうみん)の存在は大きい。自由民権運動に兆民の『民約訳解』(ルソーの『社会契約論』の訳題)やモンテスキューの『法の精神』などが与えた影響は大きい。
日本人留学生・黒田清輝(くろだせいき)がパリのラファエル・コランに学び、1930年代にはエコール・ド・パリで藤田嗣治(ふじたつぐはる)が活躍するというように、フランス画壇との交流も活発になる。ジョルジュ・ビゴー(滞日1882~1899)が明治の社会・風俗を風刺し、雑誌『トバエ』を刊行する。ピエール・ロチが二度にわたり来日し、『お菊さん』(1887)、『日本の秋』(1889)などを発表する。クロード・ファレルClaude Farrère(1876―1957)の『戦闘』(1909)のヒロインの名にゲランの香水「ミツコ」の名が由来する。
[富田 仁]
会館・学会設立と経済交流
1924年(大正13)、詩人大使ポール・クローデルは渋沢栄一と図り、日仏文化の探究、交流、伝播(でんぱ)をその使命とする文化機関として日仏会館を発足させ、『日仏文化』などの機関誌のほか、『日本歴史辞典』ほかの学術書をも刊行している。この種の団体としては1886年(明治19)に仏文会を改組した仏学会が組織されたのが最初である。今日では、各大学の教師・研究者によって、日本フランス語・フランス文学会、日本仏学史学会など全国的規模の学会が組織されて活動を重ねている。フランス語学習人口も第二次世界大戦後に急増している。1878年(明治11)6月のジュール・ベルヌの『八十日間世界一周』の翻訳(川島忠之助(かわしまちゅうのすけ)訳)に始まるフランス文学の翻訳・紹介もしだいに活発になり、主要作品のほとんどが伝えられるようになった。第二次世界大戦後はサルトル、カミュなどの実存主義思想が迎え入れられ、1953年(昭和28)には日仏文化協定も結ばれた。最近では、1997年パリに日本文化会館が開館、1997年から1998年にかけて「フランスにおける日本年」が開催された。1998年から1999年には「日本におけるフランス年」も開催されている。
一方、日仏間の産業、経済面での交流も、1971年以降はヨーロッパ共同体(EC)、ヨーロッパ連合(EU)との間で貿易交渉を行っているが、交流は盛んであり、2004年のフランスの日本からの輸入額は84億7673万ドル、フランスの日本への輸出額は67億6253万ドルとなっている。
[富田 仁]
『井上幸治編『世界各国史2 フランス史』(1968・山川出版社)』▽『Y・ラコスト他著、岡津守彦他編、高橋伸夫訳『フランス――その国土と人々』(『全訳世界の地理教科書シリーズ1』1977・帝国書院)』▽『河野健二著『世界現代史19 フランス現代史』(1977・山川出版社)』▽『日高達太郎著『ふらんす 味覚と風土』(1977・柴田書店)』▽『谷岡武雄著『フランス』(木内信藏編『世界地理7 ヨーロッパⅡ』1978・朝倉書店)』▽『高橋伸夫著『フランスの都市』(1981・二宮書店)』▽『J・プズー著、柏岡珠子訳『フランス――風土と生活』(1982・三修社・フランス教養叢書)』▽『『JETRO貿易市場シリーズ230 フランス』(1983・日本貿易振興会)』▽『菊池一雅著『フランスの産業と地域』(1983・大明堂)』▽『谷岡武雄著『フランスの都市を歩く』(1983・大阪書籍・朝日カルチャーVブックス)』▽『A・ヤング著、宮崎洋訳『フランス紀行』(1983・法政大学出版局・叢書ウニベルシタス)』▽『外務省監修『世界各国便覧叢書 フランス共和国』(1984・日本国際問題研究所)』▽『日高達太郎著『ふらんす 音の風景』(1989・六興出版)』▽『R・クロジエ著、鈴木昭一郎・青木伸好訳『フランスの地理』(白水社・文庫クセジュ)』▽『J・シャルロ著、野地孝一訳『保守支配の構造 ゴリスム1958―1974』(1976・みすず書房)』▽『舛添要一著『赤いバラは咲いたか――現代フランスの夢と現実』(1983・弘文堂)』▽『桜井陽二著『フランス政治体制論――政治文化とゴーリズム』(1985・芦書房)』▽『J・E・S・ヘイワード著、川崎信文他訳『フランス政治百科』上下(1986、1987・勁草書房)』▽『中木康夫編著『現代フランスの国家と政治』(1987・有斐閣)』▽『藤村信著『パンと夢と三色旗と――フランス左翼の実験』(1987・岩波書店)』▽『P・ビルンボーム著、田口富久治監訳『現代フランスの権力エリート』(1988・日本経済評論社)』▽『奥島孝康・中村紘一編『フランスの政治』(1993・早稲田大学出版部)』▽『M・デュベェルジェ著、時本義昭訳『フランス憲法史』(1995・みすず書房)』▽『J・ボーミエ著、青山保訳『フランス財閥物語』(1971・ダイヤモンド社)』▽『井上隆一郎・伊沢久昭編『フランス・イタリアの政府と企業』(1975・筑摩書房)』▽『藤本光夫著『転換期のフランス企業』(1979・同文舘出版)』▽『原輝史編『フランス経営史』(1980・有斐閣)』▽『遠藤輝明編『国家と経済――フランス・ディリジスムの研究』(1982・東京大学出版会)』▽『長部重康編『現代フランス経済論』(1983・有斐閣)』▽『中木康夫編『現代フランスの国家と政治』(1986・有斐閣)』▽『遠藤輝明編『地域と国家――フランスレジョナリスムの研究』(1992・日本経済評論社)』▽『ベルナール・シュノ著、長谷川公昭訳『フランスの国有企業』(白水社・文庫クセジュ)』▽『ピエール・マイエ著、千代浦昌道訳『フランスの経済構造』(白水社・文庫クセジュ)』▽『G・デュプー著、井上幸治監訳『フランス社会史』(1968・東洋経済新報社)』▽『J・J・デュペイルー著、上村政彦・藤井良治訳『フランスの社会保障』(1978・光生館)』▽『谷川稔著『フランス社会運動史』(1983・山川出版社)』▽『寿里茂著『現代社会学叢書12 現代フランスの社会構造――社会学的視座』(1984・東京大学出版会)』▽『工藤恒夫著『現代フランス社会保障論』(1984・青木書店)』▽『宮島喬・梶田孝道・伊藤るり著『先進社会のジレンマ――フランス社会の実像を求めて』(1985・有斐閣)』▽『A・レオン著、池端次郎訳『フランス教育史』(白水社・文庫クセジュ)』▽『G・ルフラン著、谷川稔訳『フランス労働組合運動史』(白水社・文庫クセジュ)』▽『A・ドーザ著、松原秀治・横山紀伊子訳『フランス言語地理学』(1958・大学書林)』▽『G・デュビィ他著、前川貞次郎他訳『フランス文化史Ⅰ~Ⅲ』(1969・人文書院)』▽『クルティウス著、大野俊一訳『フランス文化論』(1977・みすず書房)』▽『饗庭孝男編『フランス六章――フランス文化の伝統と革新』(1980・有斐閣)』▽『西川長夫・天羽均・宮島喬他著『現代フランス生活情景』(1983・有斐閣)』▽『渡辺守章・山口昌男・蓮實重彦著『フランス』(1983・岩波書店)』▽『西川長夫著『フランスの近代とボナパルティズム』(1984・岩波書店)』▽『J・ショーラン著、川本茂雄・高橋秀雄訳『フランス語史』(白水社・文庫クセジュ)』▽『桑原武夫著『フランス学序説』(講談社学術文庫)』▽『富田仁・西堀昭著『日本とフランス――出会いと交流』(1979・三修社)』▽『西堀昭著『日仏文化交流史の研究――日本の近代化とフランス人』(1981・駿河台出版社)』▽『高橋邦太郎著『日仏の交流――友好三百八十年』(1982・三修社)』▽『富田仁著『日佛のあけぼの』(1983・高文堂出版社)』▽『富田仁著『フランス語事始――村上英俊とその時代』(1983・日本放送出版協会)』

フランスの国旗

フランス位置図

フランスの地形区分

エッフェル塔

エトアール凱旋門

マルセイユ市街

カルナックの遺跡

ニームの円形闘技場

ガール橋(ポン・デュ・ガール)

ルーブル美術館

パリ・オペラ座

ポンピドー・センター
フランス(Anatole France)
ふらんす
Anatole France
(1844―1924)
フランスの小説家、批評家。本名Anatole François Thibaut。4月16日、パリのセーヌ河畔に古本屋のひとり息子として生まれる。イエズス会経営のスタニスラス学院に学び、ギリシア・ラテンの教養を身につける。信仰はもたないが、キリスト教には強い関心を抱き続け、永遠に満たされぬ人間精神の象徴として悪魔(サタン)を好んだ。高踏派の影響の下に『黄金詩集』(1873)、劇詩『コリントの婚礼』(1876)を書く。やがて『ル・タン』紙の文芸時評を担当し、これを『文学生活』全4巻(1888~92。のち、さらに1巻が加わる)にまとめた。小説家としての出世作は『シルベストル・ボナールの罪』(1881)で、当時流行の自然主義文学の解毒剤として評価された。その後の作品には『タイス』(1890)、『赤い百合(ゆり)』(1894)、『エピクロスの園』(1895)、短編集『バルタザール』(1889)、『螺鈿(らでん)の手箱』(1892)など。『タイス』は娼婦(しょうふ)タイスの救済を図る砂漠の修道僧が逆に女色に迷って地獄に堕(お)ち、娼婦は悔悛(かいしゅん)して聖女になるというこの作者独得の皮肉な小説。『エピクロスの園』は作者の思想を端的に伝える随想集。これらの作品に示されるフランスの人となりは「瞑想(めいそう)の饗宴(きょうえん)」を楽しむ皮肉で寛容な懐疑主義者である。
しかし、19世紀末、フランスの世論を二つに分けたドレフュス事件が起こるや、ゾラとともにドレフュスの側にたち、事件に揺れる左右両派の対立抗争を風刺的に描いた『散歩道の楡(にれ)』『柳のマネキン人形』『紫水晶の指輪』『パリのベルジュレ氏』からなる四部作『現代史』(1896~1901)をはじめ、『クランクビーユ』(1902)、『白き石の上にて』(1905)、『ペンギンの島』(1908)などの文学活動を通じて社会参加(アンガージュマン)の姿勢をとり、ついには社会主義を支持する。しかしフランス革命を描く『神々は渇く』(1912)では革命の狂信批判を忘れてはいない。晩年は『わが友の書』(1885)の続編『花咲く日』(1922)の執筆に没頭、老年と戦争(第一次世界大戦)の悲しみに耐えた。1921年ノーベル文学賞を受け、24年10月13日、栄光に満ちた死は国葬で報われた。芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ)をはじめ日本の諸作家に大きな影響を与えた。この作家の文学を貫く精神は現世への愛で、文体は澄明、典雅を極める。
[大塚幸男]
短編
フランスは短編も多数書いているが、作品の傾向は瞑想的で、皮肉で、いくつもの解釈を許すのが特徴である。そうした特徴的な作品を二、三あげてみる。
『バルタザール』(1889) 同名の主人公はエチオピアの若い王。シバの女王を訪ね一目で恋のとりことなり、誘われるままに宮殿を抜け出し、重傷を負いながらも甘美な抱擁に陶酔する。やがて女の心変わりを知り、天文学に没頭して悲恋を忘れていく。ところが女王は彼が自分を愛さなくなったと聞いて激怒し、即日エチオピアへ出発する。バルタザールは一夜、塔に上って奇跡的に輝く一つの星を観測していると、砂漠を蛇行してくる女王の行列が見える。彼は胸のとどろきを抑え顔をそむけ、目をあげてふたたび星を見る。すると星は「汝(なんじ)は苦しんだから選ばれたのだ」と語り、彼をベツレヘムへと導く。かくて彼は幼児(おさなご)イエスを礼拝する三博士の一人となる。
『聖母の軽業(かるわざ)師』(1890) 中世のころ、バルナベとよばれる貧しい軽業師が、ふとした機縁で修道院に拾われるが、無学なので聖母をたたえる技(わざ)をもたない。そこで聖母のために軽業の供覧を思い付く。修道院長らがそれを見て驚き、引きずりだそうとすると、聖母が下りて来て軽業師の額の汗をふいてやる。そこで修道院長は平伏して「幸福(さいわい)なるかな心の清き者……」と唱える。
『クランクビーユ』(1902) 貧しい正直な野菜行商人が警官侮辱のかどで無実の罪に問われ、生きる手だてを奪われる。そこで刑務所入りを志願して別の警官を侮辱する。だが今度はその警官から父親のような温情をかけられるという物語で、政治権力の不条理を痛烈に告発している。
[大塚幸男]
『『アナトール・フランス短編小説全集』全7巻(1939~40・白水社)』▽『『アナトール・フランス長編小説全集』全17巻(1940~51・白水社)』▽『大塚幸男訳『エピクロスの園』(岩波文庫)』
改訂新版 世界大百科事典 「フランス」の意味・わかりやすい解説
フランス
France
基本情報
正式名称=フランス共和国République française
面積=55万1500km2
人口(2010)=6296万人
首都=パリParis(日本との時差=-8時間)
主要言語=フランス語
通貨=フランfranc(1999年1月よりユーロEuro)
ヨーロッパ大陸の西部にある共和国。ヨーロッパに位置する本国のほかに,世界各地に海外県,海外領土をもっている。
自然
フランスは,面積は世界各国のうち45位,人口(ともに本国のみ)は16位(1989年央国連推計による)であるが,近・現代史においてしばしば四大国あるいは五大国の一つに数えられてきた。その理由を歴史的に,政治・経済・社会の条件から説明することはもちろん重要であるが,歴史が展開された舞台を明らかにしておくことも必要不可欠である。
フランスほど位置に恵まれた国は少ない。地球の陸半球の中央に位置し,しかも現在では世界で最も工業化が進み,生活水準の高い西ヨーロッパのほぼ中央に位置している。また赤道と北極の中間,北緯42~51°の間に広がっており,暑からず,寒からずの典型的な温帯にある。さりとて大陸の真ん中にあるわけではない。ヨーロッパ大陸にあって,大西洋と地中海とに挟まれた最も狭小な部分を占め,地中海地方と北西ヨーロッパとの性格を併せもった唯一の国である。ロシアを除いて,ヨーロッパ最大の面積をもちながら,コルシカ島を除いて全土が半径約500kmの円内にほぼ収まる六角形をなしている。
対照的な地形
フランスは低平な地形の国である。北西側半分には標高500mを超える山はなく,アルプスやピレネーの大山脈は南東と南の隅に追いやられ,フランス人の過半数は,日常,高い山を見ることがない。国土の60%が標高250m以下にある。フランス人にとって山地とは,国の外れ,国の垣根,清浄で一般大衆とは無縁のもの,悪者の巣,未完成の土地などとされ,普通でない土地,なじみのない土地なのである。
地形構造上の基本線は,東部のボージュとジュラの山地の間からソーヌ・ローヌ河谷の右辺に沿って南下し,地中海の海岸平野の北縁を経てピレネーの北側を大西洋に出るもので,一般に北西側はゆるやかな斜面が,南東側は急峻な断層崖が連なり,ピレネー北麓を別として非対称の稜線をなし,同時に重要な分水界となっている。Jの字形を描くこの基本構造線の北西側では,傾斜に従ってモーゼル川,セーヌ川がイギリス海峡に向かい,ロアール川,ガロンヌ川などが大西洋に向かって流れる一方,南東側ではソーヌ・ローヌ川が地中海に流れこんでいる。北西側に長くて流域面積の広い,傾斜のゆるやかな大河川が多い。
基本構造線の北西側は,東ヨーロッパから北西ヨーロッパに波を打つように続いている平野,台地,高原が主要な部分を占めており,約3億~4億年前のヘルシニア造山運動で形成され,長い年月の間に浸食されて高原状に低くなった古生代の山地を骨格としている。フランスでは,このヘルシニア期山地がV字状に並び,北西部にアルモリカン山地,中南部にマシフ・サントラル(中央山地),北東部にアルデンヌ山地,ボージュ山地がある。これらの山地の間の峠にあたる部分は,敷居(スイユseuil)と呼ばれるほどに低く,北西部と中南部にはポアトゥーの敷居,中南部と北東部とにはブルゴーニュの敷居がある。後者は,マシフ・サントラルとピレネーの間にあるロラゲの敷居とともに,基本構造線上の地中海・大西洋分水界の一部でもある。マシフ・サントラルには,その後に噴火した火山地形もみられるが,泥岩や片岩が浸食されて硬い石灰岩が残っており,地質構造が大きく地形に影響している。V字の底にあたる地方には,コースcausseと呼ばれる石灰岩台地が広がり,鍾乳洞や深い峡谷がみられる。
V字状に並んだ山地に囲まれた部分がパリ盆地,V字の左辺下がアキテーヌ盆地で,これらの盆地には周辺山地から運ばれた土砂が中生代から第三紀にかけて堆積し,中央部にやや低く周辺部に向かって高まる皿のような地層(石灰岩と泥岩がほぼ交互に重なっている)を形成した。ここでも石灰岩はしばしば浸食されずに残り,パリ盆地では東から南東にかけて,内側はほとんど気づかないほどの緩傾斜,外側は急峻な崖となったケスタ地形がみられる。この急崖は関門(ポルトporte)と呼ばれる部分を除いて越えがたいため,フランスの対独防衛線(たとえばマジノ線)として利用された。しかしいったん通過すれば平坦な土地が広がり,視野を遮るものはミレーの絵のように教会の尖塔だけというようになる。もちろん,一部には一つ上の地層が削り残されて(残丘),パリのモンマルトルの丘のようにかっこうの見晴し台になる。またパリ南方のボース平野のように石灰岩を基盤とする台地は透水性が高く,小河川が少ない。実際,小川のせせらぎに出会うことはまれであるが,大河川は川幅も広く,セーヌ川,モーゼル川は流量も安定して内陸河川交通が発達している。しかし,マシフ・サントラルに発するロアール川などは,水源地帯が冬季降雪・夏季乾燥の降水型を示すため,春先の雪どけによる増水と夏季の渇水との流量差が大きく,河川交通は河口付近に限られる。
V字の右辺は基本構造線に沿っており,険しく若々しい谷がローヌ河谷やラングドックの平野に落ち込んでいる。この南東側フランスは,いわゆるアルプス造山帯によって造られたアルプス,ピレネー,ジュラの大山脈とこれらをうがつ河谷によって代表される。これらの山脈は第三紀,約8000万年前に,アフリカのプレートとヨーロッパのプレートがぶつかって形成されたもので,北西フランスの地形を特徴づけるのが地層であるのに対して,南東フランスのそれは断層や褶曲(しゆうきよく)である。またボージュ山地やマシフ・サントラルにもその痕跡はあるが,第四紀に訪れた氷河期の影響をまともに受けたのはこの南東フランスで,氷河によって造られたU字型の谷はリヨン近くまで押し出してモレーン(氷堆石)を残している。ヨーロッパ第一の高峰モン・ブランをはじめ高山の多くには氷河で削られた急峻な岩肌がみえ,今なお氷河も残っている。これらの山の水を集めて流れ下るローヌ川は,日本の河川と同じく急流で,運ぶ土砂の量も多いので,河口にはカマルグcamargueと呼ぶ三角州地帯を形成し,エーグ・モルトの町のように,かつての港を内陸に取り込んでしまう一方,米作や放牧に用いられる土地を拡大している。
変化に富む気候
フランスの気候は,三つの停滞性気団と,暖かい北大西洋海流上に発生して順次西からやってくる温暖・湿潤な移動性低気圧との力関係によって決められている。停滞性気団のうち,南のアゾレス高気圧は高温・乾燥で,冬はサハラ砂漠まで後退するが,夏はフランス南部まで覆う。北のアイスランド低気圧は低温・湿潤で,直接フランスを支配するわけではないが,夏季にこれが強ければ冷夏で雨が多くなり,冬季に弱ければ厳寒で晴天が多くなるなどの影響を与える。もう一つの停滞性気団は,夏は低圧帯となり,冬は高気圧となって東から張り出してくるシベリア気団である。冬季にこれが弱まれば暖冬で雨が多くなる。
地域的にみれば,アルプス,ピレネーなどの高山地域を別として,これら三つの気団に対応した三つの気候がみられる。第1はアゾレス高気圧の影響を受ける地中海式気候である。夏の乾燥とまばゆい太陽,澄んだ空気が特徴で,アゾレス高気圧が発達したときには,この気候区はロアール川近くまで北上する。フランス南部のブドウはこの夏の太陽のおかげである。雨はこの高気圧が弱まり,シベリア高気圧との間の谷間に低気圧が進んでくる秋からで,降るときは強く,溝をうがち奔流となって表土を押し流す。そのため森林は育たず,マキmaquisと呼ばれる植物群落やガリグgarigueと呼ばれる灌木のやぶなど夏の乾燥に耐える低木の疎林となり,耕地は灌漑されるものが多い。冬は一般に温暖であるが,西からやってくる低気圧が地中海上で発達すると,内陸の高気圧からローヌ河谷に向かって寒い北風が吹き込む。これが,ゴッホの絵にみられるように防風林をも風下に傾ける強い地方風のミストラルmistralである。
第2は冬季,内陸の高気圧に支配される大陸性気候(冷帯湿潤気候)で,冬は寒く乾燥して晴天が多い。夏は内陸が低圧部となって内陸深くまで低気圧を引き込むので降水がみられる。この冬の高気圧がフランス全域を支配する厳冬もあるが,しばしば東に後退してしまう暖冬もあり,フランス東部はいわば大陸性気候への漸移帯である。山地の東側のソーヌ,ライン,モーゼルなどの河谷では,西からくる低気圧の山かげにあたるため,夏も雨が少なく気温も高いのでブドウ畑が広がっているが,気温の年較差が大きく,大陸性気候の性格がより強い。紅葉が美しく,春の芽生えも美しい広葉樹が多く,四季の変化が明瞭である。
第3はアイスランド低気圧の影響を受けつつ,移動性温帯低気圧が相次いで大西洋からやってくる海洋性気候(西岸海洋性気候)である。ブルターニュ半島の気候がその典型で,低気圧が降水とともに夏は涼しさ,冬は暖かさをもたらすので,気温の年較差が小さい。雨は糠雨となって降水日数は多いが,降水量は少ない。半島先端のブレストで年に220日も雨が降るのに,年降水量はわずか1130mmである。雨と曇りと晴れが数時間の単位で変わるほど天気の変化は激しく,とくに低気圧が内陸の高気圧とぶつかる冬には,暖かい湿った空気が急に冷やされて不安定になり,霧や暴風雨に見舞われる。イギリス海峡などで海難事故が起こるのはこのような時である。フランスの卓越風はおおまかにいって西風であるが,西風が暖かく湿った風で,冬の東風が寒いからっ風になる点は日本と逆である。この海洋性気候では,冬に太陽がほとんど見られなくなるものの,野原は緑のままである。
地域性
プロバンスとレジヨン
フランスは,さまざまな見方によって諸地域に分けられる。現在最も広く用いられている地方名は,フランス革命以後に設定された95の県(デパルトマンdépartement)名ではなく,むしろそれ以前の旧州(プロバンスprovince)またはそれを援用した22の〈地域〉(レジヨンrégionと呼び,数県をまとめたもの)の名前である。たとえば,ブルターニュは,旧州にあたる5県を指す場合と〈地域〉を構成する4県のみを意味する場合とがある。旧州名を採用していない〈地域〉名は,あまり親しまれておらず,たとえば〈サントル地域〉はトゥーレーヌ,オルレアネなどの旧州に分けて,あるいはロアール地方とまとめて呼ばれている。
これは,フランスを構成するさまざまな民族や地方文化を,歴史的な地域としての州の名前によって代表できるからで,主要な旧33州のうち16州の名前が17地域の名として用いられている。アルザス,アキテーヌ,オーベルニュ,ブルゴーニュ,ブルターニュ,シャンパーニュ,コルス(コルシカ),フランシュ・コンテ,ラングドック,リムーザン,ロレーヌ,ノルマンディー,ピカルディー,ポアトゥー,プロバンス,ルーシヨンの16州がそれであり,ノルマンディー州は2地域(オート・ノルマンディー,バス・ノルマンディー)に分けられている。トゥーレーヌ州の主都トゥールが,何県の県都であるかを覚えることはフランス人でも面倒なことであり,各県に割り当てられた番号(郵便,自動車などさまざまな分野に用いられている)で,トゥールは37番の県の県都と覚える場合が多い。ちなみにパリ県は75番である。
フランスを全体としてみるには,33の旧州単位では細かいので,フランスの北半分を西フランス,北フランス,東フランス,パリ盆地に分けて,まとめて(広義の)北フランスと呼び,南半分をアルプス地方,マシフ・サントラル地方,アキテーヌ盆地,地中海地方に分けて,まとめて南フランスと呼ぶこともある。その区分線はほぼジロンド川の河口からジュラ山脈にかけて引かれる。この線はまた,フランス語の〈なまり〉の区分線でもあり,南側のオック語langue d'oc,北側のオイル語langue d'oïlに大別される。フランス語のほかに,周辺地域にはブルトン語,アルザス語,カタルニャ語,フラマン語,バスク語などの言語があって,地域性を形成する要素の一つとなっている。
景観
地方文化の差異を意識するのは,まず目に見える景観として展開する土地利用,耕地の形状,民家や集落の形態,人々の服装などによってである。
フランスのように,農用地率が55.6%で日本の4倍近くもあり(1991),山岳地帯が周辺部にしかない国では,風景の基本的構成要素は,平地や丘陵に展開する農地である。その農地の37%が牧草地または牧場であり,しかもそのほかに牧草畑などの飼料畑が耕地として分類されているから,日本の風景における水田以上にフランスの風景においては緑の草原が支配的である。実際に牧草畑であるのか草地であるのかを区別しようとすれば,家畜が放たれているか否かによることになるが,輪作されている小麦やテンサイ畑でも,収穫後であれば家畜を入れることもあるので,草地と耕地の見分け方はやはり難しい。
もちろん,地域ごとに作目の違いがみられ,農業の地域性は比較的明瞭に現れており,フランス全体を一括することは難しい。たとえば南フランスでは,平地ではブドウや野菜などに専門化しつつある地中海式農業が行われて樹園地が広いのに対して,アルプスやマシフ・サントラルの山地では草地が広い。北フランスでは,シャンパーニュやブルゴーニュのブドウ畑,ノルマンディーや東フランスの酪農に専門化した草地,ブルターニュのリンゴが同時栽培されている牧草地,パリ盆地から北にかけての牧草と小麦,トウモロコシなどの穀物やテンサイが輪作されている耕地など,それぞれの地域において地域性の豊かな景観がみられる。また大西洋岸では野菜や花の園芸農業が盛んである。しかし国全体でみれば,樹園地率自体は日本と大きな差がなく,これら地域的に多様な土地利用も,フランスの風景において草地が卓越するという印象をぬぐうことはできない。
土地利用以上に人の目をひくものの一つは,耕地の形状である。ブルターニュ,バス・ノルマンディー,バンデなど西フランスでは,ボカージュbocageと呼ぶ畦畔林に囲まれた耕地が視界を遮り,森林率は低いものの,風景としては森林に満ちた地方の印象を与える。その成立の理由は,防風のため,土壌の乾燥を防ぐため,家畜を囲い込むため,独立の精神が旺盛であるため,薪炭を得るためなど,さまざま挙げられて議論されている。これは,農業の機械化と規模拡大を進めるための耕地整理の障害になるとして一時伐採されたが,干ばつに見舞われたため,その後はあまり進展していない。逆に,森に閉ざされず,地平の際まで視界の開けた開放耕地(オープン・フィールド)は,とくにパリ盆地から北の地方では大規模な企業的農業が行われているので,ひとつひとつの耕地も広く,機械化も進んでいる。しかし南フランスでは経営規模が小さいこともあって,開放耕地のみられる場合でもひとつひとつの耕地は狭い。
集落の形状もこの耕地と対応している。ボカージュ地域では散村が支配的であり,孤立した農家はボカージュに囲まれて隠れてしまい,わずか数戸の小村(アモーhameau)が教会を中心に目につくだけである。他方,開放耕地の地域では集村が多い。北フランスでは,広い耕地のただなかに教会の尖塔を中心とした塊村が一般的である。また南フランスでは,丘陵など防衛上の要地に形成された大集落が一つの典型を示している。これは,ときには城壁に囲まれて都市とみまがうばかりの規模であるが,住民に農民が含まれている場合も少なくなく,地中海地方では農村までが都市的であるといわれる。また集落を構成する民家も,南や西フランスでは石造が多いのに対して,東から北フランスでは木造,あるいは柱やはりに木を用いたものが多い。フランス人は,これを〈石の文化のラテン〉,〈木の文化のゲルマン〉と対応させてとらえている。また同じ石造でも,南フランスの赤瓦で傾斜の少ない屋根に対して,西フランスの草ぶきや青黒いスレートぶきの傾斜の強い屋根は,ケルト文化を示しているとされている。散村地方では,小学校が小規模で,どんなに小さな小村でもみられる教会で初等教育を受ける者が多く,中等教育は寄宿学校で受ける割合が高い。それだけに教会が運営する私立学校の力が公立学校より強い。それが西フランスから神父が多く輩出することの基礎にあるといえるし,また熱心なキリスト教信者も西フランスに多い。
フランスの地域性を意識させられるものでは,風景のほかにさまざまな社会生活上の差異がある。その点では,セーヌ川とローヌ川の各河口を結ぶ線でフランスを二分し,南西フランスと北東フランスに分ける考え方もよく用いられている。所得や教育の水準,住宅その他の社会資本の充実度,工業化や農業の近代化の程度など,さまざまな社会経済的指標が,この区分線の南西側が貧しく,北東側が豊かであることを示している。
住民
フランスの人口は約5800万である。しかし〈フランス人〉は何人いるか,誰もわからない。たとえばフランスに征服された,あるいは併合された人々,独自の言語・文化をもつ民族が,フランス国土の六角形のそれぞれのほぼ頂点付近を占めている。北隅にはフラマン人,北西隅にはブルトン人,南西隅にはバスク人,南隅にはカタルニャ人,南東隅にはプロバンス人,北東隅にはアルザス人がおり,コルシカ島にはコルシカ人がいる。フランスがヨーロッパの中央に位置していることは,そこが諸民族が出会い通過する交差点にあたることを意味し,これら少数民族はすべて国境の向こう側に同族の人々をもっているのである。これら少数民族の言語のうち,国営放送が地方で独自の番組を製作し放送しているのはブルトン語だけである。ブルターニュ地方の大学にはブルトン語の講座も置かれている。
フランス全体で359万6000(1990)の外国籍滞在者(観光客など3ヵ月未満の者を除く)がおり,なかでもマグレブ3国出身者139万3000,イベリア諸国出身者86万6000が多い。外国籍の就業者162万の67.7%が労働者またはサービス業就業者である。つまりフランスの労働者・サービス業就業者の12.3%が外国籍である。フランス国籍を取った外国生れの人々はこれに含まれていない。
フランス人になることは簡単である。帰化し,フランス語を話し,フランス人のように生活すればよいのである。なまりなどは,ミディのなまりや北フランスなまりなど,本来のフランス人の中にもあるのだから問題にならない。人種からいっても,フランス人には白人,黒人,黄色人のさまざまな人々が流れ込み混血しているのであって,人種差別,民族差別はあるが日本より寛容である。他の人種でも,フランス人になった人々は,職業その他の点で社会階層上の差別または不平等を人種上の差別より強く意識するはずである。したがって六角形の隅にいる各少数民族も,大枠では自分をフランス人と考えている。フランス人とは,結局のところ,フランス語を話す民族のうちフランス国籍をもつ者というべきであろう。その中には,2言語併用者としてフランス語も使う周辺部少数民族の大部分が含まれており,さらには外国人の2世も加わってしまうわけである。言い換えれば二重民族籍の人々が多いのである。
執筆者:田辺 裕
歴史
いまここでその歴史を扱おうとする〈フランス〉なる存在は,最初から一つにまとまった国であったのでもなければ,単一の文化を構成していたのでもない。フランスという名称がフランク族に由来し,領域名としては9世紀のカロリング朝の分割から生まれた西フランクFrancia occidentalisに発するとはいえ,カペー朝の国王がフランク人の王Roi des Francsからフランスの王Roi de Franceと称するようになったのは,13世紀初めのことにすぎなかった。〈フランス〉なるものは,その国家も社会も文化も,長い歴史を通じて,多種多様な要素の衝突,交錯,融合のなかから,徐々に形づくられてきたのであった。フランスの歴史とは,この長い文明形成の歩みをいうのであって,国家もまた文明を構成する一要素にすぎない。
多様な人的構成
このガリア(現在のフランス)の地に人類の活動の跡を求めるとすれば,われわれは何十万年かの昔にさかのぼらねばならない。ここ100年ほどの間に急速に発展した考古学の研究によれば,このユーラシア大陸西端の地には,旧石器時代前期以来の人骨,石器が数多く発見され,氷河期と間氷期の間隙を縫うようにして,原初人類の活発な活動がみられたことが明らかとなっている。シェル・アシュール文化をはじめとしてマドレーヌ文化に至るまで,旧石器時代の諸段階を表す名称に,フランスの地名が数多く用いられているのも,その証左である。1868年に,南フランス,ドルドーニュ地方のクロマニョンで発見された人骨群(クロマニョン人)は,旧石器時代後期に属するが,新人(ホモ・サピエンス・サピエンス)の原型を示すものとして,重要な指標とされている。また近くのラスコーの洞窟からは,1940年,約1万7000年前のものと推定される壮大な壁画が発見され,スペインのアルタミラと並ぶヨーロッパ原始芸術の代表作とされている。フランスの歴史は,このはるけき昔に始まるのである。
氷河期が終わって以来,ヨーロッパの中心部に位置するガリアの地は,諸民族大移動の十字路の趣があった。大規模な移動が一応終息する10世紀末に至るまで,さまざまな人間集団が来たりまた去って,そこに多様な混交をつくり出した。〈フランス人〉なるものを産み落とす人的要素は,著しく多様であるということを,まず心得ておかねばならない。それは,偏狭な人種理論を免れるための,最良の教訓である。
第1に,前3000年ころから始まる新石器時代には,南西部中心にイベリア人,南東部中心にリグリア人の名で知られる集団が定着していた。メンヒルやドルメンに代表される巨石記念物は彼らの所産であり,その分布状態からも,彼らがガリア諸地域に広範に定着していたことがわかる。
フランス人がしばしば自分たちの最も古い祖先と考えているケルト人は,実は,前9世紀ころより,ドナウ川流域から移動してきた新しい集団であった。彼らは優れた鉄器文化をもち,前5世紀ころには,ラ・テーヌ文化の名で知られる最盛期を現出した。カエサルの《ガリア戦記》によれば,ケルト人は多くの部族に分かれ,広い土地を所有する貴族と祭儀をつかさどる神職ドルイドが,平民を統轄していた。霊魂の不滅を信じ,樹木や泉を崇拝するケルトの信仰は,キリスト教が導入されたのちも,民間信仰の形で生き続けている。民衆の間に伝わる説話や習俗のなかには,ケルト起源のものが数多くあることが民俗学者によって指摘されている。フランス人の間にみられる,深刻な問題を洒落のめしたり,権威を茶化したり,興奮しやすく覚めやすいといった気風を,ガリア気質esprit gauloisと呼んでケルトの遺産とみなす者もいる。ケルト人は,前1世紀半ばローマの軍勢に屈するまで,900年にわたってガリアの地を支配した。これはローマの支配,ゲルマンの支配よりも長いのであり,フランス文化の基層を考えるとき,ケルト文化の遺産は重視されねばならないだろう。
ローマは,前2世紀末より南ガリアに進出し,地中海沿岸地域を属州としていたが,ケルトの部族間抗争をきっかけに,前58-前51年カエサルに率いられたローマの軍勢は,ガリア全土を征服してしまう。カエサルに対峙したケルトの指導者ウェルキンゲトリクスは,前52年アレシアの戦に敗れ,ローマに運ばれて処刑されたが,ケルト礼賛者にとっては,これこそまさに屈辱の歴史であった。ガリアにおけるローマの支配は,以後500年に及び,フランスの将来に絶大な影響を及ぼすこととなった。その後ゲルマンによる,これまた500年以上に及ぶ支配が後に続いたにもかかわらず,フランス文化がスペイン文化やイタリア文化とともにラテン文化と称されるのも,ローマの影響が深部にまで及んでいたことを示している。とりわけそれは,俗ラテン語を経て古フランス語へと展開する言語の継承関係に最もよく表れているといえよう。
ローマ人の支配がガリアにとって第1の衝撃であったとすれば,第2の衝撃はいうまでもなく4世紀から6世紀にかけてのゲルマン人の大移動である。さまざまなゲルマンの部族がガリアの地に来たりまた去ったが,最終的に定着したのはライン川下流から移り来たったフランク族であった。彼らの首長クロービスは,476年の西ローマ帝国滅亡の後,481年フランク王国を建設し,メロビング朝を創始した。8世紀になると,メロビング王家は弱体化し,宮宰ピピン(3世)により王位を奪われ,ここにカロリング朝が成立した。そして,ピピンの子シャルルマーニュ(カール大帝)の下で,フランク王国は最盛期を迎えることになる。フランク族による支配の浸透度は地域により異なるが,ガリアの北部・東部において密であったことは疑いない。ゲルマン起源の地名の分布にも,それは明瞭にあらわれている。
フランスは,北フランスと南フランスとの間に顕著な対照がみられるが,これには風土的な要因と並んで,ローマ支配とゲルマン支配がそれぞれの地域に及ぼした影響の違いが色濃く投影されている。たとえば法制史において,北の慣習法(ゲルマン法)に対し,南における成文法(ローマ法)の存続。家制度において,北の単婚家族・均分相続に対する,南の拡大家族・長子相続制。農業制度において,北の馬を主軸とする三圃制に対する南の牛を主軸とする二圃制。封建制についても,北における典型的な発展と南の後進性,といった対照がそれである。
このように,先史以来の歴史を顧みるとき,フランス文明形成の背景には,少なくともケルト,ローマ,ゲルマンという,三つの要素の重要性を認めなくてはならない。そのいずれを重くみるかは,主観的願望が強く投影されることもあって,論者によって意見の分かれるところであるが,ここではむしろ,フランス文明の複合性を確認しておくことの方が,重要な意味をもっている。
共同性の形成
このような多様な要素のなかから,フランス文明の名で呼びうるような共通の絆が形成されてくるのは,中世,とりわけ11世紀以降の中世盛期においてである。確かに,カール大帝没後の,ベルダン条約(843)とメルセン条約(870)によるフランク王国の3分割は,西フランクなる枠組みを生み,のちのフランス王国形成の端緒をなすといってよいが,むしろより重要なのは,フランク王国の末期から始まり,10~11世紀において大きく展開するガリア社会の変化であった。第1に注目されるのは,農業生産の顕著な発展であり,農業技術の革新(水車の普及,繫駕(けいが)法の改良,三圃制の普及など)と村落共同体の一般的形成を通じて,安定的・持続的な農業社会がその基礎を固めた事実である。この農業生産の発展は,やがて手工業生産と商品交換の拠点としての都市の形成を促し,地域経済の発展をもたらすことになる。第2には,とくにライン川とロアール川に挟まれたガリア北部を中心に,領主による局地的な領域支配を基礎とする封建的政治秩序が古典的な形で開花した事実が指摘されよう。そして第3には,キリスト教が,まさにこの時期において,その影響力を強め,11世紀以降,カトリック教会の末端組織である聖堂区が,おりしも形を整える村落共同体と重なり合うように,フランス全土にその網の目を広げていった事実がある。
こうした,社会のさまざまなレベルにおける組織化の進展のうえに立って,987年ユーグ・カペーに始まるカペー朝の諸王が,〈フランス〉なるものを生み出す絆の役割を果たすこととなった。とりわけ,12世紀末のフィリップ2世(尊厳王),13世紀中葉のルイ9世(聖王)の時代において,フランス国王の勢威は内外において格段に高まったといってよい。国王は,地上における神の代理人として,また人民の父として,さらには正義をもたらす裁き人として,政治統合のシンボルの役を果たした。カペー王権の基盤は,元来パリ地域を中心とする北フランスにあり,南フランスは,政治的にも文化的にも,独自の地位を占めていたが,13世紀初頭,南フランスに広まったアルビジョア派(カタリ派)に対する弾圧(アルビジョア十字軍)をきっかけに,フィリップ尊厳王は南への支配をも一挙に強化することになった。このように,統一の形成に当たり,政治の力が大きく作用していることが,フランスの特徴として注目されねばならない。
それと並んで,キリスト教文化の開花が,一面それは国境を越える性格をもつとはいえ,ケルト,ローマ,ゲルマンといった複合的要素の上に成り立つフランスを一つの文化的共同体として結び合わせるのに,大きく貢献したといえよう。11~12世紀,フランス全土にわたってのロマネスク芸術の開花,次いで,12世紀後半より北フランスを中心に展開するゴシックの大聖堂は,中世フランス人に共通の心性を形づくった最大のファクターであった。そして,それがまた,即位に当たっては,ランス大司教の聖祓を受け,十字軍に身をもって参戦し,瘰癧(るいれき)患者を癒す力(ローヤル・タッチ)をも備えたフランスの国王の権威を支えることにもなったのである。
14~15世紀のフランスは,中世末の危機の時代であった。1328年カペー朝の断絶を機に,王位継承をめぐるバロア朝とイギリス王家との対立から,両者は1339年以来,1世紀以上にわたる百年戦争に突入した。繰り返し戦場となったフランスは,戦乱による直接の被害に加え,軍隊による略奪にあえいだ。しかも,14世紀初め以来の農業生産の停滞は,たび重なる飢饉を引き起こし,体力の弱った民衆に,中近東から侵入したペストが大量死をもたらした。こうした状況のなかで,1358年,E.マルセルに率いられたパリ市民の反乱と,周辺農村のジャックリーの乱が勃発した。イギリスとフランスの対立と重なり合う形で,国内においては,イギリスと手を結ぶブルギニョン派と,王太子を頂くアルマニャック派が相争ったこの百年戦争の間,王権は確かに弱体化したが,対立する有力諸侯の力も弱まり,国民意識の芽生えがみられるなど,やがて絶対王政の成立へと連なる水面下の動きは強まっていたといってよい。ジャンヌ・ダルクの登場は,決して祖国愛の表れといったものではないが,広域的な連帯を促すシンボルとしての意味をもったといえるだろう。
アンシャン・レジーム
16世紀から革命までの約3世紀を,今日の歴史学は,アンシャン・レジームと呼ぶ。これは,いうまでもなく,革命以後の新体制に対して旧体制を意味する語であるが,必ずしも否定的な意味合いでのみ用いられるのではない。旧体制が革命によって打倒されたことは確かであるが,同時に,この300年は,フランスが国民国家として編制されるための条件をつくり出し,文化的にもフランスの独自性が明確に打ち出された時代であった。その開幕を告げる16世紀は,ルネサンスと宗教改革の時代として特徴づけられるが,中世末の危機から脱出した経済の活況に支えられて,あらゆる分野で,新しい時代への胎動がみられる。この頃,アルプスのかなたのイタリアでは,すでに学芸のルネサンスは広範な展開をみせていたが,イタリア戦争(1494-1559)を期にその影響は強まり,フランソア1世は,イタリアよりレオナルド・ダ・ビンチをはじめ多くの芸術家を招いた。ロアール川流域のシュノンソーやアンボアーズなどにルネサンス風の明るい城館が相次いで建造され,城はもはや戦いのためのものではなくなる。中世以来の伝統に固執するソルボンヌ神学部に対しては,1530年コレージュ・ド・フランスの前身〈王立教授団〉が創設され,ギリシア語,ヘブライ語の原典への道を開いた。〈今やいっさいの学問は復旧せしめられ,もろもろの言語研究も再興せしめられ候〉とラブレーはガルガンチュアの筆を借りて書いている。他方,信仰の領域では,ルターに続いてカルバンが,カトリック教会との決別を宣し,ジュネーブを拠点に,新たな信仰への回心を説いた。こうして,16世紀の後半フランスは,教皇派とユグノーとが激突するユグノー戦争(1562-98)へと突入することになる。まさに生みの苦しみの半世紀であった。すべては疑われなくてはならない。戦乱の渦中に生きたモンテーニュは〈われ何をか知る〉と問い,《随想録》3巻を書きしるしたが,この〈人間とは何か〉との永遠の問いこそは,ユマニスムの伝統となって,フランスの思想の根幹を支えることになる。モンテーニュの懐疑は,次の世紀デカルトに受け継がれ,理性をもってすべての思索のかなめとする合理主義の精神を生み,他方では,パスカルにより〈考える葦〉人間への深い省察へと導かれ,フランス近代精神の基礎が築かれたのであった。
ユグノー戦争の激動は,ブルボン朝初代のアンリ4世の下に一応の決着をみ,続くルイ13世,ルイ14世の時代には,リシュリュー,マザラン,コルベールという有能な政治家に助けられ,王権は急速に強化されていった。国内の政治的・法的統一を希求する法服ブルジョアジーや新貴族,地主層に支えられ,国際商業戦において国家の支援を不可欠とする商人ブルジョアジーの期待に応えつつ,絶対王権はその基礎を固めていく。三十年戦争(1618-48)への直接参戦をきっかけに,国内引締めと徴税強化のため王国の諸地方には,国王の意を体したアンタンダン(地方長官)が常置されるようになり,コルベールの下では重商主義政策が全面的に展開された。単に政治や経済の領域にとどまらず,社会のあらゆる面で,規律の強化が図られた。言語についてはすでに,1539年のビレル・コトレの王令によって,裁判記録にフランス語を用いることが義務づけられていたが,これは一つには,中世以来の普遍主義の象徴であるラテン語の使用を排除することを通じて,国民国家としての自立性を主張し,他方では,南フランスのオック語をはじめ,各地に生き続ける地域語の使用を禁じてフランス語を国家の言語として強制する,王権の意思を表明したものである。1635年に設立されたアカデミー・フランセーズは,言語の規格化をいっそう推進することになった。宗教の面でも,ナントの王令(1598)によって新教徒にも信仰の自由が許容されたものの,陰に陽にユグノーへの圧迫は続き,ついには1685年ナントの王令は廃止され,単一宗教の原理へと逆戻りした。以後,フランスは圧倒的にカトリックの国としてとどまることになる。王権による信仰の統一は,しかし,リシュリュー枢機卿が三十年戦争に際し新教派のスウェーデンと手を結んだことにもみられるように,国家利害に従属させられたものであった。フランス王権が,しばしばローマ教皇庁と対立し,ガリカニスムの傾向を強めたのも同じ理由による。こうして,もろもろの身分集団は,厳格な規律の下に階層化され,その頂点に国王が君臨することとなる。最後の貴族反乱であるフロンドの乱(1648-53)は,このような規制強化への反撃の試みであったが,時代の趨勢には抗しえなかった。
自らの栄光の象徴としてベルサイユ宮を造営したルイ14世は,この王宮に儀礼の網の目によってみごとに統御された宮廷社会を組織することにより,ヨーロッパの諸君主に,絶対王政の統治システムの理念型を提示したのであった。時を同じくして開花した古典主義の芸術がまた,全ヨーロッパに確固とした美の規範を提示した。ボルテールがこの17世紀を〈ルイ14世の世紀〉と名づけたのも,ゆえなしとしない。フランスは,政治においても芸術においても,ここに初めて独自の様式を生み出すことに成功し,しかもそれを国境を越えて準拠さるべき普遍的価値として高く掲げたのであった。フランス人の思考にしばしばみられる一種の中華思想や,フランスの文化を普遍的文明の体現とみなす傾向は,自らをローマの継承者とする意識によるところが大きいが,このような理念は,初めてここにその現実的な根拠をもつに至ったといってよい。
しかし,ブルボン絶対王権の栄光を支えていた身分制秩序や社会的規律は,18世紀に入ると,厳しい批判にさらされることとなった。経済の面でも,産業の担い手である新しいブルジョアジーがしだいに力を蓄え,王権によるさまざまな規制に批判を強めた。とりわけイギリスが急速に経済力を伸ばし,世界経済の主導権を握ろうという情勢を前にして,依然旧来の領主制や身分的免税特権を維持しようとする王権との軋轢は強まるばかりであった。思想の面でも絶対王権への批判が噴出してきた。そもそも,いかなる権威を前にしても,必ず異議を申し立てる者のいるのが,フランスの大きな特徴である。モンテスキューとボルテールを先駆者として,ディドロを中心とするアンシクロペディスト(百科全書派),ケネーを始祖とする重農学派(重農主義)が強力な思想運動を展開した。そして,ついにはルソーが,絶対王権を支える社会構造を全面的に否認する理論をひっ下げて登場することになる。
革命がもたらしたもの
18世紀末葉,アンシャン・レジーム社会の矛盾は激化し,いち早く産業革命を成就したイギリスからの側圧もいっそう強まった。王政府は,上からの改革を推進して事態を乗り切ろうと試みるが,特権身分の反対にあって身動きがとれない。ルイ16世は1789年5月に,1614年以来実に175年ぶりに全国三部会を召集したが,かえって火に油を注ぐ結果となり,ついに同年7月14日,バスティーユ襲撃事件となって爆発した。フランス史に大転換をもたらしたフランス革命の発端であった。以後,99年ナポレオン(1世)によるブリュメール18日の軍事クーデタに至るまでの10年余の間に,フランスは,その社会構造においても,権力秩序においても,根底的な変革を経験することになる。
革命の過程は,いくつかの段階に分けることができよう。1789年に始まる第1段階においては,自由主義貴族と上層ブルジョアジーの主導の下に,立憲君主政の形をとりながら,旧体制の法的構造を廃絶することが中心課題となっていた。《人権および市民権の宣言》(人権宣言)第1条における〈人間は,生れながらにして,自由であり,権利において平等である〉との宣言は,まさに新しい社会の到来を告知するものにほかならない。92年8月10日の革命側によるテュイルリー宮襲撃に始まる第2の段階は,内外から高まる反革命の危機に対し,都市の民衆(サン・キュロット)や農民の圧力の下に,急進的ブルジョアジーにより,徹底した社会革命が遂行された時期である。とりわけ93年6月以降の山岳派による革命独裁を通じて,徹底した社会的デモクラシーの実現が追求された。領主諸権利の無償廃棄は,中世以来連綿として続いた領主制に,決定的な打撃を与えた。そして,94年テルミドール9日のロベスピエールの失脚に始まる第3の段階は,反革命の粉砕により勝利を手にしたブルジョアジーが,民衆の圧力を排除しつつ,ブルジョア支配の安定を目ざした収拾段階である。しかもなお,最終的に革命の成果を守るためには,ナポレオンの軍事独裁に頼らざるをえなかった。こうしてナポレオンによる99年ブリュメール18日のクーデタは,1804年の第一帝政成立へと連なる。
以上の過程を通じて,フランス革命を特徴づけているのは何であろうか。第1には,社会構造および権力秩序の根底的な転換が遂行されたことであり,その後王政復古という事態を招いても,アンシャン・レジームの社会が復活することは二度となかった。第2には,変革に当たって民衆が,ブルジョアジーの利害を超えて強力に介入したことであり,このことが革命後のフランスに,資本主義化の遅れをもたらすと同時に,社会的デモクラシーの理念を強烈に刻みつけた。第3には,革命の理念を,単にフランスに固有の問題としてではなく,普遍的な原理として掲げ,世界の変革にまで至ろうとしたことであり,これこそトックビルが,フランス革命を宗教的な革命になぞらえた理由であった。第4には,革命がその最も急進化した段階で革命独裁の形をとり,さらに収拾の段階でナポレオンの軍事独裁の形をとったことから,極度の中央集権化・制度的画一化の傾向を引き起こしたことが挙げられよう。ここで,革命の特質を詳述したのは,それが単に革命の性格づけにとどまらず,革命以後のフランス社会を大きく特徴づけることになるからである。
勝ち誇るブルジョアジーと労働者の世界
1814年,ナポレオンの失脚によって第一帝政が崩壊して以来1世紀の間に,フランスは,王政復古(1814-30),七月王政(1830-48),第二共和政(1848-52),第二帝政(1852-70),第三共和政(1870-1940)と,めまぐるしくその政治体制を変えた。しかもその転換点には常に,七月革命(1830),二月革命(1848),六月蜂起(1848),ナポレオン(3世)のクーデタ(1851),普仏戦争(1870-71)の敗戦とパリ・コミューン(1871)という,劇的な事件が介在している。
19世紀のフランスは,その進路の選択において,試行錯誤を繰り返したといってよい。政治のイデオロギーとしては,王党派,共和派,ボナパルティストが拮抗し,王党派はその内部でさらに正統王朝派とオルレアン王党派(七月王政派)とに分かれている。これらはいずれも,革命の過程ですでに切られたカードであり,フランスは100年をかけてそれぞれの有効性を確かめなおしたともいえる。以上のような党派の見取図と重なり合って,左翼と右翼という区分がまた,政治的立場を大きく分ける枠組みとして定着していくが,これまた革命議会における議席の配置に発するものであり,フランスの政治生活に革命のもたらした遺産の大きさを思わせる。時代の大きな流れは,王政主義から共和主義へと向かってはいたが,それが決定的となるのは,19世紀末,ドレフュス事件の経験を経て,第三共和政が一応の安定をみてからのことである。むしろ,この間を通じて,フランスの独自性は,ボナパルティスムの潮流にあり,経済の後発性に基づく国家主導主義(ディリジスム)の伝統と,社会的デモクラシーが逆説的に生み出す超越的リーダーへの依存が,フランスの政治風土にこの独自の様相を付与したのであった。
政治体制のたび重なる転換の背後で,フランスの社会は,ゆっくりとではあるが着実に変容を遂げていった。その第1は,何といっても資本主義経済の展開とその影響である。フランスにおける産業革命は,18世紀以来の経済の発展を受け継ぎつつ,イギリスの側圧の下に展開するが,足どりがきわめて緩慢なところにその特徴があった。繊維工業に始まり金属工業へと及ぶ資本主義的生産方式への転換は,19世紀初頭より半世紀以上もかけ1870年ころに完了する。しかし緩慢であったとはいえ,とりわけ第二帝政下の発展には顕著なものがあった。貴族や地主に代わって,ブルジョアジーがわが物顔にふるまう社会が誕生した。銀行家や貿易商や工場主,そしてフランスにはとりわけ多かった金利生活者が,単に経済のみでなく,社会生活においても,価値体系においても,主導権を掌握していった。産業活動では,イギリスの工業家に大きく水をあけられながら,生活の色調をすっかりブルジョア風に染め上げた点においては,フランスのブルジョアジーは卓越していた。イギリスがジェントリーの国となったとすれば,フランスはまさにブルジョアジーの国となったのである。
生産の組織の変化と並んで,鉄道の建設と道路網の整備は,中心的な都市だけではなく,地方にまで変化の波をもたらした。1850年に3000kmであった鉄道延長は,70年には1万7000km,19世紀末には4万5000kmに達した。革命を経て領主制は廃棄されたとはいえ,資本主義化された農村は限られており,地方農村における生活はアンシャン・レジーム以来の伝統的スタイルを守っていたといってよい。しかし,鉄道と道路は,商品経済と都市文明の射程距離を一挙に拡大し,農村もまた,局外者としてとどまることは難しくなった。国家の行政機構においても,教育制度においても,中央からのコントロールは日ましに強まっていった。ブルトン語をはじめとし,なお各地に保たれていた地域語も,標準語化政策の強行の前に退潮を余儀なくされた。
社会の変化の第2の特徴は,ブルジョアジーの制覇と対をなす労働者階級の登場である。産業革命の展開が緩慢であったために,フランスでは,長いこと,アンシャン・レジーム以来の職人の伝統が,労働の世界の基調をなしていた。先端的な産業部門には,近代的工場労働者層も形成されたが,彼らすらも,この基調から大きく踏み出すことはしなかった。ブルジョアジーからは〈危険な階級〉と警戒され,蔑視されながら,彼らは頑固にその独自の世界,固有の共同性を確かめ合っていった。七月革命や二月革命から,六月蜂起を経て,パリ・コミューンに至るまで,彼らは常に街頭のバリケードの主役であり,社会主義思想をも,自己流に改変してわがものとした。フランスの労働運動を特徴づける革命的サンディカリスムも,このような伝統の所産である。
変化の第3として注目されるのは,新しい知識層の登場であった。家柄と身分によるエリートに代わって,革命は,能力による,そして知性によるエリートの活躍の場を一挙に拡大した。エコール・ポリテクニクやエコール・ノルマル・シュペリウールなどグランドゼコールは,これら新しいエリートの苗床となった。コレージュ・ド・フランスはミシュレやキネを教授に迎え,活気を取り戻した。作家,芸術家は,ブルジョアの俗物性を鋭く批判し,個我の自立を求め精神の優位を掲げた。こうしてパリは,近代の芸術運動と新しい知的活動の中心となった。17世紀に続いて,フランスは再び世界の文化の先導者の役割を担うことになる。
世界体制の中のフランス
ヨーロッパは,早くより,外部世界との関係の上に,その発展を築き上げてきた。とりわけ,15世紀末の大航海時代に始まる絶対王政期には,ヨーロッパ,新大陸,東インド(東南アジア)を結ぶ三角貿易が,ヨーロッパ経済を支える基本的な枠組みをなしていたといってよい。フランスも,16世紀における探検時代を経て,リシュリューからコルベールに至る重商主義政策の下で三角貿易を推進した。またアフリカ大陸の黒人奴隷をアンティル諸島に導入し,アンティル諸島から砂糖,タバコ,コーヒー,綿花をフランス本国にもたらす三角貿易を組織し,多大の利益をあげたのであった。18世紀に入り,イギリスとの七年戦争(1756-63)に敗れ,北アメリカとインドからは撤収するが,依然アンティル諸島をめぐる三角貿易は活発であり,ボルドーやナントの繁栄はその表れであった。
絶対主義期の植民地貿易は,革命とともに終焉をみるが,19世紀には,資本主義列強の一員としての新たな植民地支配が始まる。自由・平等・友愛の旗を掲げたフランスも,その点ではためらうところがなかった。むしろ,その普遍的文明の担い手としての意識は,未開の地に文明の光をもたらすものとして,植民地化を美化することともなった。1830年のアルジェ占領に端を発する北アフリカへの進出は,アルジェリアの完全植民地化と,モロッコ,チュニジアの保護領化に帰結する。1870年代より始まる資本主義列強によるアフリカ分割では,サハラを南下して,ガボン,コンゴ,チャド,スーダンなど,西アフリカを中心に植民地支配を拡大し,マダガスカルもまた96年フランスの領有に帰した。さらにアジアでは,中国への進出の狙いをこめて1858年に始まったインドシナへの介入は,87年のフランス領インドシナ連邦の成立をもって確固たるものとなった。この1858年は,日本との間に日仏修好通商条約が結ばれた年でもあり,ほどなく駐日公使ロッシュを通じての幕末政局への介入が始まることになる。こうして,19世紀後半を通じて形成された植民地帝国は,第2次大戦後まで維持され,戦後その独立をめぐり,第1次インドシナ戦争(1946-54),アルジェリア戦争(1954-62)と,長期にわたる植民地戦争の泥沼に足をとられることとなった。
フランスの帝国主義的進出は,植民地支配のみではなく,対外投資や企業進出の形をとっても進められた。とりわけ,1914年以前の帝政ロシアに対する投資は群を抜いている。外国公債への投資による利子取得が高い比重を占めていたことから,レーニンはフランスの帝国主義を〈高利貸的帝国主義〉と性格づけたが,近年の研究は,フランスもまた,単に利子食いのみではなく,外国の産業や鉄道への投資も積極的に推進していたことを明らかにしている。こうして,フランスは,19世紀以来の資本主義的世界体制のなかで,イギリス,ドイツと並ぶ対外進出の中心的担い手となったのであった。
現代,そして未来へ
20世紀に入って,フランスは2度の世界大戦の戦場となり,戦勝国とはなったものの,甚大な損害を被った。第1次大戦では,ドイツ軍との白兵戦のなかで,150万人の戦死者を出し,第2次大戦でも60万人を失った。戦争と革命の世紀を,フランスは生身をもって体験したのであった。第1次大戦の結果は,永遠に世界の主導権を掌中にしているかのごとく信じてきたヨーロッパに代わって,一方では,新しい文明の体現者としてのアメリカの優位が歴然となり,他方では,ロシア革命が,歴史の未来を告知するものとして登場した。しかも,ヨーロッパの危機が叫ばれるなかで,フランスは,危機の鬼子ともいうべきナチスの脅威に苦しまねばならなかった。第2次大戦を経た今日,アメリカもソ連も,新しい世界の告知者としてのイメージは大きく変わった。しかし,ヨーロッパ文明の中心的担い手と自認し,最も根源的な意味において〈近代性modernité〉を象徴する存在であるフランスが,現代をいかに生き,未来をいかに切り開くかは,依然として重い問いであり続けている。
フランスの社会自体,両次大戦に挟まれた1920年代,30年代を通じて,しだいにその変容の速度を速めた。そして,第2次大戦後,経済の高度成長をみた1950年代を画期として,その変化は加速化する。近代の価値観の上に確固とした信念を築いてきたフランス社会にも,高度産業社会に固有の,大衆社会,管理社会,技術社会の傾向が顕在化している。この変動期をいかに生きるかは,単に経済運営の組織化や技術の高度化や教育の効率化の問題ではないし,〈日本に学べ〉といったスローガンで解決できるものでも,もちろんない。それはまさに,文明の総体の問題なのであり,それであるからこそ,現代世界の未来を切り開くべき役割が,いっそうのこと強くフランスに期待されているといってよいだろう。長い歴史を通じて,常に文明のありようを問うてきたのが,まさにフランス人であったからである。
執筆者:二宮 宏之
フランスと日本
近世
フランス人と日本人の最初の出会いは1585年スペインのマドリードで伊東マンショら4人の天正遣欧使節がフランス王アンリ3世の大使に会ったときにさかのぼる。このとき,大使は日本使節をフランスに招きたいというアンリ3世の希望を伝えたが実現しなかった。遣欧使節がローマで新しく教皇となったシクストゥス5世から〈黄金拍車勲章〉を授かったとき,勲章を届け手渡したのもフランス大使であった。
日本人のフランス上陸は,1615年10月支倉常長の一行がスペインのバルセロナからローマに向かう地中海上で嵐に遭い,南フランスのサン・トロペに緊急避難して2泊したのが最初である。一方,1619年には19歳のF.カロンが平戸に上陸し,41年まで在留して日本語に熟達した。《日本大王国志》をオランダ語で著し,日本の姿を西欧に知らせたカロンは,オランダに亡命したフランス人新教徒の子でオランダ国籍をもち,39年には平戸のオランダ商館長に任命され,41年22年間の滞在を終えてオランダのハーグに戻ったが,64年フランス王ルイ14世の大臣コルベールがフランス東インド会社を設立したとき,乞われてフランス国籍を取得した。65年日本大使にルイ14世から任命され,オランダ東インド会社の抵抗に遭いながらセイロン島まで達した。しかし日本行きは阻止され,72年帰途に就き,73年リスボン港外で海難に遭って没した。この間の1637年にはフランス人神父ギヨーム・クールテが,スペイン人神父ミカエル,日本人神父ビンセンシオとともにマニラから琉球に潜入したが捕らえられ,9月27日に殉教した。この頃には日本の工芸品がヨーロッパの宮廷で珍重され,マリー・アントアネットやポンパドゥール夫人らの周辺には漆器,象嵌の屛風,陶器や蒔絵の手箱がオランダ経由でもたらされ,茶の消費も増大し,日本への関心が高まった。
フランス革命の2年前の1787年ルイ16世の命を受けたラ・ペルーズは日本近海を測量して宗谷海峡を発見し,ラ・ペルーズ海峡と命名した。彼は北海道に上陸し,3日を過ごしている。しかし日本の鎖国政策はフランスの直接接触を許さず,オランダ商館が仲介した。フランスの学問もオランダ訳で伝わった。オランダ通詞で医者の楢林鎮山(栄休)はA.パレの《外科学》をオランダ訳で入手,穿顔術,下肢切断術,血管結紮などを知り自著で広めた。1787年(天明7)にはショメル神父Noël Chomel(1633-1712)の《百科辞典Dictionnaire universel》のオランダ語版が,オランダ商館長ティチングから楢林重兵衛に贈られた。1811年(文化8)から高橋作左衛門景保,馬場佐十郎,大槻玄沢らがこれを訳しはじめ,39年(天保10)までに主要部分を《厚生新編》69巻として刊行した。高橋作左衛門景保の父至時(よしとき)はJ.ラランドの天文学書を1787年にオランダ訳から訳している。
幕末
1807年ロシアのフボストフとダビドフはサハリン(樺太)と択捉(えとろふ)島を襲い,番人を拉致して箱館奉行あてに書簡を置いていった。これがフランス語であったため,幕府はオランダ商館長H.ドゥーフに翻訳を依頼するとともに,オランダ通詞本木庄左衛門(1767-1822),馬場佐十郎に命じてドゥーフからフランス語を学ばせた。これが公式のフランス語学習の初めである。この頃,オランダ商館からのニュースによる《風説書》や斎藤拙堂(正謙)の著作でナポレオンの活躍は日本人の注目を浴びた。佐久間象山も憧れ,頼山陽は1818年(文政1)に在世中のナポレオンをたたえる詩《仏王郎詩》を書いている。
松代藩の蘭学者,村上英俊はスウェーデンの学者ベーセリウスの《化学提要》を注文したところ,フランス語の原本が届いたことからフランス語を独学で覚え,1854年(嘉永7)《三語便覧》3巻,64年(元治1)《仏語明要》4巻を刊行し,仏学の祖といわれた。1844年那覇に入港したフランスの軍艦アルクメーヌ号で渡来したパリ宣教師会師フォルカードは,1年滞在し日本語を学習した。クリミア戦争(1853-56)はロシアの勢力がアジアで強くなることをイギリス,フランスに懸念させ,フランスはパリ宣教師会師メルメ・ド・カション,プティジャン,ジラールを那覇に送って日本語を習得させた。55年フランスは琉球と和親条約を結び,ナポレオン3世は日本にグロ男爵を送って58年日仏修好通商条約の締結にこぎつけ,59年にデュシェーヌ・ド・ベルクールを初代総領事として江戸に派遣した。62年幕府は竹内下野守保徳を訪欧使節として送りナポレオン3世に謁見させた。この一行には福沢諭吉,福地源一郎(桜痴),上田友助(敏の父),箕作秋坪,松木弘安(寺島宗則)なども加わっていた。パリで独学で日本語を学んでいたレオン・ド・ロニーLéon de Rosnyは一行中の洋学者と交遊し,翌年から東洋語学校で日本語を教え始め,使節団員の書き残した文書を利用して教科書《日本文集》を作った。
ベルクールの後任L.ロッシュはイスラム世界で長く外交官の経験があり,アラビア語に堪能でイスラムに改宗し,現地語の重要性をよく認識していたので,1864年日本に着任すると,日本語に習熟したメルメ・ド・カション神父を外交官に採用し,薩長を支持するイギリスに対抗して幕府を支持した。さらにメルメ・ド・カションが箱館で交際した栗本瀬兵衛(鋤雲)や小栗上野介忠順(ただまさ)ら,幕府の親仏派と結び,技師ベルニーFrançois Léonce Verny(1837-1908)を来日させて横浜製鉄所,横須賀造船所を建設させ,後にドレフュス事件の際の陸軍大臣となるシャノアーヌJules Chanoine(1835-1915)大尉を筆頭とする軍事顧問団を送り,富岡製糸場のためにはブリュナPaul Brunat(1840-1908?)を呼んだ。65年にはメルメ・ド・カションに横浜フランス語学校を開かせ,67年のパリ万国博覧会には幕府に日本館を出させるとともに,将軍慶喜の弟,徳川昭武をフランスに留学させた。この時の随員,渋沢栄一はパリで近代商業を見聞し,のちに日本経済の大立者となった。
近代
明治維新でロッシュの親幕政策は破綻したが,日仏協力の路線は敷かれていた。近代化へのフランス人の寄与は大きく,多くの御雇外国人が数えられる。法律でのG.E.ボアソナード,G.H.ブスケ,軍事のシャノアーヌ,デュシャルム,マルクリー,A.C.デュ・ブスケ,ガス事業のペルグラン,軍楽隊のダクロン,鉱山開発のコアニェら,数限りない。
日本からも西園寺公望,大山巌,伏見宮,閑院宮,中江兆民などフランスに留学する者が多く出,山本芳翠,黒田清輝,久米桂一郎らが画家のパリ留学の先鞭をつけた。1875年には古市公威(きみたけ)が留学,80年博士号(工学および理学)を取って帰国した。明治10年代からは洋風宮廷建設のため家具職,大工,庭師など,多くの職人が技術習得のためフランスに渡り,ブドウ栽培,ブドウ酒醸造,革細工,製本術,航空術,潜水艦などを学びに行く者も現れた。
普仏戦争(1870-71)で第二帝政が倒れ,フランスが共和国に戻ったことは,日本政府をプロイセンに近づけ,フランスは民権論者に好まれる国になった。渡六之介はパリ・コミューンの経験を《巴里籠城記》に残している。
1900年前後のいわゆるベル・エポックのフランスは日本美術に関心を示したが,画商の林忠正(1853-1906)は1867年のパリ万国博覧会で浮世絵に開眼した作家のゴンクールと協力しながら,1890年から1901年の11年間に版画15万6487枚,絵本類9708冊,掛物846を日本から送らせ,売りさばいた。
フランス文学の邦訳は1878年川島忠之助のベルヌ《80日間世界一周》に始まり,翌年フェヌロンの《テレマックの冒険》を宮島春松が訳し,さらにはデュマの《五九節操史》,ユゴー,ゾラ,ドーデ,モーパッサンらの作品が翻訳され,フランス文学愛好の基を築いた。初期の翻訳は英語を介するものも多かった。大正時代にフローベール,ボードレールがイギリスのA.W.シモンズの《文学における象徴主義運動》(1899)によって紹介され,フランス文学は青年の心をとらえた。
明治以来のフランスの寄与としてはフロジャック師,ド・ロ神父,メール・マチルドら多くの宣教師も忘れることはできない。彼らは病院を建て教育に尽力し,貧民を救済し,信頼を得た。清仏戦争(1884-85)によってフランスはベトナムを植民地とし,また日清戦争後,フランスを含む三国干渉によって遼東半島を放棄させられたこともあって日仏関係はやや疎遠になった。日英同盟(1902)はフランスとロシアを近づけ,またフランス領インドシナ,ニューカレドニアに日本移民が流入したためフランス国内に反日論が起こった。
日露戦争で日本は列強の一つとなったが,財政難から親仏の西園寺首相はフランスで外債を募集した。1907年日仏協約が結ばれ,12年には日仏銀行,日仏協会が設立された。翌13年にはコットJoseph Cotte(1875-1949)が東京にアテネ・フランセを開いて,フランス語,フランス文学,ギリシア・ラテン語の教授を始め,多くの日本人をフランス文化に開眼させた。旧制高校のドイツ語教育を軸とするドイツ文化の影響の前に,幕末以来のフランス嗜好が衰えるのを憂えたフランスは,第1次大戦後まずジョッフル元帥を訪日させ,続いて東洋学者クーランをはじめ多くの使節を送ってきた。彼らの報告に基づき,詩人大使P.クローデルと渋沢栄一は24年財団法人日仏会館を東京に開き,フランス人研究者を常駐させた。クローデルはまた貴族院議員稲畑勝太郎と協力して27年京都日仏学館を開き,フランス語,フランス文化の普及に努めた。美術,文学,服飾,美容,映画などの分野でも大正,昭和とフランスの影響は広がっていった。
日本は1936年日独防共協定を,40年には日独伊三国同盟を結び,40年9月フランス領インドシナに進駐した。45年3月敗戦を見こした日本軍は,インドシナのフランス人を要職から排除し,8月敗戦と同時にホー・チ・ミンがベトナムの独立宣言をする道を開いた。
第2次大戦後
フランスの敗戦と日本の軍国主義の下で筆の重かった学者,評論家は戦後一斉にレジスタンス運動,伝統的人文主義,実存主義などを紹介し,フランス文学は注目を集めた。しかし戦時中にもバレリー全集,アナトール・フランス全集やアラン,デカルトの著作などが出版され続け,渡辺一夫がラブレーの翻訳を地道に刊行していたことも注意しなければならない。少数の愛好者に支えられていたフランス派音楽も戦後は愛好者が増え,フランスで学んだ安川加寿子,池内友次郎らが東京芸大教授になった。フランス政府が文化使節としてジョルジェ・デュアメルやピアニストのラザール・レビを送り,多くの聴衆を集めた。1953年に日仏文化協定が結ばれるとともに政府間の交流も親密になり,日本からは吉田茂(1954),岸信介(1959),池田勇人(1962),田中角栄(1973),三木武夫(1975),鈴木善幸(1982),竹下登(1988),宇野宗佑(1989)の各首相がフランスを公式訪問し,フランスからはポンピドゥー首相(1964),ジスカール・デスタン大統領(1979),ミッテラン大統領(1982,86,89)が日本を公式訪問した。フランスでも正規に日本語を教える高校が現れはじめ,84年には日本語が教授資格試験(アグレガシヨン)に認められた。
執筆者:松原 秀一
政治
政治的風土
〈革命〉の伝統と,イデオロギー的対立,そして複雑な社会階級的構成がフランスの政治構造を永く規定してきた。他の西欧諸国に先がけてすぐれた共和政の伝統を築きながら,革命ないしそれに類する政変をたびたび経験してきたこの国では,政治的対立が一般に原理と原理の対立として観念される傾向が強く,たとえば〈左翼〉,〈右翼〉という言葉が政治的シンボルとして重用されてきた。また国民の心情からいうと,〈革命〉の伝統ゆえか,実際の利害関心とは別に,左翼的・革命的な立場表現を好むという傾きがあり,保守的政治勢力さえも,その命名や公式的ステートメントでは,しばしば急進的な表現に訴える。さらに愛国心の強さという点でも,国民の間に共通の態度がみられ,フランス人は政治的立場にかかわらず多かれ少なかれナショナリストだといわれる。たとえば,戦時下の対独レジスタンスのように国民が政治的立場を超えて結集したことや,かつての米ソの対立の谷間にあって独自の核武装を推進することにほとんど全国民のコンセンサスが見られたこと,などにそれが現れている。
しかし近年,新しい政治意識もみられる。1980年代から90年代にかけて社会党中心の左翼が政権を担うことで,左翼の政策も現実主義的色合いを濃くし,かつてに比べ一般に左右の政治的立場が接近してきている。したがって,イデオロギー的論争よりも具体的政策(たとえば失業対策,雇用の増大など)をめぐっての論争がより重みを増している。これにいっそう拍車をかけたのが89年に始まるソ連・東欧社会主義の崩壊であり,左翼も,〈社会主義〉を表看板に掲げることなく資本主義的市場経済を前提とした体制認識をもつようになり,政策論争の土俵にもかなり共通性がみられるようになった。一方,ヨーロッパ統合(ECからEUへ)が進むことによって,他の西欧諸国との協調が以前に増して求められるようになっている。特に,かつて〈宿敵〉視されたドイツとの間には,1980年代から少なくとも指導層のレベルで〈パリ-ボン枢軸〉と称されるような緊密な連携がみられるようになった。フランス一国のナショナリズムを超えてヨーロッパ主義とでもよぶべき協調的姿勢に向かおうとする動きもみられる。
反面,従来弱小勢力にすぎなかった極右がショービニズム(排外主義)の傾向をはらんだ内向きのナショナリズムを掲げ,支持を伸ばしていることも無視できない。極右の国民戦線(フロン・ナシオナル)は1984年の欧州議会選挙で11%の得票を記録して以来,各種選挙で10~15程度の票を集めており,少なくとも得票上では,今や第三の勢力となりつつある。これは,この国における発展途上国出身の移民・難民の増大への反発や,ヨーロッパ統合によって国家主権が削減されることへの危機感をばねとする現象とみられている。しかし,極右に投ぜられる票は,これに政権獲得を期待しての票ではなく,現状(移民の増大,失業,中小商工業の危機)に対する〈抗議〉票とみられている。なお,小選挙区制の下では極右が国会に議席をもつことは今のところ困難である。
また,左翼支持の表が青年層や知識人層では環境保護派(エコロジスト)に流れるようになったのも1980年代からの傾向である。環境問題の重要性が認識されたこと,その他の市民の意識の多様化を反映している動きといえよう。その得票率は数パーセントであるが,同派は社会党と連携して,政権の一翼を担うこともあった。
フランスでは,イギリスやドイツに比べ伝統的に諸政党の分立の傾向が強く,左翼-右翼の対立構図をとりながらも,二大政党制をなしているとはいえない。左翼では社会党と共産党,右翼では共和国連合(旧ド・ゴール派),フランス民主連合(中道)等が並立しており,政党間のかけひきやその都度の連携も複雑である。以前はこの政党分立が,頻繁な離合集散,内閣の交代を結果し,政治の不安定をもたらしていたが,第五共和政の下では7年間の長い任期をもつ,より強い権限をもつ大統領の下で,政治構造は比較的安定するようになった。多党政治の不安定さと頻繁な政権交代の下で統治の連続性を保障するうえで,フランスでは行政官僚制が大きな力を果たしてきた。それは西欧の他の国々に比べて,より中央集権的である。第五共和政の下で執行権が強化されることで官僚の力も維持されるが,他方,経済成長が進み,市民意識も多様化し,地域の開発要求が強まるにつれ,地方分権化への要請も高まった。こうした背景のなかで,ド・ゴールの下で〈地域圏〉(レジオン)の創設,ミッテランの下で地方分権化改革がそれぞれ行われ,中央集権的行政の手直しも進められた。
第五共和政とその変容
1958年に成立した第五共和政は,フランスの政治的伝統をある面で体現し,またある面でそれを断ち切り,新たな政治的状況を生み出した。アルジェリア独立問題など国家的危機の収束において第四共和政議会勢力が無力を露呈し,これがド・ゴール将軍の登場を促しただけに,第五共和政は,強力な大統領権限をはじめとする執行権の優位を制度の根幹としている。これによって,政党分立による政治の不安定という事態には一応終止符が打たれたものの,議会の権限は縮減され,権力の比重は大きく執行権の側に傾いた。
この強い執行権を日常的に円滑に機能させるためには,強力な政府と官僚団,組織された官僚機構などの国家装置をもたなければならない。こうして第五共和政の下では,行政,政策形成,経済運営などにあたる専門的・技術的官僚,すなわちテクノクラートの役割が増大している。このテクノクラート主導の傾向は,経済近代化政策などにも反映され,EC(ヨーロッパ共同体)に対応しうる資本主義の高度化を至上命令とし,有力企業へのてこ入れ,生産性の低い旧型企業の利害の切捨て,効率的な地域開発などが目ざされ,良かれ悪しかれ政策面でテクノクラート的合理主義が前面に出ていた。外交面では,独自のナショナリズムに立ち,対米,対ソの自主外交をうたい,西側諸国のなかできわめて独自の位置を占めた。
しかし,ポンピドゥー大統領(在任1969-74)を経て,非ゴーリストのジスカール・デスタンValéry Giscard d'Estaing(1926- ,在任1974-81)へと政権が移行するなかで,与党の基盤がより中道寄りに拡大され,議会の機能がいくぶんか重視されるようになった。また,ECとその拡大に同意が示されるなど,その限りで対外的な姿勢にも変化がみられた。
他方,左翼はこの間野党の座にとどまりつづけたが,1970年代からの社会党,共産党,左翼急進運動などの連合の力を背景にして81年にはミッテランFrançois Mitterand(1916-96)が大統領選に勝利を得,社会党主導の左翼政権が誕生した。ミッテラン政権は,国有化の拡大,税制の改革などを実施し,分権化の改革に着手している。82年および83年の法は,国の権限の地方への委譲,市町村への県知事の監督権の縮小,地域圏の地方公共団体への格上げなどを含んでいて,種々限界はあるが,長年の中央集権的構造に手直しを加えている。しかし左翼政権は,当初の財政政策の失敗から緊縮財政に転じ,鉄鋼産業の合理化にも乗り出すなど国有企業の改革にも着手し,労働者階級との軋轢も覚悟の上で社会経済の近代化を図ることとなった。これは左翼のアイデンティティにも重大な影響を与え,同政権からの共産党の離脱を結果することとなった。また,90年代には統合の進むEC,EUの下で,種々の制度の調和化への圧力が強まり,フランス独自の経済・財政制度を維持することも困難となる。すなわち,国有企業の民営化や財政赤字の削減が強く求められ,ミッテラン,次いでシラクJacques Chirac(1932- )政権はその対応に苦慮することとなった。これらさまざまな意味で,第五共和政の当初の政治構造は大きな変容をとげてきた。
大統領と政府
第五共和政憲法によれば,大統領の任期は7年で,当初は間接選挙(国会議員,県会議員,市町村会の代表などによる)が定められたが,ド・ゴール初代大統領の強い意向から,1962年の国民投票によって直接普通選挙に改められた。この大統領が首相を任命するが,首相は国民議会がその不信任を可決した場合などには大統領に辞表を提出しなければならない(第50条)から,議院責任内閣制的メカニズムも具備されていないわけではない。〈半大統領制〉などと呼ばれるゆえんである。大統領は首相の提案により,他の大臣を任命し(第8条),閣議を主宰する(第9条)。大統領は重要問題については直接に国民投票に付することができ(第11条),さらに国民議会を首相および両院議長に諮問したのち解散することができる(第12条)。さらに憲法第16条は,大統領に,国の独立などが脅かされる場合,一定の条件の下で非常措置をとる権限も認めている。そのほか,大統領は政令ordonnance,命令décretに署名し,文官,武官などを任命する(第13条)。
首相は,前述したように議会(下院)に対して責任を負い,その点で大統領とは立場が違う。大統領と並ぶいま一人の政府の指導者とみることもできるが,大統領がいわば政府の〈真の首長〉として内外の重要政策の決定に当たるとすれば,首相はこれを補佐し,かつ執行機関としての政府の活動を指導し,法律の施行を保障するといってよい。実際には,内政一般や経済,社会,財政などの個別政策の決定,執行は,首相以下の政府にゆだねられることが多い。憲法の諸規定は,首相が大統領と一体となって行動することを想定しているが,重要政策において両者の見解が対立するような場合,首相の辞表提出により解任されることもありうる。また,国民議会の多数が大統領とは異なる政治勢力によって占められる場合,大統領は,政治的立場を異にする首相を指名せざるをえず(いわゆるコアビタシヨン),両者の対立は恒常化する。
議会と諸機関
議会は,下院にあたる国民議会Assemblée Nationaleと上院にあたる元老院Sénatから成る。前者は任期5年で直接選挙,単記2回投票,後者は任期9年で3年ごとに3分の1ずつ改選され,市町村会の代表を中心とする選挙人団による間接選挙をもって構成される。前述したように第四共和政に比べ第五共和政の下では議会の力は低下したが,その実態は,下院の権限が大幅に削減され,上院の権限が若干強化されているという点にある。ただし,下院が上院より優越的地位にあることには変りがない。
第五共和政憲法では,議会の立法の可能な範囲の事項が限定的に列挙されている(第34条)。基本的な事項は含まれているとはいえ,この点が議会の権限をめぐっての第四共和政との最も大きな変化であろう。列挙されている事項以外のものは,政府の命令の性格をもつとされる(第37条)。また,議員提出の法律案および修正案が国庫収入の減少または支出の創設や増加を生ずる場合は受理されない(第40条)。なお,常任委員会の数が減らされ,各院に6以下(第四共和政下では19)と定められていることも(第43条),審議権に加えられた制限といえよう。
議会の運営に関していえば,原則としてすべての法律案は同一条文で両院において審議され,採決されねばならない。両院の意見が各2回の審議ののち不一致の場合,また政府が緊急を宣した場合,首相は両院協議会に成案の提出を求めることができ,それでも成案が得られないときには,最終的に下院が議決権をもつ(第45条)。予算案は下院が先議権をもつが,40日以内に採決をしない場合,政府はこれを上院に付託することができ,両院不一致の場合は下院に最終議決権があるが,通算70日以内に採決されないときは,政府は予算案の各項を政令により執行することができる(第47条)。
憲法上定められているおもな機関としては,ほかに次のようなものがある。
(1)憲法院Conseil Constitutionnel 憲法の遵守を確保するため,組織法および議院規則について,また通常の法律および批准前の国際的協定について合憲性を審査する(ただし,審査請求権は公権力機関および国会議員に限られる)。その裁決は絶対的,終局的であり,いかなる機関へも上訴は許されない。憲法院は大統領と両院議長がそれぞれ3人ずつ任命する9人の委員(任期9年,3分の1ずつ3年ごとに改選)と元大統領(任期は終身)から構成され,そのうち1名が大統領により院長に任命される。
(2)高等司法会議Conseil Supérieur de la Magistrature 裁判官の任命に関し政府に提案を行い,司法権の独立性にかかわる問題につき諮問を受け,また破毀(はき)院院長を議長に,裁判官の懲戒裁判をも行う。大統領(高等司法会議議長),司法大臣(同副議長)および大統領によって任命される9名の任命委員から構成される。
(3)高等法院Haute Cour de Justice 大統領の大反逆罪,閣僚が職務上犯した重罪,軽罪について裁判する。両院からそれぞれ選出された12名ずつの議員をもって構成される。
(4)経済社会評議会Conseil Économique et Social 経済・社会問題に関する計画案や政府提出の法律案について,政府の諮問を受けて意見を答申する。諮問機関ではあるが,また自発的に経済・社会問題につき必要と考えられる改革案を作成し,政府に提案することができる。委員は200名で,うち140名はおもな職能団体などから選出され,60名は政府によって任命される。任期は5年である。
なお,憲法上の機関ではないが,ほかに重要なものとしては,法案作成に関して政府に助言を与えるとともに,最高行政裁判所としても機能する参事院Conseil d'Étatがある。
政党
フランスでは,必ずしも政党が政治のなかでつねに重要な役割を演じてきたといえない。フランスの政党は他の西欧諸国に比べ党員数が多いとはいえず,共産党を除くと,その組織や規律もしばしば強固さを欠いている。フランス革命時に生まれた〈左翼〉-〈右翼〉という政治勢力の区別の観念は,少なくとも二元的分類という限りで今日まで生きている。しかしそれぞれの陣営は複数の政党を抱え,内的統一からはほど遠い状態にある。ド・ゴール派の流れを汲む共和国連合(RPR)も,フランス民主連合(UDF)も単一政党ではなく,他方,〈左翼〉とよばれる勢力も社会党,共産党,環境保護派などの連合であって,単一政党の力は弱い。すなわち,イギリスや西ドイツのような二大政党の併立,交替のシステムではなく,保守の連合(しばしばこれに中道諸派が加わる)対左翼の連合(2回目の投票ではこれに事実上極左諸勢力も合流)という形で勢力対比が生まれる。それだけに,連合内での主導権争いや国会議員,地方議員の選挙の際の連携の方式はしばしば複雑な様相を呈する。このなかにあって極右の国民戦線は独自の道を歩んでいるが,その支持者は2回目投票では大半が右翼の候補者に投票しているとみられる。
ただし執行権優位の現共和政下では,大統領のイニシアティブ(とくに解散権の行使)による与党多数派の形成が容易になり,加えて小選挙区2回投票制が得票率以上に大きな差のつく与野党勢力比をつくりだし,さらに2回目投票に向けての政党間協力(場合によっては永続的な連合)を不可避とするに至り,小政党の分立・拮抗による政治的不安定という従来の状況は大幅に変化している。
また近年,根っからの政党活動家に代わって高級官僚などを出身の母体とするいわゆるテクノクラートが政党のリーダーとして比重を高めている。これは,社会党など左翼内部においても進行している現象である。
外交
第2次大戦後の冷戦構造のなかで西側陣営の一員としてアメリカへの従属を強いられ,植民地戦争の打ち続く敗北で屈辱をなめてきたフランスは,ド・ゴールの下で,〈ナシヨンnationの栄光〉の回復を目ざし,独自のナショナリズムに立って,対米,対ソ,自主外交を展開した。しかし,ド・ゴール後,アメリカとの関係もかなり修正され,イギリスのEC加盟を認めるなど(1973),EC重視の姿勢を打ち出した。前述したように,ドイツとの協調によるヨーロッパ統合の積極的推進は,過去20年来の変わらない方針となっている。ミッテランはこうした外交路線をほぼ受け継ぎ,第三世界との関係強化にいちだんと力を入れ,ラテン・アメリカ,アジア,アフリカに積極的に訪問外交を展開した。ただし,90年代にいたって,アフリカ諸国において生じる紛争,政変,クーデタ等に旧宗主国として介入を求められ,軍事介入をする機会がたびたびあったが,その都度困難にも遭遇し,対アフリカ諸国との関係は再検討を迫られている。一方,シラク大統領の下で95年に核実験の再開が国際世論の反対を押し切って行われ,アジア,オセアニア諸国から激しい反発を受けた。自前の〈核〉戦力を維持するというフランスの政策も,冷戦終了後の緊張緩和のなかでやはり再検討を迫られているといえよう。
軍事
1950年代に大部分の海外植民地を失い,以後軍事面では本国の防衛を主とするに至ったフランスであるが,上述のようにド・ゴール時代にアメリカの〈核の傘〉の下に入ることを嫌い,NATOとも一線を画し,自主防衛の道を進んできた。いわゆる核抑止力による自国領土の防衛を政策の基本としているが,前述のように,その核実験再開には強い国際世論の反発があった。今日,戦略核兵器としては原子力潜水艦,ミラージュIV A型爆撃機,中距離弾道ミサイル(IRBM)などを保有している。なお,フランスはかなり規模の大きな兵器産業をもち,世界有数の武器輸出国となっており,この面で間接的に中東や第三世界の情勢に影響を及ぼす可能性があることも否定できない。徴兵制が敷かれ,18歳以上の男子は兵役に服することが義務となっていたが,シラク大統領は1996年この兵役の廃止を打ち出した。なおフランスは,1996年,1966年以来脱退していたNATOの軍事機構に部分的に参加することとなった。
司法
第五共和政憲法では,司法権の独立は,高等司法会議の補佐をうけた大統領によって保障されている(第64条)。
フランスの近代的法典のほとんどが編さんされたのは,ナポレオン1世の時代であり,司法組織もこれに伴って整備されたが,その後時代を経るとともに実情に合わせての改革が加えられてきた。1958年12月の裁判所組織の改革は大規模なもので,とくに民事裁判組織のなかで,民事裁判所に代えて大審裁判所Tribunal de Grande Instanceが設置された。なお,フランスでは伝統的に行政裁判権は行政権に属するものとされ,司法組織とは別に行政裁判所Tribunal Administratif,前述の参事院などの行政裁判組織がある。そこで,司法裁判組織との間に管轄の争いが生じる場合に備え,権限裁判所Tribunal des Conflitsが置かれている。
司法組織は,大別して民事裁判にかかわるものと,刑事裁判にかかわるものとに区別される。
(1)民事裁判組織 小審裁判所Tribunal d'Instanceと大審裁判所に分けられる。小審裁判所は原則として郡を単位として設けられ,小規模,小額の訴訟を扱う。大審裁判所は原則として県を単位に,県庁所在地に置かれ,訴額または事件の性質によって小審裁判所その他の第一審裁判所の管轄とされるものを除く,いっさいの民事事件を扱う。小審裁判所の管轄事項のうち特定のものについての控訴は,大審裁判所が扱う。ただし一般的には,控訴については全国にある控訴院Cour d'Appelがこれにあたる。最終審としては,刑事裁判と同じく破毀院Cour de Cassationがある。
その他,民事の特別裁判所として,商事裁判所,労働審判所,小作関係同数裁判所があり,これらではいずれも判事が,職業活動に従事する者を選挙権者として(間接選挙の場合もある),職域別・地域別などによって選出されるという点に特徴がある。
(2)刑事裁判組織 フランスでは,犯罪に次のような基本区分が設けられている。すなわち,法が体刑などをもって罰する殺人,強盗などの罪にあたる〈重罪crime〉,法が懲治刑をもって罰する脅迫,傷害,窃盗などの罪である〈軽罪délit〉,法がおもに罰金などの取締刑をもって罰する軽い罪にあたる〈違警罪contravention〉の3種がそれである。そして,これらに応じて裁判の管轄や手続も違っている。
まず重罪院Cour d'Assisesは,重罪を管轄し,法廷は3名の裁判官と市民から選ばれる9人の陪審員からなり,非常設の裁判所である。その判決は終審で下され,控訴することができない。軽罪裁判所Tribunal Correctionnelは,軽罪の審理にあたるもので,大審裁判所に設置されている。法廷は3名の裁判官で構成され,陪審員はない。判決は第一審のそれとして下され,控訴が認められる。控訴審は,控訴院軽罪部があたる。違警罪裁判所Tribunal de Policeは,小審裁判所に設置され,管轄地域内において発生した違警罪を扱う。第一審として下された判決のうち,特定のものについては控訴が可能であり,同じく控訴院軽罪部がこれにあたる。
重罪院および控訴院の判決に対しては,法律手続に関してのみ,破毀院に上告することができる。
地方行政
フランスの地方行政は,ナポレオン1世時代に整備された中央集権的制度が1世紀半以上にわたって維持されてきた。このため,地方自治の発達は制約を受け,地方公共団体は一般に国の行政単位という性格が強かった。しかし,1982年ミッテラン政権の下で地方分権化の改革案が議会を通過し,年来の制度にも新しい変化がもたらされることになった。
フランスは,96の県département,四つの海外県département d'outre-mer,四つの海外領territoire d'outre-mer,二つの(海外)地域公共団体collectivité territorialeから成り,約3万6000の市町村communeをもっている。1964年以来新たに21(のちに22)の〈地域〉(レジヨンrégion)が設けられ,広域的な地域開発圏として機能するようになった。
各県には,政府によって任命され,県における国の受任者,および県行政事務の執行機関の役割を果たす知事préfetが置かれていた。その権限は強く,治安の維持,法令や政府の決定の執行,各省出先機関の監督,市町村の監督などに及んでいた。それに対して,直接選挙によって選出される県会Conseil Généralがある(任期6年)。しかし,その権限は限られており,県知事の諮問機関という性格が強かった。ところが82年の改革では,知事の占めていた県行政の執行機関としての機能は,県会議長に移されることになった。すなわち知事は国の受任者,地方公共団体としての県の執行責任者は公選原理に基づく県会議長,というふうに区別され,全体として県の自治の権利が強められている。
市町村においては,直接選挙によって市町村会Conseil Municipalの議員が選ばれ(任期6年),議員の互選によってその議長である市町村長maireが選ばれる。この意味で,市町村は県よりも自治体的性格が強い。また,1992年に批准された〈マーストリヒト条約〉により,EC加盟各国では,市町村選挙の選挙権を加盟国出身の滞在者に認めることが定められ,フランスも憲法を改正し,これを制度化している。市町村長は,法令の公示や戸籍管理など国の委任事務を行うとともに,市町村会を主宰し,その議決や予算を執行する。しかし,市町村は大は100万都市から小は人口100未満の寒村までも含む規模のまちまちな団体であり,小規模である場合財政上その他で県や政府に依存することは避けられず,自治は名ばかりのものとなり,この点にも大きな問題がある。なお82年の改革では,県知事など上級機関の市町村への監督権限がかなり弱められている。
執筆者:宮島 喬
経済,産業
第2次大戦後の成長
19世紀半ばまで,イギリスに次いで世界第2の経済大国を誇ったフランスは,世紀末から20世紀初頭には後発のドイツ,アメリカに追い越され,第2次大戦時には経済的後進国に数えられるにいたった。この経済的没落の最大の理由は,産業革命に続く資本主義の発展期において,先進工業国に等しく見られた〈人口爆発〉がフランスにおいては生じなかった事実に求められる。すなわち1830-1930年の100年間にイギリス,ドイツ,アメリカの人口はそれぞれ3倍,2倍,13倍(移民の流入が大きい)に増大したにもかかわらず,フランスはわずか1.3倍にとどまった。このため国内消費市場の大規模な発展は望めず,労働力供給も制約されざるをえなかった。この人口抑制をもたらしたものは,中世の百年戦争や黒死病から始まり,大革命とナポレオン帝政下の相次ぐ戦乱へと続く,たび重なる大量死に直面したフランス人がその心の底深くに無意識のうちにしみ込ませていた〈人口増加は失業と悲惨をもたらす〉という確信であり,〈マルサス主義〉と呼ばれるものにほかならない。そしてそれが経済活動に反映されて〈産業のマルサス主義〉を生み出す。小規模な同族経営の支配と手工業,小商人層の肥大化が,他の西欧諸国に比して著しい。とりわけ過当競争と過剰生産とによる企業倒産という強迫観念にとりつかれ,変化や拡張を嫌い,保護主義へと傾斜する。そして利潤は拡大再生産のために再投下されるよりも,しばしば国債や外債など,安全性と収益率の保障された非生産的な資金運用にまわされたのであった。
しかし第2次大戦後,フランスはめざましい経済成長を達成し,これまでの伝統的な社会経済構造は大きな変貌を遂げるにいたった。その変貌のありさまを以下にあげてみよう。(1)農業人口と農村人口の大幅な低下が進み(1946年のそれぞれ36%,47%から75年の11%,32%へ),フランスは農業国から工業国に変貌し,しかも都市型社会と呼ばれるにふさわしい先進工業国の仲間入りをした。(2)戦後,劇的ともいうべき出生率の上昇がみられ(1.5%から2.0%へ),これが少なくとも1960年代半ばまで続いた。(3)フランス人の間に持続的な変化や拡張を積極的に受け入れる精神的風土が確立した。大衆はより多く消費を望み,企業は新たな需要を満たすために喜んで投資を進める。そして国家機関と産業界にはダイナミックな発展を求める〈新しい型の人間〉が進出して指導的な地位に就いた。〈マルサス主義〉がなおフランス人の意識に色濃く残っている事実は否定しえないにせよ,戦前と比べて戦後のフランスは大きく変貌したといわなければならない。
経済発展の3段階
第2次大戦後のフランスの経済発展は,大きく3段階に分けられる。すなわち,(1)解放後,経済再建が行われた戦後復興期,(2)ド・ゴールが大統領に就いて第五共和政が始まった1958年からオイル・ショックの1973年までの高度成長期,そして,(3)その後今日まで続く低成長期である。
(1)戦後復興期(1945-57) 終戦後,フランスが直面した最大の問題は,戦火によって壊滅的打撃を受けた生産設備(農業は戦前水準の7割にとどまったが,工業は2割にまで落ち込んだ)の復興であったが,同時にフランス産業が体質的に備えていた〈マルサス主義〉からの脱却,すなわち経済構造の近代化を断行することが最重点の課題とならざるをえなかった。こうして国有化と計画化とがフランス経済近代化達成のための二つの武器となった。
まず国有化は,自動車メーカーのルノーの例にみるように,対独協力派への制裁という〈愛国的性格〉を有していた点も当初は無視しえなかったが,しだいに近代化を目的とする方向に収斂されていった。それは,(a)石炭,電力,ガスのエネルギー部門と鉄道,航空の運輸部門といったインフラストラクチャー部門の国有化,(b)四大預金銀行,保険といった金融部門の国有化にほかならない。これによって小規模分散性の打破(電力会社1860社,ガス会社724社をそれぞれ1社にまとめる),産業融資の拡大,経営の積極化,政府の財政的てこ入れ,大規模な近代化と生産能力拡大などが図られることになった。
次に計画化は,当初アメリカの対欧復興援助(マーシャル・プラン)への受け皿となり,経済復興のための基幹部門への投資割当て(傾斜生産方式)をなす〈真の〉国家計画(計画の立案者である経済学者モネJean Monnet(1888-1979)の名をとってモネ・プランと呼ばれる)として構想された。しかし経済の再建とともに,統制的手段の採用はしだいに放棄され,減税措置や利子補給,起債認可,各種助成金や奨励金などを見返りに,企業が投資契約を国と交わす,という刺激と合意とによる誘導的手法が導入されるようになった。そして来たるべき5ヵ年間の中期的な経済・社会の方向と枠組みとを明確に定めるべく,広範な経済主体(官僚,経営者,農民,労働者,青年,地方代表)が各種の近代化委員会や経済社会審議会に加わった。資本主義国の多くにみられる単なる経済予測のシステムにとどまるものではなく,〈積極的計画〉である点が,フランス流計画化の特色となった。この国有化と計画化とを主たる政策手段にする公的部門の肥大化により,戦後のフランスは,典型的な混合経済économie mixteの国となり,また官僚による政治経済の全面的コントロール,というディリジスムdirigisme(国家主導主義)の伝統がいっそう強まることになった。
(2)高度成長期(1958-73) 1958年にEEC(ヨーロッパ経済共同体)が成立した。同時にこの年ド・ゴールが大統領に選ばれ,第五共和政が始まった。こうして開放経済に移行したフランスは,強力なゴーリスト体制を武器に経済基盤の強化に取り組んだ。当時,アメリカ資本は自国内の資本過剰傾向から対欧進出を積極化させており,しかも71年まではフランスへの直接投資が西ドイツへのそれを上回る勢いで進んでいた。このため,アメリカによるフランスの〈植民地化〉と〈技術奴隷化〉の危機が,官民あげて叫ばれるにいたったため,ド・ゴールが採用した産業政策の目標は,(a)経済的・技術的,とりわけ軍事的な独立の確保を目ざすための,独自のコンピューター開発(プラン・カルキュル),コンコルド,エアバス計画(イギリスと協力),アメリカなどとは違ったカラー方式(SECAM)をとるカラーテレビの開発(ソ連と協力),(b)重要産業のてこ入れによる国際競争力の強化(鉄鋼,造船,化学,機械などの〈業種別計画〉),(c)企業税制改革や株式市場の強化,金融機関の統合による企業再編の促進,などにあった。この時期に,政府の積極的な産業政策に助けられて,大規模な集中合併運動が展開され,企業規模は著しく拡大し,寡占体制が成立するにいたった。産業構造も高度化し,重化学工業が拡大した。農業においても,フランスに伝統的な小農paysanが急速に減少していき,北部小麦地帯の資本主義的借地農fermierを中心に大型化が進んだ。
1959-73年のフランスの経済成長率は年平均5.5%をしるし,日本(10.5%)を除く主要国を上まわった(イタリア5.1%,西ドイツ4.8%,アメリカ3.9%)。この高度成長は輸出の大幅な伸びによって支えられたが,労働生産性と資本生産性との著しい向上がそれを可能にしたといえる。他方この間の労働分配率をみると,フランスはいずれの主要国をもしのぐ高い水準を続けていた。組織率は著しく低い(二十数%)にもかかわらず,きわめて政治化しているフランスの労働組合(CGT,CFDT)が,賃金引上げに強力な闘争を展開し,政府,経営者は比較的安易に労働側の主張を受け入れ,労賃コストの上昇を価格引上げのインフレ政策によって吸収するという傾向が強かったためである。次の低成長時代の訪れとともに,この矛盾が顕在化し,フランスの経済的地位は大きく揺らぐことになった。
(3)低成長期(1973-) 1973年の第4次中東戦争の結果生じたオイル・ショックによって世界は低成長時代に入った。フランスにおいても,インフレ,雇用,成長,国際収支などのそれぞれの局面で困難が深まったために左翼政党が躍進し,その結果,左右の政治勢力間で,また政府部内でも,政策の優先順位をめぐって対立が激化する時代が始まった。
とりわけ経済再建の方法について,リベラリズム(アメリカでは社会主義的傾向をさすが,ヨーロッパ的文脈では正反対に新保守主義を意味する)とディリジスムとの間のイデオロギー対立が深まった。保革の政権交替がめまぐるしく生じ,自由主義と介入主義との間で政策スタンスの180度転換が繰り返された。
まず1974年に非ゴーリストから初の大統領に就任した中道右派のジスカール・デスタンは,脱ゴーリスムの自由化政策を掲げて低成長時代に立ち向かった。だが失業の増大には歯止めが掛からず,1973年の40万人が,次期大統領選の行われる81年には170万人に急増してしまい,大統領の座は24年ぶりに社会党のミッテランにさらわれることになった。左翼連合政権は,国有化と計画化とによる介入主義で経済の立直しを図ろうとしたが,やがてフランス経済をがたがたにさせて,緊縮政策への政策転換を余儀なくされたのである。
ミッテランは1989年に奇跡の再選をなしとげ,ナポレオンの支配を上回る14年の長期大統領政権の座を誇ったかにみえるが,実はこの2期の大統領期間中それぞれ1回ずつ,1986-88年と1993-95年にコアビタシヨンcohabitation(保革共存。左翼大統領と保守首相との保革共存)に追い込まれ,実権を削がれてしまっていた。その後1995年に,ネオゴーリストのシラクがようやく社会党から大統領の座を奪還したものの,わずか2年にして選挙戦で敗れ,さらに第3次のコアビタシヨン(今回は右派大統領のもとでの左派内閣)が訪れることになった。
大統領の任期7年と国民議会の5年との差がこの〈フランス的例外〉を生んだ元凶である。フランスでは1981年以降,合計5回の総選挙が行われてきたが,いずれの場合も例外なく政権交代が実現し,いわば民主主義のお手本を示してきた。とはいえ短期の政策転換は,改革の不徹底や経済運営の非連続をもたらし,マイナス面は小さくない。
低成長時代におけるフランス経済政策は,このように比較的短期間に振幅の大きい変化が繰り返された点に特徴があるが,時の推移とともにこの揺れ幅が小さくなってきたことも事実である。とくに第2次ミッテラン大統領時代以降,左右間の政策収斂が進んだ。それは第1に,失業の増大と国際競争力の低下,というフランスの構造問題が深刻化して,政策の許容幅が大きく狭められてきたためであり,第2には,新保守主義と介入主義というイデオロギー的原理主義がしだいに有効性を失い,リアリズムが力を伸ばしてきたからである。
ミッテランのフランス
1981年5月,ミッテランがジスカール・デスタンを破って大統領に選ばれ,23年ぶりに左翼政権が誕生し,フランスはその相貌を大きく変えることとなった。新政権の取り組んだ構造改革の第1は,ジスカール・デスタン大統領の自由化政策によって弱体化した混合経済の基盤を再び強化することにあり,国有化の拡大と計画化の復権がその主たる手段となった。1974年の石油危機以降,フランス経済は長期不況に陥り,とりわけ民間企業が衰退色を深めていったとき,国有企業のみはこれとは逆にかなり大幅な成長をしるしていた。このためミッテラン政権は,国有企業拡大による産業の活性化を図った。そして重化学,エレクトロニクス,情報などの戦略的6巨大企業と,世界各地で投資活動を展開する金融資本グループである2大事業銀行と,39大預金銀行とを国有化した。この結果売上高でみる製造業全体に占める公的セクターの比率は18%から32%に,また貸出比率でみる国有銀行のシェアは20%から33%へと,それぞれ大幅な増大をみせた。
次に経済計画については,ジスカール・デスタン前大統領下に進んだ非計画化の動きに歯止めをかけた。すなわち,既存の計画庁と国土整備庁とを,協同組合活動を統括するために新設した社会経済庁と併せて,計画・国土整備省の管轄下においた。そしてこれまでの〈経済社会発展計画〉を〈経済社会文化発展計画〉と名称変更して計画の対象領域を広げ,また〈計画第2法〉を制定して財政的裏づけを与え,真に執行されうるものとした。こうしてジスカール・デスタン大統領下に自由化が図られた混合経済の基盤は再び強化され,保護主義と介入主義の伝統がよみがえった。
構造改革の第2は,社会党の公式理論たる自主管理社会主義socialisme autogestionnaireの理念を表現する,(a)地方分権化と,(b)労働者の権利拡大とにある。フランスは中央集権の最たる国といってよい。フランスに現存するほぼすべての官職と行政制度とはナポレオン帝政以来変わっておらず,県知事は任命制であった。市町村には完全な地方自治が与えられておらず,県知事による後見監督制度が存在していた。道路,鉄道,通信網の〈すべての道はパリに通じる〉。地方発パリ行きの空の第1便は,許認可を求めて中央官庁詣でに精を出す重役,地方議員,市町村長で満席になる。租税全体に占める地方税の比率はイギリス25%,ドイツ35%と比べると,フランスは19%と格段に低い。
ミッテラン新政権はこの中央集権の伝統にメスを入れた。まず集権制の牙城たる内務省を内務・地方分権省に改組し,県知事制を廃止して住民が直接選出する県議会の議長に県の行政執行権をゆだね,また市町村に完全な自治を与えることにした。地方税の比率も25%にまで引き上げられることになった。そして各種行政権限も大幅に地方自治体に移譲されることになり,フランスの集権的伝統も大きく揺らぐ可能性がある。モーロア首相はこれを〈静かな革命〉と呼んだ。
フランスは先進国中最も所得格差の大きい国(OECDの1976年のレポート)であるばかりでなく,労使関係においてもきわめて後進的である。一方では同族経営が支配的で経営者が家父長意識を捨てきれず,他方で組合の組織率は二十数%とヨーロッパでは並外れて低く,しかも政治傾向ごとに組織は分裂している。このように労働者の苦情や不満を組織化するルートに欠けており,団体交渉の伝統が乏しく,自然発生的な山猫ストが頻発する。ミッテラン政権は,この硬直的労使関係の近代化を狙って,労働者の企業内権利拡大を定めた四つの法律を次々に成立させ(時の労相の名を冠して〈オルー法〉と呼ばれる),従来の労働法典の過半を書き替えるにいたった。そのおもな内容は,団体交渉の義務化,経営内容の開示,就労規則や労働条件に対する労働者の集団的表現権の認知などにある。
さて以上のようにミッテラン政権の誕生とともに,フランスの伝統的な時代遅れの社会構造は変化を遂げつつある。しかし新政権が当初国際環境を無視してケインズ主義による景気浮揚策に走った(最低賃金と社会保障給付の大幅引上げ,6万人の公務員増員,とくに1982年度予算を前年比27.6%膨張させた)ことから,インフレーションを激化させた。さらに国有化がイデオロギーの先走りから効率化を欠いた独善的なものに終わり,また保護主義的・介入主義的性格が強く,エレクトロニクスなど先端産業中心の産業政策に対する経営者の不満が急激に高まり,経済の長期停滞を招くにいたった。こうして83年3月の地方選挙での敗北を機に,ミッテランは大胆な政策転換に踏み切り,ドロール・プラン(時の蔵相の名を冠する)と呼ばれる包括的な厳しい引締策に転じ,賃金,物価の抑制,衰退産業の人員整理,政府介入の縮小などを行おうとした。
ミッテラン政権下に進められたフランス経済・社会の大胆な構造改革は,経済政策の失敗によってもたらされた長期不況によって,十分成果を挙げていない。しかし,たとえ社会党政権が短命に終わろうとも,この改革が70年代に進んだフランス社会の変貌,とりわけ〈新しい労働者階級〉をはじめとする新中産階級の肥大化に応える限りで,極端な後戻りは不可能であろう。
執筆者:長部 重康
社会,文化
社会の中の文化の位置
今日のフランス国家には,ルイ14世やナポレオンやド・ゴールが体現していたような軍事的・政治的威光はない。経済は停滞し,国際的発言権は低下している。フランスに誇るべきものがあるとすれば,それは文化の伝統であり,同時に,その文化を問い直していく文化の革新の姿勢である。文化なきフランスという観念は成立しえない。事実この社会で文化は高い位置を与えられている。文化への崇拝の念は幼少期からの教育をとおして人びとの精神に深く刻みこまれている。またこの社会において成功するためには文化=教養を深く吸収している必要があり,作家,芸術家,学者はもとより,ジャーナリスト,出版人,政治家に対しても,教養豊かな知識人であることが要求される。とりわけ重視されるのは言語表現であり,多くの知識を参照しつつ自己の考えを独自の角度から表明する言語技術の習得が,学校教育の中心に置かれている。著名な政治家(ブルム,ド・ゴール,マンデス・フランス,ミッテラン)がすべて一流の文人であるのは偶然ではない。
しかし文化に対するこの崇拝の念は,他方,文化の制度化と,知識人の特権化を生み出してきた。16世紀にフランソア1世の創設したコレージュ・ド・フランス,17世紀にリシュリューの創設したアカデミー・フランセーズ,19世紀初頭ナポレオンによって国立劇場に指定されたコメディ・フランセーズは,文化の三大殿堂として,それぞれ,学問,言語,演劇の領域で,規範としての機能を保ち続けている。また総合大学(ユニベルシテuniversité)は今でこそ大衆化の道をたどっているが,これに代わって高等専門学校(グランドゼコール)が競争試験の厚い壁を設けることによって,少数エリートの養成に努めている。これらの古典的制度機関と並んで,近年では,ラジオとテレビが強力な制度的媒体として登場した。すべて国営であり,しかも限られた数のチャンネルしかもたないこれらのメディアをとおして,知識人は世論に絶大な影響を及ぼしうる立場にある。たとえば現在,テレビの最大の人気番組は〈アポストロフ〉と題された知識人による大討論の中継であり,数百万の視聴者の目を釘づけにするこの番組は,書物の売行き,映画や芝居の興行成績を左右するだけでなく,社会的なできごとについての人びとの意見形成に少なからぬ役割を果たしている。またある調査によれば,フランス人の12%は,知識人の態度表明によって選挙の際の投票を左右されるという。作家レジス・ドブレはこうした現象を〈知識人権力〉として批判しているが,1968年の五月革命も,この文化の制度化と知識人権力に対する異議申立てという側面をもっていた。文化が社会の中で占める位置はいぜんとして高いが,制度をとおした知識の伝達・習得としての文化という概念が,生活の中からの自己表現という文化の概念としのぎを削っているところに,1968年以後のフランス文化の位置がある。
フランス精神とは何か
フランス人は〈われわれはデカルト主義者だ〉と好んで口にするが,実際,明晰さと論理性とはフランス精神の最大の特徴と考えられている。たとえば,18世紀の作家リバロルによれば,〈明晰ならざるものはフランス語にあらず〉ということになる。ある人びとはまた,ベルサイユ宮殿を念頭に置きながら,人工的な秩序と調和をフランス精神の真髄とするであろう。中世ゴシック建築にみられる幾何学的精神と繊細の精神との総合を重視する人もいるかもしれない。19世紀の批評家ルナンに言わせれば,〈フランスの偉大さは対立的な両極端を包容する点にある〉ということになる。しかし,フランスはまた数々の革命を経てきた国でもある。自由と反抗の精神のうちにこそ,フランス人性をみる者も少なくない。実際,フランス史の中に姿を現す最初の英雄は,カエサルの軍隊に反抗して捕虜となり,ローマで処刑されたガリアの隊長ウェルキンゲトリクスである。また今日のフランスの国家的祝祭日は7月14日,すなわち1789年パリの市民がバスティーユ監獄を襲撃した日である。そしてそのフランス革命は,自由,平等,友愛の理念を標榜していただけではなかった。1793年の憲法は次のように,蜂起の義務をさえ規定していたのである。〈政府が人民の権利を侵害すれば,蜂起は人民全体にとっても人民の各単位にとっても,義務のなかでも最も神聖にして欠くべからざる義務となる〉。同じように,ロマン主義から象徴主義を経てシュルレアリスムへ至る詩の運動の中に,サドからロートレアモンを経て,アルトー,ブランショへと通じていく散文の運動の中に,言語的規範に対する反抗と逸脱の意思を読み取ることも可能である。
しかし他の人びとはこう反論するかもしれない。フランスとは制度であり,記念物であり,過去の保存であり,伝統である,と。確かにこの社会において家族制度はいまだ神聖な絆であり,カトリック教会にしても,第三共和政下で教育への支配権を失いはしたが,風俗習慣,日常の行動様式の次元で影響力を保ち続けている。共同社会に貢献した死者をまつる記念碑は,都市においても地方においても風景と一体をなし,フランス人の集団的記憶を維持するのに重要な役割を果たしている。文化の保存装置として図書館と美術館に多大な予算が割かれているだけでなく,都市のたたずまいのうちにも伝統がおのずから感知されるように,建築上の配慮がなされている。あるいはもっと単純に他の人びとは,おしゃべり,議論好き,揶揄の精神,楽天性,社交性,心理分析の趣味,外国への無知,新しいもの嫌い,愛国心,といった言葉で日常生活の中のフランス人の像を描き出し,そこにフランス精神を重ね合わせてみるかもしれない。実際これらの特徴は,フランスの文学,哲学,建築などのうちに多かれ少なかれ検出されうるのである。
このように,フランス精神を定義する多様な視点がありうることを確認した上で,ここでは,現代フランスを理解する上で重要と思われる一つの対立軸を浮かび上がらせることにする。それは,この国の社会と文化を貫く雑種的ないしはコスモポリタン的な性格と,自己中心的ないしはナショナルな性格との対立軸である。
雑種文化とナショナリズム
〈いまだかつてフランス人種なるものは存在したことがない〉と作家モーロアがその《フランス史》の中で書いているように,フランス社会は歴史的に,多様な人種の混合によって形成されてきた。リグリア人,ケルト人,ローマ人,ゲルマン人,ノルマン人などがフランス人なるものをまず構成したのである。フランス文化と呼ばれるものにしても,その基層を形づくっているのはローマ人のもたらしたラテン語と,ローマ人をとおしてもたらされたキリスト教,さらには明晰と調和のギリシア的観念であり,この意味においてフランス文化は出発点からして雑種文化であるといっても過言ではない。
外国人,外国文化に対する姿勢は,その後,時代によって違いがあるが(たとえば17世紀のフランス社会は外部に閉じられた社会であった),今日のフランス文化の形成にとって異文化の同化,吸収の営みは欠くべからざる契機となりつつある。たとえば,絵画のピカソ,シャガールを考えてみよう。彼らはいずれもフランス以外の国に生まれ育ちながら,その才能はフランスの社会で開花し,フランス文化を代表する画家とみなされている。同じことは文学のベケット,ユールスナール,映画のゴダール,ロミー・シュナイダー,哲学のデリダ,クリステバ,シャンソンのムルージ,ムスタキなどについても言うことができる。文化的に重要なポストや役割が外国人にゆだねられることもまれではない。たとえば一時期,オペラ座の支配人の地位がイタリアの演出家ストレーレルにゆだねられたし,第2次大戦後の最も大規模な文化事業と言えるポンピドゥー・センター設計のための国際コンペでは,イギリス人とイタリア人のチームが選ばれた。またルーブル宮殿改築のための国際コンペ(1984)では,アメリカ在住の中国人が選ばれている。
他方,フランス社会は伝統的に,とりわけ1793年の〈亡命者保護法〉の制定以来,政治亡命者に原則として門戸を開いている。かつてイランからの亡命者ホメイニーを受け入れたこの国が,今ではホメイニーの政敵となった元大統領バニー・サドルを保護している。そのほか,元アルジェリア大統領ベン・ベラ,元中央アフリカ大統領ボカサら,第三世界の失権した多くの政治指導者が,フランスに抵抗の拠点ないしは安住の地を求めている。特権的な政治亡命者だけではない。フランスはまた一般の政治難民をも数多く受け入れてきた。1956年のハンガリー事件以来,東欧圏からの難民たちが後を絶たなかったし,73年のチリのアジェンデ政権崩壊以後は同国からの難民,そして近年ではベトナム,カンボジアからの難民といったぐあいに,世界情勢を直接に反映した難民がこの国に押し寄せている。その数は現在約16万人といわれ,これに移民労働者約200万人,さらにその他の定住者を合わせると,この国の外国人人口は400万人を超え,人口の約8%に達している。
外に対して開かれているということは,しかし必ずしも自分を外に開くということを意味しない。外国人を受け入れるフランス人も,決して外国旅行,外国滞在を好む民族ではない。20世紀の旅行文学者モランはこう書いている。〈世界一周はフランス的スポーツではない。ヨーロッパのいくつかの国の人によってすでに13回もの世界周航がなされていた頃,その冒険を敢行したフランス人はただの一人もなかった〉。そして今日でもフランス人は,他のヨーロッパ人に比べて外国に永住することの少ない国民である。また外国の地理にきわめてうとい国民である。他を吸収しはするが,それはあくまでもフランス社会への同化を前提としている。文化についても同様で,外国文化への関心は,対象を対象として理解し,そこに自国文化を異化するきっかけを求めるというよりは,自国文化を豊かにするという統合の発想に立っていることが多い。黒人文学に深い理解を示したサルトルにしてもこう書いている。〈われわれの言葉と神話とを用いて自己を描き出そうと努める一人一人の黒人は,この年老いた身体(フランス語)に流れこむなにがしかの新鮮な血液である〉。
他者を受け入れはするが,他者へと自分を開いていくことの少ないこうした心性は,フランスの自然条件と無関係ではない。ヨーロッパの北と南の中間に位置し,酷暑も厳寒もないフランスは,河川の若干の氾濫を除けば,自然は恩恵をもたらしこそすれ,災害をもたらすことはまれであった。起伏のゆるやかな平野や盆地,それに豊かな森林の広がるこの国は,人間が定住し,持続した生活を営むのに適した土地である。そのような土地に,移動を嫌い蟄居(ちつきよ)を好む〈定住者の知性〉(レオン・ドーデ)が発展したとしてもふしぎではない。しかし同時に,大多数が農民であったこの定住民族に,フランスは世界の中心である,といった観念を抱かせるにいたった歴史的条件にも目を向ける必要がある。長い歴史をとおしてフランスは,他者を吸収し同化するシステムをおのれのうちにつくり上げ,その過程で自己中心的なイデオロギーをはぐくんでいったのである。
その重要なモメントの第1は,ガリアの地のローマ化である。フランスはローマ文明に対し,ラテン語,法と正義の観念,論理と雄弁などを負っているが,なかでもその普遍主義的世界観,すなわち自国の文明が普遍的な文明であり,この文明の恩恵を他民族に浴させる義務があるとする世界観を受け継いだ。
第2に,中世におけるキリスト教信仰の普及とカトリック教会の支配権の確立がある。13世紀パリに創設されたソルボンヌ大学はカトリック神学研究の中心となり,教皇に次ぐ権力を有した。また北フランスの各地に建立されたゴシック式大聖堂はその数学的厳密さと色彩の抒情とによって普遍的な美を具現すると考えられた。フランスの世界的使命への確信はこの時期に誕生したと言うことができる。
第3に,ヨーロッパ全体を軍事的・経済的に制圧したルイ14世による絶対王政の確立と,その下で開花した古典主義文化がある。17世紀フランスはその行政組織の整備によって世界に君主政の範を示し,ベルサイユ宮殿と古典主義文学が表現する節度,調和,均斉は国民的であると同時に,ギリシア・ローマの文明に匹敵する普遍的スタイルの実現として受け取られた。フランス語が外交用語として国際的に認知された(1648)ことも,フランスの中心意識を強化することになった。
第4がフランス革命である。自由,平等,友愛の理念は,アンシャン・レジーム下にあった多数のフランス人の渇望の表現にとどまらず,皮肉なことに革命の混乱の中から出現したナポレオンの軍隊によって全ヨーロッパに広がり,近代市民社会の普遍的原理へと定着していった。そこからフランスのうちに〈文明の指導権〉をみる19世紀の歴史家たち(ギゾー,ミシュレ)の試みが生まれ,フランス的なもの=普遍的なものとするイデオロギーは頂点に達したのである。
けれども,フランス的なもの=普遍的なものとする発想は,非フランス的なものを排除する偏狭なナショナリズムと紙一重である。外国人は受け入れるが,それが同化を前提とするとき,同化することを受け入れない外国人は異分子として社会の周辺に追いやられかねない。そして経済的・社会的危機が高まるたびに,これらの異分子が攻撃の的となり,ときにはリンチやテロの対象となる。これが現在,アラブ,アフリカ人の移民労働者について頻繁に起こっている現象である。それを主導するのは極右勢力であるが,この極右勢力がつけ入ることのできる国民心理が存在することは否定しえない。そこから,文化の次元でのインターナショナリズムと社会生活の次元でのナショナリズムとのずれを指摘することができる。固有の風俗習慣を身につけ,言語と習慣を異にする日常生活の中の他者(黒人,アラブ,アジア人)と,今後永く,どのように共存していくか--これは今日のフランス社会が抱えている最大の問題であるといえよう。
文明の危機意識と五月革命
20世紀フランス文明は,ほかならぬ文明の危機の意識をうちに抱えている。第1次大戦直後バレリーは《精神の危機》と題する講演の中で次のような問いを立てていた。〈ヨーロッパはアジア大陸の小さな岬になってしまうのだろうか,それとも依然として地球の頭脳にとどまり続けるだろうか〉と。バレリーの危機意識は,ギリシアの幾何学に発する科学を富の開発の道具とし,支配の手段にしてしまったヨーロッパの物質文明に向けられている。他方,原子爆弾の投下によって第2次大戦が終結した1945年8月,サルトルが次のように書いたとき,その危機意識は人類の文明の存続自体へと向けられている。〈全人類も,もしもそれが生存し続けていくものとすれば,それは単に生まれてきたからという理由からそうなるのではなしに,その生命を存続せしめる決意を立てるがゆえに,存続しうるということになろう〉(《大戦の終末》)。
68年5月,学生と警官隊との衝突に端を発し,労働者のゼネストに引き継がれていった〈異議申立て〉の運動である五月革命は,1ヵ月以上にわたってフランスの社会生活を麻痺させた。それは最終的にド・ゴール体制を倒す政治革命とはならなかったが,高度成長下での文明のあり方を根本的に問い直す,新たな危機意識の噴出であった。事実,その間に街頭や大学のキャンパスや劇場で昼夜繰り広げられた感性の祭典,言葉の爆発,工場や地域や小集団の中での自治と直接民主主義の実験などは,〈解放〉のイメージを差し出しつつ,政治についての思考様式をはじめとして,文化の諸概念を一新させてしまった。この五月革命は,(1)知識の特権化,制度化への異議申立て,(2)消費社会,商品化社会への反発,(3)文化が人間の生を疎外することへの危機感の表明,(4)人間をロボット化する管理社会の告発,などによって特徴づけられる。裏返して言えば,それは絶対平等,自己決定権,欲望と想像力の解放,自発性,創造性の開花などを,〈いま,ここで〉実現しようとするユートピア的文化革命であった。それは制度的に獲得したものこそ多くはなかったが,これ以後のフランス人の行動様式,感受性,言語表現,人間関係の結び方などに,大きな変化をもたらした。70年代に発展した三大社会運動(エコロジー,フェミニズム,地域主義)はいずれも五月革命を直接に継承する運動であり,いわゆるフランス現代思想なるもの(フーコー,ドゥルーズ,ガタリ,デリダ,グリュックスマン,クリステバ)も,五月革命に出された問いをどう解くかを最大のテーマとしている。
現代フランスの諸課題
1981年5月,ミッテランが大統領に選ばれ,社会党と共産党を軸とする社会主義政権が成立した(1984年7月,共産党は政権から離脱)。この政権は,死刑制度の廃止,破壊活動防止法の廃棄,移民労働者の滞在許可の拡大,自由ラジオの認可,65歳から60歳への定年制の引下げ,約20万人を対象とした富裕税の設置,週労働時間39時間制など,一連の公約をすばやく実現していった。人権擁護と社会主義という点でこの政権のなしたことは大きい。しかし他方において経済危機は強まり,失業者の数は増加の一途をたどっている。この経済的・社会的危機をどう乗り越えるかがミッテラン政権の最大の課題である。ただこれに関連しつつ,他にも解決すべき課題が以下のようにいくつかある。
(1)地方分権の問題 1982年3月,地方分権法が成立し,これによって官選の県知事は共和国委員と名を改め,その権限が狭まり,県議会の議長が行政権を行使できるようになった。また車両の登録税,通行税の管轄権が県や地域圏に移りつつある。しかし国から地方への財源の移譲の規模はいまだ小さく,権限の分散についても中央の行政官僚の抵抗がある。ナポレオン以来の中央集権的国家組織を地方自治へ向けて改革していく試みの成否は今後にかかっている。
(2)社会保障の問題 社会保障の整備は戦後のフランスがなした大事業の一つである。それまで個々に発展してきた保障制度(病気,事故,退職)が1945-46年に統一的に再編成された。日本と比較して目につくのは,第1に財源において雇用主の負担率が高いこと(給与の40%近くを負担)である。第2に医療費の場合,いったん全額を支払った後に75~90%くらいが払い戻されるしくみである。第3に家族手当が多様かつ多額である。たとえば産前手当(未婚,既婚を問わずすべての妊婦に約30万円),出産手当(約9万円)の支給,妊婦の診察料,薬代,入院費用の全額払戻し,2児を扶養する場合には基本賃金の22%,さらに1児増えるごとに33%が加算されること等々。第4に退職後の年金が高額である(退職時の給与の約70%が生存中支給される)。けれども次の点がいま問題になっている。(a)高齢化現象に伴い生産年齢人口が相対的に減少し,社会保障会計の赤字が増大していること。(b)保険料の負担率が高いことから,企業が雇用に対して消極的であること。この2点を解決するためモーロア内閣は,失業保険の給付期間の短縮,連帯税の設置など非常手段に訴えると同時に,企業の分担率を下げる方向へと政策の転換をし始めた。
(3)高等教育改革の問題 1960年代初頭に20万人であった大学生数が84年には100万人に達している。定員を設けて入学試験をし,高度の専門家を養成するグランドゼコールはともかく,バカロレア(大学入学資格試験)を通れば原則として誰でも入学できる総合大学(ユニベルシテ)をいかに合理化して,現代社会の要求に適合させるか,これが1968年以来何回か試みられてきた高等教育改革の中心にある問いである。ミッテラン政権は,一方では平等主義の原理にのっとり,総合大学の門戸を大きく開こうとする。他方では第1サイクル(最初の2年)の中に職業教育コースを多く設置し,第2サイクル(3年,4年)への進学に歯止めをかけようとする。また学科ごとに定員を設けて,進学時に選別制を導入しようとする。サバリ案と呼ばれるこの改革案は,1983年,いっさいの選別に反対する学生たちのストライキを呼び起こした。選別制を導入すれば,平等主義と矛盾するだけでなく,各地の大学間に格差をつくりだし,国家試験制度という大前提が崩壊しかねない。社会主義政権下での大学はいかにあるべきかの議論がいまなお激しく続けられている。
執筆者:海老坂 武
フランス
Anatole France
生没年:1844-1924
フランスの小説家,詩人,評論家。本名ティボーAnatole-François Thibault。セーヌ河畔の古本屋の息子として生まれた彼は,若年から古書を通じて古典の世界に,河畔からのパリ風景を通じて古都の美に眼を開いていた。ルコント・ド・リールの知遇を得て,高踏派詩人として《黄金詩集》(1873)を発表するが,やがて関心は小説の方に向いていく。小説家としての名声が高まったのは,《シルベストル・ボナールの罪》(1881)によってである。つづいて《バルタザール》(1889),《タイス》(1890),《鳥料理レーヌ・ペドーク亭》(1893)などが,懐疑主義と厭世主義を典雅な教養で包んだ独特な味わいによって好評を博した。彼はまた《ル・タン》誌の文芸時評を担当して,ブリュンティエール流の〈独断批評〉に対立する〈印象批評〉を世にひろめた。こうして1896年にアカデミー・フランセーズ会員に選ばれるが,ドレフュス事件に際してはゾラらのドレフュス擁護派にくみした。これを契機として,《ジェローム・コアニャール氏の意見》(1893),《赤い百合》(1894)の作家は,徐々に政治や社会への関心を深め,四部作長編小説《現代史》(1897-1901)を発表し,さらには社会主義へと傾斜していく。しかし,小説《神々は渇くLes Dieux ont soif》(1912)にもみられるように,革命家の狂信もまた彼の排するところであった。1921年のノーベル文学賞を受けた彼は,その微温的な教養主義のゆえに,後にブルトンらの新世代の前衛たちの激しい攻撃の的となった。
執筆者:若林 真
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「フランス」の意味・わかりやすい解説
フランス
→関連項目アルベールビルオリンピック(1992年)|アンドラ|オランジュ|グルノーブルオリンピック(1968年)|サンテミリオン|シャモニー・モンブランオリンピック(1924年)|パリオリンピック(1900年)|パリオリンピック(1924年)|反格差社会運動
フランス
→関連項目ルメートル
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「フランス」の意味・わかりやすい解説
フランス
France
面積 54万3941km2(フランス本国のみ。海外県・海外領は除く)。
人口 6540万4000(2021推計。フランス本国のみ。海外県・海外領は除く)。
首都 パリ。
ヨーロッパ西部にある国。南西部はピレネー山脈を挟んでスペインと接し,東部はアルプスでイタリアと,ジュラ山脈でスイスと,ライン川を隔ててドイツと接し,北東部はフランドル平野およびアルデンヌ高地でベルギー,ルクセンブルクと接する。ピレネー,アルプス,ジュラの諸山脈はアルプス造山運動によるもので,高峻な山系を形成,交通の障害をなす一方,観光・保養地も提供している。これに対し,西端のアルモリカ地塊,中部南寄りのマシフサントラル,東部のボージュ山地などからなる V字形のヘルシニア系山地は中・低山性で,鉄,石炭などの資源に恵まれている。この V字形の北にパリ盆地,東にローヌ=ソーヌ河谷平野,西にアキテーヌ盆地がある。地中海に注ぐローヌ川を除くと,セーヌ川,ロアール川,ガロンヌ川など,イギリス海峡,大西洋に注ぐ諸河川は,一般に流路が長く,流れもゆるやかで,古くから交通上,産業上重要な役割を果たし,それらを結ぶ運河網も発達している。セーヌ流域のパリ盆地では,ケスタ地形が著しく,盆地の外側に向かっていくつかの急崖の列が見られる。気候は大部分が西岸海洋性気候の地域で,比較的温暖で降水も一年を通じている。しかし,地中海岸は温帯冬雨気候(地中海式気候)を示し,コートダジュールは世界的な観光地となっている。前6~前1世紀にケルト人が住みついたが,その後古代ローマ人,さらにゲルマン系のフランク民族が進出した。住民の 80%近くを占める今日のラテン系のフランス人は,これら諸民族の混血によって形成された。住民の大部分がフランス語を話し,およそ 3分の2がキリスト教のカトリックの信者。政治制度はアメリカ型大統領制とイギリス型議院内閣制の折衷型で,元首は大統領。従来の議会優位の伝統がドゴール政権時代から大統領優位の体制に変えられた。議会は下院の国民議会と上院の元老院からなり,政党は多党制が特色である。フランスは,高度に発展した資本主義国のうちでは農業の占める比重が高く,経営面積 5~35haをもつ独立経営の「小農民の国」として知られる。伝統的にコムギとブドウづくりが中心の農業で,コムギは輸出能力があり,ワインは食生活に欠かせないものとなっている。工業は長い間,織物が中心で重工業化は遅れたが,ロレーヌの豊富な鉄鉱資源をいかして発展した。第2次世界大戦後は経済の民主化や産業の国有化の計画が進められ,電力,ガス,銀行,鉄道,航空などの国有化に加え,自動車,航空機,アルミニウム工業の半数ほどが国有化されるなど,国営企業と私企業の「混合経済」によって発展してきたが,1980年代半ばから徐々に民営化が進んだ。ヨーロッパ連合 EU,北大西洋条約機構 NATO加盟国。(→フランス史)
フランス
France, Anatole
[没]1924.10.13. ツール近郊サンシールシュルロアール
フランスの小説家,批評家。本名 Anatole François Thibaut。古書商の子として生れた。皮肉かつ傍観的な懐疑主義者で,自然主義,象徴主義を批判する一方,権力に対しても批判的でドレフュス事件後社会主義に接近した。また,客観的科学的批評に対して印象批評を唱えた。 1896年アカデミー・フランセーズ会員。 1921年ノーベル文学賞受賞。主著,小説『シルベストル・ボナールの罪』 Le Crime de Sylvestre Bonnard (1881) ,『タイス』 Thaïs (90) ,4部作『現代史』 Histoire contemporaine (97~1901) ,『神々は渇く』 Les Dieux ont soif (21) ,評論集『文学生活』 La Vie littéraire (4巻,1888~92) 。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
旺文社世界史事典 三訂版 「フランス」の解説
フランス
France 原名 La République Francaise
国名はフランク(Frank)王国に由来する。前2世紀に先住のケルト人を平定してローマ人が属州(プロヴィンキア)のガリアを経営したが,5世紀にゲルマン人の大移動の結果,フランク王国が形成された。カール1世(大帝)の死後,ヴェルダン条約(843)・メルセン条約(870)によって西フランク王国となった。カペー朝(987〜1328)の時代には封建制度が発展したが,次のヴァロワ朝(1328〜1589)の時代には百年戦争(1338〜1453)に勝って中央集権化が促進され,フランソワ1世の時代にはフランス−ルネサンスの盛時を迎えた。宗教争乱を収拾して成立したブルボン朝(1589〜1830)は絶対主義の基礎を固め,ルイ14世の親政期はその全盛時代であった。しかし,アンシャン−レジーム(旧制度)に対する市民階級の不満が高まり,1789年フランス革命が勃発,立憲王政から共和政(第一共和政)へと移行した。1804年のナポレオン1世の第一帝政をへて,14年にブルボン朝が復活したが,その反動政治は1830年の七月革命によって倒れ,1848年には二月革命で第二共和政が成立した。やがて独裁権を握って第二帝政をしいたナポレオン3世は普仏 (ふふつ) 戦争に敗れて退位し,第三共和政(1870〜1940)が成立した。三国協商を結んでドイツ・オーストリアを破った第一次世界大戦後の政局は左右にゆれたが,第二次世界大戦では国土の大部分をナチス−ドイツに占領され,戦後,第四共和政が成立した。さらに,インドシナ・アルジェリア植民地では民族運動が高まり,政局は不安定となったが,事態を収拾したド=ゴールにより,1958年に第五共和政が成立した。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「フランス」の解説
フランス
ヨーロッパ西部に位置する国。漢字表記は仏蘭西。カペー朝以来王朝支配が続き,ブルボン朝では絶対王政の全盛期を迎えたが,1789年のフランス革命後に第1共和政が成立した。フランスを訪れた最初の日本人は1615年(元和元)の支倉常長一行,最初の来日フランス人は36年(寛永13)に密入国したギヨーム・クールテ神父。1858年(安政5)ナポレオン3世(第2帝政)は全権公使グロを派遣して日仏修好通商条約を締結。64年(元治元)赴任の2代目公使レオン・ロッシュは江戸幕府を支援して横須賀製鉄所や横浜仏語伝習所を建設。67年(慶応3)フランス軍事顧問団が来日。同年パリ万国博覧会に徳川昭武が将軍名代として赴くが,その前後からジャポニスムがフランス芸術に大きな影響を与えた。明治期以降は岩倉遣欧使節団の訪問,自由民権論へのフランス啓蒙思想の影響,法律顧問ボアソナードの法典編纂,日清戦争後の三国干渉などの関係をもった。交流の中心はとくに文学・思想・教育・絵画・演劇など文化面にあり,日本に与えた影響は計り知れない。太平洋戦争直前には日本軍がフランス領インドシナへ進駐。第2次大戦で本国はドイツに占領されたが,戦後ド・ゴールの政府が成立,第4共和政が発足した。1951年サンフランシスコ講和条約に調印。58年から第5共和政。正式国名はフランス共和国。首都パリ。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「フランス」の解説
フランス(アナトール)
Anatole France
1844~1924
フランスの小説家。懐疑主義,合理主義的ヒューマニズムを基調とし社会主義思想にも共鳴した。文体は簡素典雅である。印象批評を唱え,批評家としても活躍。1921年ノーベル文学賞を受けた。小説『タイス』『赤い百合』『神々は渇く』,ほかに『現代史』4巻,評論『エピクロスの国』。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
デジタル大辞泉プラス 「フランス」の解説
フランス
世界大百科事典(旧版)内のフランスの言及
【ナシオン】より
…フランス語で民族・国民・国家を意味し,フランス共和国と関連した形で,国家ないし国民を指す場合に使う。〈ナシオン〉は,〈自由・平等・博愛〉という政治的理念を共有する人々による契約共同体ないしは合意共同体という性格が強く,そこでは人種・民族や血統は二義的な重要性しかもたない。…
※「フランス」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...