デジタル大辞泉
「地」の意味・読み・例文・類語
じ〔ヂ〕【地】
1 地面。大地。つち。ち。「雨降って地固まる」
2 ある土地。その地域。「地の物」「地卵」
3 物事の基礎。下地。「地ができている」
4 化粧しない肌。素肌。「地が白い」
5 布・紙・金属などの、彩色・加工・細工などの土台となる部分。「黒い地に金の縫い取り」
6 織ったままの布地。また、布の材質。「地の厚いコート」
7 生まれつきの性格。また、本性。「つい地を出す」
8 文章の中で、会話文や引用文を除いた叙述の部分。「地の文」
9 実地。実際。
10 囲碁で、石で囲んで自分のものとした部分。
11
㋐日本舞踊で、伴奏の音楽。また、それを演奏する人。地方。
㋑日本音楽で、基礎の楽句。特に、同じ楽句を何回も繰り返して奏するもの。
㋒三味線音楽で、上調子に対する基本の調子。また、それを奏する三味線。
㋓能の地謡のこと。
㋔義太夫節の地合のこと。
[類語](2)地域・土地・地・地方・当地・御当地・当所・現地・地元・区域・地区・地帯・界隈/(7)本性・生地・下地・地金
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
じヂ【地】
- 〘 名詞 〙 ( 「じ」は「地」の呉音 )
- [ 一 ] 万物の存在する基盤としての大地。また、そのものの占める場所。ち。
- ① 大地。地面。つち。ち。
- [初出の実例]「涼はいやゆきが琴を〈略〉ねたうつかうまつるに、雲の上より響き、地の下よりとよみ、風・雲動きて、月・星さわぐ」(出典:宇津保物語(970‐999頃)吹上下)
- ② ある区画内の土地。邸宅や所有地内の土地。また、住んでいるあたりの地域。その土地。ち。
- [初出の実例]「この蔵はこの地のほどにもみえず。御供なる人に『この地の内か、見よ』とのたまふ」(出典:宇津保物語(970‐999頃)蔵開上)
- ③ 自分の影響の及ぶ地。勢力の及ぶ範囲。なわばり。
- [初出の実例]「梅もとのていしゅはあたま七といっていろしさ。おもてやぐらにも地(ヂ)がござりやしたっけ」(出典:洒落本・古契三娼(1787))
- ④ 双六(すごろく)で、盤面を左右に分け、双方各一二の罫(けい)によって区切った、そのおのおののますめ。
- [初出の実例]「二六時中の暮がたふ、白黒とのみ、何わきまゆるかたなふ候。大和本手の事ばかり、おもひきられぬ石づかい〈略〉あたまがはげて、五地(ぐヂ)も六地もみるものなく候」(出典:浮世草子・好色産毛(1695頃)二)
- ⑤ 囲碁で、終局の時点で得点に数えられる空点。生き石で囲み、相手がはいってきても、生きられない地域。日本のルールではセキの中の地は数えない習慣があり、取り石(ハマ)も相手側の地をマイナスすることによって地に換算される。計算の単位は目(もく)。地所。
- [初出の実例]「ただ地を造り、はま巻尽してぞ始て蚊の口のかゆさを覚え、菓子盆に蟻の付たるを驚く」(出典:俳諧・鶉衣(1727‐79)後)
- ⑥ 貝合わせ、歌がるたなどで、床に並べた貝や札をいう。〔雍州府志(1684)〕
- [ 二 ] 本来のもの。本質的なもの。粉飾や加工などをしないもとの形。
- ① 人の皮膚。肌。はだえ。
- [初出の実例]「更に濃い化粧の白ぎく、是れも今更やめられぬやうな肌(ヂ)になりぬ」(出典:われから(1896)〈樋口一葉〉三)
- ② 布帛や紙などで、紋様などを織り出したり染め出したりしていない、本来の生地の部分。
- [初出の実例]「下簾も香のぢに薄物重ねて、小鳥・蝶などを縫ひたり」(出典:宇津保物語(970‐999頃)楼上上)
- ③ 裁断、または加工などをしていない、織ったままの布地。また、布地の材質。
- [初出の実例]「麓には数千の官軍、冑星(かぶとのほし)を耀かし鎧の袖を連ねて、錦繍しける地の如し」(出典:太平記(14C後)七)
- ④ 扇、傘、烏帽子などに用いる、その型に切った厚紙。地紙。
- [初出の実例]「ことさら都より然るべき地を取り下して候ふ、さりながら何番に折り候ふべき」(出典:謡曲・烏帽子折(1480頃))
- ⑤ 虚構ではない現実の世界。実際。実地。
- [初出の実例]「コレ、聴きやれ。そこが狂言と云ものだは。地(ヂ)と狂言との差別(しゃべつ)はそこだはス」(出典:滑稽本・浮世風呂(1809‐13)四)
- ⑥ 連歌、俳諧で、一句に特別な意図や趣向はないが、前句に気軽く応じた、素直で無難な句。
- [初出の実例]「心深く案じぬるを紋といふ也、安々とやりたるを地といふ也」(出典:連歌教訓(1582))
- ⑦ 生まれつきの性質。もちまえ。本性。本心。
- [初出の実例]「面々に証得したる気色どもは甚しけれど、ちに哥のさまを知りて譛め譏りする人はなし」(出典:無名抄(1211頃))
- ⑧ ( その道の商売人に対して ) 素人(しろうと)。特に、素人で売春をおこなうこと。また、そのもの。地者。
- [初出の実例]「中宿で地は御無用といけんする」(出典:雑俳・柳多留‐六(1771))
- [ 三 ] 基本となるもの。他に発展するもととなるもの。他と付随しながら、その基本を構成する部分。
- ① 基礎となるもの。根底。
- [初出の実例]「忠信為二行レ仁之地一。不二亦宜一乎」(出典:童子問(1707)上)
- ② 文章や語り物で、会話や歌を除いた叙述の部分。
- [初出の実例]「すべて此物語に、作者詞、人々の心詞、双紙詞、又、草子の地あり。よく分別すべし」(出典:源氏物語一葉抄(1495頃)一)
- ③ 舞踊で、舞いに伴う楽曲。伴奏の音楽や歌。また、それをする人、楽器など。地方(じかた)。
- [初出の実例]「盆おどり是悲なく乳母も地をうたひ」(出典:雑俳・柳多留拾遺(1801)巻三)
- ④ ( 基礎の楽句の意 ) 日本音楽で、同じ楽句を何回も繰り返して奏するもの。砧地(きぬたじ)、巣籠地(すごもりじ)など。
- [初出の実例]「楽の地は、たらつくたらつくたんたらつく。此地が本地也」(出典:大蔵虎明聞書(1658‐61頃))
- ⑤ 三味線音楽で、基本の高さの三味線をいう。上調子(うわじょうし)に対立することば。
- ⑥ 「じうたい(地謡)」の略。
- [初出の実例]「〈次第〉南無妙法蓮華経、蓮華経のきゃうの字をきゃうせんと人や思ふらん〈ぢをとる間に、かさをぬぐ〉」(出典:虎明本狂言・宗論(室町末‐近世初))
- ⑦ 歌舞伎で、所作事に対し、せりふ劇の部分をいう。写実的な演技。
- [初出の実例]「所作事は狂言の花なり。地は狂言の実なり」(出典:役者論語(1776)あやめぐさ)
- ⑧ 「じがい(地貝)」の略。
- [ 四 ] 楊弓、大弓などで金銭をかける際の二銭のこと。「本朝世事談綺」に、賭金は一銭ずつ紅白の紙に包んで、それを「字」というとあるが「地」と「字」の関係ははっきりしない。また、二分五厘をいう「字」との関係もよくわからない。
- [初出の実例]「かけものは〈略〉さて銭のときは、一銭を餓鬼、二銭を地といひ、三銭を山といひ」(出典:随筆・一時随筆(1683))
ち【地】
- 〘 名詞 〙 ( 「ぢ」とも )
- ① 天に対して、地上。大地。地球。
- [初出の実例]「いやゆきが琴を〈略〉ねたうつかうまつるに、雲の上より響き地の下よりとよみ」(出典:宇津保物語(970‐999頃)吹上下)
- 「天も知るべく地も知る可く」(出典:小学読本(1874)〈榊原・那珂・稲垣〉五)
- [その他の文献]〔易経‐乾卦文言〕
- ② 海に対して、陸地。
- [初出の実例]「これは猶舟津近うてあしかりなんとて、地へわたし奉り」(出典:平家物語(13C前)二)
- ③ 土地の表面。ある区画内の土地。地面。地所。土。
- [初出の実例]「この蔵はこの地のほどにもみえず。御供なる人に、『この地の内か、見よ』とのたまふ」(出典:宇津保物語(970‐999頃)蔵開上)
- 「所を思ひ定めざるがゆゑに、地を占めてつくらず」(出典:方丈記(1212))
- ④ ある限られた地域。地方。ところ。また、そこに住む人。
- [初出の実例]「地遠人稀之処。随レ便量置」(出典:令義解(718)戸)
- 「其地を去らぬことを示した」(出典:吾輩は猫である(1905‐06)〈夏目漱石〉七)
- [その他の文献]〔孟子‐公孫丑下〕
- ⑤ ある者に支配されるところ。領地。また、その者の影響や勢力の及ぶ範囲。なわばり。
- [初出の実例]「この御てらのちは、こと所よりはちのてい、かめのこうのやうにたかければ」(出典:古本説話集(1130頃か)四七)
- ⑥ そのものの置かれた位置。たちば。地位。境遇。
- ⑦ 物の下方。床に接する部分。「天地無用」
- ⑧ 本を立てたとき、床に接する部分。天、小口、背、表紙でない部分。
- ⑨ 物の基本となる部分。基礎。根源。また、したじ。
- [初出の実例]「礼以為レ輔。忠信以為二之地一」(出典:童子問(1707)上)
- ⑩ 大地を主宰する神。地神。
地の補助注記
「ち」は「地」の漢音、「ぢ」は呉音。例文の「地」または「ち」の表記の清濁は必ずしも明らかではないので、一部「じ(地)」の項と重複してあげた。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
普及版 字通
「地」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
Sponserd by 
地 (じ)
日本音楽用語。多くは基礎,土台というような意味をもって,各分野でさまざまに用いられている。まず,芸能奏演における伴奏音楽,あるいは,合奏音楽における特定の声部をいう。たとえば,近世舞踊では,伴奏音楽を地といい,能や狂言では地謡(じうたい)の略称または通称としてこの語を用いる。近世邦楽においては,鳴物や尺八の側から見た,歌声部,三味線などをいうことがあり,三味線の上調子(うわぢようし)に対する本手(ほんて)の声部または調子を地調子(じちようし)という。地歌(じうた)や箏曲では,楽器の原旋律とは異なる,弦楽器によるもうひとつの旋律をいう。これには短い旋律が反復されるものとそうでないものとがあり,また,替手(かえで)とは明確に区別されるものと,替手と同じ性格のものとがある。つぎに,楽器によってなんども繰り返して奏され,それ自身では原則として楽式上の段落をもたらさない旋律型またはリズム型を地といい,能や狂言の囃子に多くの例がみられる。能管では,もっとも使用度の大きい呂中干(りよちゆうかん)の地のほかに楽(がく),神楽(かぐら)の地などがあり,大鼓,小鼓,太鼓のそれぞれに,地の類として分類されるいくつかの手組(てくみ)がある。それらの手組には,コイ合,ツヅケ,キザミ(刻)などのように,名称に地ということばを含まないものも少なくなく,複数の地を混用するために,単純な反復とはならない場合もあるので注意を要する。また,八拍子(やつびようし)の構造における拍節上の単位を,その拍数によって本地(8拍),トリ地(4拍),片地(一地とも,6拍),オクリ地(2拍)などという。そして義太夫節では,もっとも本来的な音楽様式と考えられる地合(じあい)の略称として用いることがある。以上述べたような地と共通する音楽構造は,この語をとくに持たない分野にも認められる場合がある。最後に,一人で複数種目の実技を習得する場合,その者がもっともしっかりと身につけていて,他種目習得の下地となっている音楽を地という。
執筆者:蒲生 郷昭
地 (じ)
万物の存在の基盤としての大地。転じて〈地色〉〈地の文〉のように本来のもの,基本的なものを指す語ともなる。このうち土地についてみると,8~9世紀に〈地〉は見開(げんかい)(現に開かれている土地)・未開を問わず,田,畠,野,山,浜などの地種をふくむ大地そのものを指す語として使われている。そのころから墾田と区別して家屋の建つ場を地といった例も見られるが,10世紀以降に田地,畠地,野地,林地などのような地の性質を示す用例が広く用いられるようになると,京・奈良・大宰府などの都市的な場をそれらと区別して,地と呼ぶようになる。京では〈地一処〉〈四条室町地〉,奈良は〈家地〉,大宰府は〈郭地〉といわれ,鎌倉時代以降も京・奈良は同様で,大宰府は〈宰府地〉と呼ばれた。鎌倉でも,13世紀半ばまでには〈浜地〉〈甘縄地〉〈鎌倉地〉のように都市的な場は地ととらえられ,幕府の支配下におかれた洛中の地は,〈京地〉〈六波羅地〉といった。また豊後の府中や常陸の国府にも地の語が見いだされ,そこに都市的な場があったことを知りうる。地奉行(地方(じかた)奉行),地方管領,地口銭(じぐちせん),地百姓・地上衆(いずれも都市の住人)など,都市に関連する言葉はみなこの地に由来する。これとは別に,地は同じころ,一方では空閑地,河原崎地,荒廃地,無縁地など,無主の土地を指す語とともに用いられ,他方では屋地,敷地,房地など家屋の建つ特定の囲われた場を示す語としても使われ,この場合〈屋幷びに地〉といわれたように屋・房と地とは別であった。前者の用例が地色,地の文などの地に通じ,後者の地が囲碁の地に当たるのであろう。また〈在地〉〈下地〉などの地は,土地の上に生ずる〈作毛〉とそれによる得分とは区別された,土地そのものを指す語であり,土地の売買などの移動に当たって,平安後期には〈在地〉の人の確認を得ることがとくに必要とされた。地主や地子・地利などの語も,この〈地〉に結びついており,京に対する田舎の意の〈地下〉の地も同様である。
執筆者:網野 善彦
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
地
じ
日本音楽および舞踊用語。 (1) 舞踊の伴奏の意で,その演奏者を「地方 (じかた) 」という。上方舞では「舞地」ともいう。 (2) 能で演技をするシテ,ワキなどの役以外の謡の斉唱者。「地謡」ともいう。 (3) 合奏形式における特定のパートの名称。 (a) 長唄で,「上調子」に対して,基本的な原曲の旋律を弾く三味線のパートを「地調子」という。 (b) 山田流箏曲で,おもにタテと呼ばれる主奏者が原曲の旋律を離れた箏の演奏をする場合をいい,単純な音型の繰返しの場合と,複雑な洒落弾きにまで発展した場合とある。 (c) 新内節で,高音 (たかね) と称する二上りで装飾的に奏する上調子に対して,本調子の三味線をいう。 (d) 地歌の手事物で,「地もの」の三弦合奏において,原曲の旋律に対して異なる特定の旋律を弾くほうの三弦をいい,特定の音型の繰返しの場合と,原旋律に対して,拍子をずらして弾くか,特定の音だけを拾っていく場合とがある。 (4) 反復される旋律もしくは音型およびリズム型。 (a) 地歌の「地もの」の「地」のなかで類型的な音型または手法に対して特定の名称のつけられたもの,すなわち「砧地」「巣籠り地」「ヒロイ地」など。箏にも応用される。また,それらの音型およびそのバリアンテ (変形) を含めて,一般に合奏においてオスティナート的に反復通奏される類型旋律をいう。 (b) 能管で,『中の舞』『男舞』『序の舞』『神舞』などの舞の曲において基本的に通奏される楽句群。普通,呂 (りょ) ,中,干 (かん) のなかの4楽句を一くさりの地という。ただし『早舞』などでは2句の反復となり,『楽』などでは,やや長い複雑な楽句群となって,その反復に従ってバリアンテが激しくなる。 (c) 小鼓,大鼓,太鼓などの囃子楽器で,基本的に通奏される楽句のリズム単元,すなわち手組の総称。「三ツ地」 (または「コイ合」) の類と,「ツヅケ」 (太鼓では「キザミ」) の類とに大別。 (5) 楽曲の構成要素となる類型的な旋律形態の様式。浄瑠璃などで,対話部の「詞」や,より旋律的な「節」に対して,朗誦的な語りの部分をいう。ただし,義太夫節では「詞」に対して,それ以外の部分をいう「地合」の略称としてもいう。また,さらに細分類されて,「地中」「地ハル」「地ウ」「地色」あるいは「…地」といった特定の曲節名称もある。 (6) 多種にわたる演奏を行う者が,下地すなわち基本として修得している種目をいう。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
地【じ】
(1)日本音楽用語。基本の意味で,1.基本の高さの三味線を,それと合奏する上調子(うわぢょうし)の三味線に対していう。2.変化する旋律に対し,反復演奏される比較的単純な旋律およびそのパターン,またその奏者(地歌・箏曲や能の囃子(はやし)など)。3.義太夫節で,純然たることばでもなく,単に歌うような節でもない説明的な部分を,地合(じあい)といい,略して地とも。(2)舞踊用語としては,舞踊に使う音楽のこと。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内の地の言及
【義太夫節】より
… しかし,舞台が大がかりになり,人形が写実的になって人間に近づき,[竹田出雲],[並木宗輔]らや,名人たちの相次ぐ逝去,火災や不祥事件などが重なって,衰退のきざしをみせはじめる。竹豊両座の退転と再興から,宮地芝居へ興行の場は移った。そして[近松半二],[菅専助]らがわずかに新作を書くにとどまって,旧作のくりかえし上演が中心となる。…
※「地」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by 
 〈チ〉
〈チ〉 〈ジ〉
〈ジ〉

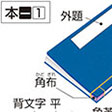








 (墜)に作り、その字は会意。神梯を示す
(墜)に作り、その字は会意。神梯を示す (ふ)の前に、犬牲などをおき、土(社)神を設けて、陟降する神を祀るところ。神の降りたつことを
(ふ)の前に、犬牲などをおき、土(社)神を設けて、陟降する神を祀るところ。神の降りたつことを (隊)という。
(隊)という。 れ、輕
れ、輕 にして昜(やう)(陽)なるものは天と爲り、重濁して
にして昜(やう)(陽)なるものは天と爲り、重濁して (いん)(陰)なるものは地と爲る。
(いん)(陰)なるものは地と爲る。 物の
物の 列(ちんれつ)する
列(ちんれつ)する なり」(段注本)とあって、地と
なり」(段注本)とあって、地と 詁〕にあげる「底なり。大なり。
詁〕にあげる「底なり。大なり。 なり。諦なり。施なり。易なり。土なり」などの訓も、音の関係を以て訓するものであるが、本義は神の降り立つところをいう。〔説文〕に籀文(ちゆうぶん)として
なり。諦なり。施なり。易なり。土なり」などの訓も、音の関係を以て訓するものであるが、本義は神の降り立つところをいう。〔説文〕に籀文(ちゆうぶん)として をあげるが、
をあげるが、 (たん)声で声が異なり、土部の〔説文新附〕にあげる墜(つい)が、地の初文であろう。金文に
(たん)声で声が異なり、土部の〔説文新附〕にあげる墜(つい)が、地の初文であろう。金文に に作る。地には異体の字が多く、
に作る。地には異体の字が多く、 字鏡〕に上古文二字、古文三字を録し、〔竜
字鏡〕に上古文二字、古文三字を録し、〔竜 手鏡〕にも
手鏡〕にも diaiは声近く、
diaiは声近く、 るるなり」とあり、後ろに遠く引く貌。
るるなり」とあり、後ろに遠く引く貌。 ・馳・
・馳・ diaiは同声。髢dyekはかもじ、施sjiaiは旗のなびく形。みななびくような、起伏や
diaiは同声。髢dyekはかもじ、施sjiaiは旗のなびく形。みななびくような、起伏や






 地・斫地・除地・勝地・壌地・心地・侵地・親地・陣地・寸地・井地・生地・聖地・整地・尺地・斥地・赤地・席地・接地・戦地・潜地・素地・掃地・堕地・宅地・沢地・拓地・
地・斫地・除地・勝地・壌地・心地・侵地・親地・陣地・寸地・井地・生地・聖地・整地・尺地・斥地・赤地・席地・接地・戦地・潜地・素地・掃地・堕地・宅地・沢地・拓地・ 地・天地・転地・田地・土地・当地・投地・動地・入地・任地・配地・
地・天地・転地・田地・土地・当地・投地・動地・入地・任地・配地・ 地・蛮地・
地・蛮地・ 地・美地・分地・平地・僻地・別地・辺地・墓地・封地・没地・本地・満地・門地・余地・輿地・要地・落地・楽地・立地・略地・両地・量地・領地・緑地・霊地・裂地・路地・露地
地・美地・分地・平地・僻地・別地・辺地・墓地・封地・没地・本地・満地・門地・余地・輿地・要地・落地・楽地・立地・略地・両地・量地・領地・緑地・霊地・裂地・路地・露地