天や天空を崇拝の対象とする民族は少なくないが,そのような信仰形式をもっとも古くから発達させたのは内陸アジアの遊牧民族であった。おそらくその日常生活が天体の観察と切っても切れない関係にあったからと思われる。こうして古代アジアの諸族において天そのものを神とみる観念が生じたが,やがてそこから天をもって世界に秩序を与える力の根源とする見方があらわれた。すなわち古代中国の〈天命〉や古代インドの〈リタ(天則)〉の観念がそれである。またこうした天の観念が人格化される場合は天上の父神=天父神とされ,しばしば大地を人格化した母神=地母神と比較対照される。この天上の父神という性格は,一般に遊牧民族に固有の家父長的・父権的な社会構成にもとづくとされ,ユダヤ教,キリスト教,イスラム教などにみられる天上の唯一神の信仰形式をも方向づけることになった。
仏教では兜率(とそつ)浄土のように天上に極楽を想定する世界観が発達したが,しかし同時に,たとえば六欲天のように天界の領域をさまざまに区分して,そこに迷いの世界を設定しているのであって,天はかならずしもそれ自体として崇拝の対象とされたのではなかった。日本の神話においては,海上のかなたに想像された常世(とこよ)の国の考え方と並んで,天上に高天原(たかまがはら)(高天原神話)をおく観念が成立し,そこには数多くの天津神(あまつかみ)が存在すると考えられた。高天原の構想は地上の政治的・社会的現実の天上への反映とみることができるが,同時に天照大神(あまてらすおおかみ)においてみられるように太陽崇拝の痕跡も否定することができない。
→太陽 →天国
執筆者:山折 哲雄
中国の天
中国では天は至上神,自然,理法,宇宙などを意味する。天空を神格化し,それを崇拝するのは,内陸の遊牧民族に共通した信仰形態であった。たとえば,匈奴(きようど)が天を祭ったことは《史記》や《漢書》にみえているし,北魏をおこした拓跋(たくばつ)部にも同様の記録がある(《魏書》)。モンゴル族の至上神テングリtengriは同時に天空を意味し,今日においてもアルタイ系民族,アジア極北民族,フィン・ウゴル語族系諸族の多くは,天空と至上神とを同じ言葉であらわしている。ユダヤ教,キリスト教,イスラム教などにおける上天の唯一神,中国における天の信仰ないし思想も,もとは同根だとし,そこに農耕的=母権的な地母神信仰に対する,遊牧的=父権的文化の特性を見いだそうとする試みもなされている(石田英一郎)。しかしながら,約3000年の長きにわたって天との親密な関係をもち続け,政治,宗教,文化,生活など,人間の生存のほぼ全域にわたって天の規制を受けたのは漢民族だけであろう。
中国における天=至上神の信仰は遠く周代にさかのぼる。それよりさき,殷代の卜辞(甲骨文)のなかに天とおぼしい文字は散見するが,至上神や天空の意味で使われているわけではなく,王国維によれば卜辞の天は頭の大きな人間の象形だという(《観堂集林》釈天)。この宗教国家で崇拝されていた至上神は〈帝〉であった。やがて,もと遊牧民だったともいわれる周が殷を滅ぼすと(殷周革命),周は天をもって帝に代える。この帝から天への転換についてはまだわからぬことが多く,両者をまったく別個の神とみるか,そこにある種の連続性を認めるか,見解が分かれている。おそらく天は周人固有の神であったと思われるが,地上のすべてのものを覆うその広大さと周人の政治的才能のゆえに,殷を滅ぼすころには,帝をはじめ群小の神々の神格をそのなかに包摂し,吸収しえていたであろう。いずれにせよ周以降,天は意志をもった宇宙の主宰者,造物主として人々の頭上に君臨する。しかし,庶民にとって天はGodというよりむしろ運命と同義であり,彼らの祈るべき対象は民間信仰やのちの道教の神々であった。天の子として天の意志を代行し,天下に君臨する王者にとっては,天は自己の権威と支配の根拠であり,かつまた王朝の命運の支配者と考えられていたから,天に強い関心を抱かざるをえないのは当然である。そのもっとも端的なあらわれが天の祭り(郊祀(こうし))にほかならない。郊祀は皇帝の重要な義務として,また彼にのみ許された特権として,歴代とり行われた。北京に偉容をとどめる天壇は,明・清の皇帝が天を祭ったところである。その際,天は昊天(こうてん)上帝と呼ばれたけれども,何らかの偶像をもっていたわけではない。
しかしながら,時代が進み人知がひらけてくるにつれ,天の人格性,超越性はしだいに希薄になってゆく。春秋戦国時代の知識人たちは天をどのように考えていたか。孔子における天は依然として偉大なGodであり,ときには祈りや期待にそむく運命的な超越者として立ちあらわれることもあったが,しかし彼はそれによって無神論に走ったりせず,そういう場合にはわが身にふりかえって人間の側の問題として受けとめようとしており,敬虔な祈りの心を失ってはいない。しかし孟子になると祈りは失われ,その代りに天は性善説の根拠として理念化され,また自然としての天もあらわれている。荀子(じゆんし)は,人間の天からの自立を主張して天・人を切りはなし,さらに天から神秘性をはぎとって自然物とみなし,〈天命を制してこれを用う〉(《荀子》天論)とまで言いきった。老子においては,天は窮極者の地位を〈道〉にゆずっている。荘子において特徴的なことは,天は人為(さかしら)に対する自然(あるがままのあり方)として理法化され,その天=自然に従って生きることが求められる。この時代にはまた,天道(自然の摂理)ということばもよく使われた。こうした思想家たちのいた一方で,古代的な人格神としての天の復権をくわだてた墨子の存在も忘れられてはならない。
上述したように,春秋戦国期には天に関する多様な見解が提出され,それらはすでに漢以後の天の思想史を先取りしている。漢代のイデオローグ董仲舒(とうちゆうじよ)は,荀子の分離した天・人をふたたび結びつけ,天人相関説(政治のよしあしに対して天が感応して禍福をくだすとする説)をとなえ,墨家的な天を復活させた。歴代の儒教は,郊祀儀礼を整備して皇帝権力につかえる一方,この天人相関説を取り入れて権力の無制限な行使に制肘を加えた。儒教において天はまた,人間の道徳性の根源とされ,宋代の新儒教(朱子学)では人間に本来的に備わっている善性を〈天理〉と呼んだ。宋代の儒者はその内なる天との合一を熱っぽく説いている。荀子の無神論は後漢の王充によって推し進められ,唐代の柳宗元や劉禹錫(りゆううしやく)に継承された。そうした動きの一方で,民衆レベルでは天の世俗化が進んでおり,唐代ころから〈天公〉〈老天爺〉といった親しげなニックネームで呼ばれるようになった。
執筆者:三浦 国雄
諸民族の神話にみる天空像
ギリシア神話で〈天空〉をあらわす男神ウラノスは大地女神のガイアの長子だが,ガイアと母子婚し,現在世界を支配している大半の神たちの祖父となった。しかし息子の一人クロノスによって,ガイアと交合しようとしたところを去勢され,大地から引き離されると同時に,天界の王の地位もクロノスに取って代わられた。ニュージーランドのマオリ族の神話でも,天空ランギは,大地パパの夫で,多くの神がこの父母から生まれたが,父母がつねに抱擁し合ったままだったために,子どもたちは暗闇の中で父の巨体に圧迫され,身動きもできずにいた。そこで彼らは相談して,世界が明るくなり自分たちが成長できるために,父母を分離させることに決めた。他の神たちの失敗のあとで,森の神のタネが父母を結び付けていた筋を断ち切り,渾身の力で空をはるか高くへ押し上げ,泣いて抗議するランギとパパを引き離した。現在でもこの分離を嘆いて,毎夜パパの溜息が霧となってランギの方へ立ち昇り,ランギの涙が露となってパパの上に降り敷く。このように天空と大地を,最古の夫婦となった男女の神とみなして,その分離により人間の生活のための空間が発生したことを物語った〈天地分離神話〉は,世界の各地に共通して見いだされる。この夫婦関係は多くの場合,天地が分離させられた後も天空神の精液にほかならぬ雨によって大地が受胎して万物を生み出すという形で,現在もなお続いていると考えられている。ただ古代エジプトの神話では,夫婦関係が逆転して,天ヌートの方が女神で,夫の大地ゲブから,大気の神シューにより押し上げられて,引き離されたことになっていた。この場合にも,ヌートは毎夜ゲブの種により受胎した太陽を,夜明けに新生させることで,いつまでもゲブの妻であり続けるとされていた。
日本神話の高天原のように,天空を神がみの住処とみなす観念も,各地の神話に共通してみられる。これと結びついて,日本のイザナキとイザナミの神話や天孫降臨神話にもみられるように,もとは天上の神界に住んでいた王家あるいは人類の始祖が,下界に降って地上の人間界を発生させたという話も,各地の神話に見いだされる。北アメリカのイロコイ族の神話によれば,人類の先祖はアタエンシクという名の女で,もとは天上に住み,首長の娘だった。ところがあるとき,父の命令によって1本の木が根こぎにされたあとに開いた穴から,そのことを怒った1人の男によって,当時まだ一面の水だった下界へ突き落とされた。すると水面にいた水鳥たちが,身を寄せ合い台を作って彼女を受けとめ,それから水中に潜り底から土を取ってくると,大亀の甲羅の上にそれを広げて,陸地を造り,その上に彼女を住ませた。北アメリカの原住民のあいだにはまた,天の端は地平線のところで,たえず上下動しており,そのすきまをうまくくぐり抜ければ,生きながら天上界に至ることができるという観念もみられる。
執筆者:吉田 敦彦


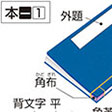







 ・忝の二字を収めるが、天の声義と関するところはない。
・忝の二字を収めるが、天の声義と関するところはない。 ・巓tyen、頂tyengと声近く、みな頂巓のところをいう。また定dyeng、題dyeも声近く、額の部分をいう。〔易、
・巓tyen、頂tyengと声近く、みな頂巓のところをいう。また定dyeng、題dyeも声近く、額の部分をいう。〔易、 〕の〔釈文〕に引く〔馬融注〕に、「其の額を
〕の〔釈文〕に引く〔馬融注〕に、「其の額を 鑿(げいさく)するを天と曰ふ」とみえる。
鑿(げいさく)するを天と曰ふ」とみえる。






