目次 海の地球科学 海の分類 海陸の分布 海の深さ 海の誕生 海洋の地殻と大陸の地殻 海水 海底堆積物 海水の運動 海の役割 生物と海 海の生態学 海の生物地理 海の生物の分散と生活史 海の文化誌 神話,伝承 民俗 地球上の陸地以外の凹所に水をたたえ,全体がひとつづきになっているところが海(海洋)である。それを満たす水が海水で,その塩分の組成率は,世界中ほぼ一定している。海岸近くの入江や,浦,潟(かた)を海とするか湖沼と呼ぶかは,多分に従来の習慣によっている。
海の地球科学 海の分類 海を分類するには,その位置や大きさ,形状,海水の特性などにより,大洋と付属海に分け,付属海はさらに地中海(大・小地中海),縁海に分ける。大洋とは太平洋,大西洋,インド洋の三つであって,その他の海は,いずれもこれらのどれかに付属させる。大洋は形も大きく,またおのおの独立した海流系をもつ。とくに注意すべきは南極海(南氷洋)で,地理的にみれば,太平洋,大西洋,インド洋の各一部にすぎないが,南極大陸をとりまく海として,このように名づけられている。海流も南極大陸をめぐって流れる東向きの周南極海流がある。
なお太平洋,大西洋をそれぞれ南北に分け,それにインド洋,南極海,北極海を加えて俗に〈七つの海〉(全地球上の海の意)と呼ぶことがある。
付属海は,その付属する大洋の海流の影響をうけ,独自の海流はもっていない。付属海中で最大のものは北極海だが,それでも大洋中最小のインド洋にくらべ,面積はわずか1/5にすぎない。大地中海とは,二つ以上の大陸にかこまれた海を指し,小地中海は大陸の中に深く湾入していて,その出入口が内部の面積にくらべて狭いものをいう。縁海とは,島や半島で不完全に大洋の本体から区切られた海をいう。大洋中最小のインド洋と,付属海中最大の北極海とでは,面積では5対1の大差があるほか,平均深度も4000m対1000mとひらきが大きい。これからしても,大洋と付属海との間には,著しい差のあることがわかる。また,三大洋で,全海洋の面積の89%を占めている。
海陸の分布 海の総面積は361.059×106 km2 で,地球の総面積509.951×106 km2 の70.8%を占めている。北半球は陸地39.3%,海60.7%(154.695×106 km2 )で,南半球は陸地19.1%,海80.9%(206.364×106 km2 )であり,北半球より南半球に海が多い。またフランスのロアール河口のナント付近とニュージーランドの南東のアンティポディーズ諸島付近をそれぞれ極とする半球をつくると,前者において陸地,後者において海洋の割合が最大となり,それぞれを陸半球,水半球(海半球とも)と呼ぶ。陸地と海洋の割合は前者で49.0%:51.0%,後者で9.4%:90.6%となり,前者の陸半球には全陸地の約84%が含まれる。
海の深さ 世界の海洋の深度は,平均約4000mであるが,世界で最も深い記録は,太平洋のマリアナ海溝にあり,1万0920mにも達する。一般に海面から約200mの深さまでは陸地の延長とみられ,大陸棚 と呼ばれる。ここから約4000mまでの深さの海底の占める面積は小さく,その傾斜は急で,これを大陸斜面という。しかし,約4000mから約6000mまでの海底の占める面積はきわめて広大で,全地球の面積の半分を占めており,これが深海底の部分である。さらに約6000mよりも深いところはごく狭く,全海洋の1.2%しかない。この部分は海溝 の中にある。海底地形
海の誕生 地球は,45.5億年ほど前,宇宙空間の星間ガスとちりが凝縮してできた。地球内部からでてきたガスによって大気がつくられ,それに含まれていた水蒸気が冷却して凹地に水がたまり,海がつくられた。堆積作用のあったことを示す38億年前の岩石が発見されていることから,38億年以前に海が存在したことは明らかである。海水の量がどのように増加してきたかについては,地球の誕生後約5億年でほとんどが形成されたとする説と徐々に増加してきたとする説があるが,前者の説を支持する人が多い。
海洋の地殻と大陸の地殻 地球のいちばん外側の殻,地殻は,大陸では軽い花コウ岩質層とその下の玄武岩質層からなり,厚さ20~70km,平均33kmであり,大洋底では玄武岩質層からなり厚さ7kmと薄く,両者はまったく異なる構造をもつ。前述のごとく大陸からは堆積作用のあったことを示す38億年前の岩石が見つかっているのに,海洋底の岩石は最も古いもので2億年前のものである。これはプレートテクトニクスによれば,中央海嶺で新しい海洋底地殻がつくられ,年間数cm~十数cmの速さで移動してゆき,海溝で再び地球内部にもぐりこむことで説明される。このことは海底の堆積物の厚さが海嶺付近で薄く,海溝に近づくにつれ厚くなること,あるいは海底の縞状磁気異常などから確かめられる。また,後者からは2億年前以降の海洋地殻の運動状態が復元でき,大陸上の古地磁気などのデータと合わせ,大陸が分裂・移動したこと,これに伴って新しい海が誕生したことが確かめられている。たとえば,大西洋は2億年前にできた大陸の裂け目が拡大してつくられたと考えられている。この考え方を過去に延長し,大陸は分裂・移動・集合を繰り返し,海の分布もこれに伴って変化してきたとする説もある(ウィルソンサイクル )。大陸移動説 →プレートテクトニクス
海水 地球上に約1.4×101 8 tの海水がある。海水は約96.5%の純水と3.5%の溶解物質とからなり,数十種の元素が含まれているが,そのうちおもな成分は,ごく沿岸域を除く外洋では,ほぼ一定の組成比をもっている。したがって,たとえば塩素の濃度(Cl)がわかれば塩分全部の濃度(S )を知ることができ,S =0.030+1.8050Clというクヌーセンの公式が成り立つ。これは地球上に海水が生成されて以来,長期間にわたって,循環,対流,拡散などによりよく混合されてきた結果である。海水
海底堆積物 海底を形成している物質を底質といい,基盤岩とその上の堆積物とからなる。海底堆積物とは海水によって運搬されて海底に沈着した物質で,これには陸上の風化物が河川によって海に運び込まれたものもあれば,風によって海上に飛ばされ,後に海に沈着したものもある。また陸上生物,あるいは海中生物の遺殻,遺体なども含まれる。
200mより浅い陸棚の海底には,陸地から運びこまれた,わりに粒の粗い陸性堆積物がある。深さ200m以深の大陸斜面では陸から運ばれてきた泥や砂は少なくて,おもにプランクトンの遺骸からなる遠洋性の堆積物と,粒の細かい陸源の泥を含む亜洋性堆積物がある。もっと深い大洋底は非常に細かい生物の遺体からできたどろどろの軟泥からなる。海底堆積物
海水の運動 海水の運動は種々雑多であるが大別してほぼ定常的なものと,だいたい一定の周期をもって繰り返すものがある。前者に属するものは海流 で,後者に属するものには潮汐 による潮浪,潮流,湾の振動(セイシュ)および津波 ,風浪 ,うねり ,内部波などがあり,日常生活に短期間周期の影響を与える。
海流によって気温,水温,塩分などの分布が支配され,またそれに従って気候,風土,生物などの分布が定まり,文明までがその影響を受けたと考えられる。
海の役割 太陽系の惑星で現在海のあるのは地球だけである。たとえば,金星では表面が高温なため水が液体として存在し得ず,火星では液体の水はなく,両極に氷があるのみである。このように地球に液体の水,すなわち海があるのは太陽からの距離と水を地球につなぎとめておくための地球の大きさが適切であったからである。
金星は大きさも密度も,地球とほぼ同じであるが,気圧は90気圧と著しく高い。また金星大気の96%を二酸化炭素が占め,いわゆる温室効果により金星表面は非常に高温となっている。もともと地球も金星と同じような大気組成をもっていたと考えられている。地球大気中に二酸化炭素がほとんど存在しない(したがって気圧も1気圧と低い)のは,海があり海水が二酸化炭素を吸収し,石灰岩やその他の炭酸塩として固定し,地殻のなかにとじこめたためである。
海水にはさまざまな化学成分が含まれており,環境の激変をやわらげることから,生物の発生,生存に好都合であったと考えられる。
日本や北アメリカ東部海岸の夏季における高温多湿は,居住するのに不快な気候として有名であるが,これに反して,北ヨーロッパや北アメリカ西部海岸は,冬季に暖かく,夏に涼しい。それはこれらの地方が,大洋の東岸にあるか,西岸にあるかで決まり,海や海流が,その地方の気候風土を支配するためである。人間生活は,古代から現代にいたるまで,海の支配する気候条件と,その風土との影響を受けることには変りがない。
古代においては,海は交通路として,陸地よりもはるかに重要であった。日本人の祖先は,大陸伝いに渡来した北方系と,黒潮にのった南方系との混合といわれる。ヨーロッパの文化も海を利用してメソポタミア平原から,地中海沿岸各地をへて遠く北ヨーロッパ,イギリスまで伝えられた。その先駆的役割を果たしたのは古代フェニキア人であるが,彼らはさらに遠くサルガッソー海までも航海していたと考えられている。しかし,彼らは商船の運航ルートを秘密にしていたので,海図や文書が現存せず,ごく一部がギリシアに口伝えされたにすぎない。前5世紀のヘロドトスの著作には,早くも大西洋の名が姿を現し,ヨーロッパ,アジアの大陸もみられる。こういった交易によって,各地の産物,文明の交流が盛んになったが,海はその物資のルートに一役を買ったばかりでなく,精神文化,各人種間の交流ルートとしても,重要な役割を担うことになったのであった。
食料の源として,古来,日本人はとくに海からタンパク質を多く求めてきた。海の面積が陸地の2倍もあり,数千mの深海まで生物が生息しているので,最近はこの深い層の魚まで漁獲の対象になっているが,それは世界の大陸棚で自由に魚がとれた時代が去って,経済水域200カイリの時代が到来しつつあることにもよる。しかし,このままではいずれ魚資源の枯渇は免れないであろう。水産資源の育成が重要な課題となりつつある。
水産資源のほかに注目されるのは,海底の鉱物資源である。海にはないものはないといっても過言ではないが,ただそれが商業ベースとして引き合うかどうかである。現在,いちばん利用されているのは食塩であるが,岩塩も石油もみなかつて海で生成されたものである。海底探査の進歩により,数千mの海底に,直径数cmのボール状のマンガン団塊 が数多く分布していることがわかり,採集に関心が集まっているが,問題はこれら海底資源が決して無限ではないことである。
近年,新しく問題になってきたのは,海洋汚染 である。とくに石油(重油)による汚染は生物を殺し,そこの生態系までも破壊しかねない。そうなると回復に数年,数十年の年月を要し,ときには回復不能の事態さえ生ずる恐れがある。また原子力の開発による海の放射能汚染も重要になってきた。こうなると,海洋汚染の人類への影響は,ただたんに食料供給の面だけでなく,海に入る太陽熱,海水の蒸発など気候への影響といった面でも無視できなくなってくるであろう。海は人類共通の財産と考えねばならないところにきている。海気相互作用 →海洋開発 →地球 南日 俊夫
生物と海 20億年以上前に,生命が誕生したのは,浅い海であったといわれるように,海は太古の昔から無数の生物をはぐくんできた。現在でも海は非常に多くの生物種が生活している場所である。海産のおもな動物群は,古生代の初め(カンブリア紀)にそのほとんどが出現しており,魚類は少しおくれて,オルドビス紀に原始的な甲冑魚として出現する。陸の生物が海から移りすむのは,その後のシルル紀である。海の生物の中には,顕花植物のアマモや,哺乳類のクジラ,アザラシ類などのように,陸上で進化したグループが,再び海に生活の場を求めて適応進化したものもいる。
海の生態学 海の生物の生活型 は,大きくプランクトンplankton(浮遊生物),ベントスbenthos(底生生物),ネクトンnekton(遊泳生物)の三つに区別される。プランクトンは,海水中に浮遊して生活し,自らの能力で移動しないものを指し,ネクトンは,強い遊泳能力をもって水中で生活するもので魚類や,イカ・タコの類,エビ類,それに水生哺乳類などが含まれる。ベントスは,海底表面や底土の中などにすむ生物群を指す。もちろん,この二つ以上の範疇に入るものや,中間的なものも多い。
海洋の生物は,例えば海水中では,サメ,クジラなどの大型の動物が,小型の魚類(イワシ,サンマ,イカなど)を食べ,小型魚類などは,橈脚類copepodaなどの動物プランクトンを食べ,動物プランクトンは植物プランクトンや,生物の死骸が分解する途中にできる生物残査(デトリタスdetritus)を食べるというように,高次消費者-二次消費者-一次消費者-生産者という食物連鎖関係で結び合った生物群集 を構成している。海の基礎生産は,植物プランクトンと,海藻および顕花植物の海草の光合成によっている。光合成には太陽光線が必要であるので,これらの植物の分布は海の浅い部分に限られている。植物プランクトンは,光が海面照度の1%になる深さまで(有光層)分布しており,海藻や海草は,一般には2~30mの深さを超えない。海の植物プランクトンによる生産量は,1ha当りほぼ1~4.5tくらいであるが,もちろん海域によって変化する。基礎生産は,海水中の無機栄養塩を利用して行われるが,特にリン酸塩と硝酸塩の量によって生産量が左右される場合が多い。栄養塩の豊富な沿岸海域では,黒潮などの貧栄養海域と比べて,数倍も生産量が高く,海底の栄養塩が有光層に常に持ち上げられている湧昇流海域では,さらに高い生産量がある。海藻や海草による生産量は,1ha当り25~85tにもなり,浅い沿岸域や小湾では,基礎生産の3分の2以上がこれら海藻(海草)による場合も知られているが,一般の海域では,基礎生産の大部分は,植物プランクトンの光合成に負っている。サンゴ礁では,サンゴ虫の肉質部に共生するゾーキサンテラzooxanthella(褐虫藻類)や,死んだサンゴ表面に付着した微小藻類による生産量が著しく大きく,海の中でも異常に高い例として知られている。
植物(生産者)によって生産された有機物は,植物食である一次消費者に食べられる。プランクトンでは,動物プランクトンの多くの種(例えば,橈脚類のカラヌス目など),ベントスでは,アミ,エビ類,ヨコエビ類やコツブムシ類などの小型甲殻類,巻貝類などが植物食性である。しかし,植物体の多くの部分は摂食されずに,バクテリアなどの微小生物によって分解される。分解の過程で,植物の遺骸や細片がデトリタスとして,多くの低次消費者たちに利用される。生きた植物を食べることによって成立する食物連鎖と,このデトリタスを基礎とするデトリタス食物連鎖とが相まって,海の生物群集の特徴的な構造をつくっている。
メビウスK.Möbiusが,海底にある一塊りのカキに多くの動植物がすみついているのを見て,〈生物共同体=生物群集〉の概念を初めて提唱したように,海の生物は,よく見える形で互いに緊密な関係をもっているものが多い。カキ礁,サンゴ礁 ,藻場 などはその比較的大規模な例であるし,クマノミとサンゴイソギンチャクやハゼとテッポウエビの相利共生,他の生物の体をすみかとする種の豊富なこと,オトヒメエビやホンソメワケベラの掃除行動など,興味深い種間関係がみられる。これらの種間関係も,海の生物群集構造の主要な一面を形づくっている。
海(海底と水中)の環境は,深さに沿って浅い方から,潮間帯,亜潮間帯と上部表層,陸棚と下部表層,陸棚斜面と漸深層,深海底と深海層,海溝に区分される。光の影響があるのは陸棚までであり,それ以深は暗黒の世界である。生物は,それぞれの区分に対応して,違った生物群集を構成している。海底にすむベントスは深くなるにつれて,大型化した種が目だつようになるが,魚類では,むしろ小型で奇妙な形をしたものが多い。また,発光器をもつ生物も多くなる。深海の水温は一年を通じて1~4℃とごく低温で,生物の代謝・成長も著しくおそい。そのため,寿命も長く,小型の二枚貝でも,100年を超えると考えられている。有光層よりも深い海の生物群集は,生産者をもたないので,主として上層の有光層から供給される有機物のくず(デトリタス)や動物の死骸を食べて栄養を取っているものと,それらを食う肉食性の動物,およびバクテリアから構成されている。そのため,浅い海と比べて,生物量や個体数は著しく少ないが,各種あたりの個体数が少ないので,種の多様性は大きいといわれている。その説明には,〈時間-安定説〉が採用されている(後述)。最近,太平洋のガラパゴス海嶺など数ヵ所のマグマの湧き出し口付近で,硫黄バクテリアの化学合成を基礎生産として,深海としては異常に豊富な生物量をもつ生物群集が発見されている。
海の生物地理 地理的な海の生物群集の分布は,大きい海流の勢力と,温度変化によって区画されている。寒帯や亜寒帯の海では,表層の海水が冷やされて下へ沈み,代りに深層の富栄養の海水が表層に上昇するという循環を繰り返しているため,栄養塩が豊富である。しかし,水温があまり低いと生物の増殖が抑えられるため,寒流が南下して暖められたり,寒流と暖流の潮境などには,生物量が非常に多いところが出現する。
寒帯・亜寒帯の海は,熱帯・亜熱帯の海に比べて,種類数が少ないこと,ほんのわずかの種類がおびただしい数で出現することなどの特徴が見られる。その原因については,暖かい海の高い生産性が,多くの種を養ってゆくことができるとする〈生産力説〉や,捕食者の多い熱帯・亜熱帯海域は競争種の共存を許すことができるとする〈捕食者説〉,環境が安定で種分化に必要な十分な時間があったところで種多様度が高いとする〈時間-安定説〉など,他にもいくつか考え方が提出されているが,いずれもすべての場合を説明しうるものではない。
沿岸の海は,栄養塩の豊富な陸水の流入があるために,常に豊富な生物量を維持している。また沿岸は,陸と海の相互作用によって,さまざまな形態の場所をつくり上げている。例えば,潮だまり のような小規模なものから,干潟 ,藻場,塩水沼沢地,汽水域 ,塩水湖,潟湖,入江,サンゴ礁,マングローブ沼沢地,内湾,内海などがあげられる。これらの環境は,その物理的性質によって,それぞれ特有の生物群集を擁している。これらの生物相の特徴をもとに,海洋に関しても陸上と同じく,海洋生物地理区を設定することができる。
海の生物の分散と生活史 海底にすんでいる動物も,分布域の拡大と個体群間の遺伝子の交流のために,生活史の初期,プランクトン生活をする幼生の時代を経る。底生生物の生活史の中で,この浮遊幼生期は,最も死亡率が高く,環境の影響を受けやすく,捕食者も多い。浮遊生活には,プランクトンを食べて成長するプランクトン栄養の幼生と,孵化(ふか)しても餌を取らず,変態し定着するまで卵黄からの栄養だけによって生活する卵黄栄養の幼生があり,後者は一般に大型卵である。卵黄栄養の幼生の浮遊期間は,プランクトン栄養の幼生より短く,この期間の死亡率を下げるために有利な形態である。そのほかに,卵胎生もしくは直達発生によって,浮遊幼生生活をもたない種類もある。この生活史型は系統分類上のグループと関係なく,ほとんどの海産動物分類群中にいくらかずつあり,一般に小型のものが多い。これら幼生の生活型は,分散の拡大と死亡率の低下という互いに相反する要求をうまく折り合わせて,進化してきたと考えられている。向井 宏
海の文化誌 神話,伝承 日本の神話では,太古にイザナキとイザナミの夫婦神によって,最初の陸地オノコロ島が造られる以前には,下界はただ一面の海原で,その上を陸の原質が,水に浮く油かクラゲのような状態で漂っていたとされている。原古には,下界が一面の海だったと見なす発想は,多くの神話に共通して見られる。旧約聖書に見られる古代イスラエル人の神話でも,神が天地を創造する以前には世界は一面の海原だったとされ,そのありさまが《創世記》の冒頭に,〈地は形なく,むなしく,やみが淵のおもてにあり,神の霊が水のおもてをおおっていた〉と記されている。インドの神話によれば,世界のはじめには,茫漠たる大洋の上で宇宙の維持者である大神ビシュヌが,一頭の巨大な蛇を寝台にして長い冥想の眠りに耽っている。時が熟するとこの神の臍から蓮が生え出て花を開き,その中に創造神ブラフマーが誕生することによって,世界の創造が開始される。古代エジプトの神話では原初には大洋ヌンだけが存在したが,そのただ中に太陽神ラーが,まずピラミッドの形をした丘の形で出現した。それから彼は,自身にほかならぬその丘の上で自瀆して男神シューと女神テフヌートを生み出し,この両神から大地ゲブと天空ヌートが生まれたという。ユーラシアから北アメリカにまたがる広大な地域には,神が水鳥などに命じて原初の大洋の底から土を取ってこさせ,それから陸地を造ったという神話が見いだされる。ポリネシアには,太古に神が魚を釣るようにして海底から陸地を釣り上げ,それによって一面の海原だった世界に,島が出現したという神話がある。
ギリシア神話によれば,海ポントスは大地女神ガイアの息子だが,母と交わって多くの子孫を得た。その中の長子が,〈海の老人〉とあだ名される非常な知恵者で年寄りの海神ネレウス で,あらゆるものに自在に変身する能力をもち,ネレイデスNērēidesと呼ばれる50人(または100人)の美神たちの父親である。海の支配者は最高神ゼウスの兄弟のポセイドン で,武器としても漁具としても使われる三つ股の矛を持ち,地震や津波の神としても恐れられた。彼の妃はネレイデスの一人であるアンフィトリテAmphitritēで,この夫婦の息子で下半身が魚の形をしたひょうきんな海神トリトンも,ネレウスやその同類のプロテウスやグラウコスなどと同様に,非常な知恵と変身の能力の持主である。日本神話の塩土老翁 (しおつちのおじ)も,変身の能力をもつ知恵者の海神であるという点で,これらの同類と認めることができる。
北欧神話の海の主エーギルÆgirは,大洋そのものを表すと思われる大釜の持主で,それで大量のビールを造り,神がみのために豪華な宴会を催す。彼の妻ラーンRánはきわめて貪婪(どんらん)な女巨人で,海難に遭った人間を網で捕らえては海底の館へ連れてきて,黄金を厳しく要求する。この夫婦の娘は,9人姉妹の波の女精たちである。海神 →創世神話 吉田 敦彦 関 敬吾
民俗 海に囲まれて生きてきた日本人ではあるが,今日,現実には,海に背を向けた生活がむしろ支配的になっている。しかし,海とかかわりをもった生活に根ざす伝統が,脈々と息づいている事がらも多い。人間の出産と死亡の時刻が潮の満干と密接に関係しているといわれることや,チャンス到来を〈潮時〉といい,〈待てば海路の日和あり〉という言葉などは,帆船時代からの海の生活に由来するものであろう。〈海千山千〉というのも,海に千年,山に千年住んだ蛇は竜になるという伝承にもとづき,世の中の裏も表もわきまえた老獪(ろうかい)な人物を婉曲に指すのである。〈海のものとも,山のものともつかない〉など,海と山とが二項対立的,ないしは相互に融和したかたちで表現されることが多い。
海上から山を目標にして船の所在を知ることを〈ヤマアテ〉といい,〈タケ(岳)をミル〉ともいう。〈山に求めた海の道〉といわれるのは,近代的操船以前の伝統的技術であり,海上で生活する人々にとって,実利と信仰のなかから生まれた端的な表現である。諸国に霊山が多いなかで,海上を航行する人たちが,ことさら崇敬の念を寄せてきた山々は,太平洋岸でも日本海側でも,切れ目なく連なっている。海の神と山の神の婚姻譚は,このような海と山との密接なかかわりを,如実に反映したものであろう。海から寄り上がったものを神体とする神社は多く,それが安置されている場所はたいてい山頂であるが,その地方としては,海をもっとも眺めやすいところに好んで祀るという神社も数多い。
《延喜式》に記載される祭りの供物をみると,海産物の方が農作物より多く,全体の6割以上を占め,多い順に塩,カツオ,ワカメ,アワビをあげることができる。アワビは神饌として重視され,志摩半島の海人たちは例年朝廷に奉献することを義務づけられていた。海水や海藻,浜の砂,塩などを潔斎の意味で信仰行事に用いる習俗は,海辺地域はもちろん,内陸の村々にもみられ,これを〈お潮井(しおい)〉といい,海に対する伝統的な心意を伝えるものである。ノシアワビは神饌として重視されてきたほか,現在でも贈物のシンボルとしてノシ(熨斗)が使われる。
塩は人間が生きてゆくのに欠かせない。日本には岩塩がほとんどないので,塩は海の水から得てきた。海辺でできる海塩が,人の背や牛馬・川船などで山奥へも運ばれ,〈塩の道〉がきりひらかれ,張りめぐらされた。
海のかなたに神の国・仏界があり,そこから年ごとに神々が人間のもとに訪れ,祝福を与えるという信仰もある。その仙界を奄美・沖縄諸島方面では,ニライカナイとかニルヤ,リュウグウという。ニライカナイは,人間生活万般につながる聖地と観念され,人間の生命もそこから生まれ,死後に行く浄土でもあり,五穀の種子や火もそこからもたらされたと信じられている。海亀はニライカナイの神の使いとされ,ときには海難から救ってくれると信じられてきた。このことは浦島太郎譚の亀と竜宮を想起させる。ニライカナイは,太陽の昇る水平線のかなたの聖地ともいうが,海と天とが日本語ではつながっているとも考えられている。原始・古代人の思考にみる根の国,底つ国,常世(とこよ)も,この海のかなたの聖地のことであったろう。北見 俊夫
 〈カイ〉
〈カイ〉 〈うみ〉「海辺・海山/青海・荒海・内海・大海・外海」
〈うみ〉「海辺・海山/青海・荒海・内海・大海・外海」 文芸雑誌。昭和44年(1969)中央公論社から創刊、昭和59年(1984)終刊。海外作品を多く紹介したほか、村上春樹の評論や唐十郎の戯曲など、さまざまなジャンルの作品を掲載。
文芸雑誌。昭和44年(1969)中央公論社から創刊、昭和59年(1984)終刊。海外作品を多く紹介したほか、村上春樹の評論や唐十郎の戯曲など、さまざまなジャンルの作品を掲載。 近藤啓太郎の長編小説。昭和42年(1967)刊。のち、昭和52年(1977)に第3部を加筆した完成版が刊行された。鴨川の漁師たちの姿を描く。
近藤啓太郎の長編小説。昭和42年(1967)刊。のち、昭和52年(1977)に第3部を加筆した完成版が刊行された。鴨川の漁師たちの姿を描く。 愛媛県出身の歌人、
愛媛県出身の歌人、 《原題、〈フランス〉La mer》ドビュッシーの管弦楽曲。1903年から1905年にかけて作曲。「三つの交響的スケッチ」という副題をもつ。印象主義音楽を代表する作品の一つとして知られる。
《原題、〈フランス〉La mer》ドビュッシーの管弦楽曲。1903年から1905年にかけて作曲。「三つの交響的スケッチ」という副題をもつ。印象主義音楽を代表する作品の一つとして知られる。



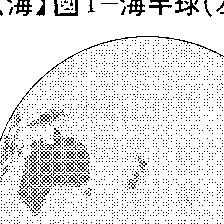
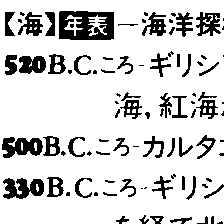
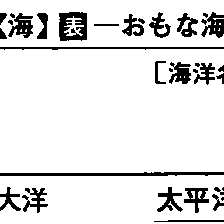



 (毎)(まい)。
(毎)(まい)。 ・
・ (悔)(かい)の声がある。〔説文〕十一上に「天池なり。以て百川を
(悔)(かい)の声がある。〔説文〕十一上に「天池なり。以て百川を るる
るる なり」とあり、天池とは大海をいう。
なり」とあり、天池とは大海をいう。 は同声。声符の
は同声。声符の












 海・沿海・烟海・河海・外海・学海・寰海・環海・観海・巨海・近海・苦海・硯海・湖海・公海・江海・航海・黄海・山海・四海・酒海・樹海・周海・曙海・深海・人海・塵海・制海・青海・絶海・浅海・宗海・掃海・滄海・蒼海・大海・
海・沿海・烟海・河海・外海・学海・寰海・環海・観海・巨海・近海・苦海・硯海・湖海・公海・江海・航海・黄海・山海・四海・酒海・樹海・周海・曙海・深海・人海・塵海・制海・青海・絶海・浅海・宗海・掃海・滄海・蒼海・大海・ 海・智海・潮海・渡海・東海・踏海・韜海・騰海・
海・智海・潮海・渡海・東海・踏海・韜海・騰海・ 海・内海・南海・入海・汎海・氷海・表海・浜海・
海・内海・南海・入海・汎海・氷海・表海・浜海・