デジタル大辞泉
「玉」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
たま【玉・珠・球】
- [ 1 ] ( 「たま(魂)」と同語源 )
- ① 球形あるいはそれに近い形の美しくて小さい石などで、装飾品となるものを総称していう。古くは、呪術的な要素を伴うものもあり、鉱物に限らず、動植物製のものをも広く含めていう。
- [初出の実例]「善き人の 正目(まさめ)に見けむ 御足跡(みあと)すらを 我はえ見ずて 石(いは)に彫(ゑ)りつく 多麻(タマ)に彫りつく」(出典:仏足石歌(753頃))
- [その他の文献]〔名語記(1275)〕
- ② 特に真珠をさしていう。まだま。しらたま。
- [初出の実例]「琴頭(ことがみ)に 来居る影媛
 摩(タマ)ならば 吾が欲る
摩(タマ)ならば 吾が欲る 摩(タマ)の 鰒白珠(あはびしらたま)」(出典:日本書紀(720)武烈即位前・歌謡)
摩(タマ)の 鰒白珠(あはびしらたま)」(出典:日本書紀(720)武烈即位前・歌謡)
- ③ その形が①に似ているものをいう。
- (イ) 水の玉の意で、露、水滴、水泡、または涙などをさしていう。
- [初出の実例]「浪のうつせみればたまぞみだれけるひろはば袖にはかなからむや〈在原滋春〉」(出典:古今和歌集(905‐914)物名・四二四)
- 「扨も扨も嬉しやと 袖に玉(タマ)をながしぬ」(出典:浮世草子・本朝二十不孝(1686)四)
- (ロ) ( 「弾・弾丸」とも書く ) ( 初期のものは丸くなっていたところから ) 弾丸。
- [初出の実例]「是は杉谷善住坊といひし鉄炮の上手、〈略〉二つ玉(タマ)をもって纔十間ばかりにてうちはづし申事も」(出典:信長記(1622)三)
- (ハ) そろばんの五珠と一珠。
- [初出の実例]「上の玉を五玉といふは」(出典:咄本・無事志有意(1798)十露盤)
- (ニ) 電球。
- [初出の実例]「おくみは二階の十六燭の電球(タマ)をはづして来て」(出典:桑の実(1913)〈鈴木三重吉〉一五)
- (ホ) レンズ。特にめがねのレンズ、カメラのレンズをいう。
- [初出の実例]「月かけをうつすめがねの玉うさぎひたゐの波にかけてこそみれ」(出典:狂歌・万載狂歌集(1783)五)
- (ヘ) 遊戯やスポーツに用いる球形のもの。ボール。または、その動き。
- [初出の実例]「私は棒を以て、球を打つを見たり」(出典:小学読本(1873)〈田中義廉〉一)
- (ト) 玉突きに用いる球。転じて、玉突きのゲームをもいう。撞球(どうきゅう)。ビリヤード。
- [初出の実例]「下で球(タマ)でも突いて居たのか知らん」(出典:野分(1907)〈夏目漱石〉二)
- (チ) 男子の生殖器。「きんたま」の略。
- [初出の実例]「へのこはれやぶれ黄水いづ、玉もかたくはれ痛み」(出典:全九集(1566頃)五)
- (リ) 一般に、玉状にまとめたものを一括していう。「うどんの玉」「毛糸の玉」など。
- [初出の実例]「煙艸を二玉(たま)に、草鞋の良(よい)のを取て参れ」(出典:怪談牡丹燈籠(1884)〈三遊亭円朝〉一五)
- (ヌ) 紋所の名。①の形にかたどったもの。玉、三つ割り玉、火焔の玉、曲玉など。
三つ割り玉@玉
- ④ ①のように美しいもの、貴重なものの意。→たまの。
- (イ) 美しい女性。また、女性の美貌。
- [初出の実例]「素人の娘でも女(タマ)さへよければ高賃を出してやとい」(出典:談義本・当世穴噺(1771)三)
- (ロ) 転じて、遊女、芸者などのこと。
- [初出の実例]「さる方から高尾を身請、言て来ても肝心の玉が知れぬで方々へ尋歩此才助」(出典:浄瑠璃・伽羅先代萩(1785)一)
- (ハ) すぐれた人、気のきいた者。
- [初出の実例]「その外に川魚屋もまだまあ多(やっ)とあれどナ。玉(タマ)といふたら的等(てきら)じゃ」(出典:滑稽本・浮世風呂(1809‐13)二)
- (ニ) 大事な人や物。話題や事件の焦点となっている人物や物。そのもの。そいつ。
- [初出の実例]「三身仏性たまはあれど、生死(さうじ)の塵にぞ汚れたる」(出典:梁塵秘抄(1179頃)二)
- ⑤ ( ④から転じて ) 一般に人や物をそれとさしていう。
- (イ) そういう人物、その程度の人物の意で用いる。軽くあざけっていう場合が多い。
- [初出の実例]「ときどきぬるい茶を汲んでこられる輩(タマ)だらう」(出典:西洋道中膝栗毛(1870‐76)〈仮名垣魯文〉六)
- (ロ) 策略などの手段に用いるもの。人、物、金銭などについていう。また、単に現物、あるいは資金としての現金などをさしていう。→玉が上がる・玉に掛ける・玉に使う。
- [初出の実例]「鉄山どのを玉にして、この縁先にてどれあふ様子」(出典:歌舞伎・彩入御伽草(1808)皿屋敷の場)
- ⑥ 蒟蒻(こんにゃく)をいう女房詞。〔随筆・貞丈雑記(1784頃)〕
- ⑦ ( 「親玉」の略 ) 親玉。第一のもの。第一人者。〔浪花聞書(1819頃)〕
- ⑧ 「たまご(卵)」の略。「掻(か)きたま」
- ⑨ 魚をすくい捕る小形の網、攩網(たも)のこと。すくいだま。たもあみ。
- [初出の実例]「汐ならぬ海士のいとなみもをかしけれ。大網、巻網、四手(よつで)、跡掛、手丸(タマ)、唐網」(出典:俳諧・本朝文選(1706)二・賦類・湖水賦〈李由〉)
- ⑩ 綱(つな)をいう。〔談義本・虚実馬鹿語(1771)〕
- ⑪ 拳(けん)の名で、「八」のこと。
- [初出の実例]「『いっかう』『ちゑ』『さんな』『玉で』『おはね』『コリャ叶はぬ、サアサア一盃』」(出典:歌舞伎・色競かしくの紅翅(1808)四)
- ⑫ ( 「玉門(ぎょくもん)」の略とも、「船玉(ふなだま)」の略ともいう ) 女性の陰部のこと。
- [初出の実例]「緋の袴召ぬと玉がすき徹り」(出典:雑俳・柳多留‐九七(1828))
- ⑬ 「玉落ち」での、まるめた紙片のこと。江戸時代、蔵宿で知行米を下げ渡す際、受取人の姓名を書いた紙片をまるめて箱に入れ、それを振ってこぼれた紙玉の名前の人から順に渡した。転じて、知行米をいう。
- [初出の実例]「『おめへいつかぢう着てきた八丈を、わっちが此むくととっけへてくんなんしな。〈略〉』『とうにまげてあらア』『フウそれでも玉とやらがおちなんしたら、だされなんすだらうね』」(出典:洒落本・傾城買四十八手(1790)やすひ手)
- ⑭ 下女の通称。下女の一般的な名「お玉」から江戸時代、京都地方を中心に用いられた語。
- [初出の実例]「あんのじゃう・旦那の御作玉が腹」(出典:雑俳・軽口頓作(1709))
- [ 2 ] 〘 造語要素 〙
- ① 名詞の上に付けて接頭語的に用いる。美しいもの、すぐれているものをほめていう。
- (イ) 特に上代、神事や高貴な物事についてのほめことばとして用いる。「玉の」の形で用いることも多い。「玉垣」「玉葛(たまかずら)」「玉串(たまぐし)」「玉襷(たまだすき)」「玉坏(たまつき)」「玉裳(たまも)」など。
- (ロ) [ 一 ]①のようにきれいなもの、あるいはそれをちりばめたものの意を添える。「玉枝(たまえ)」「玉衣(たまぎぬ)」「玉櫛笥(たまくしげ)」「玉簾(たますだれ)」「玉手(たまで)」「玉箒(たまははき)」「玉鉾(たまぼこ)」など。「玉の」の形で用いることも多い。
- ② 名詞と熟合して球形のものである意を添える。「玉石」「玉砂利」「玉ねぎ」「十円玉」など。
- ③ 評価を表わすことばと熟合して、そういう人物である意を添える。「悪玉」「上玉」「表六玉」など。
玉の補助注記
( 1 )文字は、[ 一 ]①の意味では漢字欄にあげたものの他に「珪・瑤・瓊・璧」などが当てられる。②以下の用法では「玉」が共通して用いられ、また、「玉」の字音「ぎょく」が並行して用いられるものもある。
( 2 )[ 二 ]①(イ)の用法は、主として上代に限られ、広くは字音「ぎょく」が用いられる。
ぎょく【玉】
- 〘 名詞 〙
- ① 宝石の一種。硬玉(こうぎょく)と軟玉(なんぎょく)との総称。たま。
- [初出の実例]「父は玉(ギョク)だの高麗焼だのの講釈をした」(出典:行人(1912‐13)〈夏目漱石〉塵労)
- [その他の文献]〔列子‐湯問〕
- ② 接頭語的に用いて、美麗なもの、貴重なもの、また、高貴なものの意をもって他の人に関する事物の美称に用いる。「玉音」「玉札」「玉手」「玉楼」 〔日葡辞書(1603‐04)〕
- ③ 球状のもの。たま。
- ④ 芸者、娼妓をいう。たま。
- [初出の実例]「おれも長屋で相応に口もきく玉(ギョク)をあづかって土地ところの世話もしてゐれば」(出典:洒落本・仕懸文庫(1791)三)
- ⑤ 「ぎょくだい(玉代)」の略。
- [初出の実例]「玉(ギョク)を落したり腮(あご)をひかれたりして見ねへ、勘定迄に商内を仕詰にゃアいかねへわな」(出典:洒落本・部屋三味線(1789‐1801頃))
- ⑥ ( 「玉」の字画が五画であるところから ) 江戸時代、上方遊里で、遊興の時間をはかる線香五本の符号。
- [初出の実例]「線香五本を以て玉の一字に換る」(出典:洒落本・虚実柳巷方言(1794)中)
- ⑦ ( 「玉子」の「玉」を音読して ) 飲食店などで、鶏卵、または鶏卵料理をいう。
- [初出の実例]「タマゴ(これをまたギョクなんて云やがる)、アナゴ、納豆巻、なんて注文してるから」(出典:にんげん動物園(1981)〈中島梓〉五四)
- ⑧ =ぎょくしょう(玉将)
- [初出の実例]「将棊の馬に玉を王と云は何の故ぞ、両王いまさん事を忌て、必ず一方を玉と書く、是手跡の家の口伝と云々」(出典:壒嚢鈔(1445‐46)二)
- ⑨ 取引相場でいう。
- (イ) 取引所で、売買の約定をした商品や証券。または、その数量。株式取引での株、米穀取引での米などの類。〔模範新語通語大辞典(1919)〕
- (ロ) 取引員が客から受けた売買の注文数。〔取引所用語字彙(1917)〕
- (ハ) 取引所に納める売買証拠金。
ごく【玉】
- 〘 名詞 〙 ( 「ごく」は「玉」の呉音 ) たま。ぎょく。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
普及版 字通
「玉」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
Sponserd by 
玉 (たま)
美しい光沢のある特殊な材料をさす場合にも,その材料で作った装身具などの製品をさす場合にも用いる。珠とも書く。材料としての〈たま〉には,硬玉,軟玉などの玉(ぎよく)のほかに,水晶,ザクロ石,メノウ,碧玉,トルコ石,コハク,埋木(うもれぎ)などの各種の鉱物から,真珠,サンゴなどの動物性のものも含まれる。ただし,何を〈たま〉のうちにいれるかは,時代や地域によってちがいがあり,科学的な成分のほかに,希少性にもとづく価値と,習慣による需要とが,その選定の大きな要因になっている。
装身具として用いる玉は,そのままでも〈たま〉といえる材料で作ることが多いが,金,銀やガラスなどの人工の材料,木の実や骨,角,牙,貝などの加工しやすい天然の材料で作ることも少なくない。これらの玉には,緒を通してつなぐために,貫通した孔があり,それぞれの形と孔の位置とによって,種々の名称がついている。日本でふつうに用いる玉の名称をあげると,勾玉(まがたま),管玉(くだたま),丸玉,棗玉(なつめだま),平玉(ひらだま),算盤玉(そろばんだま),切子玉(きりこだま)などがおもなものである。勾玉は湾曲した体のふくらんだ一端に偏して孔をあけたもの,管玉は細長い管状のもの,丸玉は球状のもの,棗玉は丸玉をやや長くした形のもの,平玉は扁球形で平らな面に平行に孔をあけたもの,算盤玉は二つの截頭円錐体を底面で接合した形のもの,切子玉は二つの截頭角錐体を底面で接合した形のものである。このほかに,小型の丸玉または算盤玉を小玉(こだま)と総称することが多い。江戸期の学者は,低い円壔(えんとう)形の滑石製の玉に臼玉(うすだま)の名をつけたが,滑石製小玉と呼べばよい。奈良時代に刺玉(さすだま)と呼んだものは,緒に刺し通す意味で,形からいえば丸玉あるいは小玉の類である。さらに特殊な形の玉として,蜜柑玉(みかんだま),山梔玉(くちなしだま)などの形の類似によるもの,捩玉(ねじだま)のように加工の方法によるもの,トンボ(蜻蛉)玉のように色彩の変化によるものなどの,変わった名称の玉もある。蜜柑玉は丸玉の表面に縦にくぼんだ溝をつけたもの,山梔玉は棗玉の表面に縦に溝をつけたものである。捩玉はガラスの丸玉の表面を鉄製の工具ではさんで捩ったもので,決まった基本形はない。トンボ玉はふつうは丸玉を基本形とする。なお金,銀を材料とした玉には,重量を軽減するために,分離した二つの半球形を組み合わせて中空に作ったものがあって,これらを空玉(うつろだま)と総称している。
以上の各種の玉には,みなその中心を貫通する孔があけてあるが,なかには特殊な用途に応じて,変わったあけ方をした孔をもつ玉がある。たとえば,丸玉に2方向から孔をあけて,それが十字形またはT字形に交差するものを,とくに辻玉(つじだま)と呼ぶことがある。これは数珠(じゆず)などの,緒の交点に用いる玉である。また孔が貫通せずに終わっているものに,緒の先端をさしこんで用いる場合,これを露玉(つゆだま)ということもある。玉を装身具として用いるにあたって,管玉や丸玉のような同種の玉を数多く緒につなぐ場合と,それに勾玉などの異種の玉をまじえる場合とがある。したがって,玉を数える場合にも,何顆,何珠と個数をいう場合と,何条,何連と緒に通した数をいう場合とがある。《古事記》に〈八尺勾璁(やさかのまがたま)〉というのは,緒に通した長さをいうものであり,〈五百津之美須麻流之珠(いおつのみすまるのたま)〉というのは,数の多さを五百個と形容したものであるが,もちろん勾玉ばかりをつないだものではない。なお玉は,他の装身具の装飾にも用いることがあった。小玉を衣服にとじつけることは,しばしば行われたはずである。古墳出土の金銅冠や金銅履(くつ)に,ガラス小玉を一つ一つ銅線でとじつけたものがあり,韓国では金冠に硬玉,ガラスの勾玉を垂下した例が多い。東大寺法華堂本尊(不空羂索観音)の宝冠に,勾玉,管玉,切子玉,小玉など2万数千個の珠玉を銀線に貫いて飾りつけているのは,玉の用法から逸脱したとはいえないが,正倉院の金銅幡(ばん)にとりつけた勾玉になると,そのために第2の孔をあけるなどして,まったくの転用であることを示している。
執筆者:小林 行雄
玉 (ぎょく)
yù
中国で色,光沢の美しい石を玉という。古くからおもに今の新疆ウイグル自治区崑崙山麓のホータンに産し,玉門関を通って中原にもたらされた。この美しい石に,太古の中国人は神秘な力を見いだし珍重してきた。初め神や霊魂をよらしめるもの,邪悪を払う呪力を持つもの,あるいは生成力,再生力の霊力を持つものと信じられ,呪術の具として使われた。おそらく玉に対するこの呪物観念は,石を神聖視し崇拝した原始の信仰と同源であろう。殷・周時代になって,儀礼の発展と制度化によって,玉はさまざまな形態と用途の礼器として大量に加工された。腰帯にさげた佩玉(はいぎよく)は本来は悪気からの護身のためであった。《詩経》衛風・木瓜に〈我に投ずるに木瓜を以てす,これに報ずるに瓊琚(けいきよ)(玉の名)を以てす〉とある,求愛の際の佩玉の贈答は霊魂の授受という呪術に発したものと考えられる。
古く玉を食べる習慣もあり,《周礼(しゆらい)》王府職に,王が斎(ものいみ)の儀式にあたって玉を食べる記事が見えるし,《楚辞》にも玉を食餌とする辞句が散見する。のちに神仙家の間では,玉を粒や粉にして水薬,丸薬,粘薬とした〈玉漿(ぎよくしよう)〉〈玉屑(ぎよくせつ)〉〈玉膏(ぎよくこう)〉などの仙薬が服用されたらしい。この食玉の風習も玉の呪力を体内にとりこみ止めるという呪術に由来し,その後に長寿延命を保つ法として受け継がれたと見られる。また,死者の口に含ませる〈含玉〉や手に握らせる〈握〉など副葬の玉器〈葬玉〉,玉片を金糸銀糸で綴って死者に着せた〈金縷(きんる)玉衣〉〈銀縷玉衣〉なども,もとはやはり玉に生成力,再生力をみとめ死者の復活を願ったのが起源であろう。葬玉の風習は六朝以降廃れるが,南中国の一部の地方では近年まで死者の口に翡翠(ひすい)(硬玉)をはませていた。
玉に対する呪物観念は周代すでにシンボリックな意味に転化しはじめており,玉は人徳,権威,位階,友愛などの象徴となった。とりわけ玉には種々の〈徳〉がそなわっていると信じられ,仁,義,智,勇,潔の五徳(《説文》玉字説解)のほか,九徳(《管子》水地篇)とか,十徳(《礼記》聘義)があるとされた。《礼記》玉藻に〈君子は玉に於て徳を比す〉とあるように,身に佩(お)びる玉は君子の徳の表象と考えられた。玉の持つ徳にあやかる意味もあったであろう。名前に玉の字をはじめ玉偏の文字が好んでつけられたり,玉のきず〈玷(てん)〉〈瑕(か)〉が人品の欠点,過失にたとえられるのもこうした信仰を背景にしている。中国伝統の〈徳〉の概念は起源的には呪力の概念化されたものだという説もある。後世玉に対する信仰心はしだいに薄れ,玉器は鑑賞用の工芸品として尊ばれるに至った。神話,説話の世界では,玉は不老不死の秘薬を持つとされる女神〈西王母〉と深い関係があり,この女神は玉山に住むとか,帝舜のときに来朝して玉を献上した話がある。また蛇神,竜神は口内,頭などに玉の呪宝を持つという俗信もある。
→玉器(ぎょっき)
執筆者:鈴木 健之
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
玉(ぎょく)
ぎょく
ジェードjadeともいい、普通は硬玉(ひすい)と軟玉(ネフライト)の2種類をさす。しかし、それらに類似した外観をもつ別種の鉱物からなる飾り石も含まれることがある。地名を冠したものはほとんどこの例で、カリフォルニアジェード(ベスブ石)、メキシコジェード(方解石)、トランスバールジェード(緑色の灰礬(かいばん)ざくろ石)などがある。軟玉は、透閃(とうせん)石あるいは緑閃石の非常に微細な結晶が集まってできている。世界中に産地が多く、価格も低いため、大形の美術工芸品などによく利用される。それに反して硬玉は、ひすい輝石jadeiteの微細な結晶が集まってできており、硬度も軟玉より高く、世界的に産出量が限られている。とくに緑色の美しいものは著しく価格が高く、宝石として扱われる。このようなものは現在ではほとんどみられず、ミャンマー(ビルマ)でのみ産する。白色のひすいに着色を施したものも宝石として市場に出ている。
[松原 聰]
玉(たま)
たま
美しく小さい球形をした宝石、石などの総称。古くはかならずしも鉱物性のものに限らず、広く、真珠や貝や竹の管、そのほか一部の植物の実などの動植物をも称した。用途には、装飾品のほか、宗教的、呪術(じゅじゅつ)的な要素をもつ場合があった。小さく美しいという意とともに、神聖、貴重、大切、慈しむという観念があり、接頭語として名詞につき、「玉垣(たまがき)」「玉串(たまぐし)」「玉裳(たまも)」「玉衣(たまぎぬ)」「玉櫛笥(たまくしげ)」「玉鉾(たまほこ)」など用例はかなり多い。
[藁科勝之]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
玉
たま
身体装飾に用いる垂飾(すいしょく)のうち孔をあけたものをいう。形態から勾玉(まがたま)・管玉(くだたま)・切子玉(きりこだま)・棗玉(なつめだま)・臼玉・丸玉・蜜柑玉(みかんだま)・山梔玉(くちなしだま)・算盤玉(そろばんだま)・平玉・小玉とよばれ,ガラスの地に別の色のガラスをはめこんだ蜻蛉玉(とんぼだま)を含め,総称して玉類という。材質は硬玉・碧玉(へきぎょく)・メノウ・水晶・蛇紋(じゃもん)岩・琥珀(こはく)・ガラスなどがあり,古墳後期に現れる中空に作った空玉(うつろだま)は金・銀・金銅製である。日本最古の玉は,北海道の旧石器後期の遺跡から出土した石製小玉である。縄文時代には硬玉製大珠(たいしゅ)が流行し,弥生時代には管玉が盛行するとともに,ガラス製の玉も作られ始めた。さまざまな種類・材質がそろうのは古墳時代で,古墳の副葬品としてしばしば出土。その後は飛鳥寺の塔心礎から出土した勾玉・丸玉・空玉・蜻蛉玉のように,寺院の鎮壇具や舎利荘厳具(しゃりしょうごんぐ)としても一部で使用された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
Sponserd by 
玉【ぎょく】
軟玉と硬玉の2種類に分けられる。中国で古くから装飾品として愛玩(あいがん)された玉は軟玉で,ホータン産の玉は特に珍重された。品格ある美しさのゆえに種々の伝説を生んだ。硬玉にはヒスイがある。→玉器(ぎょっき)
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
玉
高級な工芸品の原石として珍重された岩石で,玉には軟玉(nephrite)と硬玉(jade)がある.一般にjadeは硬玉をいう.硬玉は翡翠(ひすい)輝石(jadeite)と石英の集合体で,エメラルド色の良質な部分は宝石として扱われ,翡翠(ひすい)と呼ばれる.主に翡翠輝石の繊維状結晶の細かい網目で構成されているため,硬く緻密な岩石である.スペイン語でpietra di hijadaは腎臓結石の意味.
出典 朝倉書店岩石学辞典について 情報
Sponserd by 
玉
たま
岡山県南部,玉野市の中心市街地の一部。旧日比町の一部であったが,1919年,南に造船所が造られて以来急速に発展し,北に接する宇野とともに中心市街地を形成した。現在では西方の奥玉および玉原地区まで住宅地域が拡大し,玉原地区には造船所の関連企業の工場団地が造成されている。
玉
ぎょく
jade
東洋で宝石とされた石で,おもに白玉,翡翠 (ひすい) をさすが,厳密には硬玉と軟玉の2種がある。中国では先史時代以来,珍重され,さまざまな器がある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
玉
株式など証券取引所で売買されるものを総称して玉といいます。
出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内の玉の言及
【天皇】より
…また天皇への敬愛をあらわす言葉としては〈キンリサマ(禁裡様)〉〈テンシサマ(天子様)〉との表現が使われた。一方,幕末の政争に参加した志士は天皇のことをひそかに〈玉(ギョク,タマ)〉と記していた。こうした日本の君主である天皇が〈天皇〉という公式称号で統一されるのは明治になってのことである。…
※「玉」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by 
 [名]
[名] [接頭]名詞に付く。
[接頭]名詞に付く。 1㋓)ボール・まり/(
1㋓)ボール・まり/( 2㋐)宝石・
2㋐)宝石・
 〈ギョク〉
〈ギョク〉 〈たま(だま)〉「
〈たま(だま)〉「
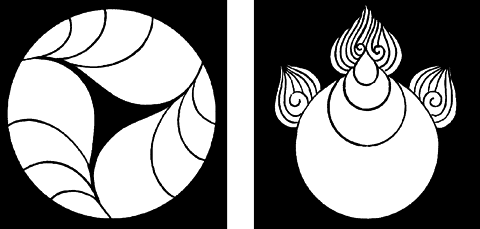







 る
る なり」とし、「潤澤にして以て
なり」とし、「潤澤にして以て なるは仁の方なり」など、仁義智勇
なるは仁の方なり」など、仁義智勇 の五徳を説く。そのことは〔
の五徳を説く。そのことは〔 子、法行〕〔管子、水地〕にみえる。玉は魂振りとして身に佩びるほか、呪具として用いられたもので、殷の武丁の妃とされる婦好墓からは、多くの精巧な玉器が発見されている。玉の旧字は王。王は完全な玉。玉は〔説文〕一上に「朽玉なり。王に從うて點
子、法行〕〔管子、水地〕にみえる。玉は魂振りとして身に佩びるほか、呪具として用いられたもので、殷の武丁の妃とされる婦好墓からは、多くの精巧な玉器が発見されている。玉の旧字は王。王は完全な玉。玉は〔説文〕一上に「朽玉なり。王に從うて點 (ごと)くす」(段注本)とあり、瑕(きず)のある玉をいう。〔詩、大雅、民労〕「王、女(なんぢ)を玉にせんと欲す」の玉は、おそらくその畜の音でよみ、「好(よみ)す」の意に解すべきであろう。
(ごと)くす」(段注本)とあり、瑕(きず)のある玉をいう。〔詩、大雅、民労〕「王、女(なんぢ)を玉にせんと欲す」の玉は、おそらくその畜の音でよみ、「好(よみ)す」の意に解すべきであろう。 など百二十五字を属し、〔新附〕に十四字。〔玉
など百二十五字を属し、〔新附〕に十四字。〔玉 〕には二百六十七字を属する。玉の文化は漢魏六朝においても、なおいよいよその多彩を加えつつあったことが知られる。
〕には二百六十七字を属する。玉の文化は漢魏六朝においても、なおいよいよその多彩を加えつつあったことが知られる。 (ぎよく)・
(ぎよく)・ (かく)の他に曲部の字をも加えている。
(かく)の他に曲部の字をも加えている。


























 玉・瓊玉・古玉・攻玉・紅玉・崑玉・紫玉・執玉・珠玉・振玉・水玉・翠玉・瑞玉・青玉・琢玉・沈玉・佩玉・貝玉・白玉・璞玉・飯玉・美玉・碧玉・宝玉・抱玉・埋玉・瑜玉・瑶玉・良玉
玉・瓊玉・古玉・攻玉・紅玉・崑玉・紫玉・執玉・珠玉・振玉・水玉・翠玉・瑞玉・青玉・琢玉・沈玉・佩玉・貝玉・白玉・璞玉・飯玉・美玉・碧玉・宝玉・抱玉・埋玉・瑜玉・瑶玉・良玉