維管束植物のうち,多年生で,茎頂の活動(伸長生長)が無限に続き,茎に形成層をもっていて二次(肥大)生長を行うもの。樹,樹木ともいい,植物学では木本植物という。草(草本植物)に対応する語。大きさによって高木(喬木(きようぼく))と低木(灌木)に区別することもある。高いものではオーストラリアのユーカリの1種のように130mに達するものがあり,小さいものでは草本と同じような生育形のコケモモやヤブコウジのような例がある。屋久島にある縄紋杉は樹齢6000年と推定され,世界でもっとも老齢の大木の一つである。
維管束植物のうち,現生のシダ植物には,ハナヤスリ科など少数の例を除いて二次肥大生長をするものがないので,典型的な木本植物はない。ヘゴの仲間は直径30cmにも及ぶ幹をつくり,木生シダ類といわれるが,この幹は立ち上がった茎(二次生長はみられず,せいぜい直径3cmくらい)の周辺に,葉柄の基部や根が絡まって太い見せかけをつくっているだけで,材の発達した真正の樹幹はもたない。古生代には,有節植物や小葉植物に属する封印木,蘆木(ろぼく)や鱗木のように高さ数十mに達するものも生育していた。裸子植物はすべて木本性で,マオウ目以外では高木になることが多い。双子葉類には木本性のものと草本性のものが多様化しているが,単子葉類では形成層ができないか,あるいはできてもその活動が貧弱なことが多い。
形成層の活動によってつくられる組織を次生組織(二次組織)というが,形成層の外側には師部,内側には木部がつくられる。木部の道管や仮道管と木部柔組織を主体としてつくられる次生組織に初生木部をあわせて材といい,木本には材がよく発達した幹がつくられる。季節のはっきりしている地域では,形成層の活動の程度が環境の影響を受け,材が一様でなくなる。温帯地方では,春から秋までのあいだ形成層は活発にはたらき,その初期には大きな道管や仮道管などのある春材を,終期には木部繊維の多い秋材をつくる。その差が歴然としているので,材の断面に生長に応じた輪が描かれる。それを年輪という。しかし,熱帯地方などのように,年間を通じて季節変化のみられない地方の木本では,形成層の活動にはほとんど変化がなく,材に年輪がつくられないことが多い。
木本植物では,地上部の茎と地下部の根がよく発達している。茎はふつう幹と枝からできており,高木では種によって形の決まった樹冠をつくる。高木が寄り集まってできた植物社会が森林であり,陸地のほとんど半分は森林に占められているが,現在急速に伐開が進められている。樹冠の形は種によって異なっているので,森林の表面の外観(林相)は森林の構成種によって異なっている。
木は古来人間の生活や文化と密接に関係しており,洋の東西を問わず神木などになって祭祀にかかわりをもつものが多い。日本では府県の木や花を指定して地方の性格を代表させることもあり,天然記念物になっている名木も多い。著名な大木の例として,スギでは前述の縄紋杉のほか,高知県長岡郡大豊町字杉,千葉県鴨川市の旧天津小湊町清澄の大杉や日光の杉並木など,ケヤキでは新潟県十日町市の旧松之山町,山形県東根市,山梨県南アルプス市の旧若草町三恵,同県北杜市の旧須玉町根古屋神社などの大木がある。
執筆者:岩槻 邦男
利用
木と人間は昔から深いかかわりをもっているが,その多くは木材の利用を通してである。木造建築の用材,こけしや漆器の木地など木材の原形をとどめたままの利用形態から,紙・パルプあるいはセロハン,木材糖化物などの原形をとどめない利用形態に至るまで,いずれも大型の木とくに高木の木部を取り出して利用するものである(〈木材〉の項目を参照)。もちろん,このような製材・加工工程を経た利用のほかに,個々の樹種の特性に応じて幹・枝の原形そのままに利用することも多い。バラ科のカマツカ別名ウシコロシの名は硬く弾性のある材が鍬や鎌の柄(束(つか))やウシの鼻輪に使われるところから生じた。ハギ類やキブシなど株立ちになる低木は炭俵のふたやすだれに供され,またマンサク類はねじって薪やものを縛るねそとして用いられるが,とくに五箇山(富山県)・白川郷(岐阜県)の合掌造の骨組みの結合には最良の材料とされた。
樹木には木材としての用途以外に,果樹,茶,コーヒーなど飲・食用,飼料木や肥料木などの農林業用,あるいは花木,庭園樹,緑化樹などの観賞・環境整備用その他さまざまの用途がある。しかし量的にはこれらほどでなくとも,特定の部位が特殊な用法に供されることも少なくない。東アジア北部産のチョウセンゴヨウやイタリアのカサマツなど多くのマツ属樹種の種子は大型で食用となり,また中国のユサン(油杉)の種子の油分は油煙として墨をつくる。トチノキやナラ類のどんぐりは渋を抜いて飼料や加工食品にされる。セイヨウネズの腋状(えきじよう)果はジンの香付けに用いられる。日本のシナノキをはじめヨーロッパ各地にみられるリンデンの仲間あるいはマメ科のニセアカシアは重要な蜜源(みつげん)樹木である。ウコギ類やタラノキなどの新芽は山菜として有名である。中国南部原産のクス科ニッケイの根の皮(肉桂皮)は菓子・料理の香辛料や薬用として広く用いられるが,同じ目的,中でも漢方に用いられる樹木はほかにも多い。漆やゴムはそれぞれウルシノキとパラゴムノキの樹皮に傷をつけて分泌される乳液を集めて加工したものである。マツ類のテルペン類,モミ属のバルサムモミなどの樹脂(やに)はそれぞれ化学製品の原料や試薬用に供されるが,ナンヨウスギ科のAgathisなどの樹脂すなわちコーパルは重要なワニス原料であり,生木に傷をつけて採るほか地中や湖沼中に埋もれているものを掘り出して用いる。日本の和紙などで代表される手すき紙は,クワ科のコウゾ,あるいはジンチョウゲ科のミツマタ,ガンピ類などの長くじょうぶでしかも光沢のある靱皮繊維を利用したものである。アイヌのアツシ(厚司)にするオヒョウニレ,あるいは西日本のヘラノキなども靱皮繊維が布地や縄,箕(み)などに利用される。サクラ類やカンバ類の樹皮は器具の装飾用として知られる。香木として珍重される樹木にビャクダン(白檀)やジンコウ(沈香)がある。前者は心材を用いるが,後者の多くは地中に埋もれて腐り残った材中の樹脂分を集めて用いる。線香はスギの葉とクス科タブノキの葉を粉末にして固めたもので,高級品には香木などを混ぜる。
執筆者:濱谷 稔夫
文化の中の樹木
木は自然の事物のうち,もっとも豊富でもっとも広範囲にわたる象徴をもつ主題の一つである。人類の文化のあらゆる時代,あらゆる地方にわたってその例を見るが,要約すればこれらは中心軸,生命と豊饒(ほうじよう),元祖的イメージに大別することができよう。
中心のシンボル
樹木は,根が地下に張り,枝が天空に伸びるために,多くの民族の文化の中で,地と天空をつなぐ宇宙軸(世界軸)axis mundiと考えられた。エリアーデは,これを〈中心のシンボリズム〉と定義している。
このような宇宙軸の観念は前3000年から前4000年ころにすでにあり,樹木にかぎらず,柱,棒,塔,山はみなこのシンボリズムを共有する。その代表的なものはスカンジナビアに伝わる〈エッダ〉の中にうたわれたイグドラシルと呼ばれるトネリコの木である。これは天,地,地下という三つの宇宙領域の中心に立ち,運命の3女神がこの木に運命の泉ウルドの水を与える。この木をたえまなくかじる巨大なヘビは,破滅と死の原理をあらわす。こうして木は,死からたえまなく再生し,永遠に回帰する宇宙の時間をも象徴する。アッシリア人も聖なる力と宇宙の再生力の象徴としての聖樹の信仰をもち,前2000年ころから多くの芸術的表現をもつ。このほか,ゴール人はオーク,ゲルマン人はボダイジュ,イスラム教徒はオリーブ,インド人はバニヤンと呼ばれるイチジク,シベリアに住む原住民族はカラマツを,それぞれ聖なる木として崇拝した。これらの木はすべて世界の軸として,天と地が結ばれる場所,神性の通り道となる。シベリアのカラマツには,太陽と月が鳥となって舞い降りる。中国およびインドの宇宙樹には12羽の太陽の鳥(黄道十二宮の象徴)が降りる。またイスラムの預言者ムハンマドは,世界軸にそって旅をし,地獄の深みから天界へとめぐるが,この階梯は多くの場合1本の木によって示される。グノーシス派神秘思想においては,〈大地と水によって養われ,七つの天に広がる〉木が,グノーシスの象徴として用いられている。
宇宙樹のイメージの中には,世界の各地に見いだされる〈さかさまの木〉がある。古代インドのベーダおよびウパニシャッドでは,さかさまのイチジクの木(アシュバッタ,バニヤン)に全世界が宿るとされる。さかさまの木は宇宙の生命の源泉が太陽にあり,天空に万物の種子が宿り,全世界にひろがることを示す。したがって,その根は実は枝であり,枝が根である。ベーダでは,この万物の超越的源泉は〈ブラフマン〉と呼ばれる種子であり,万物はその下方への顕現である。またイスラム教徒のあいだでは,〈幸福の樹〉の根は最高天に張り,枝は地下にひろがるとされる。アイルランドおよびフィンランドの民間儀礼では,さかさまの木を祭壇に立てる。オーストラリアのシューマンは,魔法の木をさかさまに植え,そこに人の血を注いだのち,これを焼く。中世のユダヤ神秘主義,とくにカバラには,神の顕現としての宇宙創造をさかさまの木としてあらわすイメージがあり,カバラ文献《バヒール》(12世紀),《ゾーハル》(13世紀)は,上から下に伸びる太陽のような木について記している。このとき,神から流出する力を〈セフィロト〉と呼ぶ。これは3枝に分かれてカバラの生命の樹をつくる。このカバラの木は,ルネサンス以降の神秘主義者たちに受け継がれ,超越的源泉からの宇宙の生成の象徴図となった。
このほか,ヨーロッパのメーポールMaypole,ナバホ・インディアンのアシ,日本における神道のサカキも,そこに神性が宿る宇宙軸のシンボルの一種であり,十字架も,このような中心のシンボリズムの発展の一つであるといえよう。
生命と豊饒のシンボル
木はまた地母神のもつ豊饒な生産力の象徴となってきた。これは上で述べた中心のシンボリズムと分かちがたい場合もある(セフィロトの木,キリスト教における十字架,エデンの中心に立つ生命の樹など)。
インドでは,樹液は地母神の乳であり,すべての女性の乳房を満たし,すべての木を流れ果実をみのらせる〈ソーマ〉あるいは〈アムリタ〉である。古代西アジアでは大地の女神イシュタルの恋人は植物神たる木で,女神と木の聖婚(ヒエロス・ガモス)によって,大地は春の再生と冬の種子ごもりを繰り返す。古代ローマでも,大地と豊饒の女神キュベレは,アッティスと聖婚し,これを殺して松に変える。ギリシアのアドニスは没薬(ミュラMyrrha)の木から生まれた。これらの植物婚あるいは人と木のメタモルフォーズ(変身)の神話はまた,人間と植物との転生のシンボルであるが,これもひろくは,宇宙的生命力の遍在を信ずるアントロポモルフィズム(擬人観)のあるところにはつねに現れている。
仏陀(ぶつだ)の母はムユウジュの下で子を生んでいる。キリスト教では,エデンの中心に生命の樹と知恵の樹が並んで立つが,しばしばこれらは1本の木としてまたは並列する木として表現され,人間の生と死を象徴する。またキリストの十字架はしばしば永遠の生命をあらわす1本の木として表現される。
古代西アジアの聖樹も,聖獣にかこまれるとき,自然に生命を与える活力のシンボルとなる。生命の樹と向かいあう動物のモティーフは,イスラム文化を通して中世ヨーロッパおよびアジアにひろく伝播(でんぱ)した。
→生命の樹
元祖的イメージ--系統樹
生命の樹のイメージは,民族または家族の神秘的根源の象徴となる。多くの民族において,木は元祖である父または母と同一視される。
木の元祖的イメージの代表的なものは,12世紀の神秘家ヨアキム・デ・フローリスによるもので,彼はキリスト教の歴史を木として見た。父であるノアからセムとヤペテの2本の幹が伸び,この2本が交差してつくる三つの輪によってキリスト教の過去,現在,未来が象徴される。《イザヤ書》(11章)にみられる〈エッサイの木〉は,ユダヤ人の歴史を象徴し,中世を通じて多くの表現を見たイメージである。エッサイの腰から生えた木には,マリアとキリストが実る。おそらくこのエッサイの木が,ヨアキムの木をはじめ,人間の生の各段階や家族の系統を示す木のシンボルの原型となったと思われる。ここから,一人の男の体から生い育つ木のイメージによって,元祖もしくは祖型とその分岐もしくは発展の系統を図示する伝統が生じた。これを百科全書的知の組織図としてみるとき,学芸や知のシンボルとしての系統樹が生ずる。レオナルド・ダ・ビンチがミラノのスフォルツァ城に描いた,根と枝におおわれた〈アッセの間(中心軸の間)〉は,彼がこれらの象徴を体得していたことを示している。
現代的想像力の中の木
木は,自然界についての人間の想像力をつねにかき立ててきた。20世紀の,バシュラール,エリアーデ,ユングなどによる研究は,中心,生命の源泉,死と再生,成長,宇宙的生命力の遍在を象徴するイメージとしての木が,現代の芸術家にも有効なテーマであることを例証している。
19世紀の,人間の内的生命と自然もしくは宇宙のそれとの照応を信じるロマン派の詩人,文学者,画家にとって,木はかっこうのテーマになった。たとえば,シェリーの《西風のオード》(1819)は,冬を前に葉を落とす木に再生の希求を象徴させた。20世紀になって,サルトルはマロニエの〈根〉を見て実存の恐怖を感じ(《嘔吐》),大江健三郎は木を主題とする一連の作品の中で宇宙樹のシンボリズムを復活させた。シュルレアリストのエルンストは森の連作を描いたが,これはロマン派と中世神秘主義を継承したもので,文明に冒されぬ人間精神の根源を象徴する。モンドリアンも木の連作によって,木のもつ宇宙的シンボリズムを水平と垂直のバランスのうちに抽象化した。クレーとカンディンスキーはいずれも木を芸術創造のプロセスにたとえ,ブランクーシは《無限の柱》によって原初の宇宙軸を再現している。
執筆者:若桑 みどり
日本における伝承と習俗
木は神霊の依代となり,神事や伝説にも多く登場する。熊野のナギ,石上・三輪(大神)・伏見稲荷のスギ,大峰のアスナロ,高野山のマキ,京都愛宕山のシキミ,伊勢朝熊(あさま)山のツゲ,天満宮のウメというように,有名な神社では特定の木が神木とされ,祭りのときにその小枝を持ち帰ることもある。とくに常緑で生命力の盛んな木は古くは広く〈さかき(榊,賢木)〉と呼ばれ,神の依代や聖域を画す柴として用いられた。神霊の依代としての木は,年中行事にも多く見られる。正月の門松,卯杖(うづえ),御竈木(みかまぎ),削花,嫁たたき棒,祝棒,左義長の芯柱などはその代表で,神霊を憑依(ひようい)させたり,木に宿った神霊や生命力を他のものに移す媒介となる。正月の初山入りでも,山から木を切ってきて,木についた神霊を大地や人に移し,農耕や人の豊饒多産を促す意図がうかがえる。木そのものに生命や精霊が宿っているという樹霊観念は,木をめぐる伝説によく見ることができる。しだれ桜,しだれ栗,逆さ杉,傘松などふつうとは異なった枝の下がった木は神霊の現じた木として神聖視されており,また三つまた木やまど木といった特異な形の木も山の神の宿木とか遊び木とされて切るのを禁じられている。高僧や武将がつえや箸(はし)をさしたものが生長して大木となったという伝説も多く,一里塚のエノキ同様,境や聖域を画した木の名残りと見られ,また各地の木下,松本,杉下などといった地名も神木の下で祭りをした跡と考えられている。フジやブドウなどつる状の木や果樹を屋敷に植えるのを忌む土地も多い。これは,木が大地の生命力や神霊を吸収し体現したものと見られたからであろう。
そのほか,アイヌは火おこし棒としての有用性の違いに注目して,ドロノキとハルニレに神話上の異なる評価を与えている。関東以西の各地方でも節分にヒイラギやトベラの小枝を軒端に挿す風習があるが,葉のとげや枝葉の臭気が悪鬼を払うと信じられたからである。また小正月に豊作を祈って飾る粟穂稗穂(あわぼひえぼ)にはヌルデやニワトコが用いられる。
執筆者:飯島 吉晴+濱谷 稔夫
 〈ボク〉
〈ボク〉 〈モク〉き。「木工・木材・木質・木製・木造・木馬・木皮/材木・
〈モク〉き。「木工・木材・木質・木製・木造・木馬・木皮/材木・ 〈き(ぎ)〉「木戸・木場/植木・草木・
〈き(ぎ)〉「木戸・木場/植木・草木・ 〈こ〉「木陰・
〈こ〉「木陰・


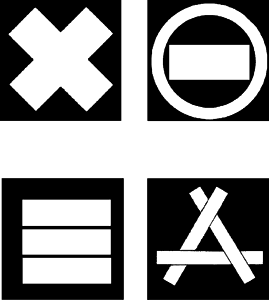



 (おほ)ふなり。地を
(おほ)ふなり。地を 〕の木部は八百二十二字に及ぶ。二書とも別に東部・林部がある。これらのうち、休の初文は禾に従い、禾は軍門の象。また東は
〕の木部は八百二十二字に及ぶ。二書とも別に東部・林部がある。これらのうち、休の初文は禾に従い、禾は軍門の象。また東は (たく)(ふくろ)の初文で、その象形の字である。
(たく)(ふくろ)の初文で、その象形の字である。







 木・
木・ 木・丘木・朽木・樛木・巨木・拱木・喬木・曲木・群木・勁木・古木・孤木・枯木・坑木・香木・高木・
木・丘木・朽木・樛木・巨木・拱木・喬木・曲木・群木・勁木・古木・孤木・枯木・坑木・香木・高木・ 木・刻木・材木・雑木・散木・算木・
木・刻木・材木・雑木・散木・算木・ 木・鑽木・質木・若木・樹木・就木・柔木・樵木・上木・植木・神木・薪木・燧木・接木・草木・叢木・大木・啄木・直木・珍木・土木・伐木・板木・扶木・斧木・浮木・桴木・腐木・風木・墓木・抱木・名木・陽木・立木・流木・梁木・霊木・連木・老木・肋木
木・鑽木・質木・若木・樹木・就木・柔木・樵木・上木・植木・神木・薪木・燧木・接木・草木・叢木・大木・啄木・直木・珍木・土木・伐木・板木・扶木・斧木・浮木・桴木・腐木・風木・墓木・抱木・名木・陽木・立木・流木・梁木・霊木・連木・老木・肋木 木
木